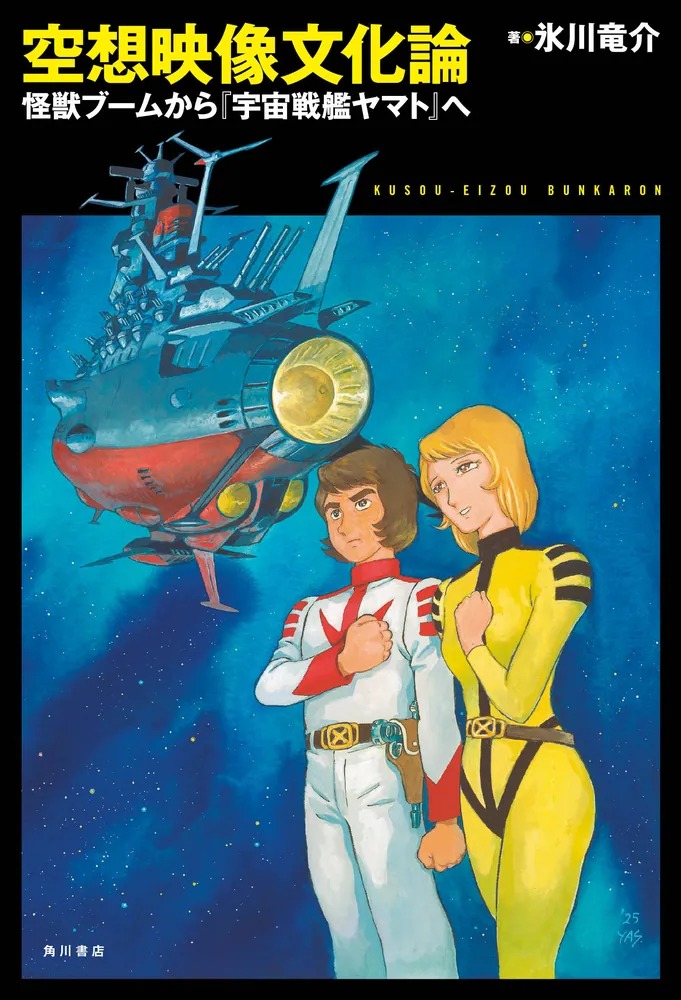公開日:2025/2/8
上映館: シアター・イメージフォーラム[東京都]ほか
公式サイト:https://www.zaziefilms.com/loshiperboreos/
(前編より)
 © Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films
© Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films
そんな『ハイパーボリア人』のストーリーは、前半と後半で大きく分かれている。前半はレオン&コシーニャの助言によってギーセンが主演となってセラーノを題材にした映画制作に取り組むシーンが大半を占め、ここで外交官として各地に駐在し、軍事政権下に帰国しネオナチ運動で名をなしたセラーノの半生が語られる。しかし後半は一転、チリ軍事政権下におけるフィクサー、ハイメ・グスマンから国家を揺るがす記録が撮影されたフィルムの探索をギーセンは命じられる。
最終的に物語は合流するのであるが、そんな同作にあって、そのメタ的な構造にもっとも強く影響されるのは、やはり主人公のギーセンだろう。彼女は全編を通じ、さまざまなポリティックスに巻き込まれていく。セラーノの半生を再現する前半のシークエンスでは仮面をかぶり、役を演じ、後半ではグスマン(およびレオン&コシーニャ)から警官になるよう命じられる。その受動的な姿は劇中いたるところで登場する、パペットのようですらある。こうしたギーセンの身体で拮抗する自意識を持った身体と人形的身体は、その他登場人物との関係性も含め、「自己」という存在の心もとなさを暴露するのだ。
 © Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films
© Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films
しかしそんなギーセンの揺れるアイデンティティにあって、ほぼ唯一揺るがぬものとして描かれているのが「血」である。輻輳する語りにあって、血は同作に一貫して反復されるテーマだと言っていい。それはなぜか。ギーセンが(はっきりとは明言はされてないものの)ドイツ系のチリ人だからである。劇中内でギーセンは両親と話すシーンが複数挿入されるが、その時話されているのはドイツ語である。ドイツから遠く離れた南米の地で、第二次世界大戦後も一部で信奉されてきたナチズムの思想や白人至上主義。ギーセンはそれに向き合いつつも、最後に明かされる誇大妄想に憑りつかれた世界に対して、連帯を呼びかける。
『ハイパーボリア人』は物語の導入時のドキュメンタリー性が徐々にエクストリームな展開になっていくことが醍醐味なのであるが、むしろその陰謀論的世界観は、現実の私たちの生活のすぐそばにあることを忘れてはならない。同作はそんな「現代」についての映画だからこそ、その結末はオープンエンドで締めくくられなければならなかった。『ハイパーボリア人』は映画がフィクションに安住できないくらいに、ポストトゥルース時代の現実が苛烈だということを黙示録的に示唆している。
 © Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films
© Leon & Cociña Films, Globo Rojo Films
『ハイパーボリア人』
第77回カンヌ国際映画祭 監督週間 正式出品
監督:クリストバル・レオン、ホアキン・コシーニャ
脚本:クリストバル・レオン、ホアキン・コシーニャ、アレハンドラ・モファット
出演:アントーニア・ギーセン
2024年 / チリ / スペイン語・ドイツ語 / 71分 / カラー / 1.85:1 / 5.1ch
原題:Los Hiperbóreos
字幕翻訳:草刈かおり
参考資料
・『オオカミの家』[映画パンフレット](ザジフィルムズ、2023)
・「アリ・アスターも舌を巻いた異形ホラー「オオカミの家」は音もすごかった! ヒットの要因、作品の聴きどころ座談会」『映画.com』https://eiga.com/news/20240407/5/
鑑賞日:2025/1/7(火)