バックナンバー
2021年12月01日号のバックナンバー
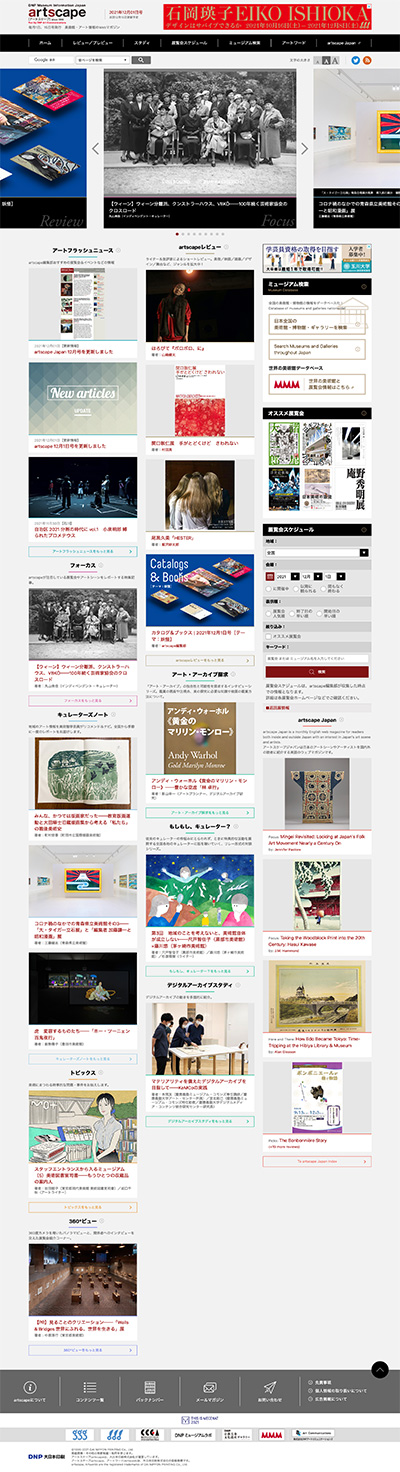
フォーカス
【ウィーン】ウィーン分離派、クンストラーハウス、VBKÖ──100年続く芸術家協会のクロスロード
[2021年12月01日号(丸山美佳)]
ウィーンは良い意味でも悪い意味でも「変わらない」「変化がとても遅い」とよく言われる。大学やミュージアムなどのインスティテューションも、蓋を開ければ外部の者に対してオープンではない閉鎖的な気質を纏っており、プログラムが意欲的であったとしても、オーストリアらしさにおいては変わることを拒んでいるように見える。それは18世紀の街並みをそのまま残すウィーンの街も同様である。しかし、目に見えない小さな変化はあらゆるところで起きており、それを拾い上げていくことは過去や現在、そして未来を考えるうえでも重要であると考えている。本稿では、ウィーンの街で100年以上継続する3つの芸術家協会の変化に触れたうえで、周縁化されたりマイノリティとされたりしてきた人々の「拡張された」コミュニティについての芸術実践を捉えてみたい。
キュレーターズノート
みんな、かつては版画家だった──教育版画運動と大田耕士旧蔵版画集から考える「私たち」の戦後美術史
[2021年12月01日号(町村悠香)]
一般的に「美術史」と言われるものが、果たしてどれだけ同時代の人の実感が伴うものなのか、自分がその時代に生きていたら見たり参加したりできるものだったのか、疑問に思うことがある。本当にこれは「私たち」の歴史なのだろうかと。近年、フェミニズムやジェンダーの視点から戦後の美術史を見直す動きが進み、女性作家の存在に光を当てることで主流とされてきた歴史を問う展覧会が数多く開催されている。こういった動きを見ていると、これ以外の視点からも「私たち」の側に引き寄せた戦後美術史があるのではと探りたくなる。
コロナ禍のなかでの青森県立美術館その3──「大・タイガー立石展」と「編集者 加藤謙一と昭和漫画」展
[2021年12月01日号(工藤健志)]
2022年1月16日(日)まで埼玉県立近代美術館&うらわ美術館で開催中の「大・タイガー立石展」。千葉市美術館、青森県立美術館、高松市美術館に埼玉の2館を加えた計5館による共同企画展である。もともと本展は千葉市美術館の水沼啓和さんが発案したもので、美術館連絡協議会(美連協)を通して参加館が募られた企画であった。2017年12月3日に幹事館である千葉市美術館で初めての会議が行なわれ、タイガー立石生誕80年の節目にあたる2021年度の開催を目指して準備がスタートした。しかし、2018年の暮れに水沼さんが突然他界され、準備は中断してしまう。半年ほど経った2019年5月21日に再度関係者が集まって対応を協議。水沼さんの遺志を継いだ千葉市美術館が幹事館継続を表明してくださり、企画は再始動。千葉市美術館(千葉県は立石が晩年を過ごしたゆかりの地)の藁科英也さんと森啓輔さん、そして60年代美術の優品を数多く所蔵している高松市美術館の牧野裕二さん、イタリア時代の立石の活動に詳しい埼玉県立近代美術館の平野到さんと菊地真央さん、「本のアート」を専門とするうらわ美術館の滝口明子さん、加えて筆者という学芸チームで、さらに立石夫人の富美子さんとANOMALYの協力を得ながら準備を進めることとなった。
虎 変容するものたち──「ホー・ツーニェン 百鬼夜行」
[2021年12月01日号(能勢陽子)]
各時代には固有の、いま生きている社会とは異なる、掴み切れない空気や風がある。文化も歴史もゆっくりとしたアニメーションのように時々刻々と移り変わっているから、現代と地続きであるはずでも、時を隔てて振り返ると、当時の風はすっかりどこかにいってしまっている。
トピックス
[PR]これからの美術館に求められる機能──千葉市美術館「つくりかけラボ」が示すこと
[2021年12月01日号(佐藤慎也)]
千葉市美術館に昨年から設置されたスペース「つくりかけラボ」。「五感で楽しむ」「素材にふれる」「コミュニケーションがはじまる」という三つの軸のもと、従来の展示室とは異なる発想でスタートしたこの場所では、すでに複数のアーティストによる滞在制作や、市民参加型のワークショップ、あるいは全館を巻き込む仕掛けが施された展示プログラムなど、一見分類不可能なものも含めた多種多様でユニークな実践が始まっている。
美術館という場所には、いまどのような機能が期待されているのだろうか。建築家であり、今年11月にオープンした八戸市美術館の館長も務める佐藤慎也氏に、今年の7月から10月にかけて展開され、各所で話題を呼んだのも記憶に新しい「飯川雄大|デコレータークラブ──0人もしくは1人以上の観客に向けて」(つくりかけラボ04)を事例のひとつとして、これからの美術館がもたらす「もの」「こと」の多面的な可能性についてご寄稿いただいた。(artscape編集部)
もしもし、キュレーター?
第3回 地域のことを考えないと、美術館自体が成立しない──尺戸智佳子(黒部市美術館)×藤川悠(茅ヶ崎市美術館)
[2021年12月01日号(尺戸智佳子/藤川悠/杉原環樹)]
「学芸員/キュレーター」という職業に対して多くの人が抱くイメージは、展覧会の企画や解説をする人、といったものかもしれません。実際はそれだけではなく、学校と連携して教育普及事業を行なったり、地域と美術館をつないだりと、外からは見えない幅広い業務に携わっているのが学芸員の日常です。
従来の「学芸員」の枠組みにとらわれず、ときに珍しい活動も展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー対談の形式で話を聴いていく連載「もしもし、キュレーター?」。第3回目の今回は、茅ヶ崎市美術館の藤川悠さんが、いま一番対話をしてみたいキュレーターである富山県・黒部市美術館の尺戸智佳子さんを訪ねます。
企画した展覧会の関連イベントとして、地域の自然や文化を深く知るためのバスツアーやイベントを近隣の文化施設と協力して開催したりと、展示室の中だけにとどまらない鑑賞体験づくりに日々奮闘する尺戸さん。地方の美術館で現代作家を扱う意義についてや、展覧会をつくるうえでのアーティストとリサーチの関係性など、示唆深い話題が豊富な対談になりました。(artscape編集部)
[取材・構成:杉原環樹/イラスト:三好愛]
※「もしもし、キュレーター?」のバックナンバーはこちら。








![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)