トークシリーズ:「Artwords」で読み解く現在形
3. 戦後日本美術の再検証する展覧会
暮沢──この10年間で、戦後の日本美術の動向を再検討するような展覧会が増えました。つい最近、国立新美術館で『「具体」−ニッポンの前衛 18年の軌跡』★31がありましたし、2005年に大阪の国立国際美術館で『もの派──再考』展がありました。いわゆる戦後の代表的な動向が問い直され、これまでなかった新しい資料や切り口での見直しという動きがあります。また、天明屋尚さん★32らのネオ日本画とかもありますし、工芸も従来とは違った光を当てるような展覧会がありました。いわゆる伝統的な美の規範に即したものではないものが出てきていますが、これらの動向についてはどう思われますか。
足立──北澤憲昭さん★33の『眼の神殿──「美術」受容史ノート』(美術出版社、1989年)が著されて、それから現代美術の人達の間でも日本近代の問い直しが始まったと言えます。現代を考えるには近代を考える必要があるということで、1990年代において、北澤さんだけではなく多くのアカデミシャンがそのような問い直しをしたと同時に、いろんなアーティストたちが日本や近代を執拗にモチーフにしたのが第一段階だと思います。歴史は繰り返すと言いますが、その後2000年代に松井冬子さん★34、天明屋尚さん、最近では金沢21世紀美術館で開かれた『工芸未来派』展★35などが出てきます。やはり二度目か三度目となると、インパクトが別のものになりますよね。笑劇というほどくだらないものではないとしても。
成相──最近では京都国立近代美術館で開かれて東京にも巡回した『「日本画」の前衛 1938-1949』展★36が意欲的な企画でした。ただ、ネオ日本画なんて言ったところで、そもそもジャンルとして明確に弁別できる根拠を持たない日本画は、未だに「内なる他者」として「日本画」の名を引きずっています。戦後の日本画滅亡論がなおも命脈を保っているともいえます。戦後美術の再検討に関して言えば、まずは半世紀以上の時間が経過したこと、それから、露骨な言い方になるかもしれませんが、5、60年代に活躍した作家や関係者が高齢に達しているために、記録や証言を残しておきたいという考えもあると思います。オーラル・ヒストリー・アーカイブの動きはその典型でしょう。
暮沢──いわゆるポストモダン研究やナショナリズム研究があり、その代表例で言えばベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』★37やエドワード・サイード★38の『オリエンタリズム』です。これらの理論的成果を日本の美術に当て嵌めようという動きがこの20年ほど大きく出てきたと思います。記録という意味では、加治屋健司さんらのオーラル・ヒストリー・アーカイブも重要ですね。
成相──今まさにその渦中ですが、特にアメリカでにわかに日本の戦後美術再評価の動きが起こっています。ブラム&ポーでのもの派展★39、MoMAの『TOKYO 1955-1970』、そして2013年にはグッゲンハイムで具体展。それらがつながっているのか偶然なのかは知らないのですが。
暮沢──現在ニューヨークでは日本の美術を題材にした展覧会が立て続けに開かれていますね。
成相──1985年にオックスフォード近代美術館で開かれた『再構成:日本の前衛1945-65』★40をはじめとして、日本の戦後美術が海外に紹介される際にはほぼ必ず「前衛」という冠が付けられます。今回「新しい前衛」を副題としたMoMAでも踏襲されていて★41、約30年にわたってスタンスは変化していないともいえます。今回重要だと思うのは、当時の美術評論が英訳されたアンソロジー(From Postwar to Postmodern, Art in Japan 1945-1989)が出ることです。これは画期的ではないでしょうか。
暮沢──1986年にポンピドゥー・センターで『前衛の日本』展があり、1994年にゲスト・キュレーターとしてアメリカのアレキサンドラ・モンロー★42を呼んだ『戦後日本の前衛美術』展がありましたが、いまだにその流れが続いているのかな。1950年代から具体や実験工房があって、読売アンデパンダン展があり反芸術があり、1970年代にもの派が来るという具合に、ほぼ定式化されている。日本で欧米の現代美術が紹介されるときにはもはや前衛なんて言葉は使われないわけだから、今後はその非対称性も問わないとならないかもしれませんね。
足立──欧米でもいろいろな日本研究の拡大があります。多くの場合、彼らは美術史ではなく地域研究から始めています。日本研究の中で未だにやられていないものとして、誰も読まない英訳が付けられていた美術館の現代美術展のカタログが何十年も経てから功を奏して、若い欧米の人たちが研究するようになったという経緯があるんじゃないでしょうか。そこには、日本人にとってはほとんど新しい内容はないのですが、英訳されたカタログ類によって、海外の人にとっては新しい研究ができるようになっています。そして、日本研究に強い関心を持った人の中でも日本語に堪能になった人が日本にやってきて、最近では日本人ですら知らないような事柄も調べていくということもあります。
成相──しかしやはりジャパン・スタディーズがエキゾチシズムを超えられないと聞くこともありますが、いかがでしょう。
足立──確かにそういう人もいますが、それは日本語ができない人で、日本語がちゃんとできる研究者たちはそういった問題を回避していると思います。実際、私の外国人の友人たちには、日本美術史や戦後文化史を、日本人と同等かそれ以上のレベルで掘り下げている人が何人もいます。一方で、日本人であっても、外国にいれば、エキゾチズムとして日本近現代美術史を扱う場合もあるのではないでしょうか。
暮沢──昨年出版されたエイドリアン・ファベル★43の『Before and After Superflat: A Short History of Japanese Contemporary Art 1990-2011』★44では、1990年代以降の日本の現代アートを村上隆★45と奈良美智★46と森万里子★47に集約する図式で説明しています。その根拠が、TASCHENの『Directory to 81 Contemporary Artists』★48にセレクトされている日本人アーティストがその3人だからと。彼のバックボーンは社会学ですが、これなどもジャパン・スタディーズの一環かもしれませんね。
足立──ちょっと読んだ限りですが、僕自身も若い頃に見た1990年代後半の美術シーンについて、それを見たはずもないイギリス人があたかも伝説のようなものとして語っていたのは、とても新鮮な思いがしました。ただし、彼は日本語ができないから、英語でインタビューできる人たちにあたって理論を組み立てていますね。でも、英語を話さない日本人もたくさんいるので、情報の偏りも感じました。彼がインタビューしていない人たちや見落としている人たちによって歴史が形成されている部分も多くあるので、そこは問題だと思います。全てを網羅することは不可能だとしても、やはり現代美術史を日本語が出来る人が書かなくてはいけない。
暮沢──足立さんと成相さんは日本が専門なので沢山さんに聞きたいのは、アメリカの現代美術が日本でどう紹介されているかについて聞きたいですね。
沢山──うーん、どうなんでしょうか。あまり紹介されていないような気がします。海外の戦後美術の単なる紹介や導入に留まらない重要な企画としては、尾崎信一郎さんのやられた「重力」展や「痕跡」展が言うまでもなく重要です。それから昨年、東京国立近代美術館で『生誕100年 ジャクソン・ポロック』展★49が、ポロックの日本での回顧展としては初めて開かれました。これは周到に準備された画期的な企画だったと思います。なので、わざわざ生誕100年と銘打つことでその企画の動機を確保しなくてもな、とも思いました。
暮沢──藤枝晃雄さん★50たちによってこれまで語られてきたポロック像や流布している言説に対して修正を迫るようなものはありましたか。
沢山──愛知県美術館の大島徹也さん★51という学芸員の方が企画された展覧会でしたが、ポロックは今まで何度か企画が持ち上がっても作品が集まらないという理由でその度に頓挫してきたようです。ですが、今回は大島さんの研究者としての功績が評価され、その信用の元に貸し出しが許可されて展覧会が実現したそうです。今回のポロック展の特徴は、しばしば指摘されていましたが、48年から50年にかけて制作された代表作があまりなくて、むしろその傍らで制作されてきた注目すべき小品が多く観られたということでしょうか。それらを観るとポロックがかなりいろいろな実験をやっていたことがわかる。カット・アウトだけではなく、小石をコラージュしたり。つまり、代表作が来なかったのではなく、むしろ積極的に考えれば、企画者の大島さんが、代表作こそを回顧展の中心軸に置くような大作主義を避けたということなのかもしれません。日本で開かれた功績も大きいですし、良い意味で修正主義的に機能した展示だったと思います。
暮沢──先日カナダのモントリオールに行く機会があり、地元の美術館をいくつか回りました。その中で、ジャン=ポール・リオペル (Jean-Paul Riopelle)★52という作家がいて、ポロックと同時代にそっくりの絵を描いています。僕が抽象表現主義の専門ではないのもあるけど、普通に見ていても区別がつかないくらいでした。彼はアンフォルメルの1人とされていて、カナダでは著名なアーティストなのですが、ポロックの同時代的な影響力を実感できました。


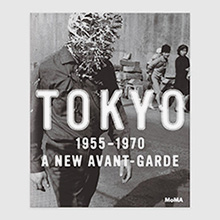
「『具体』──ニッポンの前衛 18年の軌跡」展チラシ/「『日本画』の前衛 1938-1949」展ポスター/「TOKYO 1955-1970」展 カタログ

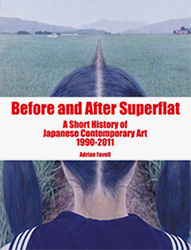

「再構成:日本の前衛1945-65」展カタログ/エイドリアン・ファベル『Before and After Superflat: A Short History of Japanese Contemporary Art 1990-2011』/「ポロック」展ポスター
★31──2012.7.7〜9.10まで国立新美術館で開催された、1954年に関西で結成された若い前衛美術グループの回顧展。東京では初めての開催。
★32──てんみょうや・ひさし:1966- 日本の現代美術家。作風は、南北朝期の婆娑羅や戦国末期〜江戸期の社会風俗である傾奇者などを絵画に採り入れ“ネオ日本画”を称する。2010年、編著『BASARA』刊行。同時に青山スパイラルガーデンで〈BASARA〉展をキュレーション開催、大きな反響を呼ぶ。作品集に『傾奇者』(PARCO出版、2004)。
★33──きたざわ・のりあき:1951- 美術史・美術評論家。専門は日本近代美術史。女子美術大学教授。1990年に、日本の近代美術の誕生を子細に検討した『眼の神殿──「美術」受容史ノート』(美術出版社)でサントリー学芸賞受賞。跡見学園女子大学教授、多摩美術大学非常勤講師を歴任。
★34──まつい・ふゆこ:1974- 日本画家。絹本(絹地)に岩絵の具を用いるという古典的な手法を用いて、人体の臓物、幽霊、動物、人の痛みなどを描く。2006年「MOTアニュアル」(東京都現代美術館)で2007年野村賞受賞。2011年「松井冬子展──世界中の子と友達になれる」横浜美術館など。
★35──2012年4月28日-8月31まで金沢21世紀美術館で開催された、「工芸の“現在性”と“世界性”を問う企画展」。
★36──2012年9月3日-10月17日まで、京都国立近代美術館で開催された、「戦前・戦後の世界にあって、ほとんど触れられてこなかった日本画」の「前衛」活動に焦点をあてた」展覧会。「1938年に結成された歴程美術協会を中心に、前衛「洋画」とのかかわり、「バウハウスと日本画」といった意外なテーマなど、激動の時代にあって未知の「日本画」表現をさぐろうとした画家たちの果敢な動向を探る」。[公式ウェブサイトより]
★37──Benedict Richard O'Gorman Anderson:1936- アメリカの政治学者。印刷技術の発展がもたらす出版を通して言語的な共同体が「国民」及び「国民国家」という、想像の共同体へと変容していく様を、本書で分析、その後のナショナリズム論、国家論に大きな影響を与えた。
★38──Edward Wadie Said:1935-2003 パレスチナ系アメリカ人。比較文学研究者、文学批評家。西欧世界が、自らの外部としてアジア・中東を認識する姿勢を批判した「エンタリズム」の理論家として知られる。著書に『オリエンタリズム』『文化と帝国主義』『パレスチナとは何か』など。
★39──ブラム&ポーはロサンゼルスのギャラリー。〈もの派〉展(Requiem for the Sun: The Art of Mono-ha)は、2012年2月25〜4月14日に、日系アメリカ人吉竹美香によってキュレーションされた。URL=http://www.blumandpoe.com/exhibitions/requiem-sun-art-mono-ha#images
★40──1985年12月8日-1986年2月9日開催。
★41──Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde ニューヨーク近代美術館Momaで、2012年11月18日-2013年2月25日まで開催。
★42──Alexandra Munroe:グッゲンハイム美術館アジア担当上級キュレーター。ジャパン・ソサエティ・ギャラリー館長時代に、「YES Yoko Ono」展、村上隆のキュレーションによる「『リトルボーイ:爆発する日本のサブカルチャー・アート』展などを手掛ける。
★43──Adrian Favell:パリ政治学院社会学部教授。デンマークのAarhus大学教授。ヨーロッパ、北アメリカ、東アジアにおける移民、移動、モビリティのプロセスなどについて研究。主な著書に、The Human Face of Global Mobility: International Highly Skilled Migartion In Europe, North America And The Asia-Pacific (Comparative Urban and Community Research), Transaction Pub (2006)、Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe (Studies in Urban and Social Change), Wiley-Blackwell; 1st edition (2008)など。2012年、1バブル崩壊以降の日本のアートシーンの動向およびアーティストについて分析した『Before and After Superflat A Short History of Japanese Contemporary Art 1990 - 2011』を刊行。
★44──社会学者エイドリアン・ファベルによる、1990年-2000年代日本の美術シーン──アーテイスト、ギャラリスト、アートライター、キュレーター、アートプロジェクト、そして美術館──についての動向と分析。
★45──むらかみ・たかし:1962- 東京藝術大学美術学部日本画科卒業。日本のアーティスト。アーティスト集団「カイカイ・キキ(Kaikai Kiki)」主宰。日本のマンガやアニメーションの手法を積極的に採り入れた絵画作品(日本画)や等身大の美少女フィギュアで知られるカリスマ的なアーティスト。2000年、奥行きや遠近法を無視し、平面生を強調する作品群を「スーパーフラット」と呼び、同名の展覧会をキュレーション、2000年代日本の現代美術を牽引した。
★46──なら・よしとも:1959- 青森県弘前市出身の画家。愛知県立芸術大学、ドイツ国立デュッセルドルフ芸術アカデミーで学ぶ。1994年、ケルンに移り住み。「2000年の帰国まで続くケルン時代は多作な時期で、代表的な奈良のイメージとして知られる挑戦的な眼差しの子どもの絵もこの頃頻繁に描かれた」[青森県立美術館ウェブサイトより]。青森県立美術館に多数の作品が収蔵されているほか、ニューヨーク近代美術館(MoMA)、ロサンゼルス現代美術館などにもコレクションされている。
★47──もり・まりこ:1967- 日本の美術家。森ビル創業者・森泰吉郎の孫。文化服装学院スタイリスト科卒業後、渡英。チェルシー美術大学、ロンドン芸術大学などで学ぶ。1993年よりニューヨークを拠点に活動。1997年ヴェネツィア・ビエンナーレにて優秀賞受賞。作品は、初期の写真・ビデオ映像から、3D映像作品、光ファイバーを使用したインスタレーションなどに広がっている。
★48──Uta Grosenick, Art Now! 2: the New Directory to 81 International Contemporary Artists, Taschen, 2008.
★49──2012.2.10〜5.6に、東京国立近代美術館 企画展ギャラリーで開催。日本初の大規模なポロック回顧で、初期から晩年までの代表的約70点が展示された。
★50──ふじえだ・てるお:1936- 美術評論家、武蔵野美術大学名誉教授。著書に、『現代美術の展開』(美術出版社)、『現代芸術の不満』(東信堂)、『絵画論の現在』(スカイドア)、『新編ジャクソン・ポロック』(東信堂)等多数。訳書に『グリーンバーグ批評選集』(勁草書房)など。
★51──おおしま・てつや:愛知県美術館キュレーター。「生誕100年 ジャクソン・ポロック展」のキュレーションによって、第7回西洋美術振興財団賞を受賞。
★52──Riopelle, Jean-Paul:1923 -2002 モントリオール生れの画家。1947年以来主としてパリで活動。ヨーロッパの抽象表現主義運動の主要メンバー。1962年、ヴェネツィア・ビエンナーレで作品を展示し、ユネスコ賞を受賞。








![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)