フォーカス
2011年、美術の展望
2011年01月15日号
執筆者一覧
阿部一直(山口情報芸術センター[YCAM])/飯沢耕太郎(写真評論家)/五十嵐太郎(建築批評)/大向一輝(国立情報学研究所准教授)/影山幸一(ア-トプランナー)/鎌田享(北海道立帯広美術館)/木村覚(美学、パフォーマンス批評)/小吹隆文(美術ライター)/酒井千穂(美術ライター)/坂本顕子(熊本市現代美術館)/SYNK(デザイン批評チーム)/須之内元洋(メディア環境学、メディアデザイン)/住友文彦(キュレーター)/角奈緒子(広島市現代美術館)/中井康之(国立国際美術館)/能勢陽子(豊田市美術館)/日沼禎子(国際芸術センター青森(ACAC))/福住廉(美術評論家)/光岡寿郎(メディア研究、ミュージアム研究)/村田真(美術ジャーナリスト)/山口洋三(福岡市美術館)/鷲田めるろ(金沢21世紀美術館)
*各掲載箇所の氏名をクリックすると詳しい略歴をご覧いただけます。
須之内元洋(メディア環境学、メディアデザイン/札幌市立大学デザイン学部助教)
2011年の関心事
2011年は、ソーシャルメディアのプラットフォーム化が成熟を迎え、PCやスマートフォンのスクリーン上だけでなく、都市空間、家電、カーナビ等々へと、本格的に浸潤してくるのではないかと思います。これはいまに始まったことでなく、何年も前からの潮流であるわけですが、2010年には、日本でもTwitter、Facebook、Ustreamなどのソーシャルメディアが一気に普及しました。国内では、グリー、DeNAのモバゲーといったソーシャルメディアも活況をみせています。これらソーシャルメディアは、さまざまな周辺メディアのハブとして機能しはじめ、プラットフォーム化がどんどん進行しています。
ソーシャルメディアが、サイネージを始めとした都市空間メディア、家電、カーナビ等々のプラットフォームとして機能するとき、どのような変化が起きるでしょうか? まず、都市や生活文化のさまざまな文脈との関係構築という視点を持った、ソーシャルメディア活用の多様なアイデア、デザインが生成されることが期待されます。また、PCやスマートフォンのように、基本的に個人が一人でスクリーンを眺めるのでなく、みんなでひとつのスクリーンを共有して楽しむというスタイルの提案、あるいは都市空間に新たな場を提供するデザインも期待できます。今後、われわれを取り巻くメディア環境において、コンテント生成の担い手をユーザーが占める割合がさらに増加することになり、プロのクリエイションのあり方にも大きな影響があるのではと思います。
2011年のプロジェクト、執筆予定の著書など
大きく二つあります。
ひとつ目は、筆者が住む札幌で今春3月12日に運用開始予定の、地下公共メディア空間のプロジェクトです★1。札幌市が計画/整備中の、札幌駅前通地下歩行空間は、JR札幌駅周辺と大通りエリアを地下歩道で接続するものですが、190万人都市としては世界でも稀有な、冬季に相当の雪に見舞われる札幌において、この空間が開通することは大きな意味を持ちます。
この地下歩行空間の中程、北2条交差点エリアに、最新の映像・音響メディア機器を備えた公共メディア空間が整備され、市民活動、創造産業、観光、芸術文化、行政広報に関するコンテントが、日々発信されていく予定です。これらのコンテントは、コンテントの発信者が自ら制作に関与し、自らの責任で発信するという点において、CGM型の運用が行なわれる予定です。
これまでに筆者は、インターネットと公共サイネージが実現するパブリックアクセスの可能性の検討、CGMを活用した継続的なコンテント運用を実現するシステムや仕組みの提案といった面で、プロジェクトの一端をサポートしてきましたが、今年いよいよ本番を迎えることになります。
★1──札幌市からのお知らせ:http://www.city.sapporo.jp/kikaku/oshirase/n2ugpr/

地下空間イメージ
二つ目は、音楽領域の再定義を行ないながら、音楽の聴き方・楽しみ方を提案する、アンビエント・レーベル「43d」の推進です★2。「43d」は、札幌を拠点として、CMやメディアアートの分野で世界的活躍をされているサウンドクリエーター大黒淳一氏とともに、昨年11月にたちあげました。すでに、北海道の雪の世界をイメージした実験的音響作品や、世界中のサウンドスケープを日常に展開するウェブサービスを発表してきました。作品のリリース、ラボからのツール・サービスの展開を両輪に、札幌から精力的な発信を行ないます。
★2──43d web=http://www.43d.jp/
関連記事(artscape編集部選)
ミュージアムIT情報:ソーシャルメディアとEveryware──メディア化するアーカイブ
住友文彦(キュレーター)
なにに注目すべきか、取り上げる対象がたくさんありすぎるので、とりあえず近い時期に絞って書くことにした。私がこれまで仕事で関わってきたり、関心を持ってきたアーティストが同時期に別の場所で行なわれるグループ展に参加するらしく、企画意図も互いに関係しそうな気がするので紹介する。
ひとつは水戸芸術館で2月12日から始まる「クワイエット・アテンションズ ─ 彼女からの出発」。木村友紀、アン・カンヒョン、ナム・ファヨンは展覧会に参加してもらったことがあるし、小林史子、スーザン・フィリップ、タチアナ・トゥルーヴェの作品にも関心を持ってきた。とくに女性の表現者という点から注目したことはないのだが、作品制作のプロセスのなかで体験する出来事や展示空間に対する反応が可視化される方法と、それが眺める、移動する、聴くといった鑑賞行為をとても自由にしていることにとても興味を持っている。
もうひとつは3月8日から始まる国立国際美術館「風穴──もうひとつのコンセプチュアリズム、アジアから」。これも名前を挙げると字数がもったいないので省くが、日本人はもちろん海外アーティストはチウ・ジージェ、ヤン・ヘギュ、ディン・Q・レーなど昨年詳しく話を聞いてきたアーティストが多い。こちらは地域に着目した企画らしい。コンセプチュアリズムと言っても、普遍主義的な位置から社会の諸問題を問うのではなく、思考を生み出すための個人的な身振りに丁寧に向き合うような表現が多声的な風通しの良さを作り出しているところに参加アーティストの共通性があるのではないだろうか。
両者は企画の括りが異なるが、1990年代以降、ポスト近代へと大きく舵取りをしてきたアートの世界における貴重な表現の実践に気付くことが可能な展覧会なのではないだろうか。

クワイエット・アテンションズ ─ 彼女からの出発
関連記事(artscape編集部選)
学芸員レポート:落合多武 展/横山裕一 展
学芸員レポート:椹木野衣『反アート入門』/光州ビエンナーレ/メディア・シティ・ソウル 2010
角奈緒子(広島市現代美術館)
政治や社会に対するリアクションとしてのアート
2010年も終わりを迎えようとしていた11月、朝鮮半島で不穏な動きがあったことは、まだ記憶に新しいだろう。怒りや恐怖、そして危機といった複雑な感情を抱くことになった、北朝鮮による突然の延坪島攻撃は、特に韓国の若者たちにとって、自分たちの民族や国家のあり方を今一度考えるきっかけになったに違いない。世界中で起こり続けるこうした事態に対し、アートはどんな力を持ちうるのだろうか。65年前の過去の記憶にいまだ苦しめられる広島の美術館に勤める私は、そんなことをいつも考えている。アーティストのなかには、私たちが何気なく暮らしている社会が孕む諸問題や政治的な動きなどを誰よりも敏感に察知し、これらの問題を取り上げ、作品として発表する者もいる。こうした社会のリアクションとしてのアートはなにも今年だけに起こる限られた動きというわけではないが、特に、先の出来事を受け、民族や国家といった普遍的な問題の考察をうながすような素晴らしい作品が生まれ、少しでも多くの人がアートを通しても、社会や世界について考える機会となることを期待したい。
昨年に引き続き今年も、世界中で国際展の開催が続く。各国際展が掲げたテーマ、シンガポール・ビエンナーレ(3月13日〜5月15日)の「OPEN HOUSE」、ヴェネツィア・ビエンナーレ(6月4日〜11月27日)の「ILLUMInations」、イスタンブール・ビエンナーレ(9月17日〜11月13日)の「Untitled」はどれも興味深く、期待も高まる。日本で8月6日に開幕する横浜トリエンナーレも注目すべき展覧会であろう。「国際展」ではないが、広島、長崎の両都市の原爆記念日を挟むこの時期、広島では「第8回ヒロシマ賞記念展覧会」を開催する。今年の受賞者はオノ・ヨーコ。「愛と平和」を訴え続けてきたオノの、新作やパフォーマンスを含む展覧会となる予定。こちらもお見逃しのないよう、ご覧いただきたい。

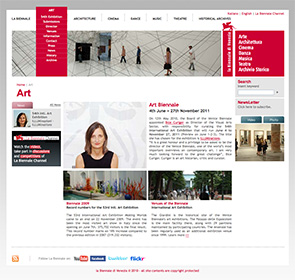
Singapore Biennale 2011 Open House、La Biennale di Venezia
関連記事(artscape編集部選)
学芸員レポート:Dialogue Tour 2010 第2回:かじことhanareの公開交流会ほか
学芸員レポート:ヒロシマ・オー/カラコン/きのこアート研究所
中井康之(国立国際美術館)
2011年の関心事
今年、注目している展覧会は、6月から9月にかけてニューヨークのグッゲンハイム美術館で開催が予定されている「李禹煥」展である。以下は、しっかりとした統計的資料等に基づくものではなく感覚的な私見であるが、歴史的な位置づけを前提とした日本の現代美術の紹介はパリやロンドン、あるいはイタリアの諸都市で開催されてきたことは間違いないだろう。こうした日本美術の紹介は、例えばパリという18世紀から20世紀初頭において美術の中心都市であった地においては、それ以降の流れがニューヨークへと移行したという単線的な流れではなく、他の諸都市(それは非西欧圏であり、かつ先進国でもある日本のような場所)において展開されていた、自己批判的な前衛的動向をクローズアップすることによる、パリを源流とした複数の前衛的な美術の流れが派生したという解釈とその検証だったのではないだろうか。翻って、アメリカが、ギリシャ・ローマから連綿と続く美術の本流としての場所であることを主張することを考えれば、例えばポンピドゥー・センター内の近代美術館で継続的に開催されたパリと他都市の関係性を問い、自らの立ち位置を相対化するような展覧会の開催はアメリカでは成立し得なかったのであろう。しかしながら、そのようなアメリカにおいても20世紀末に近づくにつれ美術の主流という概念自体が溶解を始め、自国の芸術に対して自ずから相対的にならざるを得ないような状況が生まれてきたのではないだろうか。例えば、近年では、ウォーカー・アート・センターで在仏の中国人作家ファン・ヨン・ピン、あるいは戦後日本の前衛美術運動が輩出した偉才工藤哲巳の大規模な個展などが開催されている。いずれもフランス繋がりというところが悲しくもあり可笑しくもあるのだが、それはともかく、個展とはいえ、一人の作家の芸術的な流れを汲み取ることができるような本格的な展覧会に取り組まれたことによって、それぞれ中国の85ニューウェーヴ運動以降の流れ、日本の1960年以降の読売アンパンの狂騒的な状況が汲み取れる展覧会であった(と思われる。残念ながら未見。カタログや見てきた者からの伝聞による類推)。
そのような下敷きがあるうえでの今回の「李禹煥」展は、アメリカ中部の牧歌的な都市ではなく、20世紀美術の中心地であったニューヨークで開催される。担当は、アジア美術部門上級学芸員のアレクサンドラ・モンローである。横浜美術館で15年ほど前に「戦後日本の前衛美術」展を企画したことはすでに過去のことであり、最近では村上隆が企画した「リトル・ボーイ」展を開催したジャパン・ソサエティの元館長というような紹介のされかたもしたりするが、5年ほど前にグッゲンハイム美術館に就任し、上記の「戦後日本の前衛美術」展の各論として「李禹煥」展が遂行されると考えるのが自然だろう。実際、同展は、当初の予定では2011年1月11日から開催の予定であった。それがさまざまな事由により延期され、当初の予定からおよそ半年後の6月24日からの開催となったのである(2011年1月現在の情報)。モンローの助手を務めるナンシー・リムの弁によれば、「この展覧会は円形ギャラリーだけではなく両サイドのギャラリーもすべて使用される予定で、最初の計画では50点ほどの展示を考えていたが、準備期間を延長したことによって、そのおよそ2倍、100点近くまでに拡大された」という。日本国内では、李禹煥の個展は、岐阜県美術館や神奈川県立近代美術館あるいは横浜美術館などで開催されてきたが、これだけの規模の展覧会は開催されたことはないだろう。2003年にソウルのサムソン美術館(当時サムスン・グループ本社の地下に併設されていた。現在のサムソン美術館リウムの前身)で、初期から新作、李のアトリエにあった所蔵作品までを公開した個展でも、出品点数は70点程であった。
さらには、今回のグッゲンハイム美術館における展覧会では、立体作品に関しても過去の主要な作品を集めることを考えている。ちなみに、当館(国立国際美術館)からの出品は絵画1点と彫刻1点であるが、この彫刻というのが巨大な鉄板2枚と巨石2個で構成されている。おそらくは、これまでの李禹煥の個展で、このような巨大彫刻作品を借用して展示をするという展覧会はなかったであろう。その種の作品に関しては、開催館が所蔵しているものを展示するか、あるいは新作を用意したのである。費用や設置期間を考えたときに、李の過去の巨大な彫刻作品を集めた回顧展というのは非現実的なのである。当館で所蔵しているその彫刻作品を館内に展示する場合にも、通常の美術展示を委託する業者がさらに重量物取扱部門の専門員を確保するような体制で準備する。彼らの下見も含めると、1点の設置に延べ2日必要となる。もちろん、複数点あれば効率は上がるが、例えば、今回展示するおよそ100点の内、20点がこのような巨大彫刻作品であると考えれば、作品の設置は1カ月用意しても十分とは言えない。
上述したように、当初の予定ではもう間もなく展覧会が始まるような日程であるので、さすがにカタログの編集は進んでいるようだが、展示点数が倍増したことを考えると図版部分はリスタートに近いものになったであろう。また、図版のやりとりを思い返すと、どうやらレゾネに近い機能を持たせたようなカタログを考えているようでもある。当事者の立場を考え始めると怖くもあり、このあたりで考えることを中止するが、このような壮大なる規模の展覧会を考えることが、われわれには現実的にはないことは、けっして幸せであるとはもちろん言えないだろう。
2011年のプロジェクト、執筆予定の著書など
今年は「世界制作の方法」という展覧会を準備している。このタイトルは20世紀アメリカの哲学者ネルソン・グッドマンの著書からの引用である。「世界制作」という名称はやや誇大妄想的にとらえられてしまう部分があるかもしれないが、ネルソン・グッドマンのこの単語の使用は認識論的な観点からの複数のモデルの提示という複線があり、本展ではその複数制を援用するようなかたちで9組ほどの作家たちに展示を依頼している。
関連記事(artscape編集部選)
学芸員レポート:夏の夜の夢──CAAK Lecture 35 中崎透「遊戯室について」(Dialogue Tour 2010 第4回)を聴講して
学芸員レポート:国立美術館巡回展/FLAT LAND──絵画の力/實松亮+安部貴住「循環と置換」
能勢陽子(豊田市美術館)
2011年の関心事
「現代における人間性はどうなってしまうのだろうか?」ということを、改めて問い直さなければならないような時代であると思う。多様性を帯びているようでどこか画一化されていて、呼吸困難に陥りかけているような状況のなかで、アートは一種の気付け薬のような役割をはたすだろう。そうした作品になりうるのは、ナイーブな内面世界を描き出すようなものではなく、現実に立脚しながら壮大な夢を見させるもの、また愚鈍なほどの実直さで人間存在に迫るようなものではないかと思う。そうした力を発揮できる作家として思い浮かぶのは、私にとっては曽根裕と高嶺格であり、40代になった彼らの大規模な個展、「曽根裕──Perfect Moment」(東京オペラシティ アートギャラリー、2011年1月15日〜3月27日)、「高嶺格──とおくてよくみえない」(横浜美術館、2011年1月21日〜3月30日)が年明け草々に開催されるので、非常に楽しみである。
また最近は、美術館での建築展が増えているが、それも同様に建築というものがどんなに夢のようなプロジェクトに見えようとも、それがあくまで現実社会に実現されうるものだからではないかと思う。建築家が、壮大さと現実との関わりという点で、現代作家を凌駕してきているような印象を持っている。「メタボリズム展──都市と建築」(森美術館、2011年7月23日〜11月6日)、そして他でも建築展を準備しているところがあると聞くが、美術の領域からの建築への関心は、これからも続きそうである。
そして、最近海外作家を含めたグループ展が少なくなっている気がするが、それはいまアートをひとつのテーマ性で語ることが困難になってきていることと、予算が厳しくなっているという現実的な問題があるからだろう。しかしそういうときこそ、キュレーターの視点がより明快に出るグループ展を見てみたいと思う。女性作家ばかりを扱う「クワイエット・アテンションズ ─ 彼女からの出発」(水戸芸術館、2011年2月12日〜5月8日)、またアジアのコンセプチュアル・アートに焦点を当てた「風穴──もうひとつのコンセプチュアリズム、アジアから」(国立国際美術館、2011年3月8日〜6月5日)には、特に注目したい。
2011年のプロジェクト、執筆予定の著書など
今年は担当展を持っていないから、今後の準備に充てる時期なのだが、比較的時間の余裕があるので、美術館から離れて地域に関わっていけるような活動のあり方を、同時に模索していきたいと思う。


曽根裕展、高嶺格展
関連記事(artscape編集部選)
学芸員レポート:あいちトリエンナーレ/石上純也──建築のあたらしい大きさ
学芸員レポート:高木正勝ピアノソロコンサートツアー「Ymene(イネメ)」 名古屋公演/トランスフォーメーション展/石上純也──建築のあたらしい大きさ
日沼禎子(国際芸術センター青森(ACAC))
2010年は、暑かった! そして、国内は本当にたくさんの「アートプロジェクト」が開催された。青森の最大のトピックは東北新幹線全線開業だった。現在、官民一体となって観光客誘致に力を注いでいる。アートプロジェクトどころではなく、青森市最大の祭りである「ねぶた祭」を、2度にわたり、原宿表参道に出張(地元では「出陣」)させる勢いだったが、東京の人々の反応はどうだったのだろう。
さて、近頃は、アートも観光やまちづくりと結びつき、産業の一端を担っている。新しい産業が発展することは良いことだ。その一方で、経済効果、費用対効果という価値感での評価を得ることとは遥か遠く離れ(あるいはまったく関係なく)、けれどもアートによって光を求める人、場に対して、私たち職業的にアートの仕事に関わる者ができることはなにかを、もっと考える必要があると思っている。例えばアーティストが深く思索し、物をつくるためには、成果を求めない制作環境やトライ&エラーができる場が絶対的に必要である。しかし、いま、多くの発表の場が全国でつくられているにもかかわらず、その前段階としてのそれらの制作の場や実験的な発表ができる環境は、実は疲弊の一途をたどっているのではないか。例えば90年代前後から希求されてきた「アートセンター」「オルタナティヴ・スペース」「アーティスト・イン・レジデンス」という場やシステムが、これからの時代、どう人材と呼応し、発展していくかを検証することはとても重要であると思う。このことは筆者自身の功罪を告白することでもあるし、新たな決意へと向かうことでもある。多くのプロジェクトや場が育ち、あるところはその役割を終えることもあろうが、そうした繰り返しのなかで、多くの経験を共有し、現場を支える多様な人材が育ち、支援者も生まれ、より社会と繋がっていくようになれば素晴らしいと思う。
関連記事(artscape編集部選)
学芸員レポート:ネットワークをカタチに──秋冬・青森のアートシーン:「ラブラブショー」&「文化芸術による創造のまちあおもりプロジェクト」
学芸員レポート:Nadegata Instant Party「24 OUR TELEVISION」──アーティスト、市民スタッフ、地元メディアがつくる24時間の出来事


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)