
artscapeがスタートした1995年から現在(2025年)にかけて、美術館・博物館の組織としての役割自体が「作品を中心とした資料の収集・保管」から「作品に関する情報の(特にオンラインでの)公開・活用」に変化し、これに対応するため、法制度を含め、制度上・組織上さまざまな変化があった。本稿では30年間の変遷を、美術館・博物館を中心とした制度上の変化にできるだけ絞ってわかりやすく示すことを目的としつつ、2000年6月15日号以降の「Museum Software & Technology 美術館IT施設情報」、2001年12月15日号からからはじまった連載「美術館IT情報」(2003年09月15日号以降「ミュージアムIT情報」)、2008年08月08日号からの「デジタルアーカイブ スタディ」を中心とするartscapeの過去の記事に触れながら辿っていく。
はじめに~概観
1995年は「インターネット元年」と呼ばれる。マイクロソフト社がWindows 95を発売した。インターネットは既に存在しており、首相官邸やホワイトハウスのウェブサイトも前年に開設されていたとはいえ、ウェブサイトを閲覧する機能までが付属した初のパッケージソフトが市販されたことで、大手家電メーカーがインターネット接続サービスに参入した。それに続いてNTTの「テレホーダイ」の開始、数々の検索サービスや大手新聞社サイトの開設、個人ニュースサイト界と日記界の発生といった形で加速度的に普及していった。ここから、情報通信環境の変化が日常生活のあらゆる側面に広がっていく。Javaも登場し、amazon.comも開設されたこの年にartscapeが生まれた。
個人的な回想となるが、当時、まだ海外旅行もしたことがない中学3年生だった筆者は、同年秋に刊行された慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の村井純による『インターネット』(岩波新書)を書店で手にし、そのユートピア的な側面に強く感化され、即購入したことを記憶している。なお、その時に隣に置かれていて一緒に購入したのが、前年に同じく岩波新書から刊行されていた西垣通『マルチメディア』であった。
当時は「インターネット時代」「マルチメディア時代」が到来しつつある、という言い回しがよく使われていた。後述するが、現在定着した和製英語である「デジタルアーカイブ」が生まれたのも、この時期と考えられている。
1.黎明期(1995-2005年)
(1)「マルチメディア時代」における初期のビジョン
1995年2月にベルギー・ブリュッセルで開かれたG7 Ministerial Conference on the Global Information Society(情報社会に関する関係閣僚会合)において合意された11項目のひとつには「電子博物館・美術館構想」が含まれていた。当時は「文化資産の保存に役立つあらゆるデータを集積し、国際的なマルチメディア・データバンクを構築する」というヴィジョンが唱えられていた。
日本国内でも、先駆的な取り組みは既に始まっており、例えば1994年からコレクションの画像データベースの構築をスタートしてきた東京国立博物館は1995年から情報発信を試験的に開始し、1996年からはカラー写真検索システムを公開した。

(2)デジタルアーカイブの発展―JDAAの発足と文化情報の公開に向けた取り組み
「デジタルアーカイブ」は1996年に日本で設立された「デジタルアーカイブ推進協議会(JDAA)」(会長:平山郁夫)の準備会議のなかで、当時東京大学教授であった月尾嘉男が「かつての図書館などの電子版」という意味から提案した用語ともされているが(artscape 2004年1月号「ミュージアムIT情報」)それ以前から用例はあったのかもしれない★1。とはいえ「デジタルアーカイブ」が定着したのは以後のJDAAの功績によるところが大きい。JDAAは設立以降、有形・無形の文化資産をデジタル情報の形で記録、その情報のデータベース化、そして情報ネットワークを利用して発信するというデジタルアーカイブの構想を発信し続けた。
2000年10月20日、東京国際フォーラムで100周年記念式典と同時に「女子美デジタルアーカイブ」サイトがオープン。これはartscape2000年11月15日号「Museum Software & Technology 美術館IT施設情報」で取り上げている。
2001年4月にはJDAAより初の「デジタルアーカイブ白書2001」が刊行される。なお、7月にはオンデマンド版も刊行され、artscape2001年07月25日号「Museum Software & Technology 美術館IT施設情報」で紹介している。
(3)デジタルアーカイブ整備初期の課題
この時期画像等の「公開」については自ずと限界があった。インターネットの通信速度、データ量の問題から、当時の「マルチメディア」は「CD-ROM」等のパッケージメディアが主流であり、クラウドストレージサービスも登場前であった。また、ディスプレイ性能等による画質の制約は当然のこととして、現在に至るまでの課題である、権利処理の壁もより高かった。 美術作品の著作権処理に関する現場の課題は、artscape2001年5月15日号から7月25日号にかけて3回に分けて「Museum Software & Technology 美術館IT施設情報」のコーナーに掲載された記事「美術作品と著作権」(株式会社DNPアーカイブ・コム 国谷泰道)でも触れられている。
・「美術作品と著作権(1)――いつ、いかなる状況で、問題になるか」
・「美術作品と著作権(2)――いかなる団体が、どのような機能を果たしているか」
・「美術作品と著作権(3)――著作権者と使用者、それぞれの主張の間で」
2000年頃までは、美術館・博物館が独自のWebサイトを公開し、そのなかでそれぞれが独自に収蔵品等を公開するなどしていたが、2002年ごろからは、著作権処理を含めて整理されたデジタル資料を多数有する機関による積極的なデータベース公開の動きが加速していく。
| 2002年 | 国立国会図書館は電子図書館である「近代デジタルライブラリー」を開始 |
| 2003年 | NHKが埼玉県川口市に「NHKアーカイブス」を開館。文化庁「文化遺産オンライン」開始 |
| 2004年 | 国立国会図書館総合目録ネットワーク事業の一般公開が開始(その後2012年1月に「国立国会図書館サーチ(NDL サーチ)」に移行) |
他方で、公開されていくデータベースの仕様が不統一であるといった問題も表面化し、データベースの横断検索を可能にしていくために、この時期にはメタデータ規則の標準化への取り組みも進められていった。
ちなみに地方館ではそもそも仕事にコンピュータを用いておらず、Eメールすら使用していないところが多かった時代である。理想と技術の進展とは裏腹に、日本のミュージアムにおけるデジタルアーカイブ整備への道のりは、まだ一部で始まったばかりであったといえよう。
2.ネットワーク化と法改正の始動(2005-2017年)
(1)「公文書管理法」とアーカイブ意識の高まり
2005年 国立公文書館が「国立公文書館デジタルアーカイブ」の公開を開始。この頃から関係者のなかで「MLA連携(M=museum[博物館] L=library[図書館] A=archives[公文書館])」という言葉が使われるようになった。
2008年8月15日号からはartscapeで不定期連載として影山幸一による「デジタルアーカイブスタディ」のシリーズの掲載が始まる。第2回にあたる2009年3月15日号でこのMLA連携について触れているが、当時の現状を「特に美術館を含むミュージアムでは図書館に比べ情報化の進展が遅れており、より現場に即した対策が求められている」と指摘している。

2009年はリーマン・ショックや歴史的な政権交代があったが、デジタルアーカイブの制度や組織に関連する出来事も多い年であった。麻生太郎首相(当時)と文化庁が主導し、補正予算により117億円を計上した国立メディア芸術総合センター(仮称)の事業が政権交代により中止になるものの、6月の著作権法改正(2010年1月施行)では図書館、公文書館、博物館による情報保存のためのデジタル化が著作権者に無許可で可能になった(著作権法第31条第1項第2号)。また7月には国立国会図書館法が改正され(2010年4月施行)、インターネット資料についての取扱が規定されたが、それだけではなく国立国会図書館のデジタルアーカイブ事業「大規模デジタル化事業」には国の補正予算127億円が投じられた。また公文書管理法の制定(2011年施行)も同年である。
artscape2011年12月01日号の影山幸一「デジタルアーカイブスタディ」では、2009年からの動きを振り返る形で、国立国会図書館の長尾真館長へのインタビューを行なっている。
(2)美術館・文化財領域の動き
このような一連の「記録を残し、活用する」というアーカイブへの法改正や予算措置は、行政全体や現場の意識を変えるとともに、図書館・公文書館に比してデジタル化が進まない博物館・美術館・文化財領域に対しての危機感も増したといえよう。 そして2011年に文部科学省から告示された「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」第9条においては、新たな項目「情報の提供等」が追加された。
|
(情報の提供等) 第九条 博物館は、当該博物館の利用の便宜若しくは利用機会の拡大又は第七条の調査研究の成果の普及を図るため、次に掲げる業務を実施するものとする。 一 実施する事業の内容又は博物館資料に関する案内書、パンフレット、目録、図録等を作成するとともに、これらを閲覧に供し、頒布すること。 二 博物館資料に関する解説書、年報、調査研究の報告書等を作成するとともに、これらを閲覧に供し、頒布すること。 2 前項の業務を実施するに当たっては、インターネット等を積極的に活用するよう努めるものとする。 |
この基準の策定公表は博物館法で定められたものであるが、それ以前の「公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準」を改めたものであり、この年から、公立美術館だけでなく私立美術館も対象に加えられたうえで、情報提供が定められたという点で画期的であった。
ところが、翌2012年に部分改正された博物館法では、それ以前と変わらず、保有する収蔵品・資料のメタデータ整備等、デジタルアーカイブに必須といえる業務について、規定がないままであった。言い換えれば、この法改正においては、デジタルアーカイブの業務は(法的に必須な)基本的業務ではなく、付加的業務という位置付けにとどめ置かれてしまったのである。これが解消されるのは2023年施行の現行博物館法への改正を待たなければならなかった。
同じころ、EUでは、2013年6月に「公共セクター情報の再利用指令」を改正し、EU内の全公共文化施設に対して所蔵作品デジタルアーカイブのオープンデータ化を義務付けた。なお既に2500万件の文化遺産情報を有していたポータルサイト「Europeana(ヨーロピアナ)」はオープン済みであり、さらなる拡充が約束された。artscape2013年08月15日号の「デジタルアーカイブスタディ」でも、これを伝えている。
(3)振興法・新たな機関の模索とそのレガシー
国内の関係者も手をこまねいていたわけではなく、2010年に設立された一般財団法人デジタル文化財創出機構やその関係者の働きかけにより、2012年に超党派国会議員による「デジタル文化資産推進議員連盟」と、生貝直人(現・一橋大学法学研究科教授)や弁護士の福井健策らによる民間団体「文化資源戦略会議」が発足★2。2013年後半には「デジタルアーカイブ振興法」の立法および「国立デジタル文化情報保存センター」の整備が模索された。しかし既に進められていた構想もあるなかで、複数省庁間の縄張り調整、著作権処理の難航、予算・体制の不透明さや関係者間でのコンセンサスが十分でなかったこと等の原因により政治的合意形成ができず、法案化以前に頓挫してしまった。
振興法や新たな機関の構想は放棄されたものの、関係者の尽力により2016年には知財戦略本部で「デジタルアーカイブジャパン(DAJ)」構想がまとめられ、2019年の「ジャパンサーチ」正式公開につながるとともに、例年、補正予算が編成される度に文化財等のデジタル化・アーカイブ関連の予算が組み入れられるようになった。目に見えた制度や機関の新設こそ見送られたが、国政においてデジタルアーカイブへの投資が基盤的部分への投資として理解されることが定着した時代であったといえるだろう。なお、2017年には「デジタルアーカイブ学会」も発足している★3。

3.DX時代の到来と著作権法の緩化(2018~2022年)
(1)著作権法改正による「権利制限規定」の拡大
保存に関して2009年改正で可能になったとはいえ、公開を含む利用拡大に向けてはまだまだ著作権処理の困難さが大きな壁となっていた。そこで、デジタルアーカイブの利用推進を目的とする改正が行なわれた。2018年改正(2019年施行)第47条(展示に伴う利用)の改正では、それまでも認められていた展示解説のための小冊子掲載用への限定的な複製(印刷)に加えて、美術館等が、展示作品の解説や紹介のためにタブレット端末等でサムネイル画像を表示することが無許諾で可能になった。
また、2019年1月に美術や写真の著作権者の団体などが全国美術館会議などの間で合意した「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」において、収蔵作品の場合には、展示する目的で収蔵している原作品(寄託作品を含む)も第47条各項の対象とすることとし、「美術館、博物館は、展示する目的で収蔵している作品のデジタル画像について、本ガイドラインに従い、自館のウェブサイト上で公開することができる」とした。ただし画像サイズは32,400画素以下の「サムネイル」に限られており、また、このガイドラインはあくまで今回ガイドラインの策定に参加した権利者および利用者★4において合意した利用の範囲を示したものであり、それ以外の法人・個人間に適用されるものではない。またガイドラインに策定した団体間であっても上記サムネイルを除き著作権侵害となるため、画像についての権利処理そのものが不要になったわけではない★5。artscape2019年09月15日号の「デジタルアーカイブスタディ」では、「美術の著作権2019──データベース・アーカイブ・美術館」として甲野正道(大阪工業大学知的財産学部教授)がこの改正を詳細に伝えている。
なお、その後2021年の第31条(図書館等における複製)の改正では、国立国会図書館等から個人の利用者へ直接デジタルデータを送信する図書館等公衆送信サービスについて、絶版等資料以外でも一定条件下で無許諾で可能となった。これは美術館・博物館等の図書館サービスにも影響がある。
(2)著作権法と権利保護の課題
このように一部の例外は定められたが、現在でも、著作権保護が及ぶ作品等について、著作権者に許諾を得ずオンラインデータベース上でその画像を公開することはできない。
また、著作権に関する正確な知識の普及も必要である。筆者がとある美術館で収蔵品管理のデータベースを見学させていただいた際に気付いた例を紹介しよう。著作権の保護期間は2018年12月30日をもって「著作者の死後50年」から「死後70年」に延長されたのだが、その際に、いったん死後50年(※海外作家の場合「戦時加算」を考慮する必要がある)を経てパブリック・ドメインとなった作家の作品については、遡って70年に延長されることはない。例えば1960年に死亡した作家の作品は(1961年1月1日から残存保護期間を数え始めるので)2018年12月29日時点で死後57年+363日が経過している。よってこの作家の作品についてはパブリック・ドメインとなっているので、2018年12月30日になっても(またそれ以降も)著作権の保護は復活せず、自由利用が継続される。このことは文化庁のウェブサイト上にも明確に解説されている。
ところが、そのように本来パブリック・ドメイン作品であったのにも関わらず、ある館で利用されている所蔵品データベースシステム上は単純に「(作者死後70年が未経過のため)著作権が残存している作品」として示されてしまっていたのである。
これは「データベースシステムの実装における単純なエラー」として済ますわけにはいかない。というのも、死後50年以上が経過している作家の著作権相続人を全員見つけるというのは実質的に不可能であり、もしそれを見た学芸員等の担当者がシステム上の表示に疑問を抱かず、本当はパブリック・ドメインであることに気が付かなければ、その後10年以上も「著作権処理ができていないため公開ができない作品画像」として扱われてしまうだろう。 これは比較的単純な例であるが、実際はいわゆる「戦時加算」等もあり複雑なケースも多く、このような著作権処理の必要性に関する正確な留意点を業界全体で常識にしていく必要はまだまだあるのではないだろうか。
(3)コロナ禍とDXが加速させた「デジタルミュージアム」
2020年のCOVID-19パンデミックによる休館措置は世界中で起き、バーチャルツアーやオンライン展覧会を普及させ、制度改正などと関係なく、それまで「来館者のための補助ツール」だったデジタルアーカイブが、「来館できない人への主たる提供価値」へと変わった。また、行政やデジタル化が遅れた業界へのデジタル・トランスフォーメーション(DX)が叫ばれ、2021年には政府にデジタル庁が設置される。
デジタル化への機運が高まるなかで2020年8月に正式オープンした「ジャパンサーチ」は、さまざまなデジタルアーカイブと連携し統合的に検索を可能にしたシステムで、「デジタルアーカイブジャパン推進委員会・実務者検討委員会」が中心となり、国立国会図書館がシステムを開発・運用し各連携機関の協力によりメタデータをつなぐハブとなった。2020年12月01日号の「デジタルアーカイブスタディ」(影山幸一)が、正式公開後の「ジャパンサーチ」についてレポートしている。
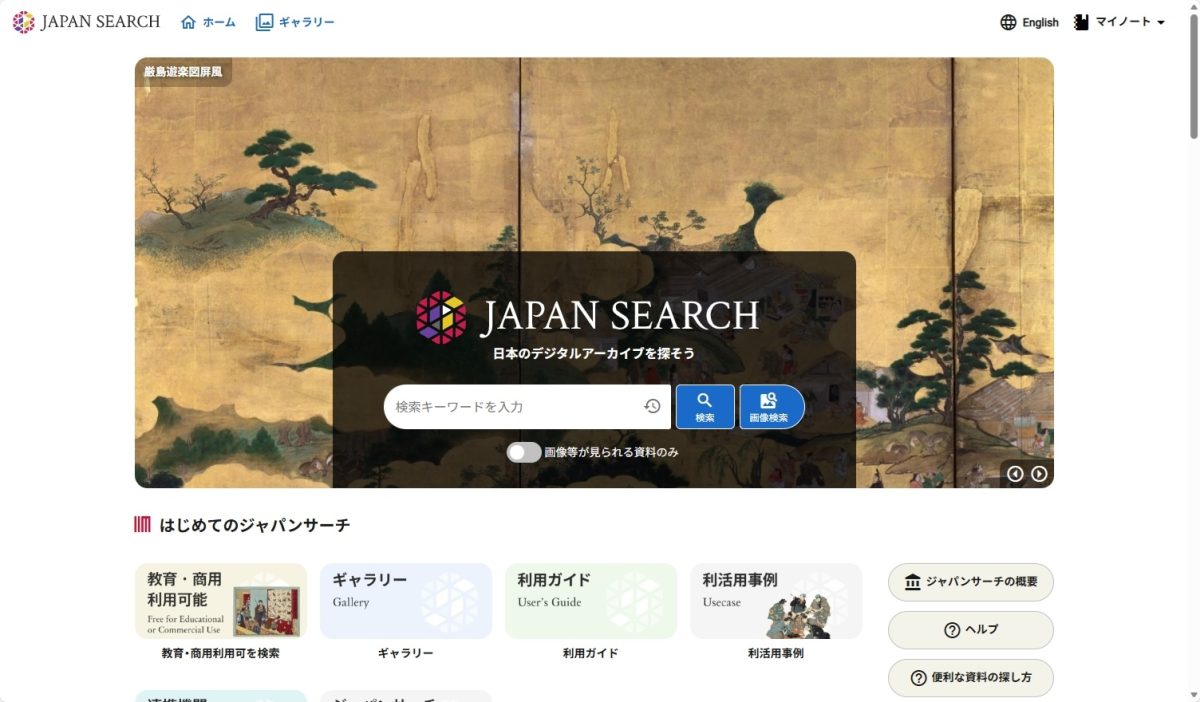
4.博物館法の抜本改正と「SHŪZŌ」の誕生(2023年~現在)
(1)デジタルアーカイブの義務化
2022年、70年ぶりの博物館法抜本改正(2023年4月施行)が実現。これをもって、ようやくデジタルアーカイブが博物館の本来的業務として法的に位置づけられた(第3条3項)。
|
(博物館の事業) 第三条 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。 (中略) 三 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。 (後略) |
文化庁の特設ウェブサイトでは、これについて以下のように説明している。
|
デジタルアーカイブの作成と公開 博物館が持つ資料をデジタル化して保存するデジタルアーカイブの作成は、利用者がインターネットを通じて資料の情報へアクセスするため、あるいはインターネットを通じて博物館が自館園の魅力を発信していくための基盤となる取組です。 これまで、博物館法の中で列挙された博物館の事業の中には、このデジタルアーカイブの作成の取組は、明確には位置づけられていませんでした。 しかしながら、通信環境が整い、モバイル端末が広く普及してきたことで、メディアとしてのインターネットの重要性は非常に大きくなっています。また、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの博物館が閉館を余儀なくされる状況が広がった中で、特にインターネットを利用した博物館活動の意義が再認識されています。 新たな制度では、デジタルアーカイブの作成と公開を、博物館が行う事業の一つとして新たに明確に位置付けて、取組を推進していきます。 |
また本改正は博物館登録要件も緩和しており、今後、より多様な主体(企業ミュージアムや大学博物館など)の登録が促進され、多様な所蔵品やアーカイブを有する組織の保護と継続的な情報公開に結びつく可能性も開かれた。
個人的見解ではあるが、このようにデジタルアーカイブを本来的な業務とする改正が行なわれたからには、今後は単にメタデータの提供だけでなく、所蔵品の収蔵や寄託の際には、できるだけ広範かつ確実にデジタルアーカイブ上の画像等の利用許諾を得ておくべきである。むしろそれこそが博物館・美術館の責務といえるであろう。
(2)国立アートリサーチセンター(NCAR)と「SHŪZŌ」
2023年3月、独立行政法人国立美術館のなかに国立アートリサーチセンター(National Center for Art Research: NCAR)が設立された。
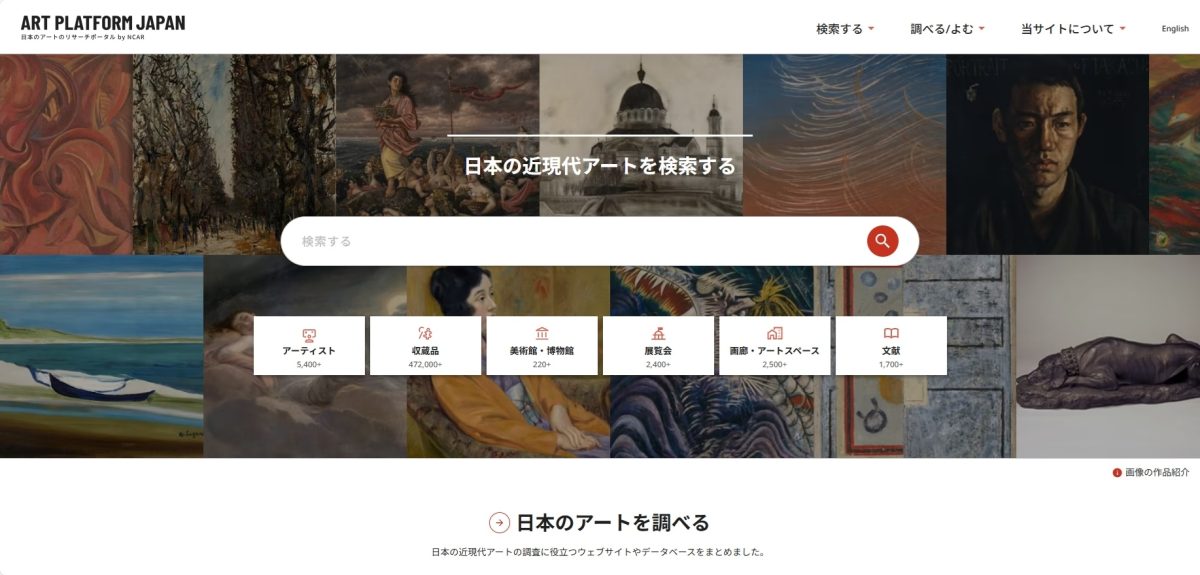
日本の美術館は欧米に比べ小規模で分散しており、「ナショナル・コレクション」としての統合的な発信力が弱いという課題に対応するため、「SHŪZŌ(Japan National Art Collection Search)」は、全国の美術館の所蔵作品の所在情報を日英両言語で横断検索することを可能とした。また、「ジャパンサーチ」(国会図書館運営)とも連携し、日本の美術資産(約6万点以上)のメタデータを、利活用しやすい国際標準形式で整備していくハブ機能も有している。これまで個別の館で死蔵されがちだった作品データが、教育、観光、学術研究等、それぞれの文脈で「つながる」インフラとなった★6。なお、前章で紹介したメディア芸術データベースについても、2023年度よりNCARが「メディア芸術データベースに係る調査研究事業」にて運営している。

むすび:保存から公開、そして「循環」へ
1995年からの約30年間で、日本の博物館法制度におけるデジタルアーカイブの位置づけは大きく変わった。特に著作権法(第31条、第47条等)と博物館法(第3条)の改正により、デジタルアーカイブ構築・公開は、法的リスクなどを理由に消極的になることは許されず、むしろ社会に対する義務となった。
ただ、例えば「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」で合意された、無断利用可能な「(32,400画素以下の)サムネイル」は、200ピクセルの正方形のサイズですら違反となってしまい、あまりにも通常の情報検索環境とかけ離れた低画質過ぎる水準と感じる。おそらくこちらは、著作権法上の別の条文(譲渡目的付随複製の47条の2)が2009年に制定された際に、政令(文部科学省令)によりデジタル方式で複製する場合およびデジタル方式で公衆送信する場合の基準を32,400画素以下と定めたことをそのまま取り入れたのではないかと推測する。
しかし、47条の2が定められたのは2009年6月であり★7、16年も昔の基準である。
なお私見では、現在の情報環境でこの基準で低画質に複製・公表することはむしろ著作権法上の翻案権ないし著作者人格権(同一性保持権)の侵害となる可能性を懸念している(精細度を政令で定めることとしている47条の2と異なり、47条は関係団体が合意によって決めている点も、そのリスクを高めるものと考えられる)★8。むしろ「権利者に対する補償システムが現状十分でない」という点を議論すべきではないか。これは近年のAI学習に関する論点とも重なる。
今後のデジタルアーカイブの課題は、ある程度整備された法とシステムの上で、「二次利用(商用利用やクリエイティブなリミックス)」をどこまで許容するのかという、運用ポリシーの設計、そして、著作権者の権利と社会全体が得ている利益のバランスが崩れた場合に、どのようにそれを補償していくのかという「補償の仕組み」に移っていくとかと思われる。なおこの点については、コロナ禍に既に「授業目的公衆送信等補償金制度」が実現しており、完全ではないとはいえ、著作権管理団体への補償金制度もスタートしている。
さらに近年、新たな国際的課題となっている「芸術家の適正報酬と社会保障」の観点とも合わせ、デジタルアーカイブの次の30年は、公平な補償金制度の実現が重要な論点となっていくのではないだろうか。
★1──例えば1994年12月に幕張メッセで開催されたイベント「マルチメディア’94」のなかで「世界の文化を未来に継承するデジタルアーカイブ国際会議」が行なわれている。
★2──artscape2015年03月01日号では、同年1月26日に文化資源戦略会議が東京・日比谷図書文化館で開いた「アーカイブサミット2015」をレポートし、関係者による次の動きに向けた雰囲気を伝えている。https://artscape.jp/report/topics/10107909_4278.html
ちなみに文化資源戦略会議のWEBサイトは閉鎖されたが、国立国会図書館のウェブアーカイブプロジェクト「WARP」にてアーカイブされている。https://warp.da.ndl.go.jp/waid/30509
★3──なおほかにも、2010年度より5カ年計画で文化庁「メディア芸術デジタルアーカイブ事業」が行なわれ、単なる画像保存ではなく、エミュレーション(旧環境の模倣)やマイグレーション(新環境への移行)といった技術的検証が国の予算で実施されるようになった。そしてその成果の一環として、2015年3月、マンガ、アニメーション、ゲーム、メディアアートの作品情報等を収録した「メディア芸術データベース(開発版)」サイトを公開した。公開当初には、マンガ単行本約25万冊・マンガ雑誌約8万冊の情報と所在情報、またTV 放映アニメ・劇場版アニメ・OVA 作品約9,000タイトルの情報、家庭用ゲーム対応ソフト・アーケードゲーム・PC ゲーム約3万5千タイトルの作品に関する情報が登録されていたほか、メディアアート・現代アート関連の展覧会・イベント情報26件も公開された。
★4──一般社団法人日本美術家連盟、一般社団法人日本美術著作権連合、一般社団法人日本写真著作権協会、公益財団法人日本博物館協会、全国美術館会議、一般社団法人日本書籍出版協会。
★5──その場合でも作家名、作品名、所在情報等、著作権の生じないメタデータはオンラインデータベース上に公開することは可能である。
★6──余談ながら筆者もNCAR設立以前に「文化庁アートプラットフォーム事業」でSHŪZŌの構想段階から関わり、全国の美術館への協力依頼などの事務にも携わった。今は離れた立場にいるが、今後益々の発展を祈っている。
★7──同じ月に発売された最新のiPhone3GSの解像度は320×240=76,800画素である。当時の画素でいえばiPhoneの画面の42%程度をサムネイルとして許容していた。仮に現行の第19世代モデルのなかで最も画素数の少ないiPhone17の画素(2,622×1,206=3,162,132画素)で同じ割合とすると133万画素、1,150ピクセル角の正方形よりも大きい面積である。さすがにこれではサムネイルとはいえないにしても、41万画素(640ピクセル角程度)程度で考えるのが妥当ではないかと思える。
★8──もとより、このガイドラインは策定に参加した権利者団体、利用者団体間の合意でしかなくそれ以外の法人・個人に適用されるというものではないが、文化庁よりも現場に近い団体であるからこそ、国民全体の利益を考え、47条の2についての政令に対して改正の必要があるという合理的状況判断を踏まえて関係各団体間の再調整が望まれるところである。
2008年以前の関連記事
「著作権とアート」「ミュージアムIT情報」 https://artscape.jp/artscape/reference/archives/kageyama_bn.html







