トークシリーズ:「Artwords」で読み解く現在形
1. 写真の終わり?──『デジグラフィ──デジタルは写真を殺すのか?』
飯沢──『デジグラフィ──デジタルは写真を殺すのか?』(中央公論新社、2004)がどのようにできたかから話しましょう。大きな動向として、デジタルカメラは1990年代の初め頃から実用化され始めていましたが、その頃のデジタルカメラはご存知のように精度が非常に悪いものでした。15万〜30万画素程度でしたので、ほとんど玩具のカメラのようだったと思います。インターネット環境が一般化してくるのが90年代後半頃なので、デジタルカメラを活かしてネットワークの中で使っていく動きも、その段階ではそれほど大きな動きにはなっていませんでした。この本にも出ている小林のりおが、先駆的にwebにデジタルカメラで撮った画像を毎日日記のように公開したのが90年代終わり頃です。だから、実質的には、90年代はデジタル化のプレ段階だったという印象があります。
おふたりと比べれば、ずいぶん遅いと思いますが、僕がパソコンを使い始めたのは2000年です。個人的にも写真を含めたいろいろな仕事をやっていく環境が、2000年以降と以前ではまったく変わってきました。言ってみれば、2000年以降にパソコンやデジタルカメラを使い始めたことはある種のショックであり、これまでの写真のあり方とまったく違うものが起こり始めている予感というか、ある種の確信を持ちました。そのことについて、自分なりに答えを出さなくてはいけないという思いで書いたのが『デジグラフィ』です。明らかにそれ以前以後では写真の位相が違っていて、アナログカメラで撮影する方法とは違う写真、僕の言葉で言えば「デジグラフィ」という写真のあり方が出てきた。それがどのようなことなのかということを5つのポイントで書いたのがこの本です。具体的には、
1──改変性(画像を自由に変更できる)
2──現認性(画像をその場で確認できる)
3──蓄積性(画像を大量に記録・保存できる)
4──相互通信性(画像を簡単に送受信できる)
5──消去性(画像をすぐに消せる)
という点ですね。
この5つのポイントが正しかったかどうかはわかりませんが、その時点では、それ以前のアナログ的な写真のあり方(Photography)とデジグラフィ(Digigraphy)を分ける大きな違いなのではないかと認識して書いたということです。
小原──「消去性」に関しては、飯沢さんもどこかで発言していたかもしれませんが、アナログよりもデジタルデータの方がむしろ消去しづらい側面もありますよね。特にウェブにアップしてしまうと、どこかで誰かが保存していたりして、何度もゾンビのように甦ってきたり、サーバーやHDの中などで残り続ける。昔書いた文章とか消してほしいのに(笑)。
飯沢──「消去性」については、みなさんがいろいろ指摘されたところですし、僕自身も一番問題だと思っているので、ここで反論する意図はありません。要するにデータ化されている写真のあり方と、フィルムや印画紙のようなかたちで物質と映像が一体化している写真とのあり方の違いを言いたかっただけの話です。その時に「消去性」がある意味わかりやすいというか、考えをまとめていくためには便利な概念だったのでそれをあえて使ったということです。
小原──写真とは違いますが、最近ニューヨーク近代美術館(MoMA)がテレビゲームを収蔵し始めましたよね。パックマンとかシムシティとかテトリスやなんかを。「インタラクション・デザイン」★1の一例ということのようです。要はデータを集めるということですが。
飯沢──データすらコレクションの対象としているということですよね。僕がその当時考えていたことよりも、いわゆる記号的な画像、データのあり方が、相当強固なアーカイブ性を持っていたということがわかったということもあります。だから、あっという間に消えてなくなるというような、簡単なことではなかった。このことは認めてもいいと思っています。
当時は、アナログ的な写真のあり方と、デジタル的な写真のあり方の対比に主眼を置いていましたのですが、今はその対比という考え方自体が違っていたのではないかと思っています。当時は、アナログとデジタルとを完全に違うものとして捉えていた。また、その頃から携帯電話で写真を撮れるようになった。そうなると、画像の生産と消費の体系そのものが変わってきてしまったので「アナログ/デジタル」という対立軸で捉えることができなくなってきたのではないかというのが端的な印象です。それは2004年の段階で萌芽が見えてきていて、その数年後にはっきりわかったという感じですね。
土屋──2004年当時のことを振り返ると、この頃はまだインターネットに夢がありましたよね。時間軸を正確におさえているわけではありませんが、2000年代に入ってからブロードバンドが一般化します。そこで、写真をアップしても比較的サクサク見られるようなネット環境が整備された。その中で、小林のりおのように、写真家が自分でウェブサイトを立ち上げ写真を毎日アップしていくようになった。
飯沢──小林のりおの「DIGITAL KITCHEN」★2はほぼ毎日アップされていましたからね。それも、いまだに続いています。
土屋──でも、いまだに続いているかどうかわからないところがポイントです。当時はすごく新奇でした。そこには、ネット空間に写真をアップするということの特殊性というものがありましたよね。私は2004年の段階では毎日、彼ら/彼女らのアップした写真を巡回していました。しかし、そのような興味がどんどんなくなっていった。おそらく写真というメディアの特殊性が、ネット上の空間では維持できなかったということでしょう。つまり、ネット上では写真もまた画像一般になってしまうわけです。pixivにアップされるものや、フェイスブックやツイッターでもいいですが、そこにアップされるネタ写真のようなものと、コツコツと真面目に撮影している写真家が表現として写真をアップするということの差異がなくなったということです。
飯沢──差異がなくなるということもありますが、表現としてやっている人たちにとって当時小林のりおが書いていたロマンチシズムというものがサクっとなくなってしまったということでしょう。まともにそういうことを考えて、いまだにネット上で何か写真の表現を展開できると考えている人は、ゼロとは言いませんが、あまりいないような気がします。要するに、当時僕らが感じていた新しい表現メディアとしてのネットの可能性は、はっきりいって雲散霧消した。ブログの写真を細かく毎日チェックしている人がいたらお目にかかりたいくらいです。
小原──「DIGITAL KITCHEN」をずっと見てきているわけではないのですが、初期の段階と今の段階では画像自体が変わってきているでしょうか?
飯沢──小林のりおの写真はそんなに変わっていないような気がします。画像のあり方が変わるってどういうことですか。
小原──単純にデジタルカメラの性能の問題です。
飯沢──僕はネットはそういう質的な差異をほとんど無化してしまうのではないかと思っています。解像度の低いもので撮ろうが、携帯やスマホで撮ろうが、立派なデジタル一眼レフで撮ろうが、構図をきちんと整えて撮ろうが、何をやろうが、そこでの差異は、ほとんど虚しいことになってしまうわけです。だから、当時僕が考えていたことは、もしネットの空間にデジタル画像をアップするということが新しい表現として成立するとしたら、誰かがそれについての批評言語をつくらないといけないと思ったわけです。批評言語をつくるということは、ある意味それをずっと見続けないといけないということですが、正直、僕はそんなことをやる気はまったくありませんでした。小原さんや土屋さん、あるいはもっと下の世代の人がやったのかといえばやってない。だから、この空間の中で表現上の何かが生まれてくるというのは、正直幻想だったんだろうな、というのが今の僕の感想です。
小原──中平卓馬★3さんが1971年のパリ青年ビエンナーレ★4で展示した「サーキュレーション」★5は撮った先から次々と展示していくものでしたが、デジタル写真をネット上にアップしていくことの先駆けだという見方もできるのでしょうか
飯沢──それも違うのではないかと感じます。中平さんの『サーキュレーション』が改めて出てきたときに、「その時代に中平さんがデジタルカメラを持っていたらどうなっていたのかな」ということをやはり考えました。あの行為をネット上で中平さんが展開したのだろうかと。
小原──やらないでしょうね。
飯沢──やらないし、やったところであまり意味もないと思います。『サーキュレーション』は、撮った写真をその場で現像してその場で飾っていくということで、ある種の空間を占拠していく物質性が必ず入ってくるわけです。そのように空間を写真で埋めていく感じが、ネットの場合はないですよね。ですから、そこに対して何か反応して言葉を書いていくのは、正直僕にとってはすごく難しいし、できないなと思います。
土屋──はっきりしたことは、表現としての写真が、結局のところ近代的な考え方からまったく抜け出ていないということですね。つまり、作家と作品というものが一対一対応していて、それに対して我々がよいとか悪いとか判断しているということが、むしろはっきりした。
飯沢──そう。そこで逆に、むしろ僕が最後の写真評論家でしかないということもはっきりした。つまり、近代的な写真表現のところで作家の仕事をフォローしていくようなことをやるのが僕の仕事であるということです。そこから先はどうなるかわかりませんが、ソーシャル・ネットワーク上で蠢いている映像表現ということをもしも誰かがフォローしてくれるのだとしたら、バトンタッチするしかない。それは僕の仕事じゃないと思います。だから、『デジグラフィ』を書いたことで、自分の仕事の範囲がよくわかりました。
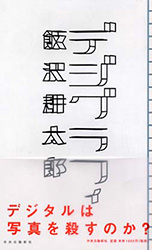

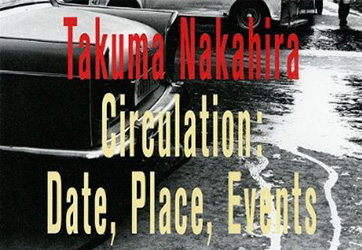
飯沢耕太郎『デジグラフィ──デジタルは写真を殺すのか?』(中央公論新社、(2004)
小林のりお「Digital Kitchen」
中平卓馬『サーキュレーション──日付、場所、行為』(オシリス、2012)
★1──「Artwords」内、インタラクション・デザインを参照。
★2──こばやし・のりお:1952- 写真家。武蔵野美術大学映像学科教授。写真集『LANDSCAPE』で日本写真協会賞新人賞(1987)、『FIRST LIGHT』で第8回木村伊兵衛賞(1993)受賞。1997年よりweb上にデジタルカメラで撮影した写真「DIGITAL KITCHEN」を「experimental work」として公開。http://www.artbow.com/kitchen/index.html
★3──なかひら・たくま:1938- 写真家・写真批評家。1968年、多木浩二、高梨豊らと写真同人誌『PROVOKE』を創刊、戦後写真のあり方に大きな転換をもたらす。主な写真集に『来るべき言葉のために』(風土社、1970)、『新たなる凝視』(晶文社、1983)など多数。写真批評集については『なぜ、植物図鑑か 中平卓馬映像論集』中平卓馬(Artwords参照)。
★4──「Artwords」内、パリ青年ビエンナーレを参照。
★5──1971年、パリ青年ビエンナーレに参加した中平卓馬が、現地で撮影し、その日のうちに展示するという約1週間の実験的なプロジェクト《Circulation: Date, Place, Events》の作品群。写真集として『サーキュレーション──日付、場所、行為』(オシリス、2012)が刊行されている。
2. 静止画/動画
土屋──デジタルの技術によって起こったことのひとつはデジタルとアナログのハイブリッドです。元々デジタルカメラは、アナログカメラのシミュレートで発展しています。一方写真家は、デジタルカメラで撮る人もいれば、アナログで撮る人もいるわけですが、制作プロセスには、かなりの程度デジタル技術が介在している。
飯沢──銀塩カメラで撮って、モノクロームの銀塩のプリントを暗室作業で現像して、最終的に壁に飾る──最初から最後までアナログ──という写真家の方が珍しい。フィルムの画像をスキャニングしている人もたくさんいるし、デジタルプリントするのは当たり前になってしまっているわけです。ハイブリッドとはそういうことですね。そのことも含めて2000年当時の状況に対して僕は割と純粋に「こっちはアナログ」「こっちはデジタル」と色分けをしようと思っていました。一瞬ですが。しかし、それも1〜2年後にはほとんど意味がないことが見えてきた。そこで考えたことは、「では、そのなかでの写真的なものというのはどのようなものなのか」ということです。結局、デジタルでもアナログでもないハイブリッドな状況で写真的なものがいろいろな人たちに評価されたり、何か言葉が生まれたりする場合の典拠となるもの、基本となるものは何なのかと言うと、静止画像だと考えています。そして静止画像であることの意味を考えました。しかし、ここ2〜3年ですが、写真家が動画を使い始めている。
小原──動画を撮るためにカメラを買うというのではなく買ったカメラにたまたま付いていたということで撮り始める写真家が多いですよね。松江泰治★6さんのように。
飯沢──確かに松江さんの例が一番よくわかりやすいと思います。僕は、実は松江さんの動画にはそういう意味ですごくショックを受けました。静止画像の鬼みたいな人だと僕はずっと思っていたので、その彼が平気で動画を使って、IZU PHOTO MUSEUM★7で2012年に発表したような作品を作り始めている状況を見ていると、静止画と動画という境界線もこれまたそんなに強固な境界線だったのか、と今は考えています。
小原──最初はビデオカメラに静止画機能が付いた時にはほとんど一時停止のような形だったので、画質が粗く使えませんでしたが、最近はデジタルカメラに動画機能が付くようになって画質は飛躍的に向上しましたね。ただもはや一眼レフでの動画機能は付属的な要素として付いただけのものとも言い難くなってきている。
飯沢──松江さんは、最初はそんなこと気にしないで、動画撮影機能が付いていたから少し遊んでみようかなという感じで始めたらこれが意外とおもしろかったと、言ってます。
小原──最近のゴダール★8などの撮影風景をネットで見ましたが、音声は別録りで一眼レフカメラを使っていました。動画と静止画の差はほとんど無くなってきているのかもしれません。
土屋──私は差があると思う。静止画像の場合は、日本の文脈で説明すると、東松照明の群写真以降の話だと思いますが、要するに、相互に写真が関係しあうということがある。前から後ろへ進むというナラティヴではなく、あるイメージからあるイメージへジャンプできるという、インタラクションの発生は動画では無理です。
飯沢──動画でも、モンタージュ的な操作をしていけば可能ではないですか。
土屋──もちろん、動画のシークエンスの中で、カットつなぎとか、モンタージュということはあり得ますが、空間的な距離が離れたものが関係しあうということはありませんよね。
飯沢──確かに動画の場合は、同時に二つは入ってこないですからね。モンタージュは時間軸の中での相互関係なので、東松照明★9の写真は写真集だとよくわからないけど、壁に並べることを考えればわかりやすい。静止画像の場合は同時に目に入って来る。これは僕の持論ですが、静止画像は記憶に残るというか記憶に食い込む。記憶をつかむ力が動画と比べると強い気がします。
小原──いつでも自分のペースで見られますし。
飯沢──そういうこともありますよね。もちろん動画的なものと静止画的なものを厳密に考えていけば相当違いはあると思いますが、表現者レベルで考えると松江泰治でも宮本隆司★10でも、僕らが考えているよりもずっと簡単に動画と静止画の間を行ったり来たりできます。これはやはり2010年代に近づいたこの時期、僕の『デジグラフィ』以降の顕著な現象のような気がします。それ以前は、そんなに簡単に二つの領域を行ったり来たりすることは、やれるようでやられていなかったのではないかと思います。もちろん、本橋成一さんみたいなドキュメンタリーの人が映画をつくって、写真集をつくることはあります。ですがあれはそういうレベルではないです。
小原──動画と静止画の両方を表現の手段としている人も多くいると思います。僕が自分でビデオカメラを回す際に思うことは、たとえば一秒間に30コマの動画を数分間撮り、そこから静止画に抜き出そうとしても、面白いカットがあまりなくて選べない。つまりどこかで止めるべき瞬間を選びたいのですが、静止画としてはものすごい量を撮っているにもかかわらず選べるカットが出てこないことが多々あります。スチルの人が動画を撮った際にものすごくクオリティに落差があることがあるのですが、逆もまた然りだと思いますね
飯沢──動画でずっと撮っているわけですから、そこから決定的な瞬間が選べないというのはおもしろい話ですね。ただ、『デジグラフィ』でも書きましたが、デジタルカメラによって、新聞社やスポーツ写真のあり方が変わってきてしまいましたよね。陸上の100m走などでもそうですが、スポーツの場面をほとんど動画みたいなかたちで撮影している。そして、一場面を選んで紙面に載せるのは写真家ではなく、編集者です。それは、たとえばカルティエ=ブレッソン的な決定的瞬間を撮ったものと、質の差はあるのか。僕はそこがよくわからない。
小原──動画から静止画を選んで、その写真を見てもおもしろいという作家もまだ出てきてないのかもしれません。機材の発展に作家性が規定されてくるという事態は写真史においてよくあることではありますが。
飯沢──松江泰治さんの場合は、写真のような画面でずっと据えっぱなしにしておいて、そこに羊が少し動く、車が動いていくという作品なので、考えてみたら動画だろうと静止画像だろうと構造的な変化はない。そういうものではなく、ドキュメンタリーのようなスナップショット的に撮るとつまらなくなる。
土屋──そう考えると、写真家がデジタルカメラで撮る動画も、独立した動画作品として捉えられるかどうかは、やはりあやしいですね。それは「写真家が撮った動画」です。
飯沢──今のところはそうですね。宮本隆司さんの「木を見て森を見ず」(2010)★11もそうです。だから、僕はそこから先はわからないと思います。
小原──僕は、画面の細部が少しずつ変化していくという、松江さんの作品は批評性があると思うのですが、ただ、他の写真家で動画を撮っている作品が本当におもしろいかというと残念ながら僕はあまりそうは思いません(笑)。
土屋──写真家の動画もいろいろあるけれど、今は初期のビデオアートのような感じになっている。基本的にカメラは回しっぱなしです。そこに何かしら遅延が起こり、差異みたいなものが抽出できるかもしれないということを探っている状態です。
飯沢──写真家による動画は、ある意味始まったばかりなので、もう少し様子を見ないといけないかもしれない。そういう意味では、川内倫子★12が「照度 あめつち 影を見る」で展示した動画作品は松江さんや宮本さんとは違います。シークエンスのつなぎで見せていく。素朴と言えば素朴。だから、それにもう少し物語性のような要素も入ってきたりすると、少し違うものになっていく可能性もある気がします。
小原──基本的には風とか光とかの話になってしまう。「印象派の映像」というか何というか。リュミエール★13の映画を見た方がよっぽどいいのではないかと思います。ゴダールがいうように「リュミエール=印象派の最後の画家」としては。
飯沢──でもわからないですよね。そこから新たな展開もあり得る。沖縄の山城知佳子★14さんなんかはおもしろいと思いますけどね。
小原──あの人は変わっていますね。
土屋──でも、基本的に彼女は映画を撮る発想ですよね。写真家という意識は彼女にはまったくない。
飯沢──静止画像のほうがむしろ映画的な発想なのですね。映画のスチールみたいなものです。映画は映画で発達してきた百何十年という歴史性を踏まえなければやはり映像作品としての強度、クオリティを保てないわけだから、松江さんにしても、川内倫子にしてもこれからでしょう。そこから映画的な語彙というようなものをどれくらい取り入れて作品化できるかということにかかってきますからね。
小原──リュミエールだって何か起こるわけですよね。シークエンスがあり、何か出来事が起こっているわけです。多くの写真家の動画作品はそこまでも至っていない。本当にただ「風が吹きます」とか「水面がキラキラします」というだけだったりする。リュミエール的な映画の野生のようなものに回帰しようとしているのか、それとは関係なく行われていることなのか、ほとんどが後者だと思います。
飯沢──少しまとめて言えば、デジタル以降の可能性としては、静止画像の可能性と動画を超えるような可能性が出てきていることは間違いないので、『デジグラフィ』以降の問題として考えなくてはいけないことのひとつだと思います。


「松江泰治展──世界・表層・時間」(IZU PHOTO MUSEUM、2012)チラシ
川内倫子「照度 あめつち 影を見る」展(東京都写真美術館、2012)チラシ
★6──まつえ・たいじ:1963- 写真家。1996年第12回東川賞新人作家賞受賞、2002年第27回木村伊兵衛写真賞受賞、2012年第28回東川賞国内作家賞受賞。主な作品集に『CC』『gazetteer』(大和ラヂヱーター製作所、2005年)『JP-22』(大和ラヂヱーター製作所、2006年)『cell』(赤々舍、2008年)など。
★7──静岡県長泉町東野クレマチスの丘(スルガ平)347-1に2009年にオープンした写真美術館。美術館の内装・造園設計を杉本博司が担当。http://www.izuphoto-museum.jp/
★8──Jean-Luc Godard:1930- フランスの映画作家。『勝手にしやがれ』でヌーヴェル・ヴァーグ映画の旗手に。以降、一時商業映画と距離を置き、映画のあり方、制度を問い直す実験作・異色作を制作。1988-1998にかけてビデオ映画『ゴダールの映画史』 Histoire(s) du cinémaを制作。カッセルのドクメンタXでこの作品を観た批評家の柄谷行人は、「ゴダールの『映画史』は、20世紀のモニュメントとして、この世紀末に屹立するだろう」と評した。
★9──とうまつ・しょうめい:1930-2012 戦後日本を代表する写真家。写真集に『〈11時02分〉NAGASAKI』(写真同人社、1966)、『太陽の鉛筆 沖縄・海と空と島と人びと・そして東南アジアへ』(毎日新聞社、1975)、『廃園』(PARCO出版局、1987)、『Visions of Japan』(光琳社出版、1998)。Artscape2013年2月15日号の「FOCUS」に甲斐義明氏の東松照明追悼文が掲載されている。
★10──みやもと・りゅうじ:1947- 写真家、神戸芸術工科大学教授。建築雑誌の編集を経て写真家に。作品は都市-建築の廃虚、崩壊する姿を捉えたものが多く、1995年の阪神淡路大震を記録した『KOBE 1995 After the Earthquake』は、磯崎新がキュレーションした1996年のベネチア・ビエンナーレの建築展でも展示され金獅子賞を受賞。作品集に『建築の黙示録』(平凡社、1988)、『九龍城砦』(平凡社、も1997)、『CARDBOARD HOUSES』(BEARLIN、2003)など。
★11──震災後15年を経た神戸の自然を動画撮影した作品。飯沢耕太郎の展評が以下に掲載されている。http://artscape.jp/report/review/author/1197769_1838,1,list1,85.html
★12──かわうち・ともこ:1972- 写真家。2002年第27回木村伊兵衛賞受賞。2013年第29回写真の町東川賞国内作家賞。芸術選奨新人賞受賞。作品集に『『うたたね』(リトル・モア、 2001)、『あめつち』(青幻舎、2013)など。
★13──Auguste Marie Louis Lumière, Louis Jean Lumière. フランスの映画発明者。兄弟。映像をスクリーンに投影して上映する「シネマトグラフ・リュミール」を考案、実写の映画制作も手がけた、映画の功労者。
★14──やましろ・ちかこ:1976- 映像作家。映像作品に《I Like Okinawa Sweet》(2004)、《アーサ女》(200)、《あなたの声は私の喉を通った》(2009)など、自らの出身地である沖縄を主題とする作品を制作。







![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)