トークシリーズ:「Artwords」で読み解く現在形
5. 写真アーカイブスと著作権──写真は誰のものか
──建築業界では「国立近現代建築資料館」というものが湯島にできました。建築家は、作品が図面などでしか残りませんから。写真も、写真集として残っている人はよいですが、残っていない写真家の人もたくさんいますよね。そういう人たちの資料はどうなるのでしょうか。つまり、写真美術館はできましたが、写真家のアーカイブはないのでしょうか。
小原──どの写真家もそうだと思いますが、本人が亡くなった後に遺族が処理に困って捨てられるか、美術館やギャラリストが関わる場合もあります。ただ、ギャラリストやコレクターが入ってもハゲタカみたいに買い捌かれたりなどいろいろあるようです。遺族の方でも「これは作品だから美術館に預けよう」という意識はまだ定着していないと思います。
飯沢──でも、キャパシティの問題もありますから難しいですよね。アナログ時代であれば、写真家のフィルムをすべて扱うということになります。でもフィルムを預かっても、それを活用しなければあまり意味がないわけです。預かるだけならできるかもしれませんが、それをどうインデックス化して公開していくかというシステムはまだできていません。日本写真家協会は、数年前から「日本写真保存センター」という名前であらゆる写真家のアーカイブを活用していくための研究を始めています。そして、いろいろなところに働きかけをして、公的機関としてつくろうという動きはあります。ですが僕は少し懐疑的です。それができたところで、どのように運営していくかという問題が検討されていないからです。
アーカイブは閉じてはダメです。どういうシステムで公開していくのかは、写真の場合ものすごく難しい。今やっているのが日本写真家協会なので、その著作権管理機関になってしまうような気もします。そうなると、いろいろ大変なことになると思います。今でも木村伊兵衛の写真を借りると1点5万円かかります。そんなことがすべての写真でやられはじめたら、出版などがすごく不自由になってしまう。
小原──借用の際に借用料がかかって、またさらに掲載の時にも掲載料がかかる。余計に閉じてしまいますよね。借りる側も躊躇してしまいますし。
飯沢──「両刃の剣」ということを彼らが自覚していればいいんですが、職能団体はどうすればお金に結びつくかを考えてしまうので、資料として公開するより、コピーライトの対象としてお金に代えようというアーカイブになる可能性が非常に高いです。それは由々しき問題だと思います。
では、どうしたらいいのかという答えはないのですが。
小原──デジタル画像も商品化されていくということですよね。
飯沢──そうです。要するにカラオケのように使われたら一回何円、というシステムになっていく可能性があります。
小原──アマナイメージズはデジタルのイメージだけではなく現代作家のプリントも集め始めていますよね。
飯沢──将来的にそれらをビジネスに結びつけるということはみんな考えていると思います。ですが、それを自由に利用できる、コピーライトという近代的な権利意識から外れて、自由に使用できるというような、ある意味アナーキーな部分は写真が元々持っていた性格です。ですが、管理体制の中に取り込まれてしまうと、その部分がどんどん薄くなっていくと思います。
小原──初期の写真にはコピーライトがないですよね。ベアト★54のネガをスティルフリード★55が引き取ってプリントして売るとか面白いことになっている。
飯沢──著作権管理者がいないわけですからね。写真家が亡くなってから50年経つと、著作権が外れていくわけですが、そうではないものはすべて著作権の網の目の中に取り込まれていくという可能性が高い。写真の場合、それは非常に問題だと思う。
土屋──有名な写真家にしろ無名の写真家にしろ、仮にとりあえず取っておきましょう、ということになったとしても、では、写真の作品としての所在はどこにあるのかという話になるのだと思います。おもしろい例として、私はそれほどカメラ雑誌を見る方ではありませんが、たまに見ると毎月、木村伊兵衛の新作が出ているわけです。死後40年近く経っているのにいまだに新作が発表され続けているという(笑)。こんなおかしなことが起こっているのも、日本独特の文化だと思います。
小原──木村伊兵衛の代理として誰かが選ぶということですか?
飯沢──そうです。著作権の管理者ということですね。
小原──木村伊兵衛本人は作品としては出したくなかった写真の可能性も十分あるでしょうね。
飯沢──そうですね。僕は作家の意志も絶対的なものではないと思っています。最近では、ゲイリー・ウィノグランド★56の作品を、トッド・パパジョージ★57が再解釈して選んだ展覧会を開いていて、これはこれでおもしろい。つまり、作家本人の選ぶというキャパシティを超えた何かが出てくる可能性があります。そのあたりはポジティブに評価できる。
小原──作家はやはり、同じものを選ぶ傾向がありますよね。写真は撮影の時からほとんどの作業が選ぶことと関わっていると言えます。構図にしても機材にしても被写体にしても選ぶことが重要になってくる。ですから、第三者がコンタクトから選んだ場合はかなり違うものになると思いますね。
土屋──第三者が選んだ方がおもしろくなる場合もあります。そうなると写真のコピーライトとは、どこに帰属するのか。法的には撮影した人に帰属するということはわかりますが、もう少し理念的に考えると著作者はもう少し柔軟なもので、揺らぐものですよね。要するに、作家の主体というものはかなり揺らぐ。そこが写真のおもしろいところです。
飯沢──その通りですね。一点モノの絵画とは違うおもしろさですよ。それは、かつてからずっとあるわけだから、大事にした方がよいと思います。
小原──委ねることができるということですね。先日の宮崎学展では、選んだのも、画像を加工したのも僕でした。もちろん撮影したものすべてから選ぶわけではありませんが。宮崎さん本人は「僕は一次生産者ですから本の編集や展示は二次生産者に任せるんだ」とおっしゃっていました。
飯沢──それをもっと積極的に考えれば写真に関わる人たちの批評行為、二次創作行為でもあるわけなので、そこを閉じてしまうとつまらないで。
小原──非常にアンビバレントですよね。両方成立するのが写真のおもしろいところです。
──最近亡くなられた東松照明の作品などはどのように保存されていくのでしょうか。
小原──彼はおそらく自分の作品をどう残すかということに後半の人生を費やしたと思います。そのかいがあって終の住処となった沖縄ではいろいろなプロジェクトが動き始めていますね。東松さんが「写真100年展」を組織した時からその問題はずっと脳裏にあったのではないでしょうか?
飯沢──しっかりした奥さん(泰子さん)がいるので大丈夫だと思います。奥さんが東松さんの代理人の役割を果たしていくでしょう。東松さんの後期は、奥さんが動かしていたとも思います。それくらいの大きな立場です。
小原──東松さんは本当に先のことをずっと考えていた人ですよね。写真史の中に自分をどのように位置づけるかということに意識的だった写真家ですし、自らに連なる後進の写真家を多く輩出しました。WORKSHOP写真学校の看板なんかも保存してあるぐらいですから相当なものですよ。自分について書かれた記事なんかもちゃんと保存しているはずです。
飯沢──70年代に森山大道さんや荒木経惟さんと一緒にやっていたワークショップ写真学校の看板。僕も、それは実際に見たことがあります。
小原──個人のレベルではなかなか難しい事ですよ。しかも授業の録音までしている。東松さんのように生きているうちに先のことを考えて管理して、動くことのできた人はいいのですが、そうではない人が非常に多いので、たとえ優れた写真家でも残されたフィルムや作品の末路は厳しいものがあります。
飯沢──雲散霧消も含めて写真だとも言えます。だからあまり変に「絶対こうしなくてはいけない」と決める必要はないのかもしれない。
小原──例えばダムに沈みゆく村をせめて写真で残そうと撮っていたような場合、写真までなくなってしまったら数十年後村自体がなかったことになってしまうことだってありえますよね。撮影されることもなく忘れ去られてしまった村は数多くあると思います。
★54──Felice Beatow:1832-1909
イタリア生まれのイギリスの写真家。19世紀後半、アジア諸国の開国、植民地戦争、建築や肖像写真活などを撮影した、初期の報道写真家、戦争写家。1963年来日、横浜の居留地に写真館を開き、「横浜写真」を撮る(「Artwords」内、横浜写真を参照)。同時に、日本各地の風景や、人々の風俗を多数撮影した。
★55──Baron
Raimund von Stillfried:1839-1911 オーストリア-ハンガリー帝国出身の写真家。1869年来日、71年、横浜居留地に写真館を開館。北海道開拓使のお雇い写真家などを努めた後、77年にはベアトの写真業務を引き継いだ。
★56──Garry
Winogrand:1928-1984 アメリカの写真家。コンテンポラリー・フォトグラフィの中心人物。ウィリアム・クライン、ロバート・フランクなどの影響のもとに写真を撮り始め、1967年MoMAで開催された「New
Documents」展に、ダイアン・アーバス、リー・フリードランダーと共に出展、新しいドキュメータリー写真家として、また、社会的風景派として注目される。
★57──Tod
Papageorge:1940- アメリカの写真家・写真批評家。ゲリー・ウィノグランドの『PUBLIC RELATIONS』の編集にも携わり、序文を執筆。
6. 3.11と写真
飯沢──その問題は震災と写真という問題に関わりますよね。東北各地で今まさに起きつつあります。それもいろいろな問題を孕んでいるので、僕もなかなかこれが一番正しいということを言えませんが。
土屋──私は、写真家が撮ることによって記録に留められるということを過剰に言うのも危険だと思います。映画監督のジャン=リュック・ゴダールがずっと主張していることですが、アウシュビッツが撮られた映画は、必ずどこかに存在するはずだと言うわけですよ。つまり映像が一般化した時代において、撮られないものは存在しないという発想です。
飯沢──その想像力は大事かもしれないですね。ただ、物理的になくなってしまうことは、ダムに沈んだ村や、実際に津波で消えてしまった集落もあるわけですから、ゴダールのように言ってしまうのもしょうがないと思います。僕が今考えているのは、震災後にニュースで話題になった津波で流された写真を拾い集めて修復して返すという運動(写真救済プロジェクト)のことです。あれも両刃の剣のような気がしてしまします。
小原──本来は、人に見せるようなものではなく、アルバムの中でひっそりと家族だけに見られていたものでしょう。写真の公私の境が津波に攫われてしまった。
飯沢──消えなくてはいけない写真も沢山あったはずなんだ。
小原──それが公開されて体育館など公の場に並んでいる。これには驚きました。
飯沢──強制というのは残酷な話ですよね。
小原──捨てたはずなのに何度も戻ってくるという(笑)。
飯沢──志賀理江子★58さんの『螺旋海岸notebook』(赤々舎)の中の話ですね。あれおもしろい話ですよね。
小原──最後は「これはゴミです」と書いておかなければ誰かが拾って手元に戻ってきてしまうという。
飯沢──あの時に美談として処理された写真修復運動はもう一度考え直したほうがよいと思います。写真を修復するという行為に対しても疑問があります。津波に洗われて消えたわけですが、それは写真の運命だったし、津波に洗われなくても退色して真っ白になることもある。高橋宗正★59さんという方が、赤々舎で津波に流されて退色してしまった白っぽい写真を展示していました(「LOST & FOUND」展)。あれは写真本来のあり方ですね。だからわざわざ修復しなくてもいいんだと思います。
小原──ただ、他人の写真を勝手に持ってきて被災地から離れた東京で展示されたことがありましたが、僕はそれもまた微妙な気がします。動かしてはいけないものもあるのではないかと思いますが。
飯沢──その場所で真っ白なままに置いておくのがひとつのかたちですよね。
小原──作者が不明であることを口実に、ギャラリーに無断で持ち込みインスタレーションのように展示したのにはちょっと首をかしげました。
飯沢──それが、彼の「作品」になってしまったわけですね。震災後の写真の運命を考えるとそれは象徴的ですね。もうひとつ、震災によって写真の意味が変わるという現象があちこちで起こったでしょう。例えば、尾仲浩二★60が撮った90年代東北の風景で『海町』というシリーズ。これは、津波によって撮った場所がなくなってしまった。結果、その写真の意味が変わってしまった。表現としてのあり方を考えるのであれば志賀理江子さんの話をすればいいと思いますが、それ以上に写真の存在が問われ直したということも間違いありません。最初にデジタルの話をしましたが、デジタルではなく、残ってきているものはやっぱりモノとしての写真です。
小原──志賀理江子さんの津波で流されたハードディスクは復活したそうで驚きました。モノクロは津波に洗われても洗浄すればほぼ完全に元通りになっていましたが、カラーは表面が溶けてしまっていました。
飯沢──人間の身体は歳をとるに連れてボロボロになって、病気になって死んで、灰になって埋められておしまいですが、そういった人間の身体の持っている運命と、写真一枚一枚の持っている運命に、割と近い部分があったということを改めて感じました。
小原──写真に一生があるとしたら、それを早回しした感じですね。
飯沢──だから、「早回ししていいのか?」と。津波で強制的に早回しさせられたようですが、人間も突然病気になったり交通事故に遭って死んでしまうわけですから、それは素直に受け入れたほうがよかったのかなという気が今はしています。
小原──やはり微妙ですよね。「写真が残ってよかった」と言う人も当然いますし。
飯沢──確かにそれも否定はできないで。僕も最初は、あのようなニュースを聞いた時に「いい話だな」と思ったけれど、いま、2年経ってもう一度考えなおしてみると、すごく微妙です。
小原──少なくとも、第三者がそんなに自由に扱っていいものではなかったはずです。
土屋──ともあれ、写真はアナログでも、デジタルのデータでも、残ってしまいます。それは善悪の彼岸にあっていい/悪いではありません。捨てても亡霊のように帰ってくるというのは特性でもあり、写真の最も気持ち悪いところであり、逆に言えばそこに可能性がある。
飯沢──気持ち悪いところであり、おもしろいところでもありますよね。それがいろいろなところで見えてきたのはとても大きかったと思います。最近そのあたりのことをちゃんと書いておいた方がよいと思い始めました。僕はたまたま東北出身で、仙台市宮城野区に実家があるので、震災直後はある感情の昂ぶりの中で目が曇ったとは言いませんが、揺れた部分がありました。今、僕だけではなくいろいろな人たちがまた震災について考え直す時期にきているのかなという気がします。2年という時間がよい意味で作用し始めるとおもしろいと思います。
小原──いろいろな人が被災地を被写体にしに行きましたね。
飯沢──そのことの是非が、当時から言われているわけですが、僕は行った人について何か言う気はありません。
小原──荒木経惟さんの「2011.3.11」は日付だけを3.11にして東京で撮るという偽日記の形式でした。あれは個人的にはしっくりきました。IZU PHOTO MUSEUMでの「荒木経惟写真集展 アラーキー」の最後のコーナーに展示したのですが、「私写真」というよりも高度経済成長以降の東京のドキュメントという色合いが強くなった気がしました。その帰結として3.11があるような。
飯沢──「東京でも震災は撮れるんだ」ということをはっきり教えてくれました。
他にも何人かおもしろいことをやった人たちがいます。大きな出来事があった時に、それぞれの反応の仕方が、後々いろいろ見えてくるわけですよね。震災だけではなく、1945年8月15日の終戦の時も、今見直すとおもしろい反応がありますよね。濱谷浩★61は太陽を撮っている。濱谷浩のその反応はおもしろいですよね。太陽を撮ったその日にすき焼きを食べています(笑)。
小原──濱谷浩は実は……。
飯沢──相当のワルですね(笑)。そういう人がいる一方で、朝日新聞社を辞めてしまった影山光洋★62みたいに茫然自失した写真家もいます。います。ひとつの出来事の写真家に及ぼす影響力が、2年くらい経って少しずつ見えてきているので、しつこく検証したほうがよいだろうと思っています。震災関連では、僕は畠山直哉★63の『気仙川』(河出書房新社、2012)のテキストには少し困りました。言葉は元々強制力が強いので、あの畠山さんがこれをやっていいのかな、と少し思いました。震災以後の行動を逐一書いているので、写真をニュートラルに見ることができなくなってしまう。
小原──ある意味で、畠山さんがずっと作家として避けてきたことですがそれをやらざるを得なかった。正直びっくりしました。
飯沢──そうなんですよ。これも微妙ですが、それだけのインパクトがあったということなのでしょう。ただ、やはり言葉の持つ力が強いことは間違いない。
土屋──3.11では冷静だった人なんて誰もいなかったわけで、よいとか悪いと言うのはあまり生産的ではないと思います。
飯沢──僕が言いたいのは、もう過去の出来事として終わったように考えられることは良くないので、しつこく考えるべきだということです。それは、写真家もわれわれ写真関係者もそうです。それははっきりしています。その中で、志賀さんの写真の意味もきっと出てくると思います。
小原──彼女は名取市の北釜という集落に移り住み、そこで作品制作をしながら日常の行事なども撮っていました。震災後に津波を被った写真の洗浄をおこなっていましたが、それは集落の中での写真係としてやったことだと思うんです。
飯沢──そこははっきりしています。
小原──たとえば、富士フィルムのような企業が広報の一環のような形でやるのとは違ったと思います。彼女は集落の中での彼女の役割として、ずっと記録してきたわけですから。写真に関することは撮影以外にも彼女の役割として皆に認知されていた。
飯沢──「せんだいメディアテーク」の近くにある「magellan(マゼラン)」という古本屋さんで、志賀さんが2009年にベトナムで撮った「ブラインドデート」というシリーズを展示していました。先日たまたま仙台の実家に帰った時に寄ってみたら、村のカメラマンとして撮った写真集が置いてあって、やはりそれがおもしろかったです。エキセントリックな写真ではなく、非常に淡々と地域の行事だけを撮っている当たり前の記録写真だということがおもしろいですね。そういった写真が片方にあるということが、志賀理江子さんを考える時に大きなポイントだと思います。作品で表現していることの評価と、小原さんが言われた村のカメラマンとしての写真家のあり方との落差と、つながりですね。
小原──つながっていますね。
飯沢──つながっていると思うけれど、作品として見ている限りはかなり落差があります。そこは深く考えなくてはいけないことのひとつだと思っています。表現として論じる人も沢山いると思いますが、僕等世代よりも若い人たちがもっとまともに取り組んでほしいと思うのは、志賀理江子さんのやってきたような、地域社会との関わりの中でのカメラマンのあり方です。大きなテーマだと思いますね。
小原──通常、外部の人間でないと撮り得ないと思います。ある共同体があった時に、その中で日常的に行われていることは、内部にいる限りはあまり記録しようとは思わないですよね。

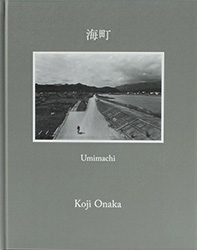

志賀理江子「螺旋海岸」(せんだいメディアテーク、2012)チラシ
尾仲浩二『海町』(スーパーラボ、2011)
畠山直哉『気仙川』(河出書房新社、2012)
飯沢──沖縄の問題とつながるような気がするんですけど。どうですか?
小原──沖縄の祭祀を撮影した比嘉康雄★64さんなんかもそうだと思いますよ。沖縄のシマ(集落)がそれぞれあり、そこに別のところから入ってきて撮影する。沖縄の中でも集落が違えば言葉も違うというくらいですから。今秋からIZU PHOTO MUSEUMで予定している増山たづ子★65さんのような人もいますが。ただダムに沈んだ徳山村内でも集落はそれぞれありますので、単純に共同体の内部の人間が撮るということも言えないと思います。
飯沢──増山さんみたいな例は珍しいですよね。北釜で言えば、志賀理江子さんではない他の誰かが撮るということですよね。
小原──それはほとんどないですよね。あとは伊江島の阿波根昌鴻とかでしょうか。伊江島の場合も撮影しておかないとなかったことにされてしまうような出来事が多々あったわけですから。米軍という圧倒的な力を前に小さなカメラで抵抗するという意味では増山さんとも重なります。
飯沢──外部から来る立場としては稀人であり、地域社会とどう関わりながらひとつのイメージを組織していくのかという問題でした。これは、明治以来写真が日本に入ってきた時から様々な取り組みがあったような気がします。ですが、今の日本の社会状況の中で地域ごとの特殊性がどんどん希薄になってきている時に、改めて写真というメディアの可能性や表現を地域の特殊性と結びつけることは可能性があると思います。答えは出ていませんが、いくつかの例があり、それらをうまくつないでいくと、新しい可能性が見えてくるのではないかと思います。その具体的な例のひとつが沖縄だと思います。
小原──沖縄については色々言いにくいですね。「比嘉康雄展」は、沖縄でつくった展覧会を日本(本土)に持ってきました。普通、巡回展は都市部から地方へと行くと思いますが、これはその逆です。
飯沢──IZU PHOTO MUSEUMでやったのはなぜですか?
小原──実行委員の方たちと企画が立ち上げた時からの計画です。「文化戦争」だと言っている人もいましたね。通常とは逆ルートの巡回展に可能性を感じたという理由です。もちろん比嘉康雄という写真家への尊敬もありましたし。
飯沢──IZU PHOTO MUSEUMは他の美術館と違う特殊性があります。東京や大阪などの大都市ではなく、かと言って地方の美術館やせんだいメディアテークなどとも違いますよね。だから、グローバルな問題に取り組むことができます。一方、地域性の問題として、「富士幻景──富士にみる日本人の肖像」★66のような、両面での展示の可能性があると思います。
小原──そうですね。富士山もいわゆるご当地ものではありますが、単に地域性ということではなく、この山の表象から日本の近代を概観してみようという趣旨でしたので「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展の富士山バージョンとも言えます。つまり、写真が渡来したペリー来航の頃から敗戦までの100年間を対象にしました。

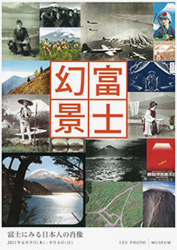
「母たちの神──比嘉康雄展」(沖縄県立博物館・美術館、2010)
「富士幻景──富士にみる日本人の肖像」(IZU PHOTO MUSEUM、2011)展チラシ
★58──しが・りえこ:1980- 宮城県在住。2008年、『CANARY)』(赤々舎、2008)、『Lilly』(アートビートパブリッシャーズ、2008)で第33回木村伊兵衛写真賞受賞。2009年、ニューヨーク国際写真センターインフィニティアワード新人賞を川内倫子とともに受賞。各地に滞在し、地域のフィールドワークを通して写真を撮るというスタイルで作品を制作。最新作『螺旋階段』も、宮城県の名取市北釜地区に住みつき「地域カメラマン」として撮影した。2011年の東日本大震災に遭遇、被災する。
★59──たかはし・まさむね:1980-
写真家。2002年「キヤノン写真新世紀」優秀賞を写真ユニットSABAにて受賞。2008年 「littlemoreBCCKS第1回写真集公募展」リトルモア賞受賞。2010年写真集『スカイフィッシュ』(赤々舍)。「LOST
& FOUND」の詳細はhttp://lostandfound311.jp/ja/を参照。
★60──おなか・こうじ、1960- 写真家。1992年、『背高あわだち草』で写真の会賞受賞。2002年、東川賞新人作家賞受賞。2006年、日本写真協会賞新人賞受賞。1988年自主ギャラリー「街道」を開設。写真集『海町』については、「1991年-1993年に三陸地方(宮古、釜石、陸前高田、石巻、気仙沼、鮎川、小名浜)を旅した際、港町の穏やかな日常の風景を記録したもの」と語られている。http://www.onakakoji.com/
★61──はまや・ひろし:1915-1999
写真家。1939年、新潟県高田市を訪問を機に雪国の習俗の記録を開始、1956年に『雪国』として結実する。続く『裏日本』で毎日出版文化賞受賞。農婦の、胸まで泥につかる田植えの写真は、衝撃的なドキュメンタリー写真として知られる。
★62──かげやま・こうよう:1907-1981
報道写真家。朝日新聞写真部に勤務。東北大凶作(1934)、2.26事件(1936)、南京陥落(1937)などを撮影。記録写真の鬼、と呼ばれた。
★63──はたけやま・なおや:1958-
写真家。1997年『都市のマケット』(写真展など)、作品集『LIME WORKS』(シナジー幾何学、1996)で第22回木村伊兵衛賞受賞。作品集『気仙川』は、高田市出身の写真家が、震災まえとその後の故郷の姿を、写真と言葉で構成したドキュメント。収録された写真を含む展覧会「NaturalStories」展(東京写真美術館
2011.10.1 - 12.4)で、2011年芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
★64──ひが・やすお:1938-2000 写真家。フィリピン生まれ。沖縄を代表する写真家。1968年、嘉手納空軍基地でのB52爆撃機墜落事故をきっかけに写真家を志す。民俗学者谷川建一との出会いを通して沖縄文化の古層に関心を深め、儀礼・習俗写真を多数撮影。
★65──ますやま・たづこ:1917-2006
アマチュア写真家として、ダムに沈んでゆく、故郷岐阜県揖斐郡徳山村の、生活-風景一切を撮り続けた。撮影した写真は8万枚に及ぶといわれる。
★66──artscape2011年9月15日号に、倉石信乃氏の展評が掲載されている。







![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)