トークシリーズ:「Artwords」で読み解く現在形
7. 「日本写真の1968」──「日本写真」「戦後写真」
飯沢──なんだかんだ言って「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展ってかなり大事な展覧会だったんですね。
小原──僕は写真への入り口が中平卓馬さんだったということもあります。彼が自ら関わった「写真100年」展の展評で「日本の写真史は日本の近代化のプロセスと重なっている」というような言い方をされていて、非常に影響を受けました。日本写真の100年を概観するような展覧会はできなくても富士山に限定した「富士写真100年」展なら可能かなと。
飯沢──「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展があり、今回は東京都写真美術館での「日本写真の1968」展で、僕はけっこうおもしろかったと思います。やはりあの時代に今の問題とつながってくるような問題意識がはっきりいろいろ現れてきた。それこそ、中平卓馬さんや森山大道さんが登場してきた時代です。
小原──ちょうど明治維新から100年後に近代を振り返って、前に進むような感じですね。振り返ることで写真の前衛へ躍り出る。『プロヴォーク』★67は「写真100年」展から生まれたようなものですね。
飯沢──地域性という問題で言えば、「日本写真の1968」展の最後に学生写真連盟のメンバーたちの共同制作の展示がありました。あれが印象深かった。これまでほとんど触れられていなかったところです。実はキュレーターの金子隆一★68さんが運動に深くコミットしていたので、あのような写真が出てきたと思います。考えてみれば各地域の学生たちが自分の問題意識を持って地域に関わっていく先駆的な仕事ですよね。広島でも、北海道でも、大上段に振りかぶった問題意識ではなく、個々の日常性の中から見えてくる問題をそれぞれのやりかたでした。ある写真の運動論や見方が厚みを持って出てきていたということに、僕はショックを受けました。
小原──今やってもいいですよね。
飯沢──おそらくできないと思います。今は志賀理江子のように、個人レベルでは地域社会との関わりがありますが、「日本写真の1968」展であったのは集団です。集団自体が解体してしまっています。かつて、沖縄や広島や北海道でも、若い無名の写真家たちが自分たちの問題意識を重ね合わせ共同ができたという土壌があったわけです。もちろん時代がそういう時代であり、全共闘運動のような組織論を写真でやろうとしたということには違いないわけですが。
小原──単に自主的にというだけではなく相当な強制力が働いていたと思いますが。
飯沢──福島辰夫★69さんがやっていた「491」という組織の特殊性もあるのかもしれません。誰かがリーダーとしていて、そこで号令一下でみんなが行動するという。
小原──ある種宗教に近いのかしれません(笑)。
飯沢──それはあったかもしれません。やはりひとりひとりの自発的な意志も働いているんですよね。その可能性はもう少し考えた方がよいのではないかと思います。しかし、どうも気にかかったのが、写真家の名前が出てこないわけです。集団としての名前は出てきますが、個々の写真家ひとりひとりの固有の名前というものをすべて消してしまっているところに時代の持っている特殊性を感じます。今それはできないだろうと思います。
小原──中平さんたちも無名で誌面に発表したりもしていましたね。
飯沢──論理的な帰結のようにしてアノニマスな動きになっていったわけですが、今そのような問題意識で何かをやるという土壌はないですね。
小原──今は地域おこしくらいでしょうか。
飯沢──地域おこしとしてやったとしても、おそらく固有名が出てくると思います。出さないとなかなかうまく成立しません。けれど、アノニマスな集団の可能性としてみると、僕はかなりおもしろかった。
──批評家として、2004年に亡くなったスーザン・ソンタグ★70や2010年に亡くなった多木浩二★71さんなど、「写真批評家」という存在についてお話しいただけませんか。
土屋──振り返ってみると写真に特化した批評家はすごく限られた人しかいなかったですね。飯沢さんの世代だと、伊藤俊治★72、金子隆一、それより前の世代だともう重森弘淹★73くらいの世代になってしまう。
飯沢──その間に西井一夫★74がいます。それから、長谷川明。でも西井一夫は若くして亡くなってしまいましたし、長谷川明★75もご病気以降は現代写真をフォローする体制ではないね。遡って渡辺勉★76、重森弘淹、福島辰夫。
土屋──もっと遡ると伊奈信男★77。ですから、日本に写真評論家なんてほとんどいないというのが私の結論です。今回の「アートワード」執筆の依頼をいただいて思ったのは、写真の言説が更新されていない、新しい理論的な枠組みがつくられていないということです。それは我々のような言論人の責任もあると思います。もう一方で起こっているのは、写真がアカデミズムの中で取り上げられるようになったということです。おそらく飯沢さんの世代以降の話だと思いますが。
飯沢──あまり活発ではないと思いますね。でも、写真史的な掘り起こしは確かにこの10年間でずいぶん進みました。
土屋──アカデミズムの中での写真の研究は、オーソドックスな美術史歴史研究としてではなく、むしろ視覚文化研究のひとつのヴァバリアントとしての写真研究が盛んです。IZU PHOTO MUSEUMとからめれば、ジェフリー・バッチェンみたいな人たちが出てきたということです。要するに、社会的な広がりの中で写真を見ていきましょうというものです。
飯沢──確かに、イメージや表象という議論は進んできていますね。
土屋──逆に、オーソドックスな作家論や作家に対する調査というものがまったくなされていません。たとえば写真美術館の展覧会を見ていていつも思うのですが、カタログを買ってもほとんど資料価値がありません。ろくに参考文献も完備されていないので、こんなものを買って何の意味があるんだろうといつも思います。
飯沢──目黒美術館の正木基★78さん並みのリサーチがないと。あの「石内都展ひろしま/ヨコスカ」展★79のカタログはすごかった。しょうがないことではありますが、写真美術館の学芸員は、あのような書誌学の訓練がないのです。正木さんのような分厚い書誌データをつくるのは、情熱とやる気の問題です。正木さんのようなやや狂った人が掘り起こす情熱を共有できるか、ということですよね。
土屋──アカデミズムの中に写真史家があまりいませんよね。
飯沢──残念ですけど、あまり興味のある対象ではないんですかね。僕は一応大学院を出ているわけですが、嫌で逃げ出したほうですが、大学に留まって各論的に研究をやっていく人がもう少し増えてもらえるといいと思います。日本の写真論は総論と各論の両方が欠けている。
土屋──去年、東京国立近代美術館で「実験場1950s」がありましたよね。あの時に原稿(「1950年代の写真表現における『地方』──木村伊兵衛と濱谷浩を中心に」)を依頼されて、木村伊兵衛と濱谷浩の地方表象をテーマに作家論プラス状況論みたいなものを書いたのですが、木村伊兵衛も濱谷浩も、日本では重要な写真家ということになっているにもかかわらず、モノグラフすらない。
飯沢──それは個々の施設、美術館や大学の状況と深く関わっているような気がします。
小原──単純に時間と労力、予算の問題ですよ。
飯沢──ということですよね。実際にやられていて、よくわかると思いますが(笑)。
小原──短い準備期間の中で展覧会のオープンを第一目標にしてそのほかは余裕があればというところで。急いで間違いだらけのカタログを作る必要はないと思いますので、いつも遅れがちなのですが(笑)。ただ展覧会と関係なく終わった後も書籍としても通用するようなものにしたいと思って編集しています。
飯沢──そういうトレーニングをしっかりやるのがアカデミズムの役割だと思いますが。それに対してわれわれのような在野が勝手なことを言ってちょっかいを出したり、穴埋めをしていくような補完体制があるというのが一番よい状態ですよね。片方がしっかりしていないから、一時僕はいろいろなことをやらされてしまっていました。他にも割と細かいところまでやった人はいますが、本当はその役割は、アカデミズムが担ってくれるとありがたいんです。
小原──あと、美術館のキュレーターも頑張らないといけないのかもしれません。
飯沢──総論と各論の両方が欠けているということで言えば、日本の写真史の通史がありません。通史をつくるにはこれまたものすごいエネルギーが必要で、資料集めから、組み立てていく構築力をひっくるめてやらなくてはいけません。僕自身もやらなくてはいけないとは思ってはいますが、そのためには、アカデミズム並の資料収集保存体制とどこかの出版社が蛮勇を奮って全10巻くらいの本をつくるみたいな企画を通してくれないとどうしようもないわけです。今の出版状況を考えるとかなり厳しいですよね。
土屋──「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展は写真家たちによってやられたわけで、結局写真家たちが偉かった。写真評論家は何をやっていたのだと(笑)。
飯沢──でも、まさに多木浩二さんも関わっていて、むしろ多木さんを写真の世界に引っ張り込んだのは「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展でしたから。そうなると、現在は何年になるのですかね。
小原──150年以上は経っていますね。
飯沢──僕が生きているかどうかはわかりませんが、「ダゲレオタイプ200年」ですね。2039年を目標にしてやはり、写真史の再構築を考えなくてはいけない時期です。少なくとも日本の写真史のある程度の跡づけといいますか。枠組みの作り方のようなことは考えなくてはいけない。
小原──「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展以降は日本写真史を更新するような展覧会もないですからね。海外で少しあった程度で。
飯沢──チラッと部分ですよね。総体としては、いまだにやり切れていません。そんなことは一個人がやろうとしても、無理なわけです。かといって、ある機関、写真美術館や大学がやるのも少し違うと思います。なかなか難しい問題です。僕が責任を感じているわけではないのですが、僕自身のこれからのライフワーク、人生を考えてみれば、実は来年還暦なんですよ。自分でびっくりしてしまうくらいです。70歳代になるとかなり厳しいと思うんですよね。なので、動けるのはあと10年だと自分で思っているので、あまり言いたくないのですが、この10年でやるしかないのかなと思っています。日本の写真史全5巻、ないし全10巻。これは出版社が動かないとどうしようもないことですし、どこかに資料室をつくってもらわないと。僕が平凡社の荒俣宏さんのように、資料室の主になるという感じでやらない限り無理ですよ。
小原──大風呂敷なので展覧会と絡めないと難しいとは思います。
飯沢──IZU PHOTO MUSEUMでやってください(笑)。東京都写真美術館はそのような展覧会をしっかり組む人材もビジョンもないと見ています。
小原──ヨーロッパの国々ではHistory of Photographyという自国の写真史に関する展覧会をよくやっていますよね。
飯沢──ヒューストン美術館で「The History of Japanese Photography」がありましたよね。ですが、100点で日本写真史をやるなんて、日本人にはとてもこわくてできないですよね。ヒューストンのキュレーターのアン・タッカー(Anne Wilkes Tucker)がやったからみんな納得しましたが、蛮勇といいますか、暴力的な展覧会です。ですが、それに近いようなことをする必要があるわけですよね。200点規模で日本の写真展をやると。
小原──それも難しいですね。
飯沢──そのための基礎資料と枠組みが必要です。考えてみると、日本写真史をどのように枠付けていくのかということは誰もやっていません。
小原──しかもそこにアノニマスなものを入れていくとなると……。
飯沢──入れざるを得ないでしょう。表現史としてならやれないこともないですが、それではまったくおもしろくない。
土屋──僕はあり得ると思うんですよ。全何巻にしてその中に詳細に客観的なデータを書き込むというものではなく、歴史をつくるには必ずバイアスがかかっているわけです。「写真100年 日本人による写真表現の歴史」展にしても、ものすごいバイアスがかかっている。
小原──仮想敵があったからそうしたモチベーションがあったのかもしれない。
飯沢──「記録」という言葉に対するバイアスのかかり方はすごいものがありますよね。
土屋──ですから、歴史を作るというものは非常にイデオロギッシュなものであって、例えばそれが美術の方では、椹木野衣さんの『日本・現代・美術』(新潮社、1998)や、遡れば千葉成夫さんの『現代美術逸脱史──1945〜1985』(晶文社、1986)、あるいは針生一郎の『戦後美術盛衰史』(東京書籍、1979)、そういうものがあったりするわけですが、要するにすべて偏っているわけですよ。それによって歴史は形成されてきたわけで、飯沢さんのお仕事でいえば、『戦後写真史ノート?写真は何を表現してきたか』(中公新書、1993)がそれにあたるのかもしれません。
飯沢──あれだってダメですよ。バイアスのかかり方がそういう意味では足りません。
土屋──でも、そこまで情熱を持って写真について書いている人は飯沢さんくらいしかいないということです。飯沢さんを褒める会にしたくないのですが(笑)。
飯沢──本当はだって、晩年は「きのこ文学」を研究して終るはずだったんですよ。ところが、こういうところに呼び出されてくると、つい昔とった杵柄ではありませんが、そういうことを言わざるを得ない。でも、やはり写真のことを考え出してから30年ですからしょうがないかもしれません。そろそろ、やってきたことに対する自分なりの落とし前はつけなくてはいけないわけですから。来年がそういう意味ではよい区切りになるので、真面目にやろうと考えています。
小原──ジェフリー・バッチェン★80ではないですが「複数の写真史」を作っていかなくてはいけないということですよね。個々の写真家に歴史的な評価を与えていくということと同時に写真史の構築も写真美術館の重要な役割のはずです。「写真100年」展の時には日本に写真専門の美術館はなかったわけですが、今はいくつかあるわけですから。
飯沢──まずそのためにはひとつ目をやらないといけない。それができない限りは複数もないわけですから。ナオミ・ローゼンブラム★81や、ジョン・シャーコフスキー★82がやろうとしていたことくらいでいいんですよね。
小原──たとえば、どこかで明治期の第一弾をやるとして、第二弾を別の場所で続けていく感じなら可能かもしれませんが。あるいは一カ所の会場で何期かに分けて展示するような。一年かけて鑑賞するのもいいかもしれない。
飯沢──そういうことですね。それから今後10年くらいで一斉にいろんな美術館でやっていくということですね。
小原──さまざまな美術館が連動して「複数の写真史」が出てくればいいのですが。
飯沢──それは難しいですが、こういう場での発言がいろいろな人が何かを考え始めるきっかけになるような気がします。ひとりでは無理なので、美術館や出版社の人たちの協力体制の中で、僕らの能力が活きてくるというのがベストですね。
小原──たったひとつの山をあつかった「富士幻景」だけでも非常に大変でしたから、気の遠くなるような作業だとは思います(笑)。
飯沢──それにしても最近、これまで誰も注目していなかったような写真家の仕事がやっぱりおもしろいですね。「ここはちゃんと見ておかなくてはいけない」という人が、ボコボコ出ていますよね。それも含めて、「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展の書き換えが、ないとどうしようもないところまで来ていますね。たとえば、幕末明治の島霞谷★83という人は、誰も注目していませんでしたからね。
小原──そうですね。田本研造★84や鳥居龍蔵★85の評価も全然されていませんね。鳥居龍蔵のような人の写真を日本写真史の中でどのように位置づけるかということは非常に重要でしょう。人類学や植民地の問題とも重なってきますし。植民地をテーマにした展覧会も見たことがないですね。現代作家の展覧会もいいですが、やるべきことは腐るほどあるはずです。
飯沢──鳥居龍蔵やグァテマラで写真館を経営していた屋須弘平★86のような人たちの評価とか。そうやって、いろいろなところにいろいろなものがあるということが、この20年くらいで見えてきているので、それを写真史というレベルで再組織化することを始める必要があります。
それとは別に、総合的な写真論も必要です。これは土屋さんのおっしゃるとおりで、パラダイムは出ていませんよね。つまり、ロラン・バルトやスーザン・ソンタグのように考える人が、写真にちゃんと向き合ってないという気がします。
土屋──一国写真史を語るには、今はいいタイミングです。それはなぜかと言えば、東松照明さんが亡くなられたからです。つまり「戦後日本」を背負ったのはあの人しかいなかったわけです。もし「日本写真」があるとすれば、やはりそれを体現している東松照明という写真家の存在を通さなければ、それは現れないと思います。
飯沢──そうですね。「日本写真」ということについてもしっかり考えなくてはいけない時期です。日本の写真家たちがやっている仕事の質というもの。今まではどうしても内容がクローズアップされてきたと思いますが、僕は日本写真を考える時に、フォルマリスティックな部分も大事だと思っています。形としてどうかということを考えることもこれから大事です。以前「カリグラフィー」と書いたことがありますが、空間のつかみ方や輪郭の見せ方に、日本の写真家たちの独特なフォルムの感覚があるような気がします。今、そのようなことも少し考えています。
土屋──東松さんが亡くなったことの意味は、やはり戦後日本が終わったということなのだと思います。
飯沢──それは是非読みたいです。「戦後写真」という言い方も、一人歩きしているけれど、中身を見てみたら何を言っているかよくわからないとところがありますね。それぞれが、それぞれの意味を込めて語ってしまっていますから。
小原──日本の場合、戦後と戦前はかなり連続していますから、「戦後写真」と一言では言えないですよね。戦中第一線で活躍していた人材がそのまま戦後も大先生として君臨し続けるような国ですから。
土屋──でも、それを切断したのが東松さんですよね。
飯沢──と言うより、東松さんの世代ということですよね。この世代に一種の切断が起こっているということだけは間違いないわけです。切断にしろ、連続にしろ、やはり戦後写真のアウトラインを、東松さんを通じてでも、また他の人たちでもよいので、出すべきだと思います。そうすれば問題がもっとはっきりしてくるでしょう。終わったというのであれば、その終わった後に何かが蠢いている、何かが起こっているわけですから。
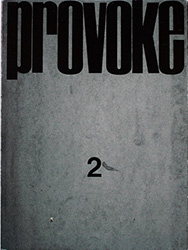

『PROVOKE』2号
ジェフリー・バッチェン『写真のアルケオロジー』(青弓社、2010)
★67──「Artwords」内、『プロヴォーク』を参照。
★68──かねこ・りゅういち:1948-
写真批評家・写真史研究。東京都写真美術家学芸員。著編書に『日本近代写真の成立』(柏木博、伊藤俊治、長谷川明と共著、青弓社、1987)、『日本写真史の至宝』全6巻・別巻1(国書刊行会、2005〜2007、飯沢耕太郎と共同で監修)、『日本写真集史
1956-1986』(著者:金子隆一・アイヴァン・ヴァルタニアン、発行:赤々舎)。2009年12月15日号のartscapeに、飯沢耕太郎の『日本写真集史
1956-1986』レビューが掲載されている。
★69──ふくしま・たつお:1928- 写真批評家。1950年代後半より写真批評を開始。「10人の眼」展(「Artwords」を参照)、「いま!!東松照明世界・展」などをオーガナイズ。批評家としての軌跡は、「福島辰夫写真評論集全3巻」(窓社、2011-2012)にまとめられている。
★70──Susan
Sontag:1933-2004 アメリカの批評家。著書に『反解釈』(竹内書店、1971、ちくま学芸文、1996)、『隠喩としての病い』(みすず書房、1982)、『エイズとその隠喩』(みすず書房、1990)など。1972年、晶文社から翻訳出版された『写真論』スーザン・ソンタグについては、「Artwords」参照。
★71──たき・こうじ:1928-2011
批評家・思想家。1960年代半ばから、建築・写真・現代美術の批評を開始。1968年、中平卓馬、高梨豊、岡田隆彦らと「思想のための挑発的資料」としての写真同人誌『PROVOKE』を創刊、戦後写真と批評言語にひとつの転回点をもたらす。図像学的-現象学的な方法と視点から、建築、デザイン、美術、写真などの広範な文化領域を解読。岩波書店より刊行されている『写真論集成』多木浩二については「Artwords」内を参照。
★72──いとう・としはる:1953-
美術・写真批評。東京芸術大学美術学部先端芸術表現科教授。専門の美術史・写真史の枠を越え,アートとサイエンス,テクノロジーが交差する視点から多角的な評論活動を行なう。おもな展覧会企画・監修に「移動する聖地」(1998、ICC)、「CHIKAKU四次元との対話」(2006年、岡本太郎美術館)など。著書に「20世紀写真史」「ジオラマ論」「機械美術論」「電子美術論」等多数(藝大教員紹介頁より)。
★73──しげもり・こうえん:1926-1992
写真評論家。1960年、自身が設立した東京フォトスクールを東京写真専門学校と改称、多くの写真家を送り出す。著書に『写真芸術論』(美術出版社、1967)、『世界の写真家』(ダヴィッド社、1990)など。
★74──にしい・かずお:1946-2001
写真批評家。毎日新聞社入社後『サンデー毎日』『毎日グラフ』を経て『カメラ毎日』編集部勤務。著書に『日付けのある写真論』(青弓社、1981)、 『写真的記憶』
(1997、青弓社) 、 『20世紀写真論・終章―無頼派宣言 』(青弓社、2001)、『写真編集者―山岸章二へのオマージュ』(窓社、2002)など。
★75──はせがわ・あきら:1949-
写真批評家。編集者。朝日ソノラマ在籍時、森山大道、荒木経惟、深瀬昌久の写真集を編集。著書に『写真を見る眼―戦後日本の写真表現』(青弓社、1995)。
★76──わたなべ・つとむ:1908-1978
写真批評家。著書に『写真・表現と技法』(ダヴィッド社、1966)など写真撮影の技術書多数。
★77──いな・のぶお:1898-1978 戦前を代表する写真評論家。1932年に創刊された写真雑誌『光画』(artword冨山由紀子執筆の項参照)に、印象批評からの脱却を呼びかける「写真に帰れ」(「Artwords」内、「写真に帰れ」伊奈信男を参照)を発表し、近代写真批評をもたらした。『光画』に発表された論考などをふくめた論集は、写真家大島洋、『写真に帰れ─―伊奈信男写真論集』(平凡社、2005)として刊行されている。また、その業績を記念して、1976年に「伊奈信男賞」が創設された。
★78──まさき・もとい:1951-
元・目黒区美術館学芸員。「戦後日本文化の軌跡」への企画参加をはじめ、戦後日本文化と美術とのあり方を検証する企画展を手がける。主な企画展に「石内都展 ひろしま
/ ヨコスカ」「‘文化’資源としての炭鉱」展など。目黒美術館在館時の2011年、「原爆を視る1945-1970」展(4.9-5.29)を企画・担当していたが、3.11の東北地方太平洋沖地震と原発事故に配慮した館の判断で開催中止となった。
★79──2008.11.15-2009.1.11
目黒美術館で開催。
★80──Geoffrey Batchen:写真史家。カリフォルニア大学サンディエゴ校、ニューメキシコ大学、ニューヨーク市立大学グラデュエートセンターを経て、現在はニュージーランドのウェリントンヴィクトリア大学で美術史教授。著書に『写真のアルケオロジー』(前川修+佐藤守弘+岩城覚久訳、青弓社、2010)、『時の宙づりー生・写真・死』(甲斐義明、小原真史、森陽子他訳、NOHARA
2010)など。
★81──Naomi Rosenblum:写真史家。『写真の歴史』(飯沢耕太郎+大日方欣一他訳、美術出版社、1998)。
★82──John
Szarkowski:1925- 2007 キュレーター、歴史家、批評家。1962年から1991年までニューヨーク近代美術館(MoMA)写真部門のキュレーター兼ディレクターを務める。シャーコフスキーの手がけた展覧会「鑑と窓」「ニュー・ドキュメンツ」についてはartword冨山由紀子執筆の項参照。
★83──しま・かこく:1827-1870
幕末・明治時代の画家、写真家。江戸下谷に写真館を開業。妻隆は日本初の女流写真師。
★84──たもと・けんぞう:1832-1912 三重県熊野市出身の写真家。万延元年長崎より箱館に渡るも壊疽(えそ)によりロシア病院で右足を切断。ロシア領事館の医者ゼレンスキーから本格的に写真術を学び明治元年開業。北海道開拓史の依頼により、道内を撮影、北海道写真の功労者と言われる。函館戦争のおり、洋装姿の土方歳三を撮影。
★85──とりい・りゅうぞう:1870-1953
考古学者、人類学者、民俗学者。東京帝国大学人類学教室に籍を置き、「国内各地のみならず、遼東半島を皮切りに、台湾、千島列島、中国西南部、中国東北部(満州)、モンゴル、朝鮮半島、東部シベリア、サハリン(樺太)、と精力的に海外調査を敢行した⋯⋯。これらの調査にともなって発表された数多くの著作や論文に加え、現地で収集した土俗資料や考古学資料は、今なお、貴重な学術資料となっている。とりわけ二千枚以上に及ぶ古写真は、今では見ることのできない東アジア、東北アジアの当時の風俗や景色を生き生きと伝えており、今もその新鮮さは失われていない」(鳥居龍蔵の乾板写真術──野林厚志国立民族学博物館)とあるように、人類学のフィールドワークに写真を使った。飯沢耕太郎は著書『日本写真史を歩く』で鳥居龍蔵に一章を当て、その写真は「驚くほど密度の濃い、イメージの集積であった」と記している。
★86──やす・こうへい:1846-1917
グァテマラの古都アンティグアに写真館を開き、1889年に一時期帰国の後、グアテマラで再び写真館を開業、さらに1895年、アンティグアに移転して写真館を営む。アンティグア市の人物・肖像写真とともに、教会、病院、庁舎などの建築物を撮影。飯沢耕太郞の『日本写真史を歩く』によれば、「これらは仕事というより、明らかに記録の意志が働いている」。1917年、アンティグアで静かに息を引き取る。
[2013年6月10日(月)、新宿にて]







![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)