フォーカス
2020年、アーティストたちの距離・時間・接触
久門剛史/高谷史郎/額田大志/市原佐都子/笹岡啓子
2020年12月15日号
2020年という年が終わろうとしています。今年は多くの人にとって、新型コロナウイルスの感染拡大という出来事がまず想起される年となったのではないでしょうか。世界的な非常事態のなかでさまざまな制限がかかりながらも、数多くの作品やパフォーマンスが新たな表現や形式を伴って発表され、artscapeではそれらを読み解く言葉たちを掲載してきました。一方で、アーティストたち自身はどのようなことをこの状況から感じ取り、思考を巡らせていたのでしょうか。「距離」「時間」「接触」といったキーワードを手がかりに、5名のアーティストに言葉を寄せていただきました。(artscape編集部)
執筆者
久門剛史(美術作家)
高谷史郎[ダムタイプ](映像作家)
額田大志(作曲家、演出家)
市原佐都子(劇作家、演出家、小説家)
笹岡啓子(写真家)
久門剛史(美術作家)
初心と未来
 [写真:来田猛]
[写真:来田猛]
普段から時間が止まったような郊外にあるスタジオにいても、世の中が一時停止しているように見えていました。2020年は自身の大きな個展が始まり、そして終わったこともあって、人生を振り返りながら心と空間の整理をしていました。そして、美術を志したときのことを思い出していました。
大学では彫刻を専攻しました。作品の周りをぐるぐると移動しながら自分との距離を確認し、上下前後左右、さまざまな角度から自分の好きな視点を探すことに心を動かされたのを覚えています。作品と対峙している他者のふるまいを観ることにも惹かれて、物理的にも精神的にも観客自身の居場所を探してもらえるような作品を志すようになりました。
美術はある種の斜に構える態度でもあると思いますが、社会の外周をぐるぐると移動して、どの角度からであれば本質を射抜けるのかということや、多層に入り組んだ世界の構造を探り、踏み込もうとする姿勢も彫刻から学んだのかもしれません。
また、感覚を試されることに興味を惹かれたり、作者のさまざまな痕跡や経験が哲学となって結晶していることにもたびたび心を奪われてきました。それは展覧会だけではなく、いろんな分野においてです。
できることなら触ってしまいたいが、触れてしまうとすぐに崩れてしまいそう、そういう精神的に卓越したバランスで保たれている作品をつくりたいし、誰かのそんな作品を見たいと思っています。そういうものに出会ったとき、時間は止まったり、一瞬で伸びたり縮んだりして、シナプスが無秩序につながり合うような経験をしてきました。わかった、となったときにストンと心が落ちるような、空白にぴったり収まると同時に急速に拡がっていくような感覚です。他者と言葉を交わさずに接触し、感動を呼び起こすことは美術の素晴らしい力だと思っています。
思い返すと、コロナ禍であっても考えていたことはほとんど変わりません。
いつものように彫刻的な視点で世界を見ようと心がけていました。
そして、初心を振り返り、深呼吸しながら未来を想像するような時間を過ごしていました。
ひさかど・つよし
1981年京都府生まれ。京都府在住。2007年京都市立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。
人生を取り巻く唯一性や永遠性を契機に、音や光、彫刻を用いて個々の記憶や物語と再会させる劇場的空間を創出している。
近年の主な展覧会に「久門剛史−らせんの練習」(豊田市美術館、2020)、「メルセデス・ベンツ アート・スコープ 2018-2020」(原美術館、2020)があるほか、「MAMプロジェクト025」(森美術館、2018)と第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展「May You Live in Interesting times」ではアピチャッポン・ウィーラセタクンとの共作を展示した。
http://tsuyoshihisakado.com/
関連記事
KYOTO EXPERIMENT 2019|久門剛史『らせんの練習』|高嶋慈(2019年11月15日号)
自然と共生する人間の営み──久門剛史「らせんの練習」/廣瀬智央「地球はレモンのように青い」|坂本顕子(2020年07月15日号)
光の無限軌道を描く──「久門剛史 ─ らせんの練習」|中井康之(国立国際美術館)(2020年08月01日号)
高谷史郎[ダムタイプ]
新作『2020』が照らす「今」
 ダムタイプ『2020』[写真:福永一夫]
ダムタイプ『2020』[写真:福永一夫]
3月28、29日に、ダムタイプの18年ぶりの新作パフォーマンス『2020』の公演がロームシアター京都で予定されていました。ヨーロッパ等での新型コロナウイルスの感染拡大のニュースとこの未知なるウイルスの情報の無さのなかで、実際どのように対応するのが適切なのか? メンバーで話し合い、劇場サイドともやり取りするなかで、ギリギリの日程で最終的に主催者の判断により公演中止が決定しました。公演は中止となりましたが、無観客の状態でパフォーマンスを実時間で上演し、それを映像として記録する方向で進めることになりました。
元々 『2020』という作品は、この瞬間に過ぎ去っていくと同時に、まだ見ぬともいえる「今」にフォーカスを当てた作品です。上映作品としての『2020』は平面の映像なのに、10月16〜18日に行なわれたロームシアター京都での上映会では、パフォーマンスを記録したその劇場舞台での上映ということもあって、実際に現前にある舞台のように見える瞬間があり、複数の時間と空間がたたみ込まれた、これも一種の3次元かもしれないと考えることもありました。
新型コロナウイルスの蔓延は地球規模の乱開発、大量の人間の移動など、現在のような社会のあり方の結果ではないかと思います。早く、新たなる考え方を全球的に共有しないと、どうにもならないように思えてなりません。
ワクチンが開発され、特効薬ができても、このウイルスの影響はかなり続くでしょう。それは、今までのシステムを守ろうとするからではないのか、と最近思います。そして、世界的な規模で、直接的なコミュニケーションが阻害されることによって我々の社会が受ける影響について心配しています。
今後の制作としても、単にインターネットを使ったリモートの何かというのではない、新しい方法を考えないといけないと感じています。ダムタイプは雑多で辺境的な環境から生まれたと思います。潔癖症が正当化されすぎる、クリーンなだけの社会……このストレスフルな現状から、何か新しい考えを発明しないといけないと感じています。
たかたに・しろう
京都市立芸術大学環境デザイン専攻卒業。1984年からアーティストグループ「ダムタイプ」の活動に参加。さまざまなメディアを用いたパフォーマンスやインスタレーションを制作し、ドイツ世界演劇祭、マルセイユ・フェスティバル、東京・新国立劇場、びわ湖ホール等での公演や、東京都写真美術館やポンピドゥー・センター・メッスでの個展等。また、坂本龍一や野村萬斎、中谷芙二子、樂吉左衞門らとのコラボレーションも多数。平成26年度芸術選奨メディア芸術部門文部科学大臣賞受賞。平成30年度京都府文化賞功労賞受賞。
http://shiro.dumbtype.com/
関連記事
ダムタイプ 新作ワークインプログレス 2019|高嶋慈(2019年04月15日号)
ダムタイプ 新作パフォーマンス『2020』上映会|高嶋慈(2020年11月15日号)
ダムタイプ|現代美術用語辞典ver.2.0
額田大志(作曲家、演出家)
二つの劇場の自由と不自由
 [Photo: Kazuyuki Matsumoto]
[Photo: Kazuyuki Matsumoto]
2020年10月下旬、東京芸術祭のプログラムとして上演されたAPAF Exhibition『フレ フレ Ostrich!! Hayupang Die-Bow-Ken!』に、私はディレクターのひとりとして参加した。本作はフィリピン、インドネシア、そして日本の3カ国のアーティストによる国際共同作品である。フィリピンとインドネシアのアーティストは来日が叶わず、クリエイションはすべてZoom上で行なわれた。本作のもっとも大きな特徴は、会場の「東京芸術劇場シアターウエスト」と「Zoom」の2カ所が、どちらも「劇場」として機能するハイブリットな上演形態にある。シアターウエストとZoom上のそれぞれに、観客とパフォーマーが存在し、四者がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら上演は進行していった。
ディレクターのひとりであるフィリピンのジェームズ・ハーヴェイ・エストラーダは、本作を「連帯の演劇」と称していた。言語や距離といったさまざまな壁を超えて、世界中から観客が集ったZoomという劇場は確かに人々のつながりを感じさせた。しかし、もうひとつの劇場であるシアターウエストの観客はどうだろうか。
私はシアターウエストの観客が、上演を通じて「世界の不自由さ」を体験することができないかと考えていた。Zoomの観客は上演中のインストラクションとして、声を発することや、歌うこと、そしてお菓子を食べることができる。シアターウエストの観客は、それをただ見つめることしかできない。本来であれば、リアルな劇場こそが参加型の空間であったはずなのに、いまはその多くが制限されてしまった。近い将来、もしかしたら「リアルな劇場で見る」というのは、観劇におけるひとつの選択肢になるのかもしれない。劇場は(ある程度)自由な表現の場所でありながら、時として不自由な空間にもなり得る。「いま、自由に表現できる場所はどこか?」を考え続けた一年間だった。
ぬかた・まさし
1992年東京都出身。作曲家、演出家。8人組バンド『東京塩麹』、演劇カンパニー『ヌトミック』主宰。
「上演とは何か」という問いをベースに、音楽のバックグラウンドを用いた脚本と演出で、パフォーミングアーツの枠組みを拡張していく作品を発表している。『それからの街』で第16回AAF戯曲賞大賞、古典戯曲の演出でこまばアゴラ演出家コンクール2018最優秀演出家賞を受賞。自作のほか、Q/市原佐都子『バッコスの信女 ─ ホルスタインの雌』などの舞台音楽、JR東海『そうだ 京都、行こう。』などの広告音楽も数多く手掛ける。
https://nuthmique.com/
関連記事
ヌトミック『それからの街』|山﨑健太(2020年03月01日号)
ヌトミック『Our play from our home』|山﨑健太(2020年07月01日号)
市原佐都子(劇作家、演出家、小説家)
外との接触とアイデンティティ
 ジョルジュ・ビゴーによる風刺画[出典:清水勲『ビゴーが見た日本人』(講談社、2001)]
ジョルジュ・ビゴーによる風刺画[出典:清水勲『ビゴーが見た日本人』(講談社、2001)]
私は住むということにこれまで頓着してこなかった。20代の頃は家賃を滞納して夜逃げして知人の家を渡り歩いたし(返済・和解済み)、自分の家をまた借りても寝るだけの場所とし、安い狭いところを選んだ。ルームシェアの一軒家にも住んだことがある。執筆はマクドナルドやベローチェ。ルームシェアが解散した後は、子供のおもりをする代わりに姉夫婦の住む一軒家に居候させてもらっていた。二年くらい姉夫婦の家でそうしていたが、いい加減出て行くことになり、いろいろなタイミングが重なって、いまの家に引っ越した。どうせお金をとられるのだ、今度は好きな場所にするために環境を整えて、最近は毎日そこにいる。執筆も感染がこわいので家になった。6月、家のなかで初めて台本を書き終えた。ミュンヘンのResideztheaterへ『おじさんの犬祭り』というギリシャ喜劇をベースにした感染症にまつわる新作を書き下ろした。本当はミュンヘンで滞在執筆のはずだったが、行けなかった。来年ミュンヘンでこの作品はリーディングされると思うが、その場に私は行けるだろうか。
家から出られないことで、DVや、経済が縮小し生活が困窮して自殺が増えていることなどを耳にすると胸が苦しくなるが、個人的には外に出ないことはさほど苦しくない。むしろ、人の前にいるということは、挨拶をしたりどこに座るかを考えたり、多少なりとも必ず良いふるまいを強いられている。コロナ禍の前まではその良いふるまいの技術が無意識に日々上がっていたように思われる。舞台は集団創作なのでその技術は必要だが、本当に自分は良い人なのだと勘違いしそうになる。作家として普段の社会生活では抑圧しなければいけない領域を作品のなかでは表出させたいと思っている。良いふるまいが板につきすぎると封じていることにも気づかなくなりそうになるが、コロナで少し立ち止まることができた。しかし、いまは来年の新作『蝶々夫人』について日々家の中で考えているが、異なる文化と接触するとき、私たちは自分が何者であるのかを強く意識する。明治時代の日本にいたフランス人画家ジョルジュ・ビゴーの描く日本の絵に強く惹きつけられる。外との接触でしか得られないアイディアがある。来年は今年より外へ出かけて行ければと思う。
いちはら・さとこ
Q主宰・劇作家・演出家・小説家。1988年大阪府生まれ、福岡育ち。人間の行動や身体にまつわる生理、その違和感を独自の言語センスと身体感覚で捉えた劇作、演出を行なう。2011年、戯曲『虫』にて第11回AAF戯曲賞受賞。2019年、小説集『マミトの天使』(早川書房)を出版。同年『バッコスの信女 ─ ホルスタインの雌』をあいちトリエンナーレにて初演。第64回岸田國士戯曲賞受賞。公益財団法人セゾン文化財団セゾン・フェロー。
http://qqq-qqq-qqq.com/
関連記事
あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈(2019年11月15日号)
リーディングパフォーマンス 市原佐都子/ジャコモ・プッチーニ『蝶々夫人』|高嶋慈(2020年04月15日号)
市原佐都子『バッコスの信女─ホルスタインの雌』|山﨑健太(2020年05月15日号)
Q オンライン版 『妖精の問題』|山﨑健太(2020年06月01日号)
Q/市原佐都子 オンライン版『妖精の問題』|高嶋慈(2020年06月15日号)
笹岡啓子(写真家)
あの日からの2020
 笹岡啓子『SHORELINE 39』より《岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里 2020年6月20日》
笹岡啓子『SHORELINE 39』より《岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里 2020年6月20日》
東日本大震災が起こった直後から「何かが変わってしまった」と人々は口にした。絆だ、連帯だと唱えながら、次第に都市部は復興景気に沸き、三陸沿岸は巨大なコンクリートで塗り固められていった。海外からの観光客が急増し、近年ではアクセスしにくいはずの地方の山間部にも世界各地から訪れた人が溢れ、私自身、撮影で赴く度に驚かされていた。そして今年、彼らの姿は一斉に消え、震災からの「復興五輪」と宣言したはずの東京オリンピックは、当然のように「コロナに打ち勝った証」となるらしい。
世のなかの関心が急速に移ろうなかで、東北の被災地域では10年という復興事業の各期限とともに整備が進んでいる。今年10月、そのひとつである石巻に建設中の復興公園予定地を訪れた。甚大な被害にあった沿岸の住宅地一帯が買い上げられて大きな公園となり、その中心には国立の追悼施設が建つという。その一角で地元住民により被災直後から運営されている小さな伝承施設を訪ねた折、「この辺、ずいぶんと変わりましたね」と天気の話のように発した私に、案内係の方は「ずっといるから何も変わってないとしか見えないね」と応えた。「ここに公園作ったって、誰も住んでないのに誰も来ないよ。わざわざこんなところまで見に来ようって人がいる?」かつての住民の大半は他所へ移転したため、もとのコミュニティを立て直すことが叶わず、新しいそれを築く困難を、条例や住民説明会の様子を交えて熱心に語ってくれた。それは誰でもない「東京から来た者」への訴えのようでもあった。地域に根ざさない専門家や担当替わりしていく行政を相手に、簡単には手放せない土地で格闘する人たちがいる。「絆」とは、決して聞こえのいいつながりなどではなく、元来、断ち切れない結びつき、あるいは自由を妨げさせる枷であったことを思い返したい。
世界的流行であるからこそ、各地の状況は地域が抱えていた問題によって異なる。パンデミックの影で強く大きな力にのみ込まれたり、すり替えられたりする出来事があってはならないと思う。私自身は移動しながら撮影をする身だが、旅の写真を撮っているわけではない。自然と人間が長い歳月のなかで傷ついたり、作り直したりしながら関わり合ってきた場所を撮ることはこれからも変わらないと思う。コロナ禍とは、そうやって築かれてきた目の前の景色を一瞬にして変えてしまう災害とは異なるようだ。少なくとも短期間では片付きそうもないこの状況の後に、私たちがどのような風景を未来へ受け渡すことができるのか。どれだけデジタル化が進もうと、写真といういまだ不自由で遅いメディアが果たせる役割のひとつは、粛々と現在を記録することだろうと思う。
ささおか・けいこ
1978年広島県生まれ。2001年から広島市中心部での撮影を始め、2009年に写真集『PARK CITY』(インスクリプト)にまとめたあと、現在まで撮影と発表を継続。東日本大震災後、被災地域を撮影した小冊子『Remembrance』(KULA)(全41号)を刊行し、2015年からは被災地を含めた日本の海岸線などを撮影した小冊子『SHORELINE』(KULA)(1〜39号)の刊行を続ける。photographers’ galleryのメンバーとして批評誌『photographers’ gallery press』(photographers’ gallery)の編集に携わり、第12号では広島の原爆写真を検証する「爆心地の写真 1945-1952」を特集。受賞歴にVOCA展奨励賞(2008)、日本写真協会新人賞(2010)、林忠彦賞(2014)ほか。
https://keikosasaoka.com/
関連記事
笹岡啓子「PARK CITY」|飯沢耕太郎(2020年02月01日号)
笹岡啓子「SHORELINE」|高嶋慈(2020年10月15日号)


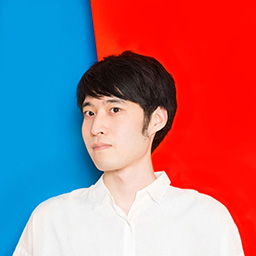




![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)