artscapeレビュー
山﨑健太のレビュー/プレビュー
市原佐都子『バッコスの信女─ホルスタインの雌』

発行所:白水社
発行日:2020/04/10
第64回岸田國士戯曲賞受賞作として市原佐都子の戯曲『バッコスの信女─ホルスタインの雌』が白水社から刊行された(同時受賞の谷賢一『福島三部作』はすでに2019年11月に而立書房から刊行されている)。選評によれば、審査員一人ひとりが最終候補作のそれぞれに対して○△×で評価を示すところから始まる選考会において、「珍しく、最初から委員全員が大意において同じ方向を向いてい」て、『バッコスの信女─ホルスタインの雌』には「誰ひとり『×』をつけなかった」(ケラリーノ・サンドロヴィッチ)らしい。平田オリザは「全体のことで言うと、今年は例年に比べてレベルが高」かったと述べており、レベルの高い最終候補作のなかでも市原の戯曲が選考委員の圧倒的支持を集めたということがわかる。私個人としてもここ数年、岸田賞の最終候補作にはすべて目を通しているが、同様の印象を持った。
『バッコスの信女─ホルスタインの雌』の主人公は一見したところ「普通の」主婦である。しかし彼女はのっけから「ケロッグのコーンフレークってマスターベーションをやめさせるために生まれたらしい」などと観客に向かってまくしたてる。性と食はこれまでの市原のほとんどすべての戯曲で中心的なモチーフとなっており、それはつまり、市原が演劇を通して生の生々しさを描き出し曝け出そうとしていることを意味する。性にせよ食にせよ、ほとんどの場合、それが他者を必要とする営みであるという点において共通しており、市原はそれらを奇妙に混線させることで人間の営みの欺瞞を暴き出す。
かつて「家畜人工授精師」として働いていた主婦が「獣人」(牛と人間のハーフであり、かつ上半身が女、下半身が男の「ハーフ」でもある)を生み出してしまうという物語は単に荒唐無稽な、あるいは作家のフェティシズムを具現化したものではなく、確固たる構造に裏打ちされたものだ。獣人は「母」である主婦を女性だけの楽園に誘い、彼女と結びつき「生まれ直す」ことを夢見るが(母乳と精液の循環!)、その願いが成就することはない。肉を食いたい、セックスがしたい、子供がほしい。他者を欲望する限りその回路を閉じることは不可能だ。自己完結のユートピアに閉じこもることはできない。
日本で性が語られるとき、反応の多くは対象への性的な興味か、私的領域に留めるべきものが公の場で語られることへの羞恥に二分され、性が十分に真っ当な議論や教育の対象となっているとは言いがたい状況がある。市原はならばとばかりに「過激」な言葉を並べ立てる。それは観客の生理的な反応をより一層引き出すだろう。だがその背後に奇妙ではあるかもしれないがある種の論理的構造が確固たる作品の枠組みとして用意されている。劇作家としての市原の強みはその両輪の確かさにある。
併録された『妖精の問題』は2016年の「相模原障害者施設殺人事件を受けて生まれた」作品で、本書のあとがきによれば市原は「事件によって、自分のなかにある優生思想や、自分が抱えている生きづらさを意識させられた」のだという。市原はさらに「できるだけ偽善的ではない方法であらゆる生を肯定することを試みたいと思った」とも書いている。「できるだけ偽善的ではない方法」というのはそこにある問題そのものから目を逸らさないということだろう。市原は演劇の上演という枠組みを利用して観客に「直視すること」を迫る。真っ直ぐな言葉で自らの創作について語る市原のあとがきも本書の読みどころのひとつだ。『妖精の問題』は5月16日(土)・17日(日)にオンライン公演が予定されている。
あいちトリエンナーレ2019で初演された『バッコスの信女─ホルスタインの雌』は、ドイツで3年に一度開かれる世界演劇祭(テアター・デア・ヴェルト)での上演も予定されていたのだが、残念ながら新型コロナウイルスの影響で演劇祭自体が2021年6月へと延期となってしまった。現時点で次は9月、神奈川芸術劇場KAATでの上演が予定されている。市原の主宰する演劇ユニット「Q」の近作は多くがレパートリー化されているが、本作は作品の規模的にも再演の機会は限られてくるだろう。この機会に再演が実現することを切に願う。
関連記事
あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』 │ artscapeレビュー(2019年11月15日号) | 高嶋慈
2020/04/18(土)(山﨑健太)
小田尚稔の演劇『是でいいのだ』/小田尚稔「是でいいのだ」

会期:2020/03/11~2020/03/15
SCOOL[東京都]
「小田尚稔の演劇」名義で演劇作品を発表してきた劇作家・演出家・俳優の小田尚稔による初小説「是でいいのだ」が『悲劇喜劇』2020年3月号に掲載された。同タイトルの演劇作品を小説化した本作で語られるのは「三月のあの日」に東京にいた5人の男女のそれからの歩みだ。
なにか劇的なことが起きるわけではない。新宿で被災し、震源地に近い実家の両親と犬の安否を気づかいつつ国分寺の自宅へ歩いて帰宅しようとする就活生(小川葉、以下2020年演劇版の配役)。夫に家を追い出された挙句に送りつけられた離婚届に署名しようとしているところで被災した女性(濱野ゆき子)。新宿西口公園で休憩していた彼女に声をかけ、その後もちょくちょく遊ぶようになる大学5年生の男(加賀田玲)。自ら離婚届を送りつけたにもかかわらず、被災後の不安からか「淋しい」と妻に電話をかけてしまう夫(橋本清)。悩んだ末に仕事を辞め、教員採用試験を受けることを決める女(澤田千尋)。彼女たちはそれぞれに自らの体験を淡々と、ときに自虐的なユーモアを交えて語る。
就活生の彼女はエントリーシートを書きながら自分の履歴を「カスみたい」だと思い「他人と比較して自分の越し方を思うと、少しだけ情けなくなる」という。三鷹まで歩いたところで中央線が動き出しているらしいことを彼女は知るが、それでも「今日は歩いて帰りたい」と彼女が思うのは「もし歩いて帰ることが出来たら、自分を自分で褒めてあげよう。失敗だらけの自分の生き方を少しは受け入れてあげよう。『これでいい』って、自分にそう言ってあげよう」と思ったからだった。
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
「是でいいのだ」というタイトルにはいくつかの由来がある。小田作品の多くは哲学者の著作をモチーフとしていて、本作ではイマヌエル・カント『道徳形而上学の基礎づけ』とV・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』がそれにあたる。小説版ではさらに赤塚不二夫の(あるいは『天才バカボン』の)影響が冒頭のエピグラフによって示唆される。
「あなたの考えは全ての出来事存在を、あるがままに前向きに肯定し受け入れることです。それによって人間は、重苦しい意味の世界から解放され、軽やかになり、また時間は前後関係を絶ち放たれて、そのときその場が異様に明るく感じられます。この考えをあなたは見事に一言で言い表しています。すなわち、『これでいいのだ』と。」(樋口毅宏『タモリ論』)
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
ところで、読者にとってこの小説の(ある部分の)語り手が誰であるか、何人の語り手がいるのかを判断することは実はなかなかに難しい。それぞれの語りの質感が似通っていることに加え、小説版では(当たり前だが)俳優もおらず、登場人物の名前も語られないからだ。しかも、語られる固有名詞やエピソードに重なる部分が多くあるため、しばしば彼女ら彼らは同一人物であるかのようにさえ思える。学生か就職しているか、未婚か結婚しているかという属性の違いだけが彼女ら彼らを見分ける手がかりとなるのだが、語りは一貫した時系列の下に進むわけではないため、同じ人物の異なる時間軸の語りが混在している可能性は排除できない。基準点となる「三月のあの日」におけるそれぞれの姿や行動だけが、彼女ら彼らが「別人」であることを示している。
彼女ら彼らに設定された共通点は、共感のための、自分ではない誰かに想像を広げるための糸口として用意されたものなのかもしれない。登場人物がそれぞれにつぶやく「大丈夫かな……」という言葉はその場そのときにいないひとへの想像力の発露にほかならない。本作は再演のたびに橋本以外の俳優を入れ替えてきていて、私の脳裏には「同一人物」を通して「別人」たちの姿も浮かぶ。
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
小説版は演劇版と語りの「感じ」も内容もほとんど同じなのだが、一箇所だけ大きな変更が加えられている。演劇版で重要な場面に登場する「もえあず」が別の人物に置き換わっているのだ。私も友人の指摘で知ったのだが、演劇版では細井くんと呼ばれる大学生の男の「推しメン」である大食いアイドル「もえあず」こともえのあずきが活動を開始したのは2012年3月13日、大食いキャラとして認知される最初のきっかけとなった番組の放送は同年10月のことらしい(Wikipediaによる)。となると、細井くんが被災時にもえあずのファンだったというのは現実的にはあり得ない設定だということになる。小説版の発表のあとに上演された演劇版でも「もえあず」が同じように登場していたことを考えると、これはわざとそのように描かれているのだろう。
 ©︎Naotoshi Oda
©︎Naotoshi Oda
実は、作中では「三月のあの日」が2011年のことだとは(観客にわかる形では)明言されず、東日本大震災という言葉も登場しない。つまり、「三月のあの日」はいつだってあり得るのだ。それはそのまま「三月のあの日」に私が思い知ったことだ。「その日」がいつ来るかは誰にもわからない。
だからこそ「是でいいのだ」という言葉は重い意味を持つ。それは素朴な現状肯定などではない。起きてしまった、変えられない過去を受け入れ、そこから再び歩みをはじめるための最初の小さな一歩。人生のいつだって、それを踏み出すことはできるはずだ。実は、仕事を辞め教員採用試験を受ける決意する彼女の語りだけは、震災のことに一切触れることがない。「あの日」がいつだってあり得ることの意味は反転する。いや、それはいつだって裏腹なのだ。過去は変えられず、未来はわからない。だから人はその一歩を踏み出す。
2016年10月に新宿眼科画廊スペース地下で初演された演劇版は、その後、三鷹にあるSCOOLに会場を移し、2018年以降、少しずつ改訂を重ねながら毎年3月に上演されている。新宿はこの作品の冒頭で「帰宅困難者」となった就活生が自宅のある国分寺への歩みをはじめた場所であり、三鷹は歩き続けた彼女が作品の最後で立っている「現在地」だ。SCOOLでの観劇を終えた観客は彼女の歩みを引き継ぐようにして帰途への一歩を踏み出す。
公式サイト:http://odanaotoshi.blogspot.com/
2020/03/14(土)(山﨑健太)
スペースノットブランク『ウエア』
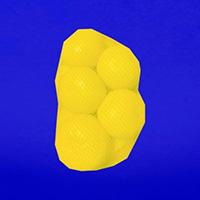
会期:2020/03/13~2020/03/17
新宿眼科画廊 スペース地下[東京都]
前作『ささやかなさ』で岸田賞作家・松原俊太郎の書き下ろし戯曲を上演したスペースノットブランク(以下スペノ)が今回「原作」を依頼したのはいじめや親子関係など自らの実体験を元にした作品で注目を集める「ゆうめい」の池田亮。松原戯曲の饒舌さにはスペノのこれまでの「文体」との共通性が感じられなくもないが、ストレートな「物語」を戯曲として書いてきた池田との組み合わせは正直言って意外だった。だが、スペノもまた、制作のプロセスにおける時間の積み重ねを現在形の舞台として立ち上げる「ドキュメンタリー」を上演してきたアーティストであり、その意味では池田との距離はそう遠くないのかもしれない。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
スペノとゆうめいが共に出演した「どらま館ショーケース2019」では、もうひと組の参加団体であった関田育子も含め、三組が三組とも何らかの意味で「ドキュメンタリー的」な手法を用いていた。あらかじめショーケースのテーマが設定されていたわけではなく、私を含む推薦者3名がそれぞれ一団体を推薦した結果のラインナップだ。演劇の「ドキュメンタリー」としての、つまりは「現実」としての側面に意識的なつくり手が30歳前後の若手には多い。あるいはそれは人的交流による部分もあるだろう。スペノとゆうめいの付き合いは長く、互いの作品にメンバーが出演することもしばしばだ。『ウエア』には音楽担当としてヌトミックの額田大志も参加しているのだが、いわば「バンド」的な連帯による作品/場づくりもまたこの世代の(あるいはここ数年の小劇場シーンの)特徴として指摘できる。
ポストパフォーマンストークでの発言によれば『ウエア』もまた池田の実体験に基づいて書かれたものらしいのだが、上演からそれを読み取ることは不可能だろう。池田による原作は上演台本のかたちに構成し直され、そこにあった(かもしれない)物語は断片となり浮遊している。観客はそれを拾い集めて元のかたちを想像するしかない。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
どうやらそこには何らかの会社の企画会議の参加者とヤクを製造販売するグループとが登場しているらしいのだが、ヤクを吸ってバッド・トリップする登場人物たちはしばしば現実と幻覚、自分と他人の区別がついていない。一方がもう一方の見る幻覚だとも思える場面もある。ナミやニコンロといった漫画『ワンピース』を思い出させる登場人物の名も現実感を乏しくする。4人の俳優(荒木知佳、櫻井麻樹、瀧腰教寛、深澤しほ)は演じる「役」(というものがあるとすればだが)をしきりに入れ替えているようで、「虚構」はやがて決壊し「現実」に流れ込む。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
作中に登場する「メグハギ」というキャラクター(Vtuber?)はさまざまな要素=キャラづけによって成り立っている。キャラクターを構成するのもまた複数のキャラクターなのだ。「メグハギ」と聞いた私が最初に連想したのは「つぎはぎ」という言葉だった。虚構のつぎはぎとしての虚構。ならば現実はどうか。
悪夢的な、とても「意味がわかる」とは言えない上演は緻密なスタッフワークによって支えられている。額田の音楽とstackpicturesの映像は全編がサンプリングによって構成され(ていると思われ)、「メグハギ」のあり方を反復する。俳優の意志によって厳密にコントロールされた身体に櫻内憧海の音響・照明が精確に対応し、観客たる私もまたその世界と合一する。バッド・トリップの手触りは外から眺める虚構としてでなく、まさに私自身が体験するものとしてそこにあった。私の横では非常口のサインまでもが同期し明滅している。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
現実/虚構の分離と一致の運動。原作に書き込まれていたであろう(しかしもちろんそのようにして想像される「原作」も一種の「メグハギ」に過ぎない)その感触をスペノの二人はきわめて高い精度で観客に触知可能なものとして立ち上げてみせた。バッド・トリップめいた「狂った」世界を手渡す演出はどこまでも理性的で巧緻だ。
5月には『ささやかなさ』東京公演が控えている。やはり容易に「わかる」とは言いがたい松原戯曲からスペノは何を引き出し体感させてくれるだろうか。
 [©︎takaramahaya]
[©︎takaramahaya]
公式サイト:https://spacenotblank.com/
関連記事
スペースノットブランク『原風景』 │ artscapeレビュー(2019年03月15日号) | 山﨑健太
ゆうめい 父子の展示・公演『あか』 │ artscapeレビュー(2018年07月01日号) | 山﨑健太
2020/03/14(土)(山﨑健太)
映画美学校アクターズ・コース『シティキラー』

会期:2020/03/05~2020/03/10(公演中止)
アトリエ春風舎[東京都]
『シティキラー』(作・演出:本橋龍)は映画美学校アクターズ・コース2019年度公演として2020年3月5日から10日にかけて上演される、はずだった。私は上演されなかったこの作品の関係者として、「無観客」で行なわれたゲネプロの現場に立ち会った。
会場入口の螺旋階段を下りると、多くの人が集まった空間が映し出された古いテレビが受付に続くドアの上方に据えられている。それは劇場の内部、舞台と客席の様子を中継した映像なのだが、そのことに気づいたのは会場に入ってからだった。ドア付近からは劇場の内部は見渡せず、ゲストハウス風に設えられたアトリエ春風舎の様子も普段とはまったく違っていたので、それが劇場内部を映したものだとは気がつかなかったのだ。だから、それが中継ではなく録画だったとしても私にはわからない。私は私のいる「今ここ」からしかものごとを見ることができない。
舞台は東京から離れたどこかのゲストハウス。ヤマミ(近藤強)が脱サラして始めたそこヤマミ荘には若者を中心にさまざまな人が集い、長期滞在する者や繰り返し訪れる者、はては移住してきた者までいる。ライブや演劇もできるスペースを備えるそこは地元の人々の交流の場にもなっているようだ。
 ©︎かまたきえ
©︎かまたきえ
「シティキラー」というのはもし地球に落ちればひとつの都市を破壊してしまうほどの大きさの隕石のことで、2019年7月頃に地球はそのシティキラーとすれ違っていた、と上演版映像の冒頭で本橋は説明する。同じような説明は劇中でもなされ、「私たちはそのことを知らなかった」と語られる一方で「遠い向こうの島」に流れ星が落ちるのが目撃される場面もある。ヤマミ荘の近くにあるクレーターは比較的最近(およそ300年前)の隕石によってできたらしい。
私がいる「今ここ」とは別の、私がいない、ことによると人間さえいない「今ここ」がある、あった、あるだろうということ。隕石や万年雪の存在が示すその事実。テーブルの上では上演が始まる前からずっと、惑星をかたどったオブジェが運動を続けていた。冒頭でヤマミ荘にやってくるコイシ(綾音)と入れ違うようにネムリ(井上みなみ)は東京に戻るが、それでもヤマミ荘の時間は続き、東京に戻ったネムリの時間も続く。彼女は東京に戻ることを冗談めかして「死ぬ」というが、もちろん彼女が死んだあとも、『シティキラー』が終わったあとも時間は続く。
 ©︎かまたきえ
©︎かまたきえ
2時間の舞台作品を15分×8回の連続ドラマへと構成し直した『シティキラーの環』(編集:和久井幸一、以下『環』)には『シティキラー』本編の映像だけでなくそのオフショット、美学校で学び公演に向けて準備を進める俳優たちの姿を捉えたドキュメンタリーパートが挿入されている。映画美学校のある渋谷のスクランブル交差点にネムリの格好で立つ井上は、果たしてどちらとしてそこに立っているのだろうか。街頭ビジョンには「新型コロナウイルス」の文字が見える。
本橋はしばしば、異なるはずの二つの時空間をひとつの同じ時空間に重ね合わせて観客に提示する手法を用いる。演劇の制約を逆手に取り、「ひとつの世界で、それぞれに異なるモノを見て生きている」人間の姿を浮き彫りにする巧みな演出だ。一方で映画は、ばらばらの時空間で撮影された素材を巧みに組み合わせることで一貫したひとつの世界をつくり出す。ところが、『環』ではむしろ、それが完結したひとつの物語世界などではないことが積極的に示されている。画面にはしばしば、画面の外の客席に座る本橋や、撮影しているカメラマンの姿までもが映り込んでいるのだ。
つまり、『環』は全体が『シティキラー』上演の(あるいは映像制作の)ドキュメンタリーとしてつくられているということだろうか。だが、カメラマンなど「余計なもの」が映り込んでいないショットも同じくらいあるのだから話は一筋縄ではいかない。切り返した先にいるはずのカメラマンがいない場面もあり、それはつまり、その部分はカメラマンが映っていない別撮りのカットにわざわざ差し替えられているということだ。
 ©︎かまたきえ
©︎かまたきえ
演劇における本橋の手法は裏返しで映像へと適用されている。例えば第2環でマコト(中島晃紀)がモリコ(宇都有里紗)に告白する場面。二人の背中越しに夜景を思わせる幻想的な光が見えるのだが、カットが切り替わると二人は座卓の上に立っていて、その周囲にはヤマミ荘の仲間たちが座り込んでいる。ひとつの世界に見えるものは、バラバラの視点を持つ者が集まることで紡がれていく。
鳥によって結ばれる二つのエピソードが印象的だ。森(?)で鳥に遭遇したオヤカタ(廣田彩)は「ここってどこですかね」と問いかける。その先にいるのはしかし、ウズベキスタンからヤマミ荘にやってきたシトラ(淺村カミーラ)の姿だ。彼女は何か言葉を返すが、それは日本語でも英語でもなく(ロシア語らしい)、オヤカタは「鳥語だからわかんねえ」とぼやく。
続く場面ではヤマミ荘で飼育されている鶏がシメられる。ワルというその鶏の名前は、ほかの鶏をいじめることから付けられたものらしい。母親(山田薫)と共に移住してきてヤマミ荘の近くに住んでいるアサト(秋村和希)は初めて鶏をシメる。その夜、実は中学のときにいじめられていたのだと彼は母親に告げる。鳥との遭遇から鳥をシメるまでの一連の流れはその後、夢のなかでの出来事のようにかたちを変えてもう一度繰り返される。だが、そこで吊るされシメられるのはワルではなく「誰か2」(百瀬葉)と呼ばれる存在だ。『環』にはその瞬間を彼女の視点から見た、首すじをカッターナイフで切りつけるアサトの姿を正面から捉えた映像も差し込まれている。
オヤカタと鳥=シトラの、ワルとアサトの、あるいは私と誰かの世界は違っている。それでもネムリの言葉を借りれば「いろんな者たちがすれ違って、すれ違って、すれ違って、かろうじてこうしてある」。学校は、劇場は、そのことを学ぶ場所だ。この作品は、映画美学校アクターズ・コースという俳優養成講座の修了公演として上演が予定されていた。
 ©︎かまたきえ
©︎かまたきえ
映画美学校:http://eigabigakkou.com/
『シティキラー』上演版映像:https://youtu.be/_aHAiDaLFBI
『シティキラーの環』第1環:https://youtu.be/eNWh038oOoU
関連記事
ウンゲツィーファ『転職生』 │ artscapeレビュー(2018年04月01日号) | 山﨑健太
2020/03/04(水)(山﨑健太)
キュンチョメ『いちばんやわらかい場所』
会期:2020/03/01~2020/03/02
ゆりかもめ台場駅周辺[東京都]
「参加者のみなさまには、子供の頃いちばん大切にしていたぬいぐるみをお持ちいただきます。もし探してもみつからない場合、もう捨ててしまっている場合は、今たいせつにしているぬいぐるみがあればそれをお持ちください。なにもない場合、自分が子供のころに一番大切にしていた『やわらかいもの』に関する記憶を思い出しながら、会場にお越しください」。
シアターコモンズ'20で開催されたキュンチョメによるワークショップ『いちばんやわらかい場所』の参加者に事前に送られてきたメールにはこう記されていた。
ゆりかもめ台場駅前に集合した20名ほどの参加者は二人一組となり、互いのぬいぐるみを紹介し合いながら歩くよう促される。私が子供の頃に大切にしていたネコのぬいぐるみは探しても見つからず、代わりにかつて高校の同級生からオーストラリア土産としてもらったコアラのぬいぐるみを持参した。私はほかにもうひとつしかぬいぐるみと呼べるものを持っておらず、ごく最近手元に来たそれはこのワークショップの趣旨に合っているとは思えなかった。一時期クレーンゲームにハマっていたこともあり、部屋にそれなりの量のぬいぐるみがあったこともあるのだが、それらはいまはない。記憶にないがおそらく捨ててしまったのだろう。
というようなことを話しながらしばらく歩いたところでペアをシャッフル。次の会話テーマはそのぬいぐるみを発見した(と出会った?)ときのこと。しばらくするともう一度シャッフルがあり、最後のテーマは「あなたを縛るもの」だ。私はコロナウイルスや花粉、金(のなさ)といったことをとりとめもなくしゃべった。
15分ほど歩いた先の会場にはウサギ、トラ、パンダ、ゾウ、カッパ、ライオン、リスなどの着ぐるみが用意されていた。参加者は今度はそれを着たうえで持参したぬいぐるみを持ってお台場の街を歩くのだという。初めて着た着ぐるみのなかは想像以上に暑く、私が選んだライオンは口のメッシュから外を覗くタイプだったので視界は極端に狭かった。心細くよろよろと歩き出すが、20人弱の着ぐるみ集団が小雨降るお台場の街に繰り出すさまは、一人ひとりはファンシーでも全体としては異様な迫力がある。
 [撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
[撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
 [撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
[撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
雨の平日、しかも昼間ということで人出はさほど多くはないものの、商業施設の集まるそのエリアにはそれなりに人がいる。着ぐるみを着た私に手を振る子供に手を振り返し、そうでなくともガラス越しに着ぐるみの集団を発見して驚く人々には自ら手を振ってみたくもなる。外国人観光客と思しき人々と記念撮影もした。
広場で集合写真を撮ると20分の自由時間だと言われ、私はショッピングモールの中に入ってみる。ギョッとする人。手を振ってくる人。話しかけてくる人。視界が狭いのでいまいちどこを歩いているのかわからない。気づけばシネマコンプレックスの入り口らしきところで、危うく係員に追いかけられそうになる。再び外に出るとリスとパンダが音楽をかけて踊っており、私はそこに合流する。
 [撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
[撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
着ぐるみは相当に無敵である。常ならざる大胆な行動ができてしまう。子供にも人気だ。小雨も気にならない。しかしそれらの行動は私の意思によるものだっただろうか。着ぐるみならば手を振るべしと思っていたところは確実にある。外見が私の行動を、他者の反応を規定する。子供も外国人観光客も係員も、着ぐるみの内側の36歳男性を見てはいない。無敵は孤独とセットなのだ。「やわらかい場所」は守られていて、守られているから「やわらかい」。
時間が来て着ぐるみを脱いだ私たちは改めて「集合写真」を撮る。それは参加者が持参したぬいぐるみたちだけが並ぶ集合写真だ。ワークショップはここで終わる。
 [撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
[撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
後日、ワークショップの様子を記録した写真が送られてきた。だがそこに記録されていたのはワークショップの後半、つまり着ぐるみを着てからの参加者の姿だけだった。そこに写っているのが「私」であることを保証するのは私自身の記憶と、ライオンが手に持つコアラのぬいぐるみだけである。私のアイデンティティはコアラのぬいぐるみとして示される。昔の写真を見ても当時のことが思い出せないというのはよくあることだ。記録は残っても記憶は薄れていく。友人に確認すれば、コアラのぬいぐるみは高校ではなく中学のときの土産だったらしい。過去と現在の私をつなぐ曖昧な記憶。その頼りないよすがとしてのぬいぐるみも既製品に過ぎず、写真に写るそれが本当に私のものであるという保証はない。コアラのぬいぐるみの記憶もほかの多くのぬいぐるみの記憶と同じように忘れられるかもしれない。そのとき、写真に写る「私」は私でなくなるだろうか。「いちばんやわらかい場所」は目には見えない。
 [撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
[撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
 [撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
[撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
 [撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
[撮影・画像提供:シアターコモンズ’20]
シアターコモンズ'20:https://theatercommons.tokyo/program/kyun-chome/
キュンチョメ:https://www.kyunchome.com/
2020/03/02(月)(山﨑健太)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)