artscapeレビュー
2022年12月15日号のレビュー/プレビュー
レオナルド・ダ・ヴィンチ理想都市模型展──感染症に立ち向かう 500年前の理想都市

会期:2022/11/17~2022/12/11
静岡文化芸術大学 ギャラリー[静岡県]
昨年末に静岡文化芸術大学を訪問した際、ミラノ時代のレオナルド・ダ・ヴィンチが構想した理想都市の大きな木造模型(3m×1.7m)があると聞いて、梱包を解いて見せてもらい、これはもっと広く知られるべきものだと感想を述べたのだが、およそ一年たって、同大学の松田達の企画によって展覧会が実現されることになった。
会場では、模型の3DCG映像、VRの体験、模型のARやプロジェクション、関連資料としてパネルや書籍などを紹介している。ちなみに、理想都市といっても、全体の輪郭が円形といった概念的なものではなく、ダ・ヴィンチのそれはかなり実践的なアイデアで、当時のペストの流行を踏まえて、疫病対策も意識したものだった。ゆえに、コロナ禍を体験した現代の視点から見ても興味深い。また人間と馬車が通る道路を上下で分離し(いまのペデストリアンデッキ)、運河を含む交通のネットワークを立体的に組み立てたり、水はけの良さなど細かく検討している。古典的なパラッツォ風の意匠を剥ぎとると、近現代の都市デザインにも通じるだろう。

2021年の訪問時に見たダ・ヴィンチの理想都市の木造模型

模型の3DCG映像

VR体験ができるコーナー

模型に投影されるプロジェクション・マッピング
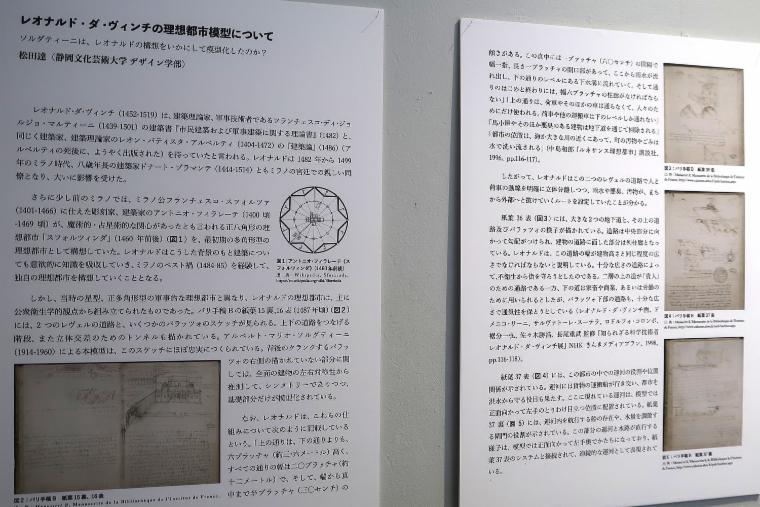
解説パネル

今回の展示

ポスターコンペ
ちなみに、あくまでもダ・ヴィンチは15世紀末にいくつかの断片的なスケッチを残しており、模型は当時のものではない。今回展示されたのは、ダ・ヴィンチの科学技術博物館の設立に尽力したにイタリア人の航空技師、マリオ・ソルダティーニが1956年に制作したものである。そして池袋の西武百貨店が1984年のイタリアン・フェアに際して、これを入手した後、解説を執筆したルネサンスの建築史家、長尾重武を通じて、武蔵野美術大学に移管されていたが、さらに静岡文化芸術大学に寄贈されていた。ともあれ、模型だけを見ると、ダ・ヴィンチがまるで全体像を構想していたような錯覚に陥るが、実際はソルダティーニが独自の解釈によってつなぎあわせている。ゆえに、モダニズム的な感覚によって再配置されたかもしれない。また詳細に観察すると、スケッチとの微妙な差異(意匠や装飾)、あるいは表現の違い(上部の壁をなくしたり、追加)などにも気づく。したがって、約半世紀以前につくられた都市模型も、別の歴史的な価値をもつ。改めて、模型が木造ゆえに、ほとんど劣化していないことにも驚かされる。実際、ルネサンス時代につくられた木造の建築模型は、今なお文化財として残っているくらいだから、相当の耐久性があるはずだ。おそらく、都市模型そのものも研究のテーマになるだろう。

パルマノヴァの模型
2022/11/27(日)(五十嵐太郎)
アンドレ・レリス『ランディ・ローズ』
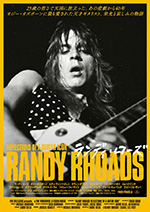
筆者がハードロックを聴きはじめたとき、ランディ・ローズはツアー中の不幸な小型飛行機の事故で亡くなった直後であり、すでに伝説的な美形のギター・ヒーローになっていた。25歳にして早逝したため、オジー・オズボーンのバンドではわずか二枚のアルバムしか参加していない。しかし、「ブリザード・オブ・オズ」(1980)と「ダイアリー・オブ・マッドマン」(1981)で披露した憂いを帯びたソロ、クラシカルなフレーズ、そして印象的なリフによって、圧倒的な影響を残すことになった。今なお、ロック系のイベントでは、「クレイジー・トレイン」(1980)などの代表作が演奏されている。したがって、死後40年もしてから公開されたドキュメンタリー映画を見ないわけにはいかない。もっとも、制作プロセスに問題があるせいか、内容は粗く、不備を感じるものだった。例えば、劇場の大画面と音響で、ランディ・ローズのライブ演奏を見られるのかと思いきや、ほとんどない。例えば、エンディングでは、素人がランディのギターをコピーした映像のリレーが流れる。実はこの映画は、ランディの家族やオジーから正式に認証を受けていないという。ゆえに、キーパーソンとなる後者への新しいインタビューがまったくない。悪魔と天使とでもいうべき、オジーとランディのコンビは、驚くべき作品を生みだしたのだから。
もちろん、非公式であろうとも、工夫すれば、おもしろいドキュメンタリーはつくれるはずだ。ただ、インタビューの人選が偏っていたり、ランディのプレイに対する音楽・技術的な解説が少ないなど、やはり不満が残る。一方で尺としても長いクワイエット・ライオット時代のエピソードの数々はあまり知らなかったので興味深い。ランディはクワイエット・ライオットの創設メンバーであり、オジーに引き抜かれるまで、このバンドでくすぶっていた。実際、今回の映画は、才能が開花し、輝いたオジーの時代ではなく、初期クワイエット・ライオットのドキュメンタリーというべき内容だろう。とすれば、盟友だったヴォーカルのケヴィン・ダブロウの貴重な証言を期待したいところだが、彼もすでに鬼籍に入り、新しいインタビューはない。ちなみに、このバンドは、ランディが亡くなった後の1983年、「カモン・フィールズ・ザ・ノイズ」が大ヒットし、これを収録したアルバム「メタル・ヘルス」がヘヴィ・メタルとして初の全米1位を獲得している。もはやランディよりも速く、巧く弾けるギタリストはめずらしくなくなった。だが、表情豊かなフレーズ、歌をひきたてるオブリガード、激しく歪んだ低音のリフ、ドラマティックな構成力を総合的に兼ね備えた、記憶に残る存在として今後も語り継がれていくだろう。
公式サイト:https://randy-rhoads.jp
2022/11/28(月)(五十嵐太郎)
KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ライカムで待っとく』

会期:2022/11/30~2022/12/04
KAAT神奈川芸術劇場[東京都]
沖縄についての物語、と言われたとき、どのような物語を思い浮かべるだろうか。『ライカムで待っとく』の登場人物のひとりはこう言う。「アメリカに支配されて、差別されて、隷属されて、その怒りや鬱憤が吹き出した末の犯行。必要なのは、そういう物語だよ」。「その方が読者の共感も狙える」し「沖縄の人たちに寄り添った記事になると思わないか」と。
沖縄本土復帰50年となる今年、「忘」をシーズンテーマに掲げたKAAT神奈川芸術劇場のプロデュース作品として、沖縄在住の劇作家・兼島拓也が書き下ろした『ライカムで待っとく』が田中麻衣子の演出で上演された。この作品は1964年、アメリカ占領下で起きた米兵殺傷事件を基に書かれた伊佐千尋によるノンフィクション『逆転』に着想を得たものだという。
 [撮影:引地信彦]
[撮影:引地信彦]
雑誌記者の浅野(亀田佳明)は、妻・知華(魏涼子)の祖父の葬儀で沖縄へ向かうため、仕事を切り上げようとしていた。そこに上司の藤井(前田一世)が沖縄出身の伊礼(蔵下穂波)を連れてやって来る。見せられた写真に写る自分そっくりの人物に驚く浅野。それは伊礼の祖父なのだという。伊礼は、祖父の手記に記されていた、かつて沖縄で起きた米兵殺傷事件のことを取材してもらえないかと浅野に依頼する。半ば押し切られるようにして浅野は取材を引き受けるが、その写真には知華の祖父・佐久本寛二(南里双六)も写っていたこと、そして佐久本が米兵殺傷事件の容疑者のひとりだったことがわかり──。
 [撮影:引地信彦]
[撮影:引地信彦]
物語は2022年と1964年を行き来し、舞台上では浅野の取材内容を再現するかのようにして過去が立ち上がっていく。あるいはそれは伊礼の祖父の手記に、伊佐の『逆転』に記された過去であるのかもしれず、何より兼島の戯曲に書き込まれた物語であることは間違いない。いずれにせよそこでは記された言葉が先にあり、因果は逆転している。再生産される物語。やがて取材を進める浅野の現在もまた、自らにそっくりだという伊礼の祖父のそれと重なり合うようにしてウロボロスの環のように閉じた因果に、あらかじめ定められた「沖縄の物語」に飲み込まれていく。現在と過去は混じり合い、そして浅野たちはある選択を迫られる。
 [撮影:引地信彦]
[撮影:引地信彦]
廃藩置県に沖縄戦。浅野に向けられた「忘れたんですか? あなたが沖縄をこんなふうにしたんですよ」という言葉が示すように、「沖縄の物語」は本土の人間が書いてきたものだ。舞台上ではそうして沖縄に与えられた物語が手際よく展開されていく。なぜだかそこに巻き込まれ戸惑う藤井に沖縄の男が放つ「こういうふうになるよって、なってるから」という言葉は痛烈だ。男は辺野古と思われる場所に座り込む人々に対しても「もうこの後どうなるか決まってるんですけど」「そのうち立ち上がって、どっか行っちゃうと思うので、それまで待っとくしかないですね」と容赦がない。しかしその視線が向けられた先にあるのは辺野古ではなく観客が座る客席なのだ。私もまた「そのうち立ち上がって、どっか行っちゃう」観客のひとりでしかない。
 [撮影:引地信彦]
[撮影:引地信彦]
 [撮影:引地信彦]
[撮影:引地信彦]
物語の案内人のようにふるまうタクシー運転手(南里)は、沖縄は日本のバックヤードなのだと言う。そういえば、舞台裏から持ち出された箱には核兵器や毒ガスが詰め込まれていたのだった。表舞台が美しく平和であるためには、そんなものはバックヤードに押し込めておかなければならない。バックヤードという言葉はまた、物語を紡ぐことそれ自体の限界を示すものでもあるだろう。言うまでもなく、舞台の上に乗るのは物語として描かれた人々だけだからだ。その背後には無数の描かれなかった人々がいる。回り舞台がいくら回転しようと舞台裏が、そこにいる人々が見えてくることは決してない(美術:原田愛)。
兼島の戯曲は軽やかなユーモアで観客を引き込んでいく。演劇の構造を利用する手つきも巧みだ。だが、その先に待ち受けている物語はあまりに重い。田中の演出と俳優陣(上記に加え小川ゲン、神田青、あめくみちこ)の演技はそれらを舞台上に見事に立ち上げており、特に南里は飄々とユーモアを、悲哀を、怒りを、諦念を演じて素晴らしかった。演劇の上演は戯曲というあらかじめ書かれた言葉によって定められたものだが、舞台上にはそれ以上のものがあるのだ。そこに僅かな希望を見出すことくらいは許されるだろうか。
 [撮影:引地信彦]
[撮影:引地信彦]
『ライカムで待っとく』の物語がどのような顛末を迎えるのか、その詳細はここには書かない。この作品はこれからも再演されていくべき作品であり、観客がその客席に居合わせることにこそ大きな意味がある作品だからだ。あるいはせめて戯曲を読むのでもいい(戯曲は雑誌『悲劇喜劇』2023年1月号に掲載)。そうして多くの人が、兼島拓也という沖縄在住の劇作家が書いたこの物語に立ち会うことを願っている。
『ライカムで待っとく』:https://www.kaat.jp/d/raikamu/
2022/11/30(水)(山﨑健太)
人間写真機・須田一政 作品展「日本の風景・余白の街で」

会期:2022/09/29~2022/12/28
フジフイルムスクエア写真歴史博物館[東京都]
須田一政は1986年に、フジフイルムスクエアの前身である東京銀座の富士フォトサロンで、「日本の風景・余白の街で」と題する展覧会を開催している。今回の展示は、その時の出品作43点から32点を選び「当時の作品の階調、色調を忠実に再現」したプリントによるものだった。
須田は写真集『風姿花伝』(朝日ソノラマ、1978)に代表されるように、6×6判の黒白写真をメインに作品を制作していた。だが1980年代になると、本作のようにカラー作品を積極的に発表し始めた。カラーフィルム(富士フイルム製のフジクローム)を使用することで、色という表現要素を手にした須田は、日常の光景に潜む悪夢のような場面を、より生々しくヴィヴィッドに描き出すことができるようになる。
本作は東京だけでなく、京都、三重・伊勢、長野・小諸、大阪など、日本各地の「観光地」で撮影した写真群を集成したものだが、そこで彼が目を向けているのは「平面上に在る日常という『かげ』の存在」であり、「自らの周辺におこり得る刹那的な特殊空間」である、そのような魔に憑かれたような特異な気配を嗅ぎ分け、素早くキャッチする能力の高さこそが須田の真骨頂であり、それはまさに本展のタイトルである「人間写真機」そのものの機能といえるだろう。
「人間写真機」というのは、どうやら本展のために考えられた造語のようだが、須田の写真家としての「習性」を見事に言いあらわしている。須田は本作以後も、2010年代に至るまで、眼差しとカメラとが一体化した「人間写真機」としての仕事を全うすることになる(2019年に逝去)。そろそろどこかで、その全体像を見ることができる展覧会を企画してほしいものだ。
公式サイト:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/220929_05.html
2022/12/04(日)(飯沢耕太郎)
鶴巻育子「芝生のイルカ」

会期:2022/12/01~2022/12/25
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
鶴巻育子は、ふとした機会から「視覚障害者の外出をサポートする同行援護従業者」として活動するようになった。目を使って仕事をする写真家である自分とは対照的な存在である彼らが、どんなふうに世界と接しているのかを知りたくなったためだという。鶴巻は視覚障害者たちと一緒にいて、彼らが発する言葉に強く惹かれるようになる。「ガラスは透明ではない」「月は穴ぼこ」「体温で感情を感じる」「境界線が変わる感じ」──今回のコミュニケーションギャラリーふげん社での個展の出品作では、それらの言葉を手がかりにしてインスピレーションの幅を広げ、「イメージを拾う」ことを試みていた。
ややトリッキーな動機の作品だが、結果的にはとてもうまくいっていた。視覚障害者という、まったく異なる状況を生きる者たちと自分の感覚とのズレを、むしろ積極的に活用することで、思いがけないイメージを収集することが可能になったからだ。それは鶴巻自身の予想をはるかに超えた世界の断片だったのではないだろうか。それらを注意深く選別し、大小のフレームにおさめて、撒き散らすように壁に掲げたインスタレーションも、とてもうまくいっていた。
鶴巻は普段は自らが主宰する東京 目黒のJam Photo Galleryで、日常のスナップ写真を中心とした作品を発表している。今回の展示は、それとはまったく違った水脈によるもので、自らの作品世界をより広げていこうという意欲を強く感じた。ただ、写真の間に言葉をバラバラに挟み込む展示構成だと、特定の言葉と写真との関係のあり方がうまく伝わってこない。その対応関係を、もう少ししっかりと明示すべきだったのではないだろうか。
公式サイト:https://fugensha.jp/events/221201tsurumaki/
2022/12/04(日)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)