artscapeレビュー
木村覚のレビュー/プレビュー
Crackersboat『flat plat fesdesu Vol. 2』Bプロ、Cプロ

会期:2013/04/23~2013/04/29
こまばアゴラ劇場[東京都]
日本のコンテンポラリーダンスにおける注目の若手作家KENTARO!!を中心としたプロジェクトチームCrackersboat。彼らが行なった、ダンスと音楽の作家たちを集めたイベントがこれだ。遠田誠や岩渕貞太など、名の知られている中堅の振付家・ダンサーも出演していたが、ぼくが見たなかでダントツに面白かったのは、Aokid×たかくらかずきだった。Aokidをはじめてぼくが見たのは、大木裕之が武蔵小金井で行なったイベントのなかでだった。ヒップホップにルーツのありそうなダンスを文系男子の雰囲気のある男の子が一人で、しかもしゃべりながら踊るという、それはそれはとても新鮮なパフォーマンスだった。今回は、たかくらかずきとのコラボレーション。イラストレーターで劇団・範宙遊泳の美術監督も行なっているたかくらは、舞台奥のスクリーンに映る机の上の世界を担当。この箱庭的世界がときに子どもの粘土遊びのようにときにゲームの画面のように変化するのに応じて、目の前のAokidはその世界に巻き込まれ、世界とともに生きようとする。Aokidのよさは、肉体が薄っぺらく思えることだ。彼のアクロバティックな動作は、それができる肉体の力量よりも肉体の軽さ薄さを見るものに感じさせる。そこがいいのだ。そもそも映像が面白く、リアリティを感じさせればそれだけ、目の前の肉体の存在意義が薄くなる、ぼくらはそうした時代に生きている。Aokidがゲームのキャラに見えてしまうとき、そこにむしろぼくらは現在の人間を感じる。今月見た『THE END』がまさにそうであったわけだが、こうした状況で踊る意味をAokidはちゃんと示そうとしている。Aokidのほかには、カラトユカリの演奏がじつにユニークだった。小さなギターをつま弾き、しっとりとした声で歌う、演奏の魅力も際立っていたのだけれど、独特の佇まいになんともいえない面白さがあった。それはなにより、微笑とともに登場し椅子に座ると、ちょこんと花の冠を頭に載せた、その瞬間に濃密だった。声で思いを届けるという、いってみればきわめてプリミティヴな行為を成功裡に遂行するには、どんなにささいなものでもある種の儀式が必要なのかもしれない。花冠は、そんな風なものに思えて、演奏中ずっと花冠とカラトユカリを交互に見続けてしまった。もっといえば、この「どうすれば場が生まれるのか」といった点に敏感になることにこそ、ダンスのなすべき仕事が隠れているのではないか、そんなことをずっと考えていた。
2013/04/27(土)(木村覚)
熊谷晋一郎『リハビリの夜』
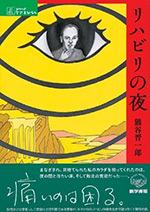
著者:熊谷晋一郎
出版社:医学書院
発行日:2009年12月
価格:2,100円(税込)
判型:A5判、264頁
例えばこんな文章が出てくる。
──「これがあるべき動きである」という強固な命令とまなざしをひりひりと感じながら、焦れば焦るほど、その命令から脱線する私の身体の運動がますます露わになっていく。
脳性まひの体とともに生活してきた、小児科医で研究者でもある熊谷晋一郎。少年期に通ったリハビリ施設でのトレイナーとの時間を振り返って綴った一文がこれなのだが、まるでダンスをめぐる文章のように読めてしまう。トレイナーが思い描く理想像を実現しようと努力しながら、それが叶わず、自分の体がバラバラになったかのように感じる。その切なさ、情けなさがとても丁寧な筆致で描かれる。この本の読みごたえがそこにあるのは間違いない。けれど、本書の白眉は、熊谷がトレイナーとトレイニーの関係性を、《まなざし/まなざされる関係》であるとき、《ほどきつつ拾い合う関係》であるとき、《加害/被害関係》であるときとに分けて論じる、その考察の確かさにある。
「自らすすんで私に従え」と告げているかのように、運動目標を押しつけるトレイナーの態度はトレイニーに対して監視的で、トレイナーにまなざされるトレイニーの体はこわばり、自壊する。こうした空しい《まなざし/まなざされる関係》やさらに強引に体の現状を見捨て体を矯正しようとする《加害/被害関係》を回避し、相互的に情報を拾い合うようにトレイナーがトレイニーに介入する状態、つまり《ほどきつつ拾い合う関係》こそ両者の望ましい関係なのではないか、と熊谷は説く。
熊谷の考察は豊かな発見に満ちている。介護という場の問題にとどまらず、ぼくが専門にしているダンスの現場にとっても充分刺激的だ。ナタリー・ポートマンが主演したバレエ映画『ブラック・スワン』に描かれたような、まなざし/まなざされる関係の苛烈さは、ダンスにおけるダンサーと見る者とのあいだに潜む基本的な状態であろう。それはそうとしてそこからさらに、ほどきつつ拾い合う関係というものへと意識を向けるのは、ダンスという枠のなかではなかなか難しい。ダンサーが目指すエリート的な身体ではなく「脳性まひの体」にフォーカスしたがゆえに、熊谷は「ほどきつつ拾い合う」などという関係を解きほぐしえたのではないか。そう思うと、ダンスという場の硬直性に気づかされる。しかし、それ以上に大事なのは、こうした視点の移動が体へ新鮮な向き合い方をうながしてくれる点に気づくことだ。他者にもわかるように自分の体験を内側から語る「当事者研究」という方法を推進してもいる熊谷の狙いは、まさにそうした新鮮な気づきを与えることにあるのだろう。
この本にはもうひとつの大きな魅力がある。「敗北の官能」「退廃的な官能」と熊谷が名づける、不可能性に直面したときに生じる独特の快楽に言及しているところだ。これをマゾヒズムに還元してしまうのは容易いが、トレイナーやボランティアと接して感じさせられる切なさや苦しさが、ある種の官能を喚起させもするということについての具体的で繊細な記述には、文学的な感動さえ受ける。授けられたこの体で生まれて死ぬほかないということは万人に共通の運命なのだ。この運命とどうきちんと向き合って自分の体ととともに生きていくか、その問いに熊谷はひとつの解答を与えてくれている。綾屋紗月との共著『つながりの作法──同じでもなく違うでもなく』もあわせて読むと、熊谷の考えをより深く知ることになるだろう。
2013/04/27(土)(木村覚)
Chim↑Pom「PAVILION」展

会期:2013/03/30~2013/07/28
岡本太郎記念館[東京都]
死を扱うと、Chim↑Pomは生き生きする。そして、彼らが死を観念としてばかりではなく、ひとつの現実として扱うとき、彼らの躍動は何かある真実に触れてしまう。そんなことが希に起こる。そのとき、出来事は事件となる。「事件」といっても、法に触れるかどうかといった話ではない。「PAVILION」展で決定的に重要な作品は、岡本太郎の遺骨を展示した《PAVILION》だろう。真っ白い光を放つディスプレイのなかに、掌に載るくらいの小さな骨が、まるで宝飾でも展示しているかのように、飾られている。岡本を骨として見るという、なんともあっけらかんとしたあけすけな仕掛けは、世界を理想化されたものあるいは美化されたものとしてではなく、ひとつの生命の運動として見るよううながしてくる。この作品を含めた展示全体にそうしたベクトルが感じられた。とくに再制作された《BLACK OF DEATH》は、自然のエネルギーに満ち満ちていると感じさせられ、強いインパクトを受けた。最初につくられた際には濃厚だったいたずら的雰囲気が希薄だったことも功を奏していた。それによって、Chim↑Pomたちの誘導で空を黒くしてしまうカラスの群れは最初のものより迫力が増しているように見えた。そこに、人間の生活の背後で普段は隠れているはずの非人間的な自然界の相貌が立ち現われた。それは恐ろしく、美しかった。岡本一人の死は自然の運動のなかのひとつのモメントであり、しかしその死も包み込んで、運動は休まず続いてゆく。Chim↑Pomが岡本太郎の死に触れて、新しい渦巻きをつくって見せた。これもまたひとつの自然の運動である。とすれば、その運動を観客の前に開示して見せたということこそ彼らが起こしている本当の事件なのである。
2013/04/21(日)(木村覚)
遠藤一郎公開ライブペイント(「遠藤一郎 展──ART for LIVE 生命の道」)

会期:2013/03/03~2013/04/14
原爆の図丸木美術館[東京都]
遠藤一郎のライヴ・ペインティングは、ともかくミニマル。そして、あえていえば「レディ・メイド」的だ。原爆の図丸木美術館の部屋一面に白い紙を敷き、遠藤は容器から明るいピンクのアクリル絵の具を取り出すと、何色も混ぜることなく、そのまま床に塗り始めた。ピンクが終わり、今度は黒。紙の真ん中に円を描き、塗りつぶす。次は黄色を取り出し、やはりどんな色も混ぜずに、ピンクが地面なら、空に相当しそうな面を黄色くした。パフォーマンスは淡々と進む。特徴的なのは、遠藤が終始「はっ、はっ、」と息を漏らしながらペイントしていることで、必要以上の緊張なり、集中なり、興奮なりが彼のなかで渦を巻いている、そう思わされる。大袈裟ともとれる息づかいとは対照的に、紙の上で展開されているものはとてもシンプルで、なんと形容しよう、ただただ「ぽかーん」としているのだ。そこに、巨大な赤い文字で、紙の左側に「泣」が、右側に「笑」が書き込まれた。これまたシンプル、ニュアンスや含意をほとんどまったく与えないただの2文字だ。遠藤はいつも、まるでマルセル・デュシャンがそうであるように、デフォルメを施さないままの、他人の手垢がべったりついた既成のものを用いる。作家の審美的個性はそれによって極限まで抑えられている。「泣」と1文字書いた途端に「く」と「な」が続く?と予想したのだが、そうした東日本大震災にまつわる類の連想を裏切り、より大きなスケールのイメージが「笑」の文字によってあらわれて、驚いた。これは人間をきわめて遠くの視点から俯瞰して見ている者の言葉だと思った。なるほど、遠藤の最近の活動に、日本列島をキャンバスに「ARIGATO」や「いっせーのーせ」の文字を書くというものがあるが、Googleを使ったあれも、宇宙からというきわめて遠くの視点から見た地球に映る文字である。彼のパフォーマンスというのは、書道家の実演パフォーマンスや、大道芸の脇で似顔絵を描く行為などと同類だと思われがちかもしれない。けれども、どこか決定的に違っていて、やはり「アート」という呼称でもあてがうほかないところがある。とはいえそれは、既存の前衛芸術系のパフォーマンスのあれやこれやともやはり相当に異なる。生命を描写するに相応しい遠藤の熱意(「はっ、はっ、」)がまずあって、その熱意がパフォーマンスの場を通過したその証しとして、なんともいえない「ぽかーん」とした空虚な痕跡を残す。その淋しいような、孤独なような、明るい色が多いのになんだか暗いその闇夜のような手触り。これこそ、遠藤一郎らしいなにかのように思うのだ。
2013/04/13(土)(木村覚)
プレビュー:Crackers boat『flat plat fesdesu vol. 2』、『駆ける女』

ダンスと音楽を混ぜ合わせたフェスティバル『flat plat fesdesu vol. 2』が開催される(2013年4月23日~29日、こまばアゴラ劇場)。KENTARO!!らが結成したプロジェクトチームCrackers boatによる企画で、A、B、Cと分かれた三つのプログラムの公演が行なわれる。個人的には、最近偏愛中のQ(演出:市原佐都子)がどんなパフォーマンスをするのか気になるところなのだが、遠田誠(Aプロ)、岩渕貞太(Bプロ)、大倉摩矢子らコンテンポラリー・ダンスや舞踏の実力ある作家が踊るほか、フレッシュなアイディアでダンス表現を更新するAokid(たかくらかずきとのコラボ)にも注目したい。青葉市子など音楽のほうも面白そうな作家たちがラインナップされている。音楽の作家たちとの公演という点からしてもそうなのだけれど、これはライブハウスで音楽の作家たちが日々行なっているような「対バン」的な仕方でダンスを楽しむことになるのだろう。こういう企画が、ダンスの鑑賞習慣を変えていくのに違いない。
そのほか、黒沢美香が上村なおか、森下真樹を振り付ける『駆ける女』(2013年4月27日~29日、スパイラルガーデン)も見逃せない。乙女度の高い黒沢の世界を2人のダンサーがどう踊ってみせるのか、楽しみだ。
2013/03/31(日)(木村覚)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)