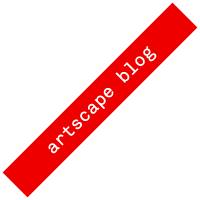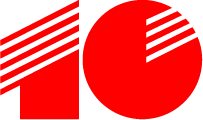結論にかえて、ゆるい未来のイメージ
少しリミットオーバ。とはいえ締めのテキストを手短かにではあるが記しておきたい。 (続きを読む…)
2011年12月3日 / 1:58 AM
続きを読むSPACE OURSELVES・・・建築はかくも柔軟で力強い
「SPACE OURSELVES」とは建築を設計する専門家だけでなくその場所で生活し日々の営みを行うすべての人=私たちによって生み出され、または発見され、あるいは実践されていく空間のあり方ということを意味している。前回は、経緯とこのSPACE OURSELVESについて述べたが、今回は個別の提案を紹介しつつ、その後の展開について記していきたい。 (続きを読む…)
2011年11月30日 / 11:04 PM
続きを読むSPACE OURSELVES・・・新しい公共のかたち
「SPACE OURSELVES」というタイトルの展覧会を今年の5月に開催した。この展覧会は「rep」の特別バージョンとして構想され、最終的には16組の建築家が参加し、京都、東京、浜松と3カ所を巡回することになった。今回はこの展覧会がどのように構想され、またどのようなメッセージをもっているのかについて述べていく。 (続きを読む…)
2011年11月30日 / 12:30 AM
続きを読むQC3:建築から 地域を 考える インタビューサイト
QCVOL,3ではこれまでの領域横断型レクチャーという形式をとらず、一年間のインタビューサイトの運営というかたちで進めている。 (続きを読む…)
2011年11月29日 / 4:49 AM
続きを読むQC:何を問うべきか? という問題提起
RADの最初のプロジェクトがこのQueryCruise(以下QC)という領域横断型の連続レクチャー。RADの結成のきっかけでもあり、現在少し形式は変わったものの継続しているプロジェクトである。世の中にはいろいろなカタチで「答え」が溢れている。けれども、その「答え」らしきものの背後にある「問い」そのものの正しさが吟味される事は少ない。よって、まずは自分たちが今必要な、そして適切な問いを設定するための連続レクチャーを企画しようと考えた。題してQuery(=問いに)Cruise(こぎだす)。 (続きを読む…)
2011年11月27日 / 2:16 AM
続きを読むKENCHIKU | ARCHITECTURE・・・最終回
先に書いたように、そもそもこのプロジェクトは2年前に日本建築が大好きなフランス人留学生と、建築の展覧会の企画を始めたばかりの私の他愛もない、それでいてなぜか確信に満ちた会話からスタートしている。その後、構想のきっかけとなる状況は変化し、想定していた会場も変更になり、結局フランス側での予算獲得はほぼ失敗(ずいぶんと希望を持たされたものだったが)し、という紆余曲折を経て今年の6月に実質的に要素が確定して進めていく事となった。 (続きを読む…)
2011年11月25日 / 12:16 PM
続きを読むKENCHIKU | ARCHITECTURE ・・・その3
2010年の夏から秋にかけては、ひたすら企画書のブラッシュアップと、助成金の申請にあけくれていた。ポンピドゥーの延期を受け、紹介を目的とした展覧会ではなく、日仏でのアイデアの交換を目的としたディスカッション重視のイベントに内容を変更し、それにともなってプロジェクトの名前を「KENCHIKU | ARCHITECTURE 」に決定。 (続きを読む…)
2011年11月21日 / 12:18 PM
続きを読むKENCHIKU | ARCHITECTURE その2
さて、ひょんなことから始まったこのプロジェクト。とにかく向かってみないと分からないだろうという事で昨年の5月にパリに飛んだ。
訪問した際に驚いたのは、日本と違って建築に関する施設の層の厚さ。 (続きを読む…)
2011年11月21日 / 10:16 AM
続きを読むKENCHIKU | ARCHITECTURE・・・その1
現在、フランスはパリで「KENCHIKU | ARCHITECTURE 2011 」というイベントを開催している。これは日本とフランスの若手建築家総勢12組が参加し展覧会とトークイベントを行なうというもので、すでに3日間のトークセッションとラウンドミーティングを終え、今月の10日まで展覧会が続けられる。これはRADだけでなく複数のメンバーによるコラボレーションと成り立っているKENCHIKU ARCHITECTURE実行委員会が主催し、会場になっているl’ESA(パリ建築特別大学)の協力のもと実現したプロジェクト。今回からは、フランスと何のゆかりもなかった我々がどうしてこのプロジェクトにいたったのか、またそこにへどのような思考が介在していたのかについて述べていきたい。
(続きを読む…)
2011年11月6日 / 9:52 AM
続きを読むrep 建築のカタチとその価値
随分間があいてしまいました。今回はrepというプロジェクトについて書きます。rep – radlab. exhibition project- とは、僕らが運営しているradlab.というスペースで実験的に行なっている建築の展覧会のことです。このradlab.は、実際足を運んでいただいた方はご存知のようにradlab.は雑居ビルの3階にある、もともとは住居だったところを少しずつ自主施行で改装したスペースで、イメージとしてあったのは建築のオルタナティブスペース。関西には東京のように建築専門のギャラリーや書店がほとんどなく、なにかしらのイベントが行われるといえば大学などの公的な機関という状況だったので、もっと気軽で実験的な試みが行なえる場を目指しました。
(続きを読む…)
2011年10月28日 / 11:07 AM
続きを読む「建築の居場所」を探して、その記録/はじめまして
みなさん、はじめまして。artscape BLOG第10タームの担当をすることになりました川勝です。大学で建築を学んだ後、2008年にRADというリサーチプロジェクトを立ち上げ、京都を拠点に活動しています。RADとは、「Research for Architectural Domain」の短縮形で、直訳すると「建築の領域を調査する」となりますが、僕らはもう少し噛み砕いて「建築の居場所」と呼んでいます。今回のblogでは、現在世界的に見いだされつつある、これまでとは少し違った切り口の「建築の居場所=ARCHITECTURAL DOMAIN」を、リサーチの結果レポートとしてではなく、その過程であるドキュメント=調査記録によって浮かび上がらせていきます。 (続きを読む…)
2011年9月7日 / 12:41 PM
続きを読む