artscapeレビュー
山﨑健太のレビュー/プレビュー
円盤に乗る派『ウォーターフォールを追いかけて』

会期:2020/10/23~2020/11/2
『ウォーターフォールを追いかけて』は「同名の戯曲に取り組みながら分断の時代におけるドラマの意義の再発見を目指す、1年間のプロジェクト」。円盤に乗る派は2018年の活動開始以来、上演と併せてシンポジウムや雑誌の発行などを行ない、その総体を公演として人の集う場所をつくり出してきた。今回もオンライン上演と合わせて読書会、上映会、シンポジウムが実施され、オンラインにおいても一貫して人が集う場を問い続ける姿勢が見える。
『ウォーターフォールを追いかけて』のオンライン上演にはいくつかのユニークな特徴がある。まず第一に「上演」がオンラインで収集された無数の声によって構成されていること。『ウォーターフォールを追いかけて』の特設サイトには上演に先がけて、誰でも参加できる「録音」のコーナーが設けられた。「録音に参加する」をクリックすると画面には戯曲の断片が表示され、参加者は「誰もいない室内で、壁の向こうにいるかもしれない誰かに聞かれないように注意しながら」録音に臨むことになる。収集された声は脚本・演出を担当するカゲヤマ気象台によって編集され、江口智之の映像とAOTQの音楽と合わせて「上演」を構成する。
そもそも、『ウォーターフォールを追いかけて』という戯曲はその成り立ちからして複数の声を孕んでいる。この戯曲は早稲田小劇場どらま館で早稲田大学の学生を対象に実施された「ドラマゼミ」の最終成果物である「部品(パーツ)」を原案(ドラマゼミメンバー:カゲヤマ気象台、片山さなみ、中西空立、マツモトタクロウ)として執筆されたものなのだ。
さらに、開演はいずれも23時に設定され、上演時間は50分程度。観客は一日の終わりを『ウォータフォールを追いかけて』過ごす。作品自体はあらかじめ編集され完成されたものだが、配信はその都度リアルタイムで行なわれていたようだ。回線が不安定なのかときおり画面が止まったり音声が途切れたりもする。画面上部にはリアルタイムの視聴人数が表示され、同じ時間、違う場所で同じ声に耳を傾けるほかの人々の存在を微かに伝える。それはラジオとリスナーの関係に似ている。だが、同じ時間に届けられるそれらの声は、夜空に瞬く星の光のように、それぞれに異なる時間、異なる場所で密やかに発せられたものだ。
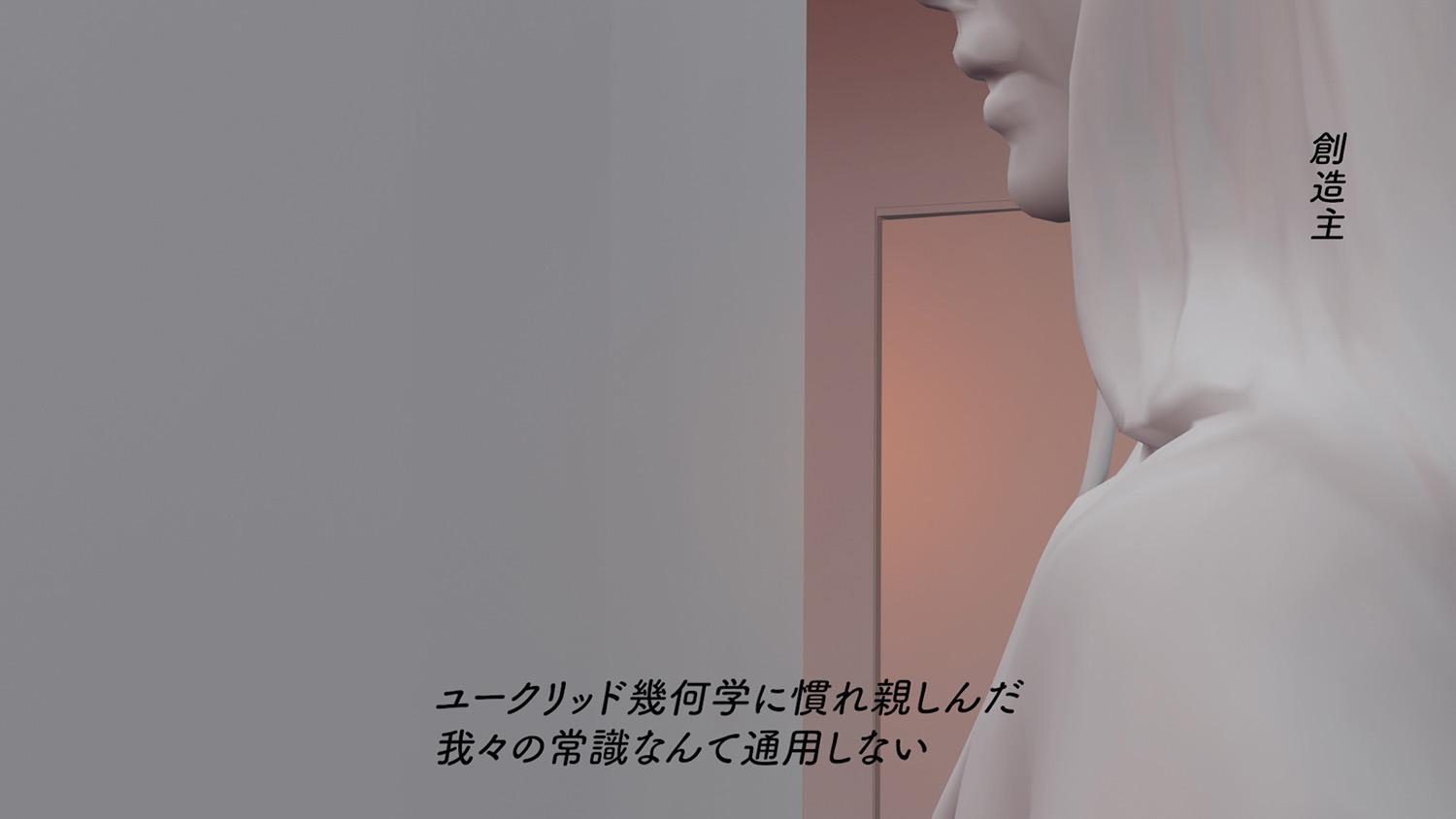
私も録音に参加したのだが、録音から上演までに1カ月以上の時間が経過していたため、自分がどのような言葉を発したかはすっかり忘れてしまっていた。他人の言葉を発する自分の声は半ば他人のもののようでもあり、上演を聞けば確かにそのような言葉を発した記憶もあるそれは、しかし私の知らない文脈のなかで発せられていた。他人の言葉が私の言葉となり、そして再び見知らぬ言葉となり広がっていく。
今回の『ウォーターフォールを追いかけて』のオンライン上演では、密やかに発せられた言葉が密やかに聴取され、同時にゆるやかな場を形成していた。そのようなあり方自体、プロジェクトのひとつの成果であり目指したところではあるだろう。では、上演が立ち上げたものはなんだったのだろうか。
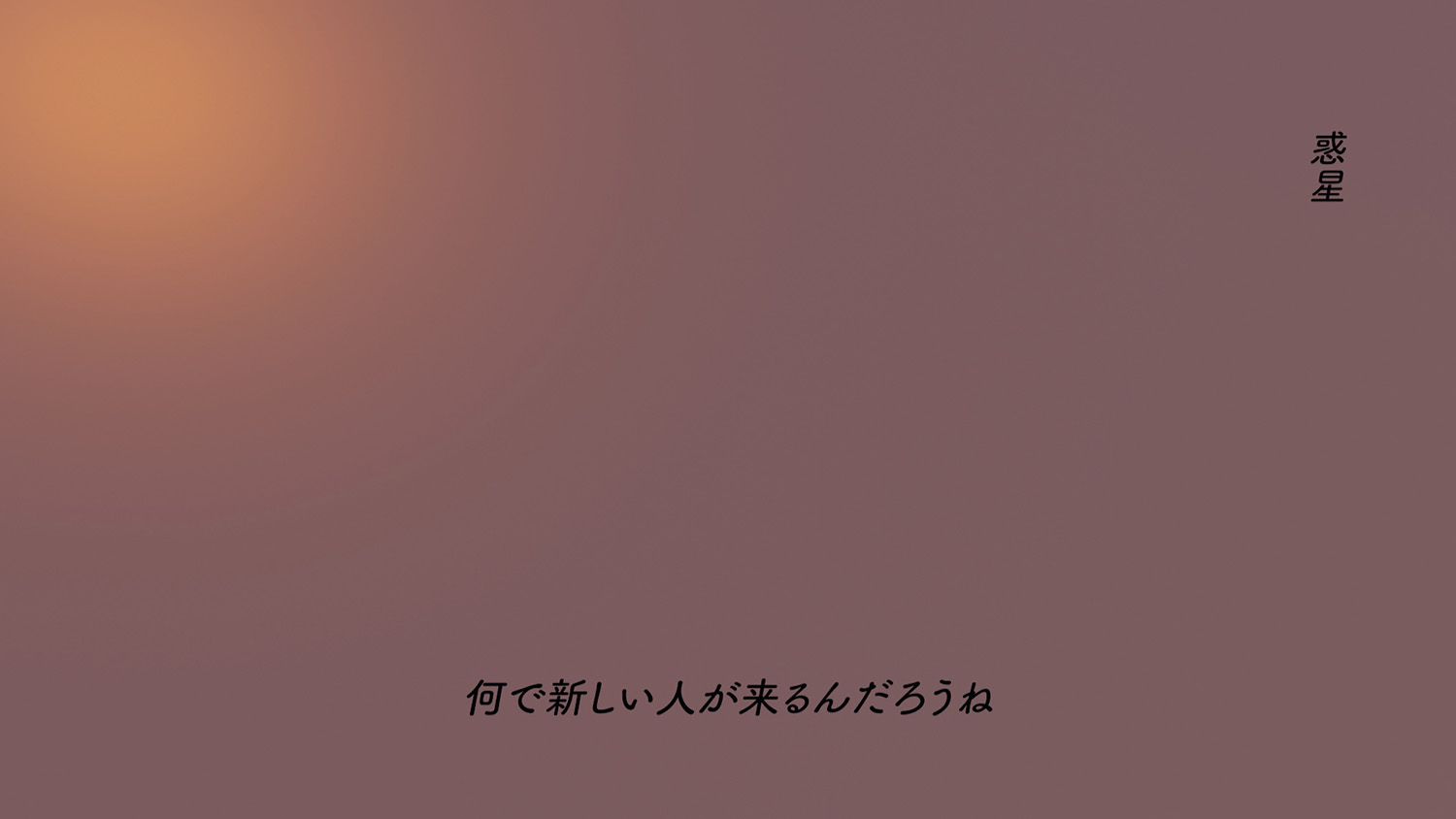
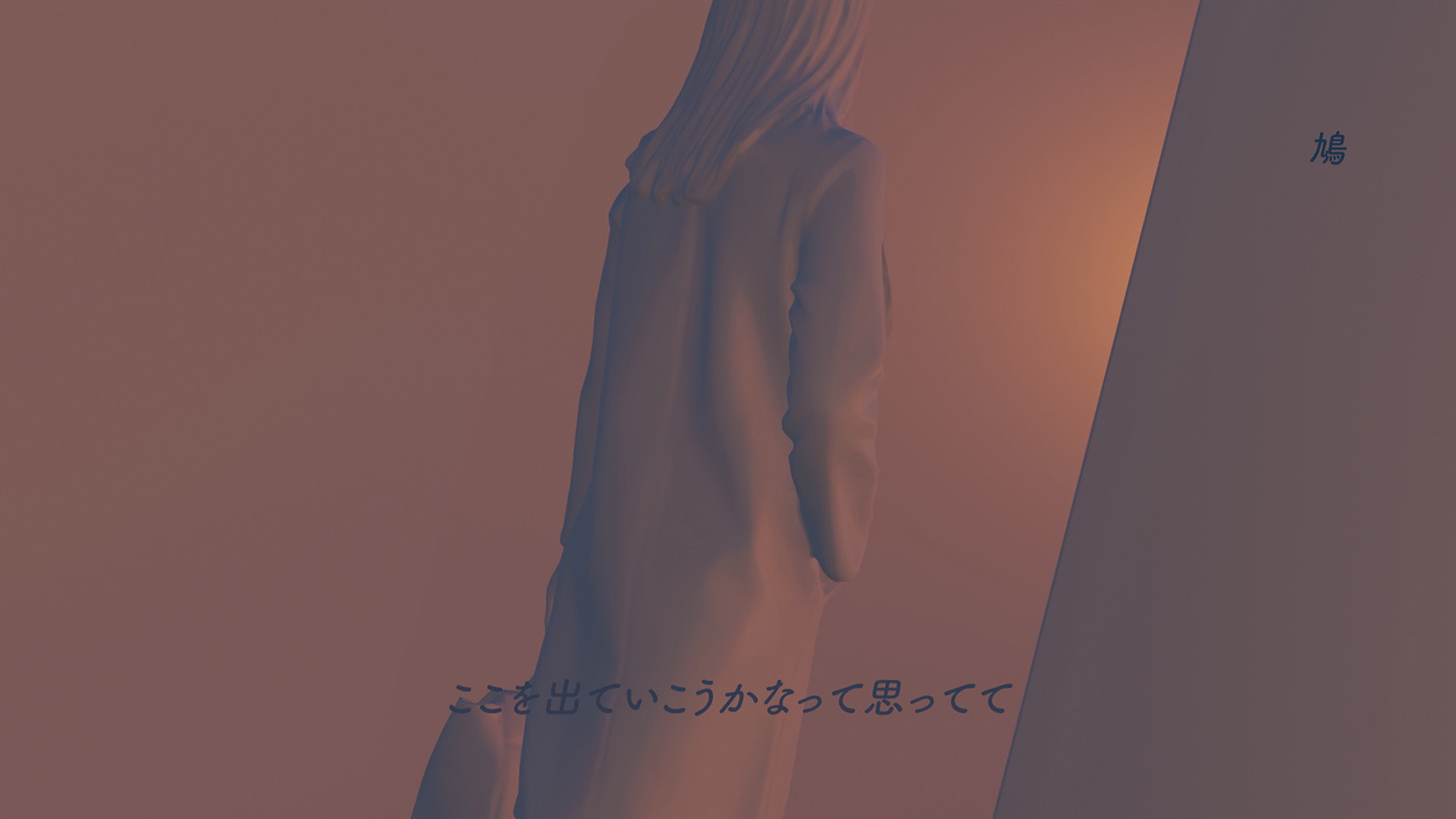
戯曲に登場する7人の人物は100以上の声によって演じられるため、聞こえてくる声だけを頼りに観客が一貫した人物像を構築することは難しい。画面には台詞とそれを発する人物の名前も字幕として表示されるものの、そうして示される一貫性を裏切るようにして声は次々と移り変わっていく。室内を漂うような映像(それは物語を表象するものではない)と音楽も相まって、主体はむしろ空間へと溶け出していくかのようですらある。今回のオンライン上演を通じて観客が戯曲で描かれた物語の全体像を把握することは困難だったのではないだろうか。おそらくそれでよいのだ。物語の全体像はわからずとも、観客のうちに言葉の断片は残るだろう。観客は戯曲のデータにアクセスすることだってできる。それに、プロジェクトはまだはじまったばかりだ。
創造主と名づけられた人物の長い長い台詞からはじまる物語に登場する人々にはどこか「間違った」世界にいるような感触がある。最後に発せられる言葉は「この世界」を生きる私にとっても切実だが、ここにはそれは記さない。プロジェクトのなかで再び戯曲の言葉と出会うとき、また改めて考えることにしたい。
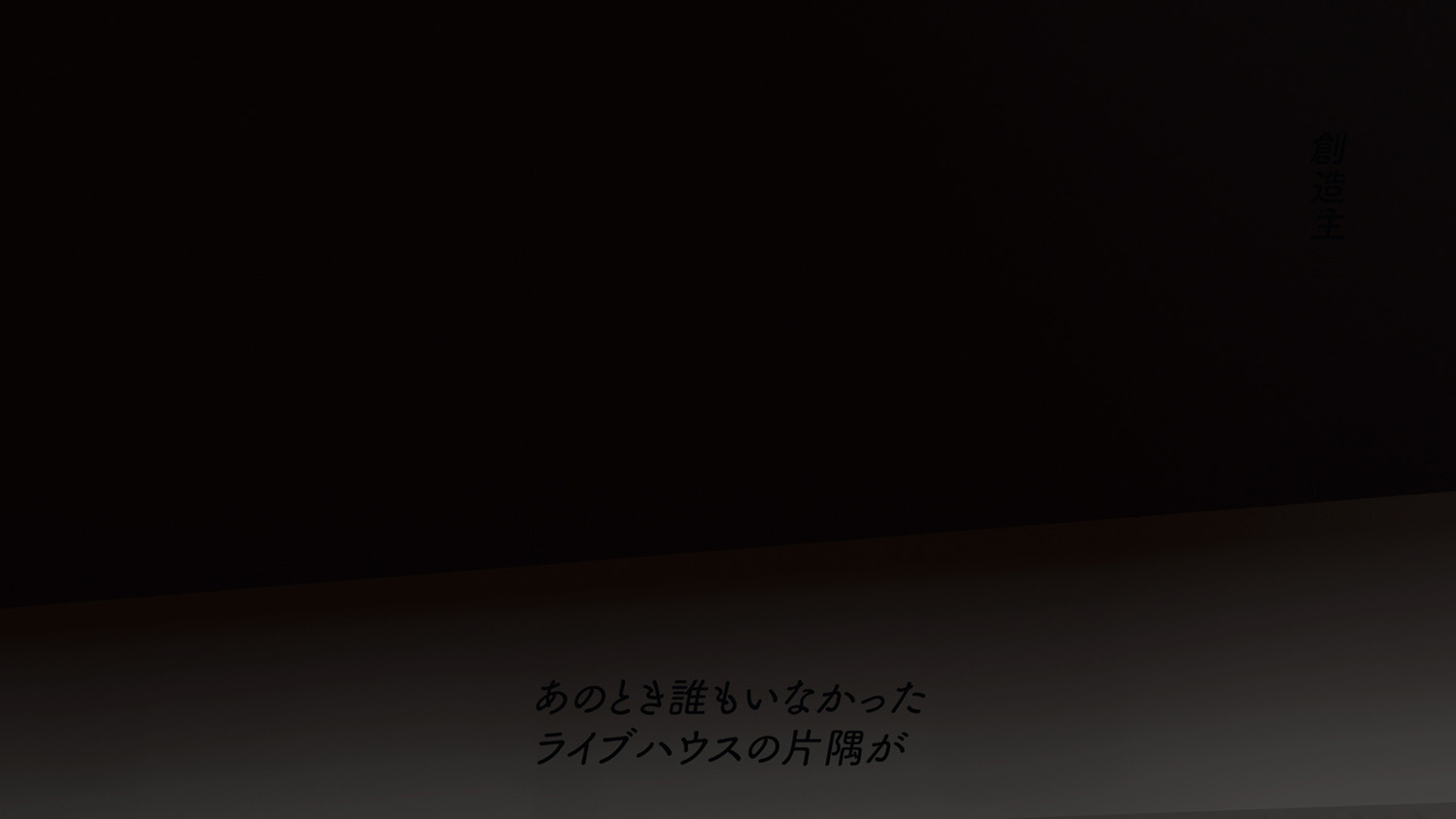
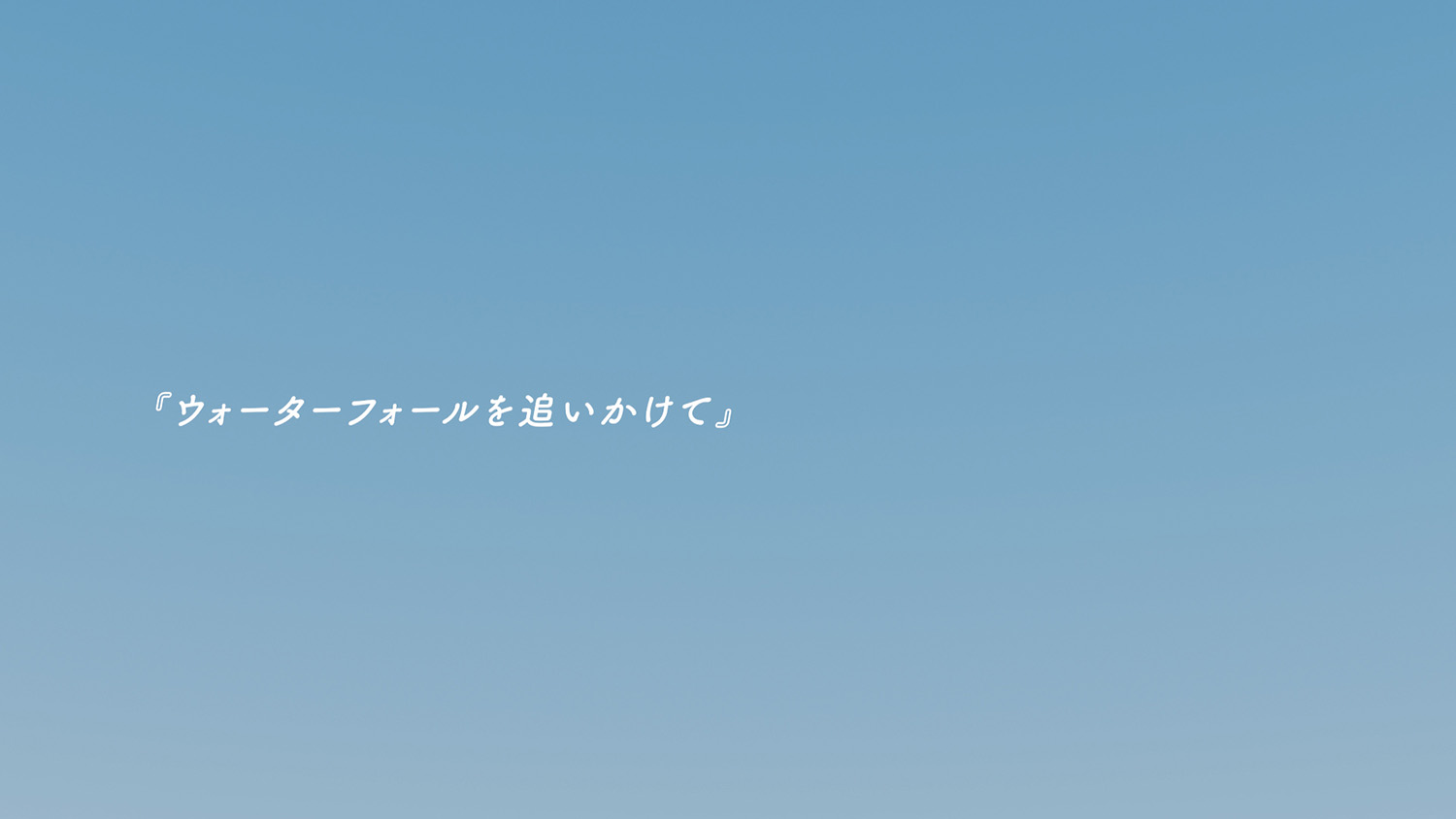
公式サイト:https://noruha.net/
2020/11/02(月)(山﨑健太)
ファビアン・プリオヴィル・ダンス・カンパニー『Rendez-Vous Otsuka South & North』

会期:2020/10/17~2020/11/12
星野リゾート OMO5東京大塚 4階 OMOベース/トランパル大塚[東京都]
『Rendez-Vous Otsuka South & North』(コンセプト・振付:ファビアン・プリオヴィル)はVRセットを使って鑑賞するダンス作品。これまでに五つのフェスティバルに招聘され、その土地ごとに異なるバージョンの『Rendez-Vous』が制作されてきた。今回はフェスティバル/トーキョー20のプログラムとして大塚駅の南口と北口を舞台に二つのバージョンが発表された。
北口バージョンの会場は星野リゾート OMO5東京大塚 4階 OMOベース。大塚駅徒歩1分の立地にあるホテルのフロントに併設されたカフェの一角で観客は作品を鑑賞する。VRセットを装着し映像がはじまると、そこに映し出されるのは先ほどまで私がいたカフェ。だが、そこで本を読み、あるいは談笑していたほかの客の姿は消え、窓の外の夕空も青空へと変わっている。誰もいない世界。それを眺める私自身の身体も見えない。気づけば白い衣装に身を包んだ4人のダンサー(近藤みどり、田中朝子、中川賢、吉﨑裕哉)が踊りはじめている——。
5分ほどのVR体験は白昼夢のようだった。現実とほとんど同じ、しかし明らかに現実ではない世界。映像が終わりVRセットを外すと窓の外は再び夕空。ほかの客も変わらず本を読み、会話を続けている。確かな現実への帰還。だが、本当に?
VRセットを介してパラレルワールドにダイブするような体験はたしかに面白かったが、北口バージョンのみを体験した時点ではやや物足りなさも感じた。カフェのテーブルや椅子を利用したダンスは日常的な空間に非日常感を持ち込む効果を上げてはいたものの、作品の主眼はダンスを見せることよりもむしろパラレルワールドを体験することに置かれているように思えたからだ。実際、当日パンフレットによれば、最初のアイディアは「大勢の人が行きかう賑やかな場所にVRブースを設置し、観客にヘッドセットを付けてもらって、そこが完全に無人になった状態を見せ」るというものだったらしい。この作品に果たしてダンスは必要か。だが、南口バージョンではダンスの存在が大きな効果を上げていた。
南口バージョンの会場はトランパル大塚。JR大塚駅と都電荒川線の線路に挟まれるようにしてある広場で、点在する植木を囲うようにベンチが設置されている。私が訪れた日曜の午後には多くの人のくつろぎの場となっていた。
北口バージョンと同じくVRセットを装着し「パラレルワールド」へと入っていく、のだが、南口バージョンほどのパラレルワールド感がないのは、そこにも駅前を行き来し、あるいは広場でくつろぐ人々の姿があるからだ。私が鑑賞した時刻やそのときの天候が映像内のそれと大きくは違っていなかったということもある。公共の場で踊るダンサーたちにチラリと目をやる通行人がいる一方、広場のベンチにはすぐ近くで踊っている人間にほとんど関心を示さないままに多くの老人が座っている。そういう周りの「感じ」も屋外でパフォーマンスが行なわれる際にはよくあるものだ。音楽によって環境音が聴覚から遮断されているという点以外は生で屋外パフォーマンスを鑑賞するのとさほど変わりがない印象を受けた。
だが、そろそろ作品も終わりだろうかという頃、何人かの老人がベンチから立ち上がり、あろうことかダンサーたちが踊っているあたりに近づきはじめる。ハプニングか(映像なのに?)とも思ったが、ベンチの老人たちはぞくぞくと立ち上がり、整然と並ぶとなんとラジオ体操をはじめたのだった。その隙間でなおも踊り続けるダンサーたち。もともと流れていた音楽に被さるようにラジオ体操の音楽が流れ、広場いっぱいに並んだ老人たちがラジオ体操をしている様子を映したまま映像はフェイドアウトしていった。
観賞後に改めて読んだ当日パンフレットによれば、老人たちは毎朝そこでラジオ体操をしていて、約20年前から広場の手入れもしているグループらしい。ダンスという非日常の時間に侵入してくる「現実」としてのラジオ体操。ロボットのようにギクシャクとベンチから立ち上がり、おもむろにラジオ体操をはじめる老人たち。ダンス作品を鑑賞しているつもりでいた私にとって、ベンチに座る老人たちの姿は背景に過ぎなかった。だからこそ、突然の老人たちの介入は私にとって非現実的な、秩序を逸脱するもののように感じられた。それこそがトランパル大塚の「現実」であるにもかかわらず。
現実には、都市には無数のレイヤーがあり、私はその一部を生きているに過ぎない。観光客向けの洒落たホテルと地元の人々の生活に根付いた広場とでは、そこから見える景色は大きく違っている。特定の場所に足を運び、しかしVRで鑑賞するという一見したところ捻れた形式が持つ意味はここにある。VRセットが映し出すのはその場にはない風景だが、その場にあっても私には見えていない風景があるのだ。
公式サイト:https://www.festival-tokyo.jp/20/program/fabien-prioville.html
星野リゾート OMO5東京大塚:https://www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/omobeb/omo/5tokyootsuka.html
2020/11/01(日)(山﨑健太)
犬飼勝哉『給付金』

会期:2020/10/24
犬飼勝哉の短編演劇『給付金』がSCOOL Live Streaming Seriesとしてライブ配信された。2019年9月に三鷹市芸術文化センター 星のホールで「MITAKA “Next” Selection 20th」参加作品として上演された『ノーマル』以来およそ1年ぶりとなる犬飼の新作はそのタイトルの通り給付金をめぐるやりとりからはじまる。
自転車、コート、旅行、猫、ルンバ。給付される十万円を何に使おうかと盛り上がるカナ(石渡愛)とユウト(矢野昌幸)。いかにも2020年の日本を反映した会話だが、それが「でもなんでカナたちってさ、十万もらえるんだろうね」「さあ。わかんない。政治家が決めたことでしょ」と着地するあたりから雲行きが怪しくなってくる。続く場面の「まずね、ニッポンって国があるのね」「あ、それ国の名前だったんだ」というユウトが見た夢に関するやりとりから判断するに、どうやらそこは「ニッポン」ではないらしい。
『木星のおおよその大きさ』(2018)、『ノーマル』(2019)と近年の犬飼は演劇を使って「普通」を相対化することを試みている。『木星のおおよその大きさ』には「観察者」たる宇宙人(?)が登場し地球人の生態を揶揄してみせ、『ノーマル』では無数の「普通」をめぐる会話が交わされた挙句に登場人物が観客席を見ながら「まあでもこれは架空の世界だからね」「現実世界ではそうは言ってらんないんじゃないの」と言って芝居が終わっていく。いずれも演劇という枠組みを通して自らの現実とは異なる「現実」を眺める観客の立場を強く意識させる趣向だ。複数のカメラによるライブ配信(とそのアーカイブ)という『給付金』の形式もまた(もしかしたらライブ配信であるにもかかわらず昼夜二公演分のアーカイブが残されていることも含めて)、「別の視点」=「別の現実」の存在を露わにする。
給付金で何を買おうかと夢が膨らむ二人だが、ユウトはカナに「電車のなかとかでさ、十万の話するのやめようよ」「俺らはさ、たまたまもらえる人だからいいけどさ、もらえない人が隣に立ってたり前に座ってたりして、十万の話聞いたら嫌な気分になるでしょ」と言う。やはりニッポンの話ではなかったのだと一瞬思いかけるが、給付金をもらえない人はもちろんニッポンにもいる。「こういう時にもらえない人の気持ちを考えないこと」が「幸せになるコツ」なのだから「他の人のことなんて考えなくていいんだよ」というカナの言葉も他人事ではない。「別の現実」を見ないことによって成立する「幸せ」はいまのニッポンを覆っている。
しかし結局、カナは他人のために自らの分の給付金を手放すことになる。カナとユウトは帰り道で夜空を横切る発光体を目撃し、その正体を探るべく向かった落下地点でユウトは異世界人(?)に憑依されてしまう。ユウトの口を借りて語る異世界人(?)曰く、カナたちに給付された十万は、本来は異世界人(?)の世界に振り込まれるもので、それが手違いでこちら側の世界に給付されてしまったため、彼らの世界は危機に瀕しているらしい。「あなたがたの十万を、私たちに譲っていただけないでしょうか」という異世界人(?)の申し出に最初は半信半疑のカナだったが、最終的に「いろいろ大変な世の中ですけど、私たちの十万で、なんとかその危機を乗り越えてください」と自らのキャッシュカードを差し出すのであった。
「他の人のことなんて考えなくていい」と言っていたカナが「別の現実」を認識しそこに手を差し伸べたように見えるこの結末が、しかしどこかしら不気味にも感じられるのは、異世界人(?)の荒唐無稽な話をカナがあまりにもあっさりと信じてしまうからだろう。その姿は陰謀論やフェイクニュースに踊らされる人々の姿を思わせる。あるいは、異世界人(?)がユウトの姿を借りていたからこそ、彼の話をカナは信じたのかもしれない。だとしたら、結局のところカナに見えているのはユウトとの二人の世界でしかない。給付金を独り占めするためにユウトがひと芝居打ったのだという可能性にも思い至らないカナの無邪気さ、そしてそれと表裏一体の残酷さは、現在の日本にとって「別の現実」と呼べるだろうか。
SCOOL Live Streaming Series 犬飼勝哉 短編演劇『給付金』2020年10月24日 15:00〜の回
公式サイト:https://inukai-katsuya.com/
犬飼勝哉『給付金』:http://scool.jp/event/20201024/
関連レビュー
犬飼勝哉『木星のおおよその大きさ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年07月01日号)
2020/10/24(土)(山﨑健太)
東京芸術祭2020 芸劇オータムセレクション『ダークマスターVR』

会期:2020/10/09~2020/10/18
東京芸術劇場シアターイースト[東京都]
私の欲望は本当に私のものだろうか。
『ダークマスターVR』はそのタイトルの通り、もともとは漫画『ダークマスター』(原作:狩撫麻礼、画:泉晴紀)を庭劇団ペニノ名義で舞台化し2003年に初演した作品を、さらにVRゴーグルを使って鑑賞するかたちに翻案したもの。ある定食屋を訪れた青年が、人付き合いが苦手だというその店のマスター(金子清文)から、自分の代わりに店に立って客の相手をしてくれないかと頼まれる。条件は月に50万の報酬と店に住み込むこと。引き受けた青年がイヤフォンを通して聞こえてくるマスターの指示通りに料理を出しているとやがて店は繁盛し始める。しかし上階にいるはずのマスターはあれきり姿を見せない──。
私が観た2016−17年版の『ダークマスター』では客席に置かれたイヤフォンを通じて観客も青年と同じようにマスターの声を聞くという趣向が用意されていた。今回の『ダークマスターVR』では、観客はマジックミラーのようなもので仕切られたブースへとひとりずつ案内され、そこでVRゴーグルを装着しフィクションの世界へと入っていく。VRゴーグルを装着した観客はひとまず主人公の青年と視点を共有しているようなのだが、観客自身の意思で視線をどこにでも向けられるVRゴーグルを通じての鑑賞では、青年が見ているものを観客もそのまま見ているとは限らない。実際、私がキョロキョロと店の内装を見回しているうちに、青年はマスターに出されたコロッケを食べ始めていた。自分のものではない身体に閉じ込められているような、そんな奇妙な乖離の感覚がそこにはあった。
この感覚は『ダークマスター』の物語とも呼応している。上階に閉じこもったきり出てこなくなってしまったマスターは、料理のみならずさまざまな欲求の解消を青年に「代行」させはじめる。トイレに行きたい。酒が飲みたい。女が抱きたい。青年は自らのものではないそれらの欲求に従い、観客は自らのものではない身体がそれらの欲求を解消する様子をその内側から眺める。このとき、観客は青年よりもむしろ青年に憑依したマスターと近い立ち位置にいるのかもしれない。バーチャルな身体を介して解消される欲求。
だがもちろん、その欲求は観客である私のものではない。だからこそ、他人の生々しい欲求をぶつけられたような不快感が残る。ヘッドフォンから聞こえてくるさまざまな音(咀嚼音、排泄音、性行為の音)がその生々しさと不快感を助長し、ときおり漂ってくる匂い(ステーキ、ナポリタン、化粧品)はバーチャルなはずの体験を観客自身の身体へと結びつける。マスターも、おそらくは青年も男性異性愛者であり、観客が男性異性愛者であった場合はそこで生じる違和感は相対的に小さいかもしれない。だがそうでない場合、自分では抱くはずのない欲求を解消するさまを「身体の内側」から見させられることになり、乖離はより一層大きなものとなる。
一方、この作品には男性異性愛者にこそショッキングなラストシーンも用意されている。店に呼び出したデリヘル嬢(日高ボブ美)との性行為の最中、一瞬だけ真っ暗になったかと思うと次の瞬間、目の前のデリヘル嬢の顔がマスターのそれへとすげ変わっているのだ。仮想現実の性行為に自らの欲望を重ね合わせていればいるほど、これには驚かされるのではないだろうか。そこにあるのが青年の欲望でもましてや観客の欲望でもなく、マスターの欲望だということを強烈に思い出させるラストシーンだ。
映像が終わると私は仕切られたブースの中に再び独りだ。だが、マジックミラーの向こう側にはほかの観客たちの姿が透けて見え、その姿は私にあまりに似ている。無数の部屋、無数の画面、無数の人。ステイホームしていてさえも、私は画面を通じて欲望を刺激され続けている。私の行動は私の欲望に基づくものだが、その欲望は果たしてどこまでが私のものか。私の欲望は他人のそれとあまりに似通ってはいまいか。劇場を出ると池袋の街には無数のネオンサインが瞬いている。それは私の欲望をコントロールしようとする誰かの欲望の光だ。
公式サイト:https://www.geigeki.jp/performance/theater249/
2020/10/13(火)(山﨑健太)
青年団若手自主企画vol.84 櫻内企画『マッチ売りの少女』

会期:2020/09/26~2020/10/04
アトリエ春風舎[東京都]
青年団若手自主企画vol.84として櫻内企画『マッチ売りの少女』が上演された。櫻内企画は青年団・お布団に所属し技術スタッフとして活動する櫻内憧海が「公演ごとに異なる演出家とタッグを組み、既成戯曲の上演を行う個人企画」。企画第一弾となる今回は1966年に早稲田小劇場の杮落としとして鈴木忠志の演出で初演された別役実『マッチ売りの少女』を橋本清の演出で上演した。
『マッチ売りの少女』は大晦日の晩、ある男(串尾一輝)とその妻(畠山峻)が夜のお茶をはじめようとしたところに女が訪ねてくるところからはじまる。市役所から来たという女(新田佑梨)の来訪の目的は判然としない。やがて女は自分はあなたたちの娘なのだと言い出すが、夫婦の娘は七つのときに電車にひかれて死んだはずである。さらに、女は外で待っている弟も呼んでいいかと問うが、そもそも夫婦に息子はいない──。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
女がマッチを売っていたのは20年前、彼女が七つの頃のことだという。この戯曲が初演された1966年から20年前と言えば戦後間もない頃だ。「男の声」によって回想されるその頃の情景も戦後の日本のそれと重なる。女はマッチを売るだけでなく、お客相手に「マッチを一本すって、それが消えるまでの間」「その貧しいスカートを持ちあげてみせ」るようなこともしていたらしい。「ささやかな罪におののく人々、ささやかな罪をも犯し切れない人々、それらのふるえる指が、毎夜毎夜マッチをすった」と男の声は語るが、その罪はもちろん「ささやか」などではない。自分たちを「この上なく善良な、しかも模範的な市民」だと言う男は「あの頃のことは忘れることです。みんな忘れちまったのです。私も忘れちまいました」などと言う。しかし終幕に至って女が発する「許して、お父様。許して下さい。マッチを、マッチをすらないで……」という言葉は、男もまた加害者であることを強く示唆している。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
過去から蘇る、闇に葬り去ったはずの罪。戦後の日本はさまざまな犠牲のうえに存在している。それはいまも変わっていない。だが、戦争を経験した世代が亡くなっていくにつれ忘却は加速し、自分にとって都合のいい過去だけを信じる者はますます増えている。だからこそ、この戯曲は(残念ながら)いまなおアクチュアルなものとしてある。
橋本は妻役に男性俳優を配し、弟役を声のみの出演とすることで、この戯曲の現代性をより鋭く浮かび上がらせてみせた。舞台上にあるのは現在と過去との対立であると同時に上の世代から下の世代への加害、下の世代から上の世代への糾弾でもあり、それはつまり現在と未来の対立でもある。そして上の世代、いや、「現在」は過去の加害にもかかわらず未だに男性中心主義に支配されている。上の世代を象徴する夫婦がともに男性俳優によって演じられているのはそれゆえだろう。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
声だけの存在である弟の立場はさらに弱い。生まれてさえいないはずの弟は、かつて男に暴行されていたのだと体に残るアザを見せる。しかしもちろん、そのアザを観客が視認することはできない。夫婦の反応からは弟の言葉は根拠のないデタラメなものであるような印象も受ける(それは実体のないフェイクニュースのようでもある)。だが、忘れてしまった罪と異なり、認識さえしていない罪を思い出すことはほとんど不可能だ。
女には四つと二つの二人の子供がいる。舞台には登場しない彼らの存在は、女の話と、「市の防災班」の男の「寝息が聞こえます。小さいのが二つ」という言葉によってのみ示される。この作品は、もっとも若い、その言葉さえも聞くことのできない子供たちの寝息が聞こえなくところで終わる。新年の朝に潰える命。過去の罪を認めまいと足掻く大人たちの傍らで、いくつもの未来の可能性がひっそりと閉じられている。その罪もまた、多くは認識されないのだろう。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
公式サイト:http://www.komaba-agora.com/play/10592
2020/10/03(土)(山﨑健太)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)