artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
カタログ&ブックス | 2024年1月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。
◆
HAND BOOK──大原大次郎 Works & Process

著者:大原大次郎
発行:グラフィック社
発行日:2023年12月8日
サイズ:A5変形判、464ページ
手書き文字をはじめとするアナログで身体的な手法を駆使し、音楽、装丁、広告、ロゴの分野で活躍する大原大次郎。現代のデザインシーンに大きな影響を与えてきたその仕事を、プロセスや考え方とともに紹介する。
自炊者になるための26週

著者:三浦哲哉
発行:朝日出版社
発行日:2023年12月9日
サイズ:四六判、336ページ
“面倒”をこえて「料理したくなる」には、どうしたらいいでしょう。“ほぼ毎日キッチンに立つ”映画研究者が、その手立てを具体的に語ります。
ラブレターの書き方

著者:布施琳太郎
発行:晶文社
発行日:2023年12月19日
サイズ:四六判、344ページ
つながりすぎた社会で
〈二人であることの孤独〉を取り戻す
若きアーティストによる
SNS時代の恋愛・制作・人生論
関係性の美学

著者:ニコラ・ブリオー
翻訳:辻憲行
発行:水声社
発行日:2023年12月25日
サイズ:四六判、256ページ
参加、出会い、待ち合わせ、はては労働行為や商取引までをも形式化する捉えどころのない作品たちは、いかにして誕生したのか。芸術理論の空白のただなかで、全面的な商品化へ向かいつつある現在のアートを読み解くための必携書!
作家主義以後──映画批評を再定義する

著者:須藤健太郎
発行:フィルムアート社
発行日:2023年12月26日
サイズ:四六判、448ページ
ひとつの映画作品を問うことにおいて、映画そのものの存立を問う、その終わりなき営みとしての「映画批評」の可能性。『評伝ジャン・ユスターシュ』の俊英による、実験゠実践の記録。
アートと人類学の共創──空き家・もの・こと・記憶

編著:服部志帆+小野環+横谷奈歩
発行:水声社
発行日:2024年1月5日
サイズ:A5判、312ページ+カラー別丁64ページ
一軒の空き家に残された「もの」から、いかにして人びとの生を描き出し、歴史を語り継ぐことができるのか。人類学者とアーティストは、それぞれの立場からこの問いに向き合い、「もの」たちの声に耳をすます。写真、家具から柱、果てはつもった埃に至るまで、空き家をくまなく探索することで浮かび上がったのは、ひとつの空き家を軸にした、ある家族の生きざまと塩江町の人びとの繋がりだった。今はなき人びとの記憶を継承するために、アートと人類学に何ができるのか。分野の壁を超えた挑戦的なプロジェクトの軌跡。
情報哲学入門(講談社選書メチエ)
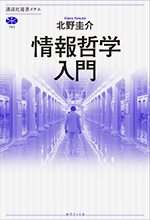
著者:北野圭介
発行:講談社
発行日:2024年1月15日
サイズ:13×18.8cm、266ページ
私たちは「情報」なしで暮らすことはできません。スマホでニュースを確認する、メールやラインをチェックする。改札を電子マネーの端末で通り抜け、車内では画面に映る広告や駅名を見る。そして会社に着けば……といったように、あらゆる場所に、無数の形で情報はあふれています。本書は、こうした現状の中で「情報という問い」に正面から取り組みます。カーツワイル、ボストロム、テグマークを通して技術との関係の中で「人間」とは何かを確認し、マカフィーとブリニョルフソン、ズボフを通して社会の中での情報がもつ機能を捉え、フクヤマ、ハラリ、サンデルを通して政治との関わりを考察します。その上で改めて「情報」というものを哲学的に規定し、情報をめぐる課題を整理します。
2024/01/15(月)(artscape編集部)
清水裕貴『岸』
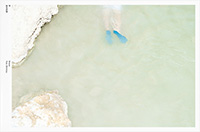
発行所:赤々舎
発行日:2023/12/08
2022年度の木村伊兵衛写真賞の最終候補に選出されるなど、注目度が上がっている清水裕貴。2011年に写真「1_WALL」展でグランプリ受賞後、コンスタントに個展を開催し、小説家としても作品を発表するなど、多面的な活動を展開してきた。本作はその彼女の最初の本格的な写真作品集である。
水/岸辺を基調テーマとする写真が連なり、その合間にポエティックな文章が挟み込まれる。あるイメージを受け止め、次のイメージを引き出していく、その流れに独特のリズムがあり、写真による「文体」がかたちをとり始めている。文章を綴る能力にも磨きがかかり、写真とことばの精妙なバランスの取り方も、とてもうまくいっているように思えた。
ただ、「この人は結局何を言いたいのだ」という肝心要のメッセージがうまく掴み取れない。淡々と進んでいく写真の流れが、大きく転調する箇所(例えば、26枚目の奇妙な人形、82枚目の兎)がいくつかあるのだが、そこに必然性が読みとれないのだ。文章のほうも、途中で「魚」になってしまう「あなた」が、「わたし」とどんな関係にあり、どのように作品世界に位置づけられるのか、その輪郭が曖昧模糊としていてリアリティが感じられない。写真と文章とを一対一で対応させる必要はないが、もう少し丁寧にフォローしていくべきではないだろうか。文章の量がやや少なすぎたのではないかとも思う。
写真とことばの両者を高度なレベルで使いこなし、新たな領域を切り拓いていく作り手としての清水裕貴への期待は大きい。見る者(読み手)を震撼させる作品に出会いたいものだ。
清水裕貴『岸』:http://www.akaaka.com/publishing/YukiShimizu-shore.html
2024/01/04(木)(飯沢耕太郎)
カタログ&ブックス | 2023年12月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。
◆
闇の精神史

著者:木澤佐登志
発行:早川書房
発行日:2023年10月17日
サイズ:新書判、310ページ
19世紀末ロシア、独立直後のジャマイカ、サイバー空間――様々な時と場所に現れた、「宇宙」をめぐる思想。分子となって銀河に散らばる全祖先の復活を唱える者、自らのルーツを土星に見出し異形の音楽を創り出す者……。果てなき頭上の漆黒に、人は何を見るのか?
ギリシアへの旅──建築と美術と文学と

著者:マリオ・プラーツ
責任編集:金山弘昌
翻訳:伊藤博明、金山弘昌、新保淳乃
発行:ありな書房
発行日:2023年10月23日
サイズ:A5判、168ページ
永遠の都ローマを知り尽くした碩学が、西欧文芸のアルカディア的幻想に誘われて、ギリシアを旅し、白い大理石の半神たちのイメージに秘められた、時空を超えた深い歴史的意味と栄枯盛衰への哀悼と芸術的精華を語る、珠玉のエッセイ集!
クリエイティブデモクラシー──「わたし」から社会を変える、ソーシャルイノベーションのはじめかた

著者:一般社団法人 公共とデザイン(石塚理華、川地真史、富樫重太)
発行:BNN新社
発行日:2023年10月25日
サイズ:A5判、320ページ
本書は、行政でのイノベーションラボ立ち上げや、地方自治体・企業・住民とともに社会課題に向けた共創に取り組む「一般社団法人 公共とデザイン」が案内する、自分の足元から社会変革への第一歩を踏み出すための思考と実践の手引きです。
瀬戸内国際芸術祭と地域創生──現代アートと交流がひらく未来

著者:狹間惠三子
発行:学芸出版社
発行日:2023年11月15日
サイズ:四六判、256ページ
毎回100万人前後が離島などの会場に来場し100億円規模の経済波及効果をあげる芸術祭。だが、それだけではない。地域資源の再発見、誇りの醸成を促し、交流と活動の連鎖から、小商いや移住・定住の増加など、地域の変化が起きている。その企画・運営、とりわけ行政と民間・住民の関わり方を読みとき成功の秘訣を示す
戦後フランスの前衛たち──言葉とイメージの実験史

編集:進藤久乃
発行:水声社
発行日:2023年11月24日
サイズ:A5判、368ページ
大戦後の芸術運動(コブラ、レトリスム、シチュアシオニスト)を俯瞰する第一部、前衛周辺の作家たち(ポーラン、ポンジュ、パタフィジック、ベケット)を論じる第二部、詩に革新をもたらした音声詩、視覚詩の展開を見据える第三部を通して、戦後フランスの前衛運動の見取図を描き出す。
移動縁が変える地域社会──関係人口を超えて

編著:敷田麻実、森重昌之、影山裕樹
発行:水曜社
発行日:2023年12月7日
サイズ:A5判、224ページ
「よそ者」と呼ばれた移動者も、今や地方の衰退が進むなか、期待をもって地域の人々に迎え入れられるようになった。本書は、都市や農村など既成の枠組みを超え、多様な移動者によってつくられる社会のあり方を各地の事例とフィールドワークを元に分析。移動者と地域社会との新しい関係性をまちづくりに生かす最新刊。
ポップ・カルチャー批評の理論──現代思想とカルチュラル・スタディーズ
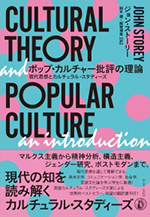
著者:ジョン・ストーリー
訳者:鈴木健、越智博美
発行:小鳥遊書房
発行日:2023年12月15日
サイズ:A5判、510ページ
マルクス主義から精神分析、構造主義、ジェンダー研究、ポストモダンまで、現代思想を通して理解できる。英米文学、コミュニケーション学、社会学、言語文化論を学ぶ学生に最適! 英国カルチュラル・スタディーズ大家による世界的ベストセラー、待望の翻訳書刊行!
2023/12/15(金)(artscape編集部)
カール・ジンマー『「生きている」とはどういうことか──生命の境界領域に挑む科学者たち』

翻訳:斉藤隆央
発行所:白揚社
発行日:2023/07/12
生命をめぐる学問の歴史は古い。とりわけ自然科学が大きく発展したこの数世紀のあいだ、生命の起源や発生をめぐる問題は、科学者たちの大きな関心事でありつづけてきた。本書は、そんな科学者たちの苦闘を、精力的な取材と魅力的な筆致によって描き出した労作である。著者カール・ジンマー(1966-)は、進化や寄生といったトピックを得意とする高名なサイエンスライターであり、本書でもその手腕は遺憾なく発揮されている。
本書には、さまざまな方法で生命にアプローチする古今の科学者たちが登場する。そのなかには、チャールズ・ダーウィン、トマス・ハクスリー、エルンスト・ヘッケルといった誰もが知る人々に加えて、かつて生命の謎を明らかにしたという名誉に浴しながら、今では歴史の闇に埋もれてしまった科学者たちも含まれる。例えば、本書のはじめに登場する物理学者ジョン・バトラー・バークは、20世紀はじめに生命を生み出す元素を発見したと公表し、一時は英国でもっとも知られる科学者となった。その論文は『ネイチャー』にも発表され大きな話題をよんだが、バークが発見したと称する「レディオーブ」なる元素が存在しないとわかると、その後の人生は転落の一途をたどった。著者によれば、晩年にバークが著した「怪しげな大著」(17頁)である『生命の発生』(1931)には、ほとんど悲痛にも感じられる次のような定義が見られるという──「生命とは生きているものだ」(18頁、傍点省略)。
本書が類書とくらべて際立っていると思われるポイントのひとつは、生命とそうでないものを隔てる基準が、しばしばそれが要請される社会的場面に応じて決定されることを抜かりなく指摘していることだろう。本書第1部「胎動」において、脳死や中絶をめぐる論争が取り上げられることの意義はそこにある。こうしたケースは、「生命とは何か」という問いが、かならずしもその起源や発生を問うこととイコールではないことを明瞭に伝えてくれる。
加えて、本書では歴史にたずねるだけでなく、生命をめぐる同時代の研究成果を紹介することも怠っていない。本書に登場する「生命」のかたちは、ヒト、ヘビ、コウモリ、さらには粘菌、ヒドラ、クマムシにいたるまで、きわめて多岐にわたる。本書は最終的に、生命の定義可能性をめぐる哲学的な議論によって締めくくられる(とりわけ、物理学者から哲学者に転じたキャロル・クリーランドの議論は示唆に富む)。だが、そのパートが説得的に見えるとしたら、数学から宇宙生物学にいたるさまざまな分野の研究者に取材した、それまでの長い道のりがあるからだろう。全体にわたり読者を飽きさせない工夫に満ちた本書は、「生命とは何か」という広大な問いをあくまで具体的な事象に即して考えるにあたり、豊かな材料を提供してくれる。
2023/12/11(月)(星野太)
フランソワーズ・ダステュール『死──有限性についての試論』

翻訳:平野徹
発行所:人文書院
発行日:2023/10/30
哲学にとって「死」は最大のテーマのひとつである。というのも、あらゆる人間に等しく訪れるものでありながら、けっして一人称的には経験しえないただひとつのものが、自分の死であるからだ。死を経験するとき、そこにおのれの意識はすでにない。わたしたちが死について知っているすべてのことは、ほかの人間、ほかの生物を通じて得られた二次的なものでしかない。このような対象を前にして、哲学が語りうることは何だろうか。宗教的な語りとも、生物学的な語りとも異なる、いかなる語りがそこでは可能だろうか。
むろん、古来より死についてはさまざまなことが書かれてきた。そうした過去の言説もふまえながら、この問題に正面から取り組んだのが本書『死──有限性についての試論』である。著者フランソワーズ・ダステュールは1942年生まれのフランスの哲学者であり、独仏の現象学をおもな専門としている。まず強調しておきたいのだが、彼女にとって死をめぐる省察はけっして余技に属するものではない。ダステュールの著作一覧には、本書のほかに死をテーマとする専門書が数冊、および子どもを対象とする、同じテーマについての平易な入門書がある(邦訳『死ってなんだろう。死はすべての終わりなの?』伏見操訳、岩崎書店、2016)。ここからわかるのは、ハイデガー、フッサール、メルロ゠ポンティらについて数多くの書物を著してきたこの哲学者にとって、死が一貫して問われるべきテーマでありつづけてきたということだ。
あらかじめ注意をうながしておくと、本書は死をめぐる包括的な哲学史ではない。ダステュールがこのテーマに取り組むにあたってもっとも頻繁に依拠するのが、著者が一番の専門とするマルティン・ハイデガーである。より積極的に言えば、死をめぐる本書の立場は、ハイデガーの思想を展開するかたちで練り上げられたものだと言ってよい。その核心をもっとも端的な言葉で言い表わすなら、おおよそ次のようになる──すなわち、死という乗り越え不可能な出来事に臨むことでのみ、われわれの生の可能性は開かれるのだ、と。
このような考えには、実のところ、まったく意外性はないだろう。あらゆる人間が、ただひとりの例外もなく固有の生をもつのは、われわれがみな死すべき存在であるからだ。人間は、理念としての永遠性や不変性とは無縁な存在であるからこそ、逆説的におのれの生を唯一無二のものとすることができる。ハイデガーこそは、こうした「死すべき存在」としての人間に、もっとも積極的な意味を与えた哲学者にほかならなかった。
ダステュールにおいても、死はけっして否定的なものとはみなされていない。むしろ、死はわれわれが世界へと開かれることを可能にする、唯一無二の地平である。とはいえ、こうした結論だけならば、前掲の子どもむけの本を読んでもそう変わりはないことになる。むしろ本書の読みどころは、そうしたありきたりの結論ではなく、その過程で示される著者の繊細な筆運びにあると言ってよい。例えば、通常「死にむかう存在(être pour la mort)」と訳されるハイデガーのSein zum Todeは、「死にかかわる存在(être relatif à la mort)」とすべきだと著者はいう(151頁、註25)。なぜなら、人間を前者のように──死に「むかう」存在として──捉えることは、死が悪しきものであるという一面的な見かたを暗黙のうちに前提してしまうからだ。こうしたケースに見られるように、本書は、古今のさまざまなテクストを誠実に読みなおすことで、死をめぐるわれわれの思索をより深いところにいざなってくれる。
なお、昨今では死をめぐる思索が「後景に退いている」(9頁)という指摘に、評者もまた同意するものである。もちろん、死が人間にとって縁遠いものになったわけではまったくない。だがその一方、「終活」にまつわるさまざまなビジネスの存在が雄弁に物語るように、われわれの社会生活においては、個々の実存的な死もまたすでに産業的なサイクルのなかに取り込まれている。そのような現代にあって、死が「忘却のなかに落ちこんでいる」(284頁)という著者の実感は広く共有されているにちがいない。全体を通じてきわめて専門的な議論からなる本書が、現代の生のありようをめぐる身近な問題意識に支えられていることは、やはり特筆しておきたい。
2023/12/11(月)(星野太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)