artscapeレビュー
村田真のレビュー/プレビュー
李晶玉展「SIMULATED WINDOW」
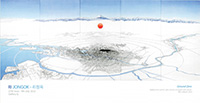
会期:2022/06/27~2022/07/09
ギャラリーQ[東京都]
この春、原爆の図丸木美術館で作品を発表したばかりの李による同題の個展。ギャラリーからいただいた丸木美術館のカタログを見ると、どうやら同じ作品が出ているようだ。丸木美術館は足の便が悪くなかなか行きづらいので、見逃した者にとってはありがたい★。
まず目に入るのが、180×450センチの大作《Ground Zero》。東京のパノラマ俯瞰図の上に赤い球体が浮き、その上(奥)に富士山が遠景として描かれている。球体の下には同心円が幾重にも広がり、赤球が核爆発であることを示唆する。つまりこれは東京上空で核爆発が起きる瞬間を描いたもの。赤球の下(グランド・ゼロ)には黒く塗り潰された領域があるが、これは皇居か。なるほど、グランドゼロとはあらゆる情報が発信されないブラックホールというわけだ。だがよく見ると、赤球の真下は皇居ではなく、やや南西方向にずれている。かつて参謀本部があった三宅坂あたりであり、近くには国会議事堂を有する日本の中枢部がグランド・ゼロに想定されているのだ。赤球の背景は白く抜かれているので日の丸に見え、その真上に富士山がそびえるというまるで日本な構図。ちなみにこの作品は、紙に鉛筆で描いた原画を2倍に拡大したデジタルプリントに着彩したもの。
ほかに《Enora Gay》と《Dome》という対作品もある。前者は広島に「リトルボーイ」を投下したB-29のコックピットを描いたもので、後者は広島の原爆ドームを内部から見上げたところ。どちらも鉄骨に覆われた半球状の形態をしているが、一方は落とした側(加害)、もう一方は落とされた側(被害)という真逆の視点から捉えているのだ。この両者が「重なったように見えた時に視点を得たような感覚があった」と作者は述べている。こうしたある意味恐るべき視点の発見を、緻密でクールな描写によって表わしているところが気持ちいい。
★──原爆の図丸木美術館「李晶玉 SIMULATED WINDOW」動画公開 https://marukigallery.jp/news/rijongok_movie/
2022/07/08(金)(村田真)
記者発表会「岡本太郎、新発見!」
渋谷ヒカリエ 8/COURT[東京都]
「このたび、従来の岡本太郎史を塗りかえる可能性が高い重要な発見がありました。つきましては、その詳細について、新たに発見された作品を会場でお見せして ご説明する記者発表会を開催いたします」とのメールが届いた。「岡本太郎史を塗りかえる」「重要な発見」というから、東京美術学校の入試デッサンか、戦時中に描かされた戦争画でも見つかったのか? いやいや、どうせ1カ月後に迫った「展覧会 岡本太郎」の煽り、大した作品じゃないんじゃないかなどと思いつつ、会場へ。
まず、岡本太郎記念館館長で同展のスーパーバイザーを務める平野暁臣氏が概要を説明。発見されたのは3点で、いずれもパリ時代(1930-40)に描かれた初期の抽象画。太郎のパリ時代の作品は帰国時に持ち帰ったが、すべて戦災で焼失したため、現在残っている《空間》《傷ましき腕》など数点はいずれも戦後に再制作されたもの。1934年制作とされるオリジナルの《空間》以前の3、4年間の作品は現物はおろか印刷物でも確認されておらず、空白の期間となっていた。今回見つかったのは、岡本太郎芸術の原点ともいうべきその時代に描かれたとおぼしき最初期の抽象画なのだ。この発見は、岡本太郎独特のスタイルがいかに確立されたか、パリの一青年がいかに芸術家になったかを解き明かしてくれるミッシングリンクといってもいい。
3作品の発見の経緯はこうだ。1993年、パリのシテ・デ・フュザンというアトリエ村のゴミ集積場に捨てられていた1点をデザイナーが拾い、翌年そのデザイナーが同じアトリエから出た2点をオークションで落札。そのうちの1点に「岡本太郎」の署名を見つけ、戦前に出たカタログも参照して3点とも岡本作品と確信したという。今回、展覧会開催を契機に3作品を日本に持ち込んで鑑定を行ない、ほぼ岡本太郎の作品に間違いないという結論に達した。
てなわけで、いよいよカーテンの裏に隠された3作品をご開帳。

記者発表会の様子。右から、吉村絵美留、平野暁臣、山下裕二の各氏[筆者撮影]
現われた作品は、いずれもモノクロームの背景にどこか《空間》(1934/54)を思わせる有機的形態が浮かび上がる構成だが、なんとも無骨でお世辞にもうまいとはいえない。「岡本太郎史を塗りかえる」「重要な発見」というにはいささか頼りないが、しかし見方を変えると、《空間》以前の暗中模索期の習作ということであれば納得できるし、岡本が日本に持ち帰らなかった理由もうなずける。つまり半端であるがゆえに真実味も高いのだ。
平野氏はこれらが岡本作品である可能性は95パーセントとしたが、続いて登壇した美術史家の山下裕二氏は99パーセント、絵画修復家の吉村絵美留氏は100パーセント近いと証言。絶対100パーセントとは断言できないものの、ほぼ間違いなく岡本作品であるということだ。だいたい日本ならともかく、フランスで贋作がつくられるほど岡本太郎は有名じゃないし。平野氏は、逆に贋作だとしたらものすごく手の込んだ詐欺で、拍手したいくらいだと述べていた。現物を見て確かめたいという人は、大阪中之島美術館(7/23-10/2)、東京都美術館(10/18-12/28)、愛知県美術館(2023/1/14-3/14)の「展覧会 岡本太郎」へ。
2022/07/08(金)(村田真)
元田久治 CARS

会期:2022/06/24~2022/07/17
アートフロントギャラリー[東京都]
東京駅や国会議事堂、あるいはパリのエッフェル塔やシドニーのオペラハウスなど、見慣れた風景が数十年後にはこうなっているかもしれないという未来の廃墟図で知られる元田の新作は、なぜか自動車がモチーフ。しかもミニカーを描いているのだ。
《CARS:Pedestrian Crossing》(2022)では、幅5メートル近い大画面に本物の道路から転写したかのような横断歩道が原寸大で描かれ、その上を数百いや千台はあろうかというミニカーがびっしりと覆っている。一瞬ガリバーの世界に迷い込んだような違和感を覚えるが、ミニカーも原寸大なのでこれはリアル世界なのだ。ミニカーはリトグラフでいっぺんに何十台も刷り、1台1台切り抜いて貼り付けているという。地面にうごめく無数の虫のような凝集感があるが、神の視点から見下ろせば現代の車社会はこのように映るのかもしれない。
おもしろいのは、ミニカーの廃車を描いた版画もあること。それも2種類あって、使い込まれてボロボロになったミニカーをそのまま描いたものと、ミニカーのオリジナル車が廃車になった姿を想像して描いたものと。しかもその下にモデルにした実物のミニカーも置いてある。これまでのリアル世界と想像世界だけでなく、絵画と版画、ミクロとマクロ、オリジナルとコピーのあいだも往還し始めたようだ。
2022/07/03(日)(村田真)
ゲルハルト・リヒター展

会期:2022/06/07~2022/10/02
東京国立近代美術館[東京都]
サブタイトルもなにもない「ゲルハルト・リヒター展」。それ以上でも以下でもない、ただリヒターの作品だけを見せる展覧会。潔いなあ。
出品作品は計138点で、うち油彩のタブローは42点。それ以外は、色見本をランダムに並べたような「カラーチャート」、プリント上に油絵具を塗った「オイル・オン・フォト」、ドローイング、ガラスおよび鏡による作品など多彩だ。また、タブローの半分以上は「アブストラクト・ペインティング」シリーズで、それ以外は写真を描き写した「フォト・ペインティング」、グレイ一色に塗られた「グレイ・ペインティング」など。なぜ内訳を書いたかといえば、どうも足りないものがあるように思えてならないからだ。年代別に見ると、8割以上は21世紀以降の作品に占められ、特に1960-80年代の作品はわずか10点しかない。圧倒的に足りないのは初期から中期にかけての作品群だ。
ぼくが初めてリヒターの作品を実見したのは1982年のドクメンタ7においてだったと思うが、そのとき訪れたいくつかの美術館でも見た記憶がある。刷り込みというのは侮れないもので、ぼくはこの時期のリヒター作品がその後の作品の評価基準になっている。当時リヒターはすでに「アブストラクト・ペインティング」を始めていた(同時に「フォト・ペインティング」も続けていた)が、近年のスキージによる制作とは違い、太い刷毛でストロークを生かして絵具を塗り重ねていく手法で、スキージの使用は限定的だった。
また、アブストラクトにもかかわらず筆跡に立体感があり、画面に奥行きがあるのは、絵具がたっぷり盛り上がった筆跡を拡大模写した70年代の「ディテール」から発展させたものだからであり、その「ディテール」は筆跡を写真に撮ってそのまま写し取るという意味で、60年代の「フォト・ペインティング」とつながっていた。つまり「フォト・ペインティング」と「アブストラクト・ペインティング」を繋ぐのが「ディテール」であり、また初期の「アブストラクト・ペインティング」なのだ。そのためリヒターは具象と抽象の概念を無効化した画家として評価される一方、作品にはどこかトリッキーな匂いが感じられたのも事実だ。いずれにせよ、今回の展示で足りないと感じるのは、「フォト・ペインティング」と「アブストラクト・ペインティング」をつなぐ、平たくいえば具象と抽象をつなぐ「ディテール」であり、初期の「アブストラクト・ペインティング」なのだ。これが欠けているため今回の出品作品はリアリズムとアブストラクトに分かれてしまい、その境界を曖昧にしたリヒターの業績が見えにくくなっていると思う。
この時代の作品が欠けているのは、今回の展覧会がゲルハルト・リヒター財団のコレクションによって構成されているからだ。財団が設立されたのは2019年と最近のことなので、過去に遡れば遡るほど作品が集めにくかったはず。カタログでも「1990年代まで、リヒターが作品を売らずにアトリエに留め置くことはあまりなかった。ようやく2000年代になって、将来に創設されるかもしれない財団を視野に入れながら、作品を取り除けておくようになった」と、ディートマー・エルガーが書いている。言い換えれば、70-80年代の作品はよく売れたということでもある。富山県美術館の《オランジェリー》(1982)1点でもあればずいぶん違っただろうに。
2022/06/29(水)(村田真)
地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング

会期:2022/06/29~2022/11/06
森美術館[東京都]
「地球の曲/地球がまわる音を聴く。/1963年春」
展覧会の冒頭に掲げられたのは、同展のタイトルにも使われたオノ・ヨーコのインストラクション集『グレープフルーツ』からの言葉だ。さらに、
「鼓動の曲/心臓の鼓動を聞く。/1963年秋」
と続く(原作はどちらも英語で表記されている)。世界に耳を澄ませ、自分に耳を澄ます。このふたつの行為が同展の方向性を指し示しているように思える。2020年に始まった新型コロナウイルスの世界的流行(パンデミック)により、いきなり世界が別のステージに移り、これまでとは違う時間が流れ始めたかのような錯覚を覚えた人も多いだろう。この2年半、自分はどのように生きていけばいいのか、世界に対して自分はなにができるのか、これまであまり考える必要のなかった問いに向き合わざるをえなくなった。この展覧会はそんな問いになにかヒントを与えてくれるかもしれない。とはいえ、16人の出品作家は国も違えば、考え方も使うメディアも表現スタイルも異なり、多様としかいえない。むしろ多様であることがひとつの答えであるといってもいい。
そんななかで目が釘付けになったのが、エレン・アルトフェストの作品。身の回りの風景や静物を緻密に描写したいわゆる写実絵画なのだが、手っ取り早く写真を用いることはせず、長時間を費やして実物を観察し、木の幹の凸凹した表面やカボチャの複雑な色合いや肌触りまで克明に再現していく。たとえば《木々》(2022)と題された絵画は、A4サイズ程度の小品にもかかわらず1年以上かけて制作したという。そこには写真からただ転写したようなインスタント絵画にはない濃密な時間が蓄積されている。それはすべての時間がスローダウンしたパンデミックゆえに可能だったに違いない。
もう1点、金沢寿美の《新聞紙のドローイング》(2021)も瞠目に値する。日々の新聞をひたすら濃い鉛筆で塗りつぶし、目に止まった文字や画像だけ残す。それを数百枚つなげて高さ5メートル、幅20メートル以上のカーテン状にして吊るしてみると、ところどころ星々が輝く漆黒の宇宙に見える。このシリーズを始めたのは2008年だが、本格的に取り組むようになったのは、社会との断絶を感じ始めた出産後の2017年からで、このコロナ禍によりますます加速したようだ。彼女は新聞を読むのではなく、塗りつぶすことによって世界とつながり、宇宙に開かれたといえるだろう。
美術館がこういう現在進行形の出来事に絡めてテーマを設定するのは難しいし、とても勇気がいることだ。ともすれば時流におもねっているとか災厄を利用しているとかいわれかねないし、ようやく実現したと思ったらすでに時代遅れになっていたというほど世の中の動きが早いからだ。実際、同展を企画したのは2020年以降のはずだが、今年に入ってからロシアがウクライナに侵攻し、安倍元首相が暗殺されるなど激震が続き、第7波がきているにもかかわらずもはやコロナへの関心は薄れきっている(というより、みんなうんざりしている)ように見える。身も蓋もないことをいえば、どんなテーマの展覧会だろうが、テーマに関係なく人を感動させる作品は変わらないということだ。
2022/06/28(火)(村田真)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)