artscapeレビュー
山﨑健太のレビュー/プレビュー
果てとチーク『グーグス・ダーダ』
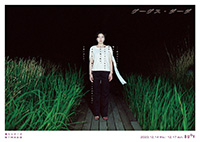
会期:2023/12/14~2023/12/17
BUoY[東京都]
流れる血が見えなければ、そこにある痛みもないことにできるのだろうか。果てとチーク『グーグス・ダーダ』(作・演出:升味加耀)の冒頭で交わされる会話は、隕石の影響で透明になってしまったというソトの人間の血の色についてのものだ。ナカとソトの境界で警備にあたっているイダ(神山慎太郎)とエダモト(横手慎太郎)の衣服がところどころ濡れて見えるのは、「清掃」でその血を浴びたかららしい。だが、イダはその臭いに軽い嫌悪感こそ示すものの、それ以上は気にすることもなくそのまま長々と雑談に興じる。そんなイダは冒頭の問いに対してイエスと答えているも同然だ。しかし、観客の関心もまた、見えない血から雑談の内容へとすぐさま移っていくだろう。少なくとも私はそうだった。見えない血を気にし続けることは難しい。
 [撮影:木村恵美子]
[撮影:木村恵美子]
『グーグス・ダーダ』の世界は分厚く高い二重の壁とその間に広がる砂漠によってナカとソトに分断されている。かつて落ちた隕石によってソトの土壌とそこに住む人間が「汚染」されてしまったというのがその理由らしい。ソトの人間はナカの人間によってランク付けされ、居住地域を指定されるなどの管理を受けている。その一端を担い「清掃」にも携わる仮国境警備隊のイダとエダモトは、一方でソトの住人である「彼」(松森モヘー)が壁の周辺をうろつくことは「できるだけのことはしてあげよ」と黙認している。「彼」は砂漠を越えようとする人たちのために水を置いて回りながら、そこを通る人々が遺していった「忘れ物」を回収しているようだ。「彼」と暮らす「彼女」(雪深山福子)はもともとはナカの住人なのだが、そのことを隠して塾の講師として働いている。その教え子のスー(中島有紀乃)は幼馴染のミカド(上野哲太郎)がテロ組織に関わろうとしているのではないかと疑うのだが──。
 [撮影:木村恵美子]
[撮影:木村恵美子]
 [撮影:木村恵美子]
[撮影:木村恵美子]
一方、ナカの人々。エダモトの妹・ユキ(小嶋直子)はソトから養子を迎え育てている。しかし、その養子であるヲトメ(若武佑華)はエダモトのところに入り浸り、どうやらソトへの思いを募らせているらしい。ヲトメの友人・ユー(渚まな美)はソトからの移民2世で、両親はソトの子供をナカの人々へと斡旋する仕事をしている。ヲトメの養子縁組もユーの両親の仲介で実現したものだ。ユキの従兄弟でありイダの妹でもあるカヤ(川村瑞樹)は兄夫婦の不妊治療に端を発するトラブルに巻き込まれつつ、友人である「彼女」のソトでの暮らしを案じている。
やがてナカへのオリンピックの誘致が決まると状況は急激に悪化しはじめ、なんとかやってきたそれぞれの暮らしも綻んでいく。ソトからの移民は排斥され、抵抗するものは容赦なく排除されていく。ユーの両親はデモで捕まり、ヲトメもまたユキとともに暮らすことはもはやできない。テロが頻発し、ミカドと「彼」は帰らぬ人となる。かけがえのないはずの命はいくらでも代わりがあるものとして扱われていく。そして拡散する陰謀論、あるいは真実。陰謀論と歴史の改竄は見分けがたく、描かれる物語はあまりに現実に近しい。
 [撮影:木村恵美子]
[撮影:木村恵美子]
 [撮影:木村恵美子]
[撮影:木村恵美子]
タイトルはドイツ語で「いないいないばあ」を意味する言葉だ。見えないことにし続けたものは、いつか歪なかたちでその姿を現わすことになるだろう。だが一方で、この物語世界においては、血さえ流れなければナカとソトの人間の区別はつかないという点も忘れてはならない。このことは、分断が暴力を生み出しているのではなく、流される血こそが、いや、血を流させる暴力こそがナカとソトとの分断を生み出しているのだということをも暗示してはいないだろうか。そういえば、同じ施設で育ったヲトメとスーの運命がナカとソトへと分かたれることになったのも、ヲトメの行為によるスーの流血が原因だった。
悪い方へ悪い方へと転がり続ける物語は、どんな解決も結末らしい結末も与えられないまま唐突に終わりを迎える。だがそれは世界の終わりではない。物語の冒頭を繰り返すように人々が行き交うなか「なにかが落ちてくる」最後の場面は、暴力と分断の終わりなき連鎖を改めて観客に突きつける。「その一発で、全部おしまいになればよかった。だけど、なにも変わらない。誰も気づかない。わたしたちは、ずっとずっと、ここにいる。多分、永遠に」。
 [撮影:木村恵美子]
[撮影:木村恵美子]
 [撮影:木村恵美子]
[撮影:木村恵美子]
 [撮影:木村恵美子]
[撮影:木村恵美子]
果てとチークの前作『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』の戯曲は第68回岸田國士戯曲賞最終候補作品に選出されている(受賞作は2024年3月1日[金]に決定)。それに伴い2月13日(火)23:59まで上演映像も無料公開中。今後の公演としては8月に『はやくぜんぶおわってしまえ』(第29回劇作家協会新人戯曲賞最終候補作品)再演、11月に『害悪』(令和元年度北海道戯曲賞最終候補作品)再再演、そして2025年1月に『はやくぜんぶおわってしまえ』の続編となる新作『きみはともだち』が予告されている。
果てとチーク:https://hatetocheek.wixsite.com/hatetocheek
『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』上演映像(2月13日[火]23:59までの配信):https://youtu.be/BsIj73v-1mM
関連レビュー
果てとチーク『そこまで息が続かない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年12月01日号)
果てとチーク『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年09月15日号)
果てとチーク『はやくぜんぶおわってしまえ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月01日号)
2023/12/16(金)(山﨑健太)
KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』
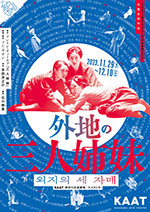
会期:2023/11/29~2023/12/10
KAAT神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉[東京都]
「優良なる国民の増加を図るために」「なるべく早く結婚せよ」「産めよ殖やせよ、国のために」。KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』(翻案・脚本:ソン・ギウン、演出:多田淳之介、翻訳:石川樹里)の終盤で引用されるこれらの言葉は、ナチス・ドイツの「配偶者選択10か条」にならって厚生省が1939年に発表した「結婚十訓」をもとにした一節だ。これらの言葉が歴然と示しているように、朝鮮を支配し戦争へと邁進する日本の植民地主義や軍国主義は家父長制と密接に結びついている。そしてもちろん、家父長制の問題は現在とも地続きだ。2020年から3年を経ての今回の再演は、そのことをまざまざと感じさせるものになっていた。
チェーホフ『三人姉妹』を原作に、舞台を帝政ロシアの田舎町から日本の植民地支配下の朝鮮へと置き換えた本作。物語は1935年4月にはじまり、翌年には日中戦争が開戦することになる36年の年末、第二次世界大戦勃発直前の39年8月、そしてミッドウェー海戦を経て戦争の主導権がアメリカへと移った後の42年10月と、そのときどきを生きる福沢家とその周囲の人々を四幕構成で描き出す。
 [撮影:宮川舞子]
[撮影:宮川舞子]
筋そのものは驚くほど原作通りだ。将校である父の赴任で朝鮮北部の軍都・羅南に住むことになった福沢家。教師として働く長女・庸子(伊東沙保)、近所に住む中学教師・倉山銀之助(夏目慎也)に嫁いだ次女・昌子(李そじん)、内地で大学教授になるという夢を果たせず、現在は英語の翻訳などをして過ごす長男・晃(亀島一徳)、そして女学校を卒業したばかりの尚子(原田つむぎ)の生活と周囲の人々との関係はゆるやかに、しかし確実に変化していく。晃はやがて朝鮮人有力者の娘・仙玉(アン・タジョン)と結婚し、昌子は父の部下であった軍人・磯部(大竹直)と互いに思いを寄せることになるだろう。一方、尚子は福沢家の離れに下宿していた朴智泰(田中佑弥)と婚約するのだが、その朴は結婚の直前、尚子に一方的に好意を抱く軍人・相馬僚(波佐谷聡)との決闘に敗れ命を落としてしまうのだった──。
 [撮影:宮川舞子]
[撮影:宮川舞子]
 [撮影:宮川舞子]
[撮影:宮川舞子]
こうしてまとめてみればこの作品では恋愛沙汰しか描かれていないようにも思える。だが、ソン・ギウンの戯曲は、福沢家とその周辺の人々の関係とその変化を通して、たかが恋愛や家族関係でさえ植民地支配や戦争と無関係ではあり得ないということを巧みに示していく。朝鮮人と日本人、女と男、軍人と民間人、内地(日本)を知るものと外地(朝鮮)で生まれ育ったもの、地方出身者と都市部出身者。属性や文化、言葉の違いは人格形成や人間関係に影響し、その歪みがもたらした帰結のひとつが相馬による朴の殺害だった。相馬の行為は女性を自らの所有の対象としてしか見ることのできない「有害な男性性」がゆえのものであり、相馬の憎悪は単に恋敵へのそれという以上に、朝鮮人の父と日本人の母をもつ朴の出自へと向けられたものだったはずだ。
 [撮影:宮川舞子]
[撮影:宮川舞子]
 [撮影:宮川舞子]
[撮影:宮川舞子]
共に生きていくはずだった朴を失って崩れ落ちる尚子を、庸子はそれでも希望を失ってはダメだと励まそうとする。最後の台詞はこうだ。「みんなで支え合って、振り返らず……、前に進みましょう」「前に? ねえ、前ってどっち?」「きっと、みんなが見てる方でしょ」。「みんなが見てる方」こそが「前」なのだという言葉は、仙玉が苛立ちを感じていた日本語の特性にも通じるものだが、一方で、家父長制が女性から意思決定の権利を奪ってきた結果でもあるだろう。教務主任への昇進の話があったときでさえ庸子は「私は……普通の女教師で充分。男の人についていくだけの、ごく普通の女……」と言っていたことが思い出される。
 [撮影:宮川舞子]
[撮影:宮川舞子]
しかも、そうして彼女たちが見つめる先にあるのは客席に座る私たちの現在にほかならず、観客の視線は合わせ鏡のように舞台上の彼女たちに注がれているのだ。「みんなが見てる方」に進んでいった先に訪れた未来、つまり観客である私たちの現在は、気づけば彼女たちの生きた過去へと折り返されてはいないだろうか。そういえば、第2幕で読み上げられる新聞記事がその年の出来事として回顧していたのは、多くの軍人や貴族が入信し、海軍までもが影響を受けた新興宗教・大本教の全国支部の解散や結核患者の急増、そして札幌と東京のオリンピック誘致などだった。「新聞を読んでるの、それとも旧聞を読んでるの?」という尚子の軽口は、2023年の日本を生きる私にとっては笑えない冗談でしかない。第3幕で客席と向き合うように置かれた鏡を覗き込んだ軍医・千葉(佐藤誓)の「なんだ、おまえか。誰かと思えば。どんな化け物かと思えば、……すっかり老いぼれだ」という言葉もまた、日本の現在へと反射するものだ。前に進むために、私はその鏡に映る醜さを直視することができているだろうか。
 [撮影:宮川舞子]
[撮影:宮川舞子]
KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』:https://www.kaat.jp/d/ThreeSisters2023
2023/11/29(水)(山﨑健太)
イエデイヌ企画『エリカによろしく』

会期:2023/11/24~2023/11/26
SCOOL[東京都]
あらゆる出来事は生起したその瞬間には意味をもたない。意味は時間の積み重ねの先に訪れる。そうして認識は塗り替えられ、過去はときに予兆として改めて現在に立ち現われることになるだろう。だがこのとき、一体どちらが世界の真の姿と言えるだろうか。『イマジナリーピーポーイントーキョー』以来3年ぶりとなるイエデイヌ企画の新作『エリカによろしく』(作:魚田まさや、演出:福井歩)は、二人の男性のきわめて私的な関係とその変化を描きながら、一方でその背後に横たわる世界の得体の知れなさを、そして不可解のヴェールの向こうに真理めいたものが閃く(あるいはそれこそがむしろ日常の背後に横たわる不可解なのかもしれないが)その一瞬を浮かび上がらせる、そんな作品だったように思う。
 [撮影:瀬崎元嵩]
[撮影:瀬崎元嵩]
 [撮影:瀬崎元嵩]
[撮影:瀬崎元嵩]
圭一(重山知儀)は恋人の仁(平山瑠璃)とともに実家に向かっている。いまはもう誰も住まないその家の整理をするためらしい。圭一の仕事がなかなか終わらず、飛行機に遅れそうになるが何とか乗り込み、空港からはレンタカーでの移動だ。道中、二人は海を見渡せる見晴台に寄る。飲み物を買った自販機で当たりが出て喜ぶ圭一。その直後、頭をもたせかけようとした圭一を振り払い、仁は別れを切り出すのだった。気まずい雰囲気のなか、二人はホテルに到着するが、車から仁を降ろした圭一はそのまま走り去ってしまう。
再び見晴台の場面。なぜか同じやりとりが繰り返されるが、圭一は頭をもたせかける代わりに缶を崖下に投げ捨てる。「何やってんの!」と驚く仁。しかし、別れ話は持ち出されず、二人はそのままホテルへと向かう。翌日、圭一の実家。同棲について、この間の部屋でいいか、引っ越しはいつにするかなどと問う仁に対し、圭一の答えはいまいちはっきりしない。挙句に圭一は二人でここに住むなどと言い出し、二人はぎこちない雰囲気のまま鍋を囲む。鍋の温度を上げようとするとブレーカーが落ち、暗闇のなか、二人は会話を続けるが、やがて圭一の声は返ってこなくなり──。
4年後。空港で偶然の再会を果たす二人。あの日、圭一は暗闇から消えてしまいそれきりだった。圭一はその理由について「予感が来たんだ」とだけ告げる。仁はいまはイギリス在住で、パートナーとの間には代理母の協力を得てもうすぐ子供が生まれるらしい。わだかまりや後悔、思い出を少しだけ言葉にして交わし、二人は別れる。生まれてくる子供の名前はエリカという。
 [撮影:瀬崎元嵩]
[撮影:瀬崎元嵩]
 [撮影:瀬崎元嵩]
[撮影:瀬崎元嵩]
こうしてまとめてみると、『エリカによろしく』という作品は基本的には二人の別れを描いた物語だと言うことができるだろう。だが、そもそも上演に立ち会う観客は、このようなかたちで物語を理解していくわけではない。言葉が提供する情報は切り詰められており、しかも上演自体が何もない舞台とリアリズムからは隔たった大まかなジェスチャーを基本とする演技によっているため、観客はその僅かな手がかりの蓄積から状況や人物の関係を類推するしかないのだ。例えば、圭一と仁が恋人同士であることが確信されるのは、実のところ仁が圭一に対して別れを切り出すまさにその瞬間においてだ。そこに至るまでの間、観客は二人が(恋人同士である可能性も視野に入れつつ)どのような関係であるかの判断を保留し続けるしかない。別れが告げられた瞬間から遡って二人の関係は恋人同士のそれだったということになるとも言えるだろう。
あるいは不可解な時間の巻き戻しについて。これについて劇中では一切の説明がなされないのだが、いずれにせよ、一度別れの場面を目撃してしまった観客は(圭一と同じく)その予感を抱いたまま二度目の二人のやりとりを見守ることになる。一度目になされてしまった別れの場面をやり過ごしてもその予感が消えることはなく、やがてその予感に耐えきれなくなるかのようにして圭一は姿を消してしまう。
そして4年後の再会。実はこの場面は作品の冒頭を反復している。実家に向かう予定なのに勤務先をなかなか出られない圭一。そして空港での仁との邂逅。すでに時間の巻き戻しを経験している観客は、またしても(別れを回避するために?)時間が巻き戻されたのではないかと思うのだが、それは別れから数年後の出来事であるらしいということがすぐに明らかになる。
 [撮影:瀬崎元嵩]
[撮影:瀬崎元嵩]
 [撮影:瀬崎元嵩]
[撮影:瀬崎元嵩]
演出の福井は当日パンフレットで「異なるもの同士がひとつにつながる瞬間」=「『Aであり、Bであろうとする』状態」に触れていた。これは何よりもまず第一に、何もない空間に「今ここ」とは異なる時空間を立ち上げる演劇の力を指すものだろう。だが、そのような瞬間は日常においても現実の裂け目のように現われる。停電の暗闇から聞こえる衣擦れの音は別れの場となった見晴台の潮騒を呼び込み、ホテルの朝食会場で不意に交わされた激しい握手は再会の握手への約束となる。あるいは紅茶とマドレーヌ。現在という表面と、その下に蠢く過去や記憶。『エリカによろしく』は演劇を通して両者をつなぐ回路を開くことで、世界というものの不可解な手触りをまざまざと立ち上げてみせたのだった。
前作に続いてきわめて演劇的な手つきでもって世界はたしかにこのようにあるのだというその様を鮮やかに示して見せた福井の演出もさることながら、魚田の戯曲が素晴らしかった。私は寡聞にして今回初めてその作品に触れたのだが、魚田は2019年から2021年にかけてロイヤルコート劇場×新国立劇場の劇作家ワークショップに参加し、2022年にはuni『すみだ川ラジオ倶楽部 川を流れる七不思議編』の劇作を担当している。二人の今後の活動にも注目したい。
イエデイヌ企画:https://iedeinu-kikaku.mystrikingly.com/
魚田まさやnote:https://note.com/sakanada_masaya/
2023/11/26(日)(山﨑健太)
新国立劇場演劇研修所第17期生公演『君は即ち春を吸ひこんだのだ』

会期:2023/11/07~2023/11/12
新国立劇場 小劇場[東京都]
『ごんぎつね』の童話作家・新美南吉とその周囲の人々を描いた原田ゆうの戯曲『君は即ち春を吸ひこんだのだ』。「日本の劇」戯曲賞2014で最優秀賞を受賞したこの作品が、新国立劇場演劇研修所第17期生公演として田中麻衣子の演出で上演された。
舞台は南吉こと本名・正八(立川義幸)の住む渡辺家の離れ。玄関と土間、大量の本が乱雑に摘まれた二間続きの六畳間。縁側から続く草木の植わった庭には南吉の童話からとったと思しきモチーフが見え隠れしている(美術:伊藤雅子)。観客はこの離れを挟むかたちで対面に配置された客席から正八たちのままならぬ生を見守ることになる。
 [撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
翌月には国家総動員法が公布されることになる1938年3月。父・多蔵(樋口圭佑)と母・志ん(小林未来)が落ち着かない様子で待っているところに正八が帰ってくる。どうやら女学校の先生に採用されたらしい。若くしてその文才を見出され、童話雑誌『赤い鳥』に作品を寄稿するなどしていた正八だったが、筆一本では食っていけない。幼い頃から体が弱く、師範学校にも通えなかった正八がようやく手にしたのが今回の女学校での職だった。両親の心配も道理である。安堵し、母屋へと帰っていく二人。入れ違うように庭からやってきたのは幼馴染のちゑ(根岸美利)だ。離れで正八を待っているところに多蔵と志んがやって来たので、慌てて庭へと逃げ出し様子を窺っていたらしい。気の置けない二人は互いに憎からず思っている様子だが、ちゑの弁を借りれば二人がどのような関係なのかは「当の本人達にすら分かっていない」。中山家の殿様の末裔であるちゑは没落気味の家を自らの手で再興したいと願っており、そのためにも医者としてさらなる立身出世を目指したい。二人の関係が微妙なままにあるのはそんな事情も関わっているようだ。だがそれでも正八は「俺とお前は特別だわ」「お前のことは俺にしか分からんげな」と言い、ちゑもそれに応じるように「私、時折思うのよ。息をね、正八っあんの息をさ、思い切り吸い込んでもいいかなって」と告げる。
 [撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
 [撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
ちゑの言葉は謎めいてはいるものの、それが作品のタイトルと呼応していることは明らかだ。『君は即ち春を吸ひこんだのだ』。南吉の日記からとられたというこの一節に含まれる「春」のイメージも手伝って、ちゑの言葉はひとまず一風変わった愛情の吐露として受け取ることができるだろう。だが、やがて正八が結核に侵されていることが観客に明かされるとき、ちゑの言葉が、生のみならず死をともにすることをも厭わないという強い思いの込められたものだったこともまた明らかになる。
しかし、だからこそ二人の関係は袋小路だ。やがてちゑは大阪で医者として働きはじめ、正八も学校の近くで下宿することになる。それでも二人の関係は「私が手を握れば正八っあんが離して、正八っあんが手を握ってくれば私が離してって感じで」変わらない。ちゑはそんな関係を「やっぱり、私は、嫌よ」と言ってみたりもするのだが、正八は「身勝手だな、お前は」と応じるばかり。そしてちゑもやはり「知ってるわ。でも、正八っあんだって」と返すのだった。身勝手と相手を思う気持ちは見分けがたく、また相手の気持ちも知っているがゆえにますます二人は身動きが取れない。
 [撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
ところが、二人の関係は思わぬかたちで終わりを迎えることになる。旅先での心臓発作でちゑが亡くなってしまうのだ。独立開業に向けた過労がゆえだろうか。服用していた精神安定剤が影響した可能性もあるらしい。その薬は、ちゑの弟の文夫(佐々木優樹)によって服用を止められてからもなお、正八が密かに渡していたものだった。いずれにせよ、はっきりとした原因はわからず、正八がどのような思いで薬を渡していたのかも語られることはない。
そして正八の体も結核という病魔に蝕まれていく。正八にとってその病は、早くに亡くなった実母の面影と、そしてその死と強く結びついている。「母さんが春の花に春の風を吹かせようと言って一緒にふぅーと息を吐いたんだ。(略)あの時咳き込んだんは俺だったか、母さんだったか、それとも、俺も母さんもどちらもだったか……」。原体験とも言える光景のなかで生きること、愛することはその愛する者の死と分かちがたく結びつき、だからこそ正八はちゑとの関係において決定的な一歩を踏み出せなかったのだろう。「俺は毎日花に息を吹きかけて、吹きかけて、死んだ母さんと一緒に息を吹きかけて、何本もの花を枯らした、枯らしてしまった……」。静かな言葉の背後に慟哭が滲む。
 [撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
 [撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]
正八の友人・畑中を演じた田崎奏太、正八の教え子・初枝を演じた飯田桃子も含め、丁寧な演技で細やかな感情の機微を舞台に立ち上げてみせた7名の若き俳優たちに拍手を送りたい。特にちゑを演じた根岸は、溌剌としながらも家への責任と正八への思いに引き裂かれ、ときに秘めた激情を溢れさせてしまうその姿を魅力的に演じていた。同じ俳優陣による公演として2月6日(火)から11日(日・祝)には演劇研修所第17期生修了公演『流れゆく時の中に─テネシー・ウィリアムズ一幕劇─』(演出:宮田慶子)が予定されている。
新国立劇場演劇研修所第17期生公演『君は即ち春を吸ひこんだのだ』:https://www.nntt.jac.go.jp/play/kimiharu_2023/
原田ゆう『君は即ち春を吸ひこんだのだ』戯曲(戯曲デジタルアーカイブ):https://playtextdigitalarchive.com/drama/detail/3
2023/11/08(水)(山﨑健太)
ロロ『オムニバス・ストーリー・プロジェクト(カタログ版)』

会期:2023/10/07~2023/10/15
東京芸術劇場シアターイースト[東京都]
SNSの普及で私の「今ここ」とは異なる時間・場所を友人知人、あるいは見知らぬ誰かがどのように生きているかを知る機会が増えた。だが、それはもちろん取捨選択を経てタイムラインへと投げ込まれた人生の断片に過ぎず、それらはときに、その周囲に私には知ることのできない時間や場所が広がっているのだということを改めてまざまざと感じさせることになる。
東京芸術祭2023の一環として上演されたロロ『オムニバス・ストーリー・プロジェクト(カタログ版)』(テキスト・演出:三浦直之)は、三浦が書き下ろした50のキャラクターをもとに、各地の⼤学や劇場でそれぞれに上演を立ち上げていくプロジェクトのオープニングとなる東京芸術祭バージョン。50のキャラクターにはそれぞれ氏名・年齢・エピソードを含む300字程度のプロフィール、そして1ページの台本だけが用意されており、それらを種に各地で創作が行なわれていくのだが、今回はその種となる台本を一挙に上演する形式での公演となった。
「オムニバス・ストーリー・プロジェクト」(以下OSP)にはロロが2015年から2021年にかけて取り組んでいた「いつ高」シリーズからの展開としての側面もあるだろう。「いつだって誰もが誰か愛し愛されて第三高等学校」という架空の高校を舞台にしたこのシリーズでは、「高校演劇で上演しやすい作品を」という三浦の思いから、上演時間60分以内などの高校演劇のフォーマットを踏まえた作品が書かれ、上演を望む高校生にはその台本が無料で提供されてきた。上演台本(=物語)以前の設定のみを手渡すOSPの試みは、「いつ高」シリーズでの試みを創作のさらに手前の段階にまで拡張するものであり、三浦と各地でOSPに関わるつくり手たちとの、そしてOSPのキャラクター同士の出会いから新たな物語が生まれてくるための場を用意するものだと言える。
 [撮影:阿部章仁]
[撮影:阿部章仁]
6人の俳優(⼤場みなみ、北尾亘、⽥中美希恵、端⽥新菜、福原冠、松本亮)、90分の上演時間で46人の登場人物(4人は今回は未登場)/35のエピソードを演じる今回のバージョンは「カタログ版」というタイトルの通り、これから展開していくプロジェクトやキャラクターを紹介する性格をもつものだ。同時に、このようなかたちでの上演はOSPのベースになっているであろう世界観を、あるいはそれが全体として描き出そうとしている世界の像をより鮮やかに示すものにもなってもいたのではないだろうか。人はほかの人の人生のごく一部しか知ることができず、しかしそれらはときに思いもよらぬかたちで関わり影響を与え合っている。OSPは続いていくことで描かれた世界の外側に、自分に見えている世界の外側に手を伸ばし続けるプロジェクトなのだ。
 [撮影:阿部章仁]
[撮影:阿部章仁]
 [撮影:阿部章仁]
[撮影:阿部章仁]
三浦は本作の構想の原点として江國香織の小説『去年の雪』を挙げているが、ここに小説と演劇との違いを見ることもできるだろう。OSPは今後も各地で創作と上演が続いていく。それはつまり、登場人物たちが実際に、観客である私が立ち会った「今ここ」ではない時間・場所を生きていくということを意味している。
今回の上演では、6人の俳優が46人もの登場人物を演じることによって生じる演劇的な効果もまた、OSPが立ち上げる世界にたしかな手触りを与えるのにひと役買っていた。複数役の演じ分けは本作の見どころのひとつだが、それでも、同じ俳優が複数の登場人物を演じることで、それらの人物があたかも同一人物であるかのような錯覚が生じる瞬間がある。そのとき、その俳優は回路となり、互いに関係のないはずの複数のエピソードを、そこに登場する人々をつなぐことになる。街ですれ違う見知らぬ他人に見知った誰かの面影を見るのにも似て、そのようにして触れ合う世界の間には少しだけ親しみが宿ることになるだろう。
実際のところ、何人かの登場人物は複数のエピソードに登場しており、つまりは文字通りの「同一人物」なのだが、名前や設定からそれがはっきりとわかる場合もあれば、上演においてはそのことが明示されていない場合もある。その場合、観客は作中に複数回登場した人物が(同じ俳優が演じているにもかかわらず)「同一人物」であることに気づかないまま上演を見続けてしまう可能性があるわけだが、それは日常においても同じだろう。通学の電車でよく見かける人物が駅前の本屋の店員だったということにある日はたと気づく、などという経験は誰にでもあるのではないだろうか。世界はそんな「すれ違い」に満ち満ちているのだ。
90分で35エピソードという驚異の上演をただ可能にするのみならず面白い上演として成立させられたのはスタッフワークの力も大きい。ときに滑らかに、ときに素早く、ときにゆるやかに溶け合いながらの場面転換を実現し、舞台上にさまざまな時空間を軽やかに立ち上げてみせたスタッフ(美術:青木拓也、照明:富山貴之、音響:池田野歩、衣裳:臼井梨恵、舞台監督:原口佳子)に大きな拍手を送りたい。
 [撮影:阿部章仁]
[撮影:阿部章仁]
 [撮影:阿部章仁]
[撮影:阿部章仁]
OSPとしては11月15日・16日に四国学院大学(香川)でSARP vol.24として『カタログ版 in 四国学院大学』の、12月16日から23日には芸術文化観光専門職大学(兵庫)でCAT舞台芸術実習公演 PAP vol.4として『饒舌なダイジと白くてコトエ、マツオはリバーでネオには記憶』の、そして2024年3月16日・17日にいわきアリオス(福島)でいわきアリオス演劇部U30による上演が予定されている。
2月にはパルコ・プロデュース2024『最高の家出』で三浦が作・演出を務め、ロロメンバーも多数出演。2023年11月には劇団のファンコミュニティ「ハワイ」の活動もスタートし、ロロの活動はますます旺盛だ。
 [撮影:阿部章仁]
[撮影:阿部章仁]
 [撮影:阿部章仁]
[撮影:阿部章仁]
ロロ:http://loloweb.jp/
パルコ・プロデュース2024『最高の家出』:https://stage.parco.jp/program/iede
ファンコミュニティ「ハワイ」:https://fanicon.net/fancommunities/5289
関連レビュー
ロロ『BGM』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年05月15日号)
ロロ『ここは居心地がいいけど、もう行く』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年08月01日号)
2023/10/15(日)(山﨑健太)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)