artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
荒木経惟「梅ヶ丘墓情」

会期:2019/05/25~2019/06/15
タカ・イシイギャラリー東京[東京都]
1994年のタカ・イシイギャラリーのオープン以来、同ギャラリーで開催されてきた荒木経惟の個展は今回で27回目になるという。彼の誕生日である5月25日からスタートする展示もすっかり恒例になった。
今年の展覧会のタイトルの「梅ヶ丘墓情」は、彼が現在住んでいる小田急線の駅名にちなむ。自らの生と写真とを縒り合わせるように作品を発表してきた荒木にとっては、ごく自然な発想と言えそうだ。だが、「東京」のような広がりのある地名をタイトルにすることが多かったことを考えると、より狭い地域に限定されていることが気になる。というのは、展示作品のうちほんの数点を除いては、ほとんどの写真がマンションの自室と屋上だけで撮影されているからだ。むろん荒木には、以前住んでいた豪徳寺のマンションの屋上を撮影し続けた『愛のバルコニー』(河出書房新社、2012)という名作があり、つい先日もJCIIフォトサロンで同名の展覧会が開催されたばかりだ。ビザールな人形たちをそこここに配置した今回のシリーズも、その延長上の作品と見ることができる。だが、以前の「バルコニー」シリーズに溢れていた、グロデスクで、ユーモラスで、悪戯っぽい「奇想」のオンパレードは、今回のシリーズではほとんど影を潜めている。むしろそこから感じられるのは、しんと静まりかえった、無味、無臭、無音の情景であり、じわじわと滲み出てくる寂寥感だ。
その肌合いの違いが「体力が日増しに衰え、外出を控えることが多くなった」(広報用リーフレット)という、現在の彼の生活の状況に由来しているのは間違いない。以前に比べて、タナトスの影が大きくせり出し、すべての写真を薄膜のように覆っている。それを創作意欲の衰えと見ることも、あながち間違いではないだろう。それでも、写真を一枚一枚見ていくうちに、この悲哀に満ちた眺めもまた、心揺さぶるものであることを受け容れざるを得なくなる。荒木がこれから先、どれだけ個展を開催できるのかはわからない。だが、最後まで見続けていこうと思う。
荒木経惟 「梅ヶ丘墓情」、2019、RP プロクリスタルプリント © Nobuyoshi Araki / Courtesy of Taka Ishii Gallery
2019/06/07(金)(飯沢耕太郎)
「明治に生きた“写真大尽” 鹿島清兵衛 物語」

会期:2019/06/01~2019/08/31
写真歴史博物館[東京都]
日本の写真史を彩る人物たちの中で、最も心そそられるのが誰かといえば、もしかすると鹿島清兵衛かもしれない。清兵衛は東京・新川の酒問屋、鹿島屋の養子で、店の財産を写真の趣味に費やし、最後はとうとう離籍されて、若い頃に習い覚えた笛の囃子方にまで落ちぶれて生涯を終えた。ロシア公使と張り合って身請けしたという新橋の名妓、ぽん太とのロマンス、富士山の写真を巨大サイズに引き伸ばして宮内省に献上し、歌舞伎の名優、九代目市川団十郎の等身大の舞台写真を撮影するなど、“写真大尽”の華やかな前半生と零落後の後半生との鮮やかな対比は、小説や芝居の格好の題材となるだろう。実際に森鷗外が『百物語』(『中央公論』反省社、1911)で、また白洲正子が『遊鬼──わが師 わが友』(新潮社、1989)で、清兵衛を小説の中に登場させている。だが、肝心の鹿島清兵衛の写真がどんなものだったのかを確認する機会はそれほど多くない。古写真研究家の井桜直美が企画・監修した今回の展覧会は、その意味で貴重なものといえるだろう。
残念ながら、宮内庁所蔵の「富士山の図」(1894)をはじめとして、オリジナル写真の借用はむずかしく、出品作品のほとんどは複製である。だが、最近のデジタル複写の技術の進化によって、実際の作品にかなり近い印象を与えることができるようになった。そこから見えてくる清兵衛の写真家としての力量が、かなり高いものであったことは間違いない。技術的にしっかりしているだけでなく、被写体をゆったりとした構図におさめた、堂々たる風格を感じさせる作品が多い。残念なことに会場が狭いので、出品点数も限られるし、ほかの同時代の写真家たちと比較するような展示もむずかしい。できればもう少し広い会場で、明治後期の写真をまとめて見る機会があればいいと思う。鹿島清兵衛のような「素人写真家」の登場によって、日本の写真表現がどのように展開していったのかは、とても興味深い問題提起になるはずだ。
2019/06/07(金)(飯沢耕太郎)
大橋愛「arche」

会期:2019/05/18~2019/06/29
POETIC SCAPE[東京都]
大橋愛は2013年に写真集『piece』(FOIL)を刊行後、次のテーマを模索するうちに、自身が小、中、高校の頃に通っていた箱根山中のカトリック系女子校、函嶺白百合学園を撮影することを思いついた。それから4年間、何度となく通い詰めて、小学生たちを周囲の環境も含めて撮り続けた写真を集成したのが、今回のPOETIC SCAPEの展覧会である。
戦時下に疎開学園として設立された同学園は、豊かな自然に包まれた環境で、のびのびと授業がおこなわれている。『piece』は身近な人の死を契機として、その鎮魂の意味を込めて編まれた写真集だった。大橋にとって、山中にひっそりと小さな王国をつくりあげている函嶺白百合学園を撮影することは、その痛手を癒す行為であり、そこは「守られること」の大切さを強く感じさせる場所だったのではないだろうか。
写真を撮影するにあたっては、学校側からかなり厳しい条件が出された。顔や個人が特定できるアングルから撮影しないこと、ひとりではなく複数が写っているようにすることなどである。やはり最初はもう少し一人ひとりの表情を見たいと思ったのだが、写真を見続けているうちに、これはこれでよかったのではないかと思えてきた。大橋が伝えたかったのは、40年前とほとんど変わらないという学校の佇まいであり、「守られること」の安らぎと、それがいつ壊れるかわからないというぎりぎりのバランスだったのではないだろうか。特定の個人が見えてくる写真を入れると、その緊密な構成が崩れてしまう。特に、同じカトリック系ミッションスクールでもあるカリタス学園の小学生たちが襲われた川崎の殺傷事件の直後だっただけに、その配慮が身に沁みたということもある。むしろ、DMにも使われた綾取りをする少女たちの手をクローズアップした写真のように、被写体の細部を、そっと距離を置いて読み解いていくことが大事になるのではないだろうか。
2019/06/01(土)(飯沢耕太郎)
川田喜久治「影の中の陰」
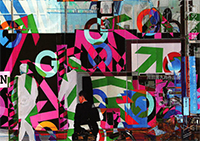
会期:2019/05/29~2019/07/05
PGI[東京都]
川田喜久治は2018年1月からインスタグラムに写真をアップし始めた。今回のPGIの個展では、2019年5月まで、つまり「『平成』の最終年から、元号が『令和』に変わるまで」ほぼ毎日アップされた370点から、約50点を選んで展示している。出品作は「1.空、雲、雨、太陽と月のメタファー、あるいは、オマージュ」、「2.『見えない都市』あるいは。『記憶のない都市』」、「3.影の中の陰」の3パートに分かれるが、「展示においてはそれぞれを混合し、異時同図のイメージスクロール(一種の絵のながれ)としている」という。
作品には、1970年代の「ロス・カプリチョス」、90年代の「ラスト・コスモロジー」、2000年代の「ワールズ・エンド」など、これまでの川田の仕事を彷彿とさせるものが数多く含まれている。つまり、インスタグラムという「新しいコミュニケーションを秘めたこの方法」を試すにあたって、彼はこれまでの自分の写真観、世界観を総点検し、そこからさまざまな手法を抽出し、全精力を傾けて「イメージスクロール」を構築しようとしているのだ。結果として、「影の中の陰」はいかにも川田らしい作品であるとともに、新たなチャレンジの意味を持つものともなった。川田は1933年生まれだから、今年86歳になるわけだが、小柄な体の奥から湧き出る創作エネルギーの噴出には、驚きを通り過ぎて唖然としてしまう。
インスタグラムへの挑戦は、川田にとって新鮮な衝撃でもあったようだ。展覧会のコメントに「あのハート印の『いいね』を繰り返す見えない人たちの呪文のような声援は、日々の光の謎の奥へと探索をうながしてくる」と書いている。インスタグラムヘのアップを契機として、さらなる未知の表現領域への飛躍も期待できそうだ。
2019/05/29(水)(飯沢耕太郎)
よみがえる沖縄 1935

会期:2019/04/13~2019/06/29
立命館大学国際平和ミュージアム[京都府]
KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2019のアソシエイテッドプログラムとして開催された写真展。1935年の朝日新聞の記事「海洋ニッポン」(全10回連載)の取材時に撮影された写真のネガ計277コマが大阪本社で見つかり、セレクトされた約100点の写真が、立命館大学 国際平和ミュージアムが所蔵する沖縄関連資料と合わせて展示された。戦前の沖縄の写真の多くが戦災で焼失したなか、10年後の太平洋戦争で破壊される前の街並みや人々の生活風景を伝える貴重な記録である。モノクロプリントに加え、AIの機械学習と住民の記憶に基づいてカラー化した写真も展示された。
展示は撮影地域ごとに構成され、「糸満」の(埋め立て前の)海と漁師、「古謝」のサトウキビ畑での農作業、「久高島」の墓や風葬の宗教的風習、「那覇」の市場の賑わいなどが活写されている。ただ、これらの写真を「豊かな自然と独自の文化に満ちた島、そこで力強く生きる明るく素朴な人々」として、ノスタルジーの対象として眼差すことには注意が必要だろう。吉浜忍(沖縄近現代史)が解説パネルで指摘するように、国家が戦時体制を固めていく時代状況においてプロパガンダ的側面をもつからだ。例えば、糸満出身者の移民先を記した世界地図を眺める、坊主頭の少年たち。後ろ姿の彼らの表情は見えないが、掲載記事の解説には「糸満人の世界分布図に感激の胸おどらす第二世たち」と記される。地図にはシンガポール、ジャワ島、ハワイなど南洋諸島が記され、移民先が「南進」政策と重なっていることを示す。また、古謝(現沖縄市)の「模範部落」でサトウキビ農作業に従事する青年団や女子青年団を撮影した一連の写真群からは、「労働の組織化による国力増産」というメッセージがうかがえる。報道写真の撮影者の眼差しのなかにある意図を脱色してこれらの写真を見ることは、歪曲にほかならない。
また、「AIの機械学習による古写真の着色」は昨今の流行である。だが今回の場合、沖縄独自の風物については学習素材が少なく、「カラーの再現」に難航したという。例えば、市場で女性が売っているカゴのなかの物が何であるのかが判別せず、別会場での展示の際、来場した高齢の女性から「海藻」だと教えてもらい、色彩が再現できたというエピソードも紹介された。これは再現可能となった事例だが、「記憶の欠落や空洞」を物語るものとして、あえて着色せず残す方法もアリなのではないかと思った。沖縄戦の破壊による消失の傷を「色鮮やかな再現=記憶の蘇生」として癒すのではなく、証言者の不在と「もはや蘇らない」記憶の空白地帯と断絶を指し示すものとして。
公式サイト:http://www.asahi.com/special/okinawa/oldphoto/
2019/05/25(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)