artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
石田榮「はたらくことは生きること──昭和30年前後の高知」

会期:2019/04/02~2019/05/06
JCII PHOTO SALON[東京都]
石田榮は1926(大正15)年に香川県に生まれ、機械見習工を経て海軍に召集され、海軍特別攻撃隊菊水隊白菊隊の整備兵として終戦を迎えた。復員後、高知県で農業機械の会社に勤めるようになり、その傍ら、譲り受けたドイツ製の「セミイコンタ」カメラで、働く人々の姿を撮影しはじめる。「家から近いこと、危険が少ないこと、そして日曜日でも仕事をしているところをテーマにしたい」と考えたのだという。昭和30年代に高知市、南国市、大豊町一帯で撮影した写真は、その後長く「セロファン製のアルバム」に入れたまま眠り続けていた。だが、2012年に大阪ニコンサロンで開催した個展「明日への希望を求めて──半世紀前の証」が注目され、2016年に写真集『はたらくことは生きること』(羽鳥書店)が刊行される。今回JCII PHOTO SALONで開催されたのは、そのアンコール展示というべき写真展である。
「浜」「港」「石灰」「農」「里」「商」の6部構成で展示された、70点余りの作品は、表現的な意図よりも記録に徹するという姿勢で撮影されたものだ。どの写真も、画面の隅々までピントが合っており、視覚的な情報量が豊かである。だからこそ、60年以上の時を隔てていても、その時代の空気感がまざまざと甦るようなリアリティがある。何よりも貴重なのは、それらの写真に、いまではほとんど失われてしまった、体を使って「はたらくこと」のありようが細やかに写り込んでいることだろう。身体性が剥ぎ取られ、抽象化してしまった現在の労働よりも、豊かで充実した生の営みが、ごくあたり前におこなわれていたことに胸を突かれる。石田が戦時中に出撃する特攻隊の兵士を見送る立場にいたことが、これらの写真を撮影し続けた動機のひとつになっていることは間違いない。まさに「はたらくことは生きること」であることを、カメラを通して日々確認することの喜びが伝わってきた。
2019/04/02(火)(飯沢耕太郎)
宮本隆司「首くくり栲象」出版記念展覧会

会期:2019/03/18~2019/03/31
BankART SILK[神奈川県]
吊り下げられたヒモの輪を前に、思い詰めた表情でたたずむ老人。ヒモに近づき、輪に首を通して、身体をゆだねる……。首くくり栲象(たくぞう)が20年ものあいだ日課にしていた首吊りパフォーマンスを捉えた写真だ。もちろん実際に首を吊るわけではなく、ヒモを顎に引っかけて身体を宙に浮かすのだが、ヘタすれば本当に首を吊ってしまいかねない(でも、昔「ぶら下がり健康法」なんてあったから意外と健康にいいかも、って真似すんなよ)。栲象は20年ほど前から、国立にある自宅の「庭劇場」で首吊りパフォーマンスを公開していたが、1年前に肺ガンで他界。同展は、近所に住む宮本隆司が撮りためた写真を展示するもので、栲象の1周忌と写真集の発売記念を兼ねた展覧会。建築や廃墟を撮り続けてきた宮本にとっては初の人物写真集となる。なんというか、おもしろい写真ではあるけれど、あまり欲しいとは思わないなあ。
2019/03/30(土)(村田真)
野村恵子「山霊の庭 Otari-Pristine Peaks」
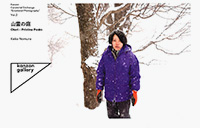
会期:2019/03/16~2019/04/13
Kanzan Gallery[東京都]
このところ、女性写真家たちの質の高い仕事が目につくが、野村恵子もそのひとりである。1990年代にデビューした彼女と同世代の写真家たちが、それぞれ力をつけ、しっかりとした作品を発表しているのはとても嬉しいことだ。野村は昨年刊行した写真集、『Otari-Pristine Peaks 山霊の庭』(スーパーラボ)で第28回林忠彦賞を受賞した。今回の展示はそれを受けてのことだが、菊田樹子がキュレーションするKanzan Galleryでの連続展「Emotional Photography」の一環でもある。
雪深い長野県小谷村の人々の暮らし、祭礼、狩猟の様子などを「湧き上がる感覚や感情を静かに受け入れながら」撮影した本シリーズは、たしかに「感情」、「情動」をキーワードとする「Emotional Photography」のコンセプトにふさわしい。特に、妊娠し、子どもを産む若い女性の姿が、大きくフィーチャーされることで、ほかの山村の暮らしをテーマとするドキュメンタリーとは一線を画するものとなった。
野村と菊田による会場構成も、とてもよく練り上げられていた。壁には直貼りされた大判プリントとフレーム入りの写真が掲げられ、写真とテキストを上面に置いた白い柱状の什器が床に並ぶ。ほかに、3カ所のスクリーンで映像をプロジェクションしているのだが、その位置、内容、上映のタイミングもきちんと計算されている。写真集とはまた違った角度から、「山に生かされて」暮らしを営む人々の姿が重層的に浮かび上がってきていた。近年、ドキュメンタリー写真における展示の重要度はさらに上がってきているが、それによく応えたインスタレーションだった。
2019/03/27(水)(飯沢耕太郎)
宮本隆司『首くくり栲象』出版記念展覧会

会期:2019/03/18~2019/03/31
BankART SILK[神奈川県]
2018年3月から活動を休止していた横浜市の現代美術スペース、BankART Studio NYKが、同市内の3カ所で活動を再開した。BankART Home、BankART Stationに続いて、坂倉準三設計の歴史的建造物《シルクセンター》の1階にオープンしたのがBankART SILKである。そのオープニング第2弾として、宮本隆司の「首くくり栲象」展が開催された。
宮本は10年ほど前から、庭先に吊り下げた縄に首を入れてぶら下がる「首くくり栲象(たくぞう)」(本名:古澤守)のパフォーマンスを写真と映像で記録してきた。いまにも崩れ落ちそうな木造平屋の「庭劇場」でほぼ毎日、首をくくってきた1947年生まれのパフォーマーは、2018年3月に亡くなり、いまはもうその「死に触れず、死を作品化する」伝説的なパフォーマンスを見ることはできない。その意味では貴重な記録といえるのだが、それ以上に、その普通ではない行為をあえて普通に撮影している宮本の撮影の仕方に共感を覚える。宮本が「庭劇場」を撮影し始めた理由のひとつは「家が近かったこと」だったようだが、自然体の撮り方にもかかわらず、そこには建築写真で鍛え上げた細やかな観察力と、精確な画面構成の能力が充分に発揮されていた。
会場では写真作品のほかに、パフォーマンスの一部始終を記録した映像作品も上映していたのだが、こちらも興味深い内容だった。フレームを固定した画面に、「首くくり栲象」のパフォーマンスが淡々と記録されているだけなのだが、途中でその傍に、巨大な猫が絶妙な間合いで出現して消えていく。むろん仕組んだものではないだろうが、その展開には意表をつかれた。なお、宮本隆司の写真と演劇評論家の長井和博のエッセイ「午後八時発動」を掲載した作品集『首くくり栲象』(BankART1929)も刊行されている。
2019/03/26(火)(飯沢耕太郎)
プレビュー:写真展「EXIT」
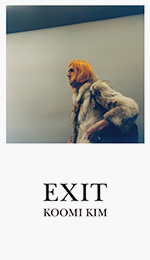
会期:2019/03/29~2019/04/19
BOOTLEG GALLERY[東京都]
2019年3月29日のEU離脱★1に向けて、いまイギリスが混乱している。この日から始まる本展は、写真家の金玖美がまさに「ブレグジット」をテーマに発表する写真展だ。混乱しているのは政治家や議員ばかりでなく、市井の人々も然り。本展はそんな市井の人々に焦点をあてた、私的なドキュメンタリーである。
金は幼少の頃、イギリスの伝承童話『マザーグースのうた』を繰り返し読み、そのなかに登場するイギリスの地名に惹かれ、いつか行ってみたいと思いを馳せて大人になったと言う。20歳のときに一人旅でイギリスを初めて訪れ、さらに写真家になった後、2004年にロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーションに留学し、その地に2年半滞在した。そんな金が2004年から15年間かけて、ロンドンを中心にイギリス各地で撮り溜めた写真が、本展では展示される。
おそらく『マザーグースのうた』が生まれた頃のイギリスと現在のイギリスとでは、国のあり方がずいぶん変わっているはずだ。金が最初に訪れたときのイギリスは、多民族、多文化が共存する、多様性のある国だった。彼女はそこに魅力を感じ、居心地の良さも感じたと言う。ちなみに金自身も在日コリアンとして生まれ、その出自に戸惑う経験もしたが、イギリスの寛容さに触れたことが自身のアイデンティティを確認する良い機会になったと言う。
写真に写されているのは、金がイギリス滞在中に引っ越しの内見で知り合った人やいっしょに暮らした人、学校の友人やそのまた友人、街で声をかけた人、そして街の何気ない風景などだ。金がかつて住んだ地域は、1990年代以降、賃料の安い空き倉庫を目当てにクリエイターが多く移り住んでいたイーストロンドンで、そこには移民も多く暮らしていた。2016年以降には、彼らにブレグジットについて話を聞きながら、撮影した。彼らはあくまでも仕事や家族、生活環境などの個人的な事情に基づいて、離脱か残留かの見解を述べた。これまで多様性を受け入れてきたイギリス社会だけに、彼らの自己主張は強く、ゆえに戸惑いも大きい。金はそんな彼らを優しく見つめるように、シャッターを切る。素のままの顔でカメラを真っ直ぐに見つめる人、カメラの存在すらないかのように部屋でくつろぐ人、抱き合うカップルなど。それらの写真はフィルムカメラで撮影され、金が調整して手焼きしたものであるため、昔のフィルム写真のように柔らかな質感をまとっている。そのためか、彼らの混乱や戸惑いよりも、その奥にある本性だけがすっと写し出されているようにも見える。この先、彼らの生活がどう変わりゆくのか……と想像を巡らせると、胸がやや詰まる。

金玖美《チェスと男》

金玖美《彼らは今、セント・アイブスに住んでいる》

金玖美《金さえあればどっちでもいい》
※2019/07/05〜2019/07/29、静岡県浜松市BOOKS AND PRINTSにて巡回展を予定。
※2019/04/11追記:会期の延長にともない、展示終了日を04/14から04/19に変更した。
★1──英議会の採決で、4月以降への離脱延期が決まりつつある(2019年3月29日現在)。
2019/03/26(火)(杉江あこ)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)