artscapeレビュー
2023年08月01日号のレビュー/プレビュー
私たちは何者? ボーダーレス・ドールズ

会期:2023/07/01~2023/08/27(※)
渋谷区立松濤美術館[東京都]
なかなかユニークな展覧会だった。人形を題材に、ここまで風呂敷を広げられるのかと感心した。民俗学的な側面もありながら、工芸や彫刻、玩具、そして現代美術まで、さまざまな分野をボーダーレスに飛び越える媒介として人形を扱っている点が興味深い。ヒトガタと書く人形は、まさに人の写しなのだ。だからこそ人に付いてまわり、人が関わる分野すべてに関係する。古くは呪詛や信仰の対象となり、雛人形や五月人形のように子どもの健康を願い、社会の規範を教える存在となり、また生人形のように市井の人々の生活や風習を描く展示物となった。本展はそんな日本の人形の歴史を順に追っていき、観る者に人形とは何かを考えさせた。
 【後期展示】《立雛(次郎左衛門頭)》(江戸時代・18〜19世紀)東京国立博物館蔵[Image: TNM Image Archives]
【後期展示】《立雛(次郎左衛門頭)》(江戸時代・18〜19世紀)東京国立博物館蔵[Image: TNM Image Archives]
私自身、人形との関わりを振り返れば、雛人形もそうだが、もっとも思い出深いのは子どもの頃に遊んだリカちゃんだろう。赤いドレスを着たリカちゃん1体と、確かスーパーマーケットのような模型のセットが家にあり、それらで友達と何度もごっこ遊びをした。子どもが大人の真似事をするごっこ遊びも、いわば、社会の規範を学ぶ一過程である。あの頃、私も含めた少女たちは、少しお姉さんになった自分の理想の姿をリカちゃんに投影して遊んでいたような気がする。そういう点で、リカちゃんは現代っ子の写しなのだ。
人の写しであるからには、人形はさまざまな面を負ってきた。戦争が色濃くなった昭和初期から中期にかけては、騎馬戦に興じる軍国少年たちを象った彫刻や、出兵する青年たちに少女たちがつくって渡したという「慰問人形」があった。慰問人形は粗末な布で手づくりされた人形とも言えないほどの出来なのだが、これは少女たちの写しであり、青年たちは出兵先でこれを見て、自らを鼓舞する力を得たのだという。また昭和初期から百貨店を彩り始めたのがマネキンだ。人々の消費の媒介として、マネキンはもはや当たり前ものになった。さらに人形は性の相手にもなる。本展の最後にはなんとラブドールの展示まであった。あまり見る機会のない、等身大の女性と男装した女性の姿をした2体のラブドールを間近にし、意外にも洋服を着た外観が普通であることに拍子抜けした。しかしどこか虚ろな眼差しがラブドールらしさを物語っている。何らかの理由でこうしたラブドールを必要とする人がおり、彼らはラブドールに家族や恋人のような愛情を注ぐのだという。人の代わりとなってさまざまな場面で人を演じる人形は、いまも昔も、人にとって欠かせないものであり続けるのだろう。
 川路農美生産組合《伊那踊人形》(1920〜30年代)上田市立美術館蔵[撮影:齋梧伸一郎]
川路農美生産組合《伊那踊人形》(1920〜30年代)上田市立美術館蔵[撮影:齋梧伸一郎]
 高浜かの子《騎馬戦》(1940)国立工芸館蔵[撮影:アローアートワークス]
高浜かの子《騎馬戦》(1940)国立工芸館蔵[撮影:アローアートワークス]
公式サイト:https://shoto-museum.jp/exhibitions/200dolls/
※会期中、一部展示替えあり。
前期:2023年7月1日(土)~30日(日)
後期:2023年8月1日(火)~27日(日)
※18歳以下(高校生含む)の方は一部鑑賞不可。
2023/07/15(土)(杉江あこ)
伊奈英次 作品展「国の鎮め ─ヤスクニ─」

会期:2023/07/04~2023/07/30
JCIIフォトサロン[東京都]
伊奈英次は全国各地の天皇陵を撮影した写真集『Emperor of Japan』(Nazraeli Press)を2008年に、靖国神社に蠢く群像を中心にカメラを向けた『YASUKUNI』(Far East Publishing)を2015年に刊行している。彼自身、長く関心を寄せてきた日本の天皇制のあり方を、「形」と「中身」の両面から問い直す意欲作といえるだろう。今回のJCIIフォトサロンの個展では、後者の拡大版ともいえる写真群58点を展示していた。
東京・九段の靖国神社はかなり特異な空間といえる。「英霊」を祀ったその場所は、右翼、天皇制信奉者、軍装マニアなどの聖地であり、異様な熱気が渦巻いている。伊奈は「靖国戦友会」「昭和天皇崇敬会」「軍装会」といった集団の構成員、あるいは「元自衛官と軍歌歌手」「異議申し立てのパフォーマー」といった奇妙なバイアスがかかった人物たちにカメラを向ける。その視点は全面肯定でも、逆にネガティブな違和感を強く打ち出すものでもない。彼らの滑稽さ、グロテスクさを暴き立てることなく、まずはしっかりと受け止め、絶妙な距離感を保って視線を投げ返している。結果として本作は客観性と主観性とがせめぎ合った、希有な人間=集団ドキュメントとして成立した。
伊奈がこのシリーズを撮影した1993-2005年頃と比較すると、現在では靖国神社側の規制が強まり、旧日本軍兵士や軍装マニアのパレードのような行事も行なわれなくなっているという。その意味では、本作はバブル崩壊後の平成時代という、特定の時期の空気感を色濃く体現したシリーズともいえるだろう。現在ではプライヴァシー保護の問題などもあり、人間=集団ドキュメントそのものが、撮りにくくなってきている。本作のような、現代の「社会的人間」のあり方を、写真を通じて探求する試みをもっと見てみたいのだが。
公式サイト:https://www.jcii-cameramuseum.jp/photosalon/2023/05/22/33356/
関連レビュー
伊奈英次『YASUKUNI』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年10月15日号)
2023/07/16(日)(飯沢耕太郎)
大橋仁『はじめて あった』
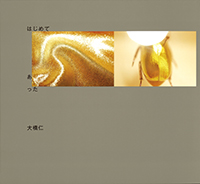
発行所:青幻舎
発行日:2023/04/10
デビュー作の『目のまえのつづき』(青幻舎、1999)から24年、「奇書」というべき大作『そこにすわろうとおもう』(赤々舎、2012)から10年余り、大橋仁の新作写真集『はじめて あった』が出た。
冒頭の波と空のカットから、いかにも彼らしい息継ぎの長いシークエンスの写真が続く。女性との性愛の場面、「パンティの森」と昆虫のクローズアップ、やがて母親と義理の父(『目のまえのつづき』の主要登場人物)が現われ、その生と死が、過去作も含めて綴られていく。さらに、渋滞中の車の中のドライバーたちを執拗に写したカットが続き、打ち寄せる波の写真で締めくくられる。
こうしてみると、大橋がいつでも「私は自分の中のはじめてに会いにいく」という姿勢を貫いて、被写体と接してきたことがよくわかる。「目のまえ」に走馬灯のようにあらわれては消えていく「私という幻私という現実」は、カメラを向けることによって、はじめて手応えのある確固たる存在としてかたちを成し、それらを連ねていくことで、確信を持ってそれらが「はじめて あった」と言い切ることができるようになる。そのような、彼自身の写真家としての基本姿勢を、大橋は本作を編むなかであらためて確認していったのではないだろうか。この「母の死とパンティと昆虫」の写真集には、なにかを吹っ切ったような、突き抜けた明るさが感じられる写真が並んでいた。
関連レビュー
大橋仁『そこにすわろうとおもう』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2013年01月15日号)
2023/07/19(水)(飯沢耕太郎)
お布団『ザ・キャラクタリスティックス/シンダー・オブ・プロメテウス』

会期:2023/07/18~2023/07/23
アトリエ春風舎[東京都]
人間の価値とは何か。そう問うとき、そこで想定されている価値とは誰にとってのものだろうか。あるいはそもそも、そこでいう価値とは何を意味しているのか。価値という言葉が金銭的なそれへと短絡されるとき、「人間の価値とは何か」と問うことは、それ自体がある種の罠として機能することになる。
お布団『ザ・キャラクタリスティックス/シンダー・オブ・プロメテウス』(作・演出:得地弘基)は、民間企業によって運営されるようになった国家・OEN(オリンポス経済ネットワーク)を舞台に、人間の価値と労働の意味を問う近未来SFだ。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
物語は、元犯罪者の社会復帰のための施設である社会再適応センターで働く「私」が、職場でのある死亡事故に疑問を持つところからはじまる。好奇心に任せて調べていくと、「P」と呼ばれるその患者はどうやら70年も前に収容され、100年以上生きていたらしい。そんなことがありえるのだろうか。そして過去の扉が開かれる。
やがてプロメテウス(大関愛)と呼ばれるその男は、戦争で荒廃した祖国を逃れてOENにやってきた移民だった。OENで働くことを希望していた男はしかし、入国管理局に長期にわたって収容されたことで心身を損ね、右手右足を失ってしまう。それでも弟を養うために働こうとする男はサイボーグ部隊に入隊。だが、男が海外に派兵されている間に弟は事故で亡くなり、部隊も男を残して全滅。生きる意味を失った男は「何もしたくない」と軍の施設に立てこもり──。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
男は文字通り「何もしたくない」のだが、そのような態度は「勤労」の義務を掲げるOENにおいては理解されず、社会の根本を揺るがす思想犯として逮捕・収監されてしまう。「何もしない」ことがテロと見なされる倒錯。だが、同じような労働拒否者はその後も増え続け、彼らの症状は「プロメテウス症候群」と呼ばれることになるだろう。「良くなれる機会に」を挨拶の言葉とするOENにおいて、彼らの存在は排除されるべきものでしかない。「思想犯」であるにもかかわらず脳に異常が見つからない「患者」たちは社会再適応センターでの「治療」を経て社会復帰させることもままならず、だからと言って簡単に処分するわけにもいかない。社会復帰さえすれば彼らは社会のなかで価値を生み出すはずだからだ。対応に苦慮した政府は、資本の集合意志とでも呼ぶべき《お言葉》にお伺いを立てる。もたらされたのは、脳だけの姿となった人間から金銭的価値を生み出し続ける錬金術だった。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
そうして人は、存在するだけで金銭的価値を生み出し続ける永久機関と成り果てる。その姿はまさにプロメテウスの名にふさわしい。山の頂きに磔にされ、3万年ものあいだ大鷲に内臓を啄まれ続ける不死の男。永遠の搾取。だが、それは同時に労働の無価値化を、労働からの解放をも意味するだろう。だから、物語の結末において、毎日が祝日へと塗り替えられてしまうのは必然なのだ。毎日が勤労感謝の日となったとき、感謝の対象であるはずの勤労は消滅する運命にある。アイロニカルなパラドックスによって顕現するユートピアはディストピアと表裏一体だ。
もちろんこれはフィクションであり、しかもそれを支える論理は(「私」の言葉を借りれば)「何かがおかしい」。脳だけの人間から利益を生み出し続けることなどできるわけがないではないか。そのおかしさの一部は、人間がすべき意志決定を《お言葉》という人間の外部の審級に委ねてしまったことに由来するものだ(たとえばアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』のシビュラシステムや『魔法少女まどか☆マギカ』のキュゥべえを思い出すとよい)。だが、「何かがおかしい」のは現実も同じだろう。綻び矛盾を露わにしながら、それでも信仰を集めるフィクションが社会のありようを定めている。現在の資本主義社会、あるいはその根底をなす貨幣システムもまた私たちの信仰によって成り立っていることは言うまでもない。
 [撮影:三浦雨林]
[撮影:三浦雨林]
さて、本作はいずれ戯曲の販売も予定しているという。ここには書ききれなかった膨大かつ複雑な設定と錯綜した筋の全体像は是非とも戯曲で確認してほしい。「金々の嘆き」「失われた『バリュー』に黙とうを捧げましょう」など連発されるパンチラインも見どころだ。
そういえば、この物語もまた、俳優の一人ひとりが同一の「私」というフィクションをその身に引き受けるところからはじまったのだった。
お布団:https://offton.wixsite.com/offton
お布団Twitter:https://twitter.com/engeki_offton
関連レビュー
お布団 CCS/SC 1st Expansion『夜を治める者《ナイトドミナント》』|山崎健太:artscapeレビュー(2022年03月01日号)
2023/07/19(水)(山﨑健太)
プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023

会期:2023/09/30~2023/10/22
ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市京セラ美術館 ほか[京都府]
14回目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023(以下KEX)。コロナ禍の制限が緩和され、海外アーティストの招聘が2年ぶりに可能となった昨年に続き、今年もタイ、韓国、ブラジル、オーストラリア、カナダなど国内外の実験的な作品が上演プログラムに並ぶ。KEX 2021 AUTUMNの「もしもし? !」、KEX 2022の「ニューてくてく」に引き続き、肩肘を張らずに身体を通して思考を広げるようなキーワードとして、今年は「まぜまぜ」を設定。「国内外でさまざまな分断や二項対立的な思考が顕著になってきた現在において、変化や交わることを積極的に取り入れ、可変性や流動性、複数性を思考の軸のひとつとしていくことを提案するキーワード」という(開催趣旨より抜粋)。
上演プログラム「Shows」には、アイデンティティを流動的で可変的なものと捉え、「言語」「文化」の純粋性を「第二言語の使用」「文化の混淆」から問う作品、ダンスという身体言語の継承について問う作品、文化的・社会的アイデンティティを構築・解体する力学について問うような作品が並ぶ。
チェルフィッチュは、日本語を母語としない俳優とともにつくり上げる新作を発表。2021年から、演劇における日本語の可能性をひらくことを目指し、ノン・ネイティブ日本語話者とのワークショップを進めてきた。「発音や文法の正しさ」という基準が排除や不可視化につながる構造は、日本の演劇のみならず、社会批評としての面ももつといえる。
韓国を拠点にシンガーソングライターや文筆家として活動するイ・ランは、在日コリアンが多く住む歴史を持ち、近年は再開発が進む京都の東九条を舞台に、観客が現地に赴いて「テキストを読む声」を聴くオーディオ・パフォーマンスを発表する。KEX 2021 AUTUMNで実験的に行なわれ、アーティストが執筆した架空のパフォーマンスを市街各地で音声で体験するプログラム「Moshimoshi City」の発展版といえる。

イ・ラン[© Lang Lee]
タイの気鋭の演出家、ウィチャヤ・アータマートは、姉弟が集う「父の命日」を複数の「タイ現代史の歴史的日付」と重ね合わせることで、個人と政治の関係や父権的国家制度を問う演劇作品『父の歌(5 月の 3 日間)』をKEX 2021 SPRINGにて映像配信した。政治的出来事の日付や検閲回避のメタファーとしてさまざまな小道具を駆使するアータマートだが、その演出手法は日付や小道具を、演劇表現を通して抑圧してきたのではないかという自省が、新作の出発点になっている。俳優は出演せず、これまでの自作に登場した小道具の役割を辿りながら、「演出家」という自らの権威性を省みるという。「神格化された絶対的権威」としての演出家に対するメタ批評をタイ近現代史や王室プロパガンダと重ね合わせていく手法は、KEX 2022で上演された、同じくタイの演出家ジャールナン・パンタチャートの『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』でも際立っており、不安定で過酷な社会状況に対する演劇の応答という点でも注目したい。

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre[© Rueangrith Suntisuk]
また、知的障害のある俳優を中心に、インクルーシブシアターの先駆けとして 30年以上にわたり活動する、オーストラリアの現代演劇カンパニー、バック・トゥ・バック・シアターが関西に初登場する。「障害のある活動家たちがコミュニティの民主主義的な運営について話し合う」という劇の構造によって、「正しさとは何か」という問いを突きつける。 メディアアーティストの山内祥太は、嗅覚アーティストのマキ・ウエダと協働し、「匂い」を体験する舞台作品を発表する。ステージ上には人間の体臭を抽出する蒸留機が置かれ、登場人物が愛する人や対象の「匂い」を追求し、それに身を浸すことで、理性と動物性、他者との境界が混じり合っていく。

山内祥太&マキ・ウエダ[© Shota Yamauchi]
香港を拠点とするサウンド・アーティスト、サムソン・ヤンは、中国の代表的な民謡「Molihua(茉莉花)」が清朝の時代に大英帝国を経てヨーロッパに伝わり、アレンジされたものが中国に「再輸入」されたという経緯をリサーチし、インスタレーションとして発表する。
一方、ダンスという身体言語の継承について問うのが、中間アヤカと、ルース・チャイルズ&ルシンダ・チャイルズ。中間は、関西ダンス史における伝説を知る人々への聞き取りやリサーチを基に、展示やパフォーマンスとして再構築し、京都市内の空き地に仮設される「劇場」で発表する。5日間を通して公開リハーサルを行なうとともに、「劇場のレパートリー」として中間自身のソロパフォーマンスも毎晩上演し、最終日に新作ソロダンスを発表。「変容し続ける踊りの場」を仮設的に都市の中に出現させることで、「もうひとつのダンスの伝説」をもくろむ。
ルース・チャイルズは、自身の叔母であり、アメリカのポストモダンダンスの振付家ルシンダ・チャイルズが1970年代に創作した 4つのパフォーマンスを現代に継承する。70年代以降さほど上演されなかった作品のラディカリズムを、「非劇場での上演」という要素も引き継いで美術館で上演し、「ダンスの上演場所」とともに歴史の継承を試みる。

ルース・チャイルズ&ルシンダ・チャイルズ[© Mehdi Benkler]
このほか、アリス・リポル/ Cia. REC(ブラジル、ダンス)、デイナ・ミシェル(カナダ、パフォーマンス)、マリアーノ・ペンソッティ/ Grupo Marea(アルゼンチン、演劇)も参加。また、関西のローカルな地域性をアーティストの視点からリサーチするプログラム「Kansai Studies」には、今村達紀、谷竜一、野咲タラ、迎英里子、山田淳也が参加。上演と関連したトークやワークショップ、上映会などのプログラム「Super Knowledge for the Future[SKF]」にも多彩なラインナップが並ぶ。

アリス・リポル/Cia. REC[© Christopher Mavric]
一方、コロナ禍、国際情勢、京都市の行財政改革、渡航費の高騰、円安の影響を受け、フェスティバルの経済状況は依然厳しい。今年からは、寄付を継続的な運営の柱のひとつとし、「KEX サポーター」をスタートする。KEXの立ち上げから10回目までのディレクターを務めた橋本裕介は、『芸術を誰が支えるのか アメリカ文化政策の生態系』(京都芸術大学 舞台芸術研究センター編、2023)を刊行し、アメリカの芸術団体、助成団体、中間支援組織の関係者へのインタビューを通して、「支援する/される」という一方通行ではなく、相互補完的で循環的な文化支援のあり方について紹介・提言している。その根底にあるのは、アートも社会を形成する基盤のひとつであるという認識である。
少子化と税収減が進むなか、文化支援に充てられる公的資金の先細りは続くだろう。「KEX サポーター」の導入は、芸術祭自体の存在意義への支持を呼びかけるものであり、個人や企業が「寄付」という形で直接的に意思を示す機会である点で、「文化の支え手」の認識を社会的に醸成する側面もあるといえる。
公式サイト:https://kyoto-ex.jp/
関連記事
寄付募集:【KEXサポーター】京都国際舞台芸術祭の活動を存続/発展させる:アートフラッシュニュース(2023年07月25日)
KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年12月15日号)
2023/07/20(木)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)