artscapeレビュー
星野太のレビュー/プレビュー
Boyan Manchev『Clouds. Philosophy of the Free Body』
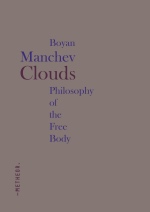
発行所:Metheor
発売日:2019/09
ソフィアおよびベルリンを拠点とする哲学者ボヤン・マンチェフは、2年前、母語であるブルガリア語で新著『雲』を上梓した★1。過去に英語、フランス語、イタリア語をはじめとする複数の言語で著されてきた哲学的散文とは打って変わって、同書は全体にわたり断片的な、ほとんど詩的と言ってもよいテクストによって構成されている。「雲とは……である」というセンテンスの執拗な反復に貫かれたこの書物では、ボードレール、ブレイク、シェリーをはじめとするわずかな例外を除けば、明示的に第三者のテクストが引用されることもない。そのスタイルは、ジョルジュ・バタイユの思想を主要な導きの糸とする『世界の変容──ラディカルな美学のために』(Éditions Lignes, 2009)や、ドストエフスキー、アルトー、ブランショらの作品をつねに傍らにおいた『変身と瞬間──生の脱組織化』(La Phocide, 2009)といった旧著(いずれもフランス語)のそれとは際立って対照的である。
筆者がマンチェフ本人から『雲』の話を聞いたのは、彼がドラマトゥルクとして関わる「メテオール」という集団が、新たに同名の出版レーベルを立ち上げたときのことだった。アニ・ヴァセヴァ(演出家、アーティスト)、レオニード・ヨフチェフ(俳優)、ボヤン・マンチェフ(哲学者、ドラマトゥルク)の3名を中心とするメテオールの舞台作品は、すでにブルガリア国内で高い評価を獲得し、その次のステップとして、同名の叢書の設立を計画しているところだった。それからわずか2年ほどのあいだに、メテオール叢書から刊行されたブルガリア語の書籍はすでに8冊におよぶ★2。そして、同叢書から刊行される9冊目の書物にして、はじめての英語の書物となるのが、ボヤン・マンチェフによる『雲』の英訳(本書)である。
はじめにも述べたように、本書は「雲」にまつわるいくぶん詩的なテクストである。同書の「プロレゴメナ」(序文)によれば、雲についての書物は、同時にそれ自体が雲のような書物でなければならない。著者の言い方に倣えば、「雲についての書物(book on clouds)」は、同時に「雲の書物(book of clouds)」にして、「雲のなかの書物(book in clouds)」でもなければならない(p. 15)。要するに本書がめざすのは、雲をめぐる抽象的な思索それ自体を、雲の形象へと接近させることである。これも著者が述べていることだが、「新たな哲学」は「新たな形式」の発明と不可分である(p. 16)。複数の文体を矢継ぎ早に切り替えていく『雲』の叙述形式もまた、まさしくそうした「新たな形式」を生み出すために選ばれたものにほかならない。
形式面だけでなく、内容面でもひとつ、本書の読みどころを紹介しておきたい。本書でもっとも特権的な人物として扱われるのは、哲学者でも文学者でもなく、ロンドン生まれの科学者ルーク・ハワード(1772-1864)である。もともと気象学には門外漢でありながら、若い頃から雲におおいに魅せられていたこのイギリス人は、のちに今日までつづく雲の分類の基本形を作り上げたことで知られる。かのゲーテとも交流のあったハワードによる雲の研究を、本書は──いささか驚くべきことに──カントの『判断力批判』(1790)とともに読むことを提案する。
なるほど、1783年に起こったアイスランドの大噴火が象徴的に示すように、雲はカントが同書で「崇高」と呼んだ自然現象と容易に結びつくものである。しかし、それはまだ物事の一面にすぎない。天空のいたるところで集合・離散を続け、そのたびごとに姿を変える雲は、噴火や雷鳴といった「崇高な」自然の象徴である以前に、私たちの思考を刺激する「形」をともなった「不定形な」現象の最たるものである(ここで著者はカントとともに、バタイユの名にも抜かりなく言及している)。そしてそれを、カントが「美的理念」と呼んだもの、すなわちいかなる概念もなしに、しかし思考を大いに刺激する理念に結びつけるのだ(p. 78)。そのような理念を産出する、「概念−以前のマグマ」としての雲(p. 80)──著者マンチェフが雲のうちに見いだすのは、「美」や「崇高」の手前に位置する、そうした感覚と理念の媒介のアナロジーなのである。
★1──同年にソフィアとプロヴディフの二都市で行なわれた『雲』のリーディング公演については、次の拙文のなかで詳述したことがある。星野太「アペイロンと海賊──『雲』をめぐる断章」、小林康夫編『午前四時のブルー』第1号、水声社、2018年。
★2──http://desorganisation.org/index.php/en/
2019/10/07(月)(星野太)
中村稔『回想の伊達得夫』

発行所:青土社
発売日:2019/07/01
詩人・中村稔(1927-)による、伊達得夫をめぐる回想録。伊達といえば、書肆ユリイカの創業者にして、のちに戦後を代表することになる若き詩人たちを世に送り出してきた伝説的な編集者である。あまり知られていないことかもしれないが、現在青土社から刊行されている雑誌『ユリイカ』は、伊達の死後に清水康雄が故人の遺志を継いで──伊達のそれと同名の雑誌として──創刊したものだ。中村稔は大作『私の昭和史』(青土社)でも伊達得夫の回想に少なくない頁を割いているが、その後『ユリイカ』に書き継がれた「私が出会った人々」でも、伊達については例外的に連載3回分が割かれている。本書の前半(第一部)にはそれら既発表原稿に加え、伊達の生前は詳らかにされることのなかった稲垣足穂との交流を追ったエセーが収められている。また本書の後半(第二部)では、伊達の生い立ちや高校・大学時代の活動をめぐる貴重な伝記的事実が明らかにされている。
伊達得夫という編集者の仕事ぶりについては、長谷川郁夫『われ発見せり──書肆ユリイカ・伊達得夫』(書肆山田、1992)や、田中栞『書肆ユリイカの本』(青土社、2009)をはじめとする先行する書物に詳しい。また、生前に伊達が書き残したものについては、『詩人たち──ユリイカ抄』(平凡社ライブラリー、2005)が幸いにして現在でも入手できる。それでもなお本書が興味深いのは、これが中村稔という詩人・弁護士の目を通した、戦後詩のある側面を伝える貴重なドキュメントになっているからだろう。著者は、あるときは刊行物の奥付や検印を手がかりに、原口統三『二十歳のエチュード』をはじめとする作品の刊行経緯をごく客観的な手法により問い詰める。いっぽう、著者の知る伊達の人柄を捉え損ねていると見える記述に対しては、ごく主観的な断言をもってこれを否定することも少なくない。本書は伊達得夫の生涯を追った包括的な伝記でもなければ、書肆ユリイカという出版社についての網羅的な研究書でもない。終始、脱線や連想を恐れない自由なスタイルで書かれた本書は、表題が示すように「回想」と形容するほかないものだろう。まるですべてを所定の型にはめていくかのような昨今の風潮のなかで、こうした自由な書物に出会えることは、おそらくそれなりに稀有な幸運であるように思われる。
2019/07/22(月)(星野太)
ウィリアム・マルクス『文学との訣別──近代文学はいかにして死んだのか』

訳者:塚本昌則
発行所:水声社
発売日:2019/03/20
ここのところ、ウィリアム・マルクス(1966-)の著作の刊行が続いている。具体的には、一昨年の『文人伝』(本田貴久訳、水声社、2017)を皮切りに、今年に入ってからは本書『文学との訣別』と『オイディプスの墓』(森本淳生訳、水声社、2019)の2冊が立て続けに翻訳・刊行された(さらに付け加えるなら、同じ版元から昨年刊行された三浦信孝・塚本昌則編『ヴァレリーにおける詩と芸術』にもこの人物のヴァレリー論が収録されている)。今年4月にコレージュ・ド・フランス教授に選出されたこの比較文学者の書物が、こうして立て続けに日本語で読めるようになったことをまずは喜びたい。
本書『文学との訣別』は、近代ヨーロッパで生じた「文学」の拡張・自律・凋落の過程を、数々のエピソードとともにたどった魅力的な書物である。著者は、文学を同時代の社会状況に還元する単純な社会反映論からも、同じくその不変性を無自覚に措定する文学論からも等しく距離を取り、「文学」がこの間に被ってきた変遷をあくまでも具体的な場面に即して跡づける。18世紀末のヴォルテールの凱旋を象徴的な始まりとする文学への崇拝は、19世紀における大衆からの断絶を経て、20世紀に急速な価値の下落をみるに至った──おそらくこうしたストーリー自体は、さして新味のあるものではない。しかし、本書の何よりの美点は、文学の「自律性の獲得」(第3章)や「形式への埋没」(第4章)といった各場面を、さまざまな作家を例に綴っていく明晰かつ魅力的な文体にこそあるだろう。近代の文学史、ひいては芸術史の流れをあらためて振り返りたいと考える読者にとって、おそらく本書は最適な書物のひとつである。
2019/07/22(月)(星野太)
ミヤギフトシ『ディスタント』

発行所:河出書房新社
発売日:2019/04/20
現代美術家・ミヤギフトシ(1981-)の「デビュー作」と銘打たれた本書には、ミヤギが2017年より雑誌『文藝』に発表してきた「アメリカの風景」「暗闇を見る」「ストレンジャー」という三篇の小説が収録されている。それぞれの語りの視点こそ異なるが、その中心にいるのは、沖縄に生まれ、大阪の専門学校を経て、ニューヨークの大学で写真を学ぶ若きアーティスト志望の男性だ。これまでのミヤギの作品、とりわけ「American Boyfriend」というシリーズに触れたことがある者にとって、これらがいわゆる「私小説」のたぐいであることは一読して明らかだろう。
美術家による小説作品、というのは過去にも例がないわけではない。古くは「尾辻克彦」のペンネームで芥川賞を受賞した赤瀬川原平のような例もあれば、近いところでは『この星の絵の具』という三部作の自伝小説を刊行中の小林正人のような例もある。しかし、ミヤギフトシという作家にかぎって言えば、ここ数年の小説への進出はなかば必然的な流れであったのではないか、と思わせるところがある。というのも、ミヤギがこれまで発表してきた作品は、《The Ocean View Resort》(2013)や《花の名前》(2015)のような映像作品であれ、《Bodies of Water》(2014)や《How Many Nights》(2017)のようなインスタレーションであれ、映像・音楽・写真・オブジェ等の組み合わせにより立ち上がる、詩情あふれる物語性をつねに伴っていたからだ。
しかしそれゆえに、と言うべきか、本書を「現代美術家による小説作品」と形容することには一種のためらいもある。というのも、すでにみずからの青春の記憶を「American Boyfriend」というシリーズに託してきたこの作家の小説を、いわゆる通常の「私小説」と同一視することは不適切であるように思われるからだ。
本書『ディスタント』に収められた三作品は、さきにも触れたような語り手や一人称の変化をはじめ、隅々まで周到に書かれた見事な小説だ。しかしそのような印象のいくばくかは、作者自身の個人的な遍歴や、過去に公にされてきたこの作家の仕事を知っていることに由来しているのかもしれない(少なくとも本書が、美術家としてのミヤギフトシの作品をなかば前提としていることは明らかであるように思われる)。だとするなら、この小説はミヤギの「American Boyfriend」というプロジェクトの一部をなしていると考えるほうが、おそらく適切だろう。少なくとも筆者はこの小説を、映像作品、インスタレーション、トークイベントをはじめとする複数の形態を取ってきた、同シリーズの新たなる一歩として受け取った。先述のように、美術家が小説家として筆を執ること自体は過去にも例がないわけではない。だが、もともと現実と虚構のあわいを行くような作品を手がけてきたこの作家を知る者にとって、本書の占める位置はきわめて複雑なものとならざるをえない。率直に読めば、この物語はミヤギフトシが東京で美術家としての活動を始めるまでの、いわば前史に相当する。しかしそれは、いったいどこまでが「本当のこと」なのか──。いずれにせよ、これまでの「私小説的な」作品の上に重ねられたこの「私小説」の存在が、この作家が構築してきた作品世界をよりいっそう豊かなものにしていることは確かである。
2019/07/22(月)(星野太)
マルク・アリザール『犬たち』

訳者:西山雄二、八木悠允
発行所:法政大学出版局
発売日:2019/05/20
本書の著者マルク・アリザール(1975-)は、これまでポンピドゥー・センターやパレ・ド・トーキョーをはじめとする文化施設で、おもに現代美術に関連する仕事に従事してきた異色の哲学者である。ここ数年は本格的に執筆活動に転じ、『ポップ神学』(2015)、『天上の情報科学』(2017)、『クリプトコミュニズム』(2019)といったユニークな著書を立て続けに発表している(いずれも未邦訳)。とくに本書『犬たち』(2018)は、150頁ほどの小著でありながら、その主題の近づきやすさもあってか、フランス本国で大きな話題を呼んだ。後述するようにけっして易しい内容ではないものの、原書の売り上げは、哲学書としては異例の1万部に達したという。
そんな本書は、人間にとって犬という存在がいかに重要なものであるかを論じる、哲学的動物論である。本書を構成する各章では、クリフォード・シマックのSF小説『都市』や、フランツ・カフカの未完の短編「ある犬の探求」、ジル・ドゥルーズやダナ・ハラウェイによる犬をめぐる哲学的考察、さらにはディズニーの『わんわん物語』やエルジェの『タンタンの冒険』のような子供向けの作品までもが、次々と呼び出される(ちなみに本書には狛犬や忠犬ハチ公も登場する)。そればかりではない。はじめに見たこの著者の経歴から予想されるように、古典絵画(デューラー、ヴェロネーゼ、ベラスケス……)から現代美術(ジャコメッティ、ヘルマン・ニッチュ、ピエール・ユイグ……)に至るまで、芸術作品における犬の表象がふんだんに参照されていることも、本書の大きな特徴である。
著者アリザールの基本的な考えを要約するなら、ほかならぬ「犬」こそがわれわれ人間を作り出したのだ、ということになる。とりわけ、犬の人間に対する信仰が、人間の神に対する信仰と相同的であり、「犬、人間、神のあいだで互いに模倣し敵対し合う三角関係」こそ、「私たちが犬たちと結ぶ愛と憎しみの近代的な関係」の起源である、という一節などは印象的だ。より平たくいえば「神に愛されたいと望むように、私たちは犬を愛し始めた」のであり、一神教とともに「私たちは犬をもうひとりの自分として扱い始め」、それによって「幸福な愚か者という犬の近代的な形象が現れたのだ」(39-40頁)。
前出のハラウェイに代表されるように、犬が人間とともに進化してきた動物である、ということはこれまでにもしばしば言われてきた。アリザールもまたそれに同意するのだが、彼はそこから一歩すすんで、犬が人間の「誕生」に果たした役割を次のように言い表わしている。曰く「人間はある他の動物から進化した動物ではありえず、二つの動物のあいだでつくり出された関係の産物」にほかならない。そうだとするなら、「まさに
以上のような明快な立場とは裏腹に、本書の道程はけっしてなだらかではない。挙げられる事例の多さに比して、ごく圧縮された短い考察をテンポよく繰り出す本書の文体は、おそらくそれなりに読者を選ぶものであるように思われる(商業的な成功を収めた哲学書の常として、フランス語で書かれた本書のレビューのなかには、絶賛に混ざってそれなりの数の呪詛が見受けられる)。また、犬にまつわる挿話を世界の神話、宗教、文学から幅広く渉猟する本書の拡がりは、著者が犬の美徳として挙げる「頑固さ」と「繊細さ」を、読者に対してもただしく要求することになろう。その道行きを助けてくれるのが、本書のほぼ全頁に見える充実した訳註である。原著には図や註のたぐいはいっさい見当たらないが、その不便を補うべく、本書にはいたるところに適切な図版と側註が添えられている。それらを導きの糸として、著者が十分に掘り下げていない犬をめぐるさまざまなトポスを開拓するのも、本書の楽しみ方のひとつであるだろう。
2019/06/09(月)(星野太)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)