artscapeレビュー
高嶋慈のレビュー/プレビュー
須藤崇規『私は劇場』 week7

会期:2020/07/14~2020/07/17
パフォーミング・アーツを中心に記録映像を手がける映像ディレクター、須藤崇規によるオンラインパフォーマンス。5月25日より開始され、毎週複数回、YouTubeで生配信され、内容は毎回異なる。本評では、7週目の7月14日の配信内容を取り上げる。
黒画面に白い文字がリアルタイムで入力され、キーボードを打つ音や車の走行音などの環境音が聞こえてくる。本作の構造はいたってシンプルだ。だが、配信時刻が近づくと日付の下の現在時刻が1分ごとに入力/修正され、アーカイブは非公開という「リアルタイム」の重視、ラフなようで周到に計算された音響、「私からあなたへの語り」という親密性、そして思索的な文章と「文字」の入力/黙読/消去という行為そのものによって、「主体」の所在や交換、簒奪の暴力性について問いかける。それは、「演劇」のフィクショナルな仮構の基盤をメタ的に問いつつ、ディスプレイの「向こう側」とこちら、「いまここ」とアクチュアルな世界的出来事とを隔てる距離を再想像/架橋しながら、「劇場」を再定義し直す深い射程を備えていた。
冒頭、現在時刻の表示に続き、「私は文字です」という文言が入力される。この自己言及的な一文は、それをディスプレイ上で「あなた」が読むとき、入力する「私」と黙読する「あなた」とのあいだで、主体の入れ替えや曖昧化が起こっていることについての思索へと展開する。また、手紙(物質)とは異なり、メールの送信は「情報のやりとり」のようだが、実際は「コピーの送信=自己複製」であるとも述べられる。ここで、本作のタイトルおよび題字デザインにも注意を払う必要がある。日本語タイトルは「私は劇場」だが、それは反対側から読まれる鏡文字として裏返っており、さらに英語で表示されたタイトルは「The Theater is You」と、意図的な(私/Youという訳語および主語の)ズレをはらんでいる。この二重性とズレは極めて示唆的だ。「私」と「あなた」の交換可能性、「翻訳」がはらむ(言語に加え)発話主体の置換、鏡像と反転、透明なディスプレイを介して向き合う「こちら」と「向こう側」、その共有可能性とズレ。ここで、黒画面はすなわち劇場のブラックボックスの謂いであり、そこに浮かび上がる白い文字は「台詞」や「字幕」であるとすれば、本作の問題意識はまずもって、「演劇」と発話主体の問題を扱うことにあると言える。
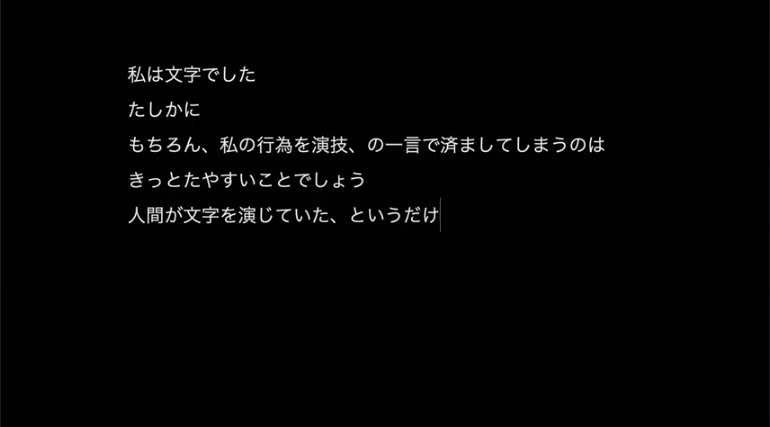
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
だが、こうした「遊戯(Play=演劇をめぐるメタ的思索)」ではいられない事態になってきたと、「文字」は告げ始める。「世界は文字であふれている」と述べたあと、話題は、香港で国家安全維持法が施行され、「香港独立!」という言葉がデモで使えず、白紙のプラカードを掲げる抗議に変わったことへと移る。この抗議について「私」が何か書けば、「配信」すなわちコピーの拡散を通じて「安全」ではなくなるかもしれないと、「私」は怯え、逡巡し、入力した文章を何度も修正し、口ごもる。いつの間にかキーボードの入力音も環境音も消え、無音が緊迫感を高める。カーソルが震えながら「今まで打ち込まれた入力画面」を辿り直し、もう一度書き出し部分に戻り、書かれた内容を「消去」する。
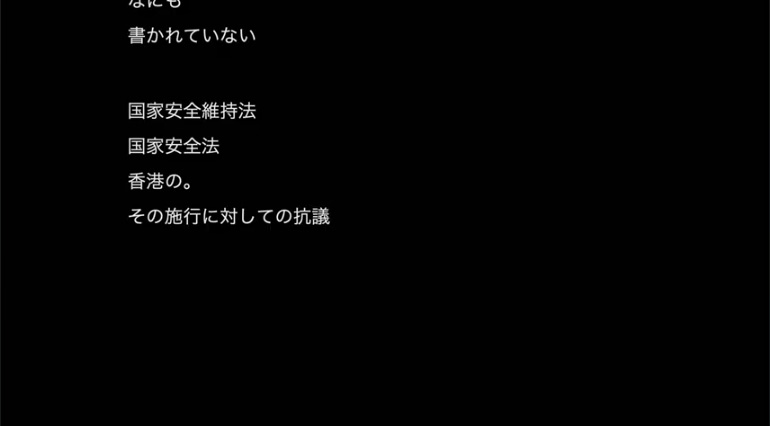
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
「消去」の暴力を自ら実行したあと、再び「こんばんは 私は文字です」という一文の入力が反復される。そして、この「暗いディスプレイ」が「私」と「あなた」の出会う場所であったこと、すなわち束の間でも「劇場」へと変容していたことが語られる。再び、キーボードの入力音と環境音が流れ始め、現実世界の手触りを取り戻していく。「もう知っているもの、すなわち過去に出会い直すためだけなら、あなたはもう劇場へは行かないだろう」「でも、劇場は、まだ知らないものに出会う場所です」。「ここが劇場」、すなわち「私」と「あなた」が共に立ち合い、出会う場所を「劇場」として希望的に肯定し、再定義しようという、ささやかだが高らかな宣言で締めくくられる。ノイズの音量が、祝福するように加速していく。
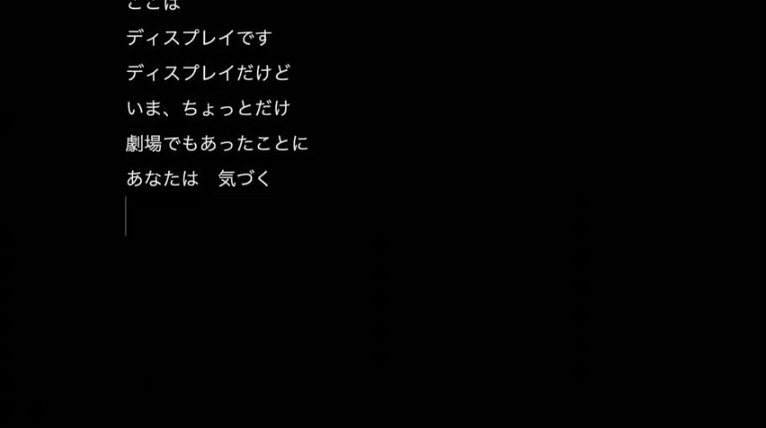
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
須藤によって「限界劇場 Marginal Theater を作る試み」と定義された本作は、「主体」の変換や転移という「演劇」の原理的要素に自己言及し、香港の白紙デモというアクチュアルな事態とその距離感をディスプレイを隔てた「私」と「あなた」のそれへと敷衍したのち、「劇場」の概念的拡張を試みる。「限界劇場」、すなわちミニマルに切り詰めた手法によって概念的・物理的限界の拡張を同時に推し進める、優れた試みだった。
題字:内田圭
公式サイト:http://sudoko.jp/theaterisyou/
関連レビュー
須藤崇規『私は劇場』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年06月15日号)
2020/07/14(火)(高嶋慈)
シアターコクーンライブ配信『プレイタイム』

会期:2020/07/12
シアターコクーン[東京都]
コロナ禍で約4ヶ月休館していた劇場、シアターコクーンの「再始動」プログラムとして企画された「ライブ配信のための演劇」。観客席も用意されているが、筆者は企画主旨のライブ配信を鑑賞した。照明・音響装置、オーケストラピットの昇降、裏方スタッフの労働など、劇場の物理的機構それ自体のオーガニックな運動を作品化する、梅田哲也の『インターンシップ』が原案。本企画では、演出家の杉原邦生を迎え、岸田國士の戯曲『恋愛恐怖病』(1926)を森山未來と黒木華が演じ、ダンサーの北尾亘(Baobab)やミュージシャンの角銅真実が加わった。
冒頭、懐中電灯の光が暗闇をまさぐり、無人の劇場バックヤードの機材が照らし出される。小さな星のような灯がポツポツと灯り、やがて眩いライトが強烈な光を投げかける。それは、休館の仮死状態の眠りから劇場を目覚めさせる、(疑似)太陽の光だ。低いモーター音のうねりとともに、歯車が回転し、規則正しく並んだロープが巻き上げられ、バトンに吊られた照明機材が上昇していく。それは、劇場の巨大な体内に張り巡らされた、血管、神経、内臓組織だ。カメラは、胎動の音とともに、巨大な体内のなかを迷路のように進んでいく。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
舞台袖の暗闇で、劇場の模型をライトで照らしながら眺めている男(森山未來)がいる。彼は台詞を発しながら、狭い通路や階段をライトで照らして探検のように進み、彼の台詞を引き取って続ける女の声に導かれるように、舞台の上へ姿を現わす。そこは、裏方スタッフが打楽器や木琴を運び込み、台本を持った女(黒木華)が歩き回っている、「準備中」の運動に満ちた空間だ。「南京豆が食いたくなった」「燈台に灯がつくまで、ここにいましょうね」「今日はなんだか重大な日だ。胸騒ぎがします」。台詞をリフレインさせ、台本の「読み合わせ」をする二人の周りを、モップ掛けするスタッフが行き交う。上昇と下降を繰り返す吊り照明から身をかわす男の動きはダンス的なムーブメントに接近し、一方その傍らでは、裏方スタッフの恰好をした別の男(北尾亘)がスポットライトのテストの下で回転している。無機的な機械音のノイズ、スタッフの業務連絡、マイクチェックなどの作業音が楽器のチューニングやハミングと交じり合い、ハーモニックに調和していく。ゆっくりと旋回するカメラは、薄暗い客席通路の階段を降りて座席につく観客の姿を映し出す。その反対側の、半透明の幕で遮られた舞台上では、「海面」を演出する青いシートがふわりと掛けられ、生き物のように呼吸する。チューニングの延長のような優しい音響が包み、夜明けを告げる鐘のような音が響き、深い霧笛を思わせる音が舞台上に「海」を目覚めさせる。「開演」、そして衣装を着替えた男と女は、海を見下ろす桟橋のような空中のブリッジに立ち、互いの恋愛観と結婚観を語るなかに恋の駆け引きとプライドが入り混じる会話劇が始まる。煮え切らない男を残して女は立ち去り、傷心の彼は、自己の分身のようなもう一人の男にモノローグを吐露し、シンクロしたダンスムーブメントを展開する。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
「演劇」が息づき始める空間を、映像ならではのカメラの運動性を活かして見る者を惹き込み、俳優・ダンサーを脱中心化し、光と影、さまざまな人や機材が交通する活性化された空間として捉え、フィクションの立ち上げをワンカットの「ドキュメンタリー」として撮る。ここで本作の賭け金は、梅田哲也の『インターンシップ』を原案として発展的に拡張させたことにある。劇場の物理的機構の運動や裏方スタッフの作業そのものを作品の素材として用いる『インターンシップ』のサイトスペシフィック性は、「どの劇場で上演しても『コンテンツ』は同じ」という同一性の担保を批評的に解体し、(国内ではKAATに次ぐ)新たな劇場での上演には意義がある。それは、「コロナ禍後の再始動」という面では成功した一方で、「上演批判・劇場批判という作品の本質的要素を、ドラマの充填によって上書きし、損ねてしまう」という両義的な結果となった。また後述するが、秀逸なカメラワーク(渡邉寿岳)は本作の特筆すべき点である一方、「オンライン配信」と「劇場での観劇」の両立は可能かという新たな課題を突き付けた。
私見では、『インターンシップ』のコアは、「舞台上に見るべきものは何もない」という表象批判・劇場批判をリテラルに遂行しつつ、劇場の物理的機構そのものを用いて圧倒的な感覚的体験の強度をつくり出した点にある。通常は不可視の劇場機構や裏方スタッフの作業という「日常」を見せたあと、俳優やダンサーが一切登場しない空っぽの舞台を、即興的なチューニングから不協和と美しさの併存した音響世界が満たし、光と影の交替劇が、夜と死を潜り抜けて再び朝と復活を迎える、壮大で抽象的なドラマなきドラマの非日常性を体感させる。だが本作では、中盤=「開演」以降、「『恋人』と『友達』の境界線をめぐる、男女の駆け引き」「女に翻弄される男」「恋に破れた男のナルシスティックな苦悩」というドラマの充填に取って替わられ、照明や音響の有機的な運動性は劇伴的に退行してしまった。また、岸田國士の戯曲の採用も、「生誕130周年」という祝祭性しかなく、戦前に書かれた戯曲と現代との時代差―「自由恋愛」の登場した大正期/既存の結婚観の残存とのジレンマや、潜在的なホモソーシャルな欲望は掘り下げられず、ファンタジックな演出のなかに曖昧に溶かされてしまう。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
また、「定点」も「全体を見渡せる一望」も放棄し、巨大な器官としての劇場空間に潜り込み、洞窟か迷路のような内部を探査し、生きもののように蠢く劇場を捉えるカメラの運動感や流動性は、『インターンシップ』における(ドラマという)中心の欠如と、舞台上を自由に歩き回りながら体感する観客の運動性や移動の自由さとリンクする。その一方で、時折カメラに映り込む「劇場で本作を鑑賞する観客」は、客席に身体を固定され、古典的なプロセニアム舞台との対面を余儀なくされており、身体性の縮減は『インターンシップ』(の発展的展開)の鑑賞体験としては不十分さが残る。感染症が完全に収束するまでは、本作のように、オンライン配信と劇場での上演の並行が(実験性としても収益の面からも)摸索されていくだろう。本作は、「オンラインのライブ配信」の試みとしては成功していたものの、「実際の劇場での鑑賞体験」とのバランスをどう取るか、という困難な課題を改めて浮き彫りにしていた。
なお本作は、7月31日~9月2日の期間、オンデマンド配信が予定されている。
公式サイト:https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/20_playtime/
関連記事
TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)
2020/07/12(日)(高嶋慈)
Disclosure トランスジェンダーとハリウッド:過去、現在、そして

「映画やテレビドラマなど映像メディアの1世紀にわたる歴史において、トランスジェンダーがいかに表象されてきたか」を批判的に検証するドキュメンタリー映画。2020年1月にサンダンス映画祭でのプレミア上映で高く評価され、6月19日よりNetflixでグローバル配信されている。ハリウッド映画を中心に、初期のモノクロサイレントフィルムから2010年代まで、膨大な映画やテレビ番組が引用され、トランスジェンダーの俳優、ライター、歴史家、プロデューサー、映画監督らが問題点を指摘し、出演作や個人的な経験について語る。本作を貫くのは、「なぜ、トランスジェンダーの役を非トランスの俳優が演じることが問題なのか?」という問いに対する多面的な回答の提示であり、横軸として人種差別問題も根深く絡んでいることが提起される(なお、歴史的背景として、アメリカでは異性装や同性愛が長く違法とされ、トランスジェンダーという言葉の普及は1990年代である)。
特に本作で中心的位置を占めるのが、黒人トランス女性の表象だ。「女装の黒人コメディアン」が繰り返しスクリーンに登場し、笑いのネタになり続けてきたのはなぜか。あるいは、性転換が起きる『フロリダ・エンチャントメント』(1914)で、「白人」女性は模範的な「紳士」になるのに対し、「黒人」男性は「粗暴なメイド」に変貌してしまうのはなぜか。そこには、「黒人男性=白人女性を脅かす危険な存在」というステレオタイプの前提があり、「女装=去勢」によって脅威を笑いの対象に転化しようとする構造があることが指摘される。また、「戯画化された女装者」は、女性蔑視のメッセージも暗に含む。
一方、「嘲笑」による無害化とは真逆のベクトルとして、「恐怖の対象」としての描写の系譜がある。例えば、『サイコ』(1960)などヒッチコックのサスペンスに登場する、「異性装の変質的な殺人者」や、『羊たちの沈黙』(1991)で殺害した女性の皮を剥いで身につけ、女性になろうとするシリアルキラー。また、「嘲笑」「恐怖」に加えて頻出するのが、「嫌悪すべき対象」として描かれる偏向である。「魅惑的な女性」の身体にペニスがあることを知って驚愕する男たちの、嘔吐シーンの数々。「暴露」は「裏切られた」と怒る男性の暴力を正当化し、スクリーン上でトランス女性たちは繰り返し殺害される。「生き延びるために性別移行したのに、『死』ばかり描かれる」とトランス女優が語る声は切実だ。
また、描写の職業的偏向も指摘される。黒人トランス女性の職業で最も多く描かれるのは、セックスワーカーだ。ただその根底にある、雇用差別と人種差別について説明されないことが真の問題なのである。
こうしたトランスジェンダーの偏った描写がステレオタイプと差別を再生産してきたこと、特に人種差別と結びついたときにより強力に作用してきた一方、史実や実話の映画化において、有色人種の「排除」「消去」「不可視化」が同時に行なわれてきたことが指摘される。例えば、1969年にニューヨークのゲイバーで起こり、セクシュアル・マイノリティの権利獲得運動の大きな契機となった「ストーンウォールの反乱」を描いた『ストーンウォール』(2015)では、有色人種のトランスジェンダーやドラァグクイーンが白人男性俳優によって演じられ、白人の歴史化(ホワイトウォッシング)であると批判される。また、主人公のトランス男性が殺害される『ボーイズ・ドント・クライ』(1999)では、彼の友人で一緒に殺された黒人男性が登場せず、「消去」されている。トランスフォビアと人種差別の強固な結びつきを「隠蔽」しようとする作用の暗示的な例として解釈可能だ。
こうした他者による一方的な表象と記号化は、非トランスのシスジェンダーとトランスジェンダーの双方に対して弊害しかもたらさない。前者に対しては、メディアが歪曲されたステレオタイプを再生産し、嘲笑、恐怖、嫌悪の対象として偏見や暴力を正当化する。一方、当事者にとっては、共感・尊敬すべき人物として肯定的に描かれないことで、深く傷つき、「私の物語」として受容できず、攻撃される恐怖と自己嫌悪に苦しむことになる。
ここで傾聴すべきは、「過去から学び、もっとトランスジェンダーについて描き、情報源を増やすことが重要」「個人として尊重して描くことで、人間性を理解し支えてくれる人が増える」という意見である。本作の後半では、2010年代以降、トランスジェンダーであることを公表した俳優たちが、トランス役として出演した作品が紹介される(黒人トランス女優ラヴァーン・コックスが美容師役を演じたドラマ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』[2013]、80年代のアフリカ系・ラテン系のLGBTQコミュニティのカルチャーを描く『POSE』[2018]など)。
従って、原題の「Disclosure」に込められた複数の意味に留意すべきだろう。それは、トランスジェンダーがスクリーン上で繰り返し「本当は男/女だ」と「暴露」される痛み、映画がその暴力の再生産に加担してきた歴史の「暴露」、そしてトランスジェンダー俳優たちのメディアへの「公表」「自己開示」によるエンパワメントでもある。他者による一方的で偏向した表象を自らの手に取り戻し、自分たち自身の生と性の肯定を通して、「いない」ことにされてきたスクリーンの向こうの当事者たちにエンパワメントを与えること。
ただ、課題も残されている。一部のセレブリティが「代表」と見なされることや、同じトランスジェンダーというカテゴリーであっても、トランス女性とトランス男性における可視化の偏向だ。トランス女性(とりわけ華やかなスター)は可視化されやすいが、ゲイと思われることを恐れる男性からの暴力や、(トランスを含む)女性の身体の商品化につながる可能性が指摘される(日本での顕著な例は、「女性専用空間」からのトランス女性の排斥がある)。一方、「より目立たない」トランス男性のメディアへの登場は少なく、「いない」ことにされてしまう。また、性自認を男女のどちらにも規定しない「ノンバイナリー」は、「登場」し始めたばかりだ。
最後に、本作を見ることで、「逆に、トランスジェンダーの俳優は、トランスジェンダーの役しかできないことになるのでは」という疑問に対しては、原理主義的主張ではなく、これまで奪われてきた機会の回復がまずなされるべきだと答えることができる。「居場所がないと、存在できない」からだ。その上で本作は最後に、「表現自体が目標ではなく、社会全体を変革する手段にすぎない」と締めくくる。
本作の問題提起の射程は、エスニックマイノリティや障害者など、さまざまなマイノリティの表象の問題とも通底する。そこで重要なのは、本作が示すように、単一の側面だけを見ていては、差別構造の本質を見逃すということだ。人種差別、性差別、ホモフォビアなど、問題の根は複雑に絡まり合っているのであり、「繰り返し語られる物語表象」において何が歪曲され、その背後で何が排除・隠蔽されているのかを問い続けること。同時に、本作で語られるように、「自分の特権を認識する」態度である。
2020/07/11(土)(高嶋慈)
京芸 transmit program 2020

会期:2020/04/04~2020/07/26
京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]
京都市立芸術大学卒業・大学院修了3年以内の若手作家を紹介するシリーズ、「京芸 transmit program」。今年度の4名は、「身体性」と「美術史への参照」の二軸で構成されている。
西久松友花は、兜や陣羽織、花魁のかんざし、銅鐸などの祭具、しめ縄や民俗的な神具といった土着的な「装飾」「意匠」を抽出して組み合わせた陶のオブジェを制作している。鮮やかな赤、金銀彩やスワロフスキークリスタルが施され、祝祭的な「ハレ」の雰囲気をまとうなかに、性(生殖)や死に対する祈りと畏怖の感情が顔をのぞかせる。

西久松友花《虚飾》[写真:来田猛 提供:京都市立芸術大学
]
「身体性」と「美術史への参照」の交差する地点にいるのが、菊池和晃だ。菊池はこれまで、筋肉やメンタルの強さを鍛える「トレーニングマシン」兼「描画装置」を自作し、自身の肉体を酷使する行為によって、ポロックや篠原有司男、李禹煥を思わせる「抽象絵画」を制作するパフォーマンスを行なってきた。過去作品《アクション》では、パンチングマシンに両脇を挟まれ、絵具の付いたボクシンググローブに殴られ、飛沫を血のように浴びながら、自らもボクシンググローブで殴り返す/キャンバスに描画していく。篠原有司男の「ボクシング・ペインティング」を思わせる制作方法によって、ポロック風のドリッピング絵画が出来上がる。また、《Muscle》では、スクワットを繰り返すことで、反対側にハケの付いた装置がシーソーのように上下運動し、李禹煥ばりのモノクロームのミニマルな絵画を大量生産する。美術史的規範としての絵画を、泥臭い身体の酷使によってナンセンスに脱構築する試みだと言えるが、「筋トレ」すなわちマッチョな肉体改造への願望は、美術史における男性中心主義やマッチョイズムを文字通り再生産してしまう危うさも秘めている。出品作《円を描く》は、歯車を組み合わせた装置のハンドルを6250回、手動で回すことで、吉原治良を思わせる「黒地に白い円」を描くものだ。今作ではマッチョさは後退し、制作行為を機械的な「労働」に還元するシニカルさのなかに、徒労に近い肉体労働としての制作行為を浮かび上がらせる。

菊池和晃《円を描く》[写真:来田猛 提供:京都市立芸術大学
]
一方、パフォーマンスとその儀式性によって「生と死」に言及するのが、小嶋晶と宮木亜菜。小嶋は、自身の母親の心臓が弱り、洞結節からの電気信号が心房心室にうまく伝わらず、意識を失うほどの徐脈になったため、心臓が元通り動くよう、「生を実感できない」というダンサーに「母親の心筋になる」ことを依頼した。パフォーマンスの記録映像では、電気コードを握りしめて洞結節からの電気刺激を受け取り、小嶋の母親の心臓と疑似的につながった男性ダンサーが、規則的な電子音と光の明滅のなか、激しくのたうち回る。それは他者の痛みを疑似的に引き受ける祈祷的行為であると同時に、ダンサー自身が踊りの根源としての生の充溢に到達しようとするもがき苦しみでもある。

小嶋晶《bpm60》より [写真:来田猛 提供:京都市立芸術大学
]
また、宮木亜菜は、展示会場にベッド、マットレス、布団、カーペット、ハンガーラックを組み合わせて設置し、「睡眠」のパフォーマンスを毎週行なった。展示された記録写真を見ると、パフォーマンスのたびにベッドや寝具の配置が大胆に変えられていく。布団で覆われた顔の見えない頭部や布団から突き出した両脚の写真は「遺体」を思わせ、眠りと死の連続性を想起させるが、「眠り」と覚醒のたびにインスタレーションは日々の新陳代謝のように生成変化し、床を這ったり垂れ下がる布団は巨大な内臓のようだ。

宮木亜菜《眠りのあきらめ》[写真:来田猛 提供:京都市立芸術大学
]
生産物としての「作品」の裏側にある肉体の酷使、「死」を通して生の充溢に触れ、生と死の(不)連続性を行き来すること。そのような本展の流れの中で再び西久松の作品を振り返ると、身体や衣服の表面を彩る装飾的モチーフが散りばめられた陶製のオブジェたちは、「不在の身体」として佇み始める。
2020/06/25(木)(高嶋慈)
渡辺真也『ユーラシアを探して──ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイク』

発行所:三元社
発行日:2020/01/21
ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイク。異なる出自や作風の二人が、1961年に西ドイツのデュッセルドルフの画廊で出会い、フルクサスへの参加を契機に生涯にわたって展開したコラボレーションを、ボイスの「ユーラシア」構想を軸に読み解こうとする研究書。ヨーロッパとアジアをひとつの大陸として接合させるボイスの「ユーラシア」について、「ヨーロッパとアジア、西と東、または二つの対立するものを一つに結びつけるための抽象的かつアーキタイプ的なメタファー」(12頁)と著者は述べる。
本書は、二人の生い立ちにも紙幅を割き、「ユーラシア」に関連するボイスの作品やアクションを年代順に辿りながら、パイクのソロ作品やパイクとのコラボレーションを間に挟んでいく。本書で紹介される「コラボレーション」は、パイクのプリペアド・ピアノを(予告せずに)ボイスが斧で破壊した《ピアノ・アクション》(1963)に始まり、フルクサスのイベントでそれぞれが発表したパフォーマンス、ボイスが制作した《チェロのための等質湿潤(通称フェルト・チェロ)》がパイクのビデオアート作品《ガダルカナル鎮魂曲》に登場したこと、1977年のドクメンタ6でパイク(シャーロット・モーマンとの共演)、ボイス(社会彫刻についてのスピーチ)、そしてダグラス・デイヴィスの3人が各自のプログラムをライブ衛星放送で中継した《サテライト・テレキャスト》、ジョージ・マチューナス追悼コンサートにおける「ピアノデュエット」とその派生物、そして東京の草月ホールで1984年に開催され、最後のコラボレーションとなった、パイクの即興ピアノとボイスによる《コヨーテⅢ》のボイスパフォーマンスと多岐に渡る。
本文450頁以上にのぼる大部の著作であり、想像上の境界や分断を超えていくものとして二人のアーティストの協働に光を当てる試みの意義は大きい。ただ、実証性よりも連想を重視した叙述は、「ユーラシア」の混沌とした神話的世界像を紡ぎ出す一方で、連想の糸に拡散してしまう恣意性の危うさを感じる。また、ボイスの生まれ育ったクレーヴェがキリスト教化以前のケルトの影響が色濃く残る神話と伝説の地であること、少年期にヒトラー・ユーゲントに所属し、第二次大戦中に搭乗した戦闘機がクリミア半島で墜落し、タタール人の手当を受けて瀕死の重傷から回復したこと(「アジア」と遊牧民との出会い)、同僚のパイロットの死のトラウマといった自伝的要素に強く依拠した作品解釈にも、疑問が残る(パイクについても同様に、日本統治下のソウルで財閥企業家の息子として生まれ、父親が日本の植民地支配に協力していた証拠の隠蔽や武器貿易への関与、朝鮮戦争勃発後の日本への避難といった「戦争の心理的な傷」とその回復が、作品解釈の基底をなす)。ケルトや北欧、ゲルマン、古代エジプト、ギリシャ、シベリアの神話や伝承、遺跡、インドの仏教説話、ジェイムズ・ジョイスの文学、「数字」に込められた象徴的・暗号的な意味など、本書はさまざまな前キリスト教的イメージや隠喩を次々と投与して連想の輪を広げていくが、それらは「分断された東と西(アジア/ヨーロッパ、西側の資本主義/東側の共産主義、北朝鮮と韓国)を統一し、戦争の傷を癒す」という解釈(単一の物語)へと収斂し、「秘教的なシャーマン」としてのボイス像の再神話化に与してしまう。
また、アジアとヨーロッパを統合した超国家的なひとつの大陸という壮大なヴィジョンは、(渡辺自身が「はじめに」で警戒するように)「大東亜共栄圏」の亡霊の召喚に加え、よりアクチュアルな事態としては、中国が提唱する「一帯一路」構想を想起させる。半世紀以上前のアーティストのラディカルな夢想は、今や、社会主義体制と新自由主義が両輪となってインフラ、物流、情報の流通網と軍事拠点の覇権的掌握をめざす巨大な経済圏に飲み込まれ、凌駕されつつある。
2020/06/20(土)(高嶋慈)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)