artscapeレビュー
高嶋慈のレビュー/プレビュー
akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』

会期:2021/01/08~2021/01/09
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
舞台芸術の「再演」において、「初演以降に流れた時間」はどのように作品内部に刻印されるのか。とりわけ、(プロの俳優やダンサーではない人々の)「個人としての生」を扱うドキュメンタリー性の強い作品の場合、この問いは分かち難く絡んでくる。akakilikeが薬物依存症回復支援施設「京都ダルク」の利用者とともにつくり上げた本作は、作品の基本構造を保持しつつ、彼ら自身が語る「ダルクに来る以前(依存症の背景)」と「2019年の初演から経過した時間」を対比的に構成し直すことで、家族との関係や彼ら自身の変化を浮かび上がらせ、「いま」をポジティブに肯定する力に満ちていた。
冒頭、akakilike主宰の倉田翠とともに登場したダルク利用者たちは、無言で客席に対峙したあと、頭上から落下した普段着の私服に着替え、「料理の共同作業」と「グループセラピーのミーティング」というダルクの日常を淡々と再現していく。一方、倉田はその傍らで独り言のように身体を動かし続ける。これが本作の基本的な構造である。

[撮影:前谷開]

[撮影:前谷開]
初演との違いは、まず、出演者が13名から6名に半減し、うち初演経験者は4名で、新たに2名が参加したことだ。コロナの影響もあるだろうが、「利用期間2年」の制限のため、利用者の入れ替わりが激しいことも一因だ。そのため、ミーティングの再現として語られる生い立ち、家族事情、薬物との関わり、日々の経験などのエピソードの多くが入れ替わり、「初演後に起こった出来事」が追加された。また演出上の変更として、冒頭のシーン構成と「衣装」の変化がある。初演では、全員がYシャツに黒いスラックスという事務的な服装で「住民説明会」を再現したが、再演では、ダブルのダークスーツ、派手な柄シャツに金のチェーンネックレスといった「ヤクザやホスト」を思わせる衣装で登場したあと、普段着に着替えて料理の共同作業に向かうことで、ダルク以前の過去/ダルクにいる「現在」への移行を視覚的に印象づけた。
また、語られるエピソードも一人ひとりの比重が増し、家族関係の変化や「いまの自分」を肯定する前向きな印象を強く感じた。絶縁状態だった父親の七回忌に出席した際、ロウソクの火が揺れるのを見た家族が「父親が喜んでいる」と語り、「自分はここにいていいんだ」と思えたこと。初演で「留置所での首吊り」を再現した出演者は、「あんたは死んだも同然」と家族に拒絶されていたが、勉強中のイラストで生計を立てたいという夢を伝えると、「生きがいを見つけたんだね」という言葉をかけてくれたことを語る。別の出演者は、年末の埼玉公演の際、見に来てくれた地元の家族の姿を客席に探した経験を語る。一方、依存症の背景には、複雑な家庭環境や児童虐待といった問題があることも語られる。
カラオケの熱唱や(最前列の観客をモデルに描く)似顔絵イラストの披露など、歓待的なサービス精神に開かれつつ、「出演者のキャラや個性」に頼る側面は否定できない。だが、本作をそれでも「ダンス作品」であると言いうるなら、この場に「ダンス」はどのように存在できるのか? 「ダンス」の居場所はどこにあるのか? と倉田自身が問いながら立ち続けている点にある。一見、即興的に自由に踊っているように見える倉田だが、「振付提供:筒井潤」のクレジットが示すように、演出家の筒井が振付けた過去作品の再現に従事しているにすぎない。「私は(他人に振付られる)ダンサーである」という態度表明とともに、倉田自身もまた、「過去の記憶」を身体的に反芻しているのだ。
「ダルクの日常」の再現の中に「過去からの移行」を語りつないでいく利用者たちと、その輪には入れない「ダンサーの私」。交わらないはずの両者だが、例えば「クスリをやってない」と嘘の否定を家族に繰り返した告白が語られる傍らで、四つん這いの倉田が激しく頭を振り続けるとき、ふと交差し共振し合うようにも見える。その両者が交わるのが、ともに食卓を囲むラストシーンだ。「LINEを無視する妻と、それでも社交ダンスを踊りたい」という叶わぬ願望を語る出演者に応えるように、倉田は「不在の誰か」と手を繋いで楽しそうに踊る。だが、そのダンスは次第に失速し、表情は逆光の闇に暗く沈み、もどかしい手探り状態に陥っていく。それは、「ここは本当に私の居場所なのか」「ダンスはそこに存在できるのか」という逡巡の自問自答であると同時に、再び「ダンス」を手探りし始める胚胎の瞬間でもある。
「作品」を固定化してしまうことは、「徐々に、あるいは目まぐるしく変わっていく彼らの生」の否定につながってしまう。状況的な要請もあるが、「再演」とは固定化でも単なる反復でもなく、「二度と繰り返せない差異を通して、過去との隔たりを計測することにこそ、作品の本質が新たに照射される」という「再演」の持つ意義を提示した好例であった。

[撮影:前谷開]

[撮影:前谷開]
公式サイト:https://akakilike.jimdofree.com/
関連レビュー
akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年10月15日号)
2021/01/09(土)(高嶋慈)
プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING
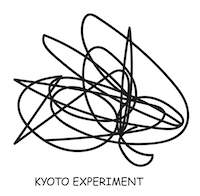
会期:2021/02/06~2021/03/28
ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都伝統産業ミュージアム、京都府立府民ホール“アルティ”ほか[京都府]
新型コロナウイルスの影響で、例年通りの秋開催から今春に会期変更となった「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING」(以下KEX)。フェスティバルの立ち上げから10年間ディレクターを務めた橋本裕介に代わり、川崎陽子、塚原悠也、ジュリエット・礼子・ナップの3人が共同ディレクターを務める新体制に移行した。川崎とナップはそれぞれKEXで制作と広報を務めており、塚原はcontact GonzoとしてKEXに何度も参加してきた一方、「KOBE-Asia Contemporary Dance Festival #3」(2014)などでのディレクター経験も持ち、それぞれの経験や得意分野を活かした連携が期待される。併せて一新されたロゴも斬新だ。
プログラム構成の大きな変化は、国内外の先鋭的な作品を上演するプログラム「Shows」に加え、アーティストが協働して3年間にわたり関西の地域文化をリサーチする「Kansai Studies」、そしてトークやワークショップなどを通じて多角的に思考を深める「Super Knowledge for the Future(SKF)」の3本柱で構成される点だ。また、関西を拠点とするアーティストを積極的に取り上げ、アジア圏のアーティストの紹介に力を入れている点も、注目すべき変化である。
上演プログラム「Shows」では、関西より、ダンサーの中間アヤカと垣尾優、音遊びの会が選出。中間は、2019 年初演のソロ作品『フリーウェイ・ダンス』を、京都版としてリ・クリエーションする。ダンスの専門的な訓練を受けていない人たちから提供してもらった「初めて踊ったときの記憶」を「振付」として踊るこの作品は、自己/他者、ダンス/日常的な所作といった境界に加え、「出入り自由で庭のような上演空間」「『ごはんの時間』も挟む4時間に及ぶ上演時間」といった仕掛けにより、「ソロダンス作品」の既存の枠組みをゆるやかに解体させていく。contact Gonzoの元メンバーで、近年は自身のソロ作品も発表する垣尾優は、「ダンスそのものに正面から向き合うことで、混沌とした『動く』ことの原初的考察」になるという新作を発表予定。また、知的障害のある人を含むアーティスト集団「音遊びの会」は、即興的なセッションを中心に演奏活動を行なっているが、今回、小説家・作詞家・ラッパーのいとうせいこうを迎え、「音と言葉のセッション」をテーマにしたコラボレーションを行なう。同じく関西の音楽シーンの紹介という点では、BOREDOMS、想い出波止場など多数のバンドで活動してきたミュージシャン、山本精一のディレクションのもと、関西の実験的表現の系譜をたどるプログラムが組まれている。
また、「Kansai Studies」では、大阪の建築家ユニットdot architectsと、京都の演出家・和田ながらが、「水」をテーマに関西各地のリサーチを行ない、ウェブサイトでのリサーチ過程の公開を経て、2022年度に3年間の成果を発表する予定だ。

中間アヤカ&コレオグラフィ『フリーウェイ・ダンス』
[Photo by Junpei Iwamoto]
アジア圏からは、インドネシアのヴィジュアル・アーティスト、ナターシャ・トンテイと、タイの若手演出家、ウィチャヤ・アータマートが参加。ナターシャ・トンテイの『秘密のグルメ倶楽部』は、人体を模した料理を、ホストの彼女自身とパフォーマーが食べるというパフォーマティブ・ディナー。ポップでグロ可愛い世界観のなかに、カニバリズムや過剰消費といった問題が潜む。また、多くの国際フェスティバルで高い評価を受けたウィチャヤ・アータマートの『父の歌(5月の3日間)』は、バンコクの小さなキッチンを舞台に、亡き父を偲ぶ姉弟の会話を通して、個人的な日常のなかにタイの政治史が交差するさまを描き出す。

ナターシャ・トンテイ『秘密のグルメ倶楽部』
[© Natasha Tontey]
KEXは過去10年を通して、「常識」「タブー」を激しく揺さぶるような挑発的な作品を取り上げてきたが、その実験性やラディカルな批評性は健在だ。特にジェンダーやセクシュアリティ、身体の表象をめぐる思考を挑発的に展開するのが、オーストリアの振付家のフロレンティナ・ホルツィンガー、カナダの振付家・ライブアーティストのデイナ・ミシェル、カナダのアート&リサーチ集団、ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネルによる3作品である。フロレンティナ・ホルツィンガーの『Apollon』(映像での上映)は、バレエの名作『アポロ』の神話的世界をベースに、6名の女性パフォーマーが出演。マシントレーニング、バレエのバーレッスンからスプラッターやワイヤーアクションが悪趣味なまでに展開し、女性の身体やジェンダー表象に問いを投げかける。デイナ・ミシェルは、ソロ作品『Mercurial George』の記録映像と新作映像作品『Lay them all down』の2本立てを上映。独自のダンス言語と繊細なジェスチャーで、自身のアイデンティティやセクシュアリティを問う。ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネルは、各国でワークショップを重ねて上演してきた『私がこれまでに体験したセックスのすべて』の日本版を上演する。多様なバックグラウンドを持つ60歳以上のシニアたちが、リアルな性体験を通して人生を語っていくという対話型演劇だ。

ママリアン・ダイビング・リフレックス/ダレン・オドネル『私がこれまでに体験したセックスのすべて』(オーストラリアでの上演、2017)[Photo by Jim Lee]
最後に、舞台芸術全体に対する相対化の視線として、キュレーター・映像作家の小原真史が企画する展覧会「イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示」がある。1903年に大阪で開催された第五回内国勧業博覧会で、アイヌ、沖縄、台湾などの先住民を「展示」した「学術人類館」をはじめ、19世紀末から 20世紀初頭に欧米諸国の博覧会で行なわれた同様の「人間の展示」の資料写真を紹介する。帝国主義と表裏一体の植民地主義や人種差別への検証とともに、家屋や生活用具を「舞台装置」のように設え、民族衣装をまとった「異民族」が日常生活を再現するさまを眼差す行為はある種演劇的でもあり、本展は、演劇あるいは劇場という装置に対する再帰的な批評性として機能するだろう。

小原真史「イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示」「学術人類館」(第五回内国勧業博覧会)1903年、個人蔵
公式サイト:https://kyoto-ex.jp/
KYOTO EXPERIMENTロゴ © 小池アイ子
2020/12/25(金)(高嶋慈)
お寿司『土どどどど着・陸』

会期:2020/12/25~2020/12/27
THEATRE E9 KYOTO[京都府]
「SF×稲作中心の古い行事が残るローカルなコミュニティ」という、一見、異色の組み合わせの演劇。だが、「見知らぬ異星に不時着してしまったエイリアン」=「新規の移住者」という視点から徹底して異化して描かれるため、「一過性のリサーチやレジデンスで地域の魅力を再発見/消費」という態度への強烈なカウンターとして機能する。
舞台中央には土のかまどと鍋が置かれ、その背後の板塀からは、柿の実をつけた枝が顔をのぞかせる。板塀の向こう側では、全身にキノコを生やした猿のような動物(ダンサーの竹ち代毬也)が身をくねらせ、柿の実をむさぼり、釜の中の飯を狙って侵入してくる。板塀の端には、ミニチュアの社(?)のような装置にご神体の白い蛇(?)のような不思議なものが巻き付き、この板塀は、家屋の内/外の境界であるとともに、人間/野生の領域を区切る象徴的な結界でもあるのだろう。

[撮影:松本成弘]
この簡略化された光景のなかに、着ぐるみのように膨れた宇宙服を思わせる衣装とヘルメットを付けた女性(筒井茄奈子)が立ち、混乱したモノローグをうわずった高い声で発し続ける。細い材木を円筒形に束ねた桶のような物体の中から、声(大石英史)が断続的に応答する。駄々をこねる幼い子どもとの会話、ご近所や地域の婦人会の人々とのやり取りのようだ。廃油を収集してロウソクを作るリサイクル活動、花壇の手入れなどの美化活動、食育という3つの「イインカイ・イインカイ」をはじめ、たくさんある自治会や婦人会、青年団の謎ルールの数々。意思疎通の困難さや価値観の齟齬は、会場のあちこちに仕込まれたスピーカーから流れる録音音声の効果とも相まって、壊れかけた通信機が発する混線した声を聴いているようだ。
あいさつ活動や見守りは「監視されている」という不安を焚きつけ、害獣の駆除は「よそ者としての疎外感」とオーバーラップする。一方、「不時着した異星で暮らす人々との会話」の合間には、田植えや農事に関するさまざまな一年間の行事が(実際に地域に住む女性2人によって)紹介され、自然のサイクルとともにある暮らしが示される。「私の生まれた星ではもっと個別だった」とつぶやく、「不時着」した女性。彼女は、古い行事を引き継ぐ食育活動での「のり巻き」づくりに対して、「私は負けない/巻けない」と宣言するが、最終的に待っているのは「(のり巻きを)巻けちゃった/負けちゃった」というオチである。「(命を)食べることの肯定、命の循環」という通奏低音が、緑と闇の濃い地域に暮らす実感として浮かび上がる。

[撮影:松本成弘]
地域に赴いてリサーチする滞在制作型の作品と本作が一線を画する特異性は、リサーチ対象をエキゾチシズムとして対象化するのではなく、自身を「エイリアン」の立場に徹底して固定化する視点の取り方にある。外部から侵入した観察者である自身の立ち位置は透明化したうえで、「珍しい風習や祭り、美しい自然、歴史の痕跡が豊富な地域」を一種の異文化として他者化するのではなく、そのようなものは所与の環境としてすでにそこにあり、自らを「その価値観やルールになじめないエイリアン」とする態度は、作・演出の南野詩恵の誠実さでもある。南野が主宰する「お寿司」はまた、衣装作家でもある彼女自身が手掛ける衣装と身体のあり方も注目だ。本作では、「SF」というフィルターに加え、「私の身体になじまない」異物感や防衛心理を強調する、服というよりも「装置」「拘束具」のような衣装によって、移住者として暮らす地域との距離が取れたのではないか。
ラストシーンで、上空から降ってくるのは、迎えに来た母船ではなく、正月を祝う鏡餅である。彼女は最後まで防護服のような宇宙服を脱ぐことはないものの、「それでも毎日ご飯は食べるし、この土地で生きていく」というしたたかさを感じた。

[撮影:松本成弘]
公式サイト:https://osushie.com/
2020/12/25(金)(高嶋慈)
劇団速度『わたしが観客であるとき』

会期:2020/12/18~2020/12/20
京都芸術センター[京都府]
2020年3月に予定していた舞台公演が延期となった劇団速度は、京都市内の路上を行き交う人々の光景と、そこにゲリラ的に挿入される俳優の行為を映像と字幕で記録/記述する映像作品をネット配信した(『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』)。そこでは、「歩く」「すれ違う」「振り返る」といった日常的な行為が、俳優の行為を指定するト書きのように「字幕」によって記述されることで、「路上の出来事を『演劇』のフレームに強制的に取り込む」暴力性が顕在化する。一方で、「映像の圧倒的な情報量」「行為の同時多発性」による言葉の追いつけなさは、その脆弱性を同時に露わにする。また、無人の上演会場が「歩く」「眺めている」「雨が降っている」という字幕とともに写し出されるとき、「不在のものの投影、二重化の眼差し」としての演劇が再びこの場に召喚される。このように「演劇」の原理的枠組みへのメタ的な思考を経て、改めて劇場で上演された本作もまた、出演者3人のきわめて個人的な語りの連鎖と共鳴を通して、サブレベルでは同時に常に「演劇」とその周辺について語るものだった。
舞台上には、上手奥から白い布のロールが床に転がっているだけで、ほかには何もない。この空虚な空間と対峙して見つめるように、客席と同じ向きで舞台前面に置かれた3つの椅子に出演者3人が座る。出演者のひとり、城間典子(記録映画作家)はヴィデオカメラをライブで回し、その映像は椅子の背後に置かれた小さな3つのモニターに中継される。目の前で起こる出来事、その記録、「過去」として固定され続ける「現在」と両者のズレ、視線とフレーム、視線の共有とその分断、不在と想起といった本作のキーワードが、ミニマルなつくりのなかに端的に提示される導入だ。

[撮影:小嶋謙介]
出演者3人は、順番に「舞台」に立ち、一見バラバラな個人的な語りを淡々と話し始める。瀬戸沙門(俳優)は、精神科の訪問看護師である父親についてのインタビューと、その仕事を「実演」してもらった経験について語る。通院が難しい精神科の患者と交わした会話を、「その人の言葉を預かる」気持ちで記録すること。遠い過去の出来事をつい昨日のことのように語る患者との会話は、一緒に「タイムマシン」に乗るような感覚であること。その仕事の「実演」に際し、他人を見る目で自分に向き合う父に感じた戸惑い。そこでは、自分が「俳優」としてその場にいられるまで待ち、肯定してくれる父の「視線」が重要だったと彼は結ぶ。

[撮影:小嶋謙介]
一方、城間は、カメラを構える自分が「透明な眼」になりたかったことと、身近な人ほどそれが難しいことを吐露する。城間が語るのは、7年前、統合失調症を罹患した友人と共同制作した映画についてだ。幻聴など自分の身に起きたことを友人自身が脚本化して自演し、城間が撮影した。城間は当時の撮影の様子を「『記憶の再演』の再演」として行なうが、手にしたカメラからモニターに中継されるのは、「無人の会場」の即物的な光景だ。「現在」しかカメラには映らないという残酷さと、その不在を想像力で埋めていくことについて、城間の語りを引き継ぐのが、畑中良太(ダンサー)の語る、かつて通ったゲームセンターの思い出だ。「そこに行くには、想像するか、夢を見るしかない」。
城間は数年間、その映画の編集をできないままだったが、最近、追加シーンを撮影したという。脚本もコンテもなく、「友人の家で家族と一緒にただ過ごす」撮影を経て気づいたのは、「ドキュメンタリー作家として『透明な眼』が理想だったが、自分との関係性もそこに織り込まれている」という事実だった。

[撮影:小嶋謙介]
「他者とどう向き合い、距離を取るか」、とりわけ家族や友人といった近しい存在であるがゆえの困難と、「役」やカメラといった媒介性の作用。それぞれ個人的な経験をバトンリレーのように語りつないだ3人は、終盤、椅子の向きを変え、客席と対面する。ラストシーンで、彼らが身を置く「舞台」は闇に沈み、「客席」は明るく照らし出される。この操作は、単純に「見る/見られる」という視線の反転というよりも、「いま目の前にいる相手、すなわち『観客』であるあなたとどう関係をつくるか」という切実な希求に思われた。彼らの語りのトーンは、「俳優としてのモノローグ」と「目の前にいる相手に向かって語りかける」の中間、「固定された台詞」と「いまここで過去を想起しつつ語ること」の狭間で不安定に漂っており、その揺らぎのなかで時々、こちらの目を見返してきたからだ。淡々と語る彼らの話を、(カウンセラーやインタビュアーのように)ただ傾聴に徹して受け止める時間は、親密とさえ言えるこの場限りの小さな共同体をともに立ち上げるための、長い助走の時間だった。その費やされた長い準備時間を共有することで、私たちはやっと、どのような関係性を結べるのかを摸索する端緒につくことができるのであり、それを可能にするのが「劇場」という場なのだ。
公式サイト: https://theatre-sokudo.jimdofree.com/
関連レビュー
劇団速度『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)
2020/12/18(金)(高嶋慈)
スペースノットブランク『光の中のアリス』

会期:2020/12/10~2020/12/13
ロームシアター京都[京都府]
『ささやかなさ』(2019)に続き、松原俊太郎の書き下ろし戯曲に挑んだスペースノットブランク。戯曲の「粗筋」を抽出することは困難だが、『ささやかなさ』同様に恋人を不慮の事故で亡くした女性(ヒカリ)が、その辛い事実への直面から逃れようと、記憶喪失と引き換えに閉じこもった自閉的な時空間の中で、彼女自身の妄想の産物のようなキャラクター(バニー、ミニー)、そして恋人(ナイト)と繰り広げる会話劇である。そこは、ルイス・キャロルさながら、メタファーが逐語的に変換され、狂った論理とナンセンスの見分けがつかない「アリス」的世界である。いや、狂っているのは、外部に広がる現実世界のほうであり、資本とファンタジーの投下による「夢の国」の精神的支配を受けた「現代日本」の病理と絶望的なまでの多幸感が、バニーとミニーによって(しばしば脱力的な言葉遊びとともに)語られる。一方で彼らは、『鏡の国のアリス』よろしく、予め決められた筋=チェス盤のルールと厳格なゲーム進行に抗い、外部への「脱出」を企て続ける。それは、「おもひで」への後退的な自閉からの、「日本」という自閉空間からの、そして「物語」という虚構からの、不可能なまでの「脱出」への希求である。
この戯曲の「上演」にあたり、スペースノットブランクは、きわめて堅固で理知的な空間構成をつくり上げた。下手側の壁は全面鏡張りになっており、舞台上の光景の「映像的複製」を生み出し続ける。その二次元性は、(作中で示唆されるディズニーとジブリのように)奥行のないアニメ的世界と呼応する。また、もうひとつの複製装置が、ライブカメラに向かって発話するバニーとミニーのアップを映し出す、4面の大型モニターである。それらは観客席を監視する4つの「眼」のように、正面2階バルコニーの高い位置に掲げられ、見下ろしている。

[photo: manami tanaka]
このように「鏡」と「ライブカメラによる中継映像」というイリュージョン生成装置で固められた空間構成のなかで繰り広げられるのは、しかし、流動的で可塑的にこねくり回される、身体の運動性と発話の熱量である。松原戯曲へのアプローチという点で、ここで地点との比較をしてみたい。地点と同様、「役」に依存してべったり癒着した身体ではなく、いかにテクストから距離を取りうるかが賭けられているが、地点の場合、(作品によって運動の「質感」は異なるものの)カンパニーとしてのある種の同質性が共有されている。一方、本作では、俳優たちは同じ戯曲に向き合い、「テクストとどのような距離がありうるのか」という問いを発話する身体に引き受けつつ、そのサーチのための受信機のセンサー幅や出力回路がそれぞれ異なっているように感じた。より正確に言えば、「センサーの感度や出力回路の差異」を望ましい「規定値」に強制/矯正しようとする(演出という)暴力性に対して、彼らは繊細に抵抗を示し続けているのだ。
そうした「抵抗」を許すのが、松原戯曲の(言葉の情報量だけに留まらない)豊穣さなのではないか。形式としては一貫して「会話劇」だが、「自然な会話」としてはそこここで破綻し、相手に応答はしているが、ちぐはぐで噛み合わない応酬がさらなる言葉のダイブを生んでいく。逐語的な意味に(誤)変換され、文脈は横滑りし続け、かと思うとトリッキーな架橋が成立し、言葉遊びが倍音的に意味を増幅させ、唐突に関西弁が「混入」し、「統一された人格」を破綻させるバグが侵入し続ける。
ただしそうした破綻やバグは、「対立」や「不和」にはドラマとして発展しない。なぜなら「裂け目」はすでにそこにあるからだ。それは、「日本」という裂け目や矛盾であり、「発語に先立って書かれた言葉」という「戯曲」が宿命的に内包する裂け目や矛盾でもある。いずれ「声に出して読まれる宿命」だが、「まだその身体を獲得していない」という、来るべき受肉の時を待つ空白としての裂け目。その裂け目を、「自然な演技」によって統合し、縫い合わせて見えなくすることこそ「嘘」である。むしろ積極的に引き受け、舞台に(不可視の「裂け目」自体を)現前させることが、戯曲に対する誠実さの発露なのだ。

[photo: manami tanaka]
最後に、「演出」に対するスペースノットブランクのもうひとつの態度として、主宰の2人、中澤陽と小野彩加自身が演じる「キング」と「クイーン」の立ち位置について触れたい。作中では、ヒカリが身を置く世界のもう一段上に属する審級として、「キング」と「クイーン」が設定されている。「キング」は舞台正面奥に置かれた演台という全体を俯瞰する位置に立ち、演台の上にノートパソコンを広げ、設計した演出プログラムの進行を見守る存在を思わせる。その背後に立った「クイーン」は、終盤まで背中を向けたまま一言も発さず、黒い服に長い黒髪という影のようなシルエットは、「そこにいる」がほぼ不可視の存在として立ち続ける。この2つの「役」が、主宰・演出の2人によって担われている点はきわめて重要だ。つまり彼らは、「演出」という(不可視の)ポジションを作品世界内に自らインストールし、メタ的に現出させているのだ。

[photo: manami tanaka]
この「キング」と「クイーン」のさらに奥の正面壁際にずらりと設置された「照明器具=舞台美術」は、「ヒカリ=光」の両義性をめぐる、(鏡とモニターに続く)第3の重要な装置である。それは、(ディズニーランドの起源でもあるアニメ)映画、すなわちファンタジーやイリュージョンへの現実逃避的な没入であるとともに、そこからの「覚醒」を促す光の投射でもある。また、客席に向けられるこの「光」は、「知らない顔がたくさん並んでいる集合写真」として観客を二次元の世界に取り込み、写真(=「死」)の領域に固定化しようとする。数メートルの高さのスタンドに設置されたライトの列は、「首をちょん切れ」と命じるクイーンの台詞によってギロチンを想起させつつ、客席に向けて一斉に光を浴びせかけるその激しい明滅は、私たちに覚醒を促す集中砲火でもあるのだ。
公式サイト: https://spacenotblank.com/
2020/12/10(木)(高嶋慈)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)