artscapeレビュー
福住廉のレビュー/プレビュー
鴻池朋子展「根源的暴力vol.2 あたらしいほね」
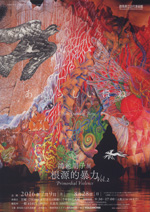
会期:2016/07/09~2016/08/28
群馬県立近代美術館[群馬県]
この夏、中国は重慶に長期間滞在した。重慶市は北京や上海と並ぶ直轄市のひとつで、中国内陸部における重要な経済拠点である。長江と嘉陵江が合流する盆地は起伏が激しく、急な斜面におびただしい超高層ビルが立ち並んでいるため、東京以上に立体的で重層的な都市風景が広がっている。街中には仰々しい高級外車と簡素な三輪自動車がめまぐるしく行き交っており、貧富の差が歴然としている感は否めない。けれどもその一方で、まるまるとした腹を出した中年男性が煙草を吹かしながら路上を堂々と闊歩したり、大勢の高齢者たちが夜な夜な広場で大音量の音楽にあわせてみんなで踊ったり、重慶の街には人の熱気というよりむしろ生きることの肯定感が強烈に立ちこめていた。言い換えれば、社会主義国であるにもかかわらず、彼らは自由に生きており、その生き様が幸福に満ちあふれているように見えたのだ。それは帰国した後、管理と自主規制が常態化した息苦しい東京から振り返ったとき、ありありと浮き彫りになった偽ざる実感である。いったいどちらが資本主義国でどちらが社会主義国なのか、しばらく考えあぐねてしまったほどだ。
とりわけ印象深かったのが、車道における歩行者の横断である。車道はあくまでも自動車の専有道路として認識されている日本とは対照的に、重慶では歩行者が車道を平気で横断する。むろん横断歩道や信号が機能していないわけではないが、それらとはまったく無関係に、まるで空いている場所を埋めるかのように、歩行者が自動車の往来を見計らいながら自由に車道を横切って行くのだ。しかも、それは一部の無法者による逸脱行為などではなく、老いも若きも、あらゆる人々が普通にそうしているのであり、さらに言えば、歩行者のみならずドライバーにも共有されている、社会一般の暗黙の了解であるようだ。
文化的な習慣の相違と言えば、そうなのかもしれない。だが、あえて深読みすれば、ここには土地をめぐる認識の根本的な相違、つまりは世界観の大きなちがいが現われているような気がしてならない。国家の体制がどうあれ、人はみな土地の上でものを考えながら日々の日常を生きている以上、思想と土地は分かちがたく結びつけられていると考えられるからだ。
周知のように、中国は社会主義国であるから土地の私有は認められていない。所有権は国が持ち、国民には使用権が与えられるにすぎない。日本でしばしば問題化されるジェントリフィケーションによる強制退去がほとんど問題にならないほど、中国では人の退去や移動、あるいは共同体の解体と再構築が頻繁に行なわれているのだ。事実、重慶の街を歩いてみても、古い街並みを丸ごと高層住宅街につくり変えている工事現場をいくつも目撃した。
それゆえ郷土愛にしても、ないわけではないが、その質は日本のそれとはかなり異なっているようだ。中国人の友人によれば、日本のように先祖代々受け継がれてきた土地を守るという使命感は、中国ではほとんど見受けられないという。先祖が暮らしていた土地と同じ場所で生きている人はきわめて稀だからだ。つまり土地に対して、よく言えば執着心がなく、悪く言えば責任感がない。言い換えれば、私の所有物ではないが、同時に、あなたの所有物でもない。そのような割り切った土地への意識が、おそらく車道を自由に歩行する身ぶりにつながっているのではないか。すなわち車道といえども、車のものではないし、私のものでもない。しかしだからこそ、空いていれば、そこは誰であれ公平に使用しうるのだと。
むろん、これは想像的な推察にすぎない。中国人の当事者からは異論が出るかもしれない。だが重慶の街並みで感じた快適で自由な雰囲気は、このような土地意識の反映ではなかろうか。歩道や広場、電車といった公共空間で中国の人々は誰もが他者への無関心を貫いている。いや、「無関心を貫く」というより、そもそも「関心がない」と言うべきか。たとえ私のような外国人が紛れていたとしても、基本的には無視されるし、一瞥されることはあっても、それ以上は何もない。個々人がそれぞれの自由を勝手に追究しているのだ。むろん国家権力による統制がないわけではないが、少なくとも市井の人々の水準で言えば、その放っておかれる雰囲気がたまらなく心地よいのだ。こうした、いわば社会主義国における徹底した個人主義は、自由社会を謳いながらも、その実たえず周囲の人々の言動に眼を光らせている日本の不自由な公共空間のありようとは、きわめて対照的だった。土地や公共空間の意味が、ことほど左様に異なることを、まざまざと実感したのである。
鴻池朋子による本展は、昨年、神奈川県民ホールギャラリーで催された展覧会の巡回展である。だが基本的な構成は踏襲しながらも、最近制作された新作もあわせて含まれているため、たんなる巡回展というより、むしろ制作しながら生きている鴻池朋子の同時代的な時間性をそのまま凝縮した現在進行形の展覧会と言うべきかもしれない。事実、全長24メートルにも及ぶ大作《皮緞帳》は新たに加筆されたうえで展示され、前回の展示には含まれていなかった版画作品なども新たに展示された。「もはやおなじものではいられない」という鴻池自身の言葉を体現したような展観であった。
この言葉には、はたしてどんな意味が含まれているのか。「全国の美術館を渡り歩きながら庶民とはかけ離れた「現代美術」を再生産するアーティストのありようが打ち棄てられているのか。あるいは、震災によって決定的な断絶を経験したにもかかわらず、その裂け目を直視することから逃避し続けている私たち自身の自己保身が撃たれているのか。いずれにせよ、この世界を構成する生命体が有機的に接合したイメージを全身で体感すればするほど、ある種の大きな切断面が心の奥底に広がるのである」。前回の「根源的暴力」展について、こう書いた。基本的な評価は変わらない。根源的暴力とは、来場者をその切断面や裂け目に直面させることを意味していると解釈する点も同じだ。けれども牛皮を縫合したポンチョの作品だけは、印象がかなり異なっていた。
前回、彼らは会場の一角にうずくまるようにして設置されていた。いずれも中身が黒いマネキンであるため、その空虚を埋める新たな身体──すなわち、「あたらしいほね」──が要請されているように見えた。「もはやおなじではいられない」のだとすれば、ではどんな身体がふさわしいのか。来場者の想像力はポンチョに収める身体のありようをめぐってどこまでも広がったのである。しかし今回の展覧会では、彼らは会場の中にも設置されていたが、大半は会場入口前のロビーにまとめて展示されていた。注目したいのは、ひな壇状に立ち並んでいたせいか、彼らを見上げると、私のもとから立ち去っていくように見えたことだ。私たちが追いつくのを待っているのかもしれないが、みな背を向けているため、いまにもこの場から飛び立ってしまうかのようだ。この違いは決して小さくない。
去りゆく彼らと残される私たち──。その非対称性を思い知ったとき、急激に浮上してきたのが土地だった。むろん美術館であるから土地そのものが剥き出しになっているわけではない。けれどもいまにも飛翔せんばかりのポンチョたちを見上げていると、逆説的に、自分たちが依って立つ土地のありかに思いを巡らせることになったのだ。向こう側の世界に消え去ってしまうかのような彼らのイメージが、こちら側の世界で生きる私たちの足元を逆照したと言ってもいい。「もはやおなじものではいられない」のだとすれば、「あたらしいほね」が必要だろう。だがそのとき、土地はどんな土地がふさわしいのか。私たちはどんな土地に立つことができるのだろう。自由や幸福はどんな土地で育まれるのだろう。どんな土地で生きていけばよいのだろう。
2016/08/17(水)(福住廉)
羽永光利アーカイブ展

会期:2016/07/23~2016/08/20
AOYAMA|MEGURO[東京都]
写真家・羽永光利(1933-1999)の写真アーカイヴを見せる展覧会。前衛芸術、舞踏、演劇、世相というテーマに整理された約400点の写真が一挙に展示された。会場の白い壁面を埋め尽くすかのように並べられたモノクロ写真の大半は、戦後美術史の現場を物語る貴重な写真ばかりで、たいへん見応えがあった。
平田実であれ酒井啓之であれ、美術の現場を記録する写真家には「時代の目撃者」という常套句が用いられることが多い。だが、とりわけ60~70年代に撮影された羽永の写真を見ていると、目撃者というより「共犯者」という言葉のほうがふさわしい気がしてならない。よく知られているように、ハイレッド・センターの《ドロッピング・イベント》(池坊会館屋上、1964年10月10日)の写真は、あらかじめ待機していた羽永が確信的に撮影したものだ。また今日、反芸術パフォーマンスとして歴史化されている、ダダカンこと糸井貫二の《殺すな》(1970)やGUNの《雪のイメージを変えるイベント》(1970年2月11日、15日)の記録写真も羽永が撮影したものである。それらの作品の作者がパフォーマンスを実行したアーティストであることは疑いないにしても、本来的にはその場かぎりで消え去ってしまう身体行為を写真として定着させた写真家の働きを過小評価すべきではない。事実、羽永によって撮影された糸井とGUNのパフォーマンス写真は、いずれも雑誌のグラビアに掲載されることで、その決定的なイメージを大衆に届けることに大いに貢献したのである。今日誰もが思い浮かべることができる、そのようなパフォーマンスのイメージは、羽永の視線と手に由来しているのだ。
翻って今日、はたして「共犯者」としての写真家はありうるだろうか。戦後美術の現場を記録した羽永の写真群を見ているうちに気づかされるのは、それらと今日における写真家の位置性と役割との偏差である。かつての写真家は、アーティストとして自立していないわけではなかったにせよ、美術家の作品を記録する役割を負わされていた。やや極端な言い方だが、写真家は美術家に従属していたと言ってもいい。だが今日の写真家は、「フォトグラファー」という呼称が定着しているように、アーティストとしての評価を高め、美術家の作品を記録する役割から相対的に解放されつつある。それは、端的に言えば、美術家自身が写真を撮影する役割を担うようになったからだろうが、より根本的には、写真そのものの性質が変容してしまったからではなかろうか。今日の写真は、とりわけデジタル技術の普及以降、大量に撮影することが可能となった反面、一回性の強度が失われ、「カメラ」に写真と動画の撮影機能があらかじめ組み込まれているように、相対的には映像との境界が曖昧になりつつある。パフォーマンスの現場を記録するという点で言えば、写真より映像のほうがふさわしいのかもしれないが、視覚的イメージの強度という点で言えば、羽永が盛んに撮影していた60~70年代に比べると、今日の写真は著しく脆弱になっていると言わざるをえない。羽永のような決定的なイメージを見せる写真家も、あるいはまた、そのような決定的なイメージに足る肉体表現を見せるパフォーマーも、今日のアートシーンのなかから見出すことは難しいからだ。
本展で発表された羽永の写真の背後に垣間見えたのは、写真による記録という表現行為に揺るぎない価値が与えられていた時代である。逆に言えば、そのように価値が機能していたからこそ、反芸術パフォーマンスはあれほどまでに強力な肉体表現を繰り返すことができたのだろう。今後、私たちはある種の信頼関係に基づく共犯関係を取り戻すことはできるのだろうか。
2016/08/17(水)(福住廉)
指田菜穂子 十二支
会期:2016/07/19~2016/09/03
西村画廊[東京都]
「百科事典の絵画化」に取り組んでいる指田菜穂子の5年ぶりの個展。特定の言葉から連想される古今東西あらゆるイメージをひとつの画面に凝縮させる画風で知られているが、今回の個展では「十二支」をテーマにした連作を一挙に展示した。
曼荼羅のような秩序立てられた画面構成と年画のような華やかな色彩。指田の緻密な絵画に通底しているのは、そのような定型である。しかし、その定型を破綻させかねないほどの膨大な情報量を詰め込むところに、指田絵画の醍醐味がある。大小さまざまな図像や記号が重複しながら同居している画面に眼を走らせると、あまりの知の物量に軽い目眩を覚えるほどだ。事実、それぞれの絵画の傍らには、イメージを言葉で図解した照応表が掲示されていたが(同じ内容は個展にあわせて発行された図録にも掲載されている)、そこには映画のワンシーンからギリシャ神話の伝説、哲学者の逸話まで、実に微細な情報が書きこまれており、指田の博覧強記に、ただただ圧倒されるばかりである。
しかし今回の個展で思い至ったのは、指田絵画が「百科事典の絵画化」を成し遂げていることは事実だとしても、その可能性の中心はむしろ「絵画の百科事典化」にあるのではないかということだ。言い換えれば、「百科事典」に重心があるように見えるが、実はそうではなく、むしろ「絵画」の方に傾いているところに指田絵画の真骨頂があるのだ。というのも指田絵画は、非常に豊かで、かつ、実にまっとうな絵画経験を鑑賞者に堪能させているからである。
例えば今年の干支である「申」。高村光雲の《老猿》や映画『猿の惑星』、ゲーム「ドンキーコング」などは誰もが知るイメージだろう。発見したときの快楽も大きい。だがナスカの地上絵や熱帯アメリカ原産の常緑高木「モンキーポッド」、小説『類猿人ターザン』を書いたエドガー・バロウズなどは、照応表で確認しないと、まずわからない。つまり既知の図像や記号は突出して見えるが、未知のそれらは後景に退いて見える。指田絵画は、鑑賞者の脳内に格納された知識の質量に応じて、その視線に奇妙な立体感と運動性を体感させるのだ。そこが面白い。
むろん絵画であるから平面性に則っていることにちがいはない。けれども平面という定型を保持しつつも、それらと対峙する鑑賞者の視線に平面という条件を内側から突き破るほどの豊かなイメージを幻視させる点は、実は絵画という芸術の王道ではなかったか。単に三次元的な奥行きを感じさせるわけではない。それぞれの図像と記号が目まぐるしく凹凸を繰り返すことで、平面を基準にしながら激しい前後運動を生じさせるのだ。それこそが、平面の純粋還元を唱えた俗流のモダニズム理論を真に受けた人々が現代絵画から放擲してしまった絵画的なイリュージョンである。それを指田は「百科事典の絵画化」によって見事に奪還した。
思えば、現代絵画の隘路は百科事典が体現するような言説空間からの切断に始まっていたのかもしれない。俗流のモダニズム理論においては、彫刻と重複する三次元性はもちろん、文学と重複する言語性も、徹底した排除の対象とされたからだ。だが、そのようにして平面性を純粋化することは、結果的に絵画という芸術を世俗世界から隔絶することになってしまった。世界との関係性を失った絵画は、貴族的なスノビズムに貢献することはあっても、その世界を生きている庶民の視線を奪うことはできない。それゆえ現代絵画に必要なのは、言葉や文字、あるいはイメージによって世界との再接合を図る「絵画の百科事典化」というプロジェクトにほかならない。
2016/07/29(金)(福住廉)
土木展

会期:2016/06/24~2016/09/25
21_21 DESIGN SIGHT[東京都]
「土木」についての展覧会。それは私たちの日常生活の基盤を構築する重要な技術知であるにもかかわらず、日常生活の基底にあるため日頃は自覚的に実感される機会は乏しい。本展は、その知られざる実態を土木の専門家やアーティストら22組によって詳らかにしたもの。
土木というと、文字どおり土や木の圧倒的な迫力やそれらと拮抗しうる重量感あふれる重機などを連想しがちだが、残念ながら本展にそのような展示はない。あるのは、来場者の「参加」を要請する当世風の展示である。例えば、エアーで膨らませたビニールのピースを積み上げさせたり、マンホールを模した穴の下から顔を覗かさせたり、来場者の参加によって土木の世界を体験することが本展の醍醐味とされている。
しかし、このような「体験」「参加」型の展示手法が土木の本質を突いているとは到底思えない。いくらそのような参加体験を繰り返してみたところで、本展には土木の本質には決して到達しえないある種の「障壁」が設置されているからだ。その「障壁」とはメディアにほかならない。
「土木」とは、土や木といった自然物を人為的に改変ないしは抑圧することで人間の利益に資する営み全般を指す。であれば、それは必然的に土や木の物質そのものと密接不可分であるはずである。ところが本展は写真や映像、ないしは建築模型というメディアによって土木の物質性を媒介するばかりで、肝心の物質そのものはほとんどと言っていいほど見せられていなかった。企画者が言明しているように、土木が日常生活の根底にあるのは事実だとしても、それを自覚的に相対化するのであれば、日常生活にあふれているメディアを多用したところで、土木を日常性のなかからつかみ出すことはできない。むしろ、非日常性こそが日常性を相対化しうるという現代美術の大原則に則れば、日常では決して出会うことのない土木の現場の生々しい物質感こそが、私たちの足下に広がる土木の世界に想像力を差し向けるはずだ。もし、あの広大な会場に重機のひとつでも展示されていたら、もしあの無機質な展示空間の床に底が見えないほどの暗い穴がひとつでも穿たれていたら、本展の印象は一変していたにちがいない。
物質の忘却と参加体験の強制。本展の特徴をあえて乱暴に要約すると、このようになる。だが、こうした点は、本展の固有の特徴というわけではあるまい。それは、ポスト・プロダクト、関係性、参加、といったキーワードによって整理されがちな、昨今の現代美術の一部の潮流と共振しているように考えられるからだ。有無をいわさず参加を強制されたり、望みもしない関係性を無理やり結ばされたり、「地域社会」という公的な題目があろうとなかろうと、平たく言えば、「大きなお世話」というほかない作品が昨今あまりにも多すぎる。だいたい赤の他人と一緒にカレーを食べたところで、それがいったい「不愉快」以外のどんな感情を惹起するというのか。夢であれ希望であれ、自らの内面をポストイットに書かせる手法も、「馬鹿のひとつ覚え」という悪態が口に出るより先に、内に秘めた心情をあけすけにさせようとする、無遠慮で無神経なふるまいに怒りが募る。一見すると、非常に民主的かつ平和的な手法であるかのようだが、そのじつ、人の心に土足で踏み込むかのような、きわめて暴力的な悪意に満ちた作品が跋扈しているのだ。
参加体験という価値観に立脚した本展は、知ってか知らずか、そのような現代美術の悪質な潮流に巻きこまれてしまっている。必要なのは、土木の世界の物質性を、いかなるメディアにも媒介させることなく、そのまま展示することだった。物質をあるがままに提示すること。そう、ポスト・プロダクトないしは関係性の美学などを吹聴するアートが、とうの昔に批判的に乗り越えたはずの「もの派」的な作品のありようが、この場合に限って言えば、じつはきわめてまっとうだったのではあるまいか。
2016/07/06(水)(福住廉)
メアリー・カサット展

会期:2016/06/25~2016/09/11
横浜美術館[神奈川県]
印象派を代表するアメリカ人女性画家、メアリー・カサットの回顧展。日本では1981年に伊勢丹美術館と奈良県立美術館を巡回した展覧会から35年ぶりにカサットの絵画を鑑賞できる貴重な機会である。油彩画をはじめ、パステル画や版画、カサットと親交のあったエドガー・ドガやベルト・モリゾ、カミーユ・ピサロらの作品、そしてカサットに大きな影響を与えた葛飾北斎や喜多川歌麿の浮世絵など、併せて112点が展示された(なお同館の後、京都国立近代美術館に巡回する[9月27日~12月4日])。
「あふれる愛とエレガンス。」──本展のチラシに記載されたキャッチ・コピーが示しているように、メアリー・カサットは愛と優美の画家として語られることが多い。事実、カサットの代名詞とも言える母子像──例えば《眠たい子どもを沐浴させる母親》(1880)や《母の愛撫》(1896頃)など──を見ると、母子に限りなく接近したスナップショット的な構図に基づいているせいだろうか、子どもに注がれた温かい視線と慈しみの感情を存分に味わうことができる。
しかしメアリー・カサットの真骨頂は、必ずしも母性愛を美しく描いた点にあるわけではない。それは、むしろ「母性愛」から女性を解放するジェンダー・フリーの視点を巧みに描き出した点にある。
本展最大の見どころは、本邦初公開となる《桟敷席にて》(1878)である。中心に描かれているのは、劇場の桟敷席からオペラグラスをとおして舞台を見つめる女性。きらびやかなドレスを着飾る周囲の女性たちとは対照的に、彼女はシックな黒いドレスに身を包んでいる。社交の場である劇場には似つかわしくないが、逆に言えば、社交を望んでいないことの現われでもある。事実、彼女の横顔から伺えるのは、脇目もふらず舞台を一心に見つめる力強い眼差しだ。左手で持つ硬く閉じられた扇子も、周囲の喧騒をよそに舞台に集中する彼女の頑なな意志を体現しているように見えなくもない。
この絵画が面白いのは、彼女の背後に男性の視線を描いているからだ。桟敷席の奥にいるのは、同じくオペラグラスで彼女を露骨に見つめる男性。身を乗り出すほどだから、おそらく好色の視線で彼女を凝視しているのだろう。けれども、彼女が男性の視線に応えることはない。あるいは、オペラグラスを持つ右手で不快な視線を遮断しているのかもしれない。いずれにせよ、この絵画には決して交わることのない2つの視線が描き出されているのである。
視線の非応答性。カサットの《桟敷席にて》に見出すことができる特徴をそのように言い表わすとすれば、それは、例えばオーギュスト・ルノワールの《桟敷席》(1874)と比較してみれば、よりいっそう際立つにちがいない。カサットが描いた控えめな彼女とは対照的に、ルノワールの描いた彼女は艶やかなドレスを着飾り、胸元のバラが華やかな印象をよりいっそう強めている。しかも、ルノワールの彼女の視線は絵画を鑑賞する私たち自身にしっかりと向けられているが、その先には対面の桟敷席から彼女をオペラグラスで見つめる男性がいることは想像に難くない。なぜなら、彼女の背後には同伴しているのだろうか、オペラグラスで劇場内の女性を物色している男性が描かれているからだ。つまり、彼女は自らに注がれた男性からの視線に応答しているわけだ。口元には、かすかな微笑みが浮かんでいるから、これから何かが始まるのかもしれない。
見る主体としての男性と見られる客体としての女性。ジェンダーアートにとっての基本的な図式を踏まえるならば、ルノワールは見られる客体としての女性を順接的に描いたのであり、その反面、カサットは見る主体としての女性を逆接的に描いたと言えよう。あるいは、カサットはルノワールが描いた旧来の女性像を転覆したと言ってもいい。男性からの視線に一切応答せず、あくまでも自らが見たい対象を一心不乱に見る。そのような自立した女性像は、印象派のみならず、当時の社会状況のなかでも画期的だったと考えられるからだ。グリゼルダ・ポロックが的確に指摘したように、「そうして積極的に見ているところを描くことによって、彼女が対象化されるのを防ぎ、彼女を視線の主体にしているのである」(『視線と差異』p.126)。
ただ、あえて深読みするならば、メアリー・カサットは見る主体としての女性を描写することで、見る主体としての男性と見られる客体としての女性という支配関係を象徴的に反転させただけではない。カサットは、そこからもう一歩踏み込んで、男性に依存しない、より自由な女性の生き方を絵画のなかで夢想していたのではなかったか。
前述したように、メアリー・カサットは母子像を繰り返し描いていたが、よく見ると、そこには父親としての男性が一切含まれていないことに気づく。むろん家庭という私的領域に囲い込まれた母と子の深い紐帯を強調して描写した結果として、公的領域と私的領域のあいだを自由気ままに往来する男性が画面から除外されてしまったと考えることもできなくはない。しかし母と子の多幸感あふれる世界を見ていると、カサットは男性=父親を意図的かつ入念に画面から排除したように思えてならない。ちょうど《桟敷席》の彼女が男性からの吟味の視線をはねつけながら、あくまでも観劇する主体として振舞っていたように、カサットは母と子だけで完結した幸福な想像世界を画面上に確信的に描写したのだ。
そこに、カサット自身が生涯未婚であり、子どもを産むこともなかったという事実を重ねて見ることは容易い。けれども重要なのは、カサットの想像力を事実によって裏づけることより、むしろその想像力に私たち自身の想像力を重ねることだろう。カサットの母子像における男性ないしは父親の不在が暗示しているのは、家父長制に束縛された母性愛とは対照的に、女性同士の連帯を示すシスターフッドによって成立する母性愛ではなかったか。その先にレズビアンにとっての家族のイメージを見出すことすらできるだろう。
2016/07/05(火)(福住廉)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)