artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
藤岡亜弥『アヤ子江古田気分/my life as a dog』
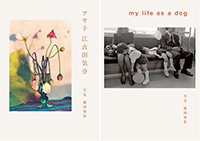
発行所:私家版(発売=ふげん社ほか)
発行日:2021/09/16
藤岡亜弥は1990年から94年にかけて、日本大学芸術学部写真学科の学生として、東京・江古田に住んでいた。今回、彼女が刊行した2冊組の小写真集は、主にその時代に撮影した写真をまとめたものだ。『アヤ子江古田気分』には、「木造の古い一軒家の2階の八畳ひと間」に大学卒業後も含めて8年間住んでいた頃のスナップ写真が、大家の「82歳のおばあさん」との暮らしの記憶を綴った文章とともに収められている。『my life as a dog』は、「大学生のときに夢中になって撮った」という子供たちの写真を集めたものだ。
どちらも彼女の後年の作品、『私は眠らない』(赤々舎、2009)や第43回木村伊兵衛写真賞を受賞した『川はゆく』(赤々舎、2017)と比べれば、「若書き」といえるだろう。とはいえ、奇妙に間を外した写真が並ぶ『アヤ子江古田気分』や、牛腸茂雄の仕事を思わせるところがある『my life as a dog』のページを繰っていると、混沌とした視覚世界が少しずつくっきりと像を結び、まぎれもなく一人の写真家の世界として形をとっていくプロセスが、ありありと浮かび上がってくるように感じる。「若書き」とはいえ、そこにはまぎれもなく藤岡亜弥の写真としかいいようのない「気分」が漂っているのだ。
木村伊兵衛写真賞受賞後、広島県東広島市に移住した藤岡は、いま、次のステップに向けてのもがきの時期を過ごしているようだ。写真学科の学生時代をふりかえることも、その脱皮のプロセスの一環といえるのだろう。だがそれとは別に、2冊の写真集をそのままストレートに楽しむこともできる。笑いと悲哀とが同居し、どこか死の匂いが漂う写真たちが、じわじわと心に食い込んでくる。
2021/12/06(月)(飯沢耕太郎)
土田ヒロミ「ウロボロスのゆくえ」

会期:2021/11/29~2022/01/17
キヤノンギャラリーS[東京都]
土田ヒロミは1939年の生まれだから、今年82歳になるはずだ。普通ならリタイアしてもおかしくない年代であるにもかかわらず、その創作意欲はまったく衰えていない。今回キヤノンギャラリーSで開催した「ウロボロスのゆくえ」展でも、新たな領域にチャレンジする姿勢が全面的に表われていた。
とはいえ、展示されていたのはバブル経済の崩壊の時期だった1990年代前半に撮影された「産業考古学」(1991-2004)と「Fake Scape(消費の風景)」(1995-2000)の2シリーズである。「産業考古学」は「日本の高度経済成長を支えてきた基幹産業の生産現場」を記録するプロジェクトで、工場地帯の光景をその物質性を強調して撮影している。一方「Fake Scape(消費の風景)」では、「大都市郊外の国道線路沿線(主に国道16号)に現われていた消費者が誘導する異様な意匠の店舗の風景」にカメラを向けた。興味深いのは、この2シリーズを合体させることで、1990年代における生産と消費の現場のうごめきが、あたかも合わせ鏡のように出現してくることである。それこそが、土田が今回の写真展のタイトルに「ウロボロス」(自分の尻尾をくわえた蛇、あるいは竜の表象)という名辞を付した理由だろう。同時にその「異様な」眺めが、2020年代の現代の都市風景のプロトタイプであることが、鮮やかに浮かび上がってきていた。
本展では、過去作にあらためてスポットを当てつつ、それらを再解釈、再構築しようとする土田の営みが、実り多い展示として実現していた。彼には、まだ現在も進行中のプロジェクトがいくつもある。現役の写真作家として、さらなる活動の広がりを期待できそうだ。
2021/12/06(月)(飯沢耕太郎)
村越としや「息を止めると言葉はとけるように消えていく」

会期:2021/11/20~2021/12/18
amana TIGP[東京都]
会場に入ると7点の作品が展示されていた。イメージサイズは60×190cm。マットの余白とフレームがあるのでさらに大きく感じる。写っているのは横長の海の景色で、水平線がちょうど画面の中央に来ている。2012年から21年にかけて、福島第一原子力発電所近くの、ほぼ同一の場所から、6×17cmサイズのパノラマカメラで撮影されたものだ。雨、あるいは霧がかかっているのだろう、湿り気を帯びたグレートーンが、画面全体を覆いつくしているものが多い。
この「息を止めると言葉はとけるように消えていく」と題されたシリーズを見て、杉本博司の作品を連想する人は多いだろう。むろん、発想もプロセスもかなり違っているのだが、見かけ上は杉本の「Seascapes」と同工異曲に思える。人によっては、村越がずっと撮り続けてきた、実感のこもった福島の風景とは違った方向に進みつつあるのではないかと感じるかもしれない。彼もそのことを充分に承知の上で、あえてこの隙のない画面構成と、モノクローム・プリントの極致というべき表現スタイルを選択しているのではないかと思う。個人的には、その方向転換をポジティブに捉えたい。村越のなかにもともと強くあったミニマルな美学的アプローチを、むしろ徹底して打ち出そうとしているように思えるからだ。不完全燃焼に終わるよりは、より先に進んだ方がいいのではないだろうか。DMの小さな画像ではよくわからなかった、彼の全身感覚的な被写体の受け止め方が、大判プリントの前に立つことでしっかりと伝わってきた。
関連レビュー
村越としや「沈黙の中身はすべて言葉だった」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年03月15日号)
2021/11/30(火)(飯沢耕太郎)
井津健郎「未発表作品展1975-2016『井津建郎 地図のない旅』」「地図のない旅」「もののあはれ」

[東京都]
井津健郎は1971年に渡米し、ニューヨークを拠点として作家活動を続けてきた。だが、昨今のアメリカの社会・文化状況への疑念が大きくなったこともあり、日本に帰国することを選択する。来年からは、金沢に居を構えて写真作品を制作していく予定だが、ひとつの区切りとして東京の三つのギャラリーで「活動50周年記念展」を相次いで開催した。
蔵前のiwao galleryでは、渡米直後の1975年から近作まで、これまで発表せずにしまい込んでいたヴィンテージ・プリント27点が「蔵出し」されていた。それらを見ると14×20インチ判の大判カメラで、「聖地」のたたずまいを撮影し、緻密かつ重厚なプラチナプリントで発表する生真面目な写真家という井津のイメージが大きく揺らいでくる。杉本博司とシェアしていたというスタジオで撮影したファッション写真風のポートレート、ヌード写真、静物や花の写真など、作風の幅はかなり広く、軽やかに遊び心を発揮したような作品も含まれていた。
ルーニィ・247ファインアーツでの展示では、井津の写真家としての転機になったという、1979年にエジプト・ギザのピラミッドを撮影した写真をはじめとして、イギリス、フランスなどの石造遺跡を撮影した写真群が並ぶ。プラチナプリントを使いこなすことができるようになり、写真家としての視点を完全に確立しテーマが定まってくる、1979〜1992年制作の充実した作品群である。
注目すべきなのは、PGIではじめて発表された新作の「もののあはれ」だろう。能面、神社の神域、そして枯れていく草花という3部構成の写真群には、日本への帰国を契機として、新たな領域に踏み出していこうという井津の意欲がみなぎっている。当然ながら、「もののあはれ」という日本の伝統的な美意識の探究が大きな目標なのだが、それをあくまでもアメリカ在住の時期に鍛え上げた、被写体の細部の物質性をしっかりと把握・描写していく視点のとり方と、高度な撮影・プリントの技術によって成し遂げようとしていることが興味深い。本作はまだ完成途上とのことだが、それが完全に形をとった時に、彼の新たな代表作となるのではないかという予感を覚える。
「未発表作品展1975-2016『井津建郎 地図のない旅』」
会期: 2021/11/17〜2021/11/28
会場:iwao gallery
「地図のない旅」
会期:2021/11/23〜2021/12/05
会場:ルーニィ・247ファインアーツ
「もののあはれ」
会期:2021/11/24〜2022/01/21
会場:PGI
関連レビュー
井津健郎「ETERNAL LIGHT 永遠の光」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年02月01日号)
2021/11/24(水)(飯沢耕太郎)
フィリア―今道子

会期:2021/11/23~2022/01/30
神奈川県立近代美術館 鎌倉別館[神奈川県]
今道子の作品は、写真という表現領域においてはかなり異色のものといえる。何しろ今が撮影しているのは、魚介類、果物、野菜などの「食べ物」や、剥製の動物、衣服、装飾品、あるいは人体などを組み合わせて作ったあり得ないオブジェであり、現実世界の再現・記録という、普通は写真の最も基本的な役目と考えられている要素はほとんど顧慮されていないからだ。そこに出現してくるマニエリスティックな画像の世界は、ほとんど今の夢想が形をとったものであるようにも見える。とはいえ、写真以外の制作手段(絵画、版画、彫刻など)で彼女の作品世界が成立するかといえば、それは不可能だろう。その緻密で、蠱惑的で、ときにはユーモラスでもある作品世界は、平面上にリアルな幻影を出現させる写真の魔術的な力の産物以外の何者でもない。その意味では、今の仕事は19世紀の写真術の発明以来積み上げられてきた、イメージの錬金術師としての写真家たちの系譜を正統に受け継ぐものともいえるだろう。
代表作100点余りによる、今回の神奈川県立近代美術館 鎌倉別館での個展は、今の初期作品から新作までを概観することができる貴重な機会となった。それらを辿り直すと、写真という表現手段を手にして、身辺の事物をテーマに作品を制作し始めた初期から、精力的に活動を続けている現在に至るまで、彼女の姿勢がほとんど変わっていないことに気がつく。とはいえ、たとえば2010年代以降のメキシコ体験をベースにした作品群のように、新たな刺激を取り込みつつ、より多元的、多層的な広がりを加えていこうとしていることが見て取れる。2001-2002年頃に集中して制作されたカラー写真のシリーズ、障子をモチーフにした「時代劇」風の連作(2010)、生きている蚕を使った作品(「目の見えない蚕」、2017)、ブレを意図的に取り入れた作品(「めまいのドレス」、2013)など、近作になればなるほど、融通無碍にさまざまな手法、スタイルを模索するようになってきている。初期から近作まで25点を「祭壇」のように配置した「フィリア」のパートなど、インスタレーションにも工夫が凝らされていた。タイトルの「フィリア」(philia)とは「──愛」を意味するギリシア語の語尾だという。今道子の「現実と非現実との間のようなもの」に対する偏愛を、うまく掬いとったいいタイトルだ。
2021/11/23(火)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)