artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
多和田有希「悪魔祓い、系統樹、神経の森」

会期:2018/08/25~2018/09/29
G/P GALLERY[東京都]
多和田有希は1978年、静岡県浜松市生まれ、東北大学で農学を学んだ後、美術に転じ、ロンドン芸術大学キャンバウェルカレッジを経て東京藝術大学大学院博士課程を修了した。インクジェットプリントの写真画像の一部をヤスリや電動消しゴムで消去したり、ハンダごてで焼き抜いたりして制作されるインスタレーション的な作品は、グループ展などでこれまでも何度か目にしたことがあるのだが、今回G/P GALLERYで開催された個展を見て、多くの可能性を秘めた作家だと感じた。
出品作品は、「打ち寄せる波のイメージを母と共に焼いた」という「I am in You」(2015~)、そして新作の《ID(transition)》と「Family Ritual」である。画面に無数の小穴が開いていたり、紐状の神経繊維が絡み合っていたりするように見える作品は、その物質性の強調に目を奪われがちだが、そこには現実世界をこのようにしか把握できないという強固な確信と、このように把握したいという切実な願望が宿っている。多和田は写真作品制作を通して、まさに自らに「悪魔祓い」の儀式を施すことを希求し続けており、最終的にはそれが自己と他者との関係の修復(セラピー)に繋がってくるということではないだろうか。これまでは、個人的な体験を発想の核に据えることが多かったが、新作では公共図書館のアーカイブスなどから引用したイメージも取り込むようになってきている。今回は、会場のスペースの関係で小品が中心だったが、より大きなサイズの作品を含むまとまった展示をぜひ見てみたい。
20180831 / Yuki Tawada / Photography by Fuyumi Murata
2018/09/05(飯沢耕太郎)
津田洋甫展──初期作品 1950-60年代
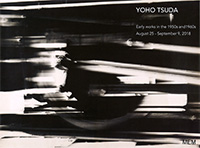
会期:2018/08/25~2018/09/09
MEM[東京都]
津田洋甫(1923~2014)は、奈良県吉野郡大塔村(現・五條市)の出身。1949年に大阪の浪華写真倶楽部(1904年創設)の会員となり、以後同倶楽部の中心メンバーのひとりとして活動した。津田の仕事のなかでは、1960年代後半以降の樹木、水をテーマにした自然写真がよく知られている。だが、今回の展示は、それ以前の「初期作品」によるものだった。
戦前の浪華写真倶楽部は、丹平写真倶楽部、芦屋カメラクラブとともに、関西「新興写真」の展開に中核的な役割を果たしていた。戦後になると、絶大な影響力を持つ指導者だった安井仲治が1942年に死去したこともあって、前衛的、実験的なスタイルは次第に影を潜め、穏当な「サロン写真」の団体に変わっていく。だが、今回展示された津田の作品を見ると、戦後の一時期までは、「一人一党」と称される個性的な表現を追求する傾向が、まだしっかりと残っていたことがよくわかる。戦争の傷跡がまだ生々しく残る建物や風景を、やや強引とさえ思えるような解釈で、コントラストの強いモノクロームの画面に定着していく津田のこの時期の写真群には、力強い生命力が脈打っていた。
残念ながら、そのテンションの高い作品制作は長くは続かなかった。1950年代になると、土門拳が主唱した「リアリズム写真」の影響が関西にも波及し、津田も社会的なドキュメンタリーへの関心を強めていく。さらにその後は自然写真を多く手がけるようになった。それでも1940~60年代初頭の時期には、津田に限らず戦前の「新興写真」を継承していこうとする動きは、全国的に展開されていたはずだ。そのあたりの動きを、もっときちんと掘り起こし、検証していかなければならないだろう。
2018/09/05(飯沢耕太郎)
川田喜久治「百幻影」

会期:2018/08/31~2018/10/11
キヤノンギャラリーS[東京都]
あらためて、川田喜久治という稀代の写真家の底力を見せつけられた。東京・品川のキヤノンギャラリーSの空間を黒い箱に見立て、そこに100点のフレーム入り大判プリント(すべて川田自身によるプリントワーク)が並べている。中心になっているのは1970年代の「ロス・カプリチョス」と80年代に開始された「ラスト・コスモロジー」の2シリーズだが、それ以前や2010年代以降の作品も含まれていた。
特筆すべきは、かなり長いスパンで撮影・制作されているにもかかわらず、作品のテンションにまったく弛みがなく、しかも一貫した指向性が貫かれていることである。会場に掲げられていたコメントには、「写真をストレートのままでなく、角度を変えながら、現れてくる世界も探ってみたい」、あるいは「夢のなかの光景が、現実を逆襲するようなトーンを思い浮かべたりした」と記されていた。このような反写実的、反現実的な作風は日本においてはむしろ稀である。その制作姿勢を、ごく初期を除いて、1960年代以来ずっと保ち続けてきたこと自体が、驚嘆すべきことといえる。
シリーズや年代ごとの括りをはずして、作品を一旦シャッフルし、イメージ相互の関係性を注意深く吟味しながら再構成した展示のレイアウトも、とてもうまくいっていた。それに加えて、田中義久がデザインしたという特注の展覧会ポスター10枚が、写真作品の合間に効果的に配置されている。1933年生まれの川田は今年85歳になるが、若々しい創作意欲にまったく衰えを感じない。これもまた驚くべきことだ。
2018/09/05(飯沢耕太郎)
寺門豪「PARADISE」

会期:2018/08/29~2018/09/11
銀座ニコンサロン[東京都]
寺門豪は1976年、栃木県生まれ。2008~09年に東京・四谷のギャラリーニエプスの運営に参加している。今回、銀座と大阪のニコンサロンで開催された「PARADISE」は、気持よく目に飛び込んでくる写真群で構成された、クオリティの高い展覧会だった。会場には「人間が消えた世界を想像しながら、無人の風景を撮影」した縦位置のカラー写真、約60点が並ぶ。すべて2014~18年に首都圏で撮影されたもので、そのなかには旧国立競技場の跡地、建設中の豊洲市場、いじめによる殺人事件の現場となった河原など、「社会的な出来事の舞台になった場所」も含まれている。感情移入を排したそっけない撮り方だが、ここ数年間に東京とその周辺を覆い尽くそうとしている、鬱陶しい空気感がじわじわと伝わってくるように感じた。
ただ、2枚の写真を1枚の印画紙にプリントして並置する会場構成が、うまくいっているかどうかは微妙だ。寺門の意図としては「個々の風景に没入するのではなく、それぞれを相対化」するということのようだが、むしろ2枚の写真の相互関係が気になってしまう。時折、1枚の写真だけをフレームに入れて展示しているのも、やや不徹底な印象を与える。また、「①人間の不在、②過去の消失、③場所の変質」を経て、そこから出現してくる世界を「PARADISE(楽園)」と呼びたいというコメントもあったが、ではなぜそれが「PARADISE」なのかという理由も明確ではない。コンセプトを形にしていくプロセスを、もう少し丁寧に追求していくと、より見応えのある作品に成長していきそうだ。
2018/09/04(飯沢耕太郎)
立木義浩「Yesterdays 黒と白の狂詩曲(ラプソディ)」

会期:2018/09/01~2018/09/29
CHANEL NEXUS HALL[東京都]
会場に掲げてあった立木義浩のコメントは以下のように書かれていた。
「ここには『世の大事』は写っていない。スナップは今(時代)を呼吸しながら撮るものだ。頭のなかで熟成したイメージを再現するものではない。」
たしかにその通りだが、では行き当たりばったりに街に出て、目についた被写体にカメラを向ければ、それでいいスナップ写真が撮れるかといえばそうではないだろう。スナップ撮影には、むろん優れた動体視力と撮影機材を正確に使いこなす能力が必要だが、それ以上に「イメージの熟成」が不可欠なのではないだろうか。この場合の「イメージ」とは、空からつかみ出すようなものではなく、長年の経験に裏づけられた、事物がこのように配置されているべきだという精妙かつ流動的な確信である。そのような「イメージ」と現実の場面とが交錯し、スパークする時に、上質のスナップ写真特有の冴え渡った画面構成が生じてくることは、アンリ・カルティエ=ブレッソン以来のスナップの名手たちの仕事が教えてくれることだ。
立木義浩もまた、写真家として本格的に活動し始めた1950年代末以来、スナップ撮影の実践に磨きをかけ、その本質を探求し続けてきた。むろん彼には、ポートレート、ファッション、ヌード、ドキュメンタリーなど、多彩な領域にまたがる優れた仕事がたくさんあるのだが、スナップ写真こそ、それらの写真を支えるベースになってきたことが、今回の展示を見てよくわかった。広々とした開放的な雰囲気の空間に、6×6判のモノクローム写真(女性モデルを街で撮影した「フォト・セッション」も含む)を中心に、縦位置の大判カラー写真を配し、心地よく耳に残るジャズのスタンダードナンバーを流した会場構成も見事に決まっていて、贅沢な気分を味わわせてくれる写真展になっていた。
2018/09/04(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)