artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
原田裕規「心霊写真/マツド」

会期:2018/07/01~2018/08/05
山下ビル[愛知県]
今年4月に東京のKanzan Galleryで開催された「心霊写真/ニュージャージー」展、そして続編の「心霊写真/マツド」展へと展開する原田裕規の関心は、おそらく、「ファウンドフォト」という手法ないしは問題機制をめぐり、匿名的な市井の撮影者/アーティスト/キュレーターという「複数の主体の座」の侵犯や撹乱にある。
先行する「心霊写真/ニュージャージー」展と同様、本展は以下4つの構成要素からなる。1)清掃やリサイクル業者から原田が引き取った、「捨てられるはずだった写真」の膨大な山。「心霊写真」というタイトルが呼び起こす期待とは裏腹に、それらは家族や友人のスナップ、行事や旅行先での記念撮影、風景写真など、ごく普通のアマチュア写真であり、モノクロとカラーが混在する。一部は輪ゴムで束ねられ、「飛行機」「宴会」といったグルーピングが読み取れる。「謎の静物」「花、オールオーバー」などの分類メモを原田が記した付箋が付けられたものもある。2)一部のみが大きく引き伸ばされ、ネガポジ反転した画像。スマートフォンのネガポジ反転機能を用いると、「元の正しい色調の画像」が液晶画面内に浮かび上がる。3)上述1)の写真から選ばれ、額装された写真。4)「百年プリント」と書かれたDPE袋と、郊外の平凡な風景を写した写真。その表面は時間を経たように黄ばんでいるが、この「黄ばみ」は原田によりPhotoshopで補正された人工的な着色である。

《百年プリント:マツド》
ここで、ファウンドフォトを用いた例として、例えばフィオナ・タンの《Vox Populi(人々の声)》や木村友紀のインスタレーション作品が想起される。《Vox Populi(人々の声)》は、展覧会開催地に住む人々からタンが収集したアマチュア写真を、構図や被写体の人数、ポーズ、撮影シーンなどでグルーピングし、ある地域や文化圏の住民が無意識的に共有する「写真のコード」のマッピングを浮かび上がらせようとする試みだ。また、木村友紀は、「発見された写真」を元の文脈からズラし、ある形態や色彩といった細部をトリガーに、別の写真やオブジェと接続させて読み替えるインスタレーションを制作する。こうしたタンや木村と異なり、1)での原田は収集した写真を一方では方向づけてコントロールしようとしつつも、半ば放棄している。観客は、「整理途中の写真の山」を実際に手に取って一枚ずつ眺めることができ、組み換えて別のグルーピングの束をつくることも許可されている。つまり観客が目にするのは、アルバムから引き剥がされて元のコンテクストを失い、アーティストによって選別された「ファウンドフォトの作品」としての新たな登録先もまだ得ていない、浮遊状態の写真なのである。原田はここで、「埋もれた匿名的な写真」を独自の視点で「発見」し、「新たな(美的、文化史的、記録的……)価値」を付与する特権的な「作者」として振る舞うことを自ら放棄している。それは、「ファウンドフォト」という手法に潜む「一方的な簒奪」 「私物化」といった暴力性に対する、批評的な態度の表明と言える。
その一方で、3)の額装された写真は、「任意の写真を選別し、フレームという装置によって他と聖別化する」行為を前景化させ、キュレーションの権力を発動させることで、アーティスト/キュレーターの職能的な弁別を撹乱する。また、4)において原田は、技術的卓抜やアーティストとしての視点の独自さを示すわけでもない。人工的な褪色を付けられた匿名的な風景の写真は、「平凡なアマチュア写真」の撮影者に自らを擬し、さらに「時間的経過」の味付けをフィクションとして加味することで、1)の収集された写真群の匿名的な撮影者の立場に自らの身を置こうとする身振りである。「撮影者の気持ちを想像して書いた文章を添える」というもうひとつのフィクショナルな仕掛けが、この偽装をより強調/暴露する。
「ファウンドフォト」の作者としてのアーティスト/キュレーター/アマチュア写真の撮影者。原田はその役割を演じ分け、曖昧化・多重化させることで、境界を侵犯的に撹乱させる。一枚の「ファウンドフォト」には、被写体となった人物だけでなく、撮影した者、現像した業者、現像された写真にかつて眼差しを注いだ者、その写真に新たな光を当てる「アーティスト」、その「ファウンドフォト」を展示作品として選別するキュレーターなど、複数の主体の関与や眼差しが透明ながら密接に折り重なっている。写真それ自体には写らない亡霊のような「彼ら」の存在をこの場に召喚し、写真の背後に透かし見ようとすること。それこそが、原田の試みにおける「心霊写真」の謂いである。

会場風景

原田が収集した、約1万枚の写真
2018/07/29(日)(高嶋慈)
山田實「きよら生まり島──おきなわ」

会期:2018/07/17~2018/07/30
山田實は1918年、兵庫県生まれ。1920年に一家で故郷の沖縄に戻り、以後、中国大陸で終戦を迎え、シベリアに抑留された1941~53年を除いては、那覇で暮らして続けてきた。2017年に惜しくも亡くなったが、存命ならば100歳ということで、その「生誕100年」を記念して開催されたのが本展である。
山田は沖縄に帰った1953年から那覇で山田實写真機店を営み、沖縄写真界の中心人物のひとりとなった。東松照明をはじめとして、「内地」の写真家が沖縄を訪れたときに、さまざまなかたちで便宜を図ることも多かった。その傍ら、アメリカ軍統治時代から本土復帰に至る沖縄の人や暮らしを丹念に撮影し、厚みのある写真群を残した。今回展示された、金子隆一のセレクトによる1950~60年代のスナップ写真40点を見ると、山田のしなやかだが強靭な眼差しの質がくっきりと浮かび上がってくる。どの写真を見ても、被写体を細部までしっかりと観察しながら撮影しているているのがわかる。例えば少女がコカコーラのマークが入っている缶で水浴びをしている写真があるが、山田は明らかにそこに目をつけてシャッターを切っている。一見穏やかな作風だが、じっくりと見ていくと、沖縄の社会的状況に対する怒りや哀しみが、じわじわと滲み出てくるような写真が多い。
山田を含めた沖縄の写真家たちの系譜を、きちんと辿り直す写真展をぜひ見てみたい。そろそろ、どこかの美術館がきちんと企画するべきではないだろうか。
2018/07/21(土)(飯沢耕太郎)
内倉真一郎「十一月の星」

会期:2018/07/13~2018/08/04
EMON PHOTO GALLERY[東京都]
東京・広尾のEMON PHOTO GALLERYが主宰するEMON PHOTO AWARDも回を重ね、昨年第7回目を迎えた。今回開催された内倉真一郎の個展は、そのグランプリ受賞の記念展である。どちらかといえば現代美術寄りの作品が目立っていたEMON PHOTO AWARDの受賞作だが、今回の内倉の「十一月の星」は、モノクロームの正統派の写真作品である。僕も審査員のひとりだったのだが、受賞が決定したとき、彼の写真のやや古風なたたずまいが、ギャラリーのスペースにうまくフィットするかどうかがやや心配だった。だが、結果的には、応募作よりもひと回り作品のスケールが大きくなるとともに、ギャラリーの空間構成にあわせて弓形に作品を吊り下げるインスタレーションもうまく決まって、見応えのある展示になっていた。
内倉は 1981年、宮崎県生まれ。今回の展示のテーマは2016年の第一子の誕生である。ともすれば紋切り型な解釈に陥りがちな被写体ではあるが、クローズアップを多用してストレートな表現を心がけ、赤ん坊の生命力の根源に迫ろうとしている。審査の時点では、テンションの高い写真が多く、やや押し付けがましく感じるところもあった。だが、展示では植物や風景のイメージをうまく配して表現を和らげている。また妊娠中の妻の写真を加えたことで、シリーズとしての膨らみも生じてきた。
とはいえ、この作品は文字通りのスタートラインだと思う。新たなテーマにもチャレンジすることで、作品世界のさらなる展開を期待したい。
2018/07/19(木)(飯沢耕太郎)
鼻崎裕介「City Light」
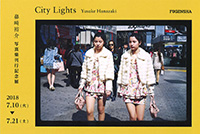
会期:2018/07/10~2018/07/21
ふげん社[東京都]
ふげん社から鼻崎裕介の新しい写真集『City Light』が刊行されたのに合わせて、ギャラリースペースで写真展が開催された。写真集の内容を的確に紹介するとともに、壁面に校正刷りを貼り付ける工夫もあって、すっきりと、よくまとまった展示を実現していた。
鼻崎は1982年、和歌山県出身で、2007年に東京ビジュアルアーツ卒業後、東京・四谷のギャラリーニエプスに参加して活動を続けている。作風はまさにオーソドックスなストリート・スナップというべきだろう。一番近いのは、日本のカラー写真のスナップの先駆である牛腸茂雄の『見慣れた街の中で』(1981)である。被写体を路上で捕捉する距離感の設定の仕方、色(特に赤と黄色)に対する素早い反応、光よりは「翳り」に引き寄せられていくようなカメラワークなど、牛腸と共通する要素が多い。表紙に双子の写真が使われていることも、牛腸のもう一つの代表作『SELF AND OTHERS』(1977)を連想させる。ただこのままだと、牛腸を含む「コンポラ写真」の焼き直しに終わってしまいそうだ。日本の写真家たちが築きあげてきた、ストリート・スナップのオーソドキシーを踏まえつつ、そこからどう出ていくかが今後の課題になるのではないだろうか。
鼻崎は和歌山県田辺市の出身だと聞いた。東京や大阪のような都会の路上ではなく、田辺のような独特の風土性を持つ場所にこだわってみるのもいいかもしれない。「路上の経験」をもっと多様な方向に開いていくべきだろう。
2018/07/19(木)(飯沢耕太郎)
平林達也「白い花(Desire is cause of all thing)」

会期:2018/07/18~2018/07/24
銀座ニコンサロン[東京都]
1961年、東京生まれの平林達也の新作「白い花」も、「ピクトリアリズム」の美意識を取り込んだ作品である。こちらは、大正から昭和初期にかけて、日本の「芸術写真」の主流となった「ベス単派」の再現というべき写真が並ぶ。大正初年から日本に輸入された単玉レンズ付きのヴェスト・ポケット・コダック・カメラは、比較的値段が安かったのと、絞りを開放にするとソフトフォーカスの画面になることで、当時のアマチュア写真家たちが「芸術写真」を制作するのに好んで使用した。高山正隆、山本牧彦、渡辺淳、塩谷定好らの作品は、彼らの理論的な指導者であった中島謙吉が「情緒、気分、想念、さうした抽象的の感覚」と称した高度な作画意識を繊細なテクニックで実現しており、近年、国内外で再評価の機運が高まっている。
平林は、その「ベス単派」へのオマージュをこめて、キヨハラ製のソフトフォーカスレンズを使った作品を構想した。花、森、女性、水などの被写体もほぼ共通しているのだが、単なる懐古趣味や絵空事に終わらないリアリティを感じる。それは、もともと平林の関心が、「あらゆる生命の根本的な命題」である「欲望と環境」に向けられているからだろう。つまり「ベス単派」の作品よりも、より生々しい、切実さを感じさせる写真が並んでいるのだ。平林は東海大学卒業後の1984年にドイに入社し、2003年には銀塩写真のプリントに定評があるフォトグラファーズ・ラボラトリーを設立した。銀塩写真の暗室作業は、その意味で、彼にとってほかに代えがたい作品制作のプロセスといえる。特に今回の展示作品には、黒の締まりと光の滲みとを両立させるために、高度なプリントのテクニックが活用されていた。
なお、展覧会にあわせてUI出版から同名の写真集(装丁・長尾敦子)が刊行された。本展は8月23日~8月29日に大阪ニコンサロンに巡回する。
2018/07/18(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)