artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
萩原朔美の仕事展

会期:2017/04/15~2017/07/02
昨年、萩原朔美が「萩原朔太郎記念 水と緑と詩のまち 前橋文学館」の館長に就任した。萩原朔太郎の孫というこれ以上ない出自に加えて、演出、編集、エッセイスト、映像・造形作家としての多面的な活動を展開している彼は、まさに同館の館長に適任といえるだろう。その萩原の「就任1周年」を記念して企画・開催されたのが本展である。「映像」、「アートブック」、「写真」、「編集」の各パートに、目眩くように多彩な作品が展示されていた。
ここでは、写真のパートを中心に見てみよう。萩原の写真の基本的な手法は「定点観測写真」である。同じポーズをとる「20代」と「60代」のポートレート。2、3歳の頃に撮影された小田急線の電車に万歳している彼の写真を、20代、30代、60代で再現した写真シリーズなどを見ていると、時の経過とともに、否応なしに死─滅びへと向かっていく人間の運命を感じてしまう。これらの「定点観測写真」もそうなのだが、萩原の写真作品にはつねに「差異と反復」に対するオブセッションがあらわれてくる。「変容を観察し変容の度合いを測ることに面白さを見出す」という彼の志向は、カメラ機能付きの携帯電話の登場でより加速してきているようだ。道路上の「丸いもの」を撮影した《circle》、鏡に自分を映して撮影した《selfy》、路上の「止まれ」の表示を、文字通り立ち止まって撮影した《とまれ》など、携帯電話で撮影した写真群は、驚くべき数に達している。物事の微妙な「差異」に徹底してこだわり、「反復」を積み重ねて視覚化していく試みは、彼自身の生と分かち難く密着することで、これまで以上に広がりを持ち始めているのではないだろうか。
萩原は、先頃東京都写真美術館で個展を開催し、6月5日に亡くなった山崎博と日本大学櫻丘高校の同級生だった。17歳の頃「写真家になる」と宣言した山崎に刺激されて、彼自身も写真家になりたいと思った時期があったという。その望みは、果たされなかったわけだが、山崎と共通する、写真というメディアの可能性を、あくまでもコンセプチュアルに問い続けていく志向は、いまなお彼のなかに脈打っている。「写真家・萩原朔美」の仕事をもっと見てみたい。
2017/06/03(土)(飯沢耕太郎)
糸川燿史写真展「大阪芸人ストリート」~1994年から1999年『マンスリーよしもと』の扉を飾った芸人たち~

会期:2017/06/01~2017/06/18
10Wギャラリー[大阪府]
大阪を拠点とするベテラン写真家で、1970年代初頭の関西フォークのミュージシャンを捉えた写真集『グッバイ・ザ・ディランⅡ』や、村上春樹の1作目の長編小説を映画化した「風の歌を聴け」のスチールで構成される『ジェイズ・バーのメモワール』などで知られる糸川燿史。本展では彼が1994年から1999年に『マンスリーよしもと』の表紙のために撮影した写真のなかから、精選した約130点が展示された。写っているのは、池乃めだか、末成由美、間寛平、チャンバラトリオ、坂田利夫、チャーリー浜などのお笑い芸人たち。約20年前の写真なので、当然ながら皆若い! なかにはすでに解散した漫才コンビや、最近はテレビで見なくなった芸人の姿もあり、時の流れが感じられた。お笑い芸人のポートレートはふざけた表情やポーズを連想しがちだが、糸川はそれを良しとしなかった。彼らを大阪各地に連れ出し、同時代の風景とともに撮影したのだ。それにより作品は、単なるポートレートを超えた時代のドキュメントとして成立している。ベタに陥りがちな素材を上手に料理した写真家の勝利である。
2017/06/01(木)(小吹隆文)
マスター・プリンター 斎藤寿雄

会期:2017/05/30~2017/07/02
JCIIフォトサロン[東京都]
世界的に見ても珍しい写真展といえるだろう。斎藤寿雄は1938年東京生まれ。1953年に株式会社ジーチーサンに入社して以来、写真印画のプリンター一筋で仕事をしてきた。1969年にドイ・テクニカルフォトに、2004年にはフォトグラファーズ・ラボラトリーに移るが、篠山紀信の「NUDE」展(銀座・松坂屋、1970)から、荒木経惟の「Last by Leica」(art space AM、2017)まで、そのあいだに手がけた写真展は数えきれない。1973年にはニューヨーク近代美術館で開催された「New Japanese Photography」展の出品作のプリントもおこなっている。名実ともに日本を代表するプロフェッショナルのプリンターといえるだろう。
今回の展示は、斎藤が思い出に残っているという写真家42人から、あらためてネガを借りてプリントした作品を集めたものだ。このようなプリンターの仕事に焦点を合わせた企画は、これまでほとんどなかったのではないだろうか。出品作家の顔ぶれが凄い。浅井慎平、荒木経惟、石内都、伊奈英次、宇井眞紀子、江成常夫、大石芳野、金村修、鬼海弘雄、北島敬三、蔵真墨、郷津雅夫、今道子、笹岡啓子、笹本恒子、佐藤時啓、篠山紀信、田村彰英、土田ヒロミ、東松照明、徳永數生、土門拳、長島有里枝、長野重一、ハービー山口、平林達也、広川泰士、深瀬昌久、細江英公、前田真三、正木博、松本徳彦、宮本隆司、村井修、村越としや、森山大道、山口保、山端庸介、山本糾、吉行耕平、渡邉博史、Adam Dikiciyan。こうして見ると、それぞれの作品に即して、プリンターの仕事の幅が大きく広がっていることがわかる。たとえデジタル化がさらに進行したとしても、斎藤のプリントから確実に伝わってくるアナログの銀塩写真の魅力は、薄れることがないのではないだろうか。今回はモノクロームのプリントだけだったが、カラーも含めた展示も見てみたい。
2017/06/01(木)(飯沢耕太郎)
鈴木のぞみ個展 Mirrors and Windows
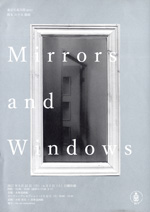
会期:2017/05/22~2017/06/03
表参道画廊[東京都]
窓や鏡に焼きつけた写真を10点ほど展示。窓と鏡は外界を見透す、または写し出すことから、しばしば絵画や写真のたとえとして用いられてきた。鈴木はその窓と鏡に外界のイメージを定着させることで「たとえ」を固定化しようとする。窓ガラスには実際にその窓から見えた風景が焼きつけられ、手鏡にはそれを使っていた人物の顔、壁掛けの鏡には室内風景がプリントされる。窓や鏡が長年見続けてきた光景が、こうして永遠に焼きつけられたわけだ。窓ガラスの風景はニエプスの最初の写真を想起させ、鏡はダゲレオタイプの銀板を思い出させる。そして窓にも鏡にも枠(額縁)がはめられていることも偶然ではないだろう。絵画出身の作者らしい発想だ。
2017/05/31(水)(村田真)
澤田華「ラリーの身振り」

会期:2017/05/30~2017/06/04
KUNST ARZT[京都府]
「写真」「複製」「認知」をめぐるゲームを仕掛ける澤田華の個展。ギャラリーに入ると、古い街灯のモノクロ写真が背丈を超えるサイズに引き伸ばされ、壁のように立ち塞がっている。傍らには、元の写真が掲載された洋書を入れ子状に写した写真があり、元の写真図版を指差す手も写っている。また、その写真図版のキャプションを訳した文章も掲示される。一方、それらの横には、粗い解像度のドットで印刷された不鮮明な画像が展示されている。何か黒っぽいものの上に白っぽいものが乗っかっているように見えるが、何なのかは分からない。奥へ進むと、同じ画像がモニターに映され、「こんな形のものではないか」と推測するいろいろなパターンの輪郭線が次々と表示されていく。別のモニターでは、同じ画像にトリミング、解像度、画像サイズの差異をさまざまに施し、Google画像検索にかけた結果が次々と羅列されていく。「ハンドバッグ」「透明な石鹸の泡」といった理解可能な検索結果もあれば、「Photoshopの底なし」「コピー&ペーストの顔」など意味不明なものもあり、「正解」は分からない。そして最後に、粘土でほぼ実物大に「復元」した物体が提示されている。これは一体何だろう。一巡して戻ると、引き伸ばされた街灯の写真の中に、小さくあの「ナゾの物体」が写っているではないか。つまりこれらは、元の写真図版の中に「発見」した正体不明の物体を突き止めるべく、写真を複写し、引き伸ばし、分析と検証を加え、立体化して復元する試みなのだ。
澤田はこれまで、《Blow-up》シリーズにおいて、印刷物や画像投稿サイトの写真画像を元に、写り込んだ「正体不明の物体」を検証するため、写真を引き伸ばし(Blow-up)、形態を分析し、3次元の物体として再物質化するプロセスを作品化してきた。それは、デジタル画像の修正が当たり前となった現代において、「ノイズ」として排除される要素を救出する身振りともとれる。また、撮影時に企図された写真の「主題」「意味」の中心から外れた周縁部、些末な細部への執拗なこだわりは、バルトの言う「プンクトゥム」を想起させる。さらに、画像の細部を拡大し、執拗に分析して特定しようとする手続きとその「失敗」は、衛星画像や監視カメラの画像解析によって「秘密の軍事施設」「犯罪の証拠」を発見しようとする監視システムへの批評ともとれる。
写真は現実を「複製」する。2次元に置換された複製イメージから、「元の物体」を復元/再物質化する。この二重の「複製」を介した手続きとそれが内包するズレへの注目は、画像イメージが「データ」として流通し、デジタル画像の加工や3Dプリンターによる立体造形といったテクノロジーに親和性を覚える時代的感性と言える。だが澤田作品の要は、何重もの情報の加工過程を実演しつつも、「元の物体」の正体を宙吊りのまま提示する点にある。「写真とテクストと実物」の提示は、コスースの《1つおよび3つの椅子》を想起させるが、ここでは、視覚記号としての写真と言語による定義と(復元された)実物は、(互いにズレを照射しつつも)「椅子」といったひとつの観念へと統合されるのではなく、写真の表面に「プンクトゥム」として付けられた「小さな傷」を押し広げ、分裂させ、写真が証立てる「かつてあった過去」を「ありえたかもしれない無数の可能態」へと増殖させていく。そのとき写真は、被写体の同一性を証立てる絶対的な根拠ではなく、むしろ亡霊のような近似値を際限なく生み出す装置となるのであり、「写されたもの」の認識をめぐる私たちの眼差しの審級こそが疑問に付されている。

澤田華《Gesture of Rally #1705》2017
2017/05/30(火)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)