artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
大西みつぐ「放水路」

会期:2014/06/18~2014/07/01
銀座ニコンサロン[東京都]
荒川放水路は明治末から昭和初期に書けて掘り進められた人工の川。「放水路」といっても川幅はかなり広く、周辺には変化に富んだ風景が広がっている。
大西みつぐは、かつてこの川の近くに住んだこともあり、「放水路」は「河口の町」(1985年)、「砂町」(2012年)といった作品の重要な舞台ともなってきた。だが今回銀座ニコンサロンで発表された約50点の写真群(9月4日~17日に大阪ニコンサロンに巡回)は、ノスタルジックな「下町」のたたずまいを浮かび上がらせる前作とは、かなり肌合いが違う。のんびりと散策を楽しむ人々も写ってはいるが、ブルーシートのホームレスの家、焚き火の痕、放置されたゴミ袋など、至る所に荒廃の気配が漂う。写真展のコメントに「東日本大震災後の東京臨海部の風景が無防備に曝されていることへの焦燥感」と記しているのを見てもわかるように、作品全体を貫いているのは、どうやら沸々と煮えたぎる怒りの感情なのではないかと思えてくるのだ。大西が作品の中で、ここまで“政治性”をあからさまに表明することはなかったのではないだろうか。「放水路」を「日本の澱」の象徴として捉えようという姿勢が、くっきりと形をとってきている。
下町の、穏やかで、ゆったりとした雰囲気を掬いとった路上スナップを期待する大西のファンにとっては、肩すかしを食うような展示かもしれない。だが、その変化は「震災後」の写真のあり方を彼なりに引き受けていこうという決意のあらわれでもある。これから東京オリンピックに至る時期の東京の景観の変化を、どう捉えて定着していくかは、多くの写真家たちにとっての大事な課題となっていくだろう。
2014/06/22(日)(飯沢耕太郎)
榮榮&映里「妻有物語」

会期:2014/06/11~2014/07/12
ミヅマ・アート・ギャラリー[東京都]
中国人の榮榮(ロンロン)と日本人の映里(インリ、本名鈴木映里)のカップルは、1990年代から二人の身体性を重ね合わせるような作品を制作してきた。今回、東京・市谷のMIZUMA ART GYALLERYで展示された「妻有物語」は、2012年の「大地の芸術祭」(越後妻有アートトリエンナーレ)への参加を機に構想・制作されたシリーズである。雪深いその地域の温泉や田んぼを背景にして、榮榮、映里、そして彼らの三人の息子たちによるパフォーマンスが展開される。
以前の彼らの作品には、自らを取り巻く社会状況への違和感を、激しく挑発するような身振りで表明するものが多かった。だが年齢を重ね、家族の絆が深まるとともに、作品の質も少しずつ変化してきた。今回のシリーズの基調となっているのは、不安や苛立ちではなく共感と安らぎである。それは彼らの作品の質感にも明確にあらわれていて、以前のコントラストの強いくっきりとしたモノクロームプリント(時に手彩色が施される)に変わって、柔らかな白っぽいトーンが選ばれている。手彫りの白木のフレームや、茶室のような空間へのインスタレーションなども、以前にはなかった試みだ。
これらを表現意識の弛み、テンションの低下と見ることもできるだろう。だが、彼らが「新たな概念のもとプリントを作り直した」のは、相当の覚悟を決めてのことだったのではないだろうか。中国と日本を行き来しつつ、新たな家族像の再構築と作品の展開を同時に進めていこうという、強く、しなやかな意志を感じとることができる展示だった。
2014/06/21(土)(飯沢耕太郎)
「バルテュス 最後の写真─密室の対話」展

会期:2014/06/07~2014/09/07
三菱一号館美術館(歴史資料室)[東京都]
東京都美術館で開催された「バルテュス展」(4月19日~6月22日、7月5日~9月7日に京都市美術館に巡回)にあわせて、とても興味深い写真展が開催された。「20世紀最後の巨匠」バルテュス(1908~2001)は、1992年~2000年にかけて、アトリエのあるスイス・ロシニエールのグラン・シャレーの一室で、アンナ・ワーリという少女をモデルに油彩画を描いていた。彼は繰り返し綿密なデッサンを描いてから本格的に制作に取りかかるのだが、この頃になると指先のコントロールがむずかしくなってくる。そこで、鉛筆でのデッサンの代わりに用いるようになったのが、カラー・ポラロイド写真であり、8年間に約2000枚が撮影されたという。そのうち約170枚を選んで、「バルテュス創作の秘密」を解きあかそうとしたのが本展である。
バルテュスはソファに横たわる少女のポーズを微妙に変えながら、光線を吟味しつつ、何枚も続けてシャッターを切っている。それはむろん、絵画作品の下絵として使用するためなのだが、写真を見ていると、単純にそうともいい切れないのではないかと思えてきた。つまり、撮影を続けているうちに、彼はポラロイド写真というメディウムの不思議な魅力に、次第に絡めとられていったのではないだろうか。ポラロイド独特のぬめりを帯びたテクスチュア、ほのかな光の中に震えるようにして出現する少女の裸体の官能性、8歳の少女が大人の女性へと変容していくプロセスを記録していくことの面白さ、それらをバルテュスは歓びとともに受け入れ、撮影の行為にのめり込んでいったのではないかと想像できるのだ。
残念なことに、彼の写真の仕事は最晩年の時期に集中している。もう少し時間があれば、「写真家・バルテュス」のさらなる飛躍を見ることができたかもしれない。
2014/06/20(金)(飯沢耕太郎)
石内都「幼き衣へ」

会期:2014/06/05~2014/08/23
LIXILギャラリー[東京都]
石内都は多摩美術大学で染織を学んだという経歴を持つ。そのためもあるのだろうか。布を被写体とする時には、独特の嗅覚を働かせ、テンションの高い作品になることが多いように思う。広島の原爆資料館の遺品を撮影した「ひろしま」のシリーズがそうだし、近作の『Frida by Ishiuchi』(RM)でも、メキシコの女流画家、フリーダ・カーロの遺品の衣裳をテーマにしている。今回東京・京橋のLIXILギャラリーで開催された「幼き衣へ」も、いかにも石内らしい作品に仕上がっていた。
本展は同時期に隣接するギャラリースペースで開催中の「背守り 子どもの魔除け」展の関連企画である。背守りとは子どもの着物の背中に縫い付けられた魔除けのお守りのことで、背後から忍び寄る魔物を防ぐために、糸で印をつけたり、刺繍を縫い込んだりする。石内都は、それらの愛らしく、心を打つお守りを中心に、お寺などに奉納、保存されている背守りのついた着物を丹念に撮影していった。
石内の撮影の仕方は、いわゆるカタログ写真とは一線を画する。着物の全体像を精確に指し示すよりは、むしろ心惹かれる細部にこだわり、画面の傾きやピンぼけなども意に介さず撮影している。結果として、その着物を実際に身に着けていた子どもたちの存在までも想像させるような力が備わっているように感じる。大小19点の作品を、バランスよく配置していくインスタレーションも、よく練り上げられていた。本年度のハッセルブラッド国際写真賞を受賞するなど、石内の充実した仕事ぶりが、作品にもよくあらわれていた。
2014/06/20(金)(飯沢耕太郎)
オサム・ジェームス・中川「GAMA CAVES」
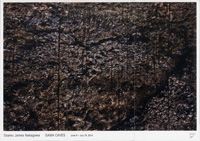
会期:2014/06/06~2014/07/19
フォト・ギャラリー・インターナショナル[東京都]
1962年にアメリカ、ニューヨークに生まれ、日本で幼少期を過ごし、テキサス州ヒューストン大学で写真を学ぶ。この経歴を見ると、オサム・ジェームス・中川が、写真を通じて「日本とアメリカという二つの国にまたがる自身のアイデンティティ」を探求する方向に進んだのは当然といえるだろう。長くアメリカ軍の統治下にあった沖縄は、彼が結婚した女性の出身地でもあった。
2000年代以降、中川は「バンタ」と称される海に面した崖を撮影し始める。「バンタ」の崖下やその周囲には「ガマ」と呼ばれる洞窟が口をあけていた。「ガマ」は宗教儀式がおこなわれる聖地であるとともに、第二次世界大戦末期に沖縄の住人たちが戦禍を逃れて身を寄せた場所でもあった。中川はその「沖縄の霊魂、祖先、歴史、記憶が宿る神聖な場所」を、懐中電灯で照らし出しながら、長時間露光で撮影していった。今回フォト・ギャラリー・インターナショナルで展示されたのは、昨年、写真集『GAMA CAVES』(赤々舎)として刊行されたこのシリーズから抜粋された作品である。
中川の仕事は、風景のディテールへの異様なほどのこだわりによって特徴づけられる。「GAMA CAVES」でも、闇の中から浮かびあがってくる洞窟の内壁の湿り気を帯びた凹凸が、恐るべき吸引力で眼をとらえて離さない。陶器やガラスのかけら、骨片、貝殻、布のようなものなど、洞窟内での暮らしの痕跡もまた克明にとらえられ、その総体が重い「問いかけ」として見る者に迫ってくる。静かだが力強い作品群だ。
なお、同時期に東京・中野の写大ギャラリーでも「沖縄─GAMA/ BANTA/ REMAINS」展が開催された(6月2日~8月3日)。「GAMA」、「 BANTA」の両シリーズに、沖縄の戦跡を撮影した「REMAINS」を加えた展示である。
2014/06/11(水)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)