artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
荒木経惟「往生写集──顔・空景・道」

会期:2014/04/22~2014/06/29
豊田市美術館[愛知県]
この欄でも荒木経惟の凄さについて何度も書いてきたのだが、豊田市美術館の「往生写集──顔・空景・道」を見て、今さらながら感嘆せずにはおれなかった。もちろん、いい仕事をしている写真家はたくさんいる。だが、写真家という存在のあり方を、荒木ほど全身全霊で全うし続けている写真家は他にいないのではないだろうか。
展示は2部に分かれていて、1963年の「さっちんとマー坊」から99年の「Aの楽園(チロ)」に至る第1部「顔・空景」の作品群は、ほぼ回顧展的な構成である。「地下鉄72」(1972年)、「裔像」(1978年)、「富山の女性」(2000年)など、これまで美術館での展覧会にはあまり出品されてこなかったシリーズも含まれているが、作品の選択、展示の仕方に意外性はほとんどない。
問題はむしろ第2部の「道」である。こちらは新作が中心なのだが、これまでの「荒木世界」を打ち壊し、再構築していくエネルギーの凄みに圧倒された。「遺作 空2」(2009年)、「チロ愛死」(2010年)など既発表の作品もあるが、2013年撮影の新作「道路」と「8月」は、表現者・荒木経惟の底力をまざまざと見せつける傑作である。新居から見下ろした路上を定点観測的に撮影した「道路」を見ていると、身近な光景が彼岸からの眺めのように見えてきて背筋が寒くなる。「8月」は金槌でカメラのレンズを叩き割って撮影した写真群。「フクシマを引きずって、フクシマがあったから、どうしてもどうしても素直に撮れない。だからレンズをぶっ壊す。ぶっ壊してそれで撮る」ということでできあがった作品だ。
前立腺癌の手術、右目の失明といった事態を受け入れつつ乗り切ることで、荒木の創作エネルギーはふたたび高揚期を迎えつつあるのではないだろうか。夏から秋にかけて、同じく「往生写集」のタイトルで開催される資生堂ギャラリー「東ノ空・P(鏡文字)ARADISE」、新潟市美術館「愛ノ旅」の展示も楽しみだ。
2014/06/10(火)(飯沢耕太郎)
荒木経惟「左眼ノ恋」

会期:2014/05/25~2014/06/21
Taka Ishii Gallery[東京都]
一時、体調が悪くなり、作家活動が続けられるかどうか危ぶまれた荒木経惟だが、予想していた通りしぶとく復活してきた。74歳の誕生日にスタートした今回の「左眼ノ恋」展でも、さまざまな工夫を凝らして健在ぶりを強く印象づけている。
「左眼ノ恋」の英語タイトルは「Love on the Left Eye」。これはむろん、オランダのエド・ファン・デル・エルスケンの名作写真集『Love on the Left Bank(セーヌ左岸の恋)』(1956年)のもじりである。荒木は昨年10月に、網膜中心動脈閉塞症という病で右眼の視力を失った。そんな非常事態すらも、作家活動に取り込んでしまうのが荒木の真骨頂で、今回の作品ではカラーフィルムの右半分を黒マジックで塗りつぶして、「左眼ノ恋」と洒落のめして見せたのだ。本来はおさまりのいい構図だったはずの「恋人(こいじん)」のKaoriのヌードや街の情景、カメラを構えるセルフポートレートなどが、黒のパートに侵食されることで、不安定な揺らぎを抱え込むことになる。さらに黒塗りの一部にひび割れが生じたり、塗り残されていたりして、画像の一部がちらちらと見える。想像力を喚起するそのあたりの効果も計算済みということだろう。
今年は豊田市美術館の「往生写集──顔・空景・道」をはじめとして、国内外の数カ所で新作の展示が予定されている。いかにも荒木らしい実験意欲が、まったく衰えていないことがよくわかった。
2014/06/07(土)(飯沢耕太郎)
小原真史・野部博子編『増山たづ子 すべて写真になる日まで』

発行所:IZU PHOTO MUSEUM
発行日:2014年5月9日
2013年10月にスタートし、2014年7月27日まで延長が決まったIZU PHOTO MUSEUMの「増山たづ子 すべて写真になる日まで」展は、じわじわと多くの観客の心を捉えつつある。巨大ダムの建設によって水底に沈んだ岐阜県徳山村で、1977年から10万カットに及ぶという膨大な記録写真を残した増山たづ子の仕事は、写真の撮影と受容の最もベーシックで普遍的なあり方を指し示しているように思えるのだ。
その展覧会のカタログを兼ねた写真集が、ようやくIZU PHOTO MUSEUMから刊行された。2006年に亡くなった増山は、生前に『故郷─私の徳山村写真日記』(じゃこめてい出版、1983年)をはじめとして、4冊の写真文集を刊行している。だが、今回の小原真史・野部博子編の写真集は、その仕事の全般に丁寧に目配りしているとともに、資料・年譜なども充実した決定版といえる。ページをめくっていると、「徳山村のカメラばあちゃん」の行動が巻き起こした波紋が、多くの人たちを巻き込みながら、さまざまな形で広がっていく様子が浮かびあがってくる。
巻末におさめられた「増山たづ子の遺志を継ぐ館」代表の野部博子の文章を読んで、増山の写真の強力な喚起力、伝達力の秘密の一端が見えた気がした。増山は写真を撮り続けながら、昔話の語り部としても抜群の記憶力と表現力を発揮していた。彼女が語る昔話の特徴の一つは「固有名詞が挿入されること」だという。普通は特定の場所、時間、名前抜きで語られることが多いにもかかわらず、彼女の話は「身近な所の話として語りはじめ、さらに地名、人名を入れて語っている」のだ。これはまさに増山の写真とも共通しているのではないだろうか。徳山村の顔見知りの人たち、見慣れた風景、毎年繰り返される行事に倦むことなくカメラを向けることによって、彼女はそこに起った出来事すべてを、「固有名詞」化して記憶し続けようとしたのだ。
2014/06/06(金)(飯沢耕太郎)
幻の前衛写真家──大西茂展
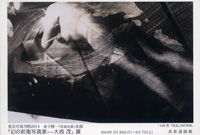
会期:2014/05/26~2014/06/07
表参道画廊[東京都]
本展は写真史家の金子隆一氏の企画で、「東京写真月間2014」の一環として開催された。大西茂(1928~94)の作品、20点がこのような形で公開されたのは初めてであり、「こんな写真家がいたのか!」という驚きを与えてくれる展示だった。この所、急速に進展している日本写真史の再構築に大きく寄与する展覧会といえるだろう。
岡山県出身の大西は北海道大学理学部で数学を学び、1953年に同大学卒業後も研究室に残って研究を続けた。一方で写真にも関心を持ち、55年になびす画廊で初個展を開催、56年の国際主観主義写真展にも出品する。57年には瀧口修造の企画によりタケミヤ画廊で第2回個展を開催する。同年『別冊アトリエ』や『フォト35』にも作品を発表するが、その後は墨象作家として活動するようになり、写真作品の発表は途絶してしまう。
大西の作風は、本展のタイトルにあるように、まさに1930年代に関西や名古屋で大きな盛り上がりを見せた「前衛写真」の衣鉢を継ぐものといえる。だが、シュルレアリスム的なコラージュやオブジェの構成を主流とする戦前の「前衛写真」とも微妙に違っていて、多重露光や現像液を刷毛のようなもので塗布する特殊な処理を多用する画面は、激しく、荒々しいエネルギーを発している。のちに、「アンフォルメル」を提唱したフランスの美術批評家、ミシェル・タピエが彼の墨象作品を高く評価したことでもわかるように、それらは写真という枠組から大きく逸脱していく要素を孕んでいたのだ。
この「遅れてきた(同時に「早過ぎた」)前衛写真家」の作品をどのように位置づけていくかは、今後の大きな課題だろう。また、1950年代という時代に、彼のような作家を生み出していく土壌があったことにも注目していかなければならない。「幻の」写真家は、大西の他にももっといそうな気がする。
2014/06/03(火)(飯沢耕太郎)
門井幸子「春 その春」

会期:2014/05/26~2014/06/08
ギャラリー蒼穹舍[東京都]
門井幸子のような写真家の作品について、うまく伝えるのはむずかしい。被写体になっているのは、ありふれているとしかいいようのない風景であり、撮影の仕方にも特に構えた所はない。それらを隅々までしっかりと気を配ったモノクロームプリントに丁寧に焼き付けて展示する。だが、今回東京・新宿のギャラリー蒼穹舍で展示された「春 その春」のシリーズを見ると、その「何でもない」写真たちが、じわじわと不思議な力で食い込んでくるような気がする。その理由を説明するのがなかなかむずかしいのだ。
彼女の写真集『KADOI SACHIKO PHOTOGRAPHS 2003-2008』(蒼穹舍、2008年)のあとがきにあたる文章に、次のように記されているのを見つけて「なるほど」と思った。
「撮り終えたあともしばらくたたずみ、その風景を見つめながら、消え去ること、そして生き続けることを思う」
誰しも「風景」を前にして、生と死について深い思いに沈むことがあるのではないだろうか。実は写真家は撮ることに集中しているので、そのような沈思黙考の時を過ごすことはあまりない。だが門井の「何でもない」写真群は、それぞれ「撮り終えたあと」の放心と思い入れの時間をたっぷりと含み込んで成立しているように見える。そしてわれわれ観客もまた、2011~14年に北海道、根室半島の早春の時期を撮影した写真を目にした後で、「春 その春」という感慨とともに、緩やかに過ぎていくその時間の厚みを追体験することになるのである。
2014/06/03(火)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)