artscapeレビュー
建築に関するレビュー/プレビュー
宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム

[岩手県]
宮古の付近で、ちょうど崎山貝塚縄文の森ミュージアムのオープンの日に通りかかる。大きな屋根や蛇籠が目立ち、アトリエノルドの設計のようだ。埋蔵文化財センターのエリアが多いせいか、外観ほど展示スペースは大きくない。巻貝型土器など、展示物は面白い。屋外の公園には復元竪穴式住居などがある。
2016/07/16(土)(五十嵐太郎)
宮古市の市役所周辺

[岩手県]
宮古市の市役所周辺へ。もう通常の様子だが、現地を訪れると、ここで前に見た風景を思い出す。やはり、一度でも現場でモノと対峙してると、データや写真ではわからない=代替できない全方位的なスケール感や空間の感覚が身体に残っている。点在している空き地は、おそらく建物が被災し、取り壊された跡だろう。
2016/07/16(土)(五十嵐太郎)
岩手県各所

[岩手県]
竣工:2012年
岩手県をまわる。各地の仮設住居や仮設商店街では、かなり役割を終え、空きが目立つところも散見される。久しぶりの田老町を訪れた。かつて街だったところに野球場が建ち、なるほど防潮堤の描くカーブに輪郭がうまく沿ってはいるが、以前は建物が建っていたことを知っていると、かなりシュールな風景だ。隣に立命館大の宗本研によるサッカーボール型の《ODENSE》が建つ。また近くでコンビニを建設中だった。そして海に散らばっていた、破壊された防潮堤のコンクリートの塊は消えている。建築としては柵に囲まれたたろう観光ホテルだけが震災遺構として、被災の痕跡を示す。もっとも、どこをどう補強して、公開しているのかが、わかりにくい。なお、近くの漁業協同組合に見覚えがあり、2011年に撮った写真を調べると、そのときと同じものが存在していた。つまり、あの津波に耐え、現在普通に使われているのだ。すごいと思うのだが、全然知られていないように思う。
写真:左=上から、仮設商店街、野球場、たろう観光ホテル 右=上から、《ODENSE》、漁業協同組合
2016/07/16(土)(五十嵐太郎)
建築家・槻橋修+建築家・福屋庄子 講演会 建築と都市の未来へ向けて──「失われた街」模型復元プロジェクトに寄せて」

会期:2016/07/09
せんだいメディアテークで開催された東北工業大学50周年記念事業において、槻橋修の「失われた街」講演の後、堀井義博とともに対談に参加した。震災後、津波で破壊される前の街の白模型をつくるというアイデアを初めてメールで受けとったとき、まだ本当の意義はよくわかっていなかったが、これはおそらくいけると思ったことをよく覚えている。実際、その後、住民とのワークショップを通じて、全国の学生たちが制作した白模型は鮮やかな色彩を獲得し、さまざまな声が付加され、街の記憶を引き出すツールに発展した。
写真:ワークショップを経て、記憶に彩られた白模型
2016/07/09(土)(五十嵐太郎)
土木展
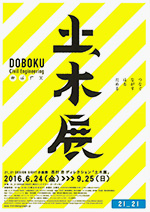
会期:2016/06/24~2016/09/25
21_21 DESIGN SIGHT[東京都]
「土木」についての展覧会。それは私たちの日常生活の基盤を構築する重要な技術知であるにもかかわらず、日常生活の基底にあるため日頃は自覚的に実感される機会は乏しい。本展は、その知られざる実態を土木の専門家やアーティストら22組によって詳らかにしたもの。
土木というと、文字どおり土や木の圧倒的な迫力やそれらと拮抗しうる重量感あふれる重機などを連想しがちだが、残念ながら本展にそのような展示はない。あるのは、来場者の「参加」を要請する当世風の展示である。例えば、エアーで膨らませたビニールのピースを積み上げさせたり、マンホールを模した穴の下から顔を覗かさせたり、来場者の参加によって土木の世界を体験することが本展の醍醐味とされている。
しかし、このような「体験」「参加」型の展示手法が土木の本質を突いているとは到底思えない。いくらそのような参加体験を繰り返してみたところで、本展には土木の本質には決して到達しえないある種の「障壁」が設置されているからだ。その「障壁」とはメディアにほかならない。
「土木」とは、土や木といった自然物を人為的に改変ないしは抑圧することで人間の利益に資する営み全般を指す。であれば、それは必然的に土や木の物質そのものと密接不可分であるはずである。ところが本展は写真や映像、ないしは建築模型というメディアによって土木の物質性を媒介するばかりで、肝心の物質そのものはほとんどと言っていいほど見せられていなかった。企画者が言明しているように、土木が日常生活の根底にあるのは事実だとしても、それを自覚的に相対化するのであれば、日常生活にあふれているメディアを多用したところで、土木を日常性のなかからつかみ出すことはできない。むしろ、非日常性こそが日常性を相対化しうるという現代美術の大原則に則れば、日常では決して出会うことのない土木の現場の生々しい物質感こそが、私たちの足下に広がる土木の世界に想像力を差し向けるはずだ。もし、あの広大な会場に重機のひとつでも展示されていたら、もしあの無機質な展示空間の床に底が見えないほどの暗い穴がひとつでも穿たれていたら、本展の印象は一変していたにちがいない。
物質の忘却と参加体験の強制。本展の特徴をあえて乱暴に要約すると、このようになる。だが、こうした点は、本展の固有の特徴というわけではあるまい。それは、ポスト・プロダクト、関係性、参加、といったキーワードによって整理されがちな、昨今の現代美術の一部の潮流と共振しているように考えられるからだ。有無をいわさず参加を強制されたり、望みもしない関係性を無理やり結ばされたり、「地域社会」という公的な題目があろうとなかろうと、平たく言えば、「大きなお世話」というほかない作品が昨今あまりにも多すぎる。だいたい赤の他人と一緒にカレーを食べたところで、それがいったい「不愉快」以外のどんな感情を惹起するというのか。夢であれ希望であれ、自らの内面をポストイットに書かせる手法も、「馬鹿のひとつ覚え」という悪態が口に出るより先に、内に秘めた心情をあけすけにさせようとする、無遠慮で無神経なふるまいに怒りが募る。一見すると、非常に民主的かつ平和的な手法であるかのようだが、そのじつ、人の心に土足で踏み込むかのような、きわめて暴力的な悪意に満ちた作品が跋扈しているのだ。
参加体験という価値観に立脚した本展は、知ってか知らずか、そのような現代美術の悪質な潮流に巻きこまれてしまっている。必要なのは、土木の世界の物質性を、いかなるメディアにも媒介させることなく、そのまま展示することだった。物質をあるがままに提示すること。そう、ポスト・プロダクトないしは関係性の美学などを吹聴するアートが、とうの昔に批判的に乗り越えたはずの「もの派」的な作品のありようが、この場合に限って言えば、じつはきわめてまっとうだったのではあるまいか。
2016/07/06(水)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)