artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
川田喜久治「ロス・カプリチョス-インスタグラフィ-2017」

会期:2018/01/12~2018/03/03
PGI[東京都]
「ロス・カプリチョス」は、1960年代末から80年代初頭にかけて制作された写真シリーズである。川田によれば「写真の発表をはじめて、10年ほど経ったころ、そのシリーズは自己解放のような気持ちで取りくんだ」のだという。たしかに、それ以前の「地図」や、同時進行していた「聖なる世界」のような緊密な構成の作品と比較すると、ゴヤの版画シリーズからタイトルを借りた「ロス・カプリチョス」は、気ままな発想のバラバラな作品の集合体であり、「自己解放」の歓びにあふれているように見える。
今回の「ロス・カプリチョス-インスタグラフィ-2017」は、70年代を中心にした旧作の再現というだけでなく、全89点のうち3分の1ほどは新作ということで、むしろこのシリーズの再構築というべき展示になっていた。こうして見ると、「ロス・カプリチョス」の発想や手法がまったく古びることなく、むしろより自由度を増したデジタル時代の作品制作のあり方を予言していたようにも思えてくる。軽やかな、だが切れ味のあるアイロニーを含んだ作品としてよみがえった「ロス・カプリチョス」は、これから先もさらに増殖し続けていくのではないだろうか。
ところで、いまや1959年に活動を開始したVIVOの創設メンバーのうち、現役の写真家として活動を続けているのは、川田だけになってしまった。やや寂しいことではあるが、この元気な展示を見ていると、まだしばらくは若々しい、活力に満ちた写真群を生み出し続けることができそうだ。
2018/01/20(土)(飯沢耕太郎)
明楽和記「AKIRA」、明楽和記+堀尾貞治「ゆき」
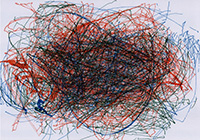
会期:2018/01/08~2018/01/20
GALLERY Ami-Kanoko[大阪府]
ギャラリーの1階と2階で明楽和記(あきらかずき)の個展「AKIRA」が、3階では明楽と堀尾貞治の2人展「ゆき」が開催された。
明楽はこれまで、色鉛筆やカラー電球、着色された既成品、さらには「他のアーティストの美術作品」を「単色の色彩」と見なして空間に配置することで作品を成立させてきた。「色(材)」という規定値や他律的なルールの設定、「絵画とは色彩の選択と配置である」とする還元的思考を空間へと拡張させる制作態度は、「絵画」「ホワイトキューブ」「キュレーション」といった制度的な問題を改めて照射する。今回、2人展の相手として堀尾貞治が選ばれた理由は、「あたりまえのこと」というコンセプトの下、身の周りの物品に毎日特定の色を一色ずつ塗り重ねていく堀尾の行為に、「色」「他律的なルール」という共通項を見出したからと理解される。
一方、個展「AKIRA」では、学生時代に影響を受けたという「具体」の作家、金山明の絵画作品を参照。金山が玩具の電気自動車(あるいは自作の電動機器)に描画材を取り付けて支持体の上で自走させて制作した絵画作品を、実物大に「模写」した作品が発表された。一見、自由奔放に描き殴ったように見えるが、「制御不可能なエネルギーの奔出」を目指すオートマティズムではなく、「機械的に描画された線の軌跡に自身の手の運動を従事させる」という作業だ。そこでは、元の制作主体としての金山明/描画主体としての身体性を取り戻そうとする明楽という2人の「あきら」が、重なり合いつつもブレながら、「機械的に描画された線」の確かさを滲ませていく。
また、もうひとつの展示室では、ファンに撹拌されたカラフルなスーパーボールが、ホワイトキューブの空間内を縦横に飛び交う作品が発表された(観客は、保護メガネと盾で身を守って中に入り「鑑賞」することができる)。ここでは、線描の自動生成装置は2次元平面から3次元空間へと拡張され、カラフルなボールの運動が自動的に「絵画」を生成/解体し続けていく。感情の発露としての線描のほとばしりであるオートマティズムの否定から出発し、機械での代替を経て、より過激化を推し進めること。その時、「絵画」は、目に見える実体を半ば失いながら、中に入った観客を身体的に脅かす暴力的な何ものかへと変貌を遂げるのである。そこでは、「作家の身体」は不在化する代わりに、私たちは別の身体――弾丸のように飛び交うボールを避けようと右往左往し、脚や肩にボールが跳ね返って新たな軌跡をつくり出す「観客の身体」を発見するのだ。
2018/01/20(土)(高嶋慈)
Unknown Sculpture #6 末永史尚「ジェネリック・オブジェクト」
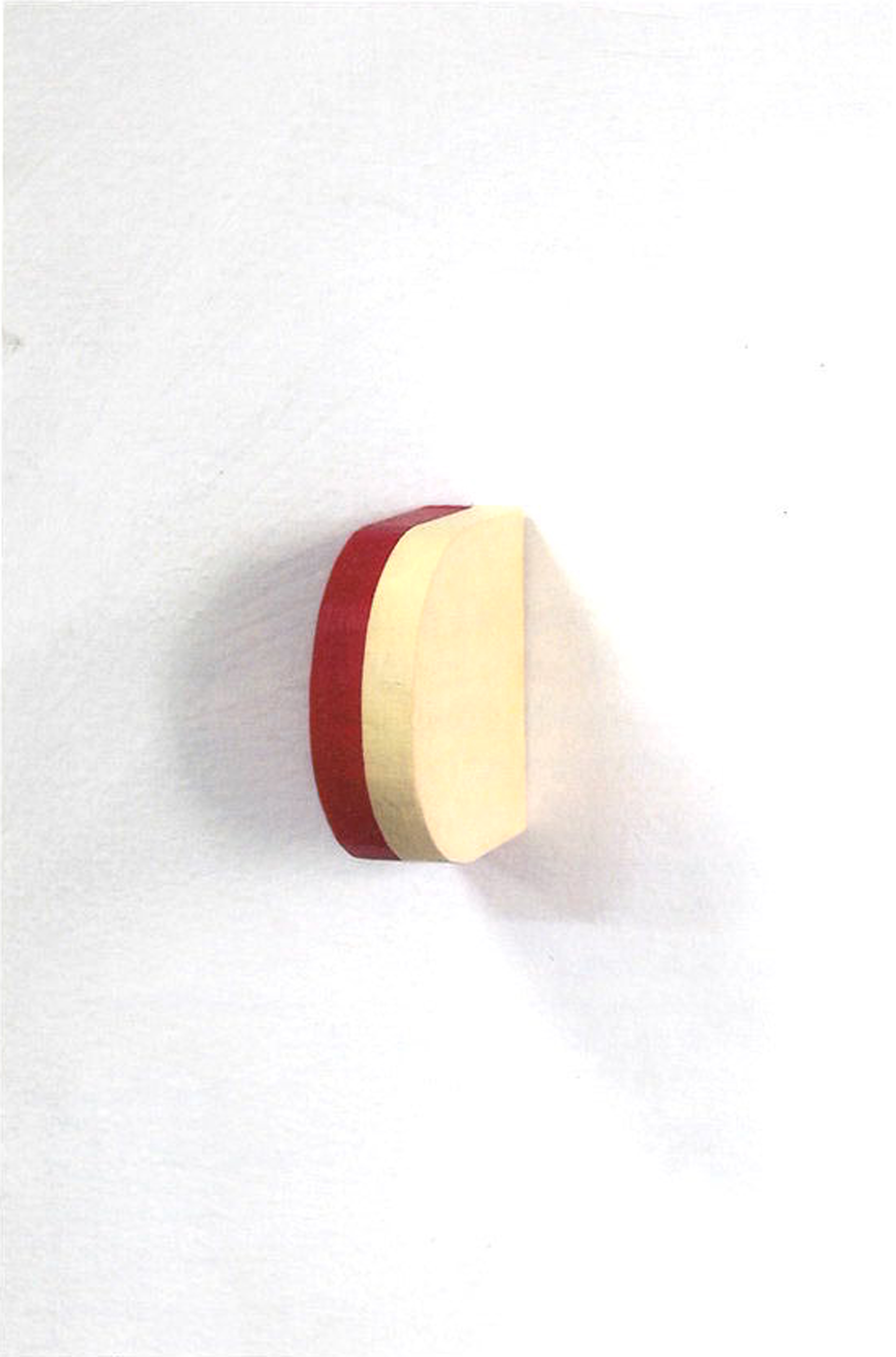
会期:2018/1/11~2018/1/28
ギャラリー21yo-j[東京都]
塀に使われるブロックが8個×2段で計16個、床に斜めに置かれている。そのいくつかにはバツ印や井桁、半円を山型に3つ重ねた青海波などの装飾が描かれている。タイトルの「ジェネリック・オブジェクト」から推測するに、これは最大公約数的なブロック塀か。四角い物体ならなんでも「絵画化」してしまう末永の新作だ(これは床置きなので「彫刻化」かもしれない)。壁には高さ5センチ、厚さ2センチほどの正方形や円形を組み合わせたような物体が突き出ている。が、展示している高さがそれぞれ異なり、色も赤や青などさまざま。これはなんだか見覚えがあるな……、この形、この大きさから察するにメジャー(巻尺)ではないか。ちょうど壁の高さを測っている状態にも見える。
ギャラリーの隅に目を転じると、ベージュと水色の四角い平らな箱がひとつずつ。これはなんだろう? ヒントは手ごろなサイズと、側面にある、折り曲げてできたような三角形にありそうだ。作品リストを見ると、正解はコピー用紙の包み。ま、正解もハズレもないが、モチーフはどれもそこらにある身近なモノばかり。それを「ジェネリック・オブジェクト」に還元して、壁、床、壁と床の境界といった絵画や彫刻の生息場所に置いている。いやーおもしろい。ギャラリーを出たら右手に青海波のブロック塀が目に入って来た。ここにあったか。
2018/01/18(村田真)
村上華子展 ANTICAMERA(OF THE EYE)

会期:2017/12/11~2018/1/19
第一生命ギャラリー[東京都]
重厚な第一生命日比谷本店のビルを入ってギャラリーに向かうと、入口から金の額縁が目に飛び込んでくる。このギャラリーには似つかわしくない作品だなと思いつつ入室してみると、額縁ではなく、縁が黄金色をした大きなプリントであることがわかる。いやそれは最初からわかっていたんだけど、いちおう書き出しとして知らんぷりして書いてみました。第一生命がスポンサーを務める「VOCA展」で昨年、佳作賞を受賞した村上華子の個展。「ANTICAMERA(OF THE EYE)」と題するシリーズは、100年ほど前に生産されたものの、未使用のまま残されていた最初期のカラー写真「オートクローム」の乾板を現像したプリント作品。だからなにかが写っているわけではなく、100年のあいだにわずかながら光学的・化学的変化を起こしてシミのような偶然の模様が成長したのだ。額縁のように見えたのも、乾板の周囲にたまたま瑪瑙のような美しいパターンが現出したもの。作者もこれを見て「お、これは絵画だ!」と思ったのではないか。
2018/01/16(村田真)
広田尚敬「Fの時代」

会期:2018/01/05~2018/03/31
ニコンミュージアム[東京都]
広田尚敬(1935~)は日本の鉄道写真の第一人者であり、60年以上にわたって素晴らしい作品を発表し、数々の名作写真集を刊行してきた。そのなかでも『Fの時代』(小学館、2009)は特に印象深い一冊である。「F」というのは、名機として知られるニコンFであり、広田は1961年にこのカメラを手に入れ、以来北海道を中心としたSLの撮影に使用するようになった。東京・品川のニコンミュージアムで開催された本展には、時には200ミリの望遠レンズにエクステンダー(レンズの長さを調整するリング)を2台つけて撮影したというそれらの写真群から、大伸ばしも含めて約60点のモノクローム作品が展示されていた。
この時期の広田の写真を見ると、彼の出現によって日本の鉄道写真の世界が大きく変わったことが実感できる。それまでの蒸気機関車の車体と走行のメカニズムを克明に記録することを目的とする写真に、幅と深みが加わってくるのだ。鉄の車体の質感や力動感に肉薄しているだけでなく、鉄道の周辺の風景、車内や駅の様子なども被写体として取り上げられるようになってくる。乗客のスナップショットは抜群の巧さだし、ブレやボケを活かした表現も積極的に取り入れている。SLをダイナミックに、多面的に捉えるにあたって、機動力を備えたニコンFの機能を最大限に活かして撮影していたことがよくわかる。
広田が新たな領域にチャレンジしていた「Fの時代」の頃と比較すると、デジタル時代の鉄道写真は、ハード的には進化して誰でもクオリティの高い写真を撮れるようになったにが、何か物足りなさを感じてしまう。撮ること、撮れたことへの歓び、ワクワク感が失われてしまったことがその大きな要因といえるだろう。このジャンルも原点回帰の時期にさしかかっているようだ。
2018/01/15(月)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)