artscapeレビュー
映像に関するレビュー/プレビュー
ライフ・イズ・カラフル! 未来をデザインする男 ピエール・カルダン

会期:2020/10/02〜
Bunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国公開[東京都ほか]
「世界でもっとも知られたフランス人」といった発言が本作のなかで聞かれたが、あながちそれは嘘ではないと思う。誰かと言えば、ピエール・カルダンである。日本をはじめ世界中で、ファッションに疎い人でも多くの人々がその名を知っている。なぜならピエール・カルダンはライセンスビジネスでもっとも成功したファッションブランドだからだ。現在、それは世界110カ国で展開されているという。それまで誰も手を出さなかったライセンスビジネスを初めて導入したことから、関係者からは「パンドラの匣を開けた」とも揶揄される。しかしその後、多くのファッションブランドが後塵を拝す結果となるのだ。
 ©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company
©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company
本作は、2020年にブランド創立70周年を迎えるピエール・カルダンの伝記的ドキュメンタリーで、過去の記録映像やさまざまな関係者からの独白によって構成されている。ピエール・カルダンの明るくポップな世界観に沿うように、映像のテンポも非常に小気味いい。かつてデザインチームの一員だったジャン=ポール・ゴルチエや、インテリアデザインとプロダクトデザインを担当したフィリップ・スタルクといったいまや大御所のデザイナーから、ナオミ・キャンベルやシャロン・ストーンらトップモデルや女優、そして日本からは森英恵や桂由美、高田賢三らがインタビューに答える。なんやかやとピエール・カルダンは周囲から愛された人物だったことが浮かび上がる。
 ©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company
©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company
物心がついた頃から私にとって、ピエール・カルダンといえばタオルに付いたロゴだった。そのイメージがずっと刷り込まれ、今日に至っている。だから「モードを民主化した天才デザイナー」とキャッチコピーにあるが、どちらかと言うと「大衆化」の表現の方がぴったりくるのではないか。いずれにしろピエール・カルダンが「私の目標は一般の人の服を作ることだ」と宣言し、プレタポルテで功績を残したことは大きい。ライセンスビジネスによりブランドが大衆化されすぎて、真のファッション性を私はよく理解していなかったが、ピエール・カルダンを象徴するコスモコール(宇宙服)ルックは未来的で、斬新で、ややユニセックスで、いま改めて見てもおしゃれである。LVMHなどの巨大コングロマリットとはまったく異なる手法で、ファッションの楽しさを大衆に与えたことはもっと賞賛されるべきだろう。
 ©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company
©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company
公式サイト:https://colorful-cardin.com
2020/08/25(火)(杉江あこ)
バウハウス100年映画祭『バウハウス 原形と神話』

会期:2020/08/08~2020/08/28(※)
東京都写真美術館ホール[東京都]
2019年にドイツの造形学校バウハウスが誕生100年目を迎え、2019年から2020年にかけて、数々の展覧会とともに開催されたのが、この「バウハウス100年映画祭」である。合計5本のプログラムが公開され、私も『バウハウス 原形と神話』『ニュー・バウハウス』の2本を観た。ここでは主に『バウハウス 原形と神話』について述べたい。当時の記録映像や元学生たちの証言などによって構成された本作を鑑賞し、また併せて本作のパンフレットも参照すると、そもそもバウハウスとは何だったのかという“原形”がまさに見えてきた。本作中で元学生たちは口を揃えてこう言う。「私たちは世界を変えると信じていた」。この自負はいったい何なのだろうと思ったが、そこには第一次世界大戦直後のドイツの社会状況が大きく関わっていたようだ。
 『バウハウス 原形と神話』
『バウハウス 原形と神話』
歴史を紐解くと、大戦末期の1918年11月にドイツ革命が起こり、皇帝が退位してドイツ共和国が発足し、戦争が終結した。1919年1月、社会民主党左派のスパルタクス団がドイツ共産党と改称し、社会主義革命を目指して武装蜂起するが、政府に弾圧されて失敗に終わる。そして同年2月、穏健な議会制と資本主義経済を掲げたヴァイマール共和国が成立する。そのヴァイマール憲法が発布されることになる地、ヴァイマールに同年4月、バウハウスは誕生した。初代校長を務めた建築家のヴァルター・グロピウスは、失敗に終わった社会主義のユートピアを学校に持ち込んだのではないかと指摘されている。それゆえに、あの「サロン芸術」を否定するバウハウス宣言があるのかと納得した。本作で、周囲から学生たちはヒッピーのように思われていたという発言もあり、やはり旧来の社会制度から解き放たれた革新的な風土が学内にはあったようだ。
 『バウハウス 原形と神話』
『バウハウス 原形と神話』
しかし革新的であればあるほど、その後、台頭する右派のナチスから批判を受ける運命となる。右派勢力から逃れるようにヴァイマールを離れてデッサウへ移転し、さらに私立学校としてベルリンで再開するものの、1933年にバウハウスは閉校となってしまう。もちろんバウハウスの教師や学生たちの運命がさまざまであったことは確かだ。ナチスから迫害を受け、若くして命を落とした学生たちが多くいる一方、アウシュビッツ強制収容所の施設建築に携わった学生もいる。ナチスに入党あるいは協力した教師もいれば、米国などへ逃亡した教師もいる。このように時代の波に翻弄された様子も、本作では明かされていく。「芸術への関心、それだけで革命だった。全ては新しくて過去の自分は無に感じた」。若者がこんな風に、芸術分野において目を輝かせて本気で言うほど、革命的なことがあるだろうか。これこそがバウハウスの真髄なのだろう。
公式サイト:https://trenova.jp/bauhaus/
※「バウハウス100年映画祭」は、今後、10月31日~11月13日に下高井戸シネマ、11月7日〜20日に横浜シネマリンほか全国公開予定。
2020/08/21(金)(杉江あこ)
13th ─憲法修正第13条─

相次ぐ白人警官による黒人への暴力に対して、BLM(Black Lives Matter)運動の人種差別抗議が大きく再熱するアメリカ。本作は、奴隷制廃止以降も現代に至るまで、黒人の大量投獄とそれを支える法制度や巨大な刑務所ビジネスによって、「見えない奴隷制度」と差別構造がアメリカ社会で温存されてきたことを鋭く問題提起するドキュメンタリー映画である(2016年製作、Netflixで公開中)。黒人のジャーナリストや研究者、活動家、弁護士、教育者、議員らの発言と膨大な映像資料を織り交ぜながら、アメリカの政治・経済・法制史を「奴隷制度の構造的温存」の観点から検証していく。その鍵となるのが、タイトルの「合衆国憲法修正第13条」である。
合衆国憲法は奴隷的拘束の禁止を規定しているが、「例外として、犯罪者は適用外」とする修正第13条が、抜け穴として利用されてきた。南北戦争後、貧困層の解放奴隷が不当に大量収監され、刑務所内での労働に従事させられ、受刑者の貸出制度というかたちで奴隷制が温存された。また、南部諸州で、黒人を二級市民化し、交通機関や病院、学校など公共施設の利用を禁止・制限する人種隔離制度を合法化したのが、ジム・クロウ法である。ジム・クロウ法は1964年に撤廃されたが、公民権運動への反動として、「法と秩序」「犯罪との戦争」をスローガンに、人種問題を犯罪問題にすり替えたのがニクソンである。こうして1970年代から黒人の大量投獄が始まり、80年代にはレーガンの提唱した「麻薬戦争」が追い打ちをかけた。白人/黒人は、使用する麻薬の種類(コカイン/クラック)でも量刑が差別化され、人種間の戦争の代理戦争としての麻薬戦争により、黒人受刑者の大量化を招いた。この事態は、黒人犯罪者への憎悪感情を選挙キャンペーンに使ったブッシュ、重罪3回で終身刑とする「スリーストライク法」によって厳罰化を推進したクリントンを経て、「法と秩序」を再び提唱したトランプ政権下へと至る。一生涯で投獄される可能性は、白人男性が17人に1人であるのに対し、黒人男性は3人に1人であり、人口の6.5%にもかかわらず、受刑者数の40.2%を占めるというデータが示される。監視下の黒人の数は、1850年代の奴隷の数より多いという。
こうした大量投獄を支えるのが、肥大化した刑務所ビジネスだ。その背後には、ALEC(American Legislative Exchange Council)というロビー団体の存在があり、企業が立法を左右していることが指摘される。ALECに加盟した銃の大手販売会社や民間刑務所運営会社によって、受刑者の安定供給につながる法律が提案されてきた。実態は刑務所である移民収容施設の急増につながる移民法もそこに含まれる。刑務所ビジネスは、刑務所運営会社に加え、電話、食事サービス、医療サービスなど周辺企業を含む巨大な企業複合体であり、受刑者=安い労働力として搾取する多種多様な製造業も密接に絡んでいる。刑務所内では、社会復帰に役立つ活動はほとんど行なわれず、ローンや就職など出所後もさまざまな社会的制約があり、「アメリカでは罪の償いに終わりがない」。
このように本作は、現在の産獄複合体が奴隷制の歴史の上に成立していること、抑圧的制度は時代に合わせて姿を変えて残存していること、問題の根は過去の歴史の不十分な総括にあることを示した上で、あとを絶たない白人警官による残忍な暴力とBLM運動の希望について最後に語る。「射殺された黒人の死体を見せるべきか」という議論には、「黒人はすでに知っているので、見る必要はない」という意見も紹介しつつ、遺族の承認を経た上で、メディアを通して黒人の経験が共有されることの意義を認める。「BLM運動は社会現象だから拳銃で止められない」「黒人は『例外』ではなく、人間の尊厳についてこの国の意識を変える」という希望が、自由を謳い上げるラップとともにラストで提示される。
膨大な映像を引用し、当事者自身の語りによって検証や告発を積み重ねる作品構造は、同じくNetflixで公開中のドキュメンタリー映画『Disclosure トランスジェンダーとハリウッド』とも共通する。もちろん、「黒人」と「トランスジェンダー」を切り分けることはできないが(『Disclosure』が中心的に扱うのは、黒人トランス女性の表象である)、『13th』は法制度と経済という現実の政治において、『Disclosure』は表象という別の政治空間において、それぞれ差別や偏見が再生産される構造を鋭く抉り出し、相補的な関係にある。
公式サイト:https://www.netflix.com/title/80091741
関連レビュー
Disclosure トランスジェンダーとハリウッド:過去、現在、そして|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年08月01日号)
2020/08/03(月)(高嶋慈)
須藤崇規『私は劇場』 week7

会期:2020/07/14~2020/07/17
パフォーミング・アーツを中心に記録映像を手がける映像ディレクター、須藤崇規によるオンラインパフォーマンス。5月25日より開始され、毎週複数回、YouTubeで生配信され、内容は毎回異なる。本評では、7週目の7月14日の配信内容を取り上げる。
黒画面に白い文字がリアルタイムで入力され、キーボードを打つ音や車の走行音などの環境音が聞こえてくる。本作の構造はいたってシンプルだ。だが、配信時刻が近づくと日付の下の現在時刻が1分ごとに入力/修正され、アーカイブは非公開という「リアルタイム」の重視、ラフなようで周到に計算された音響、「私からあなたへの語り」という親密性、そして思索的な文章と「文字」の入力/黙読/消去という行為そのものによって、「主体」の所在や交換、簒奪の暴力性について問いかける。それは、「演劇」のフィクショナルな仮構の基盤をメタ的に問いつつ、ディスプレイの「向こう側」とこちら、「いまここ」とアクチュアルな世界的出来事とを隔てる距離を再想像/架橋しながら、「劇場」を再定義し直す深い射程を備えていた。
冒頭、現在時刻の表示に続き、「私は文字です」という文言が入力される。この自己言及的な一文は、それをディスプレイ上で「あなた」が読むとき、入力する「私」と黙読する「あなた」とのあいだで、主体の入れ替えや曖昧化が起こっていることについての思索へと展開する。また、手紙(物質)とは異なり、メールの送信は「情報のやりとり」のようだが、実際は「コピーの送信=自己複製」であるとも述べられる。ここで、本作のタイトルおよび題字デザインにも注意を払う必要がある。日本語タイトルは「私は劇場」だが、それは反対側から読まれる鏡文字として裏返っており、さらに英語で表示されたタイトルは「The Theater is You」と、意図的な(私/Youという訳語および主語の)ズレをはらんでいる。この二重性とズレは極めて示唆的だ。「私」と「あなた」の交換可能性、「翻訳」がはらむ(言語に加え)発話主体の置換、鏡像と反転、透明なディスプレイを介して向き合う「こちら」と「向こう側」、その共有可能性とズレ。ここで、黒画面はすなわち劇場のブラックボックスの謂いであり、そこに浮かび上がる白い文字は「台詞」や「字幕」であるとすれば、本作の問題意識はまずもって、「演劇」と発話主体の問題を扱うことにあると言える。
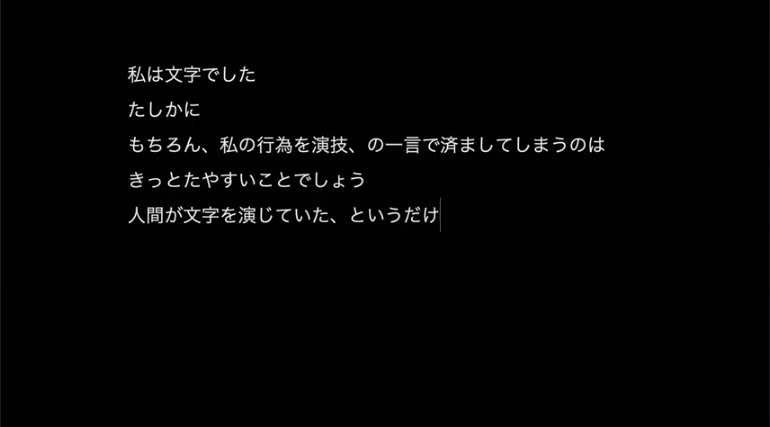
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
だが、こうした「遊戯(Play=演劇をめぐるメタ的思索)」ではいられない事態になってきたと、「文字」は告げ始める。「世界は文字であふれている」と述べたあと、話題は、香港で国家安全維持法が施行され、「香港独立!」という言葉がデモで使えず、白紙のプラカードを掲げる抗議に変わったことへと移る。この抗議について「私」が何か書けば、「配信」すなわちコピーの拡散を通じて「安全」ではなくなるかもしれないと、「私」は怯え、逡巡し、入力した文章を何度も修正し、口ごもる。いつの間にかキーボードの入力音も環境音も消え、無音が緊迫感を高める。カーソルが震えながら「今まで打ち込まれた入力画面」を辿り直し、もう一度書き出し部分に戻り、書かれた内容を「消去」する。
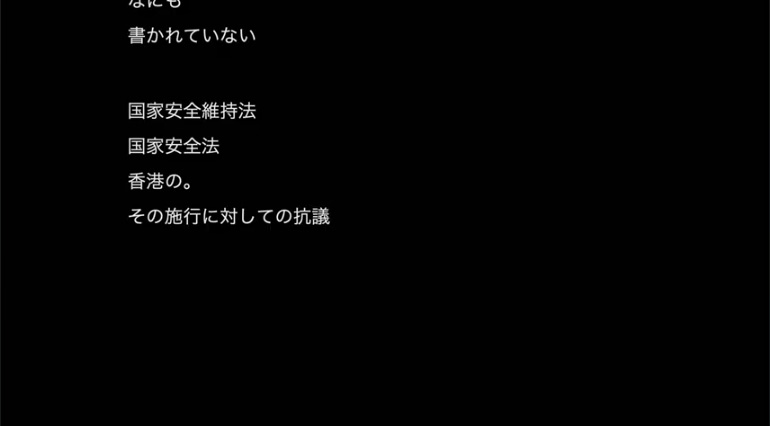
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
「消去」の暴力を自ら実行したあと、再び「こんばんは 私は文字です」という一文の入力が反復される。そして、この「暗いディスプレイ」が「私」と「あなた」の出会う場所であったこと、すなわち束の間でも「劇場」へと変容していたことが語られる。再び、キーボードの入力音と環境音が流れ始め、現実世界の手触りを取り戻していく。「もう知っているもの、すなわち過去に出会い直すためだけなら、あなたはもう劇場へは行かないだろう」「でも、劇場は、まだ知らないものに出会う場所です」。「ここが劇場」、すなわち「私」と「あなた」が共に立ち合い、出会う場所を「劇場」として希望的に肯定し、再定義しようという、ささやかだが高らかな宣言で締めくくられる。ノイズの音量が、祝福するように加速していく。
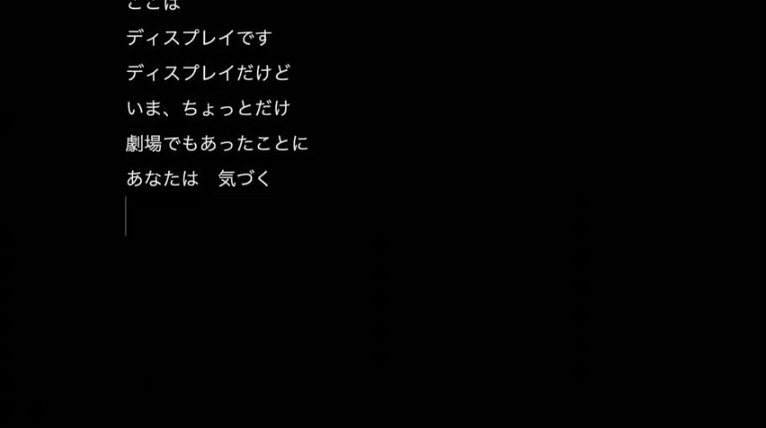
『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)
須藤によって「限界劇場 Marginal Theater を作る試み」と定義された本作は、「主体」の変換や転移という「演劇」の原理的要素に自己言及し、香港の白紙デモというアクチュアルな事態とその距離感をディスプレイを隔てた「私」と「あなた」のそれへと敷衍したのち、「劇場」の概念的拡張を試みる。「限界劇場」、すなわちミニマルに切り詰めた手法によって概念的・物理的限界の拡張を同時に推し進める、優れた試みだった。
題字:内田圭
公式サイト:http://sudoko.jp/theaterisyou/
関連レビュー
須藤崇規『私は劇場』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年06月15日号)
2020/07/14(火)(高嶋慈)
シアターコクーンライブ配信『プレイタイム』

会期:2020/07/12
シアターコクーン[東京都]
コロナ禍で約4ヶ月休館していた劇場、シアターコクーンの「再始動」プログラムとして企画された「ライブ配信のための演劇」。観客席も用意されているが、筆者は企画主旨のライブ配信を鑑賞した。照明・音響装置、オーケストラピットの昇降、裏方スタッフの労働など、劇場の物理的機構それ自体のオーガニックな運動を作品化する、梅田哲也の『インターンシップ』が原案。本企画では、演出家の杉原邦生を迎え、岸田國士の戯曲『恋愛恐怖病』(1926)を森山未來と黒木華が演じ、ダンサーの北尾亘(Baobab)やミュージシャンの角銅真実が加わった。
冒頭、懐中電灯の光が暗闇をまさぐり、無人の劇場バックヤードの機材が照らし出される。小さな星のような灯がポツポツと灯り、やがて眩いライトが強烈な光を投げかける。それは、休館の仮死状態の眠りから劇場を目覚めさせる、(疑似)太陽の光だ。低いモーター音のうねりとともに、歯車が回転し、規則正しく並んだロープが巻き上げられ、バトンに吊られた照明機材が上昇していく。それは、劇場の巨大な体内に張り巡らされた、血管、神経、内臓組織だ。カメラは、胎動の音とともに、巨大な体内のなかを迷路のように進んでいく。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
舞台袖の暗闇で、劇場の模型をライトで照らしながら眺めている男(森山未來)がいる。彼は台詞を発しながら、狭い通路や階段をライトで照らして探検のように進み、彼の台詞を引き取って続ける女の声に導かれるように、舞台の上へ姿を現わす。そこは、裏方スタッフが打楽器や木琴を運び込み、台本を持った女(黒木華)が歩き回っている、「準備中」の運動に満ちた空間だ。「南京豆が食いたくなった」「燈台に灯がつくまで、ここにいましょうね」「今日はなんだか重大な日だ。胸騒ぎがします」。台詞をリフレインさせ、台本の「読み合わせ」をする二人の周りを、モップ掛けするスタッフが行き交う。上昇と下降を繰り返す吊り照明から身をかわす男の動きはダンス的なムーブメントに接近し、一方その傍らでは、裏方スタッフの恰好をした別の男(北尾亘)がスポットライトのテストの下で回転している。無機的な機械音のノイズ、スタッフの業務連絡、マイクチェックなどの作業音が楽器のチューニングやハミングと交じり合い、ハーモニックに調和していく。ゆっくりと旋回するカメラは、薄暗い客席通路の階段を降りて座席につく観客の姿を映し出す。その反対側の、半透明の幕で遮られた舞台上では、「海面」を演出する青いシートがふわりと掛けられ、生き物のように呼吸する。チューニングの延長のような優しい音響が包み、夜明けを告げる鐘のような音が響き、深い霧笛を思わせる音が舞台上に「海」を目覚めさせる。「開演」、そして衣装を着替えた男と女は、海を見下ろす桟橋のような空中のブリッジに立ち、互いの恋愛観と結婚観を語るなかに恋の駆け引きとプライドが入り混じる会話劇が始まる。煮え切らない男を残して女は立ち去り、傷心の彼は、自己の分身のようなもう一人の男にモノローグを吐露し、シンクロしたダンスムーブメントを展開する。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
「演劇」が息づき始める空間を、映像ならではのカメラの運動性を活かして見る者を惹き込み、俳優・ダンサーを脱中心化し、光と影、さまざまな人や機材が交通する活性化された空間として捉え、フィクションの立ち上げをワンカットの「ドキュメンタリー」として撮る。ここで本作の賭け金は、梅田哲也の『インターンシップ』を原案として発展的に拡張させたことにある。劇場の物理的機構の運動や裏方スタッフの作業そのものを作品の素材として用いる『インターンシップ』のサイトスペシフィック性は、「どの劇場で上演しても『コンテンツ』は同じ」という同一性の担保を批評的に解体し、(国内ではKAATに次ぐ)新たな劇場での上演には意義がある。それは、「コロナ禍後の再始動」という面では成功した一方で、「上演批判・劇場批判という作品の本質的要素を、ドラマの充填によって上書きし、損ねてしまう」という両義的な結果となった。また後述するが、秀逸なカメラワーク(渡邉寿岳)は本作の特筆すべき点である一方、「オンライン配信」と「劇場での観劇」の両立は可能かという新たな課題を突き付けた。
私見では、『インターンシップ』のコアは、「舞台上に見るべきものは何もない」という表象批判・劇場批判をリテラルに遂行しつつ、劇場の物理的機構そのものを用いて圧倒的な感覚的体験の強度をつくり出した点にある。通常は不可視の劇場機構や裏方スタッフの作業という「日常」を見せたあと、俳優やダンサーが一切登場しない空っぽの舞台を、即興的なチューニングから不協和と美しさの併存した音響世界が満たし、光と影の交替劇が、夜と死を潜り抜けて再び朝と復活を迎える、壮大で抽象的なドラマなきドラマの非日常性を体感させる。だが本作では、中盤=「開演」以降、「『恋人』と『友達』の境界線をめぐる、男女の駆け引き」「女に翻弄される男」「恋に破れた男のナルシスティックな苦悩」というドラマの充填に取って替わられ、照明や音響の有機的な運動性は劇伴的に退行してしまった。また、岸田國士の戯曲の採用も、「生誕130周年」という祝祭性しかなく、戦前に書かれた戯曲と現代との時代差―「自由恋愛」の登場した大正期/既存の結婚観の残存とのジレンマや、潜在的なホモソーシャルな欲望は掘り下げられず、ファンタジックな演出のなかに曖昧に溶かされてしまう。

[撮影:渡邉寿岳 写真提供:Bunkamura]
また、「定点」も「全体を見渡せる一望」も放棄し、巨大な器官としての劇場空間に潜り込み、洞窟か迷路のような内部を探査し、生きもののように蠢く劇場を捉えるカメラの運動感や流動性は、『インターンシップ』における(ドラマという)中心の欠如と、舞台上を自由に歩き回りながら体感する観客の運動性や移動の自由さとリンクする。その一方で、時折カメラに映り込む「劇場で本作を鑑賞する観客」は、客席に身体を固定され、古典的なプロセニアム舞台との対面を余儀なくされており、身体性の縮減は『インターンシップ』(の発展的展開)の鑑賞体験としては不十分さが残る。感染症が完全に収束するまでは、本作のように、オンライン配信と劇場での上演の並行が(実験性としても収益の面からも)摸索されていくだろう。本作は、「オンラインのライブ配信」の試みとしては成功していたものの、「実際の劇場での鑑賞体験」とのバランスをどう取るか、という困難な課題を改めて浮き彫りにしていた。
なお本作は、7月31日~9月2日の期間、オンデマンド配信が予定されている。
公式サイト:https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/20_playtime/
関連記事
TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)
2020/07/12(日)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)