artscapeレビュー
福住廉のレビュー/プレビュー
川俣正 Expanded BankART
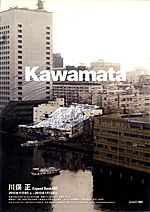
会期:2012/11/09~2013/01/13
BankART Studio NYK[神奈川県]
川俣正の新作展。大規模な個展としては2008年に東京都現代美術館で催した「通路」展以来、じつに4年ぶりである。「通路」展が川俣以外の人びとによるさまざまなプロジェクトを発進させるためのカタパルトだったとすれば、本展は川俣本人の表現に焦点を絞った文字どおりの個展である。BankARTの巨大な空間で、無数の廃材を組み合わせたインスタレーションや記録映像などを発表した。
輸送用パレットを建造物の外壁に組み上げた作品は、圧巻の一言。1階から4階まで木材がうねるように立ち上がっている。何かの怪物が建物に寄生しているかのようだ。風景を一変させるほどのスペクタクルを信条としてきた川俣ならではの力強い作品である。
ただ、室内の作品を見ると、その印象を修正することを余儀なくされる。そこに組み立てられたインスタレーションの内側に入ると、いまも伝統行事としてつくられているかまくらや、圧雪したブロックで構成したイグルーにいるような不思議に安らかな感覚が生まれたからだ。外側はたくましく、内側はやさしい。川俣の作品には、その両面が畳み込まれた厚みがあることを如実に物語る展示だった。
かつて川俣正はポストもの派の一翼を担う新人として華々しくデビューしたが、いま改めて振り返ってみれば、かまくらやイグルーという共同体に根づいた限界芸術を欠落させた都市社会において、それらを人工的かつ想像的に再生しようとする、民俗学的な作品として位置づけ直すことができるのではないか。それは、民俗学による戦後美術史の再編へと広がるはずだ。
2012/12/12(水)(福住廉)
尊厳の芸術展 ─The Art of Gaman─

会期:2012/11/03~2012/12/09
東京藝術大学大学美術館[東京都]
太平洋戦争時、アメリカで暮らしていた日系人は強制収容所に連行され、収容され、終戦後しばらくまで拘束された。強制収容所の多くは砂漠の只中に建てられたバラック小屋だったため、そこでの集団生活はきわめて過酷なものだった。しかし、彼らは厳しい生活環境を改善するために、あるいは美しく彩るために、もしくは現状を記録するために、とどのつまりは自らの尊厳を守り、貫くために、数多くの美術工芸品を制作した。
本展は、そうした「尊厳の芸術」100点あまりを見せた画期的な展覧会。仏壇や茶碗、算盤といった生活必需品から、指輪、玩具、花札といった嗜好品まで、じつにさまざま。限られた材料を最大限に駆使してかたちを整えた職人の技芸が、何よりすばらしい。作者不詳のものも少なくないが、だからこそ有名性という色眼鏡を通すことなく、ものづくりの原点を目の当たりにすることができたともいえる。生活というより、むしろ生きることそのものと密着した芸術のありようを、これほど実直に開陳した展覧会は、かつてなかったのではないか。
本展にも出品しているジミー・ツトム・ミリキタニは、アーティストとは何でも学ぶことができる存在だと言った(”Artist can learn everything”、映画『ミリキタニの猫』)。この言葉が意味しているのは、「何でもできる」という万能感ではなく、「何であれ学ぶことができる」という殊勝な柔軟性である。事実、強制収容所は言うに及ばず、そこから解放された後も、一切の生活の基盤を奪われていた日系人の多くは、生きていくために目前の職を一から学ぶ必要があった。生きるには、なにがなんでも学ばざるをえなかったのである。
翻って今日のアートを見なおしてみると、生きることが保証され、かつてとは比べものにならないほど学ぶ機会も豊かになったにもかかわらず、そこでつくられる「作品」の、なんと脆弱なことだろう。おそらく、その最たる要因は、著しく低下した技術力というより、むしろ「何でも学ぶことができる」という柔軟な発想と姿勢の欠如にあるのではないだろうか。いま必要なのは、アートを学ぶことではなく、アートにかぎらず貪欲に学ぶことからアートを立ち上げることである。アートという固定観念を鵜呑みにして、がんじがらめに呪縛されている学生にこそ、見てほしい展覧会である。今後、福島や仙台、沖縄、広島に順次巡回する予定。
2012/12/06(木)(福住廉)
青梅ゆかりの名宝展

国立奥多摩美術館[東京都]
会期:2012/11/10~2012/11/12、2012/11/17~2012/11/19、2012/11/23~2012/11/25
少なくとも東京のアートシーンにかぎっては、昨今ますます「西高東低」の傾向が続いているのではないだろうか。JR青梅線の軍畑駅から徒歩20分ほどの山奥の川沿いに新たに誕生した国立奥多摩美術館のオープン記念展を見て、なおさらその印象を強くした。
国立奥多摩美術館は、しかし、「国立」でも「美術館」でもない。その実態は、ふだん数人のアーティストによって共同スタジオとして使われている空間をそのまま展示会場にした、ある種のオープン・スタジオである。山奥のスタジオならではの広い空間を存分に使い倒した展示と、何より「奥多摩」以外の情報を詐称する大胆な発想がすばらしい。
出品したのは、太田遼、河口遙、永畑智大、二藤建人、原田賢幸、山本篤、和田昌宏、Katya and Ruith。同館館長の佐塚真啓が、彼らの作品を「青梅ゆかりの名宝」として見せた。太田が建物の棟木の真下に狭小空間をつくり、来場者にはしごで登らせて内部のフローリングとスリッパを見せれば、永畑は1階と2階を貫くかたちで巨大な鹿威しを設え、数分に一度無意味に大きな水しぶきを上げさせた。
また、無意味といえば、徹底的にナンセンスなパフォーマンス映像で知られる山本篤は、奥多摩近辺で伝統として根づいているとする「キャタラ祭」なる架空の祭りをでっち上げ、自ら地元民に扮してインタビューに答えながら、ハリボテの神輿をひとりで「キャタラ! キャタラ!」と叫びながら元気よく担ぐ映像インスタレーションを発表した。展示された神輿の表面には燃え盛る炎のイメージが貼りつけられていたが、よく見るとそれはバーベキューで用いる金網を接写した写真だった。山本が無意味の追究によって見出そうとしていたのは、おそらく燃え上がり盛り上がる祭りという理想郷であって、それを求めれば求めるほど、燃え上がることすらできない澱んだ現状が逆説的に浮き彫りになるところが、おもしろくもあり、悲しくもある。
さらに、このような狂騒的な展示にあって、ひときわ異彩を放っていたのが、河口遥だ。階下の「ビッチカフェ」でお茶や軽食を販売していたが、何かを買おうとして料金を渡すと、そのお客が男であれ女であれ誰であれ、河口はいきなり強烈なビンタを食らわした。体重の乗ったそれは、ものすごく痛い。あの痛烈な一撃にどのような狙いがあったのか、いまでも理解に苦しむが、けれどもある種の感覚が研ぎ澄まされたことは否定できない事実である。それぞれの来場者の脳裡で何かの突破口が開けることを期待していたのかもしれないし、あるいは、ただたんにビンタをかましたかっただけなのかもしれない。そういえば、昨年の6月、武蔵野美術大学近辺の「22:00画廊」で催した「そんなロマンティックな目つきをするな。」展でも、河口は両手で抱えた生肉の塊を引き千切りながら肉片を会場の床にばらまき、それらを食材にしたシチューを来場者に振舞っていたから、今回のパフォーマンスは、やはり身体の奥底にひそむ感覚を暴力的に覚醒させる作品の、きわめてミニマルなバージョンだったのだろう。いま思い出してみれば、胃の中でなかなか消化されない肉のえぐ味と、じんじんと脈打つ頬の痛みが、ともにふだんはなかなか機能することのない感覚の現われだったことが理解できる。
いずれにせよ、本展は、若手のアーティストを集めたグループ展としては、近年稀に見るほど充実した展覧会だった。コンセプチュアルであることを自称しながら、そのじつ自分好きなだけの鬱陶しい傾向や、ギャラリストの眼を意識しながら「置きに行く」志の低い傾向が東東京を席巻するなか、奥多摩の山奥で奏でられたこの狂騒曲は、ひとつの希望である。
2012/11/25(日)(福住廉)
さわひらき

会期:2012/10/23~2012/11/24
神奈川県民ホールギャラリー[神奈川県]
近年めざましい活躍を見せているさわひらきの大々的な個展。神奈川県民ホールの展示空間をすべて使った大規模な展示で期待が高まったが、いまいち消化不良の感が否めなかった。それは、おそらく地下一階の大空間に展示された映像インスタレーションが、どうにもちぐはぐな印象を残していたからだ。空間の容量に対して映像のサイズがあまりにも小さかったからなのか、あるいは映像を投射する壁面の配置が中途半端だったからなのか。いずれにせよ、さわひらきの映像の夢幻性が十分に伝わらなかったように思われる。資生堂ギャラリー(「Lineament」2012)や水戸芸術館現代美術ギャラリー(「リフレクション」2010)での展示がすばらしかっただけに、今回の展示は惜しい。
2012/11/23(金)(福住廉)
TRANS ARTS TOKYO

会期:2012/10/21~2012/11/25
旧東京電機大学11号館[東京都]
取り壊しが決定している大学校舎を会場にした大々的な展覧会。地下から地上17階まで、6階をのぞくすべてのフロアで300名以上のアーティストが作品を展示した。学生や若手アーティストが大半だとはいえ、これだけ大規模に催された展覧会は他に類例を見ない。すべて見るにはそうとうの時間と体力を要するほど、作品の数は、おびただしい。
展示された作品は、美術、建築、デザイン、ファッションなど多岐にわたっていたが、なかでも最も光っていたのは、14階。ディレクターの中村奈央が、13人のアーティストの作品を縦横無尽に展示した。建物の構造上、どの階も同じような展示空間にしがちだが、中村は教室から廊下、トイレまで14階の空間を余すことなく使い切ったところがすばらしい。壁面の一部に穴を開けて作品を見せたり(臼田知菜美)、経団連のビルが望める窓に「無職」と達筆で書いたり(キュンチョメ)、廊下の全面にスプレーで名前を書かせて芳名帳としたり(キュンチョメ)、破壊されることを前提とした空間の使い方が、他の階とは比較にならないほど、抜群にうまいのである。
若手アーティストの作品が一同に会した意義は大きい。しかし、それと同時に、それらをオーガナイズしたディレクターやコーディネーターの才覚も評価すべきではないだろうか。
2012/11/22(木)(福住廉)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)