artscapeレビュー
建築に関するレビュー/プレビュー
マルタン・ブルブロン『エッフェル塔~創造者の愛~』、ジャン=ジャック・アノー『ノートルダム 炎の大聖堂』

[全国]
もうすでに日本で公開されているが、ひと足先にパリのランドマークの建設プロセスを描いた映画『エッフェル塔~創造者の愛~』を鑑賞し、以下のコメントを寄せた。
様式なき造形ゆえに、当初のエッフェル塔は「建築」として評価されなかった。
しかし、結果的にその大胆な構造は、20世紀建築の可能性の扉を開く。
そして今や現地では目撃できない建設途中の姿が凛としていること!
この映画はなぜ一人の技術者が新しい美を創造しえたかについて独自の解釈を与えた。
ギュスターヴ・エッフェルは、いわゆる技術者であり、ボザールで様式を徹底的に学ぶ建築家ではなかったがゆえに、新しい構造の可能性を自由に考えることができたのだが、映画においてそのへんの背景はややわかりにくい。19世紀は様式にもとづく芸術的な建築が限界を迎え、構造と芸術が引き裂かれた時代だった。また、もうすでに完成した状態でしか、われわれは見ることができないので、この映画の見所のひとつは巨大なセットとしてつくられた建設途中のエッフェル塔だろう。独創的なポイントは、史実に対し、エッフェルの秘められたラブストーリー(フィクション)を組み込んだことによって、新しい解釈を与えたことである。ネタバレになるので詳細の記述は避けるが、2000年代に入り、東京タワーにスカートをはかせたいといった思いがけない卒業設計が登場し、塔の女性化に衝撃を受けたことを個人的に思いだした。塔はしばしば男性的なものとされているからだ。
パリのもうひとつのランドマークの映画が、日本では4月公開に公開される。2019年にノートルダム大聖堂の屋根で火災が発生し、燃える姿が世界に衝撃を与えた事件をモチーフにした作品『ノートルダム 炎の大聖堂』だ。当時のリアルな映像(おそらく、報道や個人が撮影した素材)も交えたドキュメンタリー・タッチの映画である。そして消防隊の視点からとらえたことが大きな特徴だ。警報が鳴ったにもかかわらず、誤作動と判断された初期発見のミス、渋滞や塔を登る途中のドアが開かないことによる初期消火の失敗が重なったうえに、そもそも消防を前提としない高い構築物ゆえに、いかに大変な現場だったことがわかる。歴史を振り返ると、尖塔は落雷によって火災を繰り返しており、われわれがよく知る姿は19世紀にヴィオレ・ル・デュクが新しくデザインしたものだ。映画では、聖遺物に対する属人的な管理にも驚かされた(もし担当者がもっと遠い場所にいて、駆けつけることができなかったら?と思う)。火災をテーマとする映画は少なくないが、これは人命救助ではなく、文化財のために消防隊が命をかける特殊な事例である。なお、セットやVFXの出来が良いことも最後に付記しておく。
『エッフェル塔~創造者の愛~』公式サイト:https://eiffel-movie.jp
『ノートルダム 炎の大聖堂』公式サイト:https://notredame-movie.com
2023/02/08(水)(五十嵐太郎)
analogueの建築
[京都府]
研究室OBを含む建築ユニットのanalogueとkiiriが共同で設計した作品を京都で見学した。美術系の大学教員の夫妻が暮らす、《等持院の住宅》の見学は、1月に案内をもらっていたが、都合がつかず、遅れての訪問となったが、おかげで空っぽの部屋ではなく、蔵書や食器などが入ったセンスのある生活感がわかる状態になっていた(今後も正式なポストやカーテンが加わる予定)。木造二階建てだが、上はロフトだけなので、かわいらしいコンパクトな家である。特徴的なのは、塀がなく、正面と背後の二面接道により視線が貫通できることや、全方位に散りばめた開口によって実際のサイズよりも広く感じることだ。また外構には通り抜け可能な細い路地的な余白を設けている。これはanalogueの村越怜が、かつて勤めていたはりゅうウッドスタジオが手がけた《都市計画の家II》を連想させるだろう。住宅地においてあえて外部の人が通り抜けできる道を提供していたからである。そして《等持院の住宅》の内部はほぼワンルームとし、中央を横断するロフトの床やカーテンで、ゆるやかに空間を分節する。このスケール感だと、什器の造形も重要であり、以前のマンションから運んだ家具にあわせたインテリアが設計されている。

《等持院の住宅》

《等持院の住宅》

はりゅうウッドスタジオ《都市計画の家II》
この家に暮らす版画家の出原司による《京都リトグラフ工房》は、歩いて3分ほどの距離だが、やはりanalogue+Kiiriが先に手がけたものである。つまり、先に仕事場としての離れができてから、家が完成した。なお、出原自身によって一度改修が行なわれていたので、鉄骨事務所に対する二度目のリノベーションである。過去の痕跡を残しつつ、開口を増やしたこと、また間仕切りをなくして、長い空間を一体化させることで、工程に沿って機械や作業台を一列に並べるというものだった。線路沿いの敷地ゆえに、開口の真横を電車が通り、正面は開放的な場とし、街に開く。

《京都リトグラフ工房》

《京都リトグラフ工房》
analogueは、名古屋の《UNEVEN HUB STORE》(2021)でもリノベーションを担当している。集合住宅の一階に入っていたスーパーマーケットの空間を改造し、ファッション、雑貨、コーヒーなどの小さな店舗群、イベントスペース、キッチン、広い通路を設けたものだ。通常、こうした施設では、インテリアはばらばらになりがちだが、建築家が街のマスターアーキテクトのように統一感をつくる試みが興味深い。いずれも単体の建築ながら、街とのつながりを強く意識したプロジェクトである。

《UNEVEN HUB STORE》

《UNEVEN HUB STORE》
2023/02/05(日)(五十嵐太郎)
伊丹豪「DonQuixote」

会期:2022/12/02~2023/01/29
CAVE-AYUMIGALLERY[東京都]
伊丹豪の新作11点がdot architectsとのコラボレーションによる会場構成で並んだ。会場の柱や梁に沿って2色の角材が走る。ぱっと見て写真作品自体への没入を阻害する鮮やかな直線は、作品が配置された建築の存在を強調する。それは本出展作が、「写真におけるアーキテクチャーへ応答するぞ」という布石のようでもあるし、写真に強烈に存在する直線性へ鑑賞者の意識を導くためのガイドのようでもある。
本展作品は、COVID-19下での東京オリンピックで焦点化される「東京」を横目に、徳島出身の伊丹が当事者性をもてると判断した範囲で撮影された関東圏の事物である★1。撮影機材は、個人購入の範囲ではそのときもっともハイエンドとされるカメラだ。ピントをずらし、全てにピントを合わせる深度合成がなされた★2、どこもかしこもピントが合ってくっきりとしたイメージは、物理的な現実の世界のなかで眼が滑ったり、何かが気になって凝視したりするといったような経験を生み出している。そういう意味でも伊丹の本作は、マチエールの強い絵画がイメージというより絵具(物)として現前しているときのような、イリュージョンへの亀裂を生じさせる視覚経験と類似性がある。そしてこの全面的に被写体を前景化させる作為は、伊丹が自身でも語るように、モチーフの脱中心化を志向したものだ。このくっきりとしたイメージは相対的にいずれのモチーフも中心性をもたないし、時には訴求力をもつモチーフがなくなるまで、周囲にモチーフを足し続けているのである。例えばそれは、伊丹の自宅のダイニングテーブルの下に垂れる真空パックされた液体の輝き。
いま述べるには雑駁で申し訳ないのだが、構成的写真であろうと、記録的写真であろうと、写真が写真であるために、その写真にまつわる文化的使用をモチーフとしたり、写真における指標性を追求するといったさまざまな作品行為があるわけだが、本展を見て、写真作品における「モチーフを足す」ということに、いかにいまの世界が抑圧的状況となっているか、ありありと私は気付かされた。
 Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY
Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY
また展覧会の構成上必見なのは、伊丹の提案でdot architectsが制作した写真の什器となっている白い板だろう。白い板は写真の大きさからひと回りだけ大きい矩形の窪みがつくられていて、その窪みに写真パネルをはめ込むと、板の表面と写真の表面のツラがぴったりと合う。額のように振る舞う白い板の窪みは、額がイメージに埃や傷を付けないようにと作品を奥まらせる機能を一切もたない。1990年代に起こったビッグピクチャー(写真作品の巨大化)とそれに伴う「ディアセック」(写真プリントの表面にアクリル接着を行なうマウント技術)による巨大写真作品の強度の増加が、ひるがえって「アクリルの表面に傷がつくと回復できない」という今日の保存修復の問題へとつながっていった状況を思い起こさせる。本展での、この「埃がついてもいい」という挙動は、プリントの力も勿論だが、写真イメージそのものの侵されなさ、鮮烈さの実在の表明に思えた。
本展は無料で鑑賞可能でした。
 Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY
Photo by Takaaki Akaishi © Go Itami Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY
★1──2023年5月4日に加筆修正を行ないました。
★2──2023年5月4日に加筆修正を行ないました。
公式サイト:https://caveayumigallery.tokyo/GoItami_DonQuixote
2023/01/27(金)(きりとりめでる)
How is Life? ─地球と生きるためのデザイン

会期:2022/10/21~2023/03/19
TOTOギャラリー・間[東京都]
経済思想・社会思想を専門とする斎藤幸平の著書『人新世の「資本論」』を一昨年あたりに読み、相当感化された私にとって、本展は大変に興味深い内容だった。いま、SDGsが叫ばれる世の中だが、本当にこれらの項目を実行するだけで地球環境を劇的に変えられるのだろうか。以前から薄々と感じていたそんな疑問に対し、同書は否と明確に答えを突き付けてくれた。本展もまた然りである。ライブラリーコーナーに「キュレーター会議で取り上げられた」という書籍が何冊か並んでいたのだが、現に、そのなかに同書も入っていたことに頷けた。
近代以降、人類は経済成長のための活動をずっと続けてきたが、さまざまな面で限界に達したいま、これ以上の成長を望むことは正しいのだろうか。そんな根本的な問いに対し、本展は「成長なき繁栄」という言葉で返す。そう、人類をはじめ地球上に棲むすべての生物がこの先も持続的に繁栄していくためには、経済成長を前提とする必要はもうないのだ。生産、消費、廃棄といった従来のサイクルで物事を捉えることを我々はいったん止め、皆が真に豊かになれる方向へ大きく転換しなければならない。そうした考えに基づいた草の根運動やプロジェクトが、いま、世界中で実践され始めているという。塚本由晴、千葉学、田根剛、セン・クアンといった第一線で活躍する建築家・建築史家4人がそれらの運動やプロジェクトを収集し紹介したのが本展だ。
 展示風景 TOTOギャラリー・間 © Nacása & Partners Inc.
展示風景 TOTOギャラリー・間 © Nacása & Partners Inc.
農業や林業、里山の仕組みを見直すといった類のプロジェクトも多く紹介されていたが、私がむしろ興味を引かれたのは都市のあり方である。特にパリをはじめ、ヨーロッパの都市が積極的に変わろうとしているのには好感を持てた。例えば車や鉄道に代わり、改めて着目されている移動手段は自転車だという。より人間に近いモビリティが求められているというわけだ。そこで問われるのが自転車道を優先した都市計画で、パリやチューリッヒなどではすでにそうした試みが始まっているという。
 展示風景 TOTOギャラリー・間 © Nacása & Partners Inc.
展示風景 TOTOギャラリー・間 © Nacása & Partners Inc.
結局、既成概念にとらわれていては何も変えられない。この危機的状況を脱するには、より柔軟な発想が必要となる。最後に観た作品「How to Settle on Earth」は、その点で非常に刺激的な内容だった。建築家・都市計画家のヨナ・フリードマンが「地球の再編成」をテーマに軽妙なイラストながらラディカルな提案をしていて、目が釘付けになった。地球および人類の未来のためには、もしかすると国境すらも取っ払う必要が出てくるのかもしれない。
公式サイト:https://jp.toto.com/gallerma/ex221021/
2023/01/21(土)(杉江あこ)
日常の風景の中に文化財を観る:地域の彫刻と建築を学ぶワークショップ
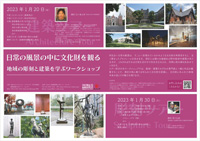
会期:2023/01/20
慶應義塾大学アート・センター [東京都]
慶應義塾大学アート・センターが企画する「日常の風景の中に文化財を観る:地域の彫刻と建築を学ぶワークショップ」の建築ツアーの講師を担当した。ちなみに、アート・センターでは美術だけでなく、槇文彦による慶応関係のプロジェクトの図面も保管しており、「アート・アーカイヴ資料展ⅩⅩⅢ 槇文彦と慶應義塾Ⅱ 建築のあいだをデザインする」(2022)などの企画展を開催している。さて、ツアーは、午前は三田キャンパスに始まり、岡啓輔による驚異のセルフビルド建築の《蟻鱒鳶ル》(そろそろ完成が近いらしい)とその斜向かいの2つのコアによる丹下健三の《クエート大使館》(1970)、午後は明治学院大学の白金キャンパス(内井昭蔵の個性的な意匠を備えた再開発を含む)、内田祥三の《旧公衆衛生院》(1938)、東京都庭園美術館と「スカイハウス再読」展まで、かなりの強行軍だったが、このエリアに多くの建築があることを再認識する。

明治学院大学の記念館、背後は内井昭蔵による再開発

内田祥三《旧公衆衛生院》
役得としては、なまこ壁の外観に対し、効果的な採光によって室内が想像以上に明るい慶應の《三田演説館》(1875)、移築され、薄い膜によってかつての空間のヴォリュームを想起させる《ノグチ・ルーム》(1951/2005)、明治学院大の《インブリー館》(1889頃)などは、これまで内部に入ったことがなく、貴重な体験だった。また学生のときのインド・ネパール旅行で犬に噛まれ、帰国後の6回目の狂犬病の注射のために、確か足を運んだ旧公衆衛生院も、数年前から郷土歴史館として公開されている。
三田キャンパスの魅力は、近現代の建築群が連携していることだろう。曾禰中條建築事務所による一連の《図書館旧館》(1912)、《塾監局》(1926)、《第一校舎》(1937)は、だんだんゴシック的な意匠を減らし、3番目はバットレスのみが残る。こうした垂直性を強調した建築に対し、槇事務所は水平性のモダニズムを得意とするが、やはり周辺環境を踏まえたデザインを試みている。例えば、《図書館新館》(1981)は、バットレスの高さを意識した垂直の要素をもち、さらにミラノのドゥオモに言及している。この大聖堂は、イタリア北部ということで、ゴシックの垂直性と古典主義の水平性が混在した意匠をもち、実際に《図書館新館》の北面の輪郭はドゥオモと似ている。また《大学院棟》(1985)は、ポストモダンが盛り上がった時代であり、槇の作品であっても、遊びや装飾のデザインが認められる。広場に対する時計塔や面ごとにファサードを変えるなど、細かく場を読み込んでいる。なお、槇事務所は《図書館旧館》の保存、免震化、リノベーションも1982年と2020年に手がけている。

《図書館旧館》

《塾監局》

《図書館新館》のドゥオモ風ファサード

《大学院棟》

「スカイハウス再読」展 展示風景
公式サイト:http://www.art-c.keio.ac.jp/news-events/event-archive/workshop-tour-2023/
特別展示・テーマ展示「ランドスケープをつくる」第2回「スカイハウス再読」
会期:2022年12月10日(土)~2023年1月29日(日)
会場:東京都庭園美術館 正門横スペース
(東京都港区白金台5-21-9)
企画展示 横浜国立大学大学院/建築都市スクール Y-GSA
2023/01/20(金)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)