artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
笹川治子「リコレクション─ベニヤの魚」

会期:2017/08/25~2017/09/17
Yoshimi Arts[大阪府]
笹川治子は、祖父が陸軍の特攻隊に送られた時の証言や資料をもとに、彼が目撃したというベニヤ板製の人間魚雷を制作している。ツギハギだらけで今にも壊れそうなベニヤ製魚雷の周囲の壁には、取り巻くように海辺や島の写真が(上下反転して)貼られている。これらの写真は、広島県の似島、江田島幸ノ浦、香川県の豊浜、小豆島など、陸軍の訓練施設があったといわれる場所を笹川がめぐって撮影し、祖父が見たであろう風景を収集したもの。人間魚雷の中は空洞になっており、取り付けられた潜望鏡を覗き込むと、(レンズ越しに上下が正しい向きで、だがぼんやりと)海辺の光景の写真が見える。その曖昧にぼやけた像は、祖父の記憶の中のおぼろげな光景とも、過去そのものに触れられないもどかしさともとれる。不鮮明さの印象は、会場内に響くくぐもったノイズ(出撃地点の浜辺で海中の音を採集)や、粗いモザイクのかかった海中の映像(と思われる)によってさらに増幅される。
笹川は以前の作品で、アニメ風の巨大なロボット戦士を透明なビニールでつくり、(空想の)兵器へのロマンや男根的なマッチョイズムを脱力させ、無力化する作品を発表してきた。本展で提示された、脆く弱い素材でハリボテ感の強いベニヤ製魚雷もまた、単に歴史的資料としての再構成に留まらず、そうしたヒロイズムへの批評を内包している。さらに、装備された潜望鏡を通して「過去と現在が折り重なった風景」を見るとき、それは風景への眼差しを再構築する装置であり、風景の中に重層的に沈殿した記憶の中へ潜航するための、想像力を駆動させる乗り物となるのだ。

笹川治子「リコレクション─ベニヤの魚 Recollection: the Plywood Fish」2017 展示風景
© Haruko Sasakawa, courtesy of the artist and Yoshimi Arts, photo by Kiyotoshi Takashima
2017/08/26(土)(高嶋慈)
Under 35 廖震平
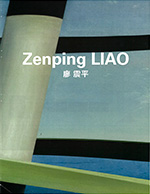
会期:2017/08/25~2017/09/13
BankART Studio NYK 1階ミニギャラリー[神奈川県]
35歳以下の若手作家に発表の機会を与えるU35シリーズの第2弾は、台湾出身の廖震平の個展。彼が描くのは一見ありふれた風景画のようだが、どこか変。例えば木が画面のちょうど中央に立っていたり、画面の枠に沿って四角い標識が描かれていたり、道路のフェンスが画面をニ分割していたり、不自然なほど幾何学的に構築されているのだ。そのため風景画なのに抽象画に見えてくる。というより具象とか抽象という分け方を無効にする絵画、といったほうがいいかもしれない。
1点だけ例を挙げると、巨大な木を描いた《有平面的樹》。右下から斜め上に幹が伸びているが、白くて丸い切り口が画面の中心に位置しているのがわかる。いったんそのことに気づくと、もうこの絵は風景も木も差しおいて、白い丸が主役に躍り出てくる。太い幹や暗い木陰や細かい枝葉は、白い丸を際立たせるための小道具にすぎないのではないかとすら思えてくるのだ。そもそも彼は風景を描いていない。風景を撮影してタブレットで拡大した画像を見ながら描いているのだ。その意味では「画像画」というべきか。だからなのか、彼の表象する風景からはなんの感動も伝わってこない。伝わってくるのは絵画を構築しようとする意志であり執念だ。そこに感動する。
2017/08/25(金)(村田真)
村田峰起 +
会期:2017/08/19~2017/09/09
ギャラリーハシモト[東京都]
身体パフォーマンスとドローイングを手がけている美術家、村田峰起の個展。白いワイシャツを着たままその背中にドローイングを描いたり、鉛筆の芯を食べたり、引きちぎった辞書を積み上げたり、自らの身体を極限まで酷使しながら「絵画」や「彫刻」という既成のジャンルを内側から突き抜ける作品が特徴だ。本展では、同じく身体パフォーマンスを中心としたインスタレーションや写真、ドローイングなどの新作を発表した。タイトルの「+」には、さまざまなクリエイターやアーティストの力を借りながら作品を制作したことの敬意が含まれている。
こう言ってよければ、村田のパフォーマンスは極めて独善的である。言葉もないまま、ただひたすら机の上にボールペンを走らせるパフォーマンスは鬼気迫るほどの迫力があり、見る者を寄せつけない。しかし、本展で映像によって紹介されたパフォーマンスは公園で行なわれたせいか、好奇心を刺激された子どもたちが次第に集まり、村田の真似をして机に殴り書きをするようになるところに、彼のパフォーマンスの真骨頂がある。それは、閉じながらも、逆説的に開くような、特異なかたちで社会的な磁力を発するのである。
だが、そもそもパフォーマンスないし非言語的な身体表現とは、そのような逆説にもとづいているのではなかったか。こちらから積極的に他者に働きかけるというより、あちらから自己に働きかけるように暗に仕向けること。言い換えれば、世界との関係性を切り結ぶためにこそ、まずは世界との関係性を切断すること。そのためにまず自発的に動き出す身体の運動性こそが、パフォーマンスの純粋な動機だったはずだ。スタンドのマイクを両手で包みながら歌い上げるロックミュージシャンのように、カメラの前で延々と炭を食べ続けるパフォーマンスにしても、当初はそのナンセンスな振る舞いに笑いを抑えることができないが、乾いた咀嚼音を耳にしながら対峙しているうちに、次第にパフォーマンスの純粋性に心が打たれるようになる。閉じれば閉じるほど、ナンセンスを極めれば極めるほど、私たちの視線は村田の身体表現に釘付けになり決して眼を離すことができない。それは彼のパフォーマンスがじつは他者を渇望していることが、私たちの脳裏にありありと浮き彫りになるからである。
まず、閉じよ。「関係性」とやらのいかがわしい言葉に踊らされて、安易に世界と関わるな。孤立を恐れず、むしろ徹底的に社会と隔絶することで、逆説的に社会的になりうることは、十分にある。パフォーマンスの真理を、村田はその肉体で語っているのである。
2017/08/22(火)(福住廉)
志賀理江子 ブラインドデート

会期:2017/06/10~2017/09/03
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館[香川県]
今回の展示の中心になる「ブラインドデート」は、2009年の夏にタイのバンコクで撮影された作品だ。展覧会の準備のためにバンコクに滞在していた志賀理江子は、二人乗りのバイクに乗るカップルの女性たちが自分に向ける強い「眼差し」に興味を持ち、それらを「集めてみたい」と考える。知り合ったタイ人の女の子とそのボーイフレンドに協力してもらって、ひたすら夜の街でバイクに同乗するカップルに声をかけ、車で併走しながら写真を撮り続けた。
そのうち「背後から目隠しをして走り続け心中した」というような事件があったのではないかという「妄想」が湧きあがってきた。調べると実際にはそんな事件はなかったようなのだが、それをきっかけとして「目が見えない」というのはどんなことなのかと考えるようになる。タイでは生まれつき全盲のカップルのポートレートも撮影した。その時に盲目の女性が語った、世界中のすべての宗教の生死についての解釈が「私には当てはまらない気がするのです」という言葉に衝撃を受ける。写真家として、視覚に強くかかわる仕事をしている彼女にとって、まったく異質な世界があることに気づいたのだ。
だが今回の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館での展示は、その「ブラインドデート」のシリーズだけに留まるものではない。会場には21台のスライドプロジェクターが並び、さまざまな画像が壁に投影されている。その多くは2012年にせんだいメディアテークで開催された「螺旋海岸」展以降に撮影されたものだ。プロジェクターが画像を送る時の機械音、点滅する赤い光、会場の奥の一角には、臨月の時にエコー検査で録音したという心臓音が響いてくる。さらに最後のパートの壁には長文のメッセージが掲げられている。彼女が今回の展示でもくろんだのは、単に写真を見せるだけではなく、視覚、聴覚、触覚など身体感覚のすべてを動員し、映像も言葉も一体化するような全身的な体験を、観客とともに味わうことだったのだ。
そこから浮かび上がってくる、今回の展示のメインテーマというべきものは「弔い」と「歌」である。志賀は展覧会開催にあたって「もしも、この世に宗教もお葬式という儀式も存在しないとしたら、大切な人が亡くなった時、あなたはどのようにその方を弔いますか?」という問いに対する答えを、アンケートのかたちで募集した。その回答の一部は会場の最後のパートに掲げられているのだが、そのなかに「思い出す、思い出す、思い出す、思い出す、飽きるまで」というものがあった。この死者を「思い出す」ことこそが、写真という表現行為の根幹にあるという考え方が、展示の全体に貫かれている。
もうひとつの「歌」については、まだ明確なイメージは掴み切れていないようだ。だが、いまはまだおぼろげではあるが、もしかすると、歓び、哀しみ、怒りなどを体現した「歌」を求め続けることが、彼女の写真家としての営みの中心になっていくのではないかという予感が僕にはある。東日本大震災以後に、2008年以来住みついていた宮城県名取市北釜を離れ、結婚、出産を経て、いまは宮城県小牛田で制作活動を展開している彼女の「次」の展開が、しっかりと形をとりつつある。
2017/08/20(日)(飯沢耕太郎)
そこまでやるか 壮大なプロジェクト展

会期:2017/06/23~2017/10/01
21_21 DESIGN SIGHT[東京都]
文字どおり「そこまでやるか」と思わずつぶやいてしまうほど壮大なプロジェクトを手がけるアーティストの活動を見せる展覧会。国内外8組の美術家や建築家らが参加した。いずれもアーティストならではの常軌を逸した想像力を披露しており、十分に楽しむことができる。
例えば西野達は美術館という既成の空間を鮮やかに裏切ってみせた。窓際のスペースに単管を組み上げ、最大で3段のベッドを設え、カプセルホテルとした。予約すれば、じっさいに宿泊することもできるという。また泥絵で知られる淺井裕介も、美術館の白い壁に土と水でダイナミックかつ繊細な絵を描くという点で言えば、美術館で想定されている空間利用を大きく逸脱していると言えるだろう。
一方、美術館という制度そのものから逸脱しているのがクリストである。本人のインタビューを交えた映像で詳しく紹介されているのは、昨年にイタリアのイセオ湖で行なわれた《フローティング・ピアーズ》。ポリエチレン製のブロック22万個を連結させた長大な桟橋で湖畔の街と島を結んだプロジェクトである。オレンジ色の布で覆われた桟橋は幅16メートル、全長3キロ。その上をおびただしい数の観光客が散歩する光景は、夢のように美しい。クリストは湖面に道を拓いたのだ。
アーティストの仕事が想像力を現実化することにあるとすれば、本展で紹介されているアーティストたちはいずれも類稀な想像力の強度と美しさを備えている。しかも、それらを根底で駆動させているのは、美術館あるいは「美術」という制度に依拠しながらも、同時に、それらから大きく逸脱する運動性である。絵画はキャンバスに閉じ込められているわけではないし、美術も美術館にしかないわけではない。グラフィティやアウトサイダーアートという例外的な周縁でなくとも、そもそもアーティストの想像力は、そのような制度とまったく無関係に飛翔することができる自由を誇っている(クリストのインタビュー映像は彼の作品履歴を振り返りながらプロジェクトに取り組むための真髄を明快に言語化している点で必見)。
既成の制度や歴史、与えられた条件の中だけで想像力を開陳しがちな、そしてそのことを不自由とも思わないほど飼い慣らされた、若いアーティストや美大生こそ見るべき展覧会である。
2017/08/20(日)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)