artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
港都KOBE芸術祭

会期:2017/09/16~2017/10/15
神戸港、神戸空港島[兵庫県]
神戸港の開港150年を記念した芸術祭。神戸という「場所の記憶」への言及として、古巻和芳と川村麻純の作品が秀逸だった。古巻和芳の《九つの詩片 海から神戸を見る》は、本芸術祭の目玉である「アート鑑賞船」に乗り、海上から鑑賞する作品の一つ。神戸の詩人たちが戦前、戦後、現代に綴った9つの詩が透明なアクリル板に記され、詩の言葉というフレームを通して、現在の神戸の風景を見るというものだ。伸びゆく線路と発展、都市の中の孤独、空襲、そして再び街が炎に包まれた震災……。紡がれた言葉は、場所の記憶への想起を誘う通路となるが、そのフレーミングは波に揺られるたびに不安定に揺れ動き、むしろ眼前の「現在」との時間的・空間的距離の中に「見えないもう一つの風景」が浮かび上がる。

古巻和芳《九つの詩片 海から神戸を見る》
川村麻純の《昨日は歴史》は、映像、写真、テクスト、音声から構成される複合的なインスタレーション。映像では、古い洋館の応接室のような室内が、ゆっくりと360度パンするカメラによって映し出され、淡々と物語る若い女性の声が重なる。明治42年に建てられた「ここ」は山の手の洋館であること、集う人々が口にする南国の果物の名前、「この町」にもあって故郷を思い出させる廟、農民の心情を歌った素朴な歌。「あの国」と「この国」の生徒が混じるも楽しかった学校の思い出、集団結婚式、言葉の通じない義母、結婚50年目に初めて帰郷できたこと。サンフランシスコ講和条約により、それまで「この国」の国民だった「彼女」は国籍を失い、自分は何者なのかという思いに苛まれる。具体的な地名や国名は一切示されないものの、被写体の洋館は台湾からの移民とその子孫が集う会館であり、「彼女」は戦前に台湾から神戸へ嫁いだ女性なのだろうと推察される。ここで秀逸かつトリッキーなのは、語りの視点の移動に伴い、「ここ」「この」「あの」という代名詞の指示内容が移り変わる点だ。「この港」(=神戸)は南米への移民を送り出し、ユダヤ人難民も「ここ」を通過したと声は語る。一方、亜熱帯としては珍しく、冬に雨の多い「ここ雨の港」は、神戸との連絡航路が結ばれた台湾の基隆(キールン)を暗示する。「この港」から「あの港」へ向かう船の中で、「彼女」はひどい船揺れのために目を覚まし、「一瞬、自分がどこにいるのか分からなくなる」。それは生理的な嘔吐感による一時の混乱であり、かつ「ここ」と「あそこ」のどちらにも定位できない移民のアイデンティティのあてどなさであり、さらには語りの視点の自在な移動がもたらす、時制と地理的な理解の混乱をもメタ的に指し示す。

川村麻純《昨日は歴史》
川村は、過去作品《鳥の歌》においても、日本と台湾の両方にまたがる女性の半生の記憶の聞き取りを元に、別の女性が語り直すことで、個人史と大文字の歴史が交錯する地点を虚実入り混じる手法で提示している(《鳥の歌》は、日本から台湾へ嫁いだ女性である点で、本作と対になる作品である)。とりわけ本作では、代名詞のトリッキーな仕掛けにより、移民のアイデンティティの浮遊性を示唆すると同時に、第三者の視点による小説風の文体を朗読する声が、「全てはフィクションではないか」という疑いを仄めかす。しかし、奥の通路に進むと、映像内で語られていた「歌」が、(おそらく記憶を語った高齢の女性自身の声で)聴こえてきた瞬間、そのエキゾティックだがどこか懐かしい旋律を奏でる声は、強く確かな実存性をもって響いてきた。それは、固有名詞を排した語りの匿名性の中に、故郷を喪失した無数の女性たちの生の記憶を共振させる可能性を開くと同時に、一筋の「声」への慈しみに満ちた敬意を手放さない態度である。
また、映像プロジェクションの背面には、写真作品5点が展示されている。室内から窓越しに見える風景を、窓のフレーミングと重ね合わせて切り取った写真だ。うち2点は、写真の上に水色の紐が水平に掛けられ、樹々の向こうに隠れた「水平線」の存在を暗示する。移民とその子孫が集う会館の室内から、窓越しに海の彼方の故郷へ想いを馳せる視線がトレースされる。一方、対峙する壁面には、19世紀アメリカの女性詩人、エミリー・ディキンソンの詩の一節が記されている。ディキンソンは後半生のほとんどを自宅から出ることなく過ごし、自室にこもって多くの詩を書いた。移住によって故郷から隔てられた女性たちが窓の外へ向ける眼差し。閉じた室内に留まったまま、詩という窓を通して、自らの内的世界への探求を鋭敏に研ぎ澄ませた女性の内なる眼差し。さまざまな時代、国籍、状況下に置かれた女性たちの幾重もの眼差しが、「窓」という装置を通して重なり合う。移民女性の歌うかそけき「歌」の背後に、幾層もの「歌」の残響が響きこだまするような、静謐にして濃密な展示空間だった。

左:川村麻純《昨日は歴史》 右:展示会場風景
公式サイト:http://www.kobe-artfes.jp/
関連レビュー
2017/09/15(金)(高嶋慈)
驚異の超絶技巧! ─明治工芸から現代アートへ─

会期:2017/09/16~2017/12/03
三井記念美術館[東京都]
美術史家の山下裕二の監修による超絶技巧の企画展。明治工芸から現代アートまで、約130点の作品を一挙に展示した。同館をはじめ全国の美術館を巡回した「超絶技巧! 明治工芸の粋」(2014-15)の続編だが、「超絶技巧」というキャッチフレーズによって明治工芸を再評価する気運は、本展によってひとつの頂点に達したように思う。質のうえでも量のうえでも、本展は決定的な展観といえるからだ。
むろん、ないものねだりを言えば切りがない。明治工芸の復権を唱えるのであれば、「繊巧美術」の小林礫斎が含まれていないのは欲求不満が募るし、現在において江戸時代の工芸技術の復興を模索している雲龍庵北村辰夫や、比類なき人体造形を手がけているアイアン澤田の作品(さらにはオリエント工業によるラブドールさえ)も、同列で見る欲望を抑えることは難しい。それでも安藤緑山の牙彫や宮川香山の高浮彫に加えて、前原冬樹の一木造りや山口英紀の水墨画など、いまこの時代を生きる同時代のアーティストたちの作品が一堂に会した展観は壮観である。とりわけ微細な陶土のパーツを土台にひとつずつ貼り合わせ、焼成を繰り返すことで珊瑚のような立体造形をつくり出す稲崎栄利子の陶磁や、明治工芸で隆盛を極めた有線七宝の技法を駆使しながら蛇と革鞄を融合させた春田幸彦の七宝など、これまでほとんど知られることのなかった作家たちの作品を実見できる意義は大きい。
超絶技巧の歴史的な系譜──。明治工芸と現代アートをあわせて展示した本展のねらいが、この点にあることは間違いない。明治工芸の真髄は戦後社会のなかで見失われたかのようだったが、きわめて例外的であるとはいえ、ごく少数の希少なアーティストによって辛うじて継承されていたことが判明した。帝室技芸員という制度的な保証があるわけでもなく、宮家や武家という特権的な顧客に恵まれているわけでもなく、文字どおり「在野」の只中で、現代における超絶技巧のアーティストたちは人知れずその技術を研ぎ澄ましていたのである。その意味で、彼らの作品を意欲的に買い集めている村田理如(清水三年坂美術館館長)や言説の面での歴史化を実践している山下裕二の功績は何度も強調するべきだろう。
しかし、その一方で、近年の超絶技巧を再評価する機運は、新たな局面に突入したという思いも禁じえない。それが明治工芸を不当にも軽視してきた近代工芸史の闇を照らし出す灯火であることは事実だとしても、その歴史的系譜を現代社会で生かすには、展覧会での紹介や言説の生産だけでは明らかに不十分だからだ。つまり、超絶技巧を現代社会のなかに定着させる実務的な取り組みが必要である。流行現象として消費するだけでは、いずれ再び「絶滅」を余儀なくされることは想像に難くない。
超絶技巧の制度化。制作に長大な時間を要するアーティストを支えるコレクターを拡充することはもちろん、あらゆるかたちでの公的な支援の体制も整えるべきであろうし、場合によっては帝室技芸員を再興することすら考えてもよいだろう。自己表現という美辞麗句を隠れ蓑にしながら学生を甘やかすだけの美術大学のカリキュラムも根本的に再考しなければなるまい。美術館も例外ではない。モダニズム、具体的にはコンセプチュアル・アートに偏重した歴史観にもとづいた公立美術館の大半は、少なくとも戦後美術に限って言えば、ほとんどゴミのような作品を後生大事に保存しているが、超絶技巧の作品と入れ替えることで戦後美術史を再編することも検討すべきである。在野の美術批評家がいまやある種の「絶滅危惧種」であるように、超絶技巧のアーティストもまた、ある種の「天然記念物」として公的な保護の対象としなければならない。「遺伝子」というメタファーを用いるのであれば、それを保護する制度化の議論を含めない限り、それはたんなる消費のためのキャッチフレーズとして、やがて忘却の彼方に沈んでいくほかないのではあるまいか。
超絶技巧とは、戦後美術を根本的に転覆しうる可能性を秘めた、きわめてラディカルな運動と思想なのだ。その可能性の中心を見失いたくない。
2017/09/15(金)(福住廉)
神戸港開港150年記念「港都KOBE芸術祭」

会期:2017/09/16~2017/10/15
神戸港、神戸空港島[兵庫県]
1858年に結ばれた日米修好通商条約に基づいて、1868年に開港した神戸港。我が国を代表する港湾の開港150年を記念して、地元作家を中心とした芸術祭が開かれている。参加作家は、小清水漸、新宮晋、林勇気、藤本由紀夫、西野康造、西村正徳など日本人作家16組と、中国・韓国の作家3名だ。会場は「神戸港」と「神戸空港島」の2エリア。ただし、神戸港エリアの一部はポートライナーという交通機関で神戸空港と繋がっており、「神戸港」と「ポートライナー沿線」に言い換えたほうがいいかもしれない。芸術祭の目玉は、アート鑑賞船に乗って神戸港一帯に配置された作品を海から鑑賞すること。港町・神戸ならではの趣向だ。しかし残念なことに、取材時は波の調子が悪く、アート鑑賞船は徐行せずに作品前を通過した。通常は作品の前で徐行してじっくり鑑賞できるということだが、自然が相手だから悪天候の日は避けるべきだろう。一方、意外な収穫と言ってはなんだが、ポートライナー沿線の展示は、作品のバラエティが豊かであること、主に屋内展示でコンディションが安定していること、移動が楽なこともあって、予想していたより見応えがあった。神戸空港という「空の港」と神戸港(海の港)を結び付けるアイデアも、神戸の未来を示唆するという意味で興味深い。会場の中には神戸っ子でも滅多に訪れない場所が少なからずあり、遠来客はもちろん、地元市民が神戸の魅力を再発見する機会に成ればいいと思う。
2017/09/15(金)(小吹隆文)
コンサベーション_ピース ここからむこうへ part A 青野文昭展
会期:2017/09/09~2017/10/15
武蔵野市立吉祥寺美術館[東京都]
青野文昭は震災以前から「修復」をテーマにした造形作品を制作してきたが、震災以後、その素材を被災物にしたことから、現在はポスト311の文脈で語られることが多い。その作品とはコラージュのように異物と異物を組み合わせた造形物。だが接続面がシームレスに処理されているため、とりわけ高い異化効果が発揮されているわけではない。むしろ、あたかもその形態が自然であるかのような佇まいで屹然とした存在感を放つところに青野作品の真骨頂がある。
本展は青野の最新作を見せた個展。同館周辺の吉祥寺の街で採集した自転車や箪笥などを縦横無尽に組み合わせた巨大なインスタレーションを発表した。いま「縦横無尽」と書いたが、これは決して比喩ではない。今回発表されたインスタレーションは、これまでの青野の作品と比べてみても、ひときわ造形の身ぶりが全面的に開示されていたからだ。
2013年、東京のギャラリイKで開催された個展では、津波に流された邸宅の床の模様と座卓を融合した作品だったせいか、全体的に水平方向のイメージが強く打ち出されていた。造形は慎重に抑制されていたと言ってよい。しかし、2015年、同じく東京のギャラリーαMでの個展あたりを契機に作品のイメージは垂直方向に転じる。記念碑に近い構築性が出現し、そこには造形への欲望が渦巻いているように見えた。
そして今回発表された新作は、その造形への欲望が外側にあふれ出ているかのようだった。トラックと箪笥が合体したかと思えば、その箪笥の中から自転車が飛び出ている。積み上げた文庫本の塊は子どものように見えるし、箪笥の中には傘をさした男が立っているようだ。これまで青野はきわめて慎重に物と物を融合させてきたが、今回の新作はむしろ大胆に物と物を合体させ、しかも人のイメージを強く打ち出すことで物と人が一体化したような世界をつくり出しているのである。
事実、このインスタレーションは内側に入り込める構造になっていたが、そこには家族写真や古時計などが残されていたせいか、まるで誰かの家庭の居間のような気配が漂っていた。人を実在させているわけではないにもかかわらず、人の気配を濃厚に立ちこめさせること。物質と物質を融合させながら、そのはざまに人間の痕跡を照らし出すこと。青野の眼と手は明らかに物質の先に人間を弄り出そうとしている。重要なのは、その人間像である。それは、むろん現代人の写実的な反映などではありえない。青野によるキメラ的造形のなかで生きる、あるいはそこから飛び出てくるかのような人間は、純然たる人間などではなく、まさしくキメラ的人間なのだ。それが等身大の自画像のように見えたとき、戦慄が走るのである。
2017/09/13(水)(福住廉)
松本美枝子「ここがどこだか、知っている。」
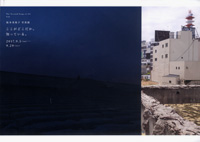
会期:2017/09/05~2017/09/29
ガーディアン・ガーデン[東京都]
松本美枝子は1974年、茨城県生まれ。1998年に実践女子大学文学部卒業後、写真家として活動し始める。写真集『生あたたかい言葉で』(新風舎、2005)、谷川俊太郎との共著『生きる』(ナナロク社、2008)など、日常を細やかに観察しつつ、思いがけない角度から描き出していくスタイルを確立していった。
今回のガーディアン・ガーデンでの個展でも、いかにも松本らしい思考と実践とを一体化した写真の展示を見ることができた。日付け入りの家族写真を再提示した「手のひらからこぼれる砂のように」(2017)、「古生代ゴンドワナ超大陸の海底あるいは高鈴山」、「震災による地盤沈下で消滅した砂浜あるいは河原子海水浴場」の2部から成る「海は移動する」(2017)、東海JCOの臨界事故をテーマにした「想起する」(2017)、日々のスナップ写真をアトランダムに上映する「このやり方なら、知っている。/ここがどこだか、知っている。」(2011~2016)、鳥取藝住祭で滞在制作した「船と船の間を歩く」(2014)、2面マルチのスライドショー「考えながら歩く」(2017)といった作品群は、一見バラバラだが、「時間と、それが流れる場所と、その中に生じる事象について、できるだけ考え続け観察する」という松本の一貫した姿勢を感じられるものになっていた。
特に興味深かったのは、会場の3分の1ほどのスペースを使ったスライドショー、「考えながら歩く」で、天気予報や歌などの日常の音と映像とが少しずつズレたりシンクロしたりしながら進行することで、観客の意識に揺さぶりをかけるつくりになっていた。われわれが「絶えず揺れ動く世界の際」にいることが、一見穏やかだが、微妙な裂け目を孕んだ映像の集積によって提示されている。展示を見ながら、そろそろ次の写真集もまとめてほしいと強く思った。
2017/09/13(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)