artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
人間写真機・須田一政 作品展「日本の風景・余白の街で」

会期:2022/09/29~2022/12/28
フジフイルムスクエア写真歴史博物館[東京都]
須田一政は1986年に、フジフイルムスクエアの前身である東京銀座の富士フォトサロンで、「日本の風景・余白の街で」と題する展覧会を開催している。今回の展示は、その時の出品作43点から32点を選び「当時の作品の階調、色調を忠実に再現」したプリントによるものだった。
須田は写真集『風姿花伝』(朝日ソノラマ、1978)に代表されるように、6×6判の黒白写真をメインに作品を制作していた。だが1980年代になると、本作のようにカラー作品を積極的に発表し始めた。カラーフィルム(富士フイルム製のフジクローム)を使用することで、色という表現要素を手にした須田は、日常の光景に潜む悪夢のような場面を、より生々しくヴィヴィッドに描き出すことができるようになる。
本作は東京だけでなく、京都、三重・伊勢、長野・小諸、大阪など、日本各地の「観光地」で撮影した写真群を集成したものだが、そこで彼が目を向けているのは「平面上に在る日常という『かげ』の存在」であり、「自らの周辺におこり得る刹那的な特殊空間」である、そのような魔に憑かれたような特異な気配を嗅ぎ分け、素早くキャッチする能力の高さこそが須田の真骨頂であり、それはまさに本展のタイトルである「人間写真機」そのものの機能といえるだろう。
「人間写真機」というのは、どうやら本展のために考えられた造語のようだが、須田の写真家としての「習性」を見事に言いあらわしている。須田は本作以後も、2010年代に至るまで、眼差しとカメラとが一体化した「人間写真機」としての仕事を全うすることになる(2019年に逝去)。そろそろどこかで、その全体像を見ることができる展覧会を企画してほしいものだ。
公式サイト:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/220929_05.html
2022/12/04(日)(飯沢耕太郎)
DAZZLER

会期:2022/11/05~2022/12/10
京都芸術センター[京都府]
生物が捕食者の目を眩ませる「擬態」は、「迷彩」という戦争技術の着想源となった。本展は、そうした擬態、迷彩、目眩しといった視覚の技術が、「不都合なものの隠蔽」「不可視化」「社会的排除」のために用いられ、ジェントリフィケーション、隔離政策、「国民の健康増進」といった生政治的権力に奉仕してきたことを突きつける、極めて明瞭な批評性に貫かれたグループ展だ。企画者の林修平のほか、永田康祐、五月女哲平、飯山由貴、吉田裕亮、木原結花が参加した。
第1展示室の永田康祐、五月女哲平、飯山由貴の作品は、「視認不可能性」「不可視化」のキーワードで捉えられる。永田康祐の映像作品《Theseus》は、都市の高層ビル群を映し出すが、像には無数の歪みが発生している。この歪みは、Photoshopの「スポット修復ブラシツール」による。修整したい範囲を指定すると、周辺の画素を用いて、周囲と滑らかに連続して自然に見えるように自動的に修整する機能だ。永田の作品では、この画像修整機能を画面全体に施すことで、元の画像は1ピクセルも残さず「修整後」のものに置き換わり、もはやその必要がなくとも「修整」がさらに上書きされていく。タイトルが示す「テセウスの船」は、「ある船を構成するパーツをすべて別のパーツに置き換えたら、それは“元の船”と同一だと言えるのか」というアポリアだ。永田の作品では、「いま、どの部分が修整中なのか」それ自体は視認できず、「修整の常態化」だけが画像の歪みとしてそこにある。映された風景にはブルーシートとタワークレーンが見え、「再開発」を示す。「画像修整」すなわち「不都合なものの排除と隠蔽」が常態化し、もはや視認不可能になった「日常の風景」に私たちが暮らしていることを、永田の作品は逆説的に可視化する。

永田康祐《Theseus》
『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]
五月女哲平は、「黒い正方形に正円」という同じ構図、同サイズの絵画を約30枚、一列に並べるが、円の色は隣と微妙に異なる明度で塗られ、灰色のグラデーションを形成し、色どうしの「境界線」を確定できない。だが、徐々に「黒」に近づいていく円は、最後の一枚で「地」と完全に同化し、画面は真っ黒に塗り潰され、一枚だけ切り離して展示される。「差異のグラデーション」が、次第に単一の色に近づき、「真っ黒」に塗り潰された沈黙を強いられる。視覚的認知についての問いと同時に、幾何学的構図が「日の丸」を想起させることで、差異を塗り潰して同化を強いていく抑圧的な構造それ自体の可視化としても解釈できる。

五月女哲平《満ち欠けの先に》
『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]
飯山由貴の《湯気 けむり 恩寵》は、大正時代の新聞記事のスクラップブックを起点に、書籍、音源、映像、当事者へのインタビューなどのリサーチ資料により、皇室プロパガンダとしての「救癩事業」を歴史的射程で掘り起こす。聖武天皇の妃・光明皇后が、ハンセン病患者の身体を清めて癒した伝説の残る法華寺の浴室。大正天皇妃・貞明皇后が詠んだ短歌を元にした歌が、強制隔離政策の推進キャンペーンとして使われたことを示すレコード。「ハンセン病療養所で皇后にお目にかかった」と話す、元患者のインタビュー。法華寺の浴室を映す映像は、立ち込める「湯気」で次第に白く曇っていく。そこに、「私たちは、亡くなって煙となることではじめて自由になる」という別の元患者の言葉が添えられることで、この「湯気」は、優生思想に基づく強制隔離政策すなわち「社会からの排除と不可視化」のメタファーとして立ちのぼる。

飯山由貴《湯気 けむり 恩賜》
『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]
飯山と同様、ハンセン病の強制隔離政策のリサーチを行なってきた吉田裕亮は、国家による「国民の身体の管理」を「スポーツ」という別の側面から扱う。《健民になるための建築》では、立方体のコンクリートブロックの上面に、「健民修練所」「建國体操」など大日本帝国が戦時中に実施した健康増進政策に関する言葉や図像が刻印されている。コンクリート基礎を剥き出しにすることで、スポーツの推奨や表彰制度による「健康な身体」の管理体制が、文字通り「国家の(見えない)基盤」を成していることを可視化する。

吉田裕亮《健民になるための建築》
『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

吉田裕亮《健民になるための建築》
『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]
また、林修平の《帝國水槽》は、一見普通の水槽だが、1942年発行の『満州水草図譜』に掲載された水草数種が飼育されている。植物の採集や飼育装置と植民地主義の関係を示す例として、近代ヨーロッパで活躍したプラントハンターが想起される。アフリカやアメリカ大陸、アジアに赴き、希少で有用な植物を採集してヨーロッパへ持ち帰り、繁殖を試みたプラントハンターは、植物学の発展に寄与すると同時に植民地主義的欲望と密接に関わっていた。林の水槽もまた、そうした欲望を「箱庭的世界の所有と管理」として提示する。

林修平《帝國水槽》
『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]
このような吉田と林の作品を、〈帝国の統治の技術〉と名づけてみよう。ここで再び飯山の作品に戻ると、「ジェンダーと性別役割分業」もまた〈帝国の統治の技術〉として巧妙に利用されてきたことがみえてくる。戦前の皇室関連の新聞記事を大量に貼り付けたスクラップブックが示すのは、軍隊(国民=兵士)のトップに君臨する「天皇の身体」だ。一方、皇后(女性・妻)には、「病人を癒す」看護とケアの役割が割り当てられてきた。明治期以降の皇室は、「近代化」を国民にお手本として示すと同時に、正統性の基盤としてさまざまな「伝統」を召喚したが、「ハンセン病患者のケア」を行なった光明皇后もその一例である。一方、戦後の「皇室の民主化」すなわち非軍事主義化により、「大元帥としての天皇の身体」は姿を消し、「ケアを担う身体」に吸収された(被災地を見舞う平成天皇「ご夫婦」はその端的な例である)。このような文脈を踏まえるとき、飯山の作品は、〈帝国の統治の技術〉としての性別役割分業もまた、「恩寵としての湯気」の背後に隠れて見えにくくなっていることを語りかけるのだ。
公式サイト:https://www.kac.or.jp/events/32708/
2022/12/03(土)(高嶋慈)
六本木クロッシング2022展:往来オーライ!

会期:2022/12/01~2023/03/26
森美術館[東京都]
日本のアートシーンの現在を見せる3年に一度の「六本木クロッシング」。7回目のテーマ(というよりサブタイトル)は「往来オーライ!」というダジャレなもの。かれこれ3年にも及ぶコロナ禍によって内外の交流が途絶え、創造活動もズタズタに分断されてしまったアートシーンにおいて、ポストコロナを見据えて人々の往来を再び取り戻そうとの意図があるようだ。もともと「創造活動の交差点」を目指す「六本木クロッシング」であってみれば、そこにさらなる往来を注ぎ込むことで六本木交差点以上の賑やかな祝祭的空間が現出するんじゃないか、と勝手に期待したが、幸か不幸かそんなことはなかった。
出品アーティストは22組。O JUNや石垣克子らの絵画、石内都や金川晋吾らの写真、青木野枝やAKI INOMATAらの彫刻、潘逸舟やキュンチョメらの映像といったように割と明快にメディアが分かれ、インスタレーションやミクストメディアは意外と少ない。しかも絵画は壁に、彫刻は床に、映像はブースに展示されるなどきちんとテリトリーが分かれ、作品同士が干渉することなくおとなしく収まっている。いやもちろんそのほうが見やすくていいのだが、展覧会全体としてはよくも悪くも「交通整理」されていて、スクランブル交差点みたいな賑わいは感じられない。もっと作家同士、作品相互の交差・往来があってもよかったのではないか。
そんななかでも、松田修、池田宏、キュンチョメらの作品が並ぶ横丁は少し吹きだまり感があって不穏な空気を漂わせていた。でもアイヌやトランスジェンダーを主題にした作品は見て楽しめるものではない(もちろん楽しけりゃいいってもんでもないが)。いちばんワクワクしたのは、やんツーから竹内公太を抜けてSIDE COREに至る並びだ。やんツーは、自律搬送ロボットが棚に並ぶ石膏像や工芸品、仏像、石ころなどからひとつを選んで運び、また戻しては別のひとつを運び……を繰り返すシジフォス的なインスタレーションを公開。竹内はランプ付きの警棒を振り回してアルファベットを描き、光跡写真に撮ってオリジナルフォントを制作。SIDE CORE/EVERYDAY HOLIDAY SQUADは、夜間工事用の照明器具を組み合わせたインスタレーションと、作業着を着たスケーターが東京を滑走する映像を出品。ストリート感あふれるコーナーになっていた。

六本木クロッシング2022展
SIDE CORE/EVERYDAY HOLIDAY SQUAD《rode work ver. Tokyo》(2018/2022)[筆者撮影]
公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/roppongicrossing2022/index.html
2022/12/01(木)(村田真)
レオナルド・ダ・ヴィンチ理想都市模型展──感染症に立ち向かう 500年前の理想都市

会期:2022/11/17~2022/12/11
静岡文化芸術大学 ギャラリー[静岡県]
昨年末に静岡文化芸術大学を訪問した際、ミラノ時代のレオナルド・ダ・ヴィンチが構想した理想都市の大きな木造模型(3m×1.7m)があると聞いて、梱包を解いて見せてもらい、これはもっと広く知られるべきものだと感想を述べたのだが、およそ一年たって、同大学の松田達の企画によって展覧会が実現されることになった。
会場では、模型の3DCG映像、VRの体験、模型のARやプロジェクション、関連資料としてパネルや書籍などを紹介している。ちなみに、理想都市といっても、全体の輪郭が円形といった概念的なものではなく、ダ・ヴィンチのそれはかなり実践的なアイデアで、当時のペストの流行を踏まえて、疫病対策も意識したものだった。ゆえに、コロナ禍を体験した現代の視点から見ても興味深い。また人間と馬車が通る道路を上下で分離し(いまのペデストリアンデッキ)、運河を含む交通のネットワークを立体的に組み立てたり、水はけの良さなど細かく検討している。古典的なパラッツォ風の意匠を剥ぎとると、近現代の都市デザインにも通じるだろう。

2021年の訪問時に見たダ・ヴィンチの理想都市の木造模型

模型の3DCG映像

VR体験ができるコーナー

模型に投影されるプロジェクション・マッピング
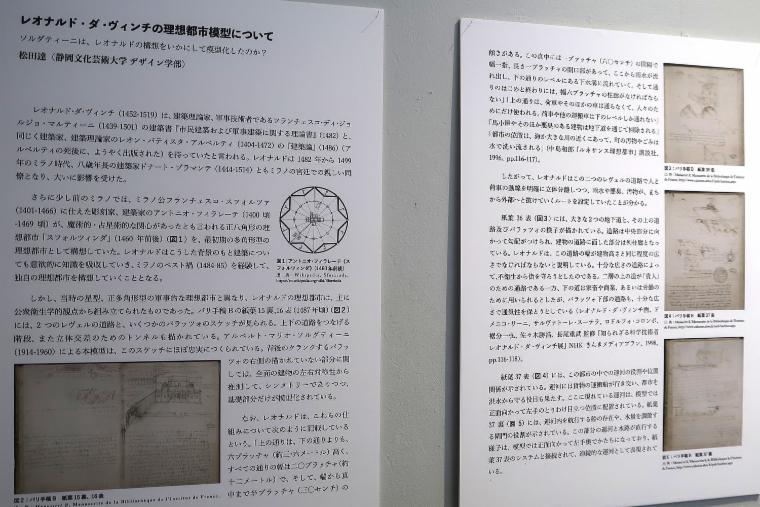
解説パネル

今回の展示

ポスターコンペ
ちなみに、あくまでもダ・ヴィンチは15世紀末にいくつかの断片的なスケッチを残しており、模型は当時のものではない。今回展示されたのは、ダ・ヴィンチの科学技術博物館の設立に尽力したにイタリア人の航空技師、マリオ・ソルダティーニが1956年に制作したものである。そして池袋の西武百貨店が1984年のイタリアン・フェアに際して、これを入手した後、解説を執筆したルネサンスの建築史家、長尾重武を通じて、武蔵野美術大学に移管されていたが、さらに静岡文化芸術大学に寄贈されていた。ともあれ、模型だけを見ると、ダ・ヴィンチがまるで全体像を構想していたような錯覚に陥るが、実際はソルダティーニが独自の解釈によってつなぎあわせている。ゆえに、モダニズム的な感覚によって再配置されたかもしれない。また詳細に観察すると、スケッチとの微妙な差異(意匠や装飾)、あるいは表現の違い(上部の壁をなくしたり、追加)などにも気づく。したがって、約半世紀以前につくられた都市模型も、別の歴史的な価値をもつ。改めて、模型が木造ゆえに、ほとんど劣化していないことにも驚かされる。実際、ルネサンス時代につくられた木造の建築模型は、今なお文化財として残っているくらいだから、相当の耐久性があるはずだ。おそらく、都市模型そのものも研究のテーマになるだろう。

パルマノヴァの模型
2022/11/27(日)(五十嵐太郎)
サトウアヤコ「日常記憶地図『“家族”の風景を“共有”する』」

会期:2022/11/23~2022/11/27
トーキョーアーツアンドスペース本郷[東京都]
会場には、たくさんの椅子があって、観賞者が机の上にある地図、言葉が書かれた単語帳のようなものや、ファイルに挟まっている文献のコピーを静かに読んでいる。机は大きく三つ点在しており、それぞれ、ある人物が家族について知りたい、知りたかったが叶わなかったという思いから「日常記憶地図」に取り組んだ様子が並べられたものであった。それぞれの尋ね手から見て、叔母/父の1940〜50年代の佐渡(新潟)、父の1950年代の鯖江(福井)、母/叔母の1960年代のジアデーマ(ブラジル)についての「日常記憶地図」が会場では示されている。
「日常記憶地図」は、サトウが2013年に開発したメソッドで、任意の人物へ「場所の記憶」について聞くことを通して、普段の関係性ではわからないその人を知ることができるというものだ。手順がパネルとハンドアウトに書かれていた。ハンドアウトには「日常記憶地図」の使い方から心づもりまで丁寧かつ簡潔に掲載されている。
〈手順〉
・思い出したい時期の地図を用意する。
・地図に、当時の家の場所、よく行く場所/道をなぞる。
・場所/道それぞれ、よく行った理由や習慣、思い出した記憶を書く(聞く)。
・最後に「愛着のある場所」について聞き、当時の生活圏を囲む。
サトウによるハンドアウトでも示唆されているが、「日常記憶地図」が可能にするのは、固定化された昔語りの解体である。写真をよすがに語るのとも、語り伝えてきた記憶を再び手繰り寄せようとするのとも違う。目の前に地図があり、その場所、ある風景について話そうとするとき、特異的な事象よりも、反復していた移動や行為、すなわち日常がベースとなる。これは、オーラルヒストリーの収集にあたって、尋ね手が年表を携えて編年的に問うことと、似て非なる行為だ。同じ地図を見て、同じ風景をお互いが初めて見ようとすることになるメソッド。このとき、語り手と尋ね手の記憶の量の不均衡は、いったん留保される。このことが本展における“共有”なのかもしれない。
正直、わたし自身はそれぞれが地図を辿ろうとするときの、その思慕がぽろっとこぼれる欠片で、居ても立ってもいられなくなってしまったのだが、パネルには、各人が体験を振り返って、落ち着いたコメントを寄せている。そのなかのひとりは、自身に子どもがいないこともあり、何かを残しておきたいという気持ちがあったかもしれないと綴っている。
「家族」のことを知っているようで、それぞれの役割を離れたときの家族のことはまるで知らないという、他者としての家族にサトウは目を向け、「日常記憶地図」を育んできた。このとき、サトウがハンドアウトで記す「そしてその記憶は、10年、20年後にまた別の“家族”に“共有”される可能性を持つ」の引用符は何を意味しうるのか。それは場所が誰かにその記憶を再度発生せしむる可能性のことなのかもしれない。その場所がたとえ消えたとしても。家族がいないとしても。
会場にある展示台には、「あなたの風景は失われることはない」「並んで風景を眺める」「人はそれぞれの世界を持つ」「日常の中で日常の話はできない」と書かれた紙片がそれぞれ置かれている。ハンドアウトにも同様の言葉が掲載されていた。何らかの切実さを抱え、尋ね手となる誰かへ向けた言葉だろう。「あなたの風景は失われることはない」。その場所がたとえ消えたとしても。家族がいないとしても。
展覧会は無料で観覧可能でした。
公式サイト:https://www.tokyoartsandspace.jp/archive/exhibition/2022/20221123-7125.html
日常記憶地図:https://my-lifemap.net/
2022/11/27(日)(きりとりめでる)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)