artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
藤本由紀夫 Broom(Coal)/Tokyo
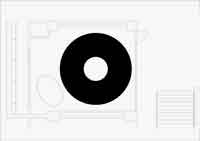
会期:2016/02/06~2016/03/06
シュウゴアーツ ウィークエンドギャラリー[東京都]
ギャラリーいっぱいに黒い石が円環状に敷かれている。石は黒光りしているので石炭とわかる。一瞬リチャード・ロングを想起したが、上を歩いてもいいというのでジャリジャリいわせながら歩いてみる。円環に沿って歩いているうちに、あ、これはレコード盤だと気がつき、自分がレコード針になった気分。「Broom(ほうき)」と題されたこの作品、最初は床に枯れ葉を敷きつめるインスタレーションから始まり(最初に発表した会場が「room B」だったので「Broom」になったとか)、次第に素材や形態を変えながら石炭のレコード盤になったという。考えてみれば石炭はレコード針に使われるダイヤモンドと同じ元素だ。横のテーブル上にはオルゴールを使った小品がいくつかあって、歯が全部そろってる手巻きオルゴールがひとつ、あとは歯が1本しかないもの、ぜんぜんないものなど。さすがに歯が1本だけではなんの音楽かわからない。また、箱のなかにオルゴールが二つ入っていて、ひとつは右から1、3、5……という奇数番目の歯、もうひとつは2、4、6……という偶数番目の歯しかない。同時に鳴らしても同調しないが、なんの曲かはなんとなくわかる。オルゴールひとつでこれだけ遊べるとは。
2016/02/13(土)(村田真)
本城直季「東京」

会期:2016/02/12~2016/03/28
キヤノンギャラリーS[東京都]
本城直季は2006年頃からヘリコプターからの空撮で東京を撮影しはじめる。主に「空気が澄んで遠くまで見通せる」正月の3カ日を選んで撮影を続けたという。それら、使い慣れた4×5インチサイズの大判カメラで撮影された写真群に、高画素のCanon EOS5Dsを使った近作を加えたのが、今回のキヤノンギャラリーSでの展示である。
デジタル一眼レフカメラでの撮影は、本城に大きな解放感をもたらしたようだ。フィルムホルダーを取り替えてセットし直さなければならない大判カメラでは、1回の飛行で撮影できるのは、せいぜい30~40カットほどだ。デジタルカメラなら撮影枚数の制限はなくなる。さらに、ちゃんと写っているのかと心配することなく、安心してのびのびとシャッターを切ることができる。そのことによって、「東京をスナップする」という感覚が強まってきた。
さらに、今回の展示で本城は大きな決断をした。画面の一部にのみピントを合わせて、あとはぼかすことで、ミニチュアのジオラマのような視覚的効果を生じさせる従来の手法の作品と、画面全体にピントが合っている作品とを並置しているのだ。結果的に、つねにうごめきつつ増殖していく巨大都市「東京」の変貌のプロセスを、多面的に定着することができたのではないかと思う。また今回の展示は、あえて東京タワーのようなランドマーク的な建造物を外した作品で構成している。「どこまでも果てしなく続く密集した建造物の景色」に限定することで、「東京」という都市の基本的なエレメントが、くっきりとあぶり出されてきた。120×150センチという大判プリントによる細密描写も含めて、「デジタル化」が彼の作品世界をどう変えていくかが楽しみになってきた。
2016/02/13(土)(飯沢耕太郎)
西野彩花個展「一齣」

会期:2016/02/10~2016/02/23
DMO ARTS[大阪府]
玄関周りの植栽や積み重ねたガラクタなど、日常生活で出会った生活感あふれる情景(主に下町)をスナップ撮影し、キャンバス上でトリミングを施し、ソフトフォーカスで表現した西野彩花の絵画。モチーフや手法は必ずしも珍しくないが、余白の生キャンバスと描画部分の対比、夕景を思わせる黄色がかった色調、強調された陰影表現が効果的で、独自の絵画世界の構築に成功している。また、作品名に撮影場所の地名を入れているのも、効果的な演出と言える。他には玩具などの品々を組み合わせた静物画もあったが、現時点では風景画の方が圧倒的に良い。作家は昨年3月に美術大学を卒業したばかりの新鋭。今後の活躍が楽しみだ。
2016/02/12(金)(小吹隆文)
原田直次郎 展──西洋画は益々奨励すべし

会期:2016/02/11~2016/03/27
埼玉県立近代美術館[埼玉県]
“油絵の先駆者”高橋由一と“近代絵画の立役者”黒田清輝のあいだに、渡欧して油彩技法を身につけた洋画家が何人かいる。五姓田義松、山本芳翠、松岡寿、原田直次郎ら明治美術会の画家たちで、みんな抜群に絵がうまい。由一や清輝よりうまいと思う。なのに由一と清輝の陰に隠れてほとんど日の目を見なかったのは、モダニズムとナショナリズムのせめぎ合いに揺れた明治美術史のいたずらというほかない。とりわけ原田直次郎は36歳で夭逝したこともあって、没後10年の1909年に親友の森鴎外が企画した遺作展以来、本格的に紹介されたことはなく、今回がじつに100余年ぶりの回顧展になるという。ただ活動期間が短かったため作品点数が少なく、松岡寿や大下藤次郎、ドイツで交流のあったガブリエル・フォン・マックスやユリウス・エクステルらの作品も出ているため、キャプションを確かめずに絵だけ見てすべて原田の作品だと勘違いするアホもいるかもしれない。原田の代表作《靴屋の親爺》や《老人》なんか何点も出ているから要注意だ。まあこれだけ作品が模写されるというのは、いかに原田が慕われていたかということの証だろう。この《靴屋の親爺》や《老人》などはよくも悪くも日本人離れした技量を誇るが、帰国後ナショナリズムの吹き荒れる日本では受け入れられず、《騎龍観音》や《素尊斬蛇》といった日本的主題に基づくキッチュな折衷絵画に向かわざるをえなかった(前者は埼玉には出品されず、後者は関東大震災で焼失)。こういう逆境のなかで制作した苦肉の作品というのは、いつの時代にも興味深いものだ。いずれにせよ、歴史のはざまに埋もれて目立たなかった画家の発掘は公立美術館の重要な役割だと思う。
2016/02/11(木)(村田真)
青木陽「Inverted Spectrum」

会期:2016/02/09~2016/02/26
ガーディアン・ガーデン[東京都]
青木陽の写真の仕事には以前から注目している。2013年に東川町国際写真フェスティバルの一環として開催された「赤レンガ公開ポートフォリオオーディション」でグランプリを受賞し、翌14年に東京・東銀座のArt Gallery M84で展示された「火と土塊」のシリーズでは、濃密なグレートーンのセレニウム調色のプリントに徹底してこだわり、印画紙上に別次元の現実を構築する。ところが第12回写真「1_WALL」展グランプリ受賞者個展として開催された「Inverted Spectrum」では、まったく異なるアプローチを試みていた。
青木が今回の写真制作を通じて見出そうとしているのは、「自分自身の置かれた状況を含む現実の中で発生する出来事の意味」である。1990年代から2000年代にかけて、女性写真家を含む若い世代が、物語性を欠いたごく私的な日常の出来事を、あたかもそのまま撒き散らすような写真を提示し、それらが広く受け入れられた時期があった。写真新世紀や写真「1_WALL」展の前身である写真「ひとつぼ」展などの審査をしていると、たしかにこの種の「日々の泡」のような写真群を大量に目にすることができた。青木の今回の試みは、かつては感覚的、無自覚的におこなわれていたプライヴェートな出来事の写真化を、論理的、自覚的に再検討しようとするものといえる。
会場に展示されているのは「ホームの扉」、「電車のシート」、「コップ」、「台所のタイル」といった「ごく身近な人々、生活の一部、時々の目先の出来事」などの断片的な画像である。だが、青木の手にかかると、それらに奇妙なバイアスがかかっているように見えてくる。手が届くようで届かない、ありそうであり得ない事物や事象──あたかもカフカの小説の中に描写されているオブジェや風景のようでもある。曖昧でありながら明晰でもあるこれらの写真群は、もしかすると「私写真」の伝統を受け継ぎつつ再構築する、新たな写真表現の可能性を孕んでいるのかもしれない。青木が次に何を見せてくれかが楽しみだ。その行方を注視していきたい。
2016/02/10(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)