artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
クレア・ビショップ『ラディカル・ミュゼオロジー』
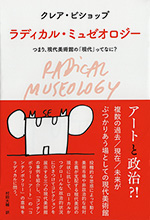
翻訳者:村田大輔
発行所:月曜社
発行日:2020/04/30
『人工地獄―現代アートと観客の政治学』(フィルムアート社、2016)、「敵対と関係性の美学」(『表象』05、2011)の邦訳が紹介されている美術史家・批評家のクレア・ビショップ。本書は、副題の「つまり、現代美術館の『現代』ってなに?」が示すように、「現代美術館」における「コンテンポラリー」の意味を問い直す美術館論である。
ビショップはまず、ロザリンド・クラウスの論考「後期資本主義的美術館の文化理論」(1990)を引きつつ、グローバル資本主義下における現代美術館のあり方を批判する。それは、スター建築家の署名を冠した巨大で派手な建造物の中で、(白人男性が多い)スター作家の個展が開かれるという、「新しさ、クールさ、フォトジェニック」といった「イメージの水準」での「コンテンポラリー」を劇場化する装置に過ぎず、コレクション形成を通した歴史との対話が軽視されているとビショップは指摘する。
またビショップは、「コンテンポラリー」の定義を時代区分で定める態度にも懐疑的だ。それは、「第二次大戦後」、「1960年代」、「冷戦終結の1989年」と、時代の変遷によって絶えず揺れ動いてきたからだけではない。そもそもそうした歴史認識自体が覇権的な西洋中心主義であり、非欧米圏のなかでも、(旧)共産圏、旧植民地およびその終結時期の差異により、「現代」の開始をどこに措定するかが異なるからだ。
ビショップはさらに、「イズムの交代史」としてのモダニズムに顕著な単線的な歴史記述の最先端に刹那的な現在として「コンテンポラリー」を位置づける態度も、未来への前進の代わりに「停滞した現在」しかないというポストヒストリカルな醒めた態度も退ける。これらに代わってビショップが提示するのは、複数の時間性が乖離しながらも重なり合う「弁証法的同時代性」であり、それは過去を通して現在の状況を理解・診断し、その変革の可能性を探る「新しい政治的想像力の基盤」(32頁)であるという。
こうした「弁証法的同時代性」の実践領域としてビショップが評価・分析するのが、コレクションを持つ現代美術館である。歴史的な文化認識の指標の保管庫でありつつ、新たに加わる収集作品によって未来に予見されるオルタナティブな価値基準をつくり上げていくコレクションは、「
ここで、「弁証法的同時代性」の実践領域である「コレクションを持つ現代美術館」と比較されるのが、グローバル化されたビエンナーレと、「年代順展示の廃止に代わって導入されたテーマ展示」である。前者は歴史から切り離された「現在主義」の追認であり、後者は多様な歴史的・地理的差異を新奇なテーマのもとに捨象し、交換可能なものとして等価にしてしまう相対主義であり、市場迎合的であるとして批判される。
では、ビショップが提起するコレクション展示の新たなパラダイムとはどのようなものか。ビショップはそのモデルを、ファン・アッベミュージアム(アイントホーフェン/オランダ)、ソフィア王妃芸術センター(マドリッド)、メテルコヴァ現代美術館(リュブリャナ/スロヴェニア)という三つの現代美術館のコレクション活動から、実践的に引き出す。再制作や過去の展覧会の再構築(ナチス時代の「退廃芸術展」「大ドイツ芸術展」[1937]も含む)によって、コレクション形成の力学を可視化し、過去との時代的距離のうちに現在を測定しようとするファン・アッベミュージアム。また、中東のコンセプチュアルなアートの紹介や、ピカソ作品のパレスチナ貸出プロジェクトは、現代オランダにおけるイスラムフォビアとの対峙を示す。ソフィア王妃芸術センターは、美術作品を映画、出版物、ポスター、雑誌といった視覚文化の時代的文脈に位置付けて紹介すると同時に、ファシズムと植民地支配の負の歴史への反省的思考を促す。メテルコヴァ現代美術館は、共産主義の失墜と旧ユーゴスラヴィアの内戦にどう向き合うかという歴史の表象についての問いを俎上にのせ、コレクション展示の「反復」と差異のうちにメッセージ性を込める。いずれも、欧米の周縁地域に位置し、アーカイブ資料を創造的に活用しながら、現在の政治的課題と歴史への反省的な眼差しの要請が、コレクションの再活性化を駆動させている点が共通する。
本評の執筆時の5月後半、すでにドイツや中国などでは美術館が再開し、非常事態宣言が全国で解除された国内でも6月初旬にかけて再開(予定)が進んでいる。世界的なパンデミックの終息とワクチンの実用化までは、大量集客型のブロックバスター展や海外からの大規模な作品貸出は難しく、国内の他館からの貸出や、特に自館のコレクションを中心に組み立てる企画が増えるだろう。それは、「収集と保存」という美術館活動の根幹に改めて光が当てられる機会である。と同時に、コレクション=価値の一元的な固定化ではなく、つねに生成される「現在」の眼差しの下でいかに過去を再編成し、未来への生産的な投企を行なっていくかという流動的なプロセスであることがより強く問われていく。そうした状況下で、本書の示唆はきわめて大きい。
2020/05/26(火)(高嶋慈)
福田和代『東京ホロウアウト』

発行:東京創元社
発行日:2020/03/19
本書は近未来小説と言うべきなのか、リアリティー小説と言うべきなのか。時は2020年7月。東京オリンピック開幕直前のおよそ10日間を描いたサスペンス小説である。そう、本来ならいまごろ、東京をはじめ日本はオリンピック一色で盛り上がり、56年ぶりの高揚感を味わっているはずだった。それなのにウイルスの恐怖に怯え、経済がこれほど冷え込むとは、いったい誰が想像しただろう。本書は2018〜2019年に雑誌連載された作品を加筆修正したものであるため、当たり前だが、東京オリンピックが開催されることを前提に書かれた。東京中がハラハラとした危機にさらされるリアリティー小説だったはずなのだ。それなのにあり得た現実(東京オリンピック)があり得なくなったいま、本書は別の意味でのファンタジーとなってしまった。サスペンス小説であるのに、小説上で起きている「現実」が非常に眩しく感じてしまったのは、私だけか。
主人公は長距離トラックドライバー。正直、本書を読むまではトラックドライバーに対して何の関心も抱いていなかったが、彼らは物流を支えるプロであることが一貫して語られる。農業や漁業生産地から問屋や市場、スーパーマーケットやコンビニエンスストアへ、また個人宅から個人宅へ。そうなのだ、いまの世の中でわずかでも止まった途端、混乱が起きかねないのが物流である。例えばコンビニエンスストアに、毎日、たくさんの弁当が並べられている。その当たり前の光景を実現するために、いったいどれだけの人々が懸命に働いているのか。誰も意識すらしていなかった社会や物流のデザインを知らしめるがごとく、本書ではさまざまなテロが起きる。トラックの荷台を狙った青酸ガス発生事件に始まり、鉄道の線路破壊、高速道路のトンネル火災、トラックの車両爆破事件など。これらの事件が重なり、物流が徐々に止まることで、「東京が空っぽになる」ことに皆が気づいて恐怖を覚えるのだ。
最大消費地である東京を支えるために、この国はあるのか。実に軽やかに書かれた小説であるのに、読後にはこうしたメッセージが重くのしかかる。華々しく開かれるはずだった東京オリンピックが延期されたいまだからこそ、それをより深く考えさせられる。
2020/05/24(日)(杉江あこ)
「見る」という超能力──マーク・チャンギージー『ヒトの目、驚異の進化』

発行所:早川書房
発行日:2020/03/05
「見る」ということについて考え始めると、宇宙や生命について思いを巡らせるのにも似た不可思議な気分になる。なぜ外の世界がこれほどリアルに「見える」のか、いや、外の世界は本当に見えているように存在するのか、私が見ている赤色と他人が見ている赤色は同じ色なのか、そもそも世界に色はついているのか、視界は私の内にあるのか、外にあるのか、なぜ、どうやって外の世界が「見える」ようになったのか、見えるようになった動物はどう変わったのか……。
最後の疑問については、アンドリュー・パーカーが『眼の誕生──カンブリア紀大進化の謎を解く』(草思社、2006)で説得力のある答えを出している。生命の誕生はおよそ35億年前に遡るが、長く緩慢な進化の末、5億4300万年前からわずか500万年ほどのあいだに(地球史からすればほんの一瞬)突如として動物種が多様化し、現在のような複雑な形態をとるようになった。この「カンブリア紀の爆発」と呼ばれる大進化を促した要因が「眼」の誕生にあったというのだ。眼(レンズ眼)を獲得することによって捕食者は獲物を見つけやすくなり、逆に被食者は逃れやすくなる。そのため、ある種の動物は素早く動ける形態に進化し、また別の種は身を硬い装甲で覆うなど、生き残るために多様なデザインを編み出していく。つまり視覚の目覚めが進化圧を促したというわけだ。
これほど「目からウロコ」の大発見ではないけれど、マーク・チャンギージーの『ヒトの目、驚異の進化』は、これまでの視覚の常識を少しずつ覆していく「小発見」の連続であり、それゆえジャブの連打のようにジワジワと効いてくる本である。チャンギージーは初めに、人間の視覚はテレパシー、透視、未来予見、霊読という4つの超能力を備えているとハッタリをかます。専門書ではなく一般向けの啓蒙書なので、ある程度のホラは許容しつつ以下4章を読み進めていくうちに、まんざらホラでもハッタリでもないことが理解されてくる。
第1章では、人間の色覚がどのように発達したかを解き明かしていく。従来は、森のなかで生活していたわれわれの祖先が、色鮮やかな木の実などのエサを見つけるために色覚を発達させたと信じられてきたが、チャンギージーは自分たちの肌の色の微妙な変化を見分けるためだったと考える。かつてあった「肌色」という絵具がなくなったのは、人種によって肌の色が異なるため差別的とされたからだが、著者にいわせれば肌の色はどんな人種でも個人でも一定ではなく、体調や感情の変化によって赤、青、緑、黄色にもなるという。もちろんわずかな変化だが、赤ちゃんがいきむと赤みが増し、肌を押さえると黄色っぽくなり、鬱血すると青みがかることは経験から知っている。こうした変化が見分けられるように人間は顔から毛がなくなって肌が露出し、また、赤ちゃんの顔色で体調を判断するため女性には色盲が少ないのだという。だから人間の色覚は、第1章のタイトルどおり「感情を読むテレパシーの力」といえるのだ。これは納得。
続いて第2章では、人間の両眼が横ではなく前についている理由を探り、それを「透視」するためと喝破する。一般に、ライオンやフクロウなど肉食動物の目は前寄りに、ウサギやニワトリなど草食動物の目は両側についているが、前者は獲物に焦点を合わせるために視野が狭く、後者は捕食者に捕まらないために視野が広いとされる。人間の目も、前方に焦点を合わせて立体視するため前についているといわれてきたが、チャンギージーは立体視より、生い茂る木の葉や枝などの障害物を通して向こう側を見るためだと指摘する。ちょうど目の前に自分の鼻があるにもかかわらず、視野の邪魔にならずに透けて見えるように(鼻の高い西洋人には不思議だろう)、両眼の視差により目の前の障害物をあたかもないかのように「透視」できるというのだ。ここでわれわれの視覚は、左右の網膜に映ったままではなく、脳が修正を加えたイメージを見ていることがわかる。
そのことは次の章でより明確化する。第3章で検討されるのは錯視。チャンギージーによれば錯視とは、人間の目が光を受けて像を結ぶまでにかかる約0.1秒の時差を取り戻すために生じる現象だという。つまり脳は0.1秒遅れの動きを先取りして、ほんの少し未来のイメージをつくりあげてしまうのだ。たとえば、中心から放射状に延びる線の上に2本の平行線を置くと中央が膨らんで見えるが、これは脳が前進中と思い込んで一瞬先のイメージをつくりあげるからだ。これが第3章のタイトル「未来を予見する力」にほかならない。
最後の第4章「霊読する力」で語られるのは、文字と視覚との相性だ。人間は文字を発明したため、百年も千年も前に死んだ人たちの考えを耳にすることができる。これが「霊読」だが、もちろんそれで終わりではない。文字にはアルファベット、ヘブライ文字、アラビア数字、漢字、ひらがな、ハングルなどさまざまあるが、それぞれの文字を基本的な形態要素に分解すると、L T X Y Fなど20種ほどに還元でき、いずれも3画程度に収まる(漢字は文字単位ではなく構成要素に分解する)。この基本的な形態要素は自然を構成する形態要素と重なるため、すべての文字は自然に似るようにつくられたと考えられる。だから表音文字だろうが表意文字だろうが、自然を見るように読むことができるのだ。つまりわれわれが文字をすらすら読めるのは、文字が自然に擬態することで人間の目に適合したからであり、言い換えれば脳が進化したのではなく、文字が進化したのである。
このように、本書はこれまで考えられてきた視覚に関する常識を次々と覆し、わくわくするような新説に書き換えていく。もちろん単なる机上の空論でもオカルティックな珍説でもなく、綿密なデータに基づいた学術的な研究成果であることはいうまでもない。原題のTHE VISION rEVOLUTIONは、革命(REVOLUTION)と進化(EVOLUTION)を重ねたものだが、それは本書で語られている視覚自体の革命と進化を意味すると同時に、本書そのものが視覚論の革命と進化であることを物語っているのではないか。視覚に関する発見はまだまだ続くだろう。それだけ視覚というものは複雑怪奇なシステムなのだ。ありがちな結論だけど、結局「見る」という能力そのものがつくづく人智を超えた超能力だと思う。
2020/05/24(日)(村田真)
パオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕ら』

訳者:飯田亮介
発行所:早川書房
発行日:2020/04/24
コロナ禍で話題を集めているという噂を頼りに、本書を手に取ってみた。このイタリア人作家の文学をこれまでに私は読んだことがないが、専門的で数学的な情報と、叙情的な言葉、強いメッセージ力が備わったエッセイ集で、心に優しく響いた。新型コロナウイルスの専門的な情報については、テレビや新聞などのメディアでさんざん報じられているので、ある程度は聞いたことのある情報であったが、著者は人類のうち感受性人口(ウイルスがこれから感染させることのできる人)を「75億個のビリヤードの球」に例えて、感染症の流行の仕組みを説明するなど、ユニークなエッセイを展開する。なるほど、こうして説明されると、誰もが頭のなかに具体的なイメージを描きやすい。訳者の力もあるのだろうが、非常に滑らかな文体で何編ものエッセイが綴られていた。
圧巻は、著者あとがきとして綴られた「コロナウイルスが過ぎたあとも、僕が忘れたくないこと」である。著者は「すべてが終わった時、本当に僕たちは以前とまったく同じ世界を再現したいのだろうか」と問いかける。そのうえで忘れたくない物事を列挙していく。自分自身の自己中心的な行動をはじめ、初期段階における人々の不信、いい加減な情報の伝播、政治家の態度、欧州の対策の遅れなどを叙情的に批判する。そして今回のパンデミックの原因が、「自然と環境に対する人間の危うい接し方、森林破壊、僕らの軽率な消費行動にこそある」とまで言及する。ウイルスと森林破壊とが直接的な関係があるのかどうかという点はさておき、つまりいまこそゼロベースで人間社会のあり方を見つめ直すときであることを、著者は訴えるのだ。
最近、よく政治家らから「コロナに打ち勝つ」といった言葉が聞かれるが、私はそれに違和感を感じてならない。どんなウイルスとも生物とも、結局、人間は共生していかなければならないからだ。コロナ時代に突入したいま、我々はどう生きるべきか。厚生労働省が打ち出した「新しい生活様式」とか、そういうことではない。実はもっとも大事なのは、我々の心のありようではないか。本書はそんなシンプルなことに気づかせてくれる。
2020/05/22(金)(杉江あこ)
鈴木理策『知覚の感光板』

発行所:赤々舎
発行日:2020年4月13日
鈴木理策は2004年に写真集『Mont Sainte Victoire』(Nazraeli Press)を刊行している。ポール・セザンヌが描き続けた南仏のサント=ヴィクトワール山を撮影したシリーズだが、このときの撮影で8×10インチの大判カメラを使い始めたことも含めて、鈴木にとって大きな転機となるシリーズだった。本書はその続編というべき写真集で、セザンヌだけでなく、クロード・モネといった19世紀の画家たちが描いたフランス各地の風景を撮影した写真が集成されている。ただし、どの写真がどの画家のどの作品をもとにしているという情報の記載は、注意深く避けられている。そのことによって、読者が夾雑物なしに鈴木の写真行為の成果に向き合うことが可能になった。
鈴木が試みたのは、身体の外で進行する、カメラという「機械の知覚」のあり方を、風景を撮影することであらためて検証することだった。肉眼でものを見るときには、過去の記憶に侵食されており、また風景そのものが刻々と変化していくので、知覚の純粋さを保つのはむずかしくなる。だが、まさに「知覚の感光板」というべき大判カメラを使えば、「純粋にものを見る」ことが可能となる。そこに、撮影者の思惑を超えた世界のあり方が出現してくるということだ。
その鈴木の意図は、本書でよく実現しているのではないだろうか。光や風といった「揺らぎ」が多くの写真に取り入れられており、ブレやボケなどをそのまま写し込んだ作品もかなりある。目の前の風景に対峙しつつ、どんな写真ができ上がってくるのかという期待を抱きながらシャッターを切っていくことの歓びが、伝わってくる作品が多かった。須山悠里による、瀟洒な装丁・デザインも素晴らしい出来栄えだ。
関連レビュー
鈴木理策「知覚の感光板」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年12月15日号)
2020/05/21(木)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)