artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
村上仁一『地下鉄日記』

発行所:roshin books
発行日:2020年
村上仁一(むらかみ・まさかず)は、2008年から写真関係の出版社に勤めるようになり、地下鉄を利用するようになった。この写真集は、その通勤の途中で撮られたモノクロームのスナップ写真を中心にまとめたものである。とはいえ、地下鉄以外の写真もかなり含まれていて、いわば「地下鉄通勤者の心象風景」というべき写真集になっている。
地下鉄の写真といえば、ウォーカー・エヴァンズが1938〜1941年にニューヨークの地下鉄の乗客を隠し撮りし、のちに写真集『Many Are Called』(1966)としてまとめたシリーズを思い出す。荒木経惟も1963〜70年に地下鉄の乗客を撮っていて、写真集『SUBWAY LOVE』(IBCパブリッシング、2005)を出版している。彼らの関心が、地下鉄の車内の乗客のどこか虚な、「無意識の」表情に向けられているのに対して、村上がこの『地下鉄日記』で引き出そうとしているのは、むしろ彼自身の内なる感情であるように見える。あとがきにあたる文章で、「いつからか私は、そんな浮き沈みのある自分の精神状態に向けてシャッターを切るようになっていった」と書いているのは、そのことを言おうとしているのではないだろうか。
その「自分の精神状態」の基調となっているのは、「深い憤り」である。といっても、何か特定の対象に向かうものではなく、脈絡のない、漠然とした、不安や哀しみと混じり合った感情の塊というべきものだ。そんな鬱屈感は、ストレスの多い現代社会に生きる誰もが抱え込んでいるものだが、いざ表現しようとすると、なかなかうまくいかないことが多い。たまたま村上は、編集者であるとともに、かつて第16回写真『ひとつぼ展』(2000)や、第5回ビジュアルアーツフォトアワード(2007)でグランプリを受賞したこともある、優れた資質を備えた写真家でもあったがゆえに、それをとても的確に引き出すことができたということだろう。
写真集のページをめくっていくと、どこか身に覚えがある光景が、次々に目の前にあらわれてきて、自分も地下鉄に乗って移動しているような気分に誘い込まれていく。
関連レビュー
村上仁一「雲隠れ温泉行」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年09月15日号)
村上仁一『雲隠れ温泉行』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年07月15日号)
2020/05/11(月)(飯沢耕太郎)
TDC DAY 2020

主催:東京タイプディレクターズクラブ
2020年4月にギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催される予定だった企画展「TDC 2020」が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となった。しかし一方で、同時開催のデザインフォーラム「TDC DAY 2020」が無観客で実施され、YouTubeでライブ配信された。会場で講演した受賞者もいれば、自宅からビデオメッセージを寄せた海外受賞者もいる。アーカイブされたそのコンテンツが、現在もオフィシャルサイトで視聴できるようになっている。というわけで、本稿は「TDC DAY 2020」のレビューとしたい。
タイポグラフィーというと、長い間、文化の中心を担ってきたのは英語を中心とする西洋文字である。その西洋文字が生きるグラフィックデザインを、日本も手本としてきたことは間違いない。国際賞である「東京TDC賞」にもそんな正統的な流れがあるが、今回の受賞作品を観ると、さらに新しい流れが生まれていることを感じた。それは中国語を使った挑戦である。受賞12作品のうち、TDC賞2作品が中国からの作品だった。そのひとつ「Big, or Small」と題した作品は、中国語による西洋環境への“侵略”を表現した実験動画である。英語でつくられた広告物を題材に、Google翻訳でその英語を中国語に翻訳し変換したらどう映るのか。いくつものグラフィックデザインの文字が変換される瞬間を動画に編集し、英語と中国語が混じり合う奇妙で無秩序な世界をつくり上げた。もうひとつの作品「the benevolent enjoy mountains “任者乐山”」は、孔子の言葉である四つの漢字「任者乐山(仁徳のある者は山を楽しむ)」を1文字ずつ立体的に変形させ、雪山に見立ててポスターにした作品だ。それらはもはや文字として認識できないが、雪山という造形で意味を伝える。この作品をデザインしたチームは、これまでに中国語と英語とを同じような印象に見せるタイプフェイスの研究もしてきたという。なんと、前者の方法とは真逆の試みではないか。西洋が中心となって築き上げたモダンデザインがグローバル化するなかで、いま、中国は母国語のアイデンティティーを探ろうとしているときなのかもしれない。中国以上に複数の文字を母国語に持つ日本にとっても、この動きは決して他人事ではないはずだ。
さて、今回の受賞作品にはもうひとつの動きがあった。それは新テクノロジーの登場である。AI(人工知能)が既存の本を読み取り、そのなかから短い詩的な言葉を選び取り、Googleでイラストレーションを検索して装飾し、インターネット印刷を使って自動的に本を出版するという、驚くべきプロジェクト「The Library of Nonhuman Books」がRGB賞に選ばれた。また紙の上でペンを走らせるときの動きを滑らかなアニメーションにした、自動的に文字を作成するツール「Grammatography」も興味深かった。この作品の開発者が言うように、まさにカリグラフィーとタイポグラフィーの良さを併せ持った技術である。2020年代に入り、タイポグラフィーを取り巻く環境がますます進化している。よりグローバルな視点に立って、今後の動きにも注目したい。
公式サイト:https://tokyotypedirectorsclub.org
2020/05/05(火)(杉江あこ)
PANDAID
運営:NOSIGNER
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、デザイナーはいったい何ができるのか。いま、多くのデザイナーがそんな思いに駆られているに違いない。2020年3月から4月にかけて、私はFacebookのタイムラインでデザイナーやデザイン関係者によるさまざまなアイデアの投稿を目にした。そのなかで多くの話題を呼んでいたのが、デザイナーの太刀川英輔が代表を務めるNOSIGNERが立ち上げたウェブサイト「PANDAID」である。
 「PANDAID」トップページ
「PANDAID」トップページ
最初に見た投稿は、「PANDAID」のコンテンツのひとつである「フェイスシールド」の動画だった。太刀川自身が中心となって開発したこれは、「A4クリアファイルを使って約30秒でつくれる」というのが最大の特徴で、A4クリアファイルに目をつけた点はさすがと言うべきである。まとめ買いをすれば1枚何十円という安価なので使い捨てしやすく、素材も透明度の高いPETやPP樹脂が多く使われているので適している。何よりA4原寸大の型紙をPDFでダウンロードでき、その型紙を印刷し、クリアファイルに挟み込んで、型紙の指示どおりにハサミを入れれば完成するというわかりやすさが魅力だ。参考までに市場に出回るフェイスシールドを見てみると、1枚数千円が平均価格だが、写真を見る限り、それらと比べても遜色がない。では、医療現場でこのA4クリアファイル製フェイスシールドを使えるのかという点については、私が知る医療従事者に聞いてみると、医薬品医療機器等法の範疇ではないため現場判断となるらしい。感染者の治療に当たる医師や看護師ならばもっと厳重なフェイスシールドが必要になるだろうが、それ以外の業務に当たる医療従事者であれば十分なのかもしれない。実際に医療従事者から好評を得ているという話も聞く。また小売店や飲食店、理美容店、介護施設など、不特定多数の人と接触しなければならない仕事に就く人たちにとっても、このフェイスシールドは役立つだろう。
「PANDAID」は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の基本情報をはじめ、個人が実践できる衛生や体力維持の方法、また助成金情報やリモートワーク術、自宅での楽しみ方など、多岐にわたる情報がひとつのウェブサイトにまとめられている点が特徴だ。非営利で自主運営、誰でも編集に参加できる共同編集というスタイルを取っている。だからこそ意図せずともフェイクニュースを流してしまう危険性も伴うため、「科学的ファクトが示されている情報を集める」などの編集方針を示す。さらに「一般の方に科学的情報が魅力的に伝わる記事とデザインを実現する」とあり、この辺りのコントロールが腕の見せどころにもなっている。NOSIGNERといえば、東日本大震災後に災害時に有効な知識や情報を集めて共有するウェブサイト「OLIVE」を立ち上げ、注目を大いに集めた。その後、それは東京都が発行したハンドブック『東京防災』の編集にもつながった。「PANDAID」もその流れを汲んだ活動のようだが、しかし「OLIVE」の充実したコンテンツに比べると、「PANDAID」はまだ途上のように見える。今後のコンテンツ拡充に期待したい。
公式サイト:https://www.pandaid.jp
2020/05/04(月)(杉江あこ)
アルベール・カミュ『ペスト』
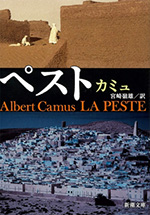
訳者: 宮崎嶺雄
発行所:新潮社
発行日:1969/10/30
フランスの文豪、アルベール・カミュの『ペスト』が、ここ最近、急にベストセラーとなり話題を呼んでいる。4月頭、私も御多分に洩れず新潮文庫を購入し、その奥付を見て驚いた。昭和44年に発行後、平成に一度だけ64刷改刷をするに留まっていたにもかかわらず、令和2年3月30日に87刷である。新型コロナウイルスが猛威を振るうこの非常事態にこそ、疫病を描いた物語を改めて読み、同時体験として共感と教訓を得たいという心理なのか。
通読してみて、やはり想像どおり、物語と現在の状況とがよく似ていて震えた。舞台はカミュの生まれ故郷であるアルジェリアの港町オラン。ひとりの医師の目と、彼の友人が残した手帳の観察記録を通して、物語は淡々と進んでいく。ネズミの死体発見から始まり、ペストが人々を徐々に襲って病や死に至らせると、町がついに封鎖されてしまう。その町の中で、医師と交流のあるさまざま立場の人たちの行動や心理がつぶさに描かれていく。この災禍を「みずからペストの日々を生きた人々の思い出のなかでは、そのすさまじい日々は、炎々と燃え盛る残忍な猛火のようなものとしてではなく、むしろその通り過ぎる道のすべてのものを踏みつぶして行く、はてしない足踏みのようなものとして描かれるのである。」とカミュは描写する。そう、現在、私たちが直面しているこの非常事態宣言下もまるで「足踏み」のようではないか。
本書は「不条理の哲学」と評されている。疫病や戦争、貧困などの不条理な状況下に置かれたとき、結局、人々が取る行動や心理は、昔もいまもあまり変わらないことが切々と伝わる。そもそも本書が発表されたのは1947年。第二次世界大戦直後だったことから、当時のフランス人にはまだ記憶に新しい戦争体験と重なったようだ。しかし当時と現在とでは、大きく異なる点がある。それは現代には進んだテクノロジーがあるということだ。当然ながら医療が進化している一方、世界中の都市がロックダウンしても、我々にはインターネットという強い武器がある。物語のなかでは封鎖された町の人々が引き離された家族や恋人と連絡を取る方法は電報しかなかったが、現代にはビデオ通話がある。学校には通えないが、オンライン授業が試み始められている。会社に通勤せずともリモートワークが実践されている。買い物もネット通販が盛んだ。インターネットだけではない。休業を余儀なくされた企業や人々の間では、新しい仕事への可能性を柔軟に探ろうとする動きがあり、また同時に新しい生活スタイルも築かれつつある。「Withコロナ」や「Afterコロナ」という言葉が生まれているように、このコロナ禍をきっかけとして、いま、社会の大きな価値転倒が起ころうとしているのかもしれない。そう考えると、疫病は人間社会を荒療治するために不意にやって来る“神”のような存在にも思えてくるのだ。疫病神とはよく言ったものである。
2020/04/30(木)(杉江あこ)
長島有里枝『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』

発行所:大福書林
発行日:2020/1/15
本書は、1990年代に台頭した若い女性写真家を中心に、「写真ブーム」を引き起こした潮流──写真評論家の飯沢耕太郎が「女の子写真」と名付けた潮流──を対象とし、代表的写真家のひとりである長島有里枝が、性差を自明なものとするカテゴリー化とそれが内包するジェンダーの不均衡な権力構造の再生産について、徹底した批判的検証を加えるものである。長島は武蔵大学大学院人文科学研究科社会学専攻に社会人枠で4年間通い、修士論文に加筆修正したものが本書である。
章立ては主に時系列順で構成され、「女の子写真」のパイオニア的存在とされる長島の1993年のデビュー、95年のヒロミックス登場を経て、90年代後半にかけて「突然」ブームが出現したのではなく、その「前史」にあたる90年代初頭に、若手女性写真家の台頭がすでに見られたことを掘り起こす作業から始まる。具体的には、1990年と91年に、初めて2年連続で女性写真家が木村伊兵衛写真賞受賞を果たしたことだ。長島は、「ブーム」を時代的な連続性の下で捉え直す視座に立ちつつ、受賞の選評、雑誌や新聞の(大半が男性による)言説を検証し、露骨なジェンダーバイアスや性差別的な眼差しの偏向、論理的破綻を暴いていく。
男性論客による「女の子写真」の言説に対する批判は、ヒロミックスについての言説を分析した4章が中核となる。そこでは、ヒロミックス特集を組んだ『スタジオ・ボイス』1996年3月号の扉に掲げられたマニフェスト「僕らはヒロミックスが好きだ。」がきわめて象徴的なように、「僕ら」=異性愛の男性の視点から、自らの欲望に奉仕するものとして一方的に語り、言説によって飼い慣らそうとする植民地的暴力が糾弾される。飯沢の論調に顕著な「自己中心的」「軽やか」「技術的な未熟さ」といった語り口は、一方でそれを「男性写真家にはない魅力」として称賛しつつ、実質的にはホモソーシャルな連帯とその背後にあるミソジニーの強化にすぎない。また、「女の子写真=技術的未熟さ」の前提とされる「コンパクトカメラなど機材の簡易軽量化」「カメラ機能付き携帯電話の普及」といった言説にも、長島は検証を加える。例えば、長島自身はデビュー当時から一眼レフカメラを使用しており、アンソロジー写真集『シャッター&ラヴ Girls are dancin’ on in Tokyo』(INFAS、1996)に紹介された写真家16名のうちコンパクトカメラで撮影した作品を掲載しているのは2、3名にすぎないこと、また若手写真家登場のピークが97、8年であるのに対し、「携帯電話・PHSの普及率が人口の50%を超えたのは2000年末」という総務省のデータを対置させる。
「未熟で傷つきやすく、(機械にも)弱い『女の子』は、安全で魅力的な庇護の対象であり、支配・所有が可能である」。男性論客たちの言葉遣いの端々には、性差に加え年齢差がはらむ権力関係の隠蔽、自己防衛、覇権争い、父権的構造が、巧妙に埋め込まれている。それらは(恐らく)無自覚だからこそ、より深刻である。またその最大の弊害は、女性写真家の表現が同世代の多くの女性の共感を呼び、「自分にもできる」というエンパワーメントを与えた面を取りこぼしてしまうことにある。
本書を通して長島は、ジェンダー・スタディーズ、とりわけジュディス・バトラーを参照し、身体的性差を唯一の基準とする二元的なジェンダー区分の自明さに疑義を呈する立場から、「女の子写真」というカテゴリー化の自明性と飯沢が論拠とする「女性原理」を切り崩していく。その先に賭けられているのは、「女の子写真」として不当に他者化・周縁化された語りを主体的にどう取り戻すかという企てだ。長島は、同時代的潮流として第三波フェミニズムに着目し、「ガーリーフォト」として記述し直すことを試みている。
本書の問題提起の射程は、90年代日本における女性写真家をめぐる言説だけにとどまらない。それは、写真界のみならず日本社会の男性中心主義が、「若い女性」をいかに抑圧/消費しているかの証左であり、「表現/語りの主体とジェンダー」という広範な問い、とりわけ「強固な二元論的性差を無批判に受け入れて自明の根拠とする語りは、表現されたものの解釈をいかに狭め、歪め、見損ね、見落としてしまうか」を冷静に告発している。
2020/04/24(金)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)