artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
川口幸也編『ミュージアムの憂鬱 揺れる展示とコレクション』

発行所:水声社
発行日:2020/06/25
コロナ禍による休館や展覧会の延期。東京五輪・パラリンピック関連事業である障害者の芸術活動支援事業と、その延期がもたらす影響。「あいちトリエンナーレ2019」での「表現の不自由展・その後」の展示中止。国立初の先住民族文化の展示施設として、ウポポイ(民族共生象徴空間)内に開館した国立アイヌ民族博物館。広島平和記念資料館のリニューアル。大阪人権博物館(リバティおおさか)の閉館。そして、福島県双葉町に開館した「東日本大震災・原子力災害伝承館」。ここ1年ほどの国内のミュージアムをめぐる状況変化を見れば、展示と収集によって「正史」を語る、近代に誕生した権力装置としてのミュージアムについて、私たちは一度立ち止まり、提起された諸問題について本質的な議論を行なう転換期にある。こうした状況下で出版された本書は、「ミュージアムがもつ多面的な役割について、功と罪の両面から、いま一度洗い直してみる」(編者あとがき)という目的で編まれ、示唆に富む。「ミュージアム─権力と暴力の器」「展示という『かたり』」「ミュージアムの来し方」「拡散するミュージアム」の4章で構成され、美術史、ミュージアム・スタディーズ、文化人類学、文化政策などの研究者や学芸員ら計14名による論考集である。
本書の論点は多岐にわたるが、上述の時事的要請との関連としては、国内の美術館の内/外で起きた展示撤去やクレームの事例の検証、アウトサイダー・アートの展示における「物量主義」の批判的検証、二風谷アイヌ文化博物館を事例に先住民観光とミュージアムの関係を論じた論考がある。
特に読み応えがあるのが、「表現の不自由展・その後」展示中止についてキュレーションの観点から多角的に検証し、「キュレーションの論理的一貫性を保つ必要性」を述べた鷲田めるろと、合衆国ホロコースト記念ミュージアムの写真展示を事例に共同体の災厄と記憶の継承について論じた横山佐紀の論考である。横山論考は、ホロコーストのメモリアル・ミュージアムにおける「痛ましいイメージ」の横溢について、「残虐な写真」の撮影主体が展示の文脈において曖昧化・不在化されていることを問題視する。「観客は、展示を通して、誰の視点に同一化させられているのか」という本質的な問いは、ホロコーストに限らず、「(美術史の、ナショナルな共同体の)語るべきナラティブ」を選別/排除するミュージアムという制度に対して向けられるべきであり、ナショナリティ、人種、ジェンダー、セクシュアリティ、階級などの構造的差別の再生産に与することを反省的に自覚しつつ、どのようにその克服と視点の相対化に転じていけるかが問われている。横山論考は、写真すなわち視覚的イメージの(大量)展示に代わり、生き残った当事者の語る「声」を聞き、証言を身体的に受け止める経験を重視する。これに異論はないが、9月20日に開館したばかりの「東日本大震災・原子力災害伝承館」では、「語り部」の口演内容に対し、国や東京電力への批判を含めないようにという要請があったと報道され、事実上の事前検閲といえる事態が発生している。「公(立施設)=政権」である事態がますます加速するのか、議論を開く批判的契機となりうるのか。「ミュージアムの功罪」が問われるのは、本書の読了で終わりではなく、これからである。
2020/09/21(月)(高嶋慈)
井奥陽子『バウムガルテンの美学──図像と認識の修辞学』

発行所:慶應義塾大学出版会
発行日:2020/02/28
哲学の一分野としての「美学(aesthetics)」が、18世紀のドイツにおいて成立した歴史の浅い学科であることはよく知られている。また、この分野の入門書を手にとったことのある者なら、この美学という言葉がギリシア語の「アイステーシス(感性)」に由来すること、さらにそこからラテン語の「アエステティカ(aesthetica)」という言葉を鋳造したのがバウムガルテンという哲学者であることも、おそらく一度は耳にしたことがあるだろう。
アレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルテン(1714-62)は、美学という学問の創設者として哲学史に名を残す一方で、長らく「顔の見えない哲学者」(iii頁)であった──そのような興味をそそる導入から、本書は始まる。その先を読み進めてみるとわかるように、実はこの表現にはいくつかの含意があるのだが、たしかにバウムガルテンという人物について、従来われわれが知りえることはごくわずかであったと言ってよい。
なるほど、つい数年前にはバウムガルテンの『美学』の文庫化という画期的な出来事もあり(松尾大訳、講談社学術文庫、2016)、一見するとその思想に接近する土壌は整っているかにも見える。しかしながら、ライプニッツ(1646-1716)やヴォルフ(1679-1754)の影響を色濃く受けた、いわゆる「ライプニッツ=ヴォルフ学派」に属するこの哲学者の仕事は、今日のわれわれにとってけっして理解しやすいものではない。第一、その著書のほとんどはラテン語で書かれており、何よりも一次テクストへの接近に困難がある。また、本書の著者が言うように、今世紀に入り「バウムガルテン・ルネサンス」(vii頁)と呼びうる研究の大幅な進展が見られるようになったとはいえ、ドイツ語以外の(たとえば英語での)研究論文の数もいまだ多いとは言えない。
本書は、そのような状況において登場した、日本語としてははじめてのバウムガルテンの研究書である。博士論文が元になっているということもあり、記述は一貫して手堅く、隅々まで読んでもほとんど曖昧なところがない。ある意味では『美学』以上に重要な『形而上学』をはじめ、バウムガルテンの美学が総体として──すなわち周縁的なテクストも含めて──扱われた、モノグラフとしては理想的と言ってよい研究書である。実際に『美学』をひもといてみるとわかるように、バウムガルテンの論述は、ヴォルフ学派の特徴である過剰なまでの「体系」への欲望に貫かれている。それが読者にとっては躓きの石となりかねないところだが、本書は、各テクストの構成を示した簡便な資料を盛り込むことにより、この問題も巧みにクリアしている。
バウムガルテンの美学を総体としてとらえなおすために、本書はタイトルにもある「修辞学」との関係に注目する。もちろんこれまでにも、黎明期の美学──バウムガルテンやカント──における修辞学との関わりを論じた書物がなかったわけではない。しかし本書はそうした既往研究にも十分に目を配りつつ、バウムガルテンの『美学』を「拡張された〈一般修辞学〉」(185頁)の試みとして読むことができる、という斬新かつ説得力ある議論を開陳する。
研究書を読む醍醐味のひとつは、ふだん漠然と共有されている臆見が鮮やかに覆されることにある。この書評のはじめにも書いたように、バウムガルテンはもともと美学を「感性の学」として構想したのだ、ということが入門書などではまことしやかに言われる。とりわけ美学を「感性学」ないし「感性論」として再建しようとするここ数十年の試みのなかで、そうした言説はいっそう広まったかに見える。しかし厳密に言えば、バウムガルテンその人が「美学」に与えた定義は「感性的認識の学」にほかならなかった(71頁)。そして、この「感性的認識」とは、現在われわれが「感性」という言葉から連想するものとけっして同じものではない。本欄では、その先にある本書の核心部分を詳しく紹介するには至らなかったが、以上の消息を知るだけでも、本書を手に取る意義は十分にあるだろう。
2020/09/15(火)(星野太)
カタログ&ブックス | 2020年9月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をartscape編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
活動の奇跡 アーレント政治理論と哲学カフェ

著者:三浦隆宏
発行:法政大学出版局
発行日:2020年6月30日
定価:3,400円(税抜)
サイズ:四六判、380ページ
アーレントが見出した「活動」の奇蹟と、哲学カフェ実践の軌跡。人生のさまざまな困難の当事者を含め、誰もが平等に声を発し、互いに耳を傾け、その人固有の存在として現われることのできる新しい政治的公共性の場所づくりが、いま求められている。哲学とその外を往還し、村上春樹と悪のモチーフ、建築や臨床の知の具体例から、「私たち」の感覚を取り戻し、思考なき全体主義を克服する道を探る好著。
A NEW RIVER

著者:岩根愛
ブックデザイン:町口覚
発行:bookshop M
発行日:2020年7月28日
定価:2,500円(税抜)
サイズ:257mm×182mm、32ページ
第44回木村伊兵衛写真賞を受賞した岩根愛の新刊。三春、北上、遠野、一関、八戸で撮影された桜のほか、各地の伝統芸能の写真で構成。
美術解剖学とは何か

著者:加藤公太
発行:株式会社トランスビュー
発行日:2020年7月30日
定価:2,500円(税抜)
サイズ:A5判、280ページ
「美術解剖学」という学問がある。古くはダ・ヴィンチが解剖のスケッチをしていたように、芸術家は人間を表現するために、人体の内部構造から多くのことを学んできた。しかし、この美術と医学のあいだにある学問について、現代的な知見に基づいてしっかりと解説した本はほとんどない。本書は、美術解剖学について、その内容から歴史までを概観した、人体を「見る目」を養う学問についての、これまでにない入門書だ。
笹久保伸写真集 Town C Difference and Repetition

著者:笹久保伸
デザイン/装画:鷲尾友公
発行:現代企画室
発行日:2020年8月1日
定価:2,800円(税抜)
サイズ:B5判、48ページ
秩父のアーティスト笹久保伸が、自身の生まれ育った秩父の町を撮影した写真集。(中略)3作目となるこの写真集では、彼の故郷である秩父のリアルな姿が映し出される。笹久保伸の目を通して見る郷里の風景には、外側からは見えない世界の細部が浮かび上がるだろう。
瀬戸内国際芸術祭2019

監修:北川フラム、瀬戸内国際芸術祭実行委員会
寄稿:北川フラム、福武總一郎、西尾洋一、高木智子
発行:青幻舎
発行日:2020年8月7日
定価:3,000円(税抜)
サイズ:B5判、296ページ
2010年に「海の復権」をテーマに掲げスタートした、瀬戸内国際芸術祭。4回目を迎えた2019年の芸術祭では、瀬戸内海の12の島々と2つの港を舞台に、春・夏・秋の3会期に分て計107日間開催された。世界32の国と地域から参加した230組のアーティストによる、瀬戸内海でしか生み出すことのできないアートやイベント、体験、食プロジェクトまでを完全収録した記録集。
押井守の映画50年50本

著者:押井守
発行:立東舎
発行日:2020年8月12日
定価:2,200円(税抜)
サイズ:A5判、320ページ
キューブリック、タランティーノ、デル・トロ…。押井守が、1968年から2017年まで、各年を代表する映画を1本ずつ選び、これまでの50年を振り返りつつ、未来の映画の可能性についても考察する。
政治の展覧会:世界大戦と前衛芸術 (政治の展覧会)

企画・制作:引込線/放射線パブリケーションズ
主催:引込線2019実行委員会
編集長:松井勝正
副編集長:中島水緒
デザイン:橋本聡
発行:EOS ART BOOKS
発行日:2020年8月27日
定価:1,500円(税抜)
サイズ:A5判、160ページ
2つの世界大戦が生じた時期の政治と芸術について、マリネッティ、リシツキーなど4人の芸術家・批評家の大戦期の活動をケーススタディとして取り上げて考察する。ホッチキス止めされた1000ソヴィエトルーブル紙幣付き。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2020/09/14(月)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2020年9月1日号[テーマ:皮膚]

テーマに沿って、アートやデザインにまつわる書籍の購買冊数ランキングをartscape編集部が紹介します。今回のテーマは、足利市立美術館(栃木県)で2020年11月3日(火・祝)まで開催中の展覧会「瞬く皮膚、死から発光する生」にちなみ「皮膚」。このキーワード関連する、書籍の購買冊数ランキングトップ10をお楽しみください。
※ハイブリッド型総合書店honto調べ。書籍の詳細情報はhontoサイトより転載。
※本ランキングで紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
「皮膚」関連書籍 購買冊数トップ10
1位:青空
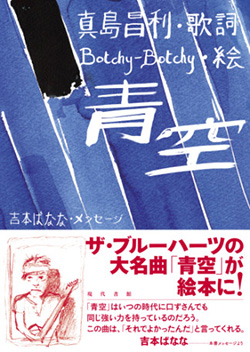
歌詞:真島昌利
絵:Botchy-Botchy
発行:現代書館
発売日:2019年12月16日
定価:1,300円(税抜)
サイズ:22cm
生まれた所や皮膚や目の色で、いったいこの僕の何がわかるというのだろう──。いつの時代に口ずさんでも同じ強い力を持っている、ザ・ブルーハーツの名曲「青空」を絵本化。吉本ばななのメッセージも収録。
2位:マルドゥック・スクランブル The 2nd Combustuion−燃焼 完全版(ハヤカワ文庫 JA)

著者:冲方丁
発行:早川書房
発売日:2010年10月
定価:700円(税抜)
サイズ:16cm、324ページ
少女は戦うことを選択した──人工皮膚をまとい、高度な電子干渉能力を得て再生したバロットにとって、ボイルドが放った5人の襲撃者も敵ではなかった。ウフコックが変身した銃を手に、驚異的な空間認識力と正確無比な射撃で、次々に相手を仕留めていくバロット。しかしその表情には強大な力への陶酔があった。やがて濫用されたウフコックが彼女の手から乖離した刹那、ボイルドの圧倒的な銃撃が眼前に迫る。緊迫の第2巻。
3位:ANIMAL MODELING 動物造形解剖学

著者:片桐裕司
発行:玄光社
発売日:2017年5月26日
定価:2,700円(税抜)
サイズ:26cm、170ページ
皮膚にあらわれる骨格の凹凸、動きによって形を変える肢体の筋、光と影による筋肉のかたち──。造形家の視点からとらえた、動物造形解剖学の決定版。ハリウッド造形界のトップの立体作品を彫刻レクチャーとともに収録する。
4位:島々百景

文と写真:宮沢和史
発行:ラティーナ
発売日:2019年7月3日
定価:2,500円(税抜)
サイズ:18×18cm、167ページ
その音楽を産んだ土壌に、人々に会いたくて旅に出るのだ。なぜその音楽が生まれたのか。それを皮膚で知り、感じたいからなのだ──。歌手の宮沢和史が、音楽に誘われ旅した島々の記憶を綴る。『月刊ラティーナ』連載を書籍化。
5位:ミメーシスを超えて 美術史の無意識を問う

著者:岡田温司
発行:勁草書房
発売日:2000年5月
定価:3,700円(税抜)
サイズ:20cm、275+13ページ
絵の見方、美術の歴史を「父の機能」の一党支配から解放する戦略とは? 無意識のイデオロギーを相対化し、主体、トラウマ、メディウムと皮膚、見る・触れる、メタファー・メトニミー等の観点から試行する。
5位:考える皮膚 触覚文化論 増補新版

著者:港千尋
発行:青土社
発売日:2010年3月
定価:2,400円(税抜)
サイズ:20cm、308ページ
棘の芸術、タトゥー・ブーム、皮膚の色の政治学、盲目論、世界皮膚の夢……。エスニック芸術からテクノロジーに至るまでの領域を渉猟してさぐる、時代のうごきを先鋭的に捉えた触覚文化論。
5位:どうぶつのことば 根源的暴力をこえて

著者:鴻池朋子
発行:羽鳥書店
発売日:2016年9月5日
定価:3,400円(税抜)
サイズ:22cm、365ページ
人間の思索のみに閉じるアートに、皮膚の森から啼き声があがる。芸術の始まりに立ち戻り、人間がものをつくることを問い直す。人間と動物の境界に出現するアートを求めて、様々な専門家との対話の旅をする。いままでのものとは全く違う想像力と出会った鴻池朋子が、語り、書く。
8位:かなでるからだ 混声合唱とピアノのための(合唱 混声)

作曲:森山至貴
詩:みなづきみのり
発行:音楽之友社
発売日:2016年5月14日
定価:1,800円(税抜)
サイズ:30cm、62ページ
「皮膚、肌」「膝」「骨」「肩」の4曲からなる組曲。「人体」をテーマにした詩は肌や骨の手触り、その存在感をコミカルに描きながら、歌い手はそれを体全体で表現する。激しくビートを刻んでアクロバチックに、ときには高音を絶唱し、狂おしく優しく人生の悲喜を、体温の熱さを奏でる。
9位:クラシック野獣主義

編著:鈴木淳史
発行:青弓社
発売日:2013年6月21日
定価:1,600円(税抜)
サイズ:19cm、173ページ
クラシックは一度はまれば出口がない怪しくも魅惑に満ちた世界だ! 迷宮のなかで頼りになるのは自分の感性だけ。聴くことの快楽を突き詰めた達人たちのほとばしる感性に身をゆだねて皮膚感覚を研ぎ澄ませ、クラシックに耽溺しつくすための咆哮的論考集。
9位:銘機礼讃2 語りだすディテール

著者:田中長徳
発行:日本カメラ社
発売日:1996年11月
定価:2,117円(税抜)
サイズ:20cm、276+16ページ
塗り直しライカの皮膚感覚、チープシックのリコーカメラ、指のパワーを保存するカメラ、気になるカメラがひしめきあう、カメラエッセイ。「銘機礼讃」から4年、待望の続編。
9位:CGテクスチャプロ技55 現場で使える実践テクニック+フリー素材
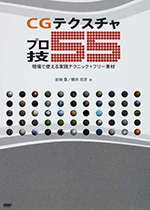
著者:岩崎塁、櫻井克彦
発行:ワークスコーポレーション
発売日:2010年12月
定価:3,800円(税抜)
サイズ:26cm、263ページ
大理石、土、木、ヘアライン、人の皮膚、紙……。3DCG作成において頻繁に使用するテクスチャを厳選し、その作成方法を分かりやすく解説。写真撮影のコツや動画のマッピングなども掲載。
◆
artscape編集部のランキング解説
「『皮膚』は、人の存在そのものを包んで成り立たせる役割を担っています。私たちは『皮膚』を通して、他者や光景の中に宿る無数の命と、生涯を通じ呼応し続けています」。これは足利市立美術館で開催中の、写真を中心とした企画展「瞬く皮膚、死から発光する生」のステートメントからの引用です。今回のランキングでも、書誌情報の本の説明のなかに「皮膚で知る/感じる」「皮膚感覚」といった表現が用いられていたことでランクインしている本が少なくありません。皮膚は感覚器官のひとつとして日常のなかで敏感に機能し、人々に強いイメージを想起させ続けているのでしょう。
その文脈で特に注目したいのが、5位にランクインした『考える皮膚 触覚文化論 増補新版』。写真家/映像人類学者である著者が古今東西の彫刻、絵画、写真、広告、あるいは民俗学的なアプローチから、皮膚を「脳のひろがり」として捉え直し、触覚についての思索をアップデートできる豊かな一冊です。続けて読むのにおすすめしたいのは、牛革などを素材に用い、「表皮」のイメージを観る者に喚起させる《あたらしい皮膚》《皮緞帳》などの作品でも知られるアーティスト・鴻池朋子による対談集『どうぶつのことば 根源的暴力をこえて』(同列5位)。鴻池が、考古学やおとぎ話の研究者などさまざまな分野の専門家と対峙し「芸術の始まり」をめぐって語る言葉には、先述の『考える皮膚』との親和性が感じられるところもあり、彼女の作品だけでなく、芸術作品全般の見方が拡張されるはず。
一方、ザ・ブルーハーツの楽曲世界を絵本化した『青空』(1位)や、金属繊維による人工皮膚を移植された少女が主人公として戦うSF作品『マルドゥック・スクランブル The 2nd Combustuion−燃焼 完全版』(2位)など、「皮膚」というキーワードを起点に、技術書からフィクションまでバラエティ豊富なランキングになりました。暑さも次第に落ち着いてくるこれからの季節、環境の変化にも身体感覚を研ぎ澄ませつつ、読書を楽しんでみてください。
※ハイブリッド型総合書店honto(hontoサイトの本の通販ストア・電子書籍ストアと、丸善、ジュンク堂書店、文教堂など)でジャンル「芸術・アート」キーワード「皮膚」の書籍の全性別・全年齢における購買冊数のランキングを抽出。〈集計期間:2019年8月20日~2020年8月19日〉
2020/09/01(火)(artscape編集部)
岡田利規『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』

発行所:白水社
発行日:2020/08/03
岡田利規の新たな戯曲集『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』には「能にインスパイアされた」2編(『NŌ THEATER』『未練の幽霊と怪物』)5本の戯曲と、岡田が能に魅せられこれらの戯曲を書くに至った背景を記した2本の短いエッセイが収録されている。
狂言「ガートルード」を除いた4本の戯曲はすべて夢幻能の形式に基づいており、つまりは亡霊が登場する物語なのだが、それらは通常の意味の亡霊=回帰する過去ではない。能「六本木」に登場する男の「こうならないことも、あるいはできたはずだった」という言葉に集約されるように、それらは失われた未来の亡霊とでも呼ぶべきものだ。
「六本木」「都庁前」「挫波」「敦賀」に登場するのはそれぞれ、自殺した金融マン、都議会で差別的な野次を飛ばされた女性議員、ザハ・ハディド、そして核燃料サイクル政策の亡霊/生霊だ。経済発展、男女平等、ザハ・ハディドのプランによる新国立競技場、そして核燃料サイクル政策。彼ら彼女らが(あるいは「私たち」が?)信じた、いまだ実現しない、あるいはすでに頓挫した輝かしい未来。
ザハが「線を描き続けて 探り続けていたビジョン」は「活気を信じることのできる 未来を信じることのできる フィクション」と呼ばれ「ザハ・ハディドのスタジアムを 今や擁した東京は」「世界を生き延びる 都市の ビジョンの ひとつとなる」と歌われて能「挫波」は幕となる。だが周知の通り、そのような未来は到来しなかった。それどころか、2020年に予定されていた東京オリンピック自体が1年後に延期され、東京オリンピックもまた失われた未来となりかねない状況が続いている(いや、それはすでに一度、1940年に失われた未来だ)。
当初、『未練の幽霊と怪物』は2020年6月に神奈川芸術劇場で(ザハの描いたものとは異なる未来と対置されるかたちで)上演される予定だった。だが、新型コロナウイルスの影響を受け、公演は(延期を前提とした)中止に。代わりにKAAT YouTubeチャンネルを通じて「『未練の幽霊と怪物』の上演の幽霊」(以下、「上演の幽霊」)が配信された。
「上演の予定がなくなった演劇は、幽霊になるのでしょうか?」という問いを掲げたこの配信では「挫波」「敦賀」それぞれが途中まで上演されたのだが、その形式もまたユニークだった。配信画面に対して斜めの位置にテーブルが置かれ、その上にはいくつかの直方体のオブジェが配されている。テーブルの奥の窓越しには路上を行き交う人の姿が見える。やがて上演が始まると直方体のそれぞれに俳優の姿が映し出される。つまり、卓上プロジェクションマッピングでの上演だったのだ。近年、岡田が継続的に取り組んでいる映像演劇のシリーズには、卓上に並んだスマートフォン2台を使った作品(「Standing on the Stage」)があったが、「上演の幽霊」をその系譜に連なるものとして見ることも可能だろう。その場にはいないはずのものと「鑑賞者」とが出会うという点において映像演劇と夢幻能とは似た部分がある。
夢幻能では旅人がある場所を訪れることで亡霊と遭遇するが、「上演の幽霊」のすぐそばを行き交う路上の人々はそこにいる「幽霊」に気がつかない。いま、私の机の上に置かれている『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』の戯曲と同じように、それは演劇未満の状態に止まっている。未来は可能性のままに潜在し、上演を、観客を待っている。戯曲の上演という演劇の形式は失われた未来を繰り返し回帰させ、そのたびに新たな未来の選択を私に迫る。
2020/08/30(日)(山﨑健太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)