artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
萩原弘子『ブラック 人種と視線をめぐる闘争』

発行所:毎日新聞社
発行日:2002/06/30
BLM(Black Lives Matter)運動の再熱は、人種差別抗議デモにとどまらず、銅像への抗議や引き倒し、奴隷制下の南部を理想化して描いた映画への批判など、「表象」と差別の構造的再生産に関わる問いへと拡張している。例えば、黒人と先住民を従えたセオドア・ルーズベルト大統領の騎馬像がアメリカ自然史博物館前から撤去され、南部バージニア州では、南北戦争時の南部軍司令官リー将軍の騎馬像も撤去が決定された。奴隷制や植民地支配に関わった人物の彫像に対する抗議は、イギリスやベルギーにも波及した。また、「従順な良き使用人」として黒人をステレオタイプ化し、奴隷制下の南部を回顧的に美化していると批判された映画『風と共に去りぬ』(1939)は、動画配信が一時停止。制作当時の時代背景や問題点の解説付きで配信再開された。同様に、理想化されたユートピアとして南部の農場を描いたディズニー映画『南部の唄』(1946)をテーマとした、米国内ディズニーランドのアトラクションも改装が発表された。
ただし、「偶像破壊」や問題のある描写の「削除」だけでは、偏った歴史と表象文化の関わりについての批判的検証の機会を奪う点で、「抹消」(そして将来的な忘却)という別の暴力性を有している。白人中心の歴史観や白人にとって都合のよい黒人表象が、視覚文化のなかでどのように生産・受容され、黒人アーティストたちはどのような批判的視座から介入し、抵抗し、観る者の眼差しを更新してきたのか。本書の刊行は2002年だが、黒人の表象文化に関わる理論的枠組みと、主に90年代の映画と現代美術作品の具体的分析で構成され、深い洞察と示唆に富む。著者の萩原弘子は黒人文化研究者で、フェミニズムの理論家グリゼルダ・ポロックの著作『女・アート・イデオロギー』(1992、ロジカ・パーカーと共著)、『視線と差異』(1998)の翻訳を手掛けるなど、ジェンダー研究にも携わっている。
「理論編」の第一章では、西洋近代が自然科学の「正当性」を根拠に支配の言説として打ち立てた「人種」というカテゴリーとその適用の恣意性、アイデンティティの政治学が「主体の再構築」として抵抗の手段になるとともに排他や本質主義に陥るジレンマ、映画を中心としたステレオタイプな黒人表象の分析研究の蓄積、「Black/black」および「ブラック/黒人」という表記をめぐる問題について概説する。「『人種』はフィクションだが、人種的周縁化は現実である」と述べる著者が「黒人」表象をめぐる政治学に着目するのは、「黒人」の分類概念が西洋近代と奴隷貿易によってつくり出され、その政治学を問い直す黒人アーティストたちの実践が、「西洋近代」とその正当性を批判的に逆照射するからだ。
特に重要なのが、「彼ら」をどう呼ぶかという呼称と命名の権力に関わる問題である。白人が支配のための分類枠として用いた「black」に対し、1960年代アメリカのブラック・パワー運動で、一方的に名付けられた側が連帯の基盤を表わす自称として奪還したのが、語頭を大文字で綴る「Black」である。著者はこの「Black」の持つ意味に敬意を払いつつ、その語を(自称ではなく)他称として用いざるをえない自身の葛藤に誠実に向き合う態度を選ぶ。さらにやっかいなのは、「ブラック/黒人」という日本語が抱える、翻訳と文脈移植の問題である。「Black」をそのまま音訳した「ブラック」に比べ、「黒人」は「色による人の分類」をより強調するが、「ブラック」の表記では、経験と闘争の共有という原語のもつ複雑なニュアンスがこぼれ落ちてしまう(著者はタイトルに「ブラック(Black)」を採用し、文中では「ブラック/黒人」を使い分けている)。
第二章では、スパイク・リーやアイザック・ジュリアン、トリン・T・ミンハなど、ハリウッドから実験的短編映画までが論じられる。通底するのは、誰が、どのような観客に向けて(奴隷制を「安全な過去」としてノスタルジックに消費する白人観客? あるいはスクリーン上で見られる[性的]対象としても視線の主体としても最も排除されてきた黒人女性観客?)、どのような欲望や視点から過去を語り直すのか、という問いである。
第三章では、イギリスで活動するブラック・アーティスト8人の作品分析が展開される(西インド諸島からの再移民やインド亜大陸にルーツを持つ者も含み、奴隷制に代わる支配システムである植民地支配の歴史も含み込む)。植民地期イギリスの富裕層の肖像画や室内空間を「アフリカ布」で覆い、富の供給源の暴露と「真正で純粋な民族性」への懐疑を示すインカ・ショニバレ。イングランド的とされる田園風景の不調和な侵入者として、黒人女性である自身のポートレートを撮影・彩色し、その美しい風景が激しい排他的空間であることを示すイングリッド・ポラード。黒人ゲイ男性として抱くエロティシズムを視覚化しつつ、ブラック・パワー運動の男性中心主義を批判するアジャムの写真。「犯罪の匂いのする不良」というメディアの黒人男性イメージを演じつつ違和感を差し込む、改宗ムスリムのフェイザル・アブドゥアラ。黒人をデザインした雑貨や玩具を、皮膚の漂白クリームにまみれさせて展示ケースに押し込め、大衆文化の愛玩・蒐集行為と博物館的装置における他者の文化の奪取や視線の非対称性を問題提起する、シャヒーン・メラリ。
本書を貫くのは、単一の「黒人性(Blackness)」があるのではなく、ディアスポラとしての経験、ナショナリティ、階級、ジェンダー、セクシュアリティ、文化的・宗教的帰属など、多面的で複雑な差異の交差するものとして捉える必要性である。「ブラック」が、連帯しえない人々とのあいだを区切る政治的境界でもあることを自覚しつつ、政治的課題に応じて差異や分断を超えて連帯するための枠組みとして用いること。その射程は、人種主義にとどまらず、「近代」への根源的な問い直しに向けられている。
2020/08/29(土)(高嶋慈)
𠮷田隆之『芸術祭の危機管理 表現の自由を守るマネジメント』

発行所:水曜社
発行日:2020/08/01
「あいちトリエンナーレ2019」での「表現の不自由展・その後」の展示中止から1年が経つ。本書は、社会批判や政治性の強い作品への攻撃や自主規制が強まることの懸念に対し、「不自由展」をめぐる一連の出来事を事例に、「表現の自由を守るマネジメント」とは何かを問う。本書の前半では、芸術祭開幕から展示中止に至る経緯をたどり、展示中止の要因についての複数の見解(キュレーションの不備、電凸対応策の不十分さ、政治家の発言、「表現の自由」の後退傾向)について検証し、展示再開に貢献したステークホルダー(津田大介芸術監督、「ReFreedom_Aichi」など参加アーティストの連帯、大村秀章知事、「あいちトリエンナーレのあり方検証・検討委員会」、ボランティア、ラーニングチーム、現場の緩やかなネットワーク)について述べる。後半では、文化行政やマネジメントの軸から、文化庁の補助金不交付決定の是非、「あいちトリエンナーレのあり方検証・検討委員会」による報告書と提言、「あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会」の報告書について検証する。著者の𠮷田隆之は文化政策やアートプロジェクト論が専門の研究者で、愛知県職員として「あいちトリエンナーレ2010」で長者町会場を担当した経歴を持つ。
とりわけ本書の骨子は、「あいちトリエンナーレのあり方検証・検討委員会」についての「検証」にあるだろう。著者は、展示再開に貢献したステークホルダーのひとつとして「検証・検討委員会」を挙げ、専門家集団である委員会が9月25日に発表した中間報告で「すみやかに再開すべき」と提言したことが、再開の正当性の根拠になったと評価する(この提言を受けて同日、大村知事が展示再開を表明したが、翌26日、この展示再開への道筋を回避するため、文化庁の補助金不交付決定の判断が出されたことに着目する)。
この肯定的な評価の一方で、著者は、「検証・検討委員会」の最終報告書の第一次提言に盛り込まれた具体策について、問題点を指摘する。問題視されるのは、「芸術祭実行委員会の会長に民間人を起用する」「専門家らで組織するアーツカウンシル的組織を設置し、芸術監督を選任する」「愛知県美術館への指定管理者制度の導入」の3点だ。これに対し著者は、「アームズ・レングスの原則」(金は出すが、口は出さない)に則った行政主体の助成において「表現の自由」が守られるべきであること、アーツカウンシル的組織による芸術監督の選任は「アーツカウンシル」の名称を用いた権力による干渉の正当化になりかねないこと、愛知県美術館はトリエンナーレ期間中に貸館をしているだけで運営形態とは関係がないこと、の論点から批判する。著者は、「検証・検討委員会」の報告書は電凸による展示中止が起きた社会的・政治的背景を看過し、津田芸術監督の責任論に終始していると批判し、上記の提言を「物議を醸さないマネジメント」であるとして退ける。
ではこれに代わり、著者が提起する「表現の自由を守るマネジメント」とはどのようなものか。
(1)展示再開時に実効性を示せた電凸対応策を情報共有すること。
(2)物議を醸すと想定される作品を展示する場合、会期前や会期中に、芸術と公共性に関する議論の場を設けること。
(3)キュレーションの自律のための環境を整えること。
(4)検閲を招きかねないガバナンス組織をそもそも作らないこと。
本書は、経緯や論点の整理という点ではコンパクトにまとめられているが、帯が謳う「なぜ世論は分断されるのか」という最大の問いには、「おわりに」で「今後の研究課題」としてふれられるだけで、実際には中心的な論題になっていないことが惜しまれる。世論の分断について分析するのであれば、作品の一部を切り取った画像がSNS上でどのような文言とともに拡散されたのかや、メディアでの報道のあり方について詳細な検証が欠かせない。また、展示中止の要因として、短期的な社会背景としては、徴用工問題をめぐる韓国との外交関係の悪化の渦中だったこと、改元と皇位継承による皇室祝賀ムード、より長期的にはヘイトスピーチの増加、第2次安倍政権の2010年代以降における美術作品の撤去や変更の増加、一方で「地域アート」の隆盛における「アート=無害で誰でも楽しめるもの」という価値観の醸成なども挙げられる。さらに歴史的射程で見れば、より深い問題の根は、戦後日本が戦争責任や加害の謝罪など過去の精算を怠ってきたことにあり、帝国主義、植民地主義、ナショナリズム、性差別の温存が、「公金の投入」を根拠として一気に吹き出したといえる。電凸対策など現場レベルの環境整備に加え、より複合的で長期的な視野に立ち、「公共性や多様性、歴史意識についての成熟した議論の場をアートがつくっていく」という意識が必要とされている。
2020/08/08(土)(高嶋慈)
カタログ&ブックス | 2020年8月1日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をartscape編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
開校100年 きたれ、バウハウス —造形教育の基礎—

監修:深川雅文、杣田佳穂
執筆:長田謙一、杣田佳穂、宮島久雄、利光功、貞包博幸、柏木 博、冨田英夫、木村理恵子、深川雅文、長谷川新、下村朝香、梅宮弘光、常見美紀子、川谷承子、高橋麻帆、橘美貴、星野立子、牧野裕二
編集:深川雅文、杣田佳穂、下村朝香、成相肇、市川飛砂(株式会社アートインプレッション)
デザイン:NOSIGNER
翻訳:原田明和
発行:株式会社アートインプレッション
発行日:2019年
定価:2,128円(税込)
サイズ:220x220mm、264ページ
本図録は、バウハウス創設100年の節目を迎え、展覧会の内容を解説とともに収録するとともに、バウハウスに関するさまざまなテーマについて今日の研究成果を反映した論文の集成に力点を置いています。併せて、バウハウスの基本文献として三つの重要原典の翻訳を収録しています。
ART in LIFE,LIFE and BEAUTY

編集:池田芙美、佐々木康之、宮田悠衣(以上、サントリー美術館)
英訳:エリザベス・ティンズリー
デザイン:高岡健太郎(日本写真印刷コミュニケーション株式会社)
発行:サントリー美術館
発行日:2020年7月22日
定価:2,500円(税込)
サイズ:B5変形、268ページ
2020年7月22日~9月13日までサントリー美術館で開催されている「リニューアル・オープン記念展 Ⅰ ART in LIFE, LIFE and BEAUTY」展のカタログ。「生活の中の美(Art in Life)」基本理念に展示・収集活動を行なってきた同館のコレクションと、古美術に造詣の深い現代作家の山口晃、彦十蒔絵・若宮隆志、山本太郎、野口哲哉の作品をクロスさせた特別展示。
没入と演劇性 ディドロの時代の絵画と観者

著者:マイケル・フリード
訳者:伊藤亜紗
発行:水声社
発行日:2020年7月28日
定価:5,000円(税抜)
サイズ:A5判、374ページ
観者の存在を前提とするミニマリズム作品を批判した概念として名高い「演劇性」は、18世紀のフランス絵画の成立条件に関わる根本的な問題として登場した。画家たちの様々な試みを見るとともに、ディドロに代表される当時の美術批評家の言説を読み解きながら、いかにして観者という存在のあり方が問題視されるようになったのか、その理論的枠組を大胆に提示する。
げいさい

著者:会田誠
発行:文藝春秋
発行日:2020年8月6日
定価:1,800円(税抜)
サイズ:四六判、320ページ
まさに鬼才。
過激に、独創的に、第一線を走り続けてきた現代美術家、会田誠。
その活躍は、いまホットな美術界だけにとどまりません。
「とにかく信じられないくらい文章がうまい。ほれぼれしちゃう」と、吉本ばななに言わしめたエッセイ。高橋源一郎、斎藤美奈子らが激賞した処女小説『青春と変態』。そんな会田誠が、最初の構想より30年以上、執筆に4年の歳月を費やした長編小説です。
未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀

著者:岡田利規
発行:白水社
発行日:2020年8月3日
定価:2,400円(税抜)
サイズ:四六判、140ページ
東京オリンピック2020招致のため、2012年に新国立競技場の設計者としてコンペで選ばれた天才建築家ザハ・ハディド。その圧倒的な造形のビジョンを白紙撤回され、その後ほどなく没した彼女をシテとして描く「挫波」。夢のエネルギー計画のため、1985年の着工以来一兆円を超す巨額の資金が投じられたものの、一度も正式稼動することなく、廃炉の道をたどる高速増殖炉もんじゅについて謡う「敦賀」。
表題作二曲のほか、夢幻能と間狂言に今日的なキャラクター(六本木駅に現れる金融トレーダーの幽霊、都庁前駅に現れるフェミニズムの幽霊、『ハムレット』のせりふを覚える舞台女優)を登場させ、資本主義に飲み込まれている現代日本の姿を描いた「NŌ THEATER」とともに、演劇論(「幽霊はアレルギー症状を引き起こさない」、「能は世界を刷新する」)を併録する。
テレビジョン テクノロジーと文化の形成

著者:レイモンド・ウィリアム
訳者:木村茂雄、山田雄三
発行:ミネルヴァ書房
発行日:2020年8月4日
定価:3,500円(税抜)
サイズ:四六判、290ページ
テレビというメディアは、それまでに普及したメディア(新聞、討論、広告など)にない、まったく新しい人的コミュニケーションをもたらした。本書は、実例を通じた精緻な分析により、テレビが与えた変化とはなにかをを問うものである。カルチュラル・スタディーズにおけるテレビ論の古典、待望の翻訳。(原書 Raymond Williams,Television:Technology and Cultural Form,2nd.ed.,Routledge,1990[Routledge Classics, 2003])
京都発・庭の歴史

著者:今江秀史
発行:世界思想社
発行日:2020年7月31日
定価:2,400円(税抜)
サイズ:四六判、232ページ
文化財保護に長年携わってきた哲学研究者が、平安から現代までの千年をガイド。
見た目や美しさだけではなく、知られざる使われ方に注目し、現場ならではの視点から解説する。
庭は単なる鑑賞物ではない。
千年以上ものあいだ、庭ではいったい何が行われてきたのか?
建築のことばを探す 多木浩二の建築写真

写真:多木浩二
文章:多木浩二、今福龍太
デザイン:高室湧人
発行:建築の建築
発行日:2020年7月14日
定価:6,000円(税抜)
サイズ:303x207mm、256ページ
本書編者のアーティスト・飯沼珠実が、本書刊行までにみつけた多木の建築写真は12,000コマを数え、収録写真の半数以上が、撮影から50年前後のときを経て、本書において初めて発表されます。
写真は被写体の竣工年順に並べられ、建築作品の基本情報に加え、本書デザイナー・高室湧人が描きおこした図面に、多木の撮影地点をプロットした資料が添えられます。さらに2本のテキスト、多木が篠山紀信写真集『家 Meaning of the House』(潮出版, 1975)に寄せた28編のエッセイのひとつ「家のことば」と、文化人類学者・今福龍太の書き下ろし「家々は海深く消え去りぬ 多木浩二の『反-建築写真』」を収録します。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2020/08/01(土)(artscape編集部)
佐々木敦『これは小説ではない』
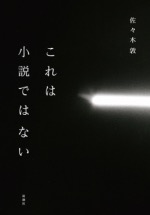
発行所:新潮社
発行日:2020/06/25
すでに広く知られているように、批評家・佐々木敦は今年に入って「批評家卒業」を宣言し、『新潮』4月号に「半睡」という初小説作品を発表した。今後も批評的なテクストは書きつづけるとのことだが、これまで著者がこだわってきた「批評家」の看板を下ろすという宣言は、わたしを含めた以前からの読者に驚きをもって受け止められた。
その理由や心境については、すでにいくつかのインタビューや著書のなかで明らかにされているため、ここで評者がわざわざ贅言を費やすにはおよばない。いずれにしても、佐々木にとって大きな節目となる今年、これまでの仕事を総決算するかのように、続々と新著が刊行されている。演劇批評集としては意外にも一冊目に当たる『小さな演劇の大きさについて』(Pヴァイン、6月)、これまで単行本未収録だったさまざまなジャンルの文章を集めた『批評王』(工作舎、8月)、雑誌『群像』での連載をまとめた『それを小説と呼ぶ』(刊行予定──『これは小説ではない』のあとがきを参照のこと)、さらに佐々木が編集長を務める文芸誌『ことばと』の創刊号(書肆侃侃房、4月)まで含めると、隔月以上のペースで何かしらの本が刊行されている。
本書『これは小説ではない』も、そうした一連の刊行ラッシュに連なるものである。しかしこの書物こそは、どうあってもこの著者にしか書けない、紛れもない主著のひとつと言って差し支えないように思う。本書のもくろみは、おおよそ次のようなところにある。すなわち、「小説とは何か」「小説に何ができるか」ということをはじめから大上段に論じるのではなく、「映画は小説ではない」「写真は小説ではない」「音/楽は小説ではない」「演劇は小説ではない」──というふうに、ほかの芸術ジャンルの可能性と限界を浮き彫りにしていくところから、来たるべき小説のポテンシャルを照射していこうという構えである。これまで「横断」ならぬ「貫通」をモットーとしてきた著者らしく、異なるジャンルを論じたどの章も、これ以外にないと思わされるような例示と分析で溢れている。
だが、おそらくこれだけでは、事の半分しか説明したことにならない。第1章「ラオコオン・エフェクト」に見られるように、本書はレッシングからグリーンバーグにいたる近代の「詩画比較論(パラゴーネ)」の基本を押さえるところから始まっている。しかし本書はそこから、各ジャンル(あるいはメディウム)の固有性とは何か、という安易な本質論にはけっして赴かない。本書の考察を導くのは、あくまでも具体的な作品である。しかも特筆すべきことに、その多くは必ずしも名作揃い(いわゆる「古典」)というわけではなく、著者が連載中に接した、あるいは過去に接してきた有名無名の作品群なのである。
かねてより、著者はたとえ大きな連載であっても、その時々に見聞した作品の「時評」を心がけているという旨のことを語っていた。それは過去の著書をひもといてみれば明らかだろう。本書もまた、紛れもなくそのような一冊である。そして、これだけ多くのジャンルにまたがるパラゴーネを遂行しつつ、それを同時に時評としても成立させることができるのは、佐々木敦を措いてほかにいまい。その意味で、本書は『新しい小説のために』(講談社、2017)や『私は小説である』(幻戯書房、2019)をはじめとするここ数年の小説論に連なる一冊であるとともに、映画から音楽へ、文学から演劇へと不断に軸を移してきた著者の、30年におよぶ批評活動の集大成でもある。
2020/07/27(月)(星野太)
内藤礼『空を見てよかった』

発行所:新潮社
発行日:2020/03/25
本書は、美術家・内藤礼による「ほぼ」言葉のみの作品集である。過去の展覧会で発表されたステートメント、文芸誌や新聞に寄せた折々の短文、それから本書のための書き下ろしや未発表の私記が、時系列順にではなく、全体でひとつの流れをつくるように配されている。「ほぼ」と言ったのは、表紙と本書の中ほどに計二点、《color beginning》という絵画作品がひそかに印刷されているからである。
何も知らずに本書を手に取った読者は、これをどのように読めばいいのか、少なからず戸惑うにちがいない。これは美術家の手による詩集ではない。まして、その作品の背後にある思想を明快な言葉で綴ったエッセイでもない。ここにあるのは「言葉」である。そして、言葉がこのように言葉として差し出されるというのは、今日において驚くべきことである。
これは詩集ではないと言ったが、それはもちろん、ここにある言葉の連なりがポエジーを欠いているという意味ではない。むしろ、行分けをふんだんに用いた本書の端々から受ける第一印象は「詩」以外の何ものでもあるまい。げんに、本書をめくり始めて数頁のうちに、「ただそこにじかにふるえ/すべてそのちからふるわし」(8頁)といった一定のリズムをもつ詩的なセンテンスが、次々と目に飛び込んでくる。ゆえに形式的に言えば、これらの言葉を詩とみなすことこそ、もっとも穏当な選択肢ではないかと思える。
他方、ここに書かれていることを、作家その人の制作論として読むことも可能だろう。たとえばこんな一節がある──「ここにはもうすでに空間があるというのに、なぜそれに触れようとしているのだろう。なぜものを置こうとしているのか。なぜものをなのか。変化をなのか。そうではない。この世界に人の力を加えることがものをつくるという意味だと言うのなら、私はつくらない」(26頁)。「作るという考えは傲慢だといつしか思うようになっていた。長い間、作ると言うことも書くこともしなかった。モノはそれ自体で生まれてくるのに、人が作るとはどうしたことだろう」(140頁)。
しかし以上のどちらなのか、と問われれば、そのどちらでもあり、どちらでもないというべきだろう。第一に、ひとつひとつのテクストにはそれらしきタイトルが一切ない。巻末の初出一覧を見ても、その書き出しが並べられているだけで、どれひとつとして「タイトル」を与えられた文字列はない。だとすると、やはり本書は丸ごとひとつの言葉の集合だと考えるべきなのだろう。
本書ではひらがなが多用されている。はじめ、それに対してわざとらしい印象を抱く読者もいるかもしれない。だが、わたしが繰り返し本書をめくるなかで感じたのは、いささか独特な漢字かな開きと、余白の取り方によって誘導された、あまり経験したことのない視線と思考の運動であった。それによって、ここにある言葉との距離がふと近くなったり、遠くなったりする。とはいえ、おそらくこれは読み手に対しても一定の調性を求めるプロセスであるため、誰もがそのような感慨を持てるものかどうか、正直なところ評者にもわからない。ただひとつ言えることがあるとすれば、この感覚は内藤礼の作品が空間中に立ち上げる独特な磁場と、きわめて類似しているということである。
現在、石川県の金沢21世紀美術館では、内藤礼の2年ぶりの個展「うつしあう創造」が開催されている(8月23日まで)。会期終了後に刊行されるそのカタログのなかで、評者はまずその作品がもたらす「驚き」について論じようと思った。そこで書いたことと、この場で本書について書いてきたことは、ほとんど同じことを言っていると思う。その驚きとは、こちらの意表を突くような暴力性をともなった驚きではなくて、長時間そこに身を浸すことにより徐々に湧き上がってくる、いわば遅効性の驚きなのである。
2020/07/27(月)(星野太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)