artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
市原佐都子『バッコスの信女─ホルスタインの雌』

発行所:白水社
発行日:2020/04/10
第64回岸田國士戯曲賞受賞作として市原佐都子の戯曲『バッコスの信女─ホルスタインの雌』が白水社から刊行された(同時受賞の谷賢一『福島三部作』はすでに2019年11月に而立書房から刊行されている)。選評によれば、審査員一人ひとりが最終候補作のそれぞれに対して○△×で評価を示すところから始まる選考会において、「珍しく、最初から委員全員が大意において同じ方向を向いてい」て、『バッコスの信女─ホルスタインの雌』には「誰ひとり『×』をつけなかった」(ケラリーノ・サンドロヴィッチ)らしい。平田オリザは「全体のことで言うと、今年は例年に比べてレベルが高」かったと述べており、レベルの高い最終候補作のなかでも市原の戯曲が選考委員の圧倒的支持を集めたということがわかる。私個人としてもここ数年、岸田賞の最終候補作にはすべて目を通しているが、同様の印象を持った。
『バッコスの信女─ホルスタインの雌』の主人公は一見したところ「普通の」主婦である。しかし彼女はのっけから「ケロッグのコーンフレークってマスターベーションをやめさせるために生まれたらしい」などと観客に向かってまくしたてる。性と食はこれまでの市原のほとんどすべての戯曲で中心的なモチーフとなっており、それはつまり、市原が演劇を通して生の生々しさを描き出し曝け出そうとしていることを意味する。性にせよ食にせよ、ほとんどの場合、それが他者を必要とする営みであるという点において共通しており、市原はそれらを奇妙に混線させることで人間の営みの欺瞞を暴き出す。
かつて「家畜人工授精師」として働いていた主婦が「獣人」(牛と人間のハーフであり、かつ上半身が女、下半身が男の「ハーフ」でもある)を生み出してしまうという物語は単に荒唐無稽な、あるいは作家のフェティシズムを具現化したものではなく、確固たる構造に裏打ちされたものだ。獣人は「母」である主婦を女性だけの楽園に誘い、彼女と結びつき「生まれ直す」ことを夢見るが(母乳と精液の循環!)、その願いが成就することはない。肉を食いたい、セックスがしたい、子供がほしい。他者を欲望する限りその回路を閉じることは不可能だ。自己完結のユートピアに閉じこもることはできない。
日本で性が語られるとき、反応の多くは対象への性的な興味か、私的領域に留めるべきものが公の場で語られることへの羞恥に二分され、性が十分に真っ当な議論や教育の対象となっているとは言いがたい状況がある。市原はならばとばかりに「過激」な言葉を並べ立てる。それは観客の生理的な反応をより一層引き出すだろう。だがその背後に奇妙ではあるかもしれないがある種の論理的構造が確固たる作品の枠組みとして用意されている。劇作家としての市原の強みはその両輪の確かさにある。
併録された『妖精の問題』は2016年の「相模原障害者施設殺人事件を受けて生まれた」作品で、本書のあとがきによれば市原は「事件によって、自分のなかにある優生思想や、自分が抱えている生きづらさを意識させられた」のだという。市原はさらに「できるだけ偽善的ではない方法であらゆる生を肯定することを試みたいと思った」とも書いている。「できるだけ偽善的ではない方法」というのはそこにある問題そのものから目を逸らさないということだろう。市原は演劇の上演という枠組みを利用して観客に「直視すること」を迫る。真っ直ぐな言葉で自らの創作について語る市原のあとがきも本書の読みどころのひとつだ。『妖精の問題』は5月16日(土)・17日(日)にオンライン公演が予定されている。
あいちトリエンナーレ2019で初演された『バッコスの信女─ホルスタインの雌』は、ドイツで3年に一度開かれる世界演劇祭(テアター・デア・ヴェルト)での上演も予定されていたのだが、残念ながら新型コロナウイルスの影響で演劇祭自体が2021年6月へと延期となってしまった。現時点で次は9月、神奈川芸術劇場KAATでの上演が予定されている。市原の主宰する演劇ユニット「Q」の近作は多くがレパートリー化されているが、本作は作品の規模的にも再演の機会は限られてくるだろう。この機会に再演が実現することを切に願う。
関連記事
あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』 │ artscapeレビュー(2019年11月15日号) | 高嶋慈
2020/04/18(土)(山﨑健太)
カタログ&ブックス | 2020年4月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
あいちトリエンナーレ2019 情の時代 Taming Y/Our Passion

編集:あいちトリエンナーレ実行委員会
監修:津田大介
発行:あいちトリエンナーレ実行委員会
発行日:2020年4月3日
定価:3,200円(税抜)
サイズ:A4変型、368ページ
全作品のヴィジュアル+解説、芸術監督及びキュレーターのエッセイ、あいちトリエンナーレ2019 作品リスト、「表現の不自由展・その後」の展示中止や再開をめぐる出来事をまとめた資料など。
AONO FUMIAKI NAOSU
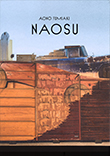
寄稿:青野文昭、小森はるか、椹木野衣、福住廉、清水建人(smt)
ブックデザイン:伊藤裕
企画・発行:せんだいメディアテーク
発行日:2020年3月20日
定価:3,500円(税抜)
サイズ:A4変形、192ページ
2019年11月2日から2020年1月12日まで開催した展覧会「青野文昭 ものの,ねむり,越路山,こえ」の展示作品や青野の過去作品を掲載した記録書籍『AONO FUMIAKI NAOSU』を出版いたします。作品図版のほかには、青野の手記や、美術批評家の椹木野衣、福住廉による各論考、青野の映像ドキュメンタリーを作成した映像作家の小森はるかの制作ノートなどを掲載。
VOCA展2020 現代美術の展望──新しい平面の作家たち

寄稿:小勝禮子、光田由里、柳沢秀行、水沢勉、家村珠代
発行:「VOCA展」実行委員、公益財団法人日本美術協会・上野の森美術館
発行日:2020年3月12日
定価:1,800円(税込)
サイズ:A4変形、104ページ
Nerhol、菅 実花、李 晶玉、黒宮菜菜、宮本華子、浅野友理子など2020年の出品作家計33人(組)の作品を掲載。
アーティスト・イン・レジデンス2019/夏「はかなさへの果敢さ」

ゲスト論考:四方幸子
アートディレクション・デザイン:木村稔将
発行:青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC]
発行日:2020年3月23日
定価:非売品
サイズ:A4並製、64ページ
青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC]で、2019年7月27日〜9月8日に開催された展覧会「はかなさへの果敢さ」のカタログ。ジャンフランコ・フォスキーノ、三原聡一郎、カルロス・ヌネスの3名が同センターのアーティスト・イン・レジデンスに参加し、滞在制作した作品を発表した。
東北の風景をきく FIELD RECORDING vol.04

編集長:佐藤李青
編集:川村庸子、嘉原妙
デザイン:内田あみか
参加者:島袋道浩、高森順子、瀬尾夏美、清水裕貴、山本唯人、山内宏泰、布田直志、松本篤、山川冬樹、岡村幸宣
発行:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
発行日:2020年1月17日
定価:非売品(ウェブサイトよりPDFダウンロード可能)
サイズ:B6判、112ページ
Art Support Tohoku-Tokyo(ASTT)は、東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業。プログラムの記録と成果を広く共有するため、さまざまなドキュメントを発行している。変わりゆく震災後の東北のいまを記録し、その先にふれるためのジャーナル『FIELD RECORDING』4号目の特集は「出来事を重ねる」。
東日本大震災を経験し、だんだんとほかの土地の厄災の経験に気がつくようになりました。同じような課題を見出し、取り組む手法への共感をもつ。そうして双方が学び合うように導き出させる視点は、まだ厄災を経験していない人々にとっても意義があるかもしれない。そして、時間が経つことで遠くなってしまう震災の経験を、遠くの人々と共有するための糸口になる可能性もあるのではないか。(「はじめに」より)
地域アートはどこにある?

編集:十和田市現代美術館
執筆:小川希、金澤韻、北澤潤、木ノ下智恵子、小池一子、里村真理、高須咲恵、ナデガタインスタントパーティー、中崎透、山城大督、野田智子、原田裕規、林曉甫、日比野克彦、藤井光、藤浩志、藤田直哉、星野太、見留さやか、ミヤタユキ、目[mé]、山出淳也、山崎亮
発行:堀之内出版
発行日:2020年3月30日
定価:3,500円(税抜)
サイズ:A5判、240ページ
2019年4月13日〜9月1日に開催された十和田市現代美術館 10周年記念企画展「ウソから出た、まこと」展のカタログ。北澤潤、Nadegata Instant Party、藤浩志の3組のアーティストを迎え、作品展示にとどまらず、「地域アートはどこにある?」というプロジェクトを進行した。展示紹介やプロジェクト中のクロストークや論稿を収録。
ヒトの目、驚異の進化──視覚革命が文明を生んだ

著者:マーク・チャンギージー
翻訳:柴田裕之
発行:早川書房
発行日:2020年3月5日
定価:1,060円(税抜)
サイズ:文庫版、322ページ
アルファベットや漢字など世界各地の文字から、字形を構成するL、K、Xほか19の「文字素」を抽出し出現頻度を解析した著者は、驚くべき事実を目の当たりにする。すべての人類は、同じ文字を読み書きしている。それは、文字が自然を模倣するように「進化」した結果である──。ヒトの目が持つ4つの超人的能力を検証、大胆かつ精緻な仮説によりかつてない興奮と発見を多分野にもたらした、視覚科学の冒険。解説/石田英敬
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2020/04/15(水)(artscape編集部)
パオロ・ダンジェロ『風景の哲学──芸術・環境・共同体』

訳者: 鯖󠄀江秀樹
発行所:水声社
発行日:2020/02/20
イタリアの美学者、パオロ・ダンジェロ(1956-)が「風景」を論じた哲学書。本書の訳者あとがきによれば、著者ダンジェロはヘーゲルやシェリングといったドイツ・ロマン主義の思想から出発し、1990年代から現在にいたるまで、近現代哲学、視覚芸術、環境美学などをめぐる数々の著書を発表してきたという(本書が初の邦訳である)。
本書は全体で九章からなり、映画(第二章)、現代美術(第三章)、環境美学(第四〜六章)、法制史(第七章)といった複数の分野を横断しつつ「風景(paesaggio)」の問題が論じられる。ここではそのすべてにふれることは不可能なので、分量的にも内容的にも本書の中心をなす「風景の哲学のために」(第一章)から、本書をつらぬく基本的なスタンスを紹介しておくにとどめたい。
何気なく本書を手にとった読者は、一読して、その問いの所在がどこにあるのか、いささか判然としない印象を受けるかもしれない。著者ダンジェロは、哲学者ヨアヒム・リッターの古典的文献「風景」(1962)をはじめ、過去に風景をめぐって書かれてきたさまざまな文献を博捜しつつ、これを絵画、環境、歴史、感情、アイデンティティといった複数のキーワードに絡めて論じる。そのため著者その人の立場が見えにくくなっていることも事実だが、私見では、以上のようなトピックの広がり自体が、何よりも著者の「風景の哲学」にたいするスタンスを表わすものである。
どういうことか。ダンジェロが指摘するように、従来の「風景の哲学」においては、その経験を性急に「絵画」や「環境」に還元する姿勢が見られた。前者の立場は、風景を描いた絵画──ないしそれを写した写真や映画──こそが現実の風景の見方を規定する、というパラドクスに依拠している。言うなればこれは、著者も引用するオスカー・ワイルドの「自然は芸術を模倣する」という有名なパラドクスによって特徴づけられるものである。他方、後者の立場は80年代に台頭した環境美学などに見て取れるものであり、美学者アレン・カールソンが唱える風景の「環境的パラダイム」がこれに相当する。これも「風景=絵画」論とはまた異なるしかたで、風景をめぐる錯雑な経験を──自然科学の対象としての──「環境」に還元するものだと言えよう。
ひとつはっきりしているのは、本書でダンジェロが批判をむけるのが、こうした還元主義的な風景論であるということだ。そのなかで比較的好意的に取り上げられるのが、ゲオルグ・ジンメルが風景の統一基盤として名指した「気分」、そしてヘルマン・シュミッツやゲルノート・ベーメといった現象学者たちによる「雰囲気」をめぐる議論である。それによれば、「主体と客体の邂逅によって成立」する「半−モノ(semi-cose)」としての雰囲気こそ、私たちの風景の知覚を特徴づけるものである(63頁)。
とはいえ先述のように、本書では、風景をめぐる多様な経験を特定の理論に落とし込むことにはたえず警戒が払われている。本書後半において、風景をめぐる議論が法、国家、農業の問題にまで広げられていくさまには、いささか散漫な印象を抱くかもしれない。しかし風景を美学的に考察するということは、私たちが風景を「認識論的な経験」や「純粋に五感的な経験」とは違ったかたちで、すなわち感情、記憶、アイデンティティといったさまざまな構成要素に依拠しながら経験しているという事実から出発することにほかなるまい(24頁)。本書はその企図を、たんなる理念としてではなく、まさしく記述のレヴェルで示している。
2020/04/07(火)(星野太)
井上雅人『ファッションの哲学』

発行所:ミネルヴァ書房
発行日:2019/12/30
ファッションの「哲学」というそのタイトルに違わず、全体を通して非常に大きな問いに貫かれた一冊である。デザイン史・ファッション史・物質生活史を専門とする著者が、これまで執筆してきた文章をもとに書き下ろしたという本書は、平易な語り口ながら、ファッションをめぐる諸問題にきわめて有益な視座をもたらしてくれる。
本書の序文である「ファッションという哲学」において、著者はのっけから「ファッションとは、衣服のことではない」と断言する。それは「ものの見方、あるいは、世界の捉え方」であり、さらに具体的に言いかえるならば、「身体」と「流行」との関わりによって、「私たち自身や、私たちを取り巻く世界が、日々変化していくという世界観である」という(i頁)。
力強い言葉である。続けて著者の言葉を借りると、「ファッションの哲学」とは、「人間がどのように身体と付き合い、自分を取り巻く世界を把握し、自分自身を形成し、世界と関係しているかについての理解の仕方」のことである(ii頁)。端的に言えば、本書が謳う「ファッションの哲学」は、人間が
従来の「ファッションの哲学」は、その国内におけるパイオニアであるところの鷲田清一をはじめ、しばしば「現象学的」と称されるような身体論に依拠することが多かった。それに対して本書が採用するのは、歴史的な事象に依拠した豊富な事例と言説である。それぞれ、コミュニケーションとしてのファッション(第1章)、身体とファッション(第2章)、物質文化史におけるファッション(第3章)、ビジネスとしてのファッション(第4章)、日常的な実践としてのファッション(第5章)といった多彩な切り口から、数多くの知見が導き出される。章のなかでも話題は次々と切り替わり、読者は必然的にリクルートスーツ、ミニスカート、コルセットなどをめぐるそれぞれのトピックについて、みずから思考をはじめるよう迫られる。
はじめにも述べたように、著者の語り口はきわめて平易であり、ほとんどの読者は本書を難なく読み通すことができるだろう。かといってそれは、本書が専門的な内容を欠いていることを意味しない。ここまで述べてきたような本書の性格は、リーダビリティへの配慮から意識的に選ばれたものであり、個々のトピックに関心をもった読者は、巻末の注から参考文献にアクセスできるよう、しかるべく工夫もされている。冒頭の大きな問いの設定にくわえて、全体に行きわたるそのような美点からも、ゆくゆくは文庫のようなかたちでの普及が望まれる一書である。
2020/04/04(土)(星野太)
甲斐啓二郎『骨の髄』

発行所:新宿書房
発行日:2020年3月20日
写真家が写真を撮り始めるきっかけは大事なことだが、それが写真の出来栄えにそのまま反映するわけではない。むしろ実際に撮影してみてわかったこと、そんな「気づき」をどのように取り込んでいくのか、元あったプランをどれだけ大胆に変更していくことができるかが重要になる。
元々、ラグビーやサッカーなどスポーツ競技を中心に撮影していた甲斐啓二郎は、フットボールの歴史を記した本で、毎年2月の「Shrove Tuesday(告解の火曜日)」に、イングランド・ダービーシャー州のアッシュボーンでおこなわれる、「Shrovetide Football」と呼ばれる行事に興味を抱く。フットボールの原型とされるこの行事では、町の真ん中を流れるヘンモア川の両岸の住民たちが、1個のボールをゴールまで運ぶことを競い合う。「教会に入らない」、「人を殺さない」ということ以外には一切のルールがないこの競技を、甲斐はほとんど予備知識なしに撮影したのだが、できあがってきた写真は予想を超えたものだった。そこには、肝心のボールはほとんど見えず、男たちが揉み合い、ぶつかり合い、密集し、駆け回っているその姿だけが写っていたのだ。つまりスポーツ写真としては完全に失敗だったわけだが、甲斐は大きな手応えを感じた。その「気づき」から、スポーツ、あるいは宗教行事の原型というべき世界各地の「祭事」を追うプロジェクトが開始されることになる。
甲斐が「Shrove Tuesday」に続いて撮影したのは、「骨の髄」(秋田県美郷町の「竹打ち」の祭事)、「手負いの熊」(長野県野沢温泉村でおこなわれる、厄年の25歳の男衆が守る社殿に松明で火を付ける「火付け」の祭事)、「Opens and Stands Up」(ジョージア西部、シュフティのShrovetide Footballによく似たボールを奪い合う行事)、「Charanga」(南米・ボリビアのマチャでおこなわれる、男たちが素手で殴り合う「Tinku(出会い)」の行事)である。これらのイヴェントの写真は、すべて「Shrove Tuesday」と同じやり方で撮影され、本書『骨の髄』に収録された。それらを見ると、甲斐が撮影したかったのが、祭りそのものではなく、むしろそこに写り込んでいない「何ものか」だったことが見えてくる。彼が写真集の「あとがき」で「『祭事』を『自然』もしくは『神』と置き換えて、『向かってくるもの』と考えると、『格闘の祭事』は『自然の猛威』とみることも出来る」と書いているのは、そのことを言おうとしているのではないだろうか。「見えないボール」は「見えない神」のメタファーとして捉えることもできそうだ。
なお、本書の刊行に合わせて、同名の写真展が銀座ニコンサロンで開催される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の広がりの影響で中止された。4月はじめの段階で、ほとんどの美術館、ギャラリーは休業を余儀なくされている。苦難の時期を乗り越えて、早く展覧会が自由に開催できるような状況になることを願いたい。
関連レビュー
甲斐啓二郎「Opens and Stands Up」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年06月15日号)
甲斐啓二郎「手負いの熊」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年11月15日号)
甲斐啓二郎「骨の髄」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年11月15日号)
甲斐啓二郎「Shrove Tuesday」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2013年10月15日号)
2020/04/03(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)