artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
安藤忠雄(原作)/はたこうしろう(絵)『いたずらのすきなけんちくか』

発行所:小学館
発行日:2020/03/03
建築家の安藤忠雄が、大阪・中之島公園内に子ども向け図書館「こども本の森 中之島」を設計し、大阪市に寄贈した(2020年3月1日開館予定だったが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、現在、開館が延期されている)。その開館に合わせて刊行されたのが本書である。なんと安藤が初めて挑んだ絵本ということで興味を惹かれ、手に取ってみた。当然、同図書館の紹介を切り口としながらも、途中から「建築とは何か」という安藤の思想に迫る内容となっていた。
主人公は小学生くらいの兄妹。父に連れられて「こども本の森 中之島」を訪れるが、父とは入り口で別れ、兄妹だけで館内を探検する。3フロア吹き抜けの構造や壁一面に設けられた本棚など、館内を一望する絵がまず大きく描かれる。肝はここからだ。本棚の脇から伸びる細い廊下を発見した兄妹は、「ひみつの においがする」と興味津々で突き進む。すると天井が高い円筒形の空間にたどり着いた。なんとも不思議な空間にワクワクする兄妹の前に、黒い服を着たおじさんが現われる。このおじさんこそ、安藤忠雄らしき人物だ。本物よりやけにスレンダーで若々しいのが気になるが、髪型はそっくりに描かれている。兄妹からおじさんへ素朴な質問が次々と投げかけられ、おじさんは率直に答える。これが実に興味深い。この円筒形の空間のように、よくわからない変な場所は何のためにあるのか。キーワードとして、おじさんは「いたずら」という言葉を使う。頑丈で機能的な建物は便利だけど、それだけではつまらない。「だから ぼくは、たてものに いたずらを しこむんだ」と。
その事例として直島の「ベネッセハウス」や大阪の「光の教会」、「住吉の長屋」など、安藤の代表的な建築作品が登場する。壁一面の十字架も、雨の日に部屋から部屋へ移動するときに傘をさして歩くことも、すべて安藤のいたずらだったのか! 子どもに向けたわかりやすい言葉として選ばれたとはいえ、いたずらという言葉は実に言い得て妙である。これは悪ふざけというよりは、「無駄なもの」という意味に近い。一見、無駄に思えるものこそ、「どんな風に使おうか」と人の想像力をかき立てるから面白いのだ。それが、安藤が建築に求める真髄だった。確かにその通りなのだ。便利なものは人の心にあまり残らないが、面白いものは心にずっと残り続ける。安藤の建築作品が印象的なのは、大人が真剣に考えて設計、施工したいたずらが仕込まれているからなのだ。
2020/03/05(木)(杉江あこ)
カタログ&ブックス | 2020年3月1日号[テーマ:デンマーク]

テーマに沿って、アートやデザインにまつわる書籍の購買冊数ランキングをartscape編集部が紹介します。今回のテーマは、東京都美術館で開催されている話題の展覧会「ハマスホイとデンマーク絵画」(2020年3月26日まで)にちなみ「デンマーク」。展示のなかでもデンマークという国の近代絵画の系譜が紐解かれており、そこに通底する静謐な魅力にハッとした人も多いのではないでしょうか。「デンマーク」というキーワードに関連する書籍の購買冊数ランキングトップ10をお楽しみください。
※ハイブリッド型総合書店honto調べ。書籍の詳細情報はhontoサイトより転載。
「デンマーク」関連書籍 購買冊数トップ10
1位:シェイクスピア全集 1 ハムレット(ちくま文庫)
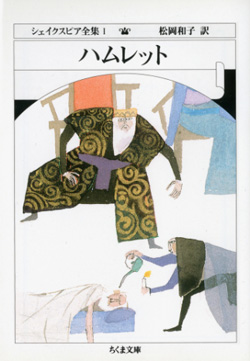
著者:シェイクスピア
翻訳:松岡和子
発行:筑摩書房
発売日:1996年1月26日
定価:660円(税抜)
サイズ:15cm、296ページ
デンマークの王子ハムレットは、父王の亡霊から、叔父と母の計略により殺されたことを知らされ、固い復讐を誓った。悩み苦しみながらも、狂気を装い、ついに復讐を遂げるが自らも毒刃に倒れる。美しい恋人オフィーリアは、彼の変貌に狂死する。数々の名セリフを残したシェイクスピア悲劇の最高傑作の新訳。脚注・解説・日本での上演年表付き。
2位:柳家喬太郎のヨーロッパ落語道中記

著者:柳家喬太郎
発行:フィルムアート社
発売日:2019年3月26日
定価:1,900円(税抜)
サイズ:19cm、245ページ
字幕付き落語に挑戦したデンマーク、アイルランドでのワークショップ、ケンブリッジ大学での落語公演、アイスランド大使公邸での晩餐会…。柳家喬太郎はじめての欧州ツアーの顚末を、写真とともに一挙公開。
3位:ヴィルヘルム・ハマスホイ沈黙の絵画(コロナ・ブックス)

監修:佐藤直樹
発行:平凡社
発売日:2020年1月26日
定価:2,000円(税抜)
サイズ:22cm、126ページ
この静寂の奥には、秘密が隠されている─。デンマークが生んだ孤高の画家ハマスホイ。国内未発表を含む代表作54点を収録し、謎めいた室内画を描き続けたその静謐さの魅力に迫る。
4位:デンマーク家具 時を超える魅惑のモダン・デザイン(別冊太陽)

編集:山根郁信
発行:平凡社
発売日:2014年5月22日
定価:2,300円(税抜)
サイズ:29cm、143ページ
控えめで上品、質感の効果と素材への細やかな配慮を体現したデンマークのデザイン。日本文化の影響、家具デザイナーの人と作品など、1940年代から現在までのデンマーク家具をデンマーク人研究者たちによる解説で紹介する。
5位:SOMETHING STRANGE THIS WAY

著者:ジャネット・カーディフ ほか
発行:青幻舎
発売日:2017年11月1日
定価:2,500円(税抜)
サイズ:B5変判、201ページ
ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラーの作品や制作風景、生活の様子をとらえた写真のほか、本人のコメントやキュレーターの論考、作品に関連したキーワードなどを収録し、彼らの独自の世界観に迫る。
6位:映画のなかの「北欧」 その虚像と実像

編著:村井誠人、大島美穂、佐藤睦朗、吉武信彦
発行:小鳥遊書房
発売日:2019年11月29日
定価:2,400円(税抜)
サイズ:21cm、294ページ
デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン…。60本以上の北欧の映画を「ストーリー」「作品の背景と現実」等の観点から幅広く紹介し、北欧の“虚像と実像”に迫る。掲載映画の詳細データ付き。
7位:ショップイメージグラフィックスイン北欧 Living, Food, Fashion, Service
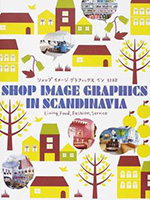
発行:パイインターナショナル
発売日:2010年9月
定価:9,800円(税抜)
サイズ:31cm、184ページ
巨匠のデザインを現代に取り入れ、新しく生み出された北欧デザイン。日本でも人気の高いスウェーデン、フィンランド、デンマークのショップアイデンティティを紹介する。
8位:最新!北欧デザイン・コレクション

編集:ヴィクショナリー
発行:グラフィック社
発売日:2018年1月10日
定価:3,800円(税抜)
サイズ:26cm、309ページ
北欧デザインの真髄ともいうべき削ぎ落としの妙技が光る、デザイン事例の数々。デンマーク、フィンランドなどを拠点とするクリエイターらの、140以上の最先端プロジェクトを紹介する。
9位:ヴィルヘルム・ハマスホイ 静寂の詩人(ToBi selection)

著者:萬屋健司
画:ヴィルヘルム・ハマスホイ
発行:東京美術
発売日:2020年1月27日
定価:2,300円(税抜)
サイズ:26cm、143ページ
19世紀末から20世紀にかけて活動したデンマーク人画家、ヴィルヘルム・ハマスホイ。デビュー作から、最後に描いた室内画まで、画家の創作活動を辿りながら、その人生と同時代のデンマーク美術の一端を紹介する。
10位:NERO YOUTH UGLY LISS LADY BIRD PUMA BLUE PINKY PINKY LITTLE SIMZ SE SO NEON

企画・監修:neromagazine
発行:nero編集部
発売日:2019年4月25日
定価:1,800円(税抜)
サイズ:29cm、157ページ
アンダー25のアーティストを中心に取材。前から、次世代のイギリスのバンド「アグリー」のサムと「レディーバード」のアレックス、後ろからデンマークのバンド「LISS」のインタビューなどが読める。
◆
artscape編集部のランキング解説
話題の「ハマスホイとデンマーク絵画」展の関連書籍(3位、9位)が複数ランクインする一方で、北欧といえばデザインのイメージがやはり根強いのか、現地のグラフィック・空間デザインなどの事例集(7位、8位)や、洗練と温かみが共存するデンマーク家具を深く知るビジュアルブック(4位)がランキングのなかでも目立ちます。
しかしそれらを押さえての1位はなんと、誰もが知るシェイクスピアの傑作「ハムレット」の新訳。シェイクスピアはそもそもイギリスの人だったはず、と思いきや、主人公ハムレットがデンマークの王子だという設定は意外と知られていません。落語家・柳家喬太郎が北欧を中心にヨーロッパを巡った際の道中記(2位)のなかで描かれるデンマークも、噺家ならではのユーモアに富んだ形容が盛りだくさんで、書き手の実感が伝わる楽しい一冊です。雑誌『NERO』(10位)に掲載のデンマーク・オーフス出身の新鋭バンド「LISS」のインタビューでは、10代でデビューした彼らの視点からの現代デンマーク観にも少し触れられるはず。
遠く離れた日本では北欧というカテゴリでひと括りにされがちですが、個別の土地の歴史やディテールを知ることでイメージの解像度がぐんと上がる体験は読書ならでは。展覧会の前でも後でも、デンマークを出発点に北欧への印象を拡張してみてください。
※ハイブリッド型総合書店honto(hontoサイトの本の通販ストア・電子書籍ストアと、丸善、ジュンク堂書店、文教堂)でジャンル「芸術・アート」キーワード「デンマーク」の書籍の全性別・全年代における購買冊数のランキングを抽出。〈集計期間:2019年2月1日~2020年1月31日〉
2020/03/02(月)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2020年02月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
スポーツ/アート

編著:中尾拓哉
著者:北澤憲昭、暮沢剛巳、鈴木俊晴、渋谷哲也、打林俊、渡邉大輔、栗本高行、大山エンリコイサム、山峰潤也、木村覚、原田裕規、犬飼博士
発行:森話社
発売日:2020年2月2日
定価:3,200円(税別)
サイズ:四六判、432ページ
競技と美術のミッシング・リンク
スタジアムの変遷や記録との関係、芸術家の参加などオリンピックをめぐる歴史から、スポーツと美術作品の顕在的/潜在的な相互作用、さらに競技、運動、観客をとりまくテクノロジーの問題、そしてeスポーツに至るまで、美術・写真・映像・身体表現など多彩な研究者、評論家、アーティストによる様々な視点から、スポーツ/アートの境界上に新たな結びつきを探る。
20XX年の革命家になるには──スペキュラティヴ・デザインの授業

著者:長谷川愛
ブックデザイン:金田遼平(YES Inc.)
発行:ビー・エヌ・エヌ新社
発行日:2020年1月24日
定価:3,200円(税別)
サイズ:A5判、192ページ
もしあなたが未来の革命家だったら──
RCAでスペキュラティヴ・デザインを学んだアーティスト長谷川愛が、MITメディアラボと東大で教えた授業をもとに、SDGsや倫理問題をふまえて社会変革に挑むための思索トレーニングブックとしてまとめた一冊(巻末付録としてワークキット+切り離せる126枚のカードを収録)。
ストリートアートの素顔──ニューヨーク・ライティング文化

著者:大山エンリコイサム
発行:青土社
発売日:2020年1月27日
定価:2,600円(税別)
サイズ: 21x15x1.6cm、252ページ
20世紀アメリカが生んだ世界最大の視覚文化=ストリートアート。貴重な取材をもとに綴られる初の人物史。
ニューヨークで制作と研究を続ける著者が、ジャン=ミシェル・バスキア、キース・ヘリング、フューチュラ2000ら12名を論じ、街角のアートと美術史、そして社会が交差する最前線に私たちを誘なう。
未来をつくる言葉:わかりあえなさをつなぐために

著者:ドミニク・チェン
発行:新潮社
発行日:2020年1月20日
定価:1,800円(税別)
サイズ:四六判、208ページ
この人が関わると物事が輝く! 気鋭の情報学者がデジタル表現の未来を語る。
ぬか床をロボットにしたらどうなる?
人気作家の執筆をライブで共に味わう方法は?
遺言を書くこの切なさは画面に現れるのか?
湧き上がる気持ちやほとばしる感情をデジタルで表現する達人──その思考と実践は、分断を「翻訳」してつなぎ、多様な人が共に在る場をつくっていく。
ふくよかな未来への手引となる一冊。
空間に線を引く──彫刻とデッサン

著者:土方明司、江尻潔、木本文平、高木貞重、大長悠子
発行:アルテヴァン
発売日:2020年1月10日
定価:2,000円(税別)
サイズ:A5判、304ページ
空間に線を引く─彫刻とデッサン展の公式図録。出品作家19名の彫刻とデッサン、あわせて300点強を網羅。酒井忠康 世田谷美術館館長を迎え、舟越桂、青木野枝が彫刻家ならではの触覚的なデッサンについて語る対談も収録。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2020/02/14(金)(artscape編集部)
ロドルフ・ガシェ『脱構築の力──来日講演と論文』

編訳者:宮﨑裕助
発行所:月曜社
発行日:2020/01/31
2014年11月、ニューヨーク州立大学バッファロー校の哲学者ロドルフ・ガシェ(1938-)が来日し、国内の複数の大学で講演を行なった。評者もそのいくつかに参加したが、ハイデガーやアーレントの精読を通じて一見ささやかな、しかし内実としては大胆かつスリリングなテーゼを打ち出していくその講演スタイルは、昨今の学術的な催事においてすっかり失われた光景であるように思われた。
その来日講演の原稿を再録し、関連するいくつかの論文を収めたものが本書『脱構築の力』である。本書は大きく前・後半に分かれ、第Ⅰ部「デリダ以後の脱構築」にはデリダとアメリカ合衆国におけるその受容を論じた「脱構築の力」「批評としての脱構築」「タイトルなしで」の3篇が、そして第Ⅱ部「判断と省察」にはアーレント論「思考の風」とハイデガー論「〈なおも来たるべきもの〉を見張ること」の2篇が収められている。「批評としての脱構築」(1979)と「タイトルなしで」(2007)をのぞく3本の日本講演は、来日後に上梓された英語の著書にそれぞれ組み込まれているようだが、それでもこれらが日本語オリジナル論集として1冊にまとめられたことの意味は小さくない。それはなぜか。
本書の「はじめに」から、ガシェが脱構築について述べた印象的な一節を引いてみよう。それによれば、主著『鏡の裏箔──デリダと反省哲学』(1986[未訳])や本書所収の「批評としての脱構築」をはじめとする「これらの著作のすべてにおいて」論じられているのは、脱構築とは「どんなテクストにも無差別に適用できるような文芸批評の方法」ではなく、「テクストの自己反照性や自己言及性を論証するというよりも、反照作用の可能性と不可能性の条件として当の反照作用から逃れるものへの探究に存している、紛れもなく哲学的なアジェンダを伴ったアプローチなのだということである」(9-10頁)。
この一節に端的に示されているように、ガシェは脱構築をたんなる「文芸批評の方法」として受容する──とりわけアメリカを中心に広まった──趨勢に抗い、あくまでそれを「哲学的なアジェンダを伴った」アプローチであることを訴える。そして、デリダその人の思想を(俗流の)「脱構築」と同一視することに明確に反対する著者の関心は、デリダにおける「思考」の特異なステータスへとむかう。それをひとつの問いのかたちで練り上げるとすれば、デリダにとって「思考するとはどういうことなのかを浮き彫りにすること」(11頁)こそが、ここでのもっとも重要な課題となるだろう。先にふれたアーレントの「判断」やハイデガーの「省察」をめぐる論文もまた、こうした「思考」の問題の延長線上にある。むろん、ガシェがデリダと二者の議論を同一視しているわけではないが、著者が「批判的警戒」と呼ぶもの(デリダ)と、アーレントおよびハイデガーの議論(「判断」および「省察」)は、その問題意識においてたしかに通底している。
対象とするテクストの綿密きわまりない解読に支えられた各論文は、読者にもそれなりの粘り強さを要求する。ホメロスやカントの言葉にあるように(第4章「思考の風」)、たしかに思考は「風」に擬えられるほど「迅速」で「非物質的な」ものである。しかしその──アーレントによれば「破壊的な」(187頁)──思考を伝達可能なものとしてくれるのは、「迂遠」で「物質的な」テクスト以外にあるまい。いずれにせよ、そうしたことへの連想をうながすガシェの日本講演が、5年あまりの時を越えて書物のかたちで刊行されたことを喜びたい。
2020/02/11(火)(星野太)
宮﨑裕助『ジャック・デリダ──死後の生を与える』

発行所:岩波書店
発行日:2020/01/24
博士論文を元にした前著『判断と崇高──カント美学のポリティクス』(知泉書館、2009年)に続く、宮﨑裕助(1974-)の2冊目の単著。著者がこの10年間、雑誌や論集に発表してきたデリダ論に加筆修正を施し、それに「生き延び」ないし「死後の生」という統一的なテーマを与えたのが本書である。
ここ数年、日本語でもようやくデリダについての充実した研究書が読めるようになった(亀井大輔『デリダ──歴史の思考』[法政大学出版局、2019年]、マーティン・ヘグルンド『ラディカル無神論──デリダと生の時間』[吉松覚・島田貴史・松田智裕訳、法政大学出版局、2017年]など)。しかしその反面、いまなおコンスタントに翻訳が続けられているデリダの著書は(おもに金額的に)一般の読者には入手しづらい状況にあり、世代を近しくするドゥルーズやフーコーとくらべると、若い読者にとってはいささか接近しがたい印象があるように見える。たとえばここ数年だけでも、講義録『獣と主権者』(西山雄二ほか訳、白水社)や論文集『プシュケー──他なるものの発明』(藤本一勇訳、岩波書店)といった待望の邦訳が成ったが、大部であり複数刊にまたがるという事情もあってか、いまひとつ読書界からの反響に乏しい。加えて、これまでに翻訳されたデリダの主著がほとんど文庫になっていないことも、大きな問題である。
そうした状況のなか現われた本書は、後期デリダについての入門的な内容を含み、同時に昨今の研究動向を踏まえた本格的な研究書でもあるという点で、画期的なものである。前述のように、過去に発表された学術論文が元になっているだけに議論の水準は高い。しかし同時に各章で扱われるのは、国家、労働、友愛、家族といった、われわれの多くにとって身近な──少なくとも馴染みのある──主題ばかりである。著者は、デリダの迂回に迂回を重ねた議論をただこちらに投げ出すのではなく、先に挙げたようなテーマをめぐる核心的な問いを「デリダとともに」立てつつ、それを「デリダとともに」よりふさわしいかたちで練り上げる。デリダに深く精通しながら、まったくデリダ的ではないその論述のスタイルが、読者をテクストのより適切な理解へと導いてくれるだろう。
なかでも、本書においてもっとも興味深いテーマは、著者がデリダから引き出してくる「生き延び(survie)」の思想であろう。序論において適切に示されているように、デリダの晩年にとりわけ顕著になるこの「生き延び」の思想は、直接的にはベンヤミンの翻訳論に遡ることができる。詳細は本書の記述に譲るが、そこで繰り返し強調されているように、ここでいう「生き延び」ないし「死後の生」とは、あくまでも言語によって媒介されるかぎりでの「生」の姿であり、その思想は実存的ないし生物学的な含意をもった(いわゆる)「生の哲学」とはまったく異なるものだ。いまなお編纂の途上にある生前の講義録や、それに関わる国内外の研究状況を見据えつつ、デリダを通じて本書が示すのは、そうした有機的ならざる「生」をめぐる刺激的な洞察なのである。
2020/02/11(火)(星野太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)