artscapeレビュー
デザインに関するレビュー/プレビュー
デジタル×ファッション──二進法からアンリアレイジ、ソマルタまで

会期:2015/07/11~2015/10/06
神戸ファッション美術館[兵庫県]
デジタルをテーマに、ファッション・ブランド、アンリアレイジとソマルタの作品を紹介する展覧会。アンリアレイジは「神は細部に宿る」というコンセプトのもと、デザイナー、森永邦彦が2003年に設立したブランドである。本展では2009年以降、近年の代表的な作品が出品されている。一言でいえば、率直で明快、曖昧さがない。シーズン・テーマをそのまま衣服に置き換えたかのような作品が並ぶ。例えば2009年S/Sの《マル
サンカク シカク》では、球体や三角錐、立方体に着せられた衣服があまりにも印象的である。レーザーカットの技術を使った2013年S/Sの《BONE》は、衣服を建築のような構造物と捉えその骨組みを蛍光色に浮かび上がらせた作品。2013-2014年A/Wの《COLOR》のように、新しい技術をつかった実験的な作品も目立つ。確かにハイテクを使っているには違いないのだが、ことさら実験的な作品に見えるのはその技術の本質を突き詰めた結果としていままでにない衣服が出来上がったからではないだろうか。一方、ソマルタは、2006年にデザイナー、廣川玉枝が、ファッション、グラフィックデザイン、サウンドクリエイト、ビジュアルディレクションを手掛けるソマデザイン社の設立と同時にファッション・プロジェクトとして立ち上げたブランドである。「身体における衣服の可能性」というコンセプトでつくられた無縫製ニットによる《Skin》シリーズは、あのレディ・ガガがPVで着用したことでも知られる。本展ではその《Skin》シリーズを中心に、トヨタとのコラボレーション《LEXUS DRESS》や3Dプリンターで製作した《Asura》のマスクとボディが出品されている。《Skin》シリーズのレースの透かし模様は、それが身体の上で正確にかたちを描くように緻密にプログラミングされる。クリスタル・ガラスをふんだんに散りばめた、自然や植物がモチーフの繊細なレースという女性的でしかない要素でありながらどこか硬質で冷たい印象を受けるのは、デジタルを経た完成度の高さからであろう。そして、「Skin」は人間の皮膚だけではなく、車や椅子といったプロダクツの表面でもありうるのである。
本展の主役の二人のデザイナーは、日本人ファッション・デザイナーの新世代といわれる世代である。いうまでもなく、前世代は1982年にパリ・コレクションで華々しいデビューを飾って「黒の衝撃」と呼ばれた世代。なかでも、アンリアレイジの森永はコム・デ・ギャルソンの川久保玲を、ソマルタの廣川は三宅一生の影響を色濃く受けていることは明らかだ。そのうえで、それぞれに前世代からの影響をよりシンプルで厳格な表現へと昇華してきた。近年、日本人ファッション・デザイナーの新世代の潮流に注目する展覧会はいくつか開催されてきたが、本展では世代から世代への継承と発展を強く意識せずにはいられなかった。[平光睦子]
2015/09/19(土)(SYNK)
ムサビのデザインV──1960-80年代、日本のグラフィックデザイン

会期:2015/09/01~2015/11/07
武蔵野美術大学美術館[東京都]
2011年から続く「ムサビのデザイン」シリーズ。これまで武蔵野美術大学が所蔵する歴史的なグラフィックデザイン、プロダクトデザインが紹介されてきた。5回目の今年は昨年同大学に寄贈された4人のグラフィックデザイナーたちのポスター作品約150点により、1960年代から80年代までのグラフィックデザインに焦点が当てられている。永井一正(1929-)、田中一光(1930-2002)、福田繁雄(1932-2009)、石岡瑛子(1938-2012)──活躍した時代は概ね重なり合うものの、4人4様、それぞれスタイルが異なるように見えるデザイナーたちの30年にわたる作品を通観したときに見えてくるものはなんなのか。本展の監修者である柏木博・武蔵野美術大学教授は1960年代末から70年代前半が日本のグラフィックデザインの変容の時期であることを指摘している。すなわち、モダンデザインの時代、デザインに普遍性が求められた時代に対する疑問、それまでのデザインのコードから脱しようという動きがこの時代に現われ、その後の日本のグラフィックデザインに多様な表現が生み出される契機となったことが、戦後第2世代の4人のデザイナーたちの作品とその変容に見えてくるとする。もうひとつ指摘されている点は、技術的な変化がデザインに与えた影響である。デザインの現場、とくに広告の分野におけるアートディレクター制度の導入はデザイナー、イラストレーター、フォトグラファー、コピーライターらの協業による新しい表現を生み出していった。またこの30年間に印刷表現も大きく変化した。シルクスクリーンとオフセットとでは表現可能なスタイルが大きく異なることはもちろん、オフセット印刷における製版技術の進歩は、とくに写真表現を自在に、そして豊かなものに変えていった。石岡暎子のポスター、福田繁雄の実験的作品を見ると、印刷技術が表現に密接に影響していた関係が顕著に見える。そして、技術進歩によって生まれた多様な表現の可能性はまた脱モダンデザインの展開と軌を一にしていたことが同時に見えてこよう。
本展のポスター、チラシ、図録には各々のポスターから解析された色の面積比がカラーチャートとして、縦軸を年代として配している。チャートの一部が左右にずれているのは印刷技法の違いを表しており、左端からオフセット、スクリーン、グラビアである。展示室の作品キャプションの左端にもこのチャートが配されており、作品の当該年度のみがカラーで、それ以外の部分は半調で示されており、作品の年代が把握できる仕掛けだ。デザインは中野デザイン事務所の中野豪雄氏。[新川徳彦]
2015/09/17(木)(SYNK)
「WASHI 紙のみぞ知る用と美」展
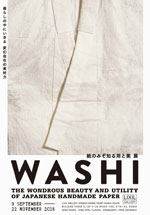
会期:2016/09/09~2016/11/22
LIXILギャラリー大阪[大阪府]
和紙の「美」についてはすぐ思いつくが、「用」の種類がこんなにあろうとは。本展は、生活の4シーン──纏う「衣」から、「食」の器、「住」空間の道具、「遊」び心ある愛玩具──に見られる、素材としての和紙の伝統的な可能性を提示している。和紙の寿命は洋紙に比べて長く、千年以上とも言われる。その耐久性に成形技術が足されれば、建具から布団、着物、お椀、傘、小物入れまで、用途は想像以上に幅広い。和紙の可変性にもびっくりしてしまう。紙をこよりにして編んでつくった丈夫な箱や傘、紙糸から織った柔らかくて気密性の高い衣類、紙の上に漆を重ねれば重さの軽い塗椀となる。展示品のなかでもロマンを感じたのは、明治期に西洋に盛んに輸出された「金唐革紙(擬革紙)」の小箱。1873年のウィーン万博で政府が出品して以来、ジャポニスムに沸く西欧で好評を得、国家主導(大蔵省印刷局)で製作されたもの。その人気は英国のバッキンガム宮殿の壁紙に使われたことでもわかるが、今は製造技術が殆ど失われて復活させるのは難しい。見た目はまさに厚みのある茶色い革、そこに浮き彫り調の凹凸で、金箔と朱色の豪華な植物文様が施されている。西欧の皮革製品を紙で代用して模倣するという技に、明治期の職人の執念を見る思いがする。私たちの暮らしを彩る変貌自在な和紙の力、ぜひ見直したい。[竹内有子]
2015/09/17(土)(SYNK)
7つの海と手しごと〈第6の海〉──インド洋とスンバ島のヒンギ/ラウ

会期:2015/08/28~2015/10/04
世田谷文化生活情報センター 生活工房[東京都]
世界各地の暮らしとクラフトを紹介する「7つの海と手しごと」シリーズ。6回目となる今回はインドネシアのスンバ島でつくられているイカット(絣織)による衣服ヒンギとラウが取り上げられている。絣の織物を指す「イカットIKAT」という言葉は、インドネシア語で「括る」「結ぶ」を意味する。揃えた糸を織りたい文様に合わせて固く括って防染し、染めたあとに糸の束を解いて織る。絣織で一番手間が掛かるのはこの括りで、文様や色に合わせて解いたり括ったりの作業が繰り返され、図案によっては1カ月から4カ月もの時間を要するという。スンバ島のこの絣織には下絵が用いられず、作業に当たる女性たちは頭のなかに記憶されている構図のとおりに手を動かして糸を括っていくのだという解説には驚かされた。かつてイカットには手紡ぎの綿糸が用いられていたが、現在では機械紡績糸が中心。しかし括りや染め、織りは手作業で行なわれている。織り手は多いが、括りができる女性の数は年々少なくなっているのは、やはりその技術が複雑で手間が掛かるものだからだろうか。伝統的な技術の継承者不足はどこでも同じ課題のようだ。ヒンギとラウは、いずれも絣織による正装衣装で祭祀や儀式などの場で着用される衣服。ヒンギは一枚布でできた男性用の腰巻き・肩掛け、ラウは筒状に縫い閉じた女性用の服である。祖先崇拝や精霊信仰のシンボルが文様となっており、そこにはインドの更紗や中国の陶磁器に描かれた文様の影響も見られるという。手間が掛かり高価なイカットは、貨幣の代わりに贈り物になったり、家畜と交換されたりもするのだという。展示品は染織作家の渡辺万知子氏が1972年以来蒐集してきたもの。ヒンギ、ラウの実物のほか、関連する工芸品、スンバ島の暮らしや文化が紹介されており、これらの織物がたんなる商品ではなく人々の生活に深く根差したクラフトであることが示されている。[新川徳彦]
2015/09/12(土)(SYNK)
六甲ミーツ・アート 芸術散歩2015

会期:2015/09/12~2015/11/23
六甲山上のさまざまな施設を舞台に現代アート作品の展示を行い、アートと六甲山の魅力を同時に満喫できるイベント。6回目を迎える今年は約30組のアーティストが出品し、会期中にはパフォーマンスやワークショップなど多彩な催しも行われている。筆者が毎年楽しみにしているのは、六甲高山植物園から六甲オルゴールミュージアムに至るルート。ここでは、貝殻のような陶の小ピースを森の中に散りばめた月原麻友美の《海、山へ行く》と、旧六甲山ホテルの電気スタンドを組み合わせて光と音がコール&レスポンスする久門剛史の《Fuzz》がお気に入りだった。また、六甲有馬ロープウェーで大規模なインスタレーションを行っている林和音の《あみつなぎ六甲》と、六甲ガーデンテラスで光とオルゴールを駆使した作品を夜間に展示している高橋匡太の《star wheel simfonia》もおすすめしたい。そして、今年にはじめて会場となった旧六甲オリエンタルホテル・風の教会では八木良太が音の作品《Echo of Wind》を出品しており、安藤忠雄建築との充実したコラボレーションが体験できる。作品、展示、環境、ホスピタリティが高いレベルで安定しているのが「六甲ミーツ・アート」の良い所。関西を代表するアートイベントとして、胸を張っておすすめできる。
2015/09/11(金)(小吹隆文)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)