artscapeレビュー
映像に関するレビュー/プレビュー
LISTEN リッスン

会期:2016/07/30~2016/09/02
第七藝術劇場[大阪府]
「聾者(ろう者)の音楽」を映像的に追究したドキュメンタリー映画。BGMや環境音も排した無音の映画であり、言語は手話と字幕のみ。手話は聾者にとっての言語だが、手指の動きに加えて、顔の表情、単語どうしの繋がりや間、テンポ、呼吸など複合的な要素が組み合わさることで、「声質」ならぬ「手質」が宿るのではないか。とりわけ、本作にも登場する「手話詩」(手話単語をベースに、ある単語の形から別の単語に変わるあいだに意味の連続性を持たせつつ、形の変化や拡張を加えたり、手型の位置や場所による押韻を行ない、視覚的に表現する)の表現者のように、熟達した聾者の手の動きには、意思伝達を超えた強弱・緩急などの抑揚や感情の揺らぎが胚胎し、「声」が「歌声」へと変化するように、音楽的な要素が存在するのではないか。そうした問題意識から、「聾者にとっての音楽」の映像化を目指す聾の映画監督・牧原依里が、聾の舞踏家・雫境(DAKEI)の協力とともに制作したのが本作。出演者15名は、日本手話を主たる言語とする聾者であり、舞踏家や「手話詩」の表現者、聾の劇団員から、バレエ経験者、舞台経験のない人までさまざまだ。ソロ、デュオ、複数人のアンサンブルの合間に、手話による彼らの語りが挿入される。「自分の中にずっと音楽があった」「手話そのものが心地よい音楽を奏でていると感じる時がある」「激しく木々を揺らす風を見ると、鳴っている音が分かる。夕陽が照らす光景を見て、イマジネーションの言葉が浮かび、私だけの歌をつくる」「見知らぬ人の発するオーラを見ると、自分の身体が突き動かされる」。
日常的に手話を使用する彼らの表現は、とりわけ指の動きの繊細さが際立つ。また、異なるシーンでも、「その人の身体の中にあるリズム」のストレートな表出によって、同一人物であると分かる。繊細な指先と全身で感情を表現する激しさの同居が圧倒的な、海辺の女性。花ひらくつぼみや風のそよぎを表現する少女。「手話詩」で「四季」の情景や移ろいを表現する男性。断片化された手話のコラージュを共鳴させ、「合奏」を紡ぐ6人の男女。心臓の鼓動のリズムを相手に渡し、呼吸を合わせながら変奏させていくカップル……。これらは、日本語の歌詞に手話を対応させた従来の「手話歌」のように、聴者にとっての音楽を置き換えたものではない点で、「聾者にとっての音楽とは何か」というアイデンティティの探求であると言える。
ただし、「無音の映像化」には両極面があるのではないか。生の舞台で見せるのではなく、「映像化」することのメリットとして、繊細な指先の動きや表情のクローズアップに加え、海辺や大樹など自然の波動を感じさせる風景を舞台装置として切り取ることが可能になる。一方で、「無音の映像」は聾者の知覚する世界そのままだろうか。ここには、彼らが「音楽のようなもの」を感じ、感情が動かされると語る、風の揺らぎや生身の肉体の発するオーラ、すなわち皮膚感覚の共振が欠けている。この映画を見る聴者は、「音のない世界」を疑似体験できても、聾者の知覚世界そのものを体験することはできない。接近しようとすればするほど、むしろ埋められない差や距離が露わになる。
音をシャットダウンすることで、むしろ際立つのは、運動の視覚性の純粋な抽出である。光が明滅するようにひらひらと舞う、素早い手の動き。空間のなかに裂け目や空隙を探しながら縫い合わせるように、新たな空間を切り開くように、何かに逆らって、あるいは身を委ねて流れるように、指先の震えが空気を震わせ微細な階調をつくり出していく。時間の展開のなかに、リフレインや変奏、アンサンブルの重層性が加わることで、無数の動きが引き出され、重ね合わせられていく。『LISTEN リッスン』を体験しているうちに感じたのは、「音(音楽)がない」のではなく、むしろ「音(音楽)が付けられていたら邪魔だ」という逆説的な確信である。
ここに至って、ダンスと音楽の同根性が開示される。ダンスは音楽であり、音楽はダンスである。あるグルーヴの胎動を感じれば、そこに「音楽」を感じうるし、何らかの情動的な要素が見る者に感じ取られることで、「身体を動かすこと」は「ダンス」と呼ばれるようになる。おそらく両者の根源は繋がっていて、耳で聴覚可能な要素で切り取れば「音楽」、身体の運動(フォルムとその変形)という視覚的要素から見れば「ダンス」と呼称されているにすぎない(従って、ダンスは「音楽」を内包しており、優れたダンサー/表現者の身体にはそのことが宿っている。たとえ微細な動きであっても、それは音の伝播のように空気を伝わって見る者の皮膚感覚を振動させ、思わず身体が動いたり、心が動かされるのだ)。
逆に言えば、本作は、無音=視覚性のみを切り取り、聴覚可能な「音」から「音楽」を切り離すことで、「音楽」の核を掴み出してみせると同時に、「ダンス」に内在する「音楽」との同根性を浮かび上がらせ、ダンスが純粋な身体の運動のみに完全には還元できないことを照射している。この地平においては、聾者/健常者という区別は存在しない。
2016/08/07(高嶋慈)
─画廊からの発言─ 新世代への視点2016

会期:2016/07/25~2016/08/06
ギャラリー58、なびす画廊、GALERIE SOL、藍画廊、ギャラリーなつか、ギャラリー川船、ギャルリー東京ユマニテ、ギャラリイK、ギャラリーQ、ギャラリー現、コバヤシ画廊[東京都]
毎年そうだが、今年も炎天下、銀座・京橋の11画廊を見て回る。40歳以下を対象とした企画展で、出品作家はぼくが見た11人中9人が女性。このなかでは最年長の佐藤万絵子(なびす画廊)はキャリアも15年に及び、もはやベテランの域だが、作品は相変わらずゴミタメのように新鮮だ。寺井絢香(ギャラリーなつか)はバナナの束を描いてるのかと思ったら、角棒の先に丸いものがついたマッチ棒みたいなものの集合体らしい。これは変! 村上早(コバヤシ画廊)と日比野絵美(藍画廊)はどちらもモノクロの銅版画だが、日比野の抽象形態に対して村上は具象、しかも村上はこってり個人的な物語を詰め込んでいる。繪畑彩子(ギャルリー東京ユマニテ)は映像と小品の展示。映像は水槽にカメや魚が泳ぐというもので、その顔や手足は人間のもの。ほとんどモノクロで、ちょっと懐かしいシュルレアリスムのコラージュを思い出させる。こういうクセの強い作品に比べれば、鉄による花の彫刻を置いた内山翔二郎(ギャラリイK)と、マユのような壷型の彫刻を出品した松見知明(ギャラリー58)のふたりの男性陣は、きわめて真っ当に見える。
2016/08/06(土)(村田真)
ヨコオ・マニアリスム vol.1

会期:2016/08/06~2016/11/27
横尾忠則現代美術館[兵庫県]
横尾忠則の作品のみならず、本人が創作と記録のために保管してきた膨大な資料を預かり、調査を進めている横尾忠則現代美術館。その成果はこれまでの企画展にも反映されてきたが、より直接的にアーカイブ資料と作品の関係に踏み込んだのが本展である。キーとなるのは横尾が1960年代から書き続けてきた日記で、作品との関連がうかがえるスケッチや写真のある見開きをコピーして、作品とともに展示している。もちろん実物の日記を並べたコーナーもある。また、展示室の中にアーカイブ資料の調査現場を移設して、美術館業務の一端を公開する斬新なアイデアも。ほかには、制作の副産物として生じた抽象画のようなパレット、郵便にまつわる作品、猫とモーツァルトと涅槃像をテーマにした作品、ビートルズにまつわる作品と資料も展示された。全体を通して、横尾が作品を生み出す過程や、発想の源が生々しく伝わってくるのが面白い。横尾自身も「発見の多い展覧会」と述べたほどだ。本展は末尾に「vol.1」とあるように、調査の進展に応じて今後も継続される予定。今まで本人ですら気付かなかった横尾忠則像を提示してくれる可能性があり、今後の展開が楽しみだ。
2016/08/05(金)(小吹隆文)
TDC 2016
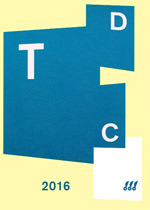
会期:2016/07/22~2016/08/27
京都dddギャラリー[京都府]
タイポグラフィを中心とするグラフィックデザインの国際コンペ「TDC」。毎回質の高いデザインを楽しませてもらっているが、その一方で十年一日のごとく選ばれ続ける巨匠デザイナーの存在に疑問を抱き、いっそ一定回数以上入賞した人は殿堂入りにして対象から外せば良いのに、と思っていた。今回も巨匠たちは選ばれていたが、その一方で着実な世代交代を感じたのもまた事実だ。筆者が特に気に入ったのは以下の2点。菅野創+やんツーによる、人工知能に手書き文字の意味を教えず、形状のみを学習させて、意味不明だけど文字らしく見える線をひたすら書き続けるドローイングマシンと、トム・ヒングストンによる、デヴィッド・ボウイのプロモーションビデオ(ラストアルバム『ブラック・スター(★)』に収録されたシングル曲『Sue(Or in A Season of Crime』)である。この2点を知っただけでも、本展に出かけた甲斐ありだ。そして今年の刺激を糧に、来年もまた出かけようと思う。
2016/08/02(火)(小吹隆文)
シン・ゴジラ
『シン・ゴジラ』は、1954年に発表されたシリーズ第1作の恐怖と崇高性を蘇らせた傑作である。特に自衛隊の迎撃にはただ歩き続けるだけだったゴジラが、米軍の攻撃には激昂し、停電になった闇の東京を焼くつくし、超高層ビルを切り裂き、やがて停止する、庵野秀明節の絶望的なまでに美しいシーン。これは日本映画史に残る。現代日本で再生した新しい怪獣映画は、津波破壊と原発事故後の想像力、安全保障をめぐる国内外の政治ドラマ、緩慢な動きと静止した立像に加え、うんざりするほど続くスペクタクルではない、限定的かつ効果的な見せ場が効いている。また、この手のジャンルにありがちな家族や恋人の個人の物語に収束させないこともよかった。
2016/08/01(月)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)