artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
七菜乃 写真展「My Aesthetic Feeling 2019」

会期:2019/08/09~2019/08/25
神保町画廊[東京都]
2016年以来続いている 七菜乃の「集団ヌード」撮影の試みにも厚みが出てきた。2017年から年1回のペースで、「My Aesthetic Feeling」と題する個展を神保町画廊で開催してきたが、今回は『七菜乃写真作品集 My Aesthetic Feeling』(芸術新聞社)の刊行にあわせて、日本家屋で撮影された新作の2シリーズ、23点が出品されていた。
やなぎみわは、写真集の巻末の対談「自分が見たい美のために」で、七菜乃の「集団ヌード」は、「いい意味でちょっとゆるくて、解放感がある」と指摘している。SNSでモデルを募集し、手袋、ベール、白靴下といった最小限の小道具を使う以外は、なるべくリラックスした雰囲気で撮影するというやり方がとてもうまくいっていて、男性目線で商品化されがちな女性ヌードから、気持ちのよい「解放感」を引き出しているのだ。ひとりのモデルを撮影すると、どうしても性的な関係性を連想させがちになるが、「集団」ではそれが薄れて、むしろ体と体の絡み合い、重なり合いの多様なヴァリエーションが引き出されてくるのも興味深い。
今のところ、各セッションの「乗り」が適度に保たれていて、作品としての完成度も上がってきた。ただ、そろそろ撮影のパターンが固定してきているようにも見える。七菜乃はやなぎとの対談で、60歳代のモデルの人も「来てほしい」と語っているが、それはぜひ実現してほしい。異質な体の持ち主が入ってくると、だいぶ違った印象になるのではないだろうか。また、これまでは最大30人ほどのモデルを撮影してきたのだが、その数がもっと増えると、撮り方──撮られ方もかなり違ってきそうだ。モデルのコントロールがより難しくなることで、逆に思いがけない場面が出現してくるかもしれない。
2019/08/12(月)(飯沢耕太郎)
『小檜山賢二写真集 TOBIKERA』

発行所:クレヴィス
発行日:2019年7月19日
小檜山賢二の新作写真集も、デジタル化によって成立した表現の開花といえる。本業は通信システムの研究者である小檜山は、2000年以降、「焦点合成」という技法で昆虫を撮影してきた。昆虫の体の各部分にピントを合わせて撮影した画像を合成して、恐るべき精度の写真を作りあげていく。だが、今回はこれまで彼が発表してきた『象虫』(出版芸術社、2009)、『葉虫』(同、2011)、『兜虫』(同、2014)といった写真集とはやや趣が違う。昆虫たちのフォルムを、超絶的な画像で定着した旧作とは違って、『TOBIKERA』には昆虫の姿は写っていない。本書の主題は、蝶や蛾のような生きものであるトビケラの幼虫が、水中に作る巣なのである。
写真集のデザインを担当した佐藤卓が、「デザインのお手本」と題した解説の文章で書いているように、それらは「正に現代アートにしか見えない」。トビケラの幼虫は、自分の周囲にある葉や木片や石粒などを、体から分泌される粘着性の物質で接合し、精妙な構築物を作り上げる。小檜山はそれらを黒バックで小さな家のように撮影している。ひとつとして同じものがないその造形は奇跡としかいいようがない。ここでも「焦点合成」が駆使されているのだが、やや非現実的な効果を生みがちなその手法が、今回は被写体のあり方と無理なく結びついていた。
自然のなかに潜む「センス・オブ・ワンダー」を引き出してくる自然写真は、デジタル化によって大きく変わりつつある。これから先もさまざまな分野で、新たな視覚的世界が切り拓かれていくのではないだろうか。なお、本書に掲載された写真の一部は、佐藤卓がディレクションした「虫展—デザインのお手本—」(21_21 DESIGN SIGHT、7月19日〜11月4日)にも展示されている。
2019/08/10(土)(飯沢耕太郎)
木藤富士夫 写真展「公園遊具 playground equipment」

会期:2019/08/07~2019/08/20
銀座ニコンサロン[東京都]
木藤富士夫は1976年、神奈川県生まれ。2005年に日本写真芸術専門学校を卒業後、フリーランスの写真家として活動し始めた。2006年からずっと撮影しているのが、各地の公園に設置されているコンクリート製の遊具である。タコや象の形の滑り台をよく見かけるが、木藤が今回発表した47点の作品を見ると、実に多様な種類があることに驚かされる。電話機、ロボット、魚の骨、巻貝、さらに鬼やガリバーまで、ありとあらゆる造形のオンパレードだ。むろん、子どもの興味を惹きつけるためのデザインなのだが、むしろ作り手の無意識の願望が形をとったような不気味さがある。
木藤の興味も、その百花繚乱のイマジネーションの乱舞に向けられているのではないだろうか。それを強調するために、彼は撮影の仕方にも工夫を凝らしている。撮影は夜におこなわれ、遊具を浮かび上がらせるために数100発から数1000発のストロボを発光させて、その輪郭や細部の質感をくっきりと浮かび上がらせる。最終的にそれらの画像を合成して、一枚のプリントとして完成させていく。結果的に、現実感と非現実感との両方を醸し出す、不思議な手触り感を備えた作品が成立してきた。デジタル化によって、これまでは撮影がむずかしかった状況をリアルに捉えることができるようになったが、本作もその成果のひとつといえそうだ。作品数はすでに200点近くになっているという。木藤はこれまで、8冊の小写真集を自費出版してきたが、そろそろ一冊にまとめる時期がきているのではないだろうか。
2019/08/07(水)(飯沢耕太郎)
江成常夫 写真展「『被爆』ヒロシマ・ナガサキ」

会期:2019/07/23~2019/08/19
ニコンプラザ新宿 THE GALLERY[東京都]
「ヒロシマ・ナガサキ」は多くの写真家たちによって撮影されてきた。土門拳の『ヒロシマ』(研光社、1958)のように記憶に食い込んでいる作品も多いし、江成常夫が今回展示した、広島や長崎の原爆資料館に保存されている被爆者の遺品や放射線を浴びた遺物も、東松照明、土田ヒロミ、石内都らが撮影している。その意味では、使い古されたテーマといえなくもないが、江成がここ10年あまり撮影し続けてきた写真群を集成した展示を見ると、その凄みに震撼させられる。
椹木野衣は、本展にあわせて刊行された写真集『被爆 ヒロシマ・ナガサキ いのちの証』(小学館)に寄せたテキスト「十字架の露光=被爆=暴露(エクスポージャ)──江成常夫のヒロシマ、ナガサキ」で、江成の写真の「触覚的」な特質について述べている。そこには、対象との距離が「ゼロ」になるような「触覚的な危機」の体験が、「いのちの証」として刻みつけられているというのだ。これまで原爆遺品、遺物の写真の多くはモノクロームで撮影されてきた。そこでは被写体が象徴的なイコンとして捉えられている。石内都の『ひろしま』(集英社、2008)はカラーで撮影されているが、彼女は遺品を宙を舞うようなあえかなイメージとして提示した。江成は、遺品、遺物にぎりぎりまで接近し、精密なカラー写真によってその物質性を「暴露」しようとする。その愚直ともいうべき撮影の仕方と、各写真に付された詳細な解説によって、われわれはまさに1945年8月6日と9日の、爆心地の地上で3000〜4000度、爆風の最大風速400メートル毎秒という恐るべきエネルギーの場に直面させられるのだ。なお、本展は8月29日〜9月11日にニコンプラザ大阪 THE GALLERYに巡回する。
2019/08/05(月)(飯沢耕太郎)
あいちトリエンナーレ2019 情の時代(開催4日目)

会期:2019/08/01~2019/10/14
愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほか[愛知県][愛知県]
残念ながら「表現の不自由展・その後」は、開幕3日目で閉鎖に追い込まれた。直接的な理由は、想定外の規模の電凸攻撃と脅迫の多さゆえに、来場者の安全を確保できないこと、またスタッフの精神的な限界である。これは公共施設に対するテロのはずだが、後に警察の初動が鈍かったことが判明している。「不自由展」の作品は、美術館や行政側が自主規制したり、おそらく議員の非公式な接触などが原因で展示中止になったものが多かったように思われたが、今回は、複数の政治家が展示の内容に介入することを公式の場で発言したことに驚かされた。確かに社会のフェイズが変わったことを示している。N国がマツコ・デラックスを批判し、ネット民もそれに同調するなど、杉田水脈や丸山穂高もそうだが、意見が異なる個人への攻撃を扇動するのは、国会議員の職務でないだろう。「不自由展」に対する政治家の圧力と同様、タガが外れている。メディアがこれをどっちもどっちの雰囲気で面白おかしく報道するのも、おかしい。
「不自由展」に関して、筆者が「あいちトリエンナーレ2013」の芸術監督だったことから、4つの新聞社を含む、複数のメディアからコメントなどの依頼が寄せられた。当時、津田監督が外部に向けて十分に発信できなかったのは、おそらく県の施設に殺到した膨大な数の脅迫への対策に追われていたのだろう。3度目に訪れた愛知芸術文化センターでは、本当に可動壁を入れて(上部は空いているが)、その奥の「不自由展」へのアクセスが塞がれていた。もっとも、この部屋は必ず通過しないといけない動線上ではなく、ルートからそれた袋小路となる位置であり、運営上の影響は比較的少ない。
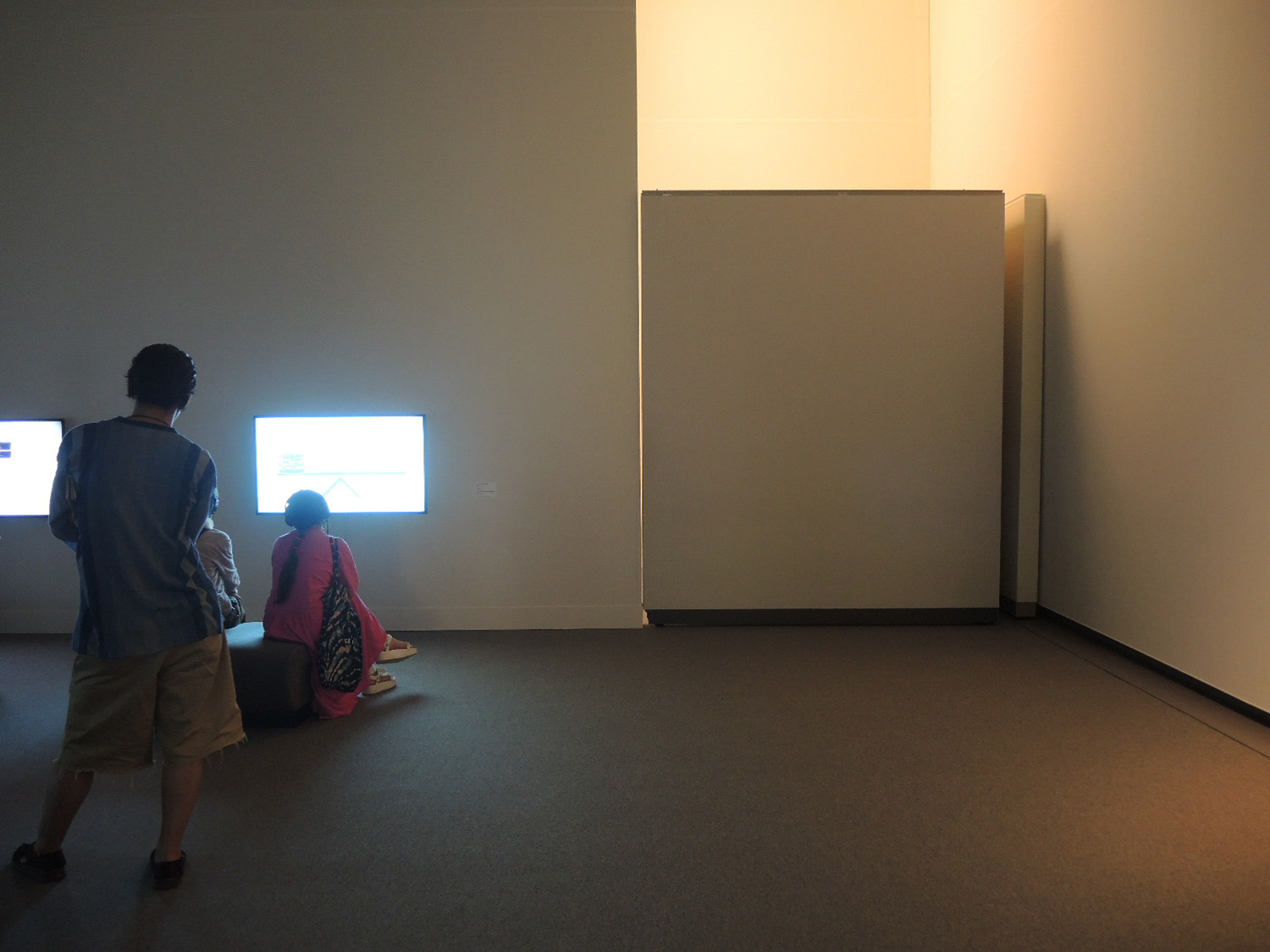
閉ざされた「表現の不自由展・その後」 へのアクセス
情報系や工芸系の作品がある、名古屋市美術館も2周目に挑戦した。初見ではゆっくり時間がとれなかった藤井光の作品は、日本統治時代の台湾における同化教育の過去の映像とその身体運動を模倣する現代の映像を並べている。そう、歴史修正主義が跋扈し、不敬罪という言葉が叫ばれ、確かに2019年が当時とリアルにつながっているのではないか。この数日、「あいちトリエンナーレ」に起きた出来事によって、作品の見え方も変わった。
3つのパフォーミング・アーツのプログラムを鑑賞したが、ベルギーで有名な連続少女監禁殺人事件を題材とし、子供たちに演じさせる形式をとったミロ・ラウ(IIPM)+CAMPOの『5つのやさしい小品』が印象に残った。日本ならばさしずめ、宮崎勤が引き起こした連続幼女誘拐殺人事件の演劇化だろうか。炎上しそうな作品である。しかし、内容は知的に構成され、演じるとは何かのメタ的な視点をもち、この日のもうひとつの演目、ドラ・ガルシアのレクチャーパフォーマンス《ロミオ》に通じるものだった。ところで、『5つのやさしい小品』の冒頭で、思いがけず「イマジン」が歌われ、いまの残酷に分断された日本を想う。

ドラ・ガルシア、レクチャーパフォーマンス『ロミオ』のポスター
公式サイト:https://aichitriennale.jp/
2019/08/04(日)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)