artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
softpad/横谷奈歩「剥離と忘却と With detachment and oblivion」
会期:2016/08/27~2016/09/10
MATSUO MEGUMI +VOICE GALLERY pfs/w[京都府]
softpadと横谷奈歩、それぞれの個展が並置された「剥離と忘却と」展。本評では、横谷奈歩の写真作品《剥離された場所》について取り上げる。「大久野島、乙女峠、キリシタン洞窟」という地名の情報だけがキャプションに記された横谷の写真は、一見すると、ピンホール写真のように像が曖昧にボケて、ブルーがかった色調ともあいまって、夢の中の光景のような幻想的な光に満ちている。梁や階段が朽ち、窓や扉が破れ、ガレキの散乱した廃墟のような室内。暗い洞窟の中に差し込む、厳かな光の柱。別の写真では、円環状に組まれた石の傍らに柄杓が置かれ、小さな池や人工的な貯水池の名残だろうかと思わせる。これらのベールに包まれたような痕跡のイメージは、具体的な土地の固有名から半ば遊離するとともに、どこか不穏な違和感をかき立てる。
その違和感は、展示台に置かれたオブジェの存在によって、ある確信へと変わる。海岸で拾ってきたらしいサンゴのかけらや陶片とともに、ミニチュアの地球儀とコップが置かれている。そして、小指の先ほどしかない地球儀とコップは、写された廃墟の床にも転がっていたのだ。一気に反転する真偽の境界。展示台の密やかなオブジェたちは、横谷自身が現実の場所に「行った」ことの物的証拠であるとともに、写されたイメージの真実を覆す、二重の仕掛けを帯びている。
このように横谷は、歴史的痕跡をとどめる場所を訪れ、リサーチや伝え聞いた話を元に模型を作成し、写真化するという二重の手続きによって、虚実の曖昧な世界を出現させている。今回、参照された3つの場所は、戦時中の毒ガス製造やキリシタン迫害に関わる土地である。広島県の瀬戸内海に浮かぶ「大久野島」は、戦時中、毒ガスを製造していたため、軍の機密事項として地図から消されていた島。横谷は、今も残る巨大な発電所跡をモチーフに模型を作成し、写真イメージへと変換した。廃墟の中をあてどなくさまようように、少しずつアングルを変えて撮られた写真のシークエンスは、虚構の空間の中に、別種の時間の流れをつくり出す。また、長崎県の五島列島にある「キリシタン洞窟」は、船で海上からしか入れない険しい断崖の洞窟で、迫害を逃れたキリシタンたちが潜伏していた場所である。亀裂から差し込む荘厳な光の柱は、安藤忠雄の「光の教会」を連想させ、受難と救済の物語を匂わせる。島根県の津和野にある「乙女峠」は、流罪となったキリシタン百数十名が、棄教を迫られて拷問を受けた場所。池に張った氷を役人に柄杓でかけられた氷漬けの刑が最も過酷だったというエピソードが、作品の背景となっている。
模型をつくって写真化する行為が虚構をリアルへと反転させる構造は、例えばトーマス・デマンドとも共通するが、メディア報道によって流通・共有されたイメージを再虚構化するデマンドに対し、横谷の作品は、実証的な手続きを踏まえ、国家権力による抑圧と忘却の過程を扱いつつ、唯一の真実の回復ではなく、「真正さ」をどこまでも曖昧にズラしていく。それは、写真/歴史の真正性への疑義を呈しつつ、幻想的で極めて美しいイメージとして結晶化させている。そうした写真とリアリティの関係に加え、歴史の痕跡の(不)可視化、時間の積層と写真のシークエンスがつくり出す時間の流れ、「閉じた部屋の窓」や「光の差し込む亀裂」が暗示するカメラ・オブスクラの構造など、写真をめぐる重層的なトピックをはらんだ展示だった。

横谷奈歩《剥離された場所 - 大久野島》(写真) 2016
2016/08/28(高嶋慈)
没後20年 星野道夫の旅

会期:2016/08/24~2016/09/05
松屋銀座8階イベントスクエア[東京都]
星野道夫がシベリア・カムチャッカ半島でヒグマに襲われて亡くなってから、早いもので20年が過ぎた。そのあいだに何度か大きな回顧展が開催され、写真集やエッセイ集も次々に編集・発行されている。彼がアラスカを拠点とする動物写真家という枠組みにはおさまりきれない、スケールの大きな思考力を備えた書き手であったことも、広く知られるようになってきた。今回の「没後20年 特別展」では、これまでの展示とは一線を画する、新たな星野道夫像を探求しようとしている。編集者の井出幸亮と写真家の石塚元太良が、星野の残した写真をネガから見返して、5部からなる会場を構成した。より若い世代による意欲的な展示である。
第1部の「マスターピース」には評価の高い名作が20点、大判のフレームに入れられて並んでいる。それらの出品作に向き合っていると、アラスカの大自然の大きな広がりを遠景として、動物たちの姿を捉えようという星野の意図がしっかりと伝わってくる。第2部の「生命のつながり」と第3部の「躍動する自然」も動物写真が中心だが、特に「躍動する自然」の章に展示された、カリブーの移動、ザトウクジラのジャンプ、天空のオーロラのうごめきなどを、シークエンス(連続場面)で見せるパートが目を引く。被写体を凝視する、星野の息づかいを感じることができるいい展示だった。
第4部の「神話の世界」は、図らずも遺作になってしまった『森と氷河と鯨 ワタリガラスの伝説を求めて』(世界文化社、1996)におさめられた写真群が中心に構成である。人類学や神話学の知見を取り入れつつ、ワタリガラスの創世神話を追ってアラスカからシベリアに渡った星野が、その先に何を見ようとしたのかを、トーテムポールや先住民族の長老たちの写真を含めて再構築している。そして第5章「星野道夫の部屋」では、残された映像やセルフポートレート、カヤック、ブーツ、アノラックなどの遺品によって、星野の魅力的な人間像を浮かび上がらせていた。
なお本展は松屋銀座の展示を皮切りに、大阪髙島屋(9月15日~9月26日)、京都髙島屋(9月28日~10月10日)、横浜髙島屋(10月19日~10月30日)に巡回する。その後も1~2年かけて全国を回る予定だという。星野道夫を直接知らない若い世代に、この不世出の写真家、エッセイストの記憶を受け継いでいきたいものだ。
2016/08/24(飯沢耕太郎)
プレビュー:UNKOWN ASIA ART EXCHANGE OSAKA

会期:2016/10/01~2016/10/02
ハービスホール[大阪府]
昨年に第1回展が開かれ、大きな成果を上げた「UNKOWNASIA」。その特徴は、日本、中国、台湾、タイ、インドネシア、フィリピンなど東南アジア各国から参加者を募ること、各国の第一線で活躍するアートディレクター、ギャラリスト、プロデューサーらを審査員として招いていること、賞の授与だけでなく、国内外での発表の機会や仕事のマッチングを行なうことだ。2回目となる今回は、会場を中之島の大阪市中央公会堂から梅田のハービスホールへと変更。会場が広くなったことにより、参加枠が180ブースへと拡大した(昨年は115ブース)。受賞後の活動やビジネスの機会までフォローするイベントは珍しく、昨年の会場は参加アーティストたちの熱気が渦巻いていた。そんな祝祭的な盛り上がりを今年もぜひ体験したい。
2016/08/20(土)(小吹隆文)
プレビュー:六甲ミーツ・アート 芸術散歩2016
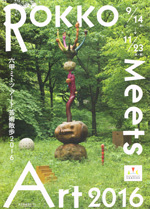
会期:2016/09/14~2016/11/23
六甲ガーデンテラス、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲山カンツリーハウス、六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、六甲ケーブル、天覧台、六甲有馬ロープウェー(六甲山頂駅)、グランドホテル 六甲スカイヴィラ、他[兵庫県]
「瀬戸内国際芸術祭」や「あいちトリエンナーレ」ほど大規模ではないが、関西を代表する同種のアートイベントとして知られているのが「六甲ミーツ・アート芸術散歩」だ。そのテーマは、六甲山上のさまざまな施設を散歩感覚で巡って現代アート作品を楽しみ、同時に六甲山の豊かな自然環境を再発見すること。普段は滅多に美術館に行かない人でも、家族で、友人同士で和気あいあいと現代アートに触れられるのが魅力である。今年は、岡本光博、開発好明、さわひらき、トーチカ、三沢厚彦など、招待と公募合わせて39組のアーティストが出品。会場は前回とほぼ同様だが、初期の安藤忠雄建築を代表する旧六甲山オリエンタルホテル・風の教会は今年の会場から外れている(残念)。山の天気は変化しやすく、夕方以降は気温が一気に下がる。雨と防寒の準備を忘れずにイベントを楽しんでほしい。
2016/08/20(土)(小吹隆文)
羽永光利アーカイブ展

会期:2016/07/23~2016/08/20
AOYAMA|MEGURO[東京都]
写真家・羽永光利(1933-1999)の写真アーカイヴを見せる展覧会。前衛芸術、舞踏、演劇、世相というテーマに整理された約400点の写真が一挙に展示された。会場の白い壁面を埋め尽くすかのように並べられたモノクロ写真の大半は、戦後美術史の現場を物語る貴重な写真ばかりで、たいへん見応えがあった。
平田実であれ酒井啓之であれ、美術の現場を記録する写真家には「時代の目撃者」という常套句が用いられることが多い。だが、とりわけ60~70年代に撮影された羽永の写真を見ていると、目撃者というより「共犯者」という言葉のほうがふさわしい気がしてならない。よく知られているように、ハイレッド・センターの《ドロッピング・イベント》(池坊会館屋上、1964年10月10日)の写真は、あらかじめ待機していた羽永が確信的に撮影したものだ。また今日、反芸術パフォーマンスとして歴史化されている、ダダカンこと糸井貫二の《殺すな》(1970)やGUNの《雪のイメージを変えるイベント》(1970年2月11日、15日)の記録写真も羽永が撮影したものである。それらの作品の作者がパフォーマンスを実行したアーティストであることは疑いないにしても、本来的にはその場かぎりで消え去ってしまう身体行為を写真として定着させた写真家の働きを過小評価すべきではない。事実、羽永によって撮影された糸井とGUNのパフォーマンス写真は、いずれも雑誌のグラビアに掲載されることで、その決定的なイメージを大衆に届けることに大いに貢献したのである。今日誰もが思い浮かべることができる、そのようなパフォーマンスのイメージは、羽永の視線と手に由来しているのだ。
翻って今日、はたして「共犯者」としての写真家はありうるだろうか。戦後美術の現場を記録した羽永の写真群を見ているうちに気づかされるのは、それらと今日における写真家の位置性と役割との偏差である。かつての写真家は、アーティストとして自立していないわけではなかったにせよ、美術家の作品を記録する役割を負わされていた。やや極端な言い方だが、写真家は美術家に従属していたと言ってもいい。だが今日の写真家は、「フォトグラファー」という呼称が定着しているように、アーティストとしての評価を高め、美術家の作品を記録する役割から相対的に解放されつつある。それは、端的に言えば、美術家自身が写真を撮影する役割を担うようになったからだろうが、より根本的には、写真そのものの性質が変容してしまったからではなかろうか。今日の写真は、とりわけデジタル技術の普及以降、大量に撮影することが可能となった反面、一回性の強度が失われ、「カメラ」に写真と動画の撮影機能があらかじめ組み込まれているように、相対的には映像との境界が曖昧になりつつある。パフォーマンスの現場を記録するという点で言えば、写真より映像のほうがふさわしいのかもしれないが、視覚的イメージの強度という点で言えば、羽永が盛んに撮影していた60~70年代に比べると、今日の写真は著しく脆弱になっていると言わざるをえない。羽永のような決定的なイメージを見せる写真家も、あるいはまた、そのような決定的なイメージに足る肉体表現を見せるパフォーマーも、今日のアートシーンのなかから見出すことは難しいからだ。
本展で発表された羽永の写真の背後に垣間見えたのは、写真による記録という表現行為に揺るぎない価値が与えられていた時代である。逆に言えば、そのように価値が機能していたからこそ、反芸術パフォーマンスはあれほどまでに強力な肉体表現を繰り返すことができたのだろう。今後、私たちはある種の信頼関係に基づく共犯関係を取り戻すことはできるのだろうか。
2016/08/17(水)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)