artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
12 Rooms 12 Artists 12の部屋、12のアーティスト UBSアート・コレクションより

会期:2016/07/02~2016/09/04
東京ステーションギャラリー[東京都]
スイスのグローバルな金融グループ、UBSは現代美術作家を長年にわたって支援してきたことで知られている。本展は、その3万点に及ぶというUBSアート・コレクションから厳選して、東京ステーションギャラリーの展示スペースを「12の部屋の集合に見立て」、12人の作家の作品、約80点を展示するという試みである。荒木経惟、アンソニー・カロ、陳界仁、サンドロ・キア、ルシアン・フロイド、デイヴィッド・ホックニー、アイザック・ジュリアン、リヴァーニ・ノイエンシュヴァンダー、小沢剛、ミンモ・パラディーノ、スーザン・ローゼンバーグ、エド・ルーシェイという出品作家の顔ぶれは、まったくバラバラだし、何か統一したテーマがあるわけではない。たしかに現代美術の多面性をよく示しているといえそうだが、このままではあまりにも場当たり的、総花的といえるだろう。
だが、写真という表現メディアを、12人中5人(荒木、ホックニー、ジュリアン、ノイエンシュヴァンダー、小沢)が使用しているという点は注目してよいだろう。台湾の歴史と社会状況を繊維産業の女性労働者の視点から再構築しようとする、陳の映像作品《ファクトリー》(2003)を含めれば、じつに半数のアーティストが写真/映像を最終的な発表の媒体としている。絵画や彫刻などの伝統的表現が、20世紀後半以降、急速に写真/映像化の波に覆い尽くされていったことが、くっきりと見えてくる展示といえそうだ。
特に注目すべきなのは、「国内未発表」という荒木経惟の連作「切実」(1972)である。荒木はこの頃、広告代理店の電通に勤務しながらゲリラ的な作品制作・発表の活動を続けていたのだが、UBSの購入時は「The Days We Were Happy」と題されていたというこの7点組のシリーズも、その時期の彼の表現意欲の高まりをよく示している。広告写真として撮影されたと思しき、タレントが登場するカラーTV、電気毛布などの写真を、まっぷたつに切断し、セロハンテープでつなげるという行為には、高度消費社会のイメージ操作を逆手にとって、批評的な写真表現につなげていこうとする荒木の意図が明確に形をとっている。『ゼロックス写真帖』(1970)や『水着のヤングレディたち』(1971)とともに、荒木の初期作品として重要な意味を持つ仕事が、このような形で出現してきたことは、驚き以外の何物でもなかった。
2016/08/16(飯沢耕太郎)
高倉大輔 作品展「monodramatic/loose polyhedron」

会期:2016/07/29~2016/08/18
Sony Imaging Gallery[東京都]
デジタル化によって画像合成が自由にできるようになると、1人の人物が多数のポーズをとった画像を、同一画面に合成するような作品が簡単に制作できるようになった。高倉大輔のように、もともと演劇に関わっていた写真家にとって、演出力が問われるこの種の写真は、自家薬籠中の物なのではないだろうか。漫画喫茶、映画館、コインランドリー、公園などの日常的な空間に、さまざまなポーズの若者たちをちりばめるように配置していく「monodramatic」のシリーズには、その才能がのびやかに発揮されており、清里フォトアートミュージアムが公募する2015年度ヤングポートフォリオに選出されるなど、評価が高まりつつある。
今回のSony Imaging Galleryでの個展では、その「monodramatic」に加えて新作の「loose polyhedron」のシリーズが展示されていた。モデルに自分自身の喜怒哀楽について「感情のバランスチャート」を書いてもらい、それにあわせて表情をつけ、「レンズからの距離感」を調整して撮影した写真を、モノクロームの画面にはめ込んでいくというポートレート作品である。こちらも、アイディアをそつなく形にしているのだが、そのバランス感覚のよさが逆に物足りなく思えてしまう。感情を喜怒哀楽という4種に固定したことで、そこからはみ出してしまうような部分がカットされ、どの写真も同じように見えてくるのだ。モデルが、若い男女(おそらくほとんどは日本人)に限定されていることも、全体にフラットな印象を与える要因になっているのだろう。
高倉に望みたいのは、あらかじめ結果が予想できてしまうような手際のよさを、一度捨て去ることだ。持ち前の演出能力を発揮する場を、より大胆に拡張していってほしい。例えば、海外で撮影するだけでも、画面のテンションは随分違ってくるのではないだろうか。
2016/08/15(飯沢耕太郎)
あいちトリエンナーレ2016 虹のキャラヴァンサライ 創造する人間の旅

会期:2016/08/11~2016/10/23
愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋・豊橋・岡崎のまちなか[愛知県]
3回目を迎えた「あいちトリエンナーレ」。芸術監督の港千尋が掲げたテーマは「虹のキャラヴァンサライ」だ。キャラバンサライはペルシャ語で「隊商宿」を意味する。虹は「多様性」の言い換えであろう。つまり、世界各国の多様な文化的・地理的・宗教的背景を持つアーティスト(虹)が旅をして愛知県(キャラヴァンサライ)に集い、新たな創造の芽が育まれる、と解釈できる。美しいがややドリーミーではではないか。取材前はそう感じていた。しかし、名古屋、豊橋、岡崎での展示を見るうち、このテーマが現在の不穏な国際情勢(テロ、紛争、難民問題、不寛容など)を反映した切実なメッセージだということに気付いた。一見ドリーミーを装って、じつはきわめて硬派な国際芸術祭。それが「あいちトリエンナーレ2016」なのである。3エリアを比較すると、規模の大きさでは圧倒的に名古屋だが、もっともテーマを体現していたのは豊橋だったと思う。岡崎も、石原邸と岡崎シビコは見応えがあった。名古屋だけを見て帰るつもりの人には、ぜひ豊橋と岡崎にも足を運びなさいと申し上げたい。また名古屋の名古屋市美術館の展示は収まりが良すぎて、おとなしい印象を与えた。国際芸術祭なのだから、もっとはっちゃけても良かったと思う。
2016/08/11(木)・2016/08/17(水)(小吹隆文)
須田一政『SUDDENLY』
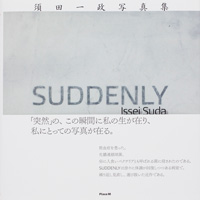
発行所:Place M
発行日:2016年5月16日
須田一政は2015年に敗血症を患っていた。化膿連鎖球菌に侵され、炎症の程度を示すCRP値は最高40に達した(基準値は0.3以下)という。その「いつ心臓が停止しても不思議ではない状態」から帰還したあとに、体調回復のために入院していた病院の病室で、繰り返し写真を見直し、「選び抜いた」近作を集成したのが本書である。
まさに「生死の境」に去来し、うごめきつつ姿を変えていくようなイメージ群が、写真集のページから溢れ出すように並んでいる。このところの須田の仕事ぶりには鬼気迫るものがあるが、この写真集でもそのただならぬ凄みに、絶句してしまうような写真が目白押しだった。特に目につくのは、液晶テレビの画面を写している写真である。須田は洋画が好きなようで、それらの一場面が断片的な映像として写しとられている。ほかにも、看板やポスターの一部を切り取った写真も多い。須田は写真集のあとがきで、スタンリー・キューブリックの「妄想や実現しなかった夢を現実と同じくらい重要なものとして扱おうとした」という言葉を引用している。このような、映像(まさに「妄想や実現しなかった夢」)を現実と等価のものとして扱う姿勢は、初期の頃からあったのだが、それがより研ぎ澄まされ、融通無碍なものになりつつある。
同年齢の(76歳)の荒木経惟もそうなのだが、須田の近作を見ていると、老いをネガティブにとらえるのではなく、むしろ何かを呼び覚ましていく契機としてとらえ直していこうとしているように見える。幽冥の世界を自由に行き来する表現が、輪郭をとりつつある。
2016/08/10(飯沢耕太郎)
アートと考古学展

会期:2016/07/23~2016/09/11
京都文化博物館[京都府]
考古学のオリンピックと呼ばれる「世界考古学会議」が京都で行なわれることを記念した企画展。考古遺物を展示するほか、アーティストと考古遺物がコラボレーションした作品も展示され、芸術と考古学の共同作業とその可能性が紹介された。参加アーティストは、安芸早穂子、日下部一司、清水志郎、伊達伸明、松井利夫、八木良太の6名。アーティストが考古学をイメージソースとするケースはままあるだろうが、考古学は芸術を必要とするのだろうか。そんな疑念を抱きつつ展覧会を見たが、これがめっぽう面白かった。例えば、純粋に記録のために描かれた遺跡の図面に、ある種の芸術性を認める、陶磁器の断片が見立てひとつで作品に生まれ変わるといった事例が、そこかしこで展開されているのだ。考古学者とアーティストが互いに専門外の領域から刺激を受け、自分のフィールドを広げていく。これこそまさにクリエイティブではないだろうか。
2016/08/09(火)(小吹隆文)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)